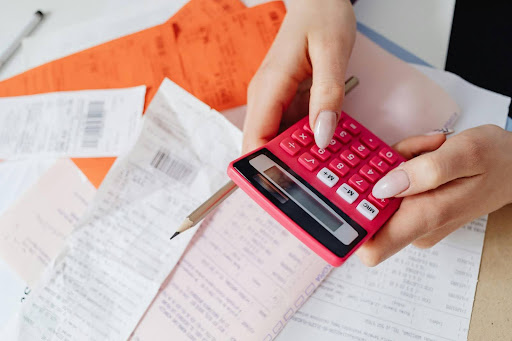
「領収書をもらい忘れてしまった」「受け取ったはずの領収書を紛失してしまった」という経験は、ビジネスシーンにおいて誰にでも起こり得ることです。法人の経理担当者や個人事業主にとって、領収書は経費を計上し、適切な税務処理を行う上で欠かせない極めて重要な証憑書類です。
しかし、取引のその場で受け取れなかった領収書を、後日になってから発行してもらうことは果たして可能なのでしょうか。また、一度発行された領収書を何らかの理由で再発行してもらう際には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
本記事では、領収書の後日発行および再発行に関する基本知識から、法的な側面、実務上の具体的な対応方法までを網羅的に解説します。万が一の事態に直面した際に、慌てず適切に対処できるよう、ビジネスパーソンとして押さえておくべきポイントを詳しく見ていきましょう。
目次
領収書の後日発行に関する基本知識
まず、代金の支払い当日に受け取れなかった領収書を、後になってから発行してもらう「後日発行」について解説します。これは、取引の事実を客観的に証明できるかどうかが鍵となります。
領収書の後日発行とは
領収書の後日発行とは、商品購入やサービス利用の対価を支払った当日ではなく、後日になってから発行・受領する手続きを指します。例えば、接待や会食の場で支払いを済ませたものの、領収書の発行を依頼し忘れてしまい、数日後に改めて取引先や店舗に連絡して発行を依頼するケースがこれに該当します。
通常、金銭の授受と同時に領収書が発行されるのが一般的ですが、多忙な状況や単純な失念により、受け取りを忘れることは少なくありません。こうした状況で、経費精算のために領収書が必要になった場合、後日発行を検討することになります。
後日発行は法的に可能か?民法486条の解釈
結論から言えば、領収書の後日発行は法的に可能です。日本の民法第486条第1項には、「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定められています。これは「受取証書交付請求権」と呼ばれ、支払いを行った側が、支払いを受けた側に対して領収書の発行を要求できる権利を保障するものです。
この条文は、必ずしも「支払いのその場で」請求しなければならないとは規定していません。したがって、支払いの事実が客観的に証明できる限り、支払いから時間が経過した後であっても、支払い側はこの権利を行使し、領収書の発行を請求できると解釈されています。
ただし、この権利を主張するためには、いつ、いくら、何に対して支払ったのかという「取引の事実」を明確に提示する必要があります。発行者側には、事実に基づかない領収書を発行しない責務があるため、請求者側がその事実を証明できなければ、発行を断られる可能性が高まります。
後日発行を依頼する際の具体的な準備
領収書の後日発行をスムーズに進めるためには、依頼する側が事前に十分な準備を整えておくことが不可欠です。発行者側が迅速かつ正確に取引内容を確認できるよう、以下の様な客観的な証拠を用意しましょう。
準備すべき書類や情報
購入時のレシート(購入明細)
最も強力な証拠となります。レシートには取引日時、金額、商品・サービス内容、店舗名が記載されており、取引の事実を明確に示します。
クレジットカードの利用明細
カード決済の場合、カード会社が発行する利用明細も信頼性の高い証拠です。Web明細の場合は、該当部分を印刷またはPDFで保存しておきましょう。
注文書や発注書の控え
BtoB取引の場合、事前に取り交わした注文書や発注書が取引の存在を証明します。
メールでの注文確認
オンラインでの取引の場合、事業者から送られてくる注文確定メールや発送通知メールが有効な証拠となります。
銀行の振込明細
銀行振込で支払いを行った場合は、振込明細書や通帳の記録が支払いの事実を証明します。
これらの証拠を提示することで、発行者側は社内記録と照合し、取引の事実を容易に確認できます。証拠が何もない状態で「領収書を発行してください」と依頼しても、架空取引への加担を疑われ、発行を拒否されるのが通常です。
依頼時の連絡方法と伝え方のポイント
準備が整ったら、発行元に連絡を取ります。電話またはメールで依頼するのが一般的ですが、丁寧な言葉遣いと明確な情報伝達が重要です。例えば、メールで依頼する場合は、以下のような文面が考えられます。
件名:領収書の再発行のお願い([取引日] [氏名または会社名])
株式会社〇〇
経理ご担当者様
平素より大変お世話になっております。
株式会社△△の□□と申します。
先日、貴社サービスを利用させていただきました下記取引につきまして、領収書を頂き忘れてしまいました。
大変恐縮ではございますが、弊社の経費精算の都合上、
領収書を発行していただくことは可能でしょうか。
- 取引日時:2024年XX月XX日 XX時頃
- 支払金額:〇〇,〇〇〇円
- 内容:〇〇代として
- 宛名:株式会社△△
- 但し書き:〇〇代として
念のため、当日のクレジットカード利用明細を添付いたします。
ご多忙の折、誠に申し訳ございませんが、ご検討いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
このように、具体的な情報を漏れなく記載し、低姿勢で依頼することで、相手方も快く対応しやすくなります。
領収書の再発行は原則不可?その理由と対応
次に、一度発行された領収書を紛失・破損等の理由で再度発行してもらう「再発行」についてです。後日発行とは異なり、再発行は法的な義務がなく、発行者側にとってリスクを伴うため、より慎重な対応が求められます。
領収書再発行に発行者の法的義務はない
領収書の「再発行」については、発行者に法的な義務はありません。前述の民法第486条は、支払いに対して一度領収書を交付する義務を定めたものであり、一度その義務を果たした以上、二度目以降の発行に応じる義務はないと解釈されています。
支払った側が領収書を紛失したのはあくまで自己責任であり、発行者側に責任を問うことはできません。したがって、再発行の依頼はあくまで「お願い」ベースとなり、発行者側の善意や判断に委ねられることを理解しておく必要があります。
なぜ発行者は再発行をためらうのか?二重発行のリスク
発行者が領収書の再発行に消極的なのには、明確な理由があります。それは、同一の取引に対して二枚の領収書が存在することによる「二重発行」のリスクです。
経費の二重計上と不正利用
最も懸念されるのが、悪意のある第三者による経費の二重計上です。元の領収書と再発行された領収書の両方を使って経費を申請されると、架空の経費が計上され、会社に損害を与えたり、税務上の過少申告につながったりする恐れがあります。
税務調査でのリスク
発行者側にとっても、安易な再発行はリスクを伴います。もし取引先が二重計上などの不正を行っていた場合、税務調査において、その不正に加担したと見なされる可能性があります。領収書の不正利用は脱税行為に直結するため、発行者側はコンプライアンスの観点から、再発行に対して非常に慎重な姿勢を取るのが一般的です。
収入印紙の再負担
取引金額が5万円(税抜)以上の場合、領収書には収入印紙を貼付する必要があります。領収書を再発行する場合、再発行された領収書も原則として課税文書に該当するため、再度収入印紙を貼付し、印紙税を納めなければなりません。これは発行者にとって純粋なコスト増となるため、再発行をためらう一因となります。
それでも再発行を依頼したい場合の交渉術
法的な義務がないとはいえ、事情を丁寧に説明し、相手方の懸念を払拭する手立てを講じることで、再発行に応じてもらえるケースもあります。
まずは、後日発行の際と同様に、取引を証明する客観的な資料を揃えましょう。その上で、なぜ再発行が必要なのか(例:経費精算で原本提出が必須である、など)、そして紛失してしまった経緯を正直に、かつ丁寧に説明します。
さらに、発行者側のリスクを軽減するための提案をこちらから行うことも有効です。
例えば、「『再発行』と明記していただいて結構です」「元の領収書が見つかった場合は必ず破棄します」といった一言を添えることで、不正利用の意図がないことを示し、相手に安心感を与えることができます。取引先との良好な関係性が構築できている場合は、相談に応じてくれる可能性も高まるでしょう。
領収書の後日発行・再発行で遵守すべき重要注意点
無事に後日発行や再発行に応じてもらえることになった場合でも、両者が遵守すべき重要なルールがあります。これらは、経理処理の正確性と税務上の正当性を担保するために不可欠です。
記載日付は「実際の取引日」が大原則
最も重要な注意点は、領収書に記載される日付です。後日発行や再発行の場合であっても、その日付は必ず「実際に金銭の授受が行われた取引日」でなければなりません。例えば、1月15日に支払いを行い、1月20日に領収書の発行を依頼した場合でも、領収書の日付は「1月15日」となります。
この日付を発行日である1月20日に変更してしまうと、事実と異なる日付の証憑書類を作成したことになり、会計帳簿の信頼性が損なわれます。悪質なケースでは、私文書偽造などの問題に発展する可能性もゼロではありません。発行者側も依頼者側も、取引の事実をありのままに記載するという原則を厳守する必要があります。
二重計上を防ぐための「再発行」の明記
特に再発行の場合、二重計上という最大のリスクを回避するための対策が必須です。発行者側は、再発行した領収書の目立つ場所(宛名の近くや備考欄など)に、必ず「再発行」という文言を明記すべきです。
可能であれば、「2024年XX月XX日付No.12345の領収書の再発行」のように、元の領収書を特定できる情報を付記すると、より確実性が高まります。こうすることで、経理担当者が処理を行う際に、これが再発行されたものであることを一目で認識でき、誤って二重に計上してしまうミスを防ぐことができます。依頼する側も、この「再発行」の記載を快く受け入れる姿勢が求められます。
収入印紙の扱いはどうなるか?
前述の通り、5万円(税抜)以上の取引における領収書の再発行では、収入印紙の扱いが問題となります。印紙税法上、領収書(金銭又は有価証券の受取書)は課税文書に該当し、再発行されたものであっても、その記載金額に応じた印紙税が課されます。
つまり、発行者は再度、印紙税を負担しなければなりません。このコスト負担を理由に再発行を断られることも十分に考えられます。高額な領収書の再発行を依頼する際は、こうした相手方の負担も理解した上で、より一層丁寧な交渉を心がける必要があります。
領収書がどうしても手に入らない場合の代替手段
発行元に後日発行や再発行を断られてしまった場合や、発行元がすでに存在しない(廃業など)場合でも、諦める必要はありません。税法上、経費として認められるためには、必ずしも「領収書」という形式の書類が必須なわけではなく、支払いの事実を客観的に証明できる他の書類で代替することが可能です。
レシートを証憑として利用する
日常的に受け取るレシートは、領収書の有効な代替手段となります。税法上、経費の証憑として認められるためには、「取引年月日」「取引金額」「取引内容」「書類の発行者(支払先の氏名または名称)」が記載されている必要があります。
一般的なレシートにはこれらの情報がほぼ網羅されているため、宛名が記載されていなくても、十分に証憑としての効力を持ちます。特に小売業、飲食業、旅客運送業などが発行するレシートは、宛名の省略が認められているため、そのまま経費精算に使用できます。
購入証明書・支払証明書の発行を依頼する
店舗や事業者によっては、領収書の再発行には応じられないものの、代わりに「購入証明書」や「支払証明書」といった独自の書類を発行してくれる場合があります。これらの書類は、特定の日に特定の金額の支払いがあったことを事業者が証明するものであり、領収書とほぼ同等の証拠能力を持ちます。
ただし、発行に際して手数料がかかる場合もあるため、事前に確認が必要です。領収書の再発行を断られた際には、代替書類としてこのような証明書の発行が可能かどうかを尋ねてみると良いでしょう。
出金伝票を起票して対応する
社内手続きの一環として、現金支出の記録である「出金伝票」を作成する方法もあります。これは、領収書が手に入らなかった場合に、支払いの事実を社内で記録・承認するための書類です。
出金伝票には、支払日、支払先、支払内容(勘定科目・摘要)、金額などを正確に記載します。慶弔費のように慣習として領収書が発行されない支出や、自動販売機での購入など、領収書の入手が物理的に困難な場合に有効です。
ただし、出金伝票はあくまで社内で作成した書類であり、第三者による証明力は領収書やレシートに比べて劣ります。税務調査の際には、その支払いの実態を裏付ける他の資料(招待状や案内メールなど)と合わせて保管しておくことが望ましいでしょう。
クレジットカード明細・銀行振込記録を活用する
クレジットカードの利用明細書や銀行の振込明細書は、非常に信頼性の高い代替証憑となります。これらはカード会社や金融機関という第三者が発行する公式な記録であり、改ざんが困難であるため、支払いの事実を客観的に証明する力が強いとされています。
特に法人カードでの支払いや法人口座からの振込は、事業に関連する支出であることの説得力を高めます。Web明細を利用している場合は、定期的にPDF形式などでダウンロードし、電子データとして保存しておく習慣をつけることが重要です。
抜本的な対策としての領収書管理の電子化
これまでの議論は、主に紙の領収書を前提としてきました。しかし、紛失や後日発行といった手間を根本的に解決するためには、領収書管理そのもののDX(デジタルトランスフォーメーション)、すなわち「電子化」が最も有効な対策です。
改正電子帳簿保存法の概要とメリット
近年、政府は経理業務のデジタル化を強力に推進しており、その中核となるのが「電子帳簿保存法」です。この法律は、国税関係の帳簿や書類を、一定の要件を満たすことで電子データとして保存することを認めるものです。
領収書を電子化することには、以下のような多くのメリットがあります。
紛失・劣化リスクの低減
データとして保存するため、物理的な紛失や、感熱紙の印字が薄くなるなどの劣化がありません。
業務効率の大幅な向上
紙のファイリングや保管場所が不要になります。また、日付や金額で瞬時に検索できるため、必要な情報をすぐに見つけ出せます。
コスト削減
保管スペース、ファイルやキャビネットなどの備品、印刷にかかる費用を削減できます。
テレワークへの対応
データは場所に縛られないため、オフィス外からでも経費精算や確認作業が可能になり、多様な働き方に対応できます。
電子取引データの保存義務
2024年1月からは、電子帳簿保存法の改正により、メールで受け取った領収書のPDFや、Webサイトからダウンロードした領収書などの「電子取引データ」は、紙に出力して保存するのではなく、電子データのまま保存することが義務化されました。
これは、すべての法人および個人事業主が対象となります。今後、ますます電子的な取引が増加することを見据え、データを適切に保存・管理できる体制を早期に構築することが、法令遵守の観点からも急務となっています。
インボイス制度と領収書の関連性
2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)も、領収書の扱いに大きな影響を与えています。消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要です。レシート型の領収書も、登録番号や適用税率、消費税額などが記載されていれば、「適格簡易請求書」としてインボイスの要件を満たします。
仕入税額控除という税務上のメリットを享受するためには、要件を満たした領収書を適切に受け取り、保存することがこれまで以上に重要になっています。電子化された領収書(電子インボイス)も同様に、適切に保存・管理しなければなりません。
まとめ
領収書の後日発行や再発行は、ビジネスの現場で直面しうる課題ですが、正しい知識と手順を踏むことで適切に対応することが可能です。後日発行については、取引の事実を証明できる客観的な証拠を提示すれば、民法の規定に基づき発行を請求できます。
一方、再発行には発行者の法的義務はなく、二重発行のリスクがあるため、原則として難しいと認識しておくべきです。しかし、丁寧な交渉と相手方のリスクを軽減する配慮により、応じてもらえる可能性も残されています。
万が一、領収書が手に入らない場合でも、レシートやクレジットカード明細、出金伝票といった代替手段で経費を計上することは可能です。それぞれの証拠能力の強弱を理解し、状況に応じて最適な方法を選択してください。
そして最も重要なのは、このような事態を未然に防ぐための体制づくりです。日頃から領収書を受け取ったら速やかに保管・処理する習慣を徹底するとともに、抜本的な解決策として、電子帳簿保存法に対応した領収書の電子化を推進することをおすすめします。これにより、紛失リスクを排除し、経理業務全体の効率化と正確性の向上を実現できるでしょう。
本記事が、領収書の取り扱いに悩むすべてのビジネスパーソンの助けとなり、日々の業務におけるトラブルを未然に防ぐ一助となれば幸いです。








不動産売買の領収書テンプレートと正しい書き方|印紙税の判定か…
不動産売買における金銭トラブルを未然に防ぎ、税務署への申告をスムーズに進めるためには、正確な領収書の…