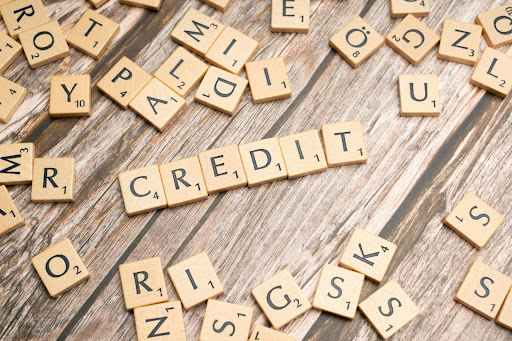
経営者や総務担当者の皆様に向けて、社員用の法人カードについて詳しく解説します。法人カードは会社経費の支払いに便利なツールですが、社員に持たせるとなるとメリットだけでなく注意点もあります。本記事では、法人カードの基礎から選び方、社員への追加発行の利点と欠点、さらに主要な法人カードの比較やおすすめまでを網羅し、「法人カード 社員用」といった関連キーワードを織り交ぜながら分かりやすく紹介します。経費管理の効率化やキャッシュフロー改善につながるポイントを押さえ、社員用法人カードの活用ガイドとしてぜひ参考にしてください。
目次
1. 法人カードとは
法人カードとは、法人企業や個人事業主向けに発行されるクレジットカードのことです。その名の通り事業用経費の決済を前提としており、個人向けカードに比べてビジネスに便利な機能が備わっています。例えば利用限度額(利用枠)が大きく設定されており、高額な仕入れ代金や出張費なども支払い可能です。また、多くの法人カードでは従業員向けの追加カードを発行でき、社員が経費支払いに利用することもできます。まずは個人用クレジットカードとの違いを押さえておきましょう。
発行対象と審査
個人カードが個人を対象に発行・審査されるのに対し、法人カードは法人代表者や法人そのものの信用情報も審査対象となります。そのため法人カードでは、代表者個人の本人確認書類に加えて会社の財務資料などの提出が求められる場合があります。
支払い口座
個人カードでは個人名義の銀行口座から利用代金が引き落とされますが、法人カードの場合は会社名義の法人口座から引き落としが行われます。法人代表者であっても、私的な口座ではなく事業用の口座からまとめて支払う仕組みです。
利用目的
法人カードは事業経費の支払いに特化しており、会社の経費とプライベート支出を明確に分けて管理できます。一方、個人カードは日常のあらゆる支払いに利用されます。法人カードを使えば会社経費の支出記録がカード明細で残るため、経費精算業務を効率化できる利点があります。
利用限度額
法人カードの限度額は個人カードよりも高めに設定される傾向があります。一般的な個人カードの枠が10万~100万円程度なのに対し、法人カードではカードのランクによっては500万円以上に及ぶケースもあります。
特にゴールドカードやプラチナカードといった上位ランクの法人カードでは、将来的な事業拡大を見据えて高い上限額が設定されることがあります。
追加カード(社員カード)
法人カードでは、契約法人に所属する従業員向けに社員用カード(追加カード)を発行できます。これは個人カードにおける家族カードに相当するものですが、利用目的が業務に限定される点が異なります。
中小企業向けの「ビジネスカード」では社員向けに数枚程度の追加カードが発行可能で、より規模の大きい「コーポレートカード」では多数の社員にカードを持たせることもできます。
付帯サービス
法人カードには事業用途に適した付帯サービスが充実しています。たとえば、出張時の旅行傷害保険や空港ラウンジ利用、経費精算ソフトとの連携サービス、取引先への支払い代行サービスなどが含まれるカードもあります。
一方、個人カードではショッピング保険やポイント優待など個人の消費活動向けのサービスが中心です。
以上のように、法人カードは会社の経費管理を助ける専用のクレジットカードです。個人カードとの違いを理解し、公私の支出を分けて適切に管理することで、経理処理の効率化やガバナンス強化につながります。特に経費精算やキャッシュフロー管理において法人カードは強力なツールとなります。次章からは、そんな法人カードを選ぶ際のポイントを見ていきましょう。
2. 法人カードの選び方
法人カードを選ぶ際には、企業の規模や利用目的に合わせて重視すべきポイントを検討する必要があります。ここでは年会費や還元率など基本的な選定基準から、付帯サービスや発行枚数制限といった注意点まで解説します。自社に最適なカードを見極めるために、以下の点をチェックしましょう。
年会費とコスト
カードの年会費は重要な比較ポイントです。法人カードには年会費無料のものから数万円のプラチナカードまで様々です。追加カード(社員用カード)の年会費も確認しましょう。発行枚数が多くなるほど、追加カード1枚ごとの年会費が積み重なり経費増加の要因となる可能性があります。例えば、あるカードでは社員用の追加カードが何枚まで無料、それ以上は1枚あたりいくらと決まっている場合があります。自社の従業員に何枚発行する予定かを考え、年会費負担とのバランスで選びましょう。
ポイント還元率・特典
支払いに対してどの程度ポイントやマイルが貯まるかも選定基準です。法人カードでも個人カード同様、利用額に応じてポイントが付与され、商品券やマイルへの交換、キャッシュバックなどに利用できます。還元率0.5%前後のカードが多い中、1%以上の高還元カードも存在します。
例えば「ポイント重視」の法人カードでは1~3%という高い還元率でポイントが貯まるものもあります。業務で頻繁に使うほどポイントが貯まりやすくなるため、経費削減効果も期待できます。ただしカードによってはポイント制度がない代わりに他のメリット(利用枠拡大など)に特化したものもあるため、重視する特典に応じて選びましょう。
付帯サービス
法人カードならではの付帯サービスも比較ポイントです。たとえば出張が多い企業であれば、旅行傷害保険や空港ラウンジサービスが付いたカードが便利です。接待や会食の機会が多いなら、グルメ優待サービスや会員制クラブの利用権などが付くカードも候補になります。
また、経費精算サービスやクラウド会計ソフトとの連携が可能なカードもあり、経理処理の効率化に役立ちます。自社の業務スタイルにマッチした付帯サービスがあるか確認しましょう。
利用限度額と支払いサイト
月間あるいは年間でどの程度の決済額が想定されるかもカード選びのポイントです。例えば、設備投資など高額決済が発生しやすい場合は、限度額が大きいカード(プラチナカード等)を選ぶ必要があります。一方で中小規模で日常経費決済が中心なら一般カードの枠でも足りるかもしれません。
また支払いサイト(締め日から引き落とし日までの猶予期間)も要確認です。カードによって月末締め翌月末払いなど支払い条件が異なりますので、自社のキャッシュフローに合ったものを選びましょう。支払い猶予が長いカードは一時的なキャッシュフロー改善につながります。
発行枚数と利用者制限
社員に何枚までカードを持たせたいかも考慮しましょう。法人カードによっては追加カードの発行枚数に上限がある場合があります。小規模事業者向けのカードでは代表者のみ利用で追加発行不可のケースもあるので注意が必要です。
従業員数が多い企業では、発行可能枚数の多いカードやコーポレートカード(大企業向けカード)を検討します。また、カード利用者を社員以外(派遣社員やアルバイト等)にも広げられるかも確認ポイントです。一般的には正社員や役員が対象ですが、最近では業務委託者にも持たせられるカードサービスも登場しています。
セキュリティと不正対策
法人カードは会社のお金を扱うため、セキュリティ面も重要です。不正利用防止の観点から、利用限度額の個別設定や利用明細のリアルタイム確認が可能なカードだと安心です。たとえばカードごとに利用先や上限額を設定できる法人カードもあり、社員の使いすぎや不正利用を防ぐことができます。
また最近ではカード券面に番号が印字されていない「ナンバーレスカード」も増えており、情報漏えいや盗難時の悪用リスクを下げる工夫がなされています。セキュリティに配慮したカードかどうかも選択の重要なポイントです。
以上のような基準をもとに、自社の利用用途に合った法人カードを選びましょう。中には「初年度年会費無料」や「◯◯万円以上利用で翌年度無料」といった条件付きでコスト負担を軽減できるカードもあります。複数のカードを比較検討し、総合的にメリットが大きい一枚を選ぶことが肝心です。
3. 法人カードを社員向けに追加発行するメリット
法人カードは代表者だけでなく、社員に対して追加カード(社員用法人カード)を発行することが可能です。社員に法人カードを持たせることで経費処理が便利になる一方、管理面でのルール整備も必要ですが、まずはメリットをしっかり把握しておきましょう。ここでは社員用法人カードを導入する主な利点を解説します。
経費精算の簡素化・効率化
社員が経費支払いに法人カードを使用すれば、立替払い後の経費精算処理を大幅に削減できます。従来、出張や接待のたびに社員が個人で立替え、領収書を集めて経理に提出し精算を受ける……という手間が発生していました。法人カードを社員に持たせれば、支払いがすべて会社のカード経由で行われるため、経費の立替え処理が不要になり事務作業の負担が減ります。利用明細に全ての経費が記録されるので、経理担当者はカード明細を見ながら各社員の経費を集計するだけで済み、精算のスピードアップと人的ミス防止につながります。
経費利用の一元管理
複数の社員がそれぞれ法人カードを使うことで、会社の経費支出を一括して可視化・管理できます。追加カードを発行すると、カードを使っている社員の経費をすべて一本化して管理できるようになります。すべてのカード利用履歴が法人名義の口座にまとまるため、経費の流れを漏れなく把握可能です。
紙の領収書ベースで各人が報告するよりも、データで管理できる分チェックもしやすく、不正やミスの発見も容易です。示すように、法人カード利用により経費の可視化が進み、経費漏れや不正利用の防止にも寄与します。特にWeb明細や管理画面上で各カードの利用状況をリアルタイム閲覧できるサービスを使えば、月次の経費集計もスムーズです。
キャッシュフローの改善
法人カードの支払いサイクルを利用して資金繰りを円滑化できる点もメリットです。社員が現金で都度支払いや精算をする場合と比べ、カード払いに集約することで支払いサイトを統一できます。
一般に法人カードの利用代金は月に一度、まとめて口座引き落としされるため、実際の支出を先延ばしできる効果があります。その間に売上入金があれば資金繰りが助かる場合もあるでしょう。また、社員への立替経費の精算も不要になるため、都度現金を準備したり振込手続きをしたりする手間も減ります。小口現金の管理が不要になり、現金紛失リスクの低減や銀行への出金回数減少による手数料節約にもつながります。
不正利用防止の仕組み
社員が法人カードを使うことは、逆に不正利用の抑止にもつながります。すべての支出が会社の明細に残るため、私的な利用や過剰な出費は後日発覚しやすく、社員にとっても「公費を使っている」自覚を促す効果があります。
加えて、カード会社側でも不正検知システムがあり、疑わしい取引は通知・ブロックされる仕組みがあります。さらに社員ごとに利用限度額を設定できるカードでは、上限を超える利用を物理的に防ぐことも可能です。例えば月◯万円までと決めておけば、それ以上は決済できないため使いすぎ防止になります。また、前述のナンバーレスカードのようにカード情報の盗難リスクを下げる工夫があるカードや、利用のたびに管理者へメール通知が飛ぶサービスなどもあり、社員カードの不正利用対策が強化されています。
ポイントやマイルの集約
社員の経費支払いを法人カードに集約することで、ポイントやマイルを効率的に貯められるメリットも見逃せません。各社員が個別に立替えて現金精算していた場合はポイントは貯まりませんが、法人カード決済にすることで利用額に応じたポイントが法人に蓄積されます。
例えば出張旅費や接待交際費、備品購入費など毎月まとまった額になる経費をカード払いすれば、年間を通じて相当量のポイントが獲得できるでしょう。そのポイントを使って会社の備品を購入したり、マイルを社員の出張航空券に充当したりすれば、実質的な経費削減につながります。
カードによってはキャッシュバック機能があるものもあり、貯まったポイント分だけ口座引き落とし額が減額される仕組みもあります。複数の社員利用分のポイントを法人で一括管理できるのもメリットです。
以上が、社員に法人カードを持たせる主なメリットです。経費関連業務の効率化や資金繰りの改善、そして会社全体の経費可視化によるコンプライアンス強化といった効果が期待できるでしょう。ポイント還元の恩恵も含め、上手に活用すれば会社経費の削減にもつながります。ただし、良いことばかりではなく留意すべきデメリットも存在します。次の章では、社員用法人カードのデメリットについて解説します。
4. 法人カードを社員向けに追加発行するデメリット
社員に法人カードを持たせることには多くの利点がありますが、同時にいくつかのデメリットやリスクも伴います。導入前にしっかり理解しておくことで、適切な対策やルール作りが可能になります。ここでは、社員用に法人カードを発行・運用する際の主なデメリットを解説します。
社員による私的利用や悪用のリスク
法人カードを社員に持たせる以上、私的利用されるリスクはゼロではありません。例えば業務とは関係ない個人の買い物にカードを使われてしまうと、公費の不正使用という重大な問題になります。
もちろん後から発覚すれば返金や懲戒処分など対応しますが、会社のお金が一時的にも目的外で使われる事態は避けねばなりません。また、経費として許可されていない用途(交際費の上限超えや社内規定外の支出など)に使われてしまうケースも考えられます。名義人以外の利用は禁止というクレジット規約の問題もあり、社員が勝手に他人に貸与するなどの行為もリスクです。
このような人為的な不正・誤用を防ぐには、後述するように社内ルール策定とモニタリングが欠かせませんが、リスクを完全に排除することは難しく、カードを渡す以上一定の信用に依存する面があるのはデメリットと言えます。
管理の手間とコスト増
社員ごとにカードを発行すると、その管理業務の手間も増加します。まず発行手続き自体、複数枚の申込みや受け渡し、カード情報の台帳管理などが必要です。発行後も、各カードの利用状況をチェックし、利用明細と経費申請内容を突き合わせる作業が発生します。社員が増えるほどこの確認作業に時間がかかり、経理部門や総務部門の負担となるでしょう。
また、追加カードの年会費が有料の場合は発行枚数に応じて経費がかさみます。例えば1枚あたり数千円の年会費でも、10枚発行すれば年間数万円の固定費となります。無料のカードを選べば直接のコストは抑えられますが、有料でも必要と判断すればその分の費用対効果を考えなくてはなりません。さらに、カード利用が増えることで経費精算システムの容量や処理も増え、場合によっては経費管理ソフトの上位プラン契約など追加コストが発生する可能性もあります。これら管理面の手間とコストは社員用カード導入のデメリットとして認識しておくべきです。
カード紛失・盗難時の対応
社員にカードを持たせる枚数が増えるほど、紛失や盗難のリスクも高まります。カードを紛失した社員が出た場合、迅速にカード会社へ連絡して利用停止措置を取る必要があります。対応が遅れると第三者に不正利用され、最悪の場合その損害を会社が被る恐れもあります(多くのカードには不正利用保険が付帯しますが、届け出が一定期間遅れると補償されないことがあります)。
また、盗難ではなくとも社員の退職時にも注意が必要です。退職者が法人カードを持ったままにならないよう、カードの回収・解約手続きを確実に行う管理体制が求められます。万一、退職後に無断利用されても会社側が支払い責任を問われかねません。複数の社員に配布する場合、どの社員にどのカード番号を渡したか、管理台帳をきちんと整備しておく必要があります。紛失・盗難・退職などの場合の社内連絡フローやカード停止手順を定め、速やかに対処できるようにしておかなければ、被害が拡大するリスクがあります。このように、カードが増えることで管理すべきリスク対応も増える点はデメリットと言えるでしょう。
社員の信用リスクと会社責任
社員用カードの利用代金支払い責任は基本的に会社(法人)にあります。たとえ社員が私的に使い込んで支払い不能となっても、カード名義人である会社に請求が来ます。最終的に社員に弁済させるにしても、一時的な立替えやトラブル対応は避けられません。また、社員の金銭感覚によってはカードを持つことで気が大きくなり、経費の浪費につながる恐れもあります。
例えば出張時の宿泊を不必要に高級ホテルにする、交際費を過度に使う等、コンプライアンス違反にならないまでも経費増大を招くケースもあり得ます。社内規定を超える利用は後から精算時に差額を個人負担させるルールも考えられますが、そもそもそうした利用が起きないよう教育・監督する手間が増えるのも一種のデメリットです。要するに、社員にクレジット決済権限を委ねる以上、会社としての信用リスクや費用管理リスクを分散することになる点を認識しておく必要があります。
以上のように、社員への法人カード追加発行には不正利用や管理負担、紛失時対応などのデメリットが存在します。特に公私混同が生じると税務面でも「経費の私的流用」と指摘されるリスクがあり、場合によっては経費が認められず法人税の追徴や横領と見なされる可能性もあるため注意が必要です。
こうしたデメリットを踏まえた上で、次章では社員用法人カードを安全・適切に運用するための注意点や管理方法について解説します。
5. 法人カードを社員向けに追加発行した際の注意点
社員に法人カードを持たせる場合、前述のデメリットに対処しリスクを低減するために、適切な運用ルールと管理体制を整えることが不可欠です。社員に法人カードを持たせる際は不正利用を防止するためのルール設定が重要となります。ここでは、社員用法人カードの発行・運用時に押さえておきたい主な注意点を説明します。
利用ルールの明確化と周知徹底
まず、社員に法人カードを渡す際には社内での利用規程を定めることが必要です。カードの利用目的はあくまで業務上の経費支払いに限ることを明文化し、私的利用を禁止する旨を社員によく周知しましょう。「どのような経費にカード利用してよいか」「利用限度額はいくらか」「仮に私的に使ってしまった場合の精算方法や処罰」など、具体的なルールを定めておきます。
たとえば出張旅費や接待交際費、備品購入費はカード利用可とする一方、日常の食事や個人の交通費は対象外、といった線引きをガイドライン化します。またポイントの扱いについても決めておくと良いでしょう。法人カード利用で貯まったポイントは会社資産であり、私的に流用すると横領に問われる可能性もあります。そのため「ポイントは会社が一括管理し、福利厚生や備品購入に充当する」といったルールをあらかじめ決め、社員に理解させておくことが大切です。
発行・回収の管理フロー
法人カードの発行管理簿を作成し、誰にいつどのカードを貸与したか、カード番号や有効期限、利用限度額、年会費区分などを記録しておきましょう。万一紛失や盗難が発生した場合にすぐ特定できるようになります。特に複数のカードを一括管理する場合、カード会社から送付される利用明細書の宛先やWeb明細のログイン情報も整理しておく必要があります。
社員が退職・異動する際のカード回収フローも決めておき、総務または人事担当と連携して確実に回収・解約する運用を行いましょう。カード会社への連絡権限も社内で決めておき、紛失時には利用者本人だけでなく管理部門にも直ちに連絡するよう周知します。紛失・盗難時の緊急連絡先(カード会社の24時間受付窓口など)を社員に配布しておくのも有効です。定期的にカード保有者リストと在籍者を照合し、不要なカードが放置されていないかチェックすることも重要です。
利用状況の定期的な監視とチェック
社員用法人カード導入後は、定期的な利用状況チェックを行いましょう。理想的には経理担当者が毎月カードごとの利用明細を確認し、社内の経費申請内容と突き合わせて不備がないか検証します。
最近ではカード利用データをリアルタイムで確認できるオンライン管理画面を提供するカードもあります。そうしたツールを活用し、月次だけでなく随時モニタリングする体制を整えるとより安心です。例えば一定額以上の利用があれば管理部門へ自動通知が行くよう設定したり、利用パターンの異常を検知するソフトを用いたりすることもできます。
経費精算システムとカード明細を連携させれば、自動で利用項目ごとに仕訳され経理担当のチェック負荷も軽減できます。不正利用やミスを早期に発見するためにも、ダブルチェック体制(利用者本人+上長や経理担当)で明細確認する仕組みを取り入れると良いでしょう。
万一の不正利用・紛失時の対応策
カードの紛失・盗難や不正利用が発覚した際の対応手順をあらかじめ決めておきます。紛失が判明した時点で迅速にカード会社へ連絡し利用停止措置を取ること、警察への届け出が必要な場合はその手順、社内報告のラインなどをフローチャート化しておくと慌てずに済みます。
不正利用の被害額が出た場合の補償はカードの会員規約に基づきますので、法人カードの補償内容(自己負担の有無、上限額など)も把握しておきましょう。多くのカードでは紛失盗難保険が付帯し、届け出から一定期間遡って被害額を補填してくれますが、発覚が遅れると補償対象外になることがあります。したがって発覚を遅らせないための監視が重要です。
また、社員による私的流用があった場合の社内処分規定(返金義務や懲戒など)も周知し、公平に適用することが大切です。場合によってはガバナンス強化のために利用状況を役員会に報告するといった仕組みを設け、組織的にカード運用を監督することも検討してください。
適切なカード種類の選択
注意点とは少し異なりますが、社員に持たせるカードの種類(グレード)も適切に選ぶことが大切です。例えば新入社員や若手スタッフには利用枠が小さめの一般カードを持たせ、役職者にはゴールドカード以上で限度額を大きめにする、といった使い分けも可能です。
無制限に高い枠を与えるのではなく、職務や役割に応じてカードの種類や限度額を調整することで、不正や浪費のリスクを減らせます。また必要ないのに高額な年会費のカードを社員分発行するとコスト増になるだけなので、本当に必要なグレードか精査しましょう。
追加カードの発行上限枚数にも注意が必要です。上限を超えて発行したい場合は別のカード会社のカードを組み合わせるなどの対応も検討します。
以上の注意点を踏まえ、社員用法人カードを適切に運用すればメリットを最大化しつつリスクを最小限に抑えることができます。要は「ルール作り」と「定期的なチェック」が肝心です。社員への教育も行い、会社の経費を扱っているという意識を共有してもらうことで、より安全で効率的なカード利用環境を整えましょう。
6. まとめ
法人カードの活用は、経費精算や資金管理の効率化に大いに役立ちます。社員に法人カードを持たせることで経費処理の簡素化、ポイント還元によるコスト削減など様々なメリットが得られ、結果として経営の効率化につながります。
一方で、社員用カード運用にはルール整備と管理体制が不可欠です。公私混同の防止策や定期的なモニタリングを行い、紛失・不正時の迅速な対応策を準備しておくことが、安心して法人カードを活用する最も重要な注意点と言えるでしょう。
カード選びにおいては、年会費やポイント還元率、付帯サービス、追加カードの発行枚数などを総合的に比較することが大切です。各社から特徴ある法人カードが提供されています。それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、自社の規模や利用ニーズに合致した一枚を選択しましょう。
最後に、社員用法人カードを導入する際は経営者自身が率先して適切に使い、社内に模範的なルール運用を示すことも大切です。法人カードは使い方次第で経費管理の強い味方になります。ぜひ本記事の内容を参考に、貴社にとってベストな法人カードを選び、賢く活用して経営効率化とガバナンス強化を実現してください。
請求書のカード決済で支払い先延ばしは「INVOYカード払い」
「急な支払いで、今月の資金繰りがピンチ…」
「あと少し支払いサイトが長ければ、この案件を受注できたのに…」
そのような悩みを抱えている法人経営者・フリーランスの方も多いのではないでしょうか?INVOYカード払いを活用すれば資金繰りの悩みを解決できます。
INVOYカード払いは、取引先から受け取った請求書の支払いをカード決済に置き換え、支払いを最大60日先延ばしできます。
「資金繰りに困っている」「入金より出金が先でキャッシュフローが大変」「大きな仕入れがあったから、できるだけ支払いを後ろ倒ししたい」などのお悩みを持つ方におすすめです。
【INVOYカード払いの4つのメリット】
- 財務審査が不要で、請求書とカードのみで利用できる
- 最短即日で取引先に振り込むことができる
- 最長30日後まで振込日を指定できる
- カードのポイントが貯まるからお得
登録は無料!突発的な支払いが発生した場合に備えてINVOYに登録しましょう。
▼請求書カード払い「INVOYカード払い」の詳細はこちらhttps://go.invoy.jp/lp/settlement/pay/








不動産売買の領収書テンプレートと正しい書き方|印紙税の判定か…
不動産売買における金銭トラブルを未然に防ぎ、税務署への申告をスムーズに進めるためには、正確な領収書の…