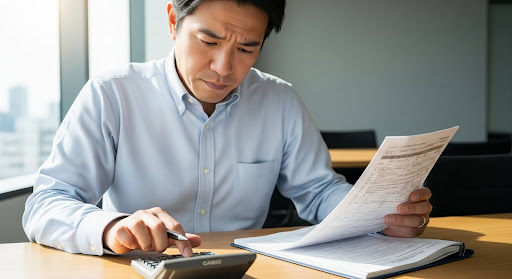
払い過ぎた税金が戻ってくる国税還付金。確定申告などを終えて還付の通知が届くと、ほっと一息つくビジネスパーソンも多いでしょう。この臨時収入を事業の資金繰りに活かしたいと考えるのは当然のことです。
しかし、この還付金、いざ会計帳簿に記録しようとすると「どの勘定科目を使えばいいのか」と手が止まってしまいがちです。個人事業主か法人か、還付される税金が所得税か消費税かによって会計処理の方法は大きく異なります。
もし処理を間違えれば、税務調査で思わぬ指摘を受け、追徴課税につながる可能性もゼロではありません。本記事では、国税還付金に関する会計処理のすべてを網羅的に解説します。
個人事業主と法人のケース別に、具体的な仕訳例を豊富に交えながら、会計初心者の方にも理解できるよう、専門用語もかみ砕いて丁寧に説明します。
この記事を最後まで読めば、もう還付金の仕訳で迷うことはなくなるでしょう。
目次
なぜ複雑?国税還付金の勘定科目を決める3つのポイント
国税還付金の仕訳が複雑に感じるのには、明確な理由が存在します。正しい勘定科目を選ぶには、いくつかの要素を正確に把握する必要があるからです。
特に重要な3つの基本原則を理解することが、適切な会計処理への第一歩となります。
納税者の区分(個人事業主か法人か)
個人事業主と法人では、事業と個人の関係性が根本的に異なります。個人事業主の場合、法律上、事業主個人と事業は同一の存在として扱われます。そのため、事業主個人の生活費に関わる側面を持つ所得税の還付は、事業の収益とはなりません。
一方、法人は事業主とは別人格の「法人格」という存在であり、法人が納める法人税は事業活動から生じる費用として扱われます。この会計上の前提の違いが、使用する勘定科目の選択に直接影響します。
還付される税金の種類(所得税、法人税、消費税など)
還付される税金が、事業活動の結果として直接生じるものか、それとも事業主個人の所得に対して課されるものかによって、会計上の意味合いが変わります。
例えば、法人税や消費税は事業活動に直接関連する税金です。しかし、個人事業主の所得税は、事業所得を含む個人の全所得に対して課される税金であり、事業上の経費とは認められていません。したがって、それぞれの還付金は異なる性質を持つものとして扱われ、使用する勘定科目も自ずと異なります。
経理方式(税込経理か税抜経理か)
特に消費税の処理において、この経理方式の違いは仕訳を決定づける重要な要素です。消費税の経理方式は、事業者が任意で「税込経理方式」と「税抜経理方式」のいずれかを選択できます。
税込経理方式は、消費税を売上や経費の金額に含めて処理し、損益計算書(P/L)に影響を与える方法です。対して税抜経理方式は、消費税を本体価格とは別の「預り金」として扱い、貸借対照表(B/S)で管理します。この根本的な認識の違いにより、還付金の仕訳方法が全く異なるのです。
【個人事業主向け】国税還付金の勘定科目と仕訳
所得税の還付:「事業主借」で処理する理由と仕訳例
個人事業主が確定申告によって受け取る所得税の還付金は、事業上の収益として計上することはできません。なぜなら、所得税は事業から得た所得などに対して課される「事業主個人の税金」であり、事業上の経費として認められていないからです。
そのため、還付金が事業用の銀行口座に入金された場合、そのお金は「事業主がプライベートな資金を事業に貸した」ものとして扱います。この会計処理に用いるのが、個人事業主特有の勘定科目である「事業主借」です。
もし、還付金をプライベート用の口座で受け取った場合は、事業とは全く関係のないお金の動きとみなされるため、帳簿への記帳(仕訳)は不要です。
仕訳例
所得税の還付金50,000円が事業用の普通預金口座に振り込まれた。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 普通預金 | 50,000円 | 事業主借 | 50,000円 |
消費税の還付:経理方式で変わる勘定科目
個人事業主の消費税還付は、採用している経理方式によって仕訳が異なります。ご自身の帳簿が「税込経理」と「税抜経理」のどちらで処理されているか、事前に確認しておきましょう。
税込経理方式の場合:「雑収入」
税込経理方式では、日々の取引で消費税額を売上や仕入の金額に含めて記帳します。この方式において、納付する消費税は「租税公課」という経費として扱われます。したがって、逆に税金が還付される場合は、経費のマイナス、すなわち事業上の収益とみなされます。
この時に使用する勘定科目が「雑収入(ざつしゅうにゅう)」です。一般的に、決算で還付される消費税額が確定した時点で、まだ入金されていなくても会計処理を行います。将来受け取る権利が確定した資産として借方に「未収消費税等」を計上し、その相手勘定として貸方に「雑収入」を計上します。
これにより、会計の発生主義の原則に基づき、還付されるべき収益をその発生した期に正しく計上できます。
仕訳例:決算時
決算で消費税の還付が30,000円と確定した。(未収計上)
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 未収消費税等 | 30,000円 | 雑収入 | 30,000円 |
仕訳例:還付金入金時
後日、還付金30,000円が普通預金口座に振り込まれた。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 普通預金 | 30,000円 | 未収消費税等 | 30,000円 |
税抜経理方式の場合:「未収消費税等」
税抜経理方式では、消費税を売上や仕入の本体価格とは別に管理します。具体的には、顧客から預かった消費税を「仮受消費税等」(負債)、仕入先へ支払った消費税を「仮払消費税等」(資産)として処理します。
決算時にはこの二つの勘定を相殺し、支払った消費税(仮払消費税等)のほうが多ければ、その差額が還付されます。この還付される金額は、「未収消費税等(みしゅうしょうひぜいとう)」という資産の勘定科目で処理します。この方法は、還付金が事業の損益に一切影響を与えない点が大きな特徴です。
仕訳例:決算時
決算で仮受消費税等が70,000円、仮払消費税等が100,000円あり、30,000円の還付が確定した。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 仮受消費税等 | 70,000円 | 仮払消費税等 | 100,000円 |
| 未収消費税等 | 30,000円 |
仕訳例:還付金入金時
後日、還付金30,000円が普通預金口座に振り込まれた。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 普通預金 | 30,000円 | 未収消費税等 | 30,000円 |
【法人向け】国税還付金の勘定科目と仕訳
法人税等の還付:中間納付から還付までの流れ
法人が法人税等の還付を受ける主なケースは、事業年度の途中で納付した中間納付額が、決算で確定した年間の税額よりも多かった場合です。この場合の会計処理は、「中間納付時」「決算時」「還付時」の3つのステップで正確に記録することが重要です。
中間納付時
中間申告で税金を納付した時点では、年間の最終的な税額はまだ確定していません。そのため、この支払いは税金費用の確定ではなく、あくまで税金の前払いとして扱います。
この時に使用する勘定科目は、資産に分類される「仮払法人税等」です。
仕訳例
法人税等の中間納付として300,000円を普通預金から納付した。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 仮払法人税等 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 |
決算時
決算を迎え、年間の法人税額が確定します。この確定額を、費用科目である「法人税、住民税及び事業税」として計上します。そして、中間納付で支払った資産「仮払法人税等」をこの費用に充当します。
もし中間納付額のほうが多ければ、その差額(還付予定額)を、資産科目である「未収還付法人税等)」や「未収入金」として計上します。この処理により、その会計期間の費用と資産を正しく財務諸表に反映させることができます。
仕訳例
決算の結果、法人税等の確定額が200,000円となり、100,000円の還付が決定した。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 200,000円 | 仮払法人税等 | 300,000円 |
| 未収還付法人税等 | 100,000円 |
還付時
後日、税務署から還付金が実際に振り込まれたら、決算時に資産として計上した「未収還付法人税等」を現金預金に振り替える仕訳を行います。これにより、資産の回収が完了したことを会計帳簿に記録します。
仕訳例
還付金100,000円が普通預金口座に振り込まれた。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 普通預金 | 100,000円 | 未収還付法人税等 | 100,000円 |
消費税の還付:個人事業主と同じ考え方
法人における消費税還付の会計処理は、個人事業主の場合と考え方は全く同じです。法人が採用している経理方式(税込か税抜か)に応じて、適切な勘定科目を選択してください。
税込経理方式の場合は、還付額は事業の収益(益金)となるため、「雑収入」として計上します。
税抜経理方式の場合は、決算時に「仮受消費税等」と「仮払消費税等」を相殺し、還付予定額を資産として「未収消費税等」で計上します。具体的な仕訳例については、前述の「【個人事業主向け】消費税の還付」のセクションがそのまま参考になります。
見落とし注意!還付加算金の正しい処理方法
税金の還付金には、納め過ぎた期間に応じた利息に相当する「還付加算金(かんぷかさんきん)」が上乗せされて振り込まれることがあります。
この還付加算金は、還付金本体とは会計処理や税務上の扱いが異なります。そのため、税務署からの通知書の内訳をよく確認し、必ず還付金と分けて処理する必要があります。
法人の場合:「雑収入」として益金算入
法人が受け取る還付加算金は、会計上「雑収入」として処理します。これは本業以外の収益(営業外収益)であり、法人税の計算上、益金(課税対象の利益)に算入されることを覚えておきましょう。
なお、還付加算金は利息に相当する性格を持ちますが、消費税の課税対象にはなりません(不課税取引)。
仕訳例
法人税の還付金100,000円と還付加算金1,000円が、合わせて普通預金に振り込まれた。(前期に未収還付法人税等を計上済み)
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 普通預金 | 101,000円 | 未収還付法人税等 | 100,000円 |
| 雑収入 | 1,000円 |
個人事業主の場合:「事業主借」と「雑所得」の二段階
個人事業主の還付加算金の処理は、法人よりも少し複雑なため特に注意が必要です。会計上の仕訳と、確定申告での税務上の申告が異なる点を理解しておくことが重要です。
まず、会計上の仕訳では、還付加算金が事業用の口座に入金された時点で、還付金本体と同じく「事業主借」で処理します。これは、還付加算金も事業主個人のものとみなされるためです。
次に、会計処理とは別に、税務上、この還付加算金は「雑所得(ざつしょとく)」として所得税の課税対象になります。したがって、確定申告を行う際には、事業所得とは別に、雑所得の欄にこの金額を記載して申告する必要があります。
帳簿に「事業主借」と記帳しただけで満足せず、確定申告書への転記を絶対に忘れないようにしましょう。この申告漏れは税務調査で指摘されやすいポイントの一つです。
仕訳例
所得税の還付金50,000円と還付加算金500円が、合わせて事業用の普通預金に振り込まれた。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 普通預金 | 50,500円 | 事業主借 | 50,500円 |
【番外編】従業員の年末調整による還付金の仕訳
事業者が税務署から直接受け取る還付金とは異なりますが、年末調整の結果、従業員に所得税を還付する場合も、会社側で会計処理が必要です。
会社は、毎月の給与から天引きした従業員の所得税を、国に納付するまで一時的に預かっています。この預かっているお金は、負債の勘定科目である「預り金」で管理されています。
年末調整で所得税を還付するということは、この預かっていた「預り金」を従業員本人に返すことを意味します。したがって、仕訳では「預り金」勘定を取り崩す処理を行います。この取引は会社の損益には一切影響しない点もポイントです。
仕訳例
年末調整の結果、従業員に10,000円を還付することになり、12月分の給与と一緒に普通預金から支払った。
(この仕訳は給与支払い全体の仕訳の一部ですが、還付に関連する部分を抜粋しています)
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 預り金 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 |
国税還付金に関するQ&A
還付金はいつ振り込まれる?
申告方法によって入金までの期間は異なります。一般的に、e-Tax(電子申告)を利用した場合は約3週間、郵送や税務署の窓口で書面提出した場合は約1か月から1か月半が目安とされています。
特に確定申告期間である2月から3月は処理が集中するため、通常より時間がかかる傾向があります。還付金の処理状況は、e-Taxのサイトにログインしてオンラインで確認することも可能です。
申告内容を間違えたらどうすればいい?
申告内容を間違えても修正は可能です。ただし、修正する時期によって手続きの名称と方法が変わります。
申告期限内に修正する場合
「訂正申告」を行います。これは、正しい内容で確定申告書を作成し直し、再度提出するだけの手続きです。最後に提出されたものが正式な申告として受理されます。
申告期限後に税金を多く払い過ぎた場合
「更正の請求」という手続きを行います。この請求が税務署に認められると、差額が還付されます。請求できる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
申告期限後に税金を少なく申告した場合
「修正申告」を行い、不足していた税額を自主的に納付します。この場合、本来の納期限からの日数に応じて延滞税が課されることがありますので、誤りに気づいたら速やかに手続きしましょう。
還付請求の時効は?
国税の還付を請求する権利は、その請求が可能となった日から5年間行使しないと、時効によって消滅してしまいます。
過去の申告で医療費控除の適用漏れなどがあった場合でも、5年以内であれば還付申告が可能です。権利を失わないよう、気づいた時点ですみやかに手続きを行うことが大切です。
ネット銀行でも受け取れる?
はい、受け取れます。楽天銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行、auじぶん銀行など、多くのインターネット銀行が国税還付金の受取口座として利用可能です。
ただし、指定できる口座は申告者本人名義の口座に限られますのでご注意ください。また、マイナンバーカードと連携して登録する「公金受取口座」を還付金の振込先に指定することもできます。
まとめ:還付金の勘定科目 早わかり一覧表
国税還付金の会計処理は、一見すると複雑に感じられるかもしれません。しかし、「誰が(納税者)」「何の税金を(税金の種類)」「どのように経理しているか(経理方式)」の3つのポイントを順番に確認すれば、使うべき勘定科目は自ずと決まります。
特に重要なポイントを再確認しましょう。
個人事業主の所得税還付は、事業の収益ではないため「事業主借」を使用します。
法人の法人税還付は、決算をまたぐ資産の動きとして「未収還付法人税等」で処理するのが原則です。
消費税の還付は経理方式で異なり、「雑収入(税込経リ)」または「未収消費税等(税抜経理)」となります。
利息である還付加算金は、法人は課税対象の「雑収入」、個人事業主は会計上「事業主借」で処理しつつ、確定申告で「雑所得」として申告することを忘れないでください。
最後に、あなたの状況に合った勘定科目が一目でわかるように、一覧表にまとめました。日々の経理業務や確定申告の際に、ぜひお役立てください。
| 納税者 | 税金の種類 | 経理方式 | 還付金の勘定科目 | 還付加算金の勘定科目 | ポイント |
| 個人事業主 | 所得税 | (適用なし) | 事業主借 | 事業主借 | 事業の収入ではない。還付加算金は確定申告で雑所得として申告が必要。 |
| 個人事業主 | 消費税 | 税込経理 | 雑収入 | 雑収入 | 事業の収益として計上する。 |
| 個人事業主 | 消費税 | 税抜経理 | 未収消費税等 | 雑収入 | 決算で仮受/仮払消費税を相殺して計上。事業の収益にはならない。 |
| 法人 | 法人税等 | (適用なし) | 未収還付法人税等 | 雑収入 | 決算で未収計上するのが原則。還付加算金は益金(課税対象)。 |
| 法人 | 消費税 | 税込経理 | 雑収入 | 雑収入 | 事業の収益(益金)として計上する。 |
| 法人 | 消費税 | 税抜経理 | 未収消費税等 | 雑収入 | 決算で仮受/仮払消費税を相殺して計上。事業の収益にはならない。 |








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…