
「仕入れの勘定科目がよくわからない」という悩みは、正確な利益計算とスムーズな確定申告への重要な第一歩です。この記事を読めば、勘定科目の選択で迷うことはなくなり、自信を持って日々の取引を記録し、事業の本当の収益性を正確に把握できるようになります。
本記事は、数多くの個人事業主や中小企業の経理をサポートしてきた公認会計士・税理士が、実際の現場で寄せられる質問と最新の税制(インボイス制度)を踏まえて執筆しました。これは単なる知識の羅列ではなく、あなたの事業を成功に導くための実践的な経理戦略です。
簿記の知識に自信がない方でもご安心ください。具体的な取引例と、そのまま使える仕訳例を豊富に掲載しました。現金取引、掛取引、クレジットカード決済など、あらゆる支払いパターンを網羅しています。この記事の通りに実践するだけで、誰でもプロレベルの記帳が可能になります。
目次
会計における「仕入れ」の正しい意味
経理の第一歩は、言葉の正確な意味を理解することから始まります。事業を行う上で頻繁に使う「仕入れ」という言葉も、会計の世界では厳密な定義が存在します。多くの事業主が抱える「何が仕入れで、何が経費か」という根本的な疑問に答えるため、まずはその土台となる知識を固めましょう。
「仕入れ」とは販売目的の購入
会計における「仕入れ」とは、販売する目的で商品や原材料などを購入することを指します。この「販売目的」という点が最も重要なポイントです。
例えば、以下のようなケースが「仕入れ」に該当します。
- アパレルショップが、店頭で販売するための洋服を卸売業者から購入する
- パン屋が、パンを製造するために必要な小麦粉やバターを仕入れる
- インターネット通販で、販売用の雑貨やアクセサリーを調達する
これらの取引はすべて、購入したモノに利益を上乗せして顧客に販売し、売上を得ることを目的としています。
会計上、すべての取引は「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」という5つのグループに分類されます。「仕入れ」は、このうち「費用」に属する項目です。費用とは、収益を得るために直接かかったコストを指します。つまり、仕入れは売上を上げるための直接的な元手であり、最終的な利益を計算する際に売上高から差し引かれる重要な項目なのです。
商品を仕入れた時点では手元に「商品」というモノが存在するため、一見すると「資産」のように思えるかもしれません。しかし、会計上のルールでは費用として処理することが定められていますので、この点は注意が必要です。
商品代金だけではない仕入れに含まれる付随費用
「仕入れ」の金額を計上する際、多くの人が商品の本体価格だけを考えがちです。しかし、会計の原則では、商品を仕入れて事業で販売できる状態にするまでにかかったすべての費用(付随費用)を仕入高に含める必要があります。これを「取得原価」と呼びます。
具体的には、以下のような費用が仕入れの金額に含まれます。
- 仕入運賃:商品が自社に届くまでの送料
- 購入手数料:仕入れ先に対して支払う手数料
- 関税:海外から商品を輸入した場合に支払う税金
- 荷役費:商品の積み下ろしにかかった費用
なぜこれらの付随費用を仕入高に含めるのでしょうか。それは、企業の利益を期間ごとに正しく計算するためです。会計には「費用収益対応の原則」という考え方があります。これは、ある収益(売上)が計上された期間に、その収益を生み出すためにかかった費用も対応させて計上すべきだ、というルールです。
商品の本当のコストは、工場出荷時の価格だけではありません。それを自社の倉庫まで運び、販売可能な状態にするまでのすべてのコストが含まれます。送料を単なる「通信費」として処理してしまうと、商品の原価が不当に低く見積もられ、その商品が売れたときの利益(売上総利益)が過大に計算されてしまいます。
付随費用をすべて取得原価に含めることで、売れた商品一つひとつの正確なコストが把握でき、より精度の高い利益計算や、適切な販売価格の設定につながるのです。
「仕入れ」と「経費」の境界線!間違いやすい勘定科目を徹底比較
「この支払いは仕入れか、それとも消耗品費か」という問いは、経理初心者が最もつまずきやすいポイントの一つです。この区別を曖昧にしたままでは、正確な利益計算ができず、税務調査で指摘を受ける原因にもなりかねません。ここでは、仕入れと混同しやすい勘定科目との違いを、具体的なシナリオを交えて一つひとつ明確にしていきます。
仕入れ vs. 売上原価:似ているようで全く違う
「仕入れ」と「売上原価」は非常によく似ていますが、会計上は明確に区別される概念です。この違いを理解することが、損益計算書を正しく読み解く鍵となります。
「仕入高」とは、会計期間中(例えば1年間)に、販売目的で購入した商品や材料の総額を指します。期中に100万円分の商品を仕入れた場合、その期の「仕入高」は100万円です。この金額には、まだ売れていない在庫分も含まれています。
一方、「売上原価」とは、会計期間中に実際に売れた商品に対応する、仕入れコストのことです。100万円分を仕入れても、そのうち80万円分しか売れなかった場合、その期の「売上原価」は80万円になります。売れ残った20万円分の商品は「在庫(棚卸資産)」として資産計上され、翌期に繰り越されます。
売上原価は、一般的に以下の計算式で算出されます。
売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 – 期末商品棚卸高
言葉だけでは難しく感じるかもしれませんが、具体例で考えると理解しやすくなります。例えば、期首の在庫が10万円、当期に仕入れた金額が100万円、期末に残った在庫が20万円だったとします。
この場合の当期の売上原価は、「10万円(期首在庫)+ 100万円(当期仕入)- 20万円(期末在庫)」となり、結果は90万円です。つまり、「期のはじめにあった在庫」と「期中に仕入れた在庫」の合計(販売可能だった商品の総額)から、「期末に売れ残った在庫」を差し引くことで、「期中に売れてなくなった分の原価」を計算しているのです。
仕入れ vs. 消耗品費:販売用か、社内用か
次に混乱しやすいのが「消耗品費」との区別です。ここでの判断基準は非常にシンプルで、「その物品が販売目的かどうか」という点に尽きます。
仕入れに該当する例としては、ネットショップが販売するために購入した雑貨やアパレル商品、飲食店が顧客に提供する料理に使う食材、商品を構成する一部となる部品や原材料などが挙げられます。
一方で消耗品費になるのは、事務所で使うボールペンやコピー用紙などの事務用品、商品を発送する際に使う段ボールやガムテープなどの梱包資材、清掃に使う洗剤や雑巾などです。工事会社が現場作業で使用する工具や資材も、それ自体を販売するわけではないため消耗品費となります。
ただし、一部グレーゾーンも存在します。例えば、商品の梱包に使う箱やリボンが、商品デザインの重要な一部を構成している場合(高級菓子の化粧箱など)は、仕入れに含めることもあります。また、修理業者が使う交換部品のように、仕入れとも消耗品費とも考えられるケースもあります。
このような場合、税務上の重要な原則は「継続性の原則」です。一度採用した処理方法は、正当な理由なく変更してはいけません。自社でルールを決め、常に同じ勘定科目で処理することが大切です。
仕入れ vs. 外注費:モノの購入か、サービスの委託か
「外注費」との区別は、購入したのが「モノ」か「サービス(業務委託)」かで判断します。
例えば、アパレルブランドがすでに完成しているTシャツを工場から購入する場合、これは「モノ」の購入であるため「仕入れ」になります。
それに対して、アパレルブランドが自社で用意した生地を外部の縫製工場に渡し、Tシャツへの縫製作業を依頼する場合は、「サービス」の購入にあたるため「外注費(または外注工賃)」として処理します。ウェブサイトのデザインを外部のデザイナーに依頼したり、経理業務を税理士事務所に委託したりするケースも同様です。
特に注意が必要なのが、外注費と「給与」の区別です。業務委託契約に基づく支払いは外注費ですが、雇用契約に基づく支払いは給与となります。この区別は税務調査で厳しくチェックされるポイントです。
なぜなら、外注費は消費税の課税仕入れとなり仕入税額控除の対象になりますが、給与は不課税であり対象にならないため、納税額に直接的な影響を与えるからです。
仕入れ vs. 荷造運賃:仕入れ時の送料か、販売時の送料か
送料の扱いは、その費用が発生したタイミングが「仕入れ時」か「販売時」かで明確に区別します。
商品を仕入れる(購入する)際に自社が負担した送料は、前述の通り、商品の取得原価の一部として「仕入高」勘定に含めて処理します。
一方で、商品を販売し、お客様に発送する際にかかった送料は、「荷造運賃」という別の勘定科目で処理します。これは商品を販売するためにかかった費用(販売費及び一般管理費)であり、梱包に使う段ボールなどの費用もここに含まれます。
これらの勘定科目を正しく使い分けないと、経営判断を誤る可能性があります。例えば、お客様への発送費用(荷造運賃)を誤って「仕入高」に含めてしまうと、売上原価が不当に高く計算されます。
その結果、売上総利益(粗利)が実際よりも低く見えてしまい、「自社の商品は儲からない」と勘違いして、不必要な値上げや仕入れ先の変更を検討してしまうかもしれません。本当の問題が会計処理のミスにあるにもかかわらずです。正確な科目選択は、単なる事務作業ではなく、自社の経営状態を正しく映し出すための重要な戦略なのです。
【早見表】もう迷わない!仕入れ関連の勘定科目
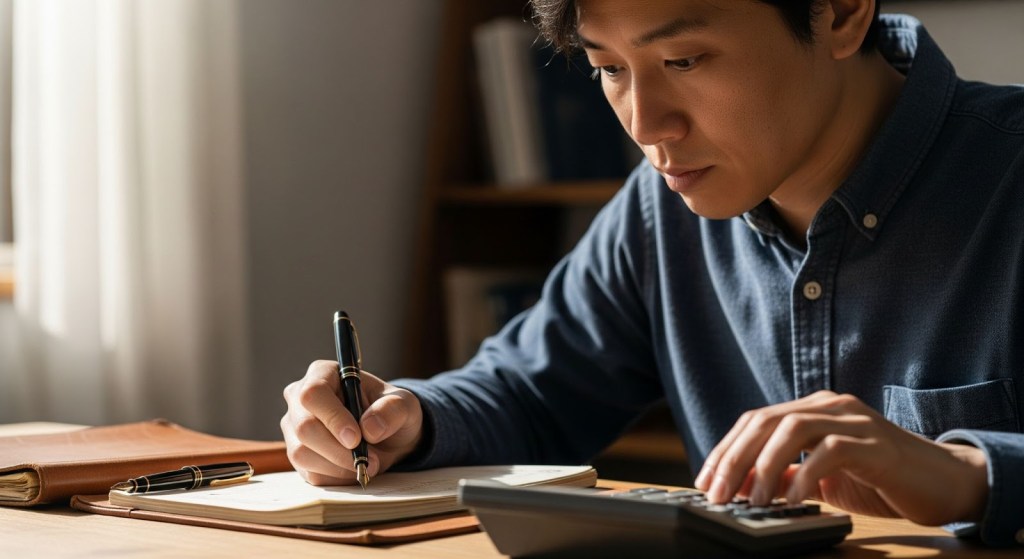
ここまでの内容を、日々の経理業務で迷ったときに参照できるよう、取引内容ごとの判断ポイントとしてまとめました。
販売目的の商品購入
販売する商品を卸売業者から購入した場合、勘定科目は「仕入高」を使用します。これは販売を目的とした「モノ」の購入にあたるためです。
商品の取得にかかる付随費用
仕入れた商品が自社に届くまでの送料なども、商品の取得に直接かかった費用(取得原価)として「仕入高」に含めます。
社内利用の備品購入
事務所で使うコピー用紙などを購入した場合、勘定科目は「消耗品費」です。販売目的ではなく、社内で消費するものが該当します。
商品販売時の送料
お客様に販売した商品を発送した際の送料は、「荷造運賃」として処理します。これは販売するためにかかった発送費用です。
外部への業務委託
デザイン業務を外部のデザイナーに依頼した場合などは、「外注費」を用います。「モノ」ではなく「サービス」の購入が判断基準です。
事務連絡の通信費
取引先に請求書を郵送した際の切手代などは「通信費」です。商品の発送ではなく、事務連絡のための費用として区別します。
【実践編】支払い方法別!仕入れの仕訳をマスターしよう
勘定科目の違いを理解したら、次はいよいよ実践です。日々の取引を帳簿に記録する「仕訳」の方法を学びましょう。ここでは、商品売買の記帳方法として最も一般的で、多くの個人事業主や中小企業で採用されている「三分法(さんぶんぽう)」に基づいて、支払い方法別に具体的な仕訳例を解説します。
基本の「三分法」とは
三分法とは、その名の通り、商品売買に関する取引を以下の3つの勘定科目を使って記録する方法です。
- 仕入(費用):商品を仕入れたときに使う
- 売上(収益):商品を販売したときに使う
- 繰越商品(資産):期末に残った在庫を管理するために決算時に使う
この方法の最大のメリットは、日々の記帳が非常にシンプルであることです。取引のたびに利益を計算する必要がなく、効率的に経理作業を進められるため、特に商品数や取引量が多い事業におすすめです。
ケース1:現金・銀行振込で仕入れた場合
最も基本的な取引パターンです。商品を仕入れ、その場で現金で支払うか、銀行振込で即時決済した場合の仕訳を見ていきましょう。
例えば、商品50,000円分を仕入れ、代金を現金で支払った場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 仕入高 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
この仕訳では、借方(左側)に費用の発生である「仕入高」を50,000円記録します。同時に、貸方(右側)で資産の減少である「現金」を50,000円記録することで、取引が完了します。銀行振込で支払った場合は、貸方の勘定科目が「普通預金」に変わるだけです。
ケース2:掛取引(後払い)で仕入れた場合
商品を先に受け取り、代金は後日(月末など)まとめて支払う「掛取引」は、企業間取引では一般的です。この場合、「買掛金(かいかけきん)」という負債の勘定科目を使います。
まず、商品100,000円分を掛で仕入れた際の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 仕入高 | 100,000円 | 買掛金 | 100,000円 |
借方には「仕入高」という費用が100,000円発生したことを記録します。貸方には、まだ代金を支払っていないため、後で支払う義務(負債)として「買掛金」を計上します。
次に、後日、買掛金100,000円が普通預金口座から支払われた際の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 買掛金 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
支払いが完了したことで、「買掛金」という負債が100,000円減少したことを借方に記録します。そして、貸方で「普通預金」という資産が100,000円減少したことを記録します。このように、掛取引では「購入時」と「支払時」の2段階で仕訳を行うのがポイントです。
ケース3:クレジットカードで仕入れた場合
クレジットカードでの支払いは非常に便利ですが、会計処理は少し特殊です。カードを利用した日と、実際に口座から代金が引き落とされる日にタイムラグがあるため、掛取引と同様に2段階での仕訳が必要になります。このときに使う負債の勘定科目は、一般的に「未払金(みばらいきん)」です。
まず、商品80,000円分を事業用クレジットカードで仕入れた際の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 仕入高 | 80,000円 | 未払金 | 80,000円 |
借方には「仕入高」という費用が80,000円発生したことを記録します。貸方には、カード会社に対して後で支払う義務(負債)が発生したため、「未払金」を80,000円計上します。
次に、後日、カード代金80,000円が普通預金口座から引き落とされた際の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未払金 | 80,000円 | 普通預金 | 80,000円 |
引き落としにより、カード会社への負債である「未払金」が80,000円減少したことを借方に記録し、貸方で「普通預金」という資産が80,000円減少したことを記録します。
ここで、「なぜ掛取引では『買掛金』なのに、クレジットカードでは『未払金』なのか」という疑問が湧くかもしれません。厳密な会計ルールでは、「買掛金」は商品の仕入れなど、企業の主たる営業活動から生じる債務に使い、「未払金」はそれ以外の取引(消耗品の購入など)から生じる債務に使うと区別されています。
クレジットカードでの支払いは、直接の仕入れ先ではなくカード会社という金融機関への支払い義務となるため、理論上は「未払金」で処理するのがより正確です。この区別により、「仕入先への支払い残高(買掛金)」と「その他の支払い残高(未払金)」を分けて管理でき、より詳細な財務分析が可能になります。
ただし、実務上はクレジットカード払いをすべて「未払金」で統一するケースも多く、税務上はそれで問題になることはありません。自社の管理のしやすさに応じてルールを統一することが重要です。
個人事業主なら必見!特有の仕入れルールと注意点
法人の会計と異なり、個人事業主の会計には特有の処理がいくつか存在します。事業とプライベートの境界が曖昧になりがちな個人事業主だからこそ、これらのルールを正しく理解し、適切に処理することが重要です。ここでは、特に「開業前の仕入れ」と「商品の家事消費」という2つのポイントに絞って解説します。
開業前に支払った仕入れ代金の扱い方
事業を始めるにあたり、開業日より前に商品や材料を仕入れることはよくあります。これらの費用は、事業を開始するための準備費用として、もちろん経費として認められます。
ポイントは、これらの費用を開業日の日付でまとめて記帳することです。そして、支払いは事業用の資金からではなく、個人のポケットマネーから出しているはずなので、貸方の勘定科目は「事業主借(じぎょうぬしかり)」を使います。
「事業主借」とは、事業主個人のお金を事業のために使った場合に用いる、個人事業主特有の勘定科目です。事業主が事業に対してお金を「貸した」というイメージで捉えると分かりやすいでしょう。
開業日を迎える前に、自己資金で販売用商品を150,000円分仕入れていた場合、これを開業日に以下のように記帳します。
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 開業日 | 仕入高 | 150,000円 | 事業主借 | 150,000円 |
このように処理することで、開業前の準備費用を漏れなく事業の経費に算入できます。
商品をプライベートで使った「家事消費」の処理
飲食店を営む事業主がお店の食材で家族の食事を作ったり、雑貨店主がお店の商品を友人にプレゼントしたりすることがあります。このように、事業用の商品(棚卸資産)をプライベートで消費することを「家事消費(かじしょうひ)」と言います。
この家事消費は、たとえお金のやり取りがなくても、「家事消費等」という勘定科目を使って売上として計上する必要があります。もし家事消費を計上しないと、その商品の「仕入高」だけが費用として計上され、対応する「売上」がないことになります。
結果として、事業の利益が不当に低く計算され、納めるべき所得税が少なくなってしまうからです。これを防ぐために、家事消費を売上とみなして計上するルールが定められています。
家事消費として売上に計上すべき金額には、明確なルールがあります。原則は「その商品の通常の販売価格」ですが、特例として、以下のいずれか高い方の金額で計上することが認められています。
- その商品の仕入価格
- その商品の通常の販売価格の70%
例えば、販売価格1,000円、仕入価格600円の商品を自家消費したとします。この場合、仕入価格は600円、販売価格の70%は700円(1,000円 × 70%)です。2つを比較すると700円の方が高いため、700円を家事消費の金額として売上に計上します。
この場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事業主貸 | 700円 | 家事消費等 | 700円 |
貸方(右側)には「家事消費等」という収益(売上)が700円発生したことを記録します。借方(左側)には、事業主が事業の商品をプライベートで使ったため、事業から個人へ資産が移動したと考え、「事業主貸(じぎょうぬしかし)」を用います。これは事業主が事業からお金やモノを「借りた(引き出した)」というイメージです。
家事消費の処理は、単なる税金対策のルールではありません。会計の基本原則である「企業実体の公準(事業と個人は別人格と考える)」を実践する良いトレーニングになります。日頃から事業とプライベートの金銭の区別を意識することで、事業の本当の収益性を正確に把握する力が養われ、より的確な経営判断につながっていくのです。
確定申告で慌てない!青色申告と仕入れの重要ポイント

日々の記帳の最終目標は、年に一度の確定申告を正しく行うことです。特に、最大65万円の特別控除など、税制上のメリットが大きい青色申告を行う事業者にとって、仕入れに関する正確な記録は不可欠です。ここでは、確定申告を見据えた仕入れの重要ポイントを解説します。
正確な利益は「棚卸し」から生まれる
どれだけ毎日丁寧に仕訳をしていても、期末に「棚卸し(たなおろし)」を行わなければ、その年の正確な利益は計算できません。棚卸しとは、期末時点(個人事業主の場合は12月31日)で、売れ残っている商品や材料の在庫を種類ごとに数え、その金額を計算する作業のことです。
なぜ棚卸しが重要なのでしょうか。それは、正しい「売上原価」を算出するために不可欠だからです。前述の通り、売上原価の計算式は以下の通りです。
売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高 – 期末商品棚卸高
この式の「期末商品棚卸高」は、実際に棚卸しをしなければ確定できません。棚卸しを怠ると、売上原価が不明となり、結果として売上総利益や事業所得を正しく計算することができなくなってしまいます。
なお、在庫の評価方法について税務署に届出をしていない場合は、「最終仕入原価法」で評価します。これは、期末に最も近い日に仕入れた単価を、期末の在庫数量すべてに乗じて評価額を計算する方法です。
2023年10月から必須!インボイス制度と仕入税額控除
2023年10月1日に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、特に消費税の課税事業者にとって、仕入れの記帳方法に大きな影響を与えました。
この制度導入に伴い、青色申告決算書や収支内訳書(白色申告)の様式が変更され、「売上金額の明細」および「仕入金額の明細」という欄が追加されました。ここには、主要な取引先の名称や所在地に加え、「登録番号(法人番号)」を記載する必要があります。
この登録番号の管理がなぜ重要かというと、消費税の「仕入税額控除」を受けるための要件と密接に関わっているからです。仕入税額控除とは、納める消費税額を計算する際に、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことができる仕組みです。
インボイス発行事業者(登録番号を持つ事業者)からの課税仕入れでなければ、原則としてこの仕入税額控除は受けられません(ただし、免税事業者からの仕入れについては、当面の間、一定割合を控除できる経過措置が設けられています)。
つまり、登録番号のない免税事業者などからの仕入れが多いと、その分、仕入税額控除が受けられず、結果的に納める消費税額が増えてしまう可能性があるのです。
この変更は、日々の経理業務を根本から変えました。これまでの記帳は過去の取引を記録する作業でしたが、インボイス制度下では、仕入れ取引一つひとつが将来の納税額を左右する「財務リスク管理」の側面を持つようになりました。
仕入先を選ぶ際にも、価格や品質だけでなく、相手がインボイス発行事業者であるかどうかが重要な判断基準となります。日々の記帳においても、インボイス発行事業者からの仕入れと、そうでないものを明確に区別して管理することが不可欠です。
帳簿と書類はいつまで保管するのか
確定申告が終わっても、帳簿や関連書類はすぐに処分してはいけません。法律で保存期間が定められています。青色申告の場合、以下の書類は原則として7年間の保存が義務付けられています。
- 帳簿類:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳など
- 決算関係書類:損益計算書、貸借対照表など
- 取引に関する書類:領収書、預金通帳、請求書、契約書など
特に、インボイス制度における適格請求書(インボイス)やその写しについても、7年間の保存が必要です。これらの書類は、税務調査の際に提示を求められる重要な証拠となりますので、きちんと整理し、定められた期間、大切に保管してください。
まとめ
本記事では、「仕入れ」の勘定科目を軸に、個人事業主や小規模法人が押さえるべき経理の基本から応用までを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを再確認しましょう。
仕入れの定義
仕入れは「販売目的」で購入した商品や原材料のことで、会計上は「費用」に分類されます。商品本体の価格だけでなく、手元に届くまでの送料や関税などの付随費用も「仕入高」に含めて計上します。
関連科目との違い
「売上原価(売れた分だけのコスト)」「消耗品費(社内利用目的)」「外注費(サービスの購入)」「荷造運賃(販売時の送料)」など、混同しやすい勘定科目との違いは、取引の目的とタイミングで正確に判断することが重要です。
支払い方法別の仕訳
掛取引では「買掛金」、クレジットカード払いでは「未払金」という負債勘定を使い、購入時と支払時の2段階で仕訳を行うのが基本です。
個人事業主特有のルール
開業前に自己資金で支払った仕入れは、開業日付けで「事業主借」を使って経費に計上します。また、事業の商品をプライベートで消費した「家事消費」は、ルールに則って計算し、「家事消費等」として売上に計上する義務があります。
確定申告との関連
正確な利益計算のためには期末の「棚卸し」が不可欠です。また、インボイス制度の開始により、仕入税額控除を受けるためには、仕入先の登録番号を管理し、適格請求書を7年間保存することが極めて重要になりました。
日々の取引を正しく仕訳し、記録していくことは、時に地道で複雑な作業に感じるかもしれません。しかし、この正確な記録こそが、自社の経営状態を映し出す鏡であり、事業を守り、未来の成長へと導くための羅針盤となります。この記事が、皆様の経理業務に対する不安を解消し、自信を持って事業を推進していくための一助となれば幸いです。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…