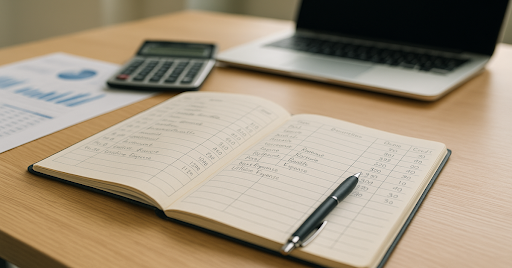
「また領収書がたまってしまった」「確定申告の時期が近づくと憂鬱になる」。個人事業主や中小企業の経営者にとって、経理業務は悩みの種になりがちです。しかし、日々の取引を正しく記録する「仕訳帳」の付け方を一度マスターしてしまえば、その悩みは驚くほど軽くなります。
この記事を読むことで、単に仕訳帳の記入方法を学ぶだけではなく、お金の流れを正確に把握し、データに基づいた的確な経営判断ができるようになります。さらに、青色申告特別控除といった大きな節税メリットを最大限に活用し、自信を持って確定申告に臨めるようになるでしょう。
「借方」「貸方」といった専門用語に戸惑う必要はありません。この記事では、簿記の知識がまったくない方でも理解できるよう、一つひとつを丁寧に分解して解説します。
手書きから会計ソフトまで、ご自身に最適な方法が必ず見つかります。どんぶり勘定から卒業し、盤石な経営基盤を築く第一歩を踏み出しましょう。
目次
そもそも仕訳帳とは?経営の根幹を支える会計の第一歩
事業を始めると、売上や経費の支払いなど、日々お金の動きが発生します。これらの取引を一つひとつ記録していくのが会計の基本です。その中でも、すべての記録の出発点となるのが「仕訳帳」です。
仕訳帳の役割と目的を理解する
仕訳帳とは、事業で発生したすべての取引を、日付順に記録するための帳簿です。いつ、どのような取引があったのかを時系列で記録するため、「会社の金融活動の日記」のようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。
仕訳帳の最も重要な目的は、日々の取引を漏れなく、かつ正確に記録し、後続の会計処理の基礎となる信頼性の高いデータを作成することにあります。この帳簿は、複式簿記という会計ルールにおける「主要簿」の一つに位置づけられており、法律的にも作成が義務付けられる非常に重要な書類です。
仕訳帳がなければ始まらない、総勘定元帳との関係性
仕訳帳とともにもう一つ重要な主要簿として「総勘定元帳」があります。この二つの帳簿の関係性を理解することが、会計全体の流れを掴む鍵となります。
仕訳帳は、「いつ、どのような取引があったか」を日付順に記録します。取引の全体像を時系列で確認するための帳簿です。
一方で、総勘定元帳は、「特定の勘定科目(現金、売掛金など)が、いつ、いくら増減したか」を勘定科目ごとに記録します。特定の資産や費用の残高や動きを確認するための帳簿です。
会計処理は以下の流れで進みます。
- 取引が発生する。
- その取引を仕訳帳に日付順で記録する。
- 仕訳帳に記録した内容を、関連する勘定科目のページ(総勘定元帳)に転記する。
- 期末に、総勘定元帳の各勘定科目の残高をもとに、貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成する。
このように、仕訳帳はすべての取引の一次記録であり、総勘定元帳や決算書を作成するための大元となるデータです。もし仕訳帳がなければ、総勘定元帳を作ることができず、結果的に正確な決算書も作成できません。
この二つの帳簿を分けることには、明確な理由があります。もし総勘定元帳しかなければ、現金の残高はわかっても、その残高がどのような取引の積み重ねで形成されたのかという詳細な経緯がわかりにくくなります。
一方で、仕訳帳だけでは、特定の日に何があったかはわかりますが、「今、現金はいくらあるのか」を把握するためには、最初からすべての取引を拾い集計し直さなければならず、非常に手間がかかります。
つまり、仕訳帳は取引の「物語性」と「追跡可能性」を担保し、総勘定元帳は「分析のしやすさ」と「要約性」を担保するという、それぞれ異なる重要な役割を担っているのです。この両輪が、正確で透明性の高い会計システムを支えています。
これだけは押さえたい!仕訳の基本ルールと勘定科目

仕訳帳を正しくつけるためには、複式簿記の基本的なルールを理解する必要があります。難しく聞こえるかもしれませんが、いくつかのポイントを押さえれば誰でも理解できます。
すべての取引は2つの側面を持つ 借方と貸方の基本
複式簿記の最も基本的な考え方は、すべての取引には「原因」と「結果」という2つの側面があり、その金額は必ず一致するというものです。例えば、「現金で備品を買った」という取引は、「備品が増えた(結果)」ことと「現金が減った(原因)」という2つの側面から捉えられます。
この2つの側面を記録するために使うのが「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」です。これは単に帳簿の左側と右側の列の名称です。覚え方として、借方の「り」は左に払う字なので左側、貸方の「し」は右に払う字なので右側、と覚えると混乱しにくいでしょう。
取引を借方と貸方に振り分けるには、まずその取引がどのグループに属するかを理解する必要があります。会計上の取引は、すべて以下の5つのグループに分類されます。
- 資産:会社が所有する財産(現金、預金、売掛金、備品など)。
- 負債:会社が将来支払う義務があるもの(買掛金、借入金など)。
- 純資産:資産から負債を差し引いた、会社の純粋な財産(資本金など)。
- 収益:事業活動によって得られた収入(売上、受取利息など)。
- 費用:収益を得るためにかかった支出(仕入、給料、家賃など)。
そして、これらのグループには、増えたときに借方と貸方のどちらに書くかという「ホームポジション」が決まっています。以下の表は、仕訳を行う上での最も重要なルールをまとめたものです。
| グループ | 借方(左側)に記入する場合 | 貸方(右側)に記入する場合 |
| 資産 | 増加 | 減少 |
| 負債 | 減少 | 増加 |
| 純資産 | 減少 | 増加 |
| 費用 | 発生(増加) | 取り消し(減少) |
| 収益 | 取り消し(減少) | 発生(増加) |
このルールさえ覚えてしまえば、どんな取引でも仕訳ができるようになります。例えば、「現金(資産)が増えた」ら借方へ、「現金(資産)が減った」ら貸方へ記入します。「売上(収益)が発生した」ら貸方へ記入します。
取引を分類するラベル「勘定科目」の選び方
「勘定科目」とは、上記5つのグループをさらに細かく分類するための具体的なラベルのことです。例えば、「現金」や「普通預金」、「売掛金」はすべて「資産」グループに属する勘定科目です。
勘定科目を正しく選ぶことは、後から帳簿を見返したときに、何にお金を使ったのかを正確に把握するために非常に重要です。初心者が勘定科目を選ぶ際には、以下の4つのルールを意識しましょう。
継続して同じ科目を使う(継続性の原則)
一度、ある取引に対して使う勘定科目を決めたら、その後も同じ種類の取引には同じ勘定科目を使い続けましょう。例えば、ガソリン代を一度「旅費交通費」で処理したら、次からも「旅費交通費」で処理します。途中で「消耗品費」などに変えてしまうと、期間ごとの費用を正しく比較できなくなります。
誰が見てもわかりやすい名称を使う
会計帳簿は、自分だけでなく税理士や税務調査官など第三者が見る可能性もあります。そのため、一般的で理解しやすい勘定科目名を使うことが重要です。会計ソフトに初期設定されている勘定科目を使うのが最も安全です。
「雑費」を使いすぎない
どの勘定科目に当てはまるかわからない少額で重要性の低い費用は、「雑費」として処理することができます。しかし、雑費は非常に便利な科目である反面、使いすぎには注意が必要です。
雑費の金額が経費全体の中で突出して大きいと、税務調査の際に「使途が不明瞭な経費が多い」と判断され、内容を厳しくチェックされる原因になります。雑費は、あくまで他のどの勘定科目にも分類できない、臨時的で少額な支出に限定して使用するように心がけましょう。目安として、販売費及び一般管理費全体の5%から10%程度に収めるのが望ましいとされています。
社内でルールを統一する
複数人で経理業務を行う場合は、どの取引にどの勘定科目を使うか、社内でルールを統一しておくことが不可欠です。担当者によって仕訳の仕方が異なると、正確な経営状況の把握が困難になります。
仕訳帳の書き方について丁寧に解説
基本ルールを理解したら、次は実際に仕訳帳を書いてみましょう。具体的な取引例をもとに、丁寧に解説します。
仕訳帳を構成する必須項目
一般的な仕訳帳は、以下の項目で構成されています。
- 日付
取引が発生した年月日を記入します。 - 摘要
取引の内容を具体的に記入します。借方勘定科目、貸方勘定科目、そして取引の詳細(取引先、品名など)を記載します。 - 元丁(元帳)
総勘定元帳のどのページに転記したかを示すページ番号を記入します。手書きの場合に重要ですが、会計ソフトでは自動で関連付けられるため、通常は空欄です。 - 金額欄(借方・貸方)
取引の金額を、借方と貸方に分けて記入します。借方と貸方の合計金額は必ず一致します。
ケース別・仕訳記入例
ここでは、個人事業主や小規模な会社でよく発生する4つの取引を例に、仕訳の考え方と記入方法を見ていきましょう。
例1:10,000円の商品を現金で販売した
この取引は、「商品が売れて10,000円の現金が増えた」と考えます。結果として現金(資産)が10,000円増加し、原因として売上(収益)が10,000円発生したことになります。
資産の増加は「借方」なので、借方に「現金 10,000」と記入します。収益の発生は「貸方」なので、貸方に「売上 10,000」と記入します。
| 日付 | 摘要 | 元丁 | 借方 | 貸方 |
| 4/1 | 現金 | 10,000 | ||
| 売上 | 10,000 | |||
| A商品売上 |
例2:50,000円の商品を掛けで販売した(代金は後日受け取り)
この取引は、「商品が売れたが、代金は後でもらう権利(売掛金)を得た」と考えます。結果として売掛金(資産)が50,000円増加し、原因として売上(収益)が50,000円発生しました。
資産の増加は「借方」なので、借方に「売掛金 50,000」と記入します。収益の発生は「貸方」なので、貸方に「売上 50,000」と記入します。
| 日付 | 摘要 | 元丁 | 借方 | 貸方 |
| 4/5 | 売掛金 | 50,000 | ||
| 売上 | 50,000 | |||
| B社 B商品売上 |
例3:事務用品(ボールペン)5,000円を現金で購入した
この取引は、「事務用品を買うために、5,000円の現金を支払った」と考えます。結果として消耗品費(費用)が5,000円発生し、原因として現金(資産)が5,000円減少しました。
費用の発生は「借方」なので、借方に「消耗品費 5,000」と記入します。資産の減少は「貸方」なので、貸方に「現金 5,000」と記入します。
| 日付 | 摘要 | 元丁 | 借方 | 貸方 |
| 4/10 | 消耗品費 | 5,000 | ||
| 現金 | 5,000 | |||
| C文具店 ボールペン代 |
例4:取引先訪問のため電車代1,000円を現金で支払った
この取引は、「移動のために、1,000円の現金を支払った」と考えます。結果として旅費交通費(費用)が1,000円発生し、原因として現金(資産)が1,000円減少しました。
費用の発生は「借方」なので、借方に「旅費交通費 1,000」と記入します。資産の減少は「貸方」なので、貸方に「現金 1,000」と記入します。
| 日付 | 摘要 | 元丁 | 借方 | 貸方 |
| 4/15 | 旅費交通費 | 1,000 | ||
| 現金 | 1,000 | |||
| JR新宿駅-渋谷駅 (D社訪問) |
「摘要欄」で未来の自分を助ける書き方のコツ
仕訳帳の中で、数字と同じくらい重要なのが「摘要欄」です。摘要欄は、その取引の背景にある「物語」を記録する場所です。数か月後、あるいは数年後に帳簿を見返したとき、この摘要欄の情報がなければ、「この5,000円は何に使ったのか」とわからなくなってしまいます。
特に税務調査では、調査官は勘定科目と金額だけでなく、摘要欄を見て取引の実態を把握します。摘要欄が具体的でわかりやすければ、取引の正当性をスムーズに説明できます。未来の自分や税理士、税務調査官を助けるために、以下のポイントを押さえた摘要を心がけましょう。
- 交通費:単に「交通費」ではなく、「利用区間(例:〇〇駅-△△駅)」「交通手段(例:電車代、タクシー代)」「目的(例:A社訪問のため)」を記載します。
- 消耗品費:単に「文具代」ではなく、「購入店(例:〇〇文具店)」「品名(例:コピー用紙500枚)」を記載します。
- 交際費:税務上、特に厳しく見られる科目です。「会食費」だけでは不十分です。「会食場所(例:レストラン〇〇)」「相手先(例:A社〇〇様)」「参加人数(例:2名)」まで記載することで、事業関連性が明確になります。
摘要欄の書き方に絶対的なルールはありませんが、「誰が、いつ見ても、この取引の内容がわかるか」を基準に、必要な情報を簡潔に記載することが重要です。
どの方法がベスト?仕訳帳の作成方法3選を徹底比較
仕訳帳を作成する方法は、大きく分けて「手書き」「Excel」「会計ソフト」の3つがあります。それぞれに特徴があるため、ご自身の事業規模や簿記の知識レベルに合わせて最適な方法を選びましょう。
手書きで作成する方法
市販の仕訳帳ノートなどを使って手書きで作成する方法は、簿記の仕組みやお金の流れを体感的に理解できるため、学習効果が非常に高いという利点があります。初期費用もノート代だけで済みます。
しかし、記入、計算、転記をすべて手作業で行うため、非常に時間がかかります。計算ミスや転記ミスが発生しやすく、ミスを発見して修正するのも大変です。また、紙の帳簿は保管場所を取る上、火災や紛失のリスクも伴います。
手書きで帳簿を訂正する場合は、修正液や修正テープの使用は避けてください。公的な書類では、訂正の履歴がわかるようにする必要があります。間違えた箇所に赤色の二重線を引き、その上や近くの余白に正しい内容を記入するのが正式な訂正方法です。必要に応じて、二重線の上に訂正印を押します。
Excelテンプレートを利用する方法
Excelなどの表計算ソフトを使って仕訳帳を作成する方法もあります。会計ソフトメーカーなどが無料で高品質なテンプレートを配布しており、これを活用できます。
テンプレートを利用すれば初期費用はほぼかかりません。合計金額の計算などを自動化できるため、手書きに比べて計算ミスを減らせる点が魅力です。
一方で、取引の入力自体は手作業になります。仕訳帳から総勘定元帳への転記も手動で行う必要があり、手間がかかる点はデメリットです。また、誤って数式を消してしまったり、ファイルの管理が煩雑になったりするリスクも考慮する必要があります。
会計ソフトを利用する方法
弥生会計、freee、マネーフォワード クラウドといった会計ソフトを利用する方法は、経理業務の効率化において最も効果的です。
銀行口座やクレジットカードを連携させれば、取引データを自動で取り込み、AIが勘定科目を推測して仕訳を自動で作成してくれます。仕訳帳を入力すれば、総勘定元帳や決算書が自動で作成されるため、転記ミスが起こりません。確定申告の書類作成までサポートしてくれる機能もあり、経理業務全体を劇的に効率化できます。
月額または年額の利用料がかかること、操作に慣れが必要な場合があることがデメリットとして挙げられますが、近年のクラウド会計ソフトは初心者でも直感的に使えるように設計されています。
事業を始めたばかりで取引量が少ないうちはExcelで基本を学び、取引が増えてきたら会計ソフトに移行するというのも一つの賢い選択です。しかし、最初から会計ソフトを導入すれば、早い段階で経理業務の負担を軽減し、本業に集中する時間を確保できるでしょう。
| ソフト名 | 特徴 | 料金目安(個人事業主向け) |
| やよいの青色申告 オンライン | シンプルな機能とわかりやすい操作性。サポート体制が充実しており、会計ソフトが初めてでシンプルな操作性を求める人に適しています。 | 年間8,000円~(税抜) ※初年度無料キャンペーンあり |
| freee会計 | 簿記の知識がなくても、質問に答える形式で直感的に入力可能。請求書発行から経費精算まで幅広く対応し、経理業務全体を効率化したい人におすすめです。 | 月額1,180円~(税抜) |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 豊富な機能と連携サービスの多さが強み。仕訳の自動提案の精度が高く、複数の銀行口座やカードを連携させてお金の管理を一元化したい人に最適です。 | 月額800円~(税抜) |
仕訳帳と確定申告 税務で損をしないための必須知識
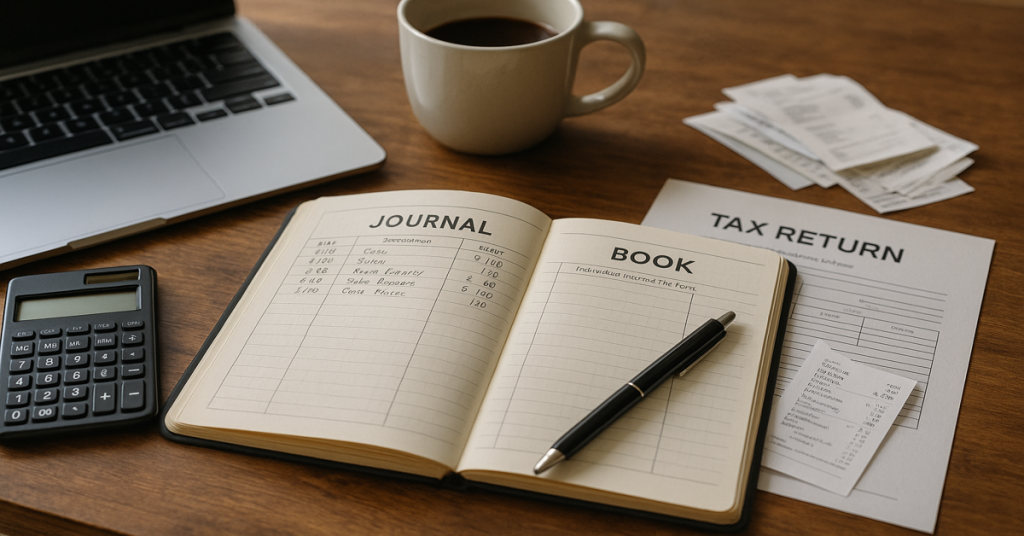
日々の仕訳帳の作成は、年に一度の確定申告のためにあると言っても過言ではありません。ここでは、仕訳帳が確定申告においていかに重要であるかを解説します。
なぜ仕訳帳が確定申告に不可欠なのか
確定申告書に記入する売上や経費の金額は、1年間の取引を仕訳帳に記録し、総勘定元帳に集計した結果です。つまり、仕訳帳は申告内容の根拠となる最も重要な基礎資料なのです。
確定申告の際に仕訳帳そのものを税務署に提出する必要はありませんが、法律で保存が義務付けられており、税務調査の際には提示を求められます。もし帳簿を作成していなかったり、内容が不十分だったりすると、以下のような厳しいペナルティが課される可能性があります。
- 推計課税:税務署が同業他社のデータなどから所得を「推計」して税額を決定します。これは通常、納税者にとって不利な計算になることが多いです。
- 青色申告の承認取り消し:後述する青色申告の様々な特典が受けられなくなります。
- 加算税・延滞税:本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとしての税金が課されます。
青色申告の特別控除(最大65万円)を目指すなら複式簿記が必須
個人事業主が確定申告を行う際には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告を選択すると、最大65万円の所得控除(青色申告特別控除)をはじめ、多くの税制上の優遇措置を受けることができます。
この最大65万円の控除を受けるための絶対条件が、「複式簿記」で記帳を行うことです。そして、複式簿記の根幹をなすのが、これまで解説してきた「仕訳帳」と「総勘定元帳」の作成です。つまり、日々の地道な仕訳作業が、最終的に数十万円単位の節税に直結するのです。
インボイス制度導入による仕訳への影響
2023年10月から始まったインボイス制度は、特に消費税の納税義務がある事業者(課税事業者)の仕訳に影響を与えます。
制度の核心は、消費税の仕入税額控除(売上にかかる消費税から仕入にかかった消費税を差し引くこと)を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になったことです。これにより、仕入や経費の支払いがあった際には、受け取った請求書や領収書がインボイスの要件を満たしているかを確認し、仕訳を区別する必要が出てきました。
例えば、適格請求書発行事業者から11,000円(うち消費税1,000円)の備品を購入した場合、支払った消費税1,000円は「仮払消費税」として仕入税額控除の対象になります。
| 借方 | 貸方 |
| 備品 10,000 | 現金 11,000 |
| 仮払消費税 1,000 |
一方、免税事業者などインボイスを発行できない相手から11,000円(消費税相当額1,000円を含む)の備品を購入した場合、原則として消費税相当額1,000円は仕入税額控除の対象になりません(経過措置あり)。そのため、消費税額を含めた11,000円全額を費用(備品)として計上します。
| 借方 | 貸方 |
| 備品 11,000 | 現金 11,000 |
このように、取引相手がインボイス発行事業者かどうかによって、会計処理と納税額が変わってくるため、日々の仕訳の重要性がさらに増しています。
知らないと危険!仕訳帳の法律上の保存期間
仕訳帳は作成して終わりではありません。法律によって、一定期間の保存が義務付けられています。このルールを守らないと、ペナルティの対象となる可能性があるため、正確に理解しておきましょう。
法律で定められた帳簿の保管義務
帳簿の保存期間は、主に「会社法」と「法人税法(個人の場合は所得税法)」という2つの法律で定められています。注意すべきは、それぞれの法律で定められている期間が異なる点です。
- 会社法:会計帳簿およびその事業に関する重要な資料について10年間の保存を義務付けています。
- 法人税法・所得税法:帳簿書類について、原則として7年間の保存を義務付けています。
法人の場合、会社法と法人税法の両方の適用を受けます。このような場合は、より長い方の期間に合わせて保存するのが原則です。したがって、法人は仕訳帳や総勘定元帳を10年間保存しておけば、両方の法律の要件を満たすことができ安心です。
個人事業主の場合は、所得税法に基づき、原則として7年間の保存が必要です。事業形態ごとの保存期間を以下の表にまとめました。
| 事業形態 | 保存すべき帳簿 | 保存期間(原則) | 注意事項 |
| 法人 | 仕訳帳、総勘定元帳など | 10年間 | 税法上は原則7年だが、会社法では10年。欠損金(赤字)が生じた事業年度の帳簿は税法上も10年間の保存が必要。 |
| 個人事業主(青色申告) | 仕訳帳、総勘定元帳など | 7年間 | 現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳など)も7年。ただし、前々年分の所得が300万円以下の場合は5年。 |
| 個人事業主(白色申告) | 収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 7年間 | 業務に関して作成したその他の帳簿(任意帳簿)や請求書・領収書などは5年間。 |
この保存期間は、法人の場合は事業年度の確定申告提出期限の翌日から、個人事業主の場合は確定申告期限の翌日(通常は3月16日)からカウントします。期間が終了するまで、帳簿はいつでも取り出せる状態で、適切に保管してください。
まとめ
仕訳帳の作成は、単なる面倒な事務作業ではありません。それは、ご自身の事業の健康状態を正確に把握し、適切な経営判断を下し、そして税務上のメリットを最大限に享受するための、最も基本的で強力なツールです。
今回解説したポイントを再確認しましょう。
- 仕訳帳は、すべての取引を日付順に記録する「主要簿」であり、会計処理の出発点です。
- 「借方」と「貸方」のルールと、5つの勘定科目グループを理解すれば、すべての取引を仕訳できます。
- 作成方法は手書き、Excel、会計ソフトがありますが、初心者のうちから会計ソフトを導入すると、業務が劇的に効率化します。
- 最大65万円の青色申告特別控控除を受けるためには、仕訳帳を含む複式簿記での記帳が必須条件です。
- 作成した仕訳帳は、法律で定められた期間(法人は10年、個人は7年が目安)きちんと保存する義務があります。
最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、一つひとつの取引を丁寧に仕訳していくことで、お金の流れは確実に「見える化」されます。その積み重ねが、漠然とした不安を自信に変え、あなたの事業をより強く、たくましく成長させてくれるはずです。
まずは無料のExcelテンプレートをダウンロードしてみる、あるいは会計ソフトの無料トライアルに申し込んでみるのはいかがでしょうか。その小さな一歩が、事業の未来を大きく変えるきっかけとなるでしょう。








建設業の2024年問題に向き合う|作業日報の効率化とDXで実…
日々の作業日報に追われる時間を短縮し、しっかりと休息を取る。あるいは、家族と過ごす時間を少しでも増や…