
法人を経営するうえで、税金の悩みは尽きないものです。特に「法人住民税」は、その仕組みが少し複雑なため、「いったいいくら支払うのか」「赤字でも払う必要があるのか」といった不安を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。
この税金への漠然とした不安は、適切な資金計画の妨げとなり、ときには予期せぬ出費につながる可能性もあります。しかし、法人住民税の仕組みを正しく理解すれば、その不安を解消し、納税を的確に管理することが可能です。
本記事を最後まで読めば、法人住民税がどのような税金で、法人税や法人事業税とどう違うのかを明確に理解できます。さらに、具体的な計算方法を学び、自社の納税額をシミュレーションできるようになります。
また、赤字決算や会社の設立・休業といった特別な状況でどう対応すべきか、そして申告と納付の期限を確実に守るための実務知識まで、網羅的に解説します。
税務の専門家でなくても理解し、実践できるように構成されています。計算例や具体的なシナリオ別の対策を通じて、貴社の経営にすぐに役立つ知識を提供します。
法人住民税を「よくわからないコスト」から「管理できる経費」へと変え、より賢明な経営判断を下すための一助となれば幸いです。
目次
法人住民税とは 法人税・法人事業税との違い
法人が納める税金には、法人税、法人事業税、そして法人住民税など、いくつかの種類があります。これらをまとめて「法人税等」と呼ぶこともありますが、それぞれは課税主体や目的がまったく異なります。まずは、法人住民税がどのような位置づけの税金なのかを正確に把握しましょう。
地域社会を支える「会費」としての目的
法人住民税とは、法人が事業所を置く都道府県および市町村へ納める地方税です。法人は個人と同じように、道路の整備、ごみの収集、警察や消防といった、その地域が提供するさまざまな行政サービスを日々利用しています。
そのため、法人は地域社会を構成する一員として、これらの行政サービスを維持するための費用を負担するべきである、という考え方に基づいています。いわば、地域社会の「会費」のような性格を持つ税金といえるでしょう。この「会費」という性質が、後述する赤字でも納税義務が生じる理由につながります。
国税である法人税との違い
法人住民税と最も混同されやすいのが法人税です。この2つの決定的な違いは、納税先と課税対象にあります。
法人税は、法人の事業活動によって得られた所得(利益)に対して課される国税です。納税先は国(税務署)であり、国の財源となります。したがって、所得がなければ(つまり赤字であれば)、原則として法人税は課されません。
一方、法人住民税は、法人が事業所を置く地方自治体(都道府県と市町村)に納める地方税です。課税の根拠は、所得だけでなく、法人の存在そのものにもあります。
このように、法人税が「国の運営費を利益に応じて負担するもの」であるのに対し、法人住民税は「地方の行政サービス益に対する負担を、その地域に存在することで応分に支払うもの」という根本的な違いがあるのです。
同じ地方税である法人事業税との違い
もう一つ、地方税である法人事業税との違いも理解しておく必要があります。法人事業税も、法人が事業を行う都道府県に納める地方税です。
法人事業税は、法人が道路や港湾などの公共施設を利用し、さまざまな行政サービスを受けて事業活動を行っていることに対して課される税金です。こちらも所得が主な課税標準となります。
法人住民税が「地域社会の構成員」であること自体に着目するのに対し、法人事業税は「事業活動そのもの」により着目した税金といえます。
法人住民税を構成する「均等割」と「法人税割」
法人住民税の仕組みを理解するうえで最も重要なのが、この税金が「均等割(きんとうわり)」と「法人税割(ほうじんぜいわり)」という2つの要素の合計で構成されている点です。この2つは性質が大きく異なるため、それぞれを分けて考える必要があります。
均等割 企業の規模で決まる固定費
均等割は、法人の所得(利益)の有無にかかわらず、資本金の額や従業員数といった企業の規模に応じて課される、定額の税金です。これは、前述した「地域社会の会費」という性格を最も色濃く反映した部分です。
たとえ事業が赤字であっても、法人がその地域に存在する限り、行政サービスは提供され続けます。そのため、その費用の一部は負担する必要がある、という考え方に基づいています。
したがって、均等割は赤字決算の場合でも納税義務があります。これは法人住民税を考えるうえで、絶対に押さえておかなければならないポイントです。
法人税割 企業の利益に連動する変動費
一方、法人税割は、国に納める法人税の額を計算の基礎(課税標準)として課される税金です。法人税は企業の利益に応じて算出されるため、法人税割もまた、間接的に企業の利益に連動する変動費的な性格を持ちます。
計算式は「法人税額 × 税率」となり、もし企業の利益がゼロまたは赤字で、納めるべき法人税額が0円であれば、法人税割も0円になります。利益が出ている法人ほど負担が大きくなる、応能負担の考え方に基づいた部分です。
均等割と法人税割の比較
この2つの違いを整理すると、以下の表のようになります。この違いを理解することが、法人住民税を正しく把握するための第一歩です。
| 特徴 | 均等割 | 法人税割 |
| 計算の基礎 | 資本金等の額、従業員数 | 法人税額 |
| 課税の目的 | 地域社会の構成員としての会費 | 利益に応じた負担 |
| 赤字の場合 | 納税義務あり | 納税義務なし |
| 性質 | 固定費的 | 変動費的 |
法人住民税の具体的な計算方法
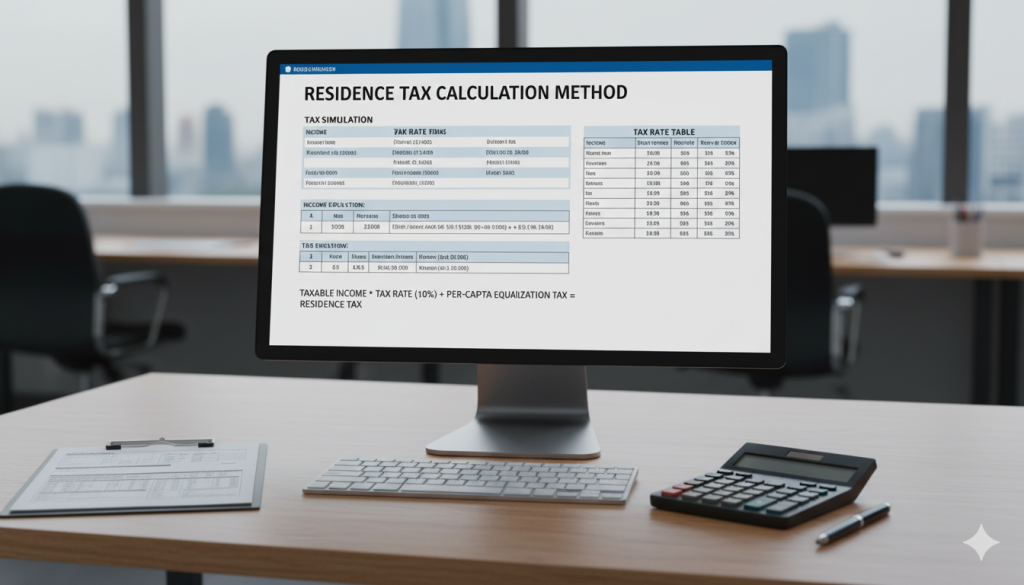
それでは、実際に法人住民税がどのように計算されるのかを、具体例を交えながら見ていきましょう。計算は「均等割」と「法人税割」をそれぞれ算出し、最後に合算する流れで進めます。
均等割の計算方法
資本金と従業員数で税額を確認する
均等割の金額は、法律で定められた標準税率を基に、各地方自治体が条例で定めています。税額は、事業年度の末日時点の「資本金等の額」と「市町村内の従業員数」の区分によって決まります。
例えば、資本金1,000万円以下で従業員数50人以下の法人の場合、標準的な税額は以下のようになります。
- 都道府県民税:20,000円
- 市町村民税:50,000円
- 合計:70,000円
自社の正確な税額を知るには、事業所がある都道府県および市町村のウェブサイトなどで税率表を確認する必要があります。多くの自治体では、財政状況に応じて標準税率よりも高い「超過税率」を採用している場合があるため、必ず確認しましょう。
設立・廃止した場合の月割計算
事業年度の途中で会社を設立したり、事業所を廃止したりした場合、均等割はその事業所に存在した月数に応じて月割計算を行います。
このとき、月数の数え方に注意が必要です。均等割の計算では、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし、存在期間が1か月に満たない場合は1か月として計算します。例えば、7か月と20日間存在した場合は「7か月」として計算します。
法人税割の計算方法
課税標準となる法人税額を特定する
法人税割の計算の出発点は、国に納める法人税額です。この法人税額が課税標準となります。法人税の申告書で算出された最終的な法人税額を用いることを覚えておきましょう。
標準税率の適用と超過税率
課税標準となる法人税額に、地方自治体が定める税率を乗じて法人税割額を算出します。標準税率は以下の通りです。
- 都道府県民税:法人税額 × 1.0%
- 市町村民税:法人税額 × 6.0%
ただし、均等割と同様に、この税率も自治体によって異なる場合があります。特に、財政的に体力のある自治体では、標準税率を超える「超過税率」を適用していることが一般的です。必ず納税先の自治体の税率を確認してください。なお、東京23区内に事業所がある場合は、都民税として一本化され、税率も異なります。
複数の事業所がある場合の按分計算
法人が複数の市町村に事業所を持っている場合、法人税割の計算は少し複雑になります。法人税額という一つの課税標準を、各市町村に公平に配分する必要があるためです。この配分作業を按分(あんぶん)といいます。
按分の基準となるのは、原則として事業年度末日時点の各事業所の従業員数です。具体的には、各市町村の従業員数を全社の総従業員数で割り、その比率に応じて法人税額を配分します。
この按分計算における月数計算では、均等割とルールが異なる点に注意が必要です。事業年度の途中で事業所を新設・廃止した場合、法人税割の按分計算では1か月に満たない端数は切り上げて1か月として計算します。例えば、3か月と10日間存在した場合は「4か月」となります。
計算シミュレーション
これまでの内容を基に、具体的な計算例を見てみましょう。
| 項目 | 計算内容 | 金額 |
| 会社情報 | 資本金1,000万円、法人税額200万円、事業所:A市(従業員10名)、B市(従業員40名) | – |
| 1. 均等割の計算 | ||
| A市 (均等割) | 50人以下区分: 50,000円 (市) + 20,000円 (県) | 70,000円 |
| B市 (均等割) | 50人以下区分: 50,000円 (市) + 20,000円 (県) | 70,000円 |
| 2. 法人税割の計算 | ||
| 課税標準の按分 | A市: 200万円 × (10 / 50) = 40万円 | 400,000円 |
| B市: 200万円 × (40 / 50) = 160万円 | 1,600,000円 | |
| A市 (法人税割) | 40万円 × (6.0% [市] + 1.0% [県]) | 28,000円 |
| B市 (法人税割) | 160万円 × (6.0% [市] + 1.0% [県]) | 112,000円 |
| 3. 納税額合計 | ||
| A市への納税額 | 70,000円 (均等割) + 28,000円 (法人税割) | 98,000円 |
| B市への納税額 | 70,000円 (均等割) + 112,000円 (法人税割) | 182,000円 |
この例のように、均等割は事業所ごとに定額でかかり、法人税割は従業員数に応じて按分された課税標準を基に計算されます。
経営者が知るべきシナリオ別の対応策
法人経営は常に順風満帆とは限りません。赤字になったり、事業を一時的に休んだりすることもあるでしょう。ここでは、そうした重要な局面で法人住民税がどうなるのか、その対応策を解説します。
赤字決算の場合
均等割の納税義務と最低納付額
結論から言うと、赤字決算であっても法人住民税の納税義務は発生します。ただし、全額ではありません。赤字の場合、所得がゼロなので法人税はかかりません。それに伴い、法人税額を基に計算する法人税割も0円となります。
しかし、企業の規模に応じて課される均等割は、赤字とは無関係に納税義務があります。前述の通り、これは法人が地域社会の構成員であることに対する「会費」だからです。
最も小規模な法人(資本金1,000万円以下、従業員50人以下)の場合でも、最低でも年間7万円(市町村民税5万円+都道府県民税2万円)程度の負担が発生することを覚えておく必要があります。資金繰りが厳しいときでも、この金額は確保しておかなければなりません。
繰越欠損金制度の活用
赤字決算は短期的には厳しいものですが、税務上は将来の節税につながる可能性があります。青色申告をしている法人の場合、その事業年度に生じた赤字(欠損金)を、翌年度以降最大10年間にわたって繰り越すことができます。
将来、事業が黒字化した際に、この繰り越した赤字と利益を相殺することで、課税所得を圧縮できます。課税所得が減れば、法人税が減り、結果として将来の法人住民税の法人税割も軽減されることになります。赤字を単なる損失と捉えるのではなく、将来の税負担を軽くするための戦略的な要素として活用することが重要です。
設立・休業・廃業時の手続き
会社のライフステージに応じて、法人住民税の手続きは異なります。特に休業時の対応は、無駄な税負担を避けるために重要です。
設立初年度
法人を設立した場合、税務署や都道府県、市町村へ「法人設立届出書」を提出します。初年度の法人住民税の均等割は、設立日から事業年度末までの月数に応じて月割りで計算されます。
休業する場合
事業を一時的に休止する「休眠」状態にする場合、注意が必要です。会社が法的に存在し続ける限り、たとえ事業活動がなくても、原則として法人住民税の均等割の納税義務は続きます。
しかし、税務署、都道府県税事務所、市町村役場にそれぞれ「異動届出書」を提出し、休業する旨を届け出ることで、均等割が免除または減免される場合があります。この措置は自治体によって対応が異なるため、自動的に免除されるわけではありません。
必ず事前に事業所のある自治体に確認し、所定の手続きを行うことが重要です。この手続きを怠ると、活動実態がないにもかかわらず毎年納税通知が届くことになります。行政手続きを能動的に行うことが、コスト管理に直結する典型的な例です。
廃業する場合
法人を廃業する場合は、解散登記を行い、清算手続きに入ります。清算中の事業年度についても申告と納税が必要です。最終的に清算が結了したら、登記を行い、「清算結了届」を各所に提出することで、法人の納税義務は完全に終了します。
申告と納付の実務
法人住民税の計算と納税額の把握ができたら、最後は申告と納付の実務です。期限を守ることが何よりも重要です。
申告と納付の期限
法人住民税の申告と納付の期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。例えば、3月31日が決算日の法人であれば、5月31日が期限となります。
法人税において申告期限の延長が認められている場合、法人住民税の申告期限も連動して延長されます。しかし、ここで注意すべきは、申告期限が延長されても、納付期限は原則として延長されないという点です。納付が遅れると延滞金が発生するため、納税資金は本来の期限までに準備しておく必要があります。
納付方法
納付方法は、自治体から送付される納付書を使って金融機関や市町村役場の窓口で支払う方法が基本です。近年では、これに加えて電子納税など多様な方法が用意されています。
クレジットカード払いやスマートフォン決済アプリに対応している自治体も増えていますが、手数料が発生する場合があるため、事前に確認することをお勧めします。自社の経理業務のフローに合わせて、最も効率的で管理しやすい方法を選択しましょう。
電子申告「eLTAX」の活用
法人住民税の申告手続きを効率化するために、eLTAX(エルタックス)という地方税ポータルシステムの利用を強く推奨します。eLTAXは、インターネットを通じて地方税の申告や納税を行えるシステムです。
eLTAXを利用するメリットは数多くあります。自宅やオフィスのパソコンから手続きが可能であり、複数の都道府県や市町村への申告を一度の操作でまとめて行えます。また、システムの利用料は無料で、市販の会計ソフトと連携できる場合も多いため、経理業務の大幅な効率化が期待できます。
特に、資本金が1億円を超える大法人は電子申告が義務化されており、税務行政のデジタル化は国全体の流れとなっています。中小企業にとっても、eLTAXの活用は事務負担の軽減とミスの防止に大きく貢献します。
よくある質問(FAQ)

最後に、法人住民税に関して経営者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 事業年度の途中で本店を移転した場合、法人住民税はどこに納める?
A1. 均等割と法人税割で取り扱いが異なります。均等割については、移転前と移転後のそれぞれの自治体に対し、事業所が存在した月数に応じて月割で按分して納付します。一方、法人税割は、原則として事業年度の末日に事業所が所在する自治体に全額を納付します。ただし、按分計算の基礎となる従業員数は、各事業所に在籍していた月数を考慮して計算する必要があります。
Q2. NPO法人や一般社団法人にも法人住民税はかかる?
A2. はい、原則としてかかります。NPO法人や一般社団法人なども法人格を持つため、法人住民税の納税義務者となります。ただし、収益事業を行っていない場合は、法人税割は課されません。均等割については、多くの自治体で減免制度が設けられています。減免を受けるためには申請が必要ですので、事業所のある自治体にご確認ください。
Q3. 納付が遅れた場合のペナルティは?
A3. 納付期限までに法人住民税を納付しなかった場合、延滞金が課されます。延滞金の利率は年によって変動しますが、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。また、申告自体が遅れたり、申告額が過少であったりした場合には、過少申告加算税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性もあるため、期限内の正確な申告・納付が極めて重要です。
まとめ
本記事では、法人住民税の基本的な仕組みから具体的な計算方法、そして経営上のさまざまなシナリオにおける対応策までを網羅的に解説しました。
法人住民税は、事業所を置く地方自治体に納める地方税であり、地域社会を支える「会費」としての性格を持っています。税額は、企業の規模で決まる固定費的な「均等割」と、利益に応じて変動する「法人税割」の2つの合計で決定されます。
経営者として最も重要な点は、赤字決算であっても均等割の納税義務はなくならないという事実です。小規模な法人であっても、最低でも年間7万円程度の負担は発生すると見込んでおく必要があります。
計算は、資本金・従業員数・法人税額の3つの要素が基本となります。複数の事業所がある場合は、従業員数による按分計算が必要となる点を忘れないでください。申告と納付の期限は、原則として事業年度終了の翌日から2か月以内です。
この期限は厳守しなければなりません。申告手続きは、効率的で間違いの少ない電子申告システム「eLTAX」の活用が推奨されます。
法人住民税は、一見複雑に思えるかもしれませんが、その構造を分解し、一つひとつの要素を理解すれば、決して難しいものではありません。この記事で得た知識を活用し、自社の納税額を的確に把握・管理することで、より健全で安定した会社経営を実現してください。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…