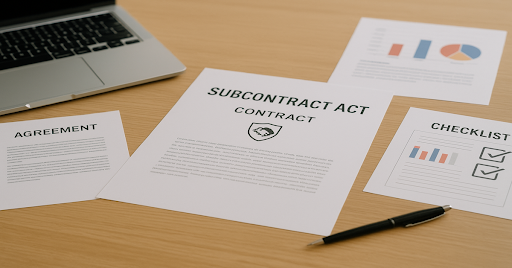
「下請法契約書」と聞いて、面倒な法律や書類作業を思い浮かべていませんか。この法律を正しく理解し活用することは、取引先との無用なトラブルを未然に防ぎ、信頼関係を築く上で重要です。
ひいては、自社の事業を安定成長させるための強力な武器にもなり得ます。下請法は単なる規制ではなく、公正な取引を通じて優良なパートナーシップを育むための羅針盤なのです。
この記事を最後まで読めば、下請法の専門家でなくとも、自社の取引が対象になるか即座に判断できます。さらに、法律に準拠した「3条書面」の必須項目を完璧に理解し、明日からでも実務で使える具体的な知識を身につけることが可能です。もう、「知らなかった」では済まされない法律違反のリスクに怯える必要はありません。
本記事では、公正取引委員会の資料や実際の違反事例に基づき、複雑な法律の要点を「取引の種類」「資本金」「禁止事項」という3つのシンプルな視点から解説します。チェックリストや具体例を豊富に盛り込んでいるため、法務部がない中小企業の経営者や担当者の方でも、自社の契約書や発注フローを自信を持って見直せるようになります。
目次
そもそも下請法とは?事業者を守るための基本ルール
まず、下請法がなぜ存在するのかを理解することが重要です。下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。この法律の根本的な目的は、取引において優位な立場に立つことが多い発注者(親事業者)が、その力を不当に利用することを防ぐ点にあります。
具体的には、受注者(下請事業者)の利益を保護し、事業者間の取引を公正なものにすることを目指しています。日本の全企業数の99.7%を占め、雇用の約7割を支える中小企業が不利益を被ることなく健全に発展することは、産業全体の基盤を強化するために不可欠です。
そのため、下請法は公正で自由な競争を促進する独占禁止法を補完する特別な法律として位置づけられています。
そして、この法律は時代の変化に合わせて進化しています。注目すべきは、2026年1月1日に現行の下請法が改正され、「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)として施行される点です。この改正は単なる名称変更ではありません。
従来の「下請代金支払遅延等防止法」という名称が示すように、これまでの法律は支払遅延といった特定の違反行為を「防ぐ」という、どちらかといえば受け身の姿勢が中心でした。しかし、新しい「中小受託取引適正化法」という名称には、取引全体をより積極的に「適正な状態にする」という強い意志が込められています。
例えば、近年の原材料費や労務費の高騰を受けて、価格転嫁のための協議に応じないといった行為も規制対象に含まれるようになり、より公正で持続可能な取引関係の構築を目指すものへと変わります。これは、法律が単なる違反の抑止力から、健全なサプライチェーンを育むための促進ツールへと役割を広げていることを示しています。
あなたの取引は対象?下請法の適用範囲を3分でチェック
「自社は関係ないだろう」と思い込むのは危険です。下請法が適用されるかどうかは、会社の規模の大小だけでなく、「取引の内容」と「両社の資本金」という2つの明確な基準によって決まります。このセクションで、自社の取引が対象になるかを確認しましょう。
ステップ1:4つの「取引内容」に当てはまるか確認する
下請法の対象となるのは、以下の4種類の委託取引です。自社の発注がこれらに該当しないか、具体例と照らし合わせてみてください。
製造委託
事業者が販売または製造を請け負う物品について、その仕様(規格、品質、デザインなど)を指定して、他の事業者に製造や加工を委託することです。例えば、自動車メーカーが部品メーカーに特定の部品の製造を委託する場合や、スーパーが自社ブランド商品の製造を食品メーカーに委託する場合がこれにあたります。
修理委託
事業者が請け負った物品の修理を、他の事業者に委託することです。例えば、家電メーカーが顧客から預かった製品の修理を、地域の修理専門業者に再委託するケースなどが該当します。
情報成果物作成委託
プログラム、映像コンテンツ、デザイン、設計図といった「情報成果物」の作成を他の事業者に委託することです。ゲーム会社が外部の制作会社にゲーム内のキャラクターデザインを委託する場合や、企業が広告代理店にウェブサイトのデザインを委託する場合などが含まれます。
役務提供委託
事業者が顧客に提供する運送、ビルメンテナンス、情報処理などのサービスを、他の事業者に委託することです。ただし、建設業者が請け負う建設工事は下請法の対象外となります。例えば、運送会社が引き受けた貨物輸送の一部区間を、別の運送会社に再委託するケースが典型例です。
ステップ2:「資本金区分」の条件を満たすか確認する
上記の取引内容に該当する場合、次に発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)の資本金が以下の組み合わせに当てはまるかを確認します。この資本金の組み合わせによって、下請法が適用されるかが最終的に決まります。
パターンA:製造委託・修理委託・一部の情報成果物作成委託(プログラム)/役務提供委託(運送、倉庫保管、情報処理)の場合
- 親事業者(資本金3億円超)が、下請事業者(資本金3億円以下の法人または個人事業主)へ発注する場合
- 親事業者(資本金1千万円超3億円以下)が、下請事業者(資本金1千万円以下の法人または個人事業主)へ発注する場合
パターンB:情報成果物作成委託(プログラムを除く)/役務提供委託(パターンA以外)の場合
- 親事業者(資本金5千万円超)が、下請事業者(資本金5千万円以下の法人または個人事業主)へ発注する場合
- 親事業者(資本金1千万円超5千万円以下)が、下請事業者(資本金1千万円以下の法人または個人事業主)へ発注する場合
ここで特に注意すべきは、2026年から施行される「取適法」による変更点です。新しい法律では、従来の資本金基準に加えて「常時使用する従業員数」という基準が追加されます。例えば、製造委託の場合、資本金が基準以下でも従業員数が300人を超えれば親事業者と見なされるようになります。
これにより、これまで下請法の対象外だった企業が、新たに対象となる可能性があります。特に、IT業界など資本金は小さいものの多くの従業員を抱える企業は、自社が対象事業者になっていないか、今のうちから確認し、コンプライアンス体制を整備しておく必要があります。この変更は、これまで下請法を意識してこなかった企業にとって大きなコンプライアンスリスクとなるため、早期の対応が求められます。
契約の心臓部!「3条書面」の作成義務と12の必須記載事項
下請法が適用される取引において、親事業者が負う最も基本的かつ重要な義務が、発注内容を記した書面の交付です。この書面は、下請法第3条に定められていることから、通称「3条書面」と呼ばれます。
なぜ「3条書面」が絶対に必要なのか?
親事業者は、下請事業者に発注する際、「直ちに」3条書面を交付しなければなりません。口頭での発注や、後から契約書を交わすといった行為は認められていません。
この義務の目的は、発注内容を客観的な書面で明確にすることで、「言った・言わない」といった水掛け論や、契約内容の曖昧さから生じるトラブルを未然に防ぎ、下請事業者を保護することにあります。
3条書面は、単なる事務手続き書類ではありません。これは、親事業者自身を将来の紛争から守るための、最も強力な「防衛策」でもあります。
例えば、後から下請事業者に「不当に安い価格で契約させられた」や「契約外の作業を無償でやらされた」と主張された場合、明確な業務範囲と具体的な対価が記載された3条書面があれば、それが合意内容の客観的な証拠となります。
実際に、2022年度に最も多かった下請法違反は、この「発注書面の不交付・記載不備」であり、その件数は636件にものぼります。この事実は、多くの企業がこの基本的な義務を軽視し、自らをリスクに晒している現状を示しています。3条書面の作成は、負担ではなく、自社を守るための不可欠なリスク管理活動なのです。
3条書面の必須記載事項リスト
自社の発注書や契約書が、以下の12の必須項目をすべて満たしているか、厳しくチェックしてください。一つでも欠けていると、下請法違反となる可能性があります。
- 親事業者および下請事業者の名称
- 委託した日(発注日)
- 給付の内容(委託業務の内容)
仕様書や図面への言及を含め、誰が見ても業務内容が特定できるように具体的に記載する必要があります。 - 給付を受領する期日(納期)
「〇年〇月〇日」のように、具体的な日付を明記します。 - 給付を受領する場所
- 検査を行う場合は、その検査を完了する期日
- 下請代金の額
原則として具体的な金額を記載します。もし発注時点で金額を確定できない場合は、明確な「算定方法」を記載しなければなりません。 - 下請代金の支払期日
物品やサービスの提供を受けた日(受領日)から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に設定する義務があります。 - 手形で支払う場合
手形の金額(または支払比率)と満期日 - 一括決済方式で支払う場合:金融機関名、貸付可能額など
- 電子記録債権で支払う場合
電子記録債権の額と満期日 - 原材料等を有償支給する場合
品名、数量、対価、引渡日、決済方法など
これらの項目を網羅した書面を「直ちに」交付することが、公正な取引の第一歩であり、自社を守るための最低限の義務です。
絶対に越えてはいけない11のライン:親事業者の禁止事項

下請法は、親事業者が優越的な地位を濫用して下請事業者に不利益を与えることを防ぐため、具体的に11項目の行為を禁止しています。これらの禁止事項は非常に厳格で、たとえ下請事業者の合意があったとしても、また親事業者に違反の認識がなかったとしても、該当すれば下請法違反と見なされます。自社の商慣行が、意図せずこれらの禁止事項に抵触していないか、以下で確認してください。
1. 受領拒否
発注した物品やサービスの受け取りを、正当な理由なく拒否する行為です。例えば、自社の在庫が増えたという一方的な理由で、発注済みの商品の受け取りを断ることは違反となります。
2. 下請代金の支払遅延
納品物を受領してから60日以内に定められた支払期日までに、下請代金を支払わない行為です。下請事業者からの請求書提出が遅れたことを理由に、支払いを60日以上遅らせることも認められません。
3. 下請代金の減額
発注時に決定した下請代金を、下請事業者に責任がないにもかかわらず一方的に減額する行為です。「協力金」や「値引き」といった名目であっても、実質的な減額は違反と判断されます。
4. 返品
受け取った物品を、下請事業者に責任がないにもかかわらず返品する行為です。例えば、シーズンが終わり売れ残った商品を「不要になったから」という理由で下請事業者に引き取らせることはできません。
5. 買いたたき
その時点で通常支払われる対価に比べて、著しく低い価格を不当に設定する行為です。複数の事業者から見積もりを取った上で、最も安い単価を基準に、さらに値引きを強要するケースなどが該当します。
6. 購入・利用強制
発注する見返りとして、自社が指定する製品やサービスを強制的に購入または利用させる行為です。取引継続を条件に、自社の新製品や関連会社の保険サービスへの加入を要求することなどが含まれます。
7. 報復措置
下請事業者が、親事業者の下請法違反を公正取引委員会や中小企業庁に通報したことを理由に、取引量を減らしたり、取引を停止したりするなどの不利益な取り扱いをすることです。
8. 有償支給原材料等の対価の早期決済
親事業者が有償で支給した原材料などの対価を、その原材料を用いた製品の下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりする行為です。
9. 割引困難な手形の交付
一般の金融機関で割り引くことが困難な、支払期日までの期間が長い手形を交付する行為です。繊維業では90日、その他の業種では120日を超える手形は、割引困難な手形と見なされます。
10. 不当な経済上の利益の提供要請
下請事業者に対して、協賛金や従業員の派遣などを不当に要求する行為です。例えば、委託内容に含まれない金型の無償保管を長期間にわたり強要することも、これに該当する可能性があります。
11. 不当な給付内容の変更・やり直し
下請事業者に責任がないにもかかわらず、無償で発注内容の変更ややり直しをさせる行為です。発注時にはなかった要求を後から追加し、「これも契約のうちだ」として無償で対応させるケースなどが違反となります。
罰金50万円だけでは済まされない。下請法違反の本当のリスク

下請法に違反した場合のリスクは、3条書面の不交付などで科される最大50万円の罰金だけではありません。それ以上に深刻なのは、企業の社会的信用を根底から揺るがす、目に見えないコストです。
企業名公表という最大のリスク
公正取引委員会が違反行為を認め、親事業者に対して是正を求める「勧告」を行った場合、その事実が企業名、違反内容の概要とともにウェブサイト上で公にされます。これは、自社が「不公正な取引を行う企業である」という公的な烙印を押されるに等しい行為です。
この情報は、既存の取引先や金融機関、消費者、そして将来の優秀な人材候補者の目に触れることになります。一度失われた信頼を回復するには、罰金の額とは比べ物にならないほどの時間と労力、そしてコストがかかることを認識しなければなりません。
近年の違反事例から学ぶ教訓
実際の違反事例は、どのような行為が問題となるかを具体的に示してくれます。
事例1:大手自動車会社による下請代金の減額
ある大手自動車会社は、下請事業者36社に対し、合理的な理由なく総額30億円を超える代金を減額していました。この事例は、企業の規模に関わらず下請法違反は厳しく追及されること、そして減額の規模が甚大になりうることを示しています。
事例2:大手小売業者による不当な減額
ある大手家電販売店は、「拡売費」「物流協力金」「リベート」といった様々な名目を使い、下請事業者への支払代金から総額7,300万円以上を差し引いていました。この事例は、いかなる名目であっても、実質的に下請事業者の利益を不当に害する減額は許されないという明確なメッセージです。
事例3:金型の無償保管問題
近年、公正取引委員会が特に注力しているのが、この「金型の無償保管」問題です。2024年度には、下請法違反による勧告件数が平成以降で最多を記録し、その多くを金型関連の事案が占めました。これは、親事業者が長期間発注のない金型を、下請事業者に無償で保管させる行為が「不当な経済上の利益の提供要請」に該当すると判断されたものです。
この動きは、単一の問題に対する取り締まり強化ではありません。公正取引委員会が、これまで業界の「商慣行」として見過ごされてきた不公正な行為に本格的にメスを入れ始めたことを示唆しています。
当局は、広く蔓延している有害な慣行を特定し、社会的な影響の大きい企業を摘発・公表することで、業界全体の意識改革を促すという戦略的な姿勢を見せています。公正取引委員会が「勧告事案は氷山の一角」と述べているように、企業は自社の「当たり前」となっている慣行が、次の摘発対象にならないか、常に自己点検する必要があります。
まとめ:公正な取引が、未来の成長を築く
本記事で解説してきたように、下請法は複雑に見えるかもしれませんが、その要点は明確です。下請法を遵守することは、単に法律違反のリスクを回避するための消極的な対応ではありません。それは、公正なパートナーシップを築き、サプライチェーン全体の競争力を高め、ひいては自社の持続的な成長を実現するための、極めて重要な経営戦略です。
最後に、明日から実践すべき3つのポイントを再確認しましょう。
- ポイント1
まず適用対象かを確認する
「取引内容」と「資本金区分」の2つの軸で、自社の取引が下請法の対象となるかを正確に見極めることが全ての始まりです。 - ポイント2
契約の基本は「3条書面」
発注内容は必ず書面で、本記事で紹介した12の必須項目を網羅して「直ちに」交付してください。これが、あらゆるトラブルを防ぐための最も効果的な予防策です。 - ポイント3
11の禁止事項は常に意識する
支払遅延や不当な減額はもちろんのこと、これまで業界の慣行として無意識に行ってきた行為が、11の禁止事項に抵触していないか、常に意識し、定期的に見直すことが不可欠です。
下請法に準拠した契約書を正しく運用することは、下請事業者を守るだけでなく、自社がクリーンで公正な企業であることを社会に示すことにもつながります。変化の激しい時代において、信頼できるパートナーとの強固な関係こそが、未来の成長を築く最も確かな土台となるのです。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…