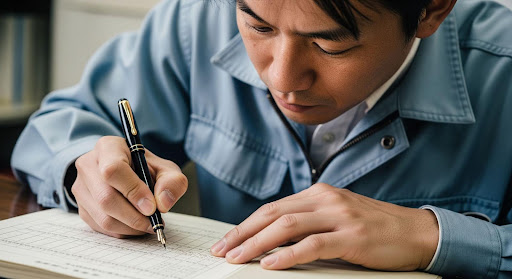
補助金や保険金を受け取ったその年、想定外の多額の税金に頭を悩ませていませんか。もし、その税負担を合法的に翌年以降に繰り延べ、手元の資金をしっかり守れる方法があるとしたら、知りたいと感じるのではないでしょうか。その有効な手段が「圧縮記帳」です。
この記事を最後まで読めば、圧縮記帳の仕組みを理解し、自社にとって最適な選択ができるようになります。税理士に相談する際も、的確な質問ができるようになり、主体的に資金計画を立てられるようになるでしょう。
「会計の専門知識がないと難しいのでは」と不安に思う必要はありません。この記事では、専門用語を一つひとつ丁寧に解説し、豊富な具体例を交えながら、誰にでもわかるように説明します。あなたも必ず、この制度を自社の味方につけることができます。
目次
そもそも圧縮記帳とは?節税ではなく課税の繰り延べ制度
圧縮記帳とは、一言でいえば「特定の収入にかかる税金の支払いを、将来に先送りする(繰り延べる)ための会計処理」です。これは法人税法や租税特別措置法で認められている正式な制度です。
なぜこのような制度が必要なのでしょうか。それは、補助金などを受け取った際に発生する税務上の問題を解決するためです。例えば、国から300万円の補助金をもらって500万円の機械を購入したとします。このとき、会計上は次のような状況が生まれます。
収入(益金)として補助金の300万円は、その年度の利益として一度に計上されます。一方で費用(損金)として、購入した機械の500万円は、法定耐用年数(例えば10年)にわたって少しずつ「減価償却費」として費用計上されます。
この結果、収入は初年度に集中するのに対し、対応する費用は長期間に分散されます。これにより、補助金を受け取った年度の利益が一時的に大きく膨らみ、多額の法人税が発生してしまうのです。せっかくの補助金が、その多くを税金として支払うことになっては、設備投資を後押しするという本来の目的が果たせません。
この問題を解決するのが圧縮記帳です。具体的には、補助金で得た利益と同額の「固定資産圧縮損」という特別な損失を計上します。この損失が補助金の利益を打ち消すため、初年度の課税所得を抑えることができます。そして、その分だけ取得した固定資産の帳簿上の価額(簿価)を「圧縮」する、つまり引き下げるのです。
ここで最も重要な点は、圧縮記帳は「節税(免税)」ではなく、あくまで「課税の繰り延べ」であるという事実です。初年度の税負担は軽くなりますが、資産の簿価を圧縮したため、翌年度以降の減価償却費は通常よりも少なくなります。
減価償却費という費用が減る分、将来の各年度の利益は増加し、結果的に税負担が増えることになります。減価償却期間全体で見れば、支払う税金の総額は圧縮記帳をしなかった場合と変わりません。
この制度は、単なる会計ルールではなく、国の経済政策の一環と理解するとより分かりやすいでしょう。政府が補助金で企業の投資を促進しようとしても、税制がその効果をすぐに奪ってしまっては意味がありません。圧縮記帳は、この二つの政策(補助金の交付と税金の徴収)の矛盾を解消し、企業の成長を円滑に支援するための賢明な仕組みなのです。
圧縮記帳のメリット・デメリットを徹底比較
圧縮記帳は、初年度の税負担を軽減する強力な手段ですが、万能ではありません。自社の財務状況や将来計画と照らし合わせて、メリットとデメリットを慎重に比較検討することが不可欠です。
メリット:手元の資金を守り資金繰りを改善する
圧縮記帳の最大のメリットは、固定資産を取得した年度の税負担を直接的に軽減し、手元の現金を確保できる点です。特に、多額の設備投資を行った中小企業にとって、資金繰りは常に重要な経営課題です。
補助金を利用したとしても、自己資金も相当額を投じているケースがほとんどでしょう。そのような状況で、補助金収入に対して多額の納税が発生すると、運転資金が圧迫されかねません。
圧縮記帳を適用すれば、この一時的な税負担を回避し、資金繰りを安定させることができます。これにより、補助金の効果を最大限に活かし、事業の成長や次の投資へと資金を振り向ける余裕が生まれるのです。
デメリット:将来の税負担増と複雑な資産管理
一方で、圧縮記帳には注意すべきデメリットも存在します。一つ目は、将来の税負担が増加する点です。前述の通り、これは課税の繰り延べです。初年度に支払わなかった税金は、翌年度以降に分割して支払うことになります。資産の簿価が圧縮された結果、毎年の減価償却費が少なく計上され、その分だけ将来の課税所得が増加するためです。
二つ目は、資産管理が複雑化することです。圧縮記帳を適用した資産は、他の資産とは区別して管理する必要があります。特に後述する「償却資産税」の計算では、圧縮前の取得価額が必要になるなど、経理担当者の事務負担が増加します。
三つ目は、早期売却時の税負担増です。もし圧縮記帳した資産を耐用年数の途中で売却した場合、帳簿価額が低く抑えられているため、売却益が通常より大きく計算されます。その結果、売却時に多額の税金が発生する可能性があります。
これらのメリット・デメリットを踏まえると、圧縮記帳を適用するかどうかの判断は、単なる会計処理の選択ではなく、会社の将来を見据えた財務戦略そのものと言えます。
例えば、現在は赤字でも数年後の黒字化と急成長が見込まれるスタートアップ企業の場合、利益が出て税負担能力が高まる将来に納税を繰り延べることは非常に有効な戦略です。逆に、将来の収益が不透明な場合は、目先の税負担を増やしてでも、将来の負担を軽くしておくという判断もあり得ます。
圧縮記帳が適用される代表的な5つのケース
圧縮記帳は、どのような場合にでも使えるわけではありません。法律で定められた特定の状況に限られます。ここでは、その代表的な5つのケースを紹介します。
国や自治体から補助金・助成金を受け取った場合
これは最も一般的で、多くの企業に関係するケースです。「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」、「IT導入補助金」といった国の施策のほか、地方自治体が交付する助成金なども対象となります。この場合の圧縮限度額は、原則として固定資産の取得に充てた補助金の金額が上限です。
火災や災害で保険金を受け取った場合(保険差益)
火災や自然災害などで所有する固定資産が損壊・滅失し、受け取った保険金の額がその資産の帳簿価額を上回った場合、その差額は「保険差益」として課税対象になります。
これは企業の意思に反して発生した利益であるため、被害からの復旧を妨げないよう、代替資産を取得した場合に圧縮記帳が認められています。圧縮限度額は、保険差益の額や代替資産の取得に充てた保険金の額などから、所定の計算式で算出されます。
固定資産を交換した場合(交換差益)
自社が所有する土地や建物などを、他者が所有する同種の固定資産と交換した場合、たとえ金銭のやり取りがなくても、税務上は時価で資産を売買したものとみなされます。
このとき、譲渡した資産の時価が帳簿価額を上回っていると「交換差益」が発生し、課税対象となります。現金収入がないにもかかわらず課税される事態を避けるため、圧縮記帳が認められています。圧縮限度額は、取得した資産の価額から、譲渡した資産の帳簿価額と譲渡経費を差し引いた金額です。
事業再編などで特定の資産を買い換えた場合
都市部にある工場を郊外に移転する場合など、国の政策的な要請に沿った事業再編のために特定の資産を譲渡し、代わりの資産(買換資産)を取得した場合に適用される特例です。
これは租税特別措置法に定められており、事業の効率化や再構築を税制面から支援することを目的としています。圧縮限度額は、譲渡対価や買換資産の取得価額をもとに、差益割合や特定の率(多くは80%)を乗じるなど、複雑な計算式で算出されます。
インフラ事業者などが工事負担金を受け取った場合
電気、ガス、水道、鉄道といった公益事業を営む法人が、サービスの利用者から施設の新設や改良のための「工事負担金」を受け取り、それで固定資産を取得した場合に適用されます。
これらのケースに共通しているのは、現金収入を伴わない利益(交換差益)や、企業の自発的な利益追求活動とは異なる理由で発生した利益(補助金、保険差益)に対して、税制上の配慮がなされているという点です。この基本原則を理解すると、一見バラバラに見えるこれらのケースが、なぜ圧縮記帳の対象となるのかが論理的に理解できるでしょう。
【仕訳例】圧縮記帳の会計処理方法2つを解説
圧縮記帳を適用すると決めた場合、具体的な会計処理の方法として「直接減額方式」と「積立金方式」の2つがあります。ここでは、「500万円の機械を、300万円の補助金と200万円の自己資金で購入し、耐用年数5年・定額法で減価償却する」という共通の例で、それぞれの方法を見ていきましょう。
中小企業におすすめの「直接減額方式」
直接減額方式は、その名の通り、固定資産の帳簿価額から補助金相当額を直接差し引く方法です。処理がシンプルで分かりやすいため、多くの中小企業で採用されています。
補助金の受領時
| 借方 | 貸方 |
| 普通預金3,000,000円 | 補助金収入3,000,000円 |
機械の購入時
| 借方 | 貸方 |
| 機械装置5,000,000円 | 普通預金5,000,000円 |
圧縮損の計上時(決算時など)
| 借方 | 貸方 |
| 固定資産圧縮損3,000,000円 | 機械装置 3,000,000円 |
この処理により、補助金収入300万円と固定資産圧縮損300万円が相殺され、機械装置の帳簿価額は500万円から300万円を引いた200万円になります。
毎年の減価償却
| 借方 | 貸方 |
| 減価償却費 400,000円 | 機械装置 400,000円 |
圧縮後の帳簿価額200万円を基に計算するため、毎年の減価償却費は200万円を5年で割った40万円となります。
会計原則に忠実な「積立金方式」
積立金方式は、固定資産の価額は本来の取得価額のまま表示し、別途、貸借対照表の純資産の部に「圧縮積立金」を計上する方法です。会計上の取得原価主義の原則に忠実ですが、税務申告時に別途調整(申告調整)が必要になるため、処理が複雑になります。
補助金の受領時と機械の購入時の仕訳は、直接減額方式と同じです。
圧縮積立金の積立時(決算時)
| 借方 | 貸方 |
| 繰越利益剰余金3,000,000円 | 圧縮積立金 3,000,000円 |
この仕訳は損益に影響を与えませんが、税務申告書上で300万円を損金として申告調整します。
毎年の減価償却
| 借方 | 貸方 |
| 減価償却費 1,000,000円 | 機械装置 1,000,000円 |
帳簿価額は当初の500万円のままなので、減価償却費は500万円を5年で割った100万円となります。
圧縮積立金の取り崩し
| 借方 | 貸方 |
| 圧縮積立金600,000円 | 繰越利益剰余金 600,000円 |
積立金300万円を耐用年数5年で取り崩すため、毎年60万円を利益として計上します(税務申告書上で調整)。これにより、減価償却費100万円と相殺され、実質的な費用は40万円となり、直接減額方式と同じ効果が得られます。
方式別・年度別の損益と税負担の比較
「課税の繰り延べ」の効果を具体的に理解するために、3つのシナリオで税負担がどう変わるかを見てみましょう(法人税率30%と仮定)。
| 項目 | 圧縮記帳なし | 直接減額方式 | 積立金方式(税務上) |
| 【初年度】 | |||
| 補助金収入 | +300万円 | +300万円 | +300万円 |
| 圧縮損 | 0円 | -300万円 | -300万円 |
| 減価償却費 | -100万円 | -40万円 | -40万円 |
| 課税所得 | 200万円 | -40万円 | -40万円 |
| 法人税等 | 60万円 | 0円 | 0円 |
| 【2年目~5年目(各年)】 | |||
| 減価償却費 | -100万円 | -40万円 | -40万円 |
| 課税所得 | -100万円 | -40万円 | -40万円 |
| 法人税等 | -30万円 | -12万円 | -12万円 |
| 【資産のみ考慮した場合の5年間の合計税額】 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
※この表は簡略化のため資産関連の損益のみを考慮しています。実際の課税所得は他の事業損益と合算されます。
この表から、初年度の税負担が「圧縮記帳なし」では60万円発生するのに対し、圧縮記帳を適用した場合は0円(または他の利益と相殺してさらに軽減)になることが一目瞭然です。そして、2年目以降は逆に圧縮記帳を適用した方が税負担が重くなり、最終的な合計税額はどの方式でも同じになることが分かります。これが「課税の繰り延べ」の正体です。
圧縮記帳で失敗しないための3つの重要注意点
圧縮記帳は正しく使えば非常に有効ですが、思わぬ落とし穴もあります。ここでは、特に注意していただきたい3つのポイントを解説します。
注意点1:償却資産税の申告は圧縮前の取得価額で行う
これは最も陥りやすい間違いの一つです。圧縮記帳は、法人税や所得税といった国税の制度です。しかし、企業が所有する事業用資産には、市区町村が課税する地方税である「償却資産税」もかかります。
そして、償却資産税の計算には圧縮記帳の考え方は適用されません。償却資産税は、その資産が持つ本来の価値に対して課税される「財産税」としての性格が強いためです。したがって、毎年1月末に提出する償却資産税の申告書には、圧縮する前の本来の取得価額を記載しなければなりません。
先の例で言えば、法人税の計算上の簿価は200万円に圧縮されていても、償却資産税の申告では取得価額500万円として計算する必要があります。これを誤ると、過少申告として後から追徴課税や延滞金が発生するリスクがあるため、絶対に注意してください。
注意点2:「少額減価償却資産の特例」との併用
中小企業には、「取得価額が30万円未満の減価償却資産」を購入した年度に一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」という非常に有利な制度があります。
この「30万円未満」という判定は、圧縮記帳を適用した「後」の金額で行うことができます。これが強力な節税テクニックにつながります。例えば、45万円のソフトウェアを導入する際に20万円のIT導入補助金を受けたとします。
圧縮記帳を適用すると、ソフトウェアの帳簿価額は45万円から20万円を引いた25万円となります。この25万円は30万円未満なので、「少額減価償却資産の特例」の対象となります。結果として、圧縮後の25万円全額をその年度の経費として一括で損金算入できるのです。
ただし、この併用技が使えるのは、国庫補助金や保険差益など「法人税法」で定められた圧縮記帳に限られます。「特定資産の買換」など「租税特別措置法」で定められた圧縮記帳と、同じく租税特別措置法上の特例である少額減価償却資産の特例は、原則として併用できないため注意が必要です。
注意点3:個人事業主は「国庫補助金等の総収入金額不算入」制度を利用する
「圧縮記帳」という用語は、厳密には法人税法上の制度を指します。そのため、個人事業主の方が補助金を受け取った場合は、圧縮記帳とは異なる制度を利用することになります。
個人事業主が適用するのは、所得税法に定められた「国庫補助金等の総収入金額不算入」という制度です。これは、補助金のうち固定資産の取得に充てた部分を、その年の総収入金額に算入しない(つまり、初めから収入として数えない)というものです。
効果としては法人税の圧縮記帳と非常によく似ていますが、根拠となる法律や確定申告で添付する書類(「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」)が異なります。個人事業主の方は、「圧縮記帳」ではなく「総収入金額不算入」のキーワードで情報を確認するようにしてください。
まとめ
最後に、圧縮記帳を検討する際の要点をチェックリストとしてまとめます。
圧縮記帳は「節税」ではなく「税金の先送り(課税の繰り延べ)」であると正しく認識していますか?
初年度の資金繰り改善というメリットは、自社にとってどれほど重要ですか?
将来の税負担増や資産管理の複雑化というデメリットを受け入れられますか?
自社の状況は、補助金、保険差益、交換など、圧縮記帳が認められるケースに該当しますか?
経理処理のシンプルさを重視するなら「直接減額方式」、会計原則を重視するなら「積立金方式」を検討しましょう。
償却資産税の申告は、圧縮「前」の価額で行うことを経理担当者と共有しましたか?
取得価額が30万円前後の資産の場合、「少額減価償却資産の特例」との併用は可能ですか?
(個人事業主の場合)「総収入金額不算入」の制度について正しく理解していますか?
この記事で得た知識は、あなたの会社にとって最適な財務戦略を立てるための第一歩です。しかし、個別の事情によって判断は変わります。最終的な意思決定の前には、必ず顧問税理士などの専門家に相談し、自社の状況に合わせた最善の策を講じるようにしてください。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…