
役員報酬の仕訳や税務上のルールは、一見すると複雑で難解に感じられるかもしれません。しかし、その仕組みを正しく理解し戦略的に活用することは、会社の利益を最大化し、健全なキャッシュフローを維持するための強力な武器となります。
もしあなたが「役員報酬の仕訳方法が知りたい」「どうすれば税務上、費用として認められるのか」といった疑問を抱えているなら、この記事はまさにそのためのものです。会計処理と報酬設計の全知識を網羅的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたは役員報酬に関する単なる仕訳の方法だけでなく、その背後にある税務上の重要原則である損金算入の仕組みを深く理解し、自信を持って会計処理と報酬設計を行えるようになっているでしょう。
日々の経理業務における不安が解消され、会社の未来を見据えた戦略的な意思決定が可能になります。
役員報酬のルールは確かに厳格ですが、決して乗り越えられない壁ではありません。
本記事では、基本的な仕訳の入力方法から、節税の鍵となる3つの給与形態、さらには税務調査で指摘されないための書類作成のポイントまで、一つひとつ丁寧に解説します。この記事を道しるべに、確実な一歩を踏み出しましょう。
目次
役員報酬の仕訳 基本と会計処理のすべて
役員報酬の会計処理を理解する第一歩は、基本的な仕訳の方法と、なぜ従業員の給与と区別されるのかを知ることから始まります。このセクションでは、その基礎を固めていきます。
なぜ役員報酬は従業員の給与と区別するのか
会計上、役員に支払う報酬は「役員報酬」という勘定科目で処理します。一方で、正社員などの従業員に支払う給与は「給与手当」や「給料賃金」といった勘定科目を使います。パートやアルバイトに対しては「雑給」という科目で区別することも可能です。
この区別は、単なる帳簿上の整理のためだけではありません。その根底には、税法上の取扱いの根本的な違いが存在します。従業員の給与は、会社の業績に貢献した対価として支払われる費用であり、原則として全額が会社の経費(損金)として認められます。
しかし、役員報酬は異なります。役員は自らの報酬額の決定に関与できる立場にあります。もし自由に報酬額を決められると、期末に会社の利益を見てからその利益の全額を報酬として受け取り、法人税の負担を不当にゼロにすることが可能になってしまいます。
このような利益操作を防ぐため、税法では役員報酬が損金として認められるための厳格なルールを設けているのです。
したがって、役員報酬と給与手当を明確に区別して仕訳することは、会社がこの税法上の違いを正しく認識し、ルールを遵守していることを示す最初の重要なステップとなります。税務調査官が財務諸表を見る際、この区別が適切に行われているかは、基本的なコンプライアンス意識を測る上での一つの指標となるのです。
役員報酬の仕訳 完全分解マニュアル
役員報酬を支払う際の仕訳は、報酬総額だけでなく、そこから天引きされる税金や社会保険料も同時に処理する必要があります。ここでは、具体的な仕訳の流れを分解して解説します。
役員報酬を支払うとき、会社は報酬の総額から以下の項目を天引き(控除)します。
- 源泉所得税
- 住民税
- 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)の役員本人負担分
これらの天引きした金額は、会社が一時的に預かっているお金であり、後日、税務署や年金事務所などに納付する義務があります。そのため、会計上は「預り金」という負債の勘定科目で処理します。
さらに、社会保険料は役員本人だけでなく、会社も同額程度を負担します。この会社負担分は、会社の経費となり、「法定福利費」という費用(販売費及び一般管理費)の勘定科目で処理します。
これらの要素をすべて組み合わせた、標準的な月次の役員報酬の仕訳は以下のようになります。
| 摘要 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 役員報酬の計上 | 役員報酬 | 500,000円 | 普通預金 | 380,000円 |
| 預り金(源泉所得税) | 20,000円 | |||
| 預り金(住民税) | 25,000円 | |||
| 預り金(社会保険料) | 75,000円 | |||
| 会社負担分の計上 | 法定福利費 | 75,000円 | 未払費用 | 75,000円 |
この仕訳を解説します。まず、借方(左側)には、費用である役員報酬の総額500,000円と、会社負担分の社会保険料である法定福利費75,000円が計上されます。
次に、貸方(右側)には、実際に役員の口座に振り込まれる手取り額(普通預金から支出)380,000円と、天引きした各種預り金の合計120,000円が計上されます。会社負担分の社会保険料は、納付するまでは未払費用として負債計上するのが一般的です。
後日、預かった社会保険料(本人負担分)と会社の負担分を合わせて年金事務所などに納付する際には、以下のような仕訳で預り金と未払費用を取り崩します。
(借方) 預り金(社会保険料) 75,000円
(借方) 未払費用 75,000円
(貸方) 普通預金 150,000円
このように、役員報酬の支払いと社会保険料の納付はセットで管理することが、正確な会計処理の基本となります。
最重要原則「損金算入」 役員報酬を費用として認めてもらうための3つの方法
役員報酬の会計処理で最も重要な概念が「損金算入」です。これを理解することが、効果的な節税とコンプライアンスの鍵となります。
なぜ「損金算入」がこれほど重要なのか
損金算入とは、会計上の「費用」を、税法上の「損金」として認めてもらうことを指します。損金が増えれば、その分だけ会社の課税対象となる所得が減り、結果として法人税の負担が軽くなります。
法人税法上、役員報酬は原則として損金に算入されません(損金不算入)。もし、支払った役員報酬が損金として認められない場合、会社は報酬を支払って現金が減っているにもかかわらず、その金額が利益として扱われ、法人税が課されてしまいます。
一方で、報酬を受け取った役員個人には所得税と住民税が課されます。これは実質的な二重課税となり、会社と個人の双方にとって大きな負担増につながります。
この厳しいルールの背景には、前述の通り「利益操作の防止」という明確な意図があります。経営者が業績に応じて自由に報酬を変動させ、法人税を意図的にコントロールすることを防ぐために、税法は「事前に決められた、客観的なルールに則って支払われる給与」でなければ損金として認めない、という立場をとっているのです。
この原則を理解すれば、複雑に見えるルールの一つひとつが、「これは利益操作にあたらないか」という視点から設計されていることがわかります。この考え方を軸に置くことが、コンプライアンスを遵守する上で最も確実な方法です。
損金算入が認められる3つの給与形態
原則として損金不算入である役員報酬ですが、以下の3つのいずれかの形態に該当する場合に限り、例外的に損金算入が認められます。
- 定期同額給与
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与です。いわゆる「毎月決まった額の月給」のことであり、役員報酬の最も基本的で一般的な形態です。 - 事前確定届出給与
役員の職務につき、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与です。具体的には、役員に対する賞与(ボーナス)を損金算入したい場合に利用します。そのためには、事前に「いつ、誰に、いくら支払うか」を税務署に届け出る必要があります。 - 業績連動給与
会社の利益や株価といった業績に関する指標を基礎として算定される給与です。報酬額が変動するため利益操作に繋がりやすいと見なされ、損金算入の要件が非常に厳格に定められています。基本的には有価証券報告書を提出している上場企業などが対象であり、多くの中小企業にとっては実用的な選択肢ではありません。
このことから、中小企業の経営者が選択すべき方法は、実質的に「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の2つに絞られます。月々の安定した報酬は定期同額給与で、業績に応じた賞与は事前確定届出給与で、という使い分けが基本戦略となります。
| 給与タイプ | 概要 | 主な用途 | 手続き | 中小企業の実用性 |
| 定期同額給与 | 毎月同額を支給する給与 | 役員の月給 | 原則、事業年度開始から3か月以内に株主総会で決定 | ◎(最も一般的) |
| 事前確定届出給与 | 事前に定めた日に定額を支給する給与 | 役員の賞与(ボーナス) | 株主総会で決定後、所定の期日までに税務署へ届出が必要 | ○(計画的な活用が必須) |
| 業績連動給与 | 業績指標に連動して支給する給与 | 業績に応じたインセンティブ報酬 | 非常に厳格な算定・開示要件あり。届出は不要。 | ×(非上場の中小企業ではほぼ利用不可) |
実践編 定期同額給与と事前確定届出給与の徹底活用術と注意点
中小企業にとって現実的な選択肢である「定期同額給与」と「事前確定届出給与」。この2つをいかに正しく、かつ効果的に活用するかが、税務戦略の要となります。
定期同額給与をマスターする 鉄則「期首から3ヶ月ルール」
定期同額給与の最大のポイントは、その金額を事業年度の途中で自由に変更できないことです。金額の改定が認められるのは、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行われる場合に限られます。この改定は、定時株主総会で決議し、その議事録をきちんと保管しておく必要があります。
この「3ヶ月ルール」を破ると、厳しいペナルティが待っています。
- 3ヶ月を超えて増額した場合
増額改定前の金額がその事業年度の定期同額給与と見なされ、増額した部分の全額が損金不算入となります。例えば、月額50万円だった報酬を期首から7ヶ月目に70万円に増額した場合、差額の20万円に残り6ヶ月を乗じた120万円が損金として認められません。 - 3ヶ月を超えて減額した場合
減額後の金額が定期同額給与の基準となります。そして、減額前に支払われた、改定後の金額を超える部分が損金不算入となります。
例えば、月額100万円だった報酬を期首から7ヶ月目に80万円に減額した場合、改定前の6ヶ月間に支払われた報酬のうち、新しい基準額80万円を超える20万円に6ヶ月を乗じた120万円が損金不算入とされてしまいます。
例外 期中の変更が認められる「臨時改定事由」
原則として期中の変更は認められませんが、以下のようなやむを得ない事情がある場合は、例外的に期中での改定が認められます。これを「臨時改定事由」と呼びます。
- 役員の職制上の地位の変更
取締役が代表取締役に昇格するなど、役員の地位や職務内容に重大な変更があった場合です。ただし、単なる名義変更で職務の実態が変わらない場合は認められません。 - 経営状況の著しい悪化
第三者である株主や債権者(金融機関など)、取引先との関係上、役員報酬を減額せざるを得ないような、客観的に見て深刻な経営状況の悪化があった場合です。単に「売上が少し落ちた」という程度では認められず、その判断は慎重に行う必要があります。
事前確定届出給与で「役員賞与」を損金にする方法
役員に賞与(ボーナス)を支給し、それを損金として認めてもらうための唯一の方法が、事前確定届出給与の制度を活用することです。この制度を利用するには、以下の3つのステップを厳格に守る必要があります。
- 株主総会での決議
まず、株主総会で「いつ(支給日)」「誰に」「いくら(支給額)」を具体的に決議します。 - 届出書の提出
次に、決議内容を記載した「事前確定届出給与に関する届出書」を作成し、所轄の税務署に提出します。提出期限は、原則として「株主総会の決議日から1か月を経過する日」または「事業年度開始日から4か月を経過する日」のいずれか早い日です。 - 正確な支給
最後に、届け出た支給日に、届け出た金額と1円たりとも違わない金額を支払います。もし支給日や金額が少しでも異なった場合、その支給額の全額が損金不算入となってしまいます。この極めて厳格なルールは、利益の状況を見てから賞与額を調整するといった利益操作を完全に排除するために設けられています。
「不相当に高額」な役員報酬と判断されないために
たとえ上記の手続きをすべて完璧にこなしたとしても、その報酬額が「不相当に高額である」と税務署に判断された場合、高額と見なされた部分が損金不算入となる可能性があります。この判断は、以下の2つの基準で行われます。
- 形式基準
定款や株主総会の決議で定められた報酬の限度額を超えて支給していないか、という基準です。限度額を超えた部分は、無条件で損金不算入となります。 - 実質基準
その役員の職務内容、会社の収益状況、従業員への給与支給状況、そして同業・同規模の他社の役員報酬水準などと照らし合わせて、その報酬額が妥当かどうかを判断する基準です。この基準は主観が入りやすく、税務調査で論点になりやすい部分です。したがって、自社の役員報酬額がなぜ妥当なのかを、客観的なデータや事実に基づいて説明できるように準備しておくことが極めて重要になります。
税務調査で否認されないための必須コンプライアンス
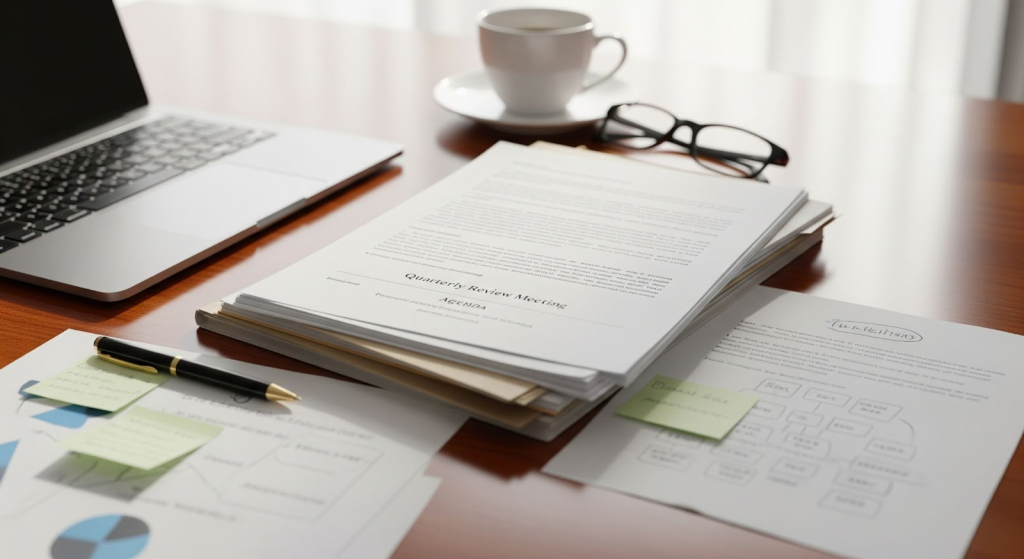
税務上のルールを守るためには、適切な会計処理だけでなく、その決定プロセスを証明する書類を正しく作成・保管することが不可欠です。
株主総会議事録の重要性と作成方法
役員報酬に関するすべての決定(新規設定、金額改定、賞与の支給など)は、必ず株主総会(または取締役会設置会社の場合は取締役会)の決議を経て行う必要があります。そして、その決議内容を証明する唯一の公式な書類が株主総会議事録です。
議事録は、単なる社内の記録ではありません。税務調査において、「役員報酬がいつ、どのような根拠で決定されたか」を証明する法的な証拠となります。議事録が存在しない、または記載内容に不備がある場合、報酬の決定プロセスが不適切と見なされ、最悪の場合、支払った報酬の全額が損金として認められなくなるリスクがあります。
議事録には、少なくとも以下の項目を正確に記載する必要があります。
- 開催日時および場所
- 出席した株主の数、議決権の数
- 出席した役員の氏名
- 議長の氏名
- 決議事項(例:「取締役報酬改定の件」)
- 議案の具体的な内容(例:改定前後の報酬月額、各役員の報酬額など)
- 採決の結果(例:「満場一致をもって承認可決」)
- 議事録作成者の氏名
これらの要素を網羅した議事録を作成し、適切に署名・押印の上、会社に保管することが、コンプライアンスの基本です。
資金繰り悪化時 役員報酬の「未払い」をどう仕訳し、どう乗り切るか
会社の資金繰りが悪化し、役員報酬を期日通りに支払えない状況に陥ることもあります。このような場合、会計処理と税務対応を誤ると、予期せぬ税負担を招くことになりかねません。
まず、最も重要なことは、たとえ現金の支払いができなくても、毎月、定められた役員報酬の額を費用として計上し続けなければならないということです。
資金繰りが厳しいからといって、役員報酬の計上そのものを止めてしまうと、それは「期中での報酬減額」と見なされ、定期同額給与のルールに違反することになります。その結果、過去に支払った給与の一部までが損金不算入とされるリスクが生じます。
正しい処理は、支払日に以下の仕訳を行い、会社が役員に対して報酬の支払い義務を負っていることを明確にすることです。
(借方) 役員報酬 500,000円
(貸方) 未払金 または 未払費用 500,000円
この未払金は、役員個人から見れば会社に対する債権となります。ここで、経営者は一つの戦略的な選択を迫られることがあります。それは、この未払金を「役員借入金」という勘定科目に振り替えるべきかという問題です。
金融機関は、経営者個人からの役員借入金を「実質的な資本」と見なし、会社の財務評価を高くすることがあります。
しかし税務上、未払金を役員借入金に振り替える行為は、「会社が役員に報酬を一度支払い、そのお金を役員が会社に貸し付けた」と解釈されます。この「支払った」と見なされた時点で、たとえ現金の動きがなくても、会社は源泉所得税を納付する義務が発生します。
一方で、未払金のままにしておけば、源泉所得税の納付義務は、原則として実際に報酬が現金で支払われた時点で発生します。資金繰りが厳しい状況では、キャッシュアウトを先延ばしにできるメリットがあります。
つまり、銀行融資などを視野に入れて財務内容を良く見せたい場合は役員借入金への振替が有効ですが、それは手元資金がない中で納税のキャッシュアウトを伴うトレードオフが存在するのです。この判断は、会社の状況に応じて慎重に行う必要があります。
戦略シミュレーション 会社と個人の手取りを最大化する役員報酬の決め方

役員報酬のルールを理解したら、次はそのルールの中で、会社と役員個人の手元に残る現金を最大化するための戦略を立てる段階です。
法人税と所得税のトレードオフを理解する
役員報酬の額を決めることは、法人税と所得税の間の「税金の綱引き」を調整することと同じです。
役員報酬を高く設定すると、会社の利益が減るため、法人税は安くなります。しかし、役員個人の所得が増えるため、所得税・住民税の負担が大きくなります。逆に、役員報酬を低く設定すると、役員個人の所得税・住民税は安くなりますが、会社の利益が多く残るため、法人税の負担が大きくなります。
会社と役員個人は、経済的には一体です。したがって、目指すべきは「法人税」と「個人の所得税・住民税」の合計額が最も少なくなるポイントを見つけることです。このポイントが、会社と個人の手元に最も多くの現金を残す「最適報酬額」となります。
利益額別 役員報酬設定シミュレーション
言葉だけではイメージしにくいこのトレードオフを、具体的な数字で見てみましょう。ここでは、役員報酬を差し引く前の会社の利益(課税所得)が500万円だった場合のシミュレーションを行います。(※税率や控除額は簡略化した概算値であり、実際の計算とは異なります)
| 項目 | ケースA | ケースB | ケースC |
| 1. 役員報酬額(年額) | 1,000,000円 | 3,000,000円 | 5,000,000円 |
| 2. 法人利益(1の後) | 4,000,000円 | 2,000,000円 | 0円 |
| 3. 法人税等(約25%と仮定) | 1,000,000円 | 500,000円 | 0円 |
| 4. 個人の課税所得(概算) | 0円 | 1,720,000円 | 3,460,000円 |
| 5. 個人の所得税・住民税(概算) | 0円 | 258,000円 | 669,000円 |
| 6. 税金合計 (3+5) | 1,000,000円 | 758,000円 | 669,000円 |
| 7. 会社と個人の手元に残る合計額 | 4,000,000円 | 4,242,000円 | 4,331,000円 |
このシミュレーションから、いくつかの重要なことがわかります。ケースAのように役員報酬を低く抑えすぎると、法人税の負担が重くなり、全体の税金合計額はかえって高くなります。一方で、役員報酬を上げていくと、法人税は減りますが、個人の税負担が累進課税で増えていきます。
この例では、法人税と所得税の合計額が最も少なくなるのはケースCであり、結果として会社と個人の手元に残る合計額が最大化されています。
もちろん、これはあくまで一例です。最適なバランスは、会社の利益水準、役員の扶養家族の状況、社会保険料の負担など、多くの要因によって変わります。重要なのは、自社の状況に合わせてこのようなシミュレーションを行い、データに基づいて戦略的な報酬額を決定するという視点を持つことです。
まとめ
本記事で解説してきた役員報酬の会計処理と税務戦略について、最後に絶対に押さえておくべき重要ポイントを再確認します。
- 勘定科目を正しく使い分ける
役員報酬と従業員の給与手当は、税法上の扱いが全く異なるため、会計上も明確に区別することがすべての基本です。 - 損金算入の原則を遵守する
役員報酬を損金にするには「定期同額給与」「事前確定届出給与」のいずれかに該当させる必要があります。中小企業にとっては、この2つが基本戦略となります。 - 「期首から3ヶ月」の鉄則を守る
定期同額給与の金額を変更できるのは、原則として事業年度開始から3か月以内です。このタイミングを逃した変更は、重い税務上のペナルティにつながります。 - すべての決定を議事録に残す
役員報酬に関する決定は、必ず株主総会等で決議し、その内容を詳細に記載した議事録を作成・保管してください。これは税務調査に対する最も重要な防御策です。 - 役員賞与は「事前確定届出給与」で
役員に税務上認められる賞与を支払うには、事前に税務署へ届出を行う「事前確定届出給与」が唯一の道です。支給日と金額の厳守が絶対条件です。 - 未払い時も必ず仕訳を行う
資金繰りの都合で報酬を支払えない場合でも、必ず毎月「未払金」として費用計上を続けてください。計上を止めると、定期同額給与のルール違反と見なされるリスクがあります。 - 常に戦略的な視点を持つ
役員報酬の決定は、単なる経費の支払いではありません。法人税と所得税のバランスを常に意識し、会社と個人の手取りを最大化する「最適報酬額」をシミュレーションを通じて設計する、高度な税務戦略です。
これらのポイントを確実に実行することで、役員報酬をめぐる税務リスクを最小限に抑え、会社の成長を力強く後押しすることが可能になります。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…