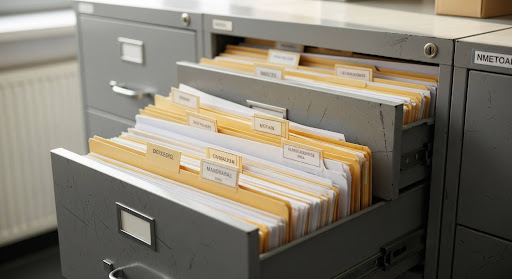
「書類の7年保管」というルールは知っていても、その「7年」をいつから数え始めればいいのか、自信を持って答えられるでしょうか。この一点を間違えるだけで、将来の税務調査で思わぬ指摘を受けるリスクがあります。この記事を最後まで読めば、その不安は確信に変わります。
本記事では、法人や個人事業主を問わず、誰もが迷う保管期間の正しい数え方から、会社法との関係、赤字決算時の特例、そして保管義務を怠った場合の罰則まで、網羅的に解説します。明日からの書類管理が、迷いなく、そして確実に行えるようになります。
複雑に見える法律も、ポイントさえ押さえれば怖くありません。具体的な計算例や、やるべきことを明確に示しますので、あなたの会社の実務にすぐに取り入れられます。
目次
これが正解!「7年保管」の正しい数え方
経理書類の「7年保管」は、法人税法で定められた事業者の重要な義務です。このルールで最も重要なのが、7年間のカウントを開始する日、すなわち起算日を正確に理解することです。
多くの方が誤解しがちですが、保管期間は書類の発行日や受領日から数え始めるのではありません。正しくは、その書類が属する事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からカウントを開始します。
法人の場合、確定申告書の提出期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。この点を踏まえて、具体的な計算方法を見ていきましょう。
法人(3月決算)の具体的な計算例
ここでは、4月1日から翌年3月31日までを事業年度とする法人を例に、2024年度(2024年4月1日から2025年3月31日)に作成・受領した帳簿書類の保管期間について、具体的な計算方法を解説します。
- 事業年度の終了日を確認する
2024年度の事業年度終了日は、2025年3月31日です。 - 確定申告書の提出期限を計算する
提出期限は事業年度終了日の翌日から2か月後なので、2025年5月31日となります。 - 保管期間の起算日(スタート地点)を特定する
起算日は、確定申告書提出期限の翌日です。したがって、スタート地点は2025年6月1日になります。 - 保管期間の満了日(ゴール地点)を計算する
起算日から満7年間保管する必要があるため、ゴール地点は2032年5月31日です。
この計算方法の背景には、税法上の理由があります。税務署が過去の申告内容に誤りを発見した場合に、税金を遡って課税(追徴課税)できる期間が原則として7年間と定められているため、その根拠資料となる書類も同じ期間保管することが求められているのです。
このルールを理解すると、実務上の大きなメリットも見えてきます。ある事業年度に属する書類は、たとえ年度初めに受け取ったものでも、年度末に作成したものでも、すべて同じ日に廃棄できるということです。
これにより、書類を保管する段ボール箱やファイルに「2024年度書類:2032年5月31日以降に廃棄可」のように年度単位で管理でき、業務が大幅に簡素化されます。
【要注意】7年とは限らない!書類保管期間の3つの重要例外
「すべての書類を7年保管すれば安心」と考えるのは早計です。実は、このルールにはいくつかの重要な例外が存在し、これを知らないと法令違反を犯す可能性があります。ここでは、すべての事業者が知っておくべき3つの例外について詳しく解説します。
例外1:会社法が定める「10年保管」の義務
法人を運営する上で、法人税法と並んで重要なのが会社法です。そして、会社法では、一部の重要な書類について10年間の保管を義務付けています。
この10年保管の対象となるのは、「会計帳簿」および「その事業に関する重要な資料」です。具体的には、総勘定元帳や仕訳帳といった主要な帳簿や、貸借対照表、損益計算書などの決算書がこれに該当します。
法人税法(7年)と会社法(10年)で期間が異なる場合、より長い方の法律に従うのが鉄則です。したがって、これらの重要書類については、10年間保管する必要があります。
なぜ二つの法律で期間が異なるのかというと、それぞれの目的が違うためです。法人税法が税務調査のために7年と定めているのに対し、会社法は株主や債権者保護の観点から、会社の財産や損益の状況をより長期間にわたって証明できるよう10年という期間を設けています。
これは民事上の時効期間なども考慮されたもので、単なる税務コンプライアンスだけでなく、企業の健全なガバナンスと法的リスク管理の観点からも重要な規定です。
一方で、個別の取引の証拠となる領収書や請求書、契約書といった書類は、会社法で明確に10年保管が義務付けられている「会計帳簿」そのものではないため、原則として法人税法の7年保管で問題ないと解釈されています。
しかし、実務上は書類の種類によって保管期間を使い分けるのは煩雑で間違いのもとになるため、多くの企業ではリスク回避と管理の簡素化のために、会計関連の書類はすべて10年で統一するという方針をとっています。
法人税法 vs. 会社法 主要書類の保管期間比較
| 書類の種類 | 法人税法 | 会社法 | 推奨保管期間 |
| 総勘定元帳、仕訳帳 | 7年 | 10年 | 10年 |
| 貸借対照表・損益計算書(決算書) | 7年 | 10年 | 10年 |
| 領収書・請求書・契約書 | 7年 | 規定なし | 7年(10年がより安全) |
例外2:赤字決算(繰越欠損金)の年度は「10年保管」が必須
事業年度が赤字(欠損)となり、青色申告をしている法人の場合、その赤字を翌年度以降の黒字と相殺して法人税の負担を軽減できる「欠損金の繰越控除」という制度があります。この制度を利用する場合、その赤字が発生した事業年度の帳簿書類の保管期間は10年に延長されます。
このルールは、欠損金の繰越控除自体が最長10年間適用可能であることと直接関連しています。つまり、税務署は、その税制優遇の根拠となる赤字が正しく計算されたものであることを、控除が適用される可能性のある全期間にわたって確認できるように、書類の保管を求めているのです。
ここで重要なのは、将来を見越した書類管理です。例えば、ある年に少額の赤字が出たとします。その時点では重要でないように思えるかもしれません。しかし、その8年後に事業が急成長し大きな利益が出た場合、8年前の赤字が節税の鍵となります。
もし、この時に7年保管のルールに従って書類を廃棄してしまっていたら、繰越控除の適用が認められず、多額の税金を納めることになりかねません。
したがって、青色申告法人で少しでも赤字が出た事業年度の書類は、金額の大小にかかわらず、自動的に「10年保管」として管理することが、将来のリスクを回避するための賢明な判断と言えます。
なお、平成30年4月1日より前に開始した事業年度に生じた欠損金については、繰越期間が9年であったため、保管期間も9年でしたが、現在では10年に統一されています。
例外3:個人事業主(青色・白色申告)の複雑なルール
個人事業主の書類保管期間は、法人よりも複雑で、青色申告か白色申告かによってルールが異なります。
青色申告者は、より詳細な帳簿付けが求められる代わりに税制上の優遇措置を受けられますが、書類保管も厳格です。仕訳帳や総勘定元帳といった複式簿記の根幹をなす「帳簿」、そして損益計算書や貸借対照表などの「決算関係書類」は7年間の保管が必要です。
同様に、領収書や預金通帳など、現金の動きに直接関わる「現金預金取引等関係書類」も7年間保管しなければなりません。一方で、見積書や注文書、納品書といった、上記以外の取引書類については5年間の保管でよいとされています。
さらに複雑なことに、7年保管が義務付けられている「現金預金取引等関係書類」についても、前々年の所得金額が300万円以下の場合には、保管期間が5年に短縮されるという特例があります。
白色申告は帳簿付けが簡易ですが、それでも書類の保管義務は存在します。収入金額や必要経費を記載した「法定帳簿」は7年間、それ以外に任意で作成した帳簿や、請求書、領収書、納品書など業務に関して作成・受領したすべての書類は5年間の保管が必要です。
このように、個人事業主のルールは非常に細分化されており、毎年所得を確認しながら書類を分別するのは非現実的で、管理ミスの原因にもなります。
そこで、最も推奨するのは、この複雑なルールを考慮せず、事業に関するすべての帳簿書類を「一律7年間保管する」というシンプルな運用です。5年で廃棄できる書類を2年間余分に保管するコストは、誤って重要な書類を捨ててしまうリスクや、管理の煩雑さに比べればごくわずかです。
個人事業主の帳簿書類 保管期間一覧
| 書類の種類 | 青色申告 | 白色申告 | 推奨保管期間 |
| 主要な帳簿 (仕訳帳、総勘定元帳など) | 7年 | 7年(法定帳簿) | 7年 |
| 決算関係書類 (損益計算書など) | 7年 | 5年 | 7年 |
| 領収書・預金通帳など | 7年(※特例あり) | 5年 | 7年 |
| 請求書・見積書など | 5年 | 5年 | 7年 |
これだけは押さえる!保管すべき「帳簿書類」の全リスト
法律で定められた期間、何を保管すればよいのかを具体的に把握しておくことは、適切な書類管理の第一歩です。法人税法などで保管が義務付けられている「帳簿」と「書類」には、主に以下のようなものが含まれます。
「帳簿」とは
「帳簿」とは、日々の取引を体系的に記録し、会社の財政状態や経営成績を明らかにするための会計記録です。これらは決算書の基礎となる非常に重要な書類です。
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 現金出納帳
- 売掛金元帳(得意先元帳)
- 買掛金元帳(仕入先元帳)
- 固定資産台帳
- 売上帳・仕入帳
「書類」とは
「書類」は、帳簿の記録内容を裏付ける証拠となる文書や、決算にあたって作成される計算書類などを指します。自社で作成したものだけでなく、取引先から受け取ったものも含まれます。
決算関係書類には、決算日時点での会社の財政状態を示す貸借対照表や、一事業年度の経営成績を示す損益計算書、期末時点での商品や製品の在庫をリストアップした棚卸表などがあります。
取引関係書類(証憑書類)には、取引の合意内容を証明する注文書や契約書、代金の請求や支払いがあったことを証明する請求書や領収書などが該当します。その他、納品書、見積書、送り状など、取引の事実を客観的に示すあらゆる書類が含まれます。
もし保管していなかったら?法令違反の恐ろしい結末
帳簿書類の保管義務を「単なる事務作業」と軽視していると、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。法令違反が発覚した場合、ペナルティは連鎖的に発生し、企業経営に深刻なダメージを与えます。その結末を、3段階の罰として解説します。
第一の罰 青色申告の承認取消と、その重大なデメリット
税務調査の際に、求められた帳簿書類を提示できない場合、その最も直接的な罰則として青色申告の承認が取り消される可能性があります。これは単に申告書の色が変わるという話ではありません。企業が享受してきた数々の税制上の優遇措置が、すべて失われることを意味します。
例えば、個人事業主にとって大きな節税効果を持つ青色申告特別控除(最大65万円)が受けられなくなります。
また、赤字を将来の黒字と相殺する欠損金の繰越控除や、30万円未満の資産を一括で経費にできる少額減価償却資産の特例も利用できなくなります。個人事業主が家族に支払う給与を経費として認める青色事業専従者給与も否認される可能性があります。
これらの優遇措置を失うことは、納税額の増加に直結し、企業の資金繰りを圧迫する大きな要因となります。
第二の罰 税務署による「推計課税」という恐怖
青色申告が取り消され、白色申告の状態になると、さらに恐ろしい「推計課税」が行われる可能性があります。これは、納税者が売上や経費の根拠となる帳簿書類を提示できない場合に、税務署が外部のデータなどから「おそらくこれくらいの所得だろう」と推計して税額を決定する制度です。
この推計課税が適用されると、悪夢のような状況に陥ります。例えば、飲食店の売上が電気やガスの使用量から推計されたり、たまたま客が多かった日の状況を基に年間の売上が算出されたりするケースがあり、実際の所得よりもはるかに過大な所得が認定されるリスクがあります。
通常の税務調査では、申告内容が誤っていることを税務署側が証明する必要があります。しかし推計課税では、「税務署の推計が間違っている」ことを納税者側が証明しなければなりません。そのための根拠書類がないため、反論は極めて困難です。
最も致命的なのは、消費税の仕入税額控除が否認されることです。仕入にかかった消費税を控除するには、請求書や帳簿の保存が絶対条件です。書類がなければこの控除が認められず、売上にかかる消費税を全額納付することになりかねません。これは事業の存続を揺るがすほどの経済的打撃となります。
第三の罰 会社法違反による過料
税法上の罰則に加え、会社法にも帳簿の作成・保存に関する規定があります。会社法第976条では、正当な理由なく会計帳簿等を作成・保存しなかった場合、100万円以下の過料に処せられると定められています。
実際には、この過料が科されるケースは税務上のペナルティに比べて稀ですが、法令違反であることに変わりはなく、企業の社会的信用を損なう一因となり得ます。最も恐れるべきは、やはり税務上の罰則です。
書類保管の未来:電子帳簿保存法への対応
デジタルトランスフォーメーションが進む現代において、書類の保管方法も大きく変化しています。その中心にあるのが電子帳簿保存法です。特に2024年1月からの改正で、すべての事業者にとって無視できない法律となりました。
3つの区分を理解する(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)
電子帳簿保存法は、書類の保存方法を大きく3つの区分に分けています。
- 電子帳簿等保存(任意)
会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿や決算書を、データのまま保存すること。 - スキャナ保存(任意)
取引先から紙で受け取った請求書や領収書を、スキャナやスマートフォンで読み取って画像データとして保存すること。 - 電子取引のデータ保存(義務)
PDFで受け取った請求書や、Webサイトからダウンロードした領収書など、電子的にやり取りした取引情報を、電子データのまま保存すること。
ここで最も重要なのは、3つ目の「電子取引のデータ保存」が、2024年1月1日からすべての事業者に対して義務化された点です。つまり、メールで送られてきた請求書を印刷して紙で保管するだけでは、もはや法令違反となるのです。
「真実性の確保」と「可視性の確保」とは?要件をわかりやすく解説
電子データを保存する際には、法律で定められた二つの要件、「真実性の確保」と「可視性の確保」を満たす必要があります。
「真実性の確保」とは、保存したデータが作成時から変更されていないことを証明するための措置です。以下のいずれか一つの方法を選択すれば要件を満たせます。
タイムスタンプが付与されたデータを受け取る。
データを受け取った後、速やかに(最長2か月と7営業日以内)自社でタイムスタンプを付与する。
訂正や削除の履歴が残る、または訂正・削除ができないシステムを利用してデータを保存する。
改ざん防止のための事務処理規程(社内ルール)を策定し、それに沿って運用する。
「可視性の確保」とは、保存したデータを、税務調査などで求められた際に、すぐに見つけて明瞭な状態で表示・印刷できるようにするための措置です。主な要件は以下の通りです。
保存場所にパソコン、ディスプレイ、プリンタなどを備え付け、操作説明書も保管しておく。
データが整然とした形式で、明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく。
「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの項目で検索できる機能を確保する。
電子取引データ保存への実践的アプローチ
義務化された電子取引データの保存要件を満たすには、主に二つのアプローチがあります。
一つ目は、手作業と社内ルールによる低コストな対応です。取引量が少ない小規模な事業者向けの方法で、改ざん防止の「事務処理規程」を策定し、ファイル名に「20241031_株式会社〇〇商事_110000」のように規則性を持たせます。さらに、これらの情報を一覧にした索引簿を別途作成することで、検索要件を満たせます。
二つ目は、システム導入による確実で効率的な対応です。ほとんどの事業者にとって、この方法が最も現実的で安全と言えるでしょう。電子帳簿保存法に対応した会計ソフトや文書管理システムを導入すれば、タイムスタンプの付与や検索機能などを自動で満たしてくれます。
システム選定の際には、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認証する「JIIMA認証」を取得している製品を選ぶと、法令要件を確実に満たせるため安心です。
電子化への対応は、もはや単なるコスト削減や業務効率化のためだけでなく、すべての事業者に課せられた法的義務となっています。
まとめ
複雑に見える書類の保管義務ですが、要点を押さえれば確実に対応できます。最後に、明日からの実務に活かすための重要ポイントを再確認しましょう。
7年保管のカウントは、書類の日付からではなく「事業年度の確定申告提出期限の翌日」から開始します。
会社法との関係や赤字決算のリスクを考慮すると、会計帳簿や決算書は「10年保管」が最も安全な選択です。
個人事業主は、青色・白色申告の複雑なルールに悩まず、「すべての事業書類を7年保管」と統一するのが現実的で確実な方法です。
書類を保管していない最大のリスクは、税務上の優遇措置を失い、「推計課税」によって実態からかけ離れた過大な税金を課されることです。
電子メールなどで受け取った請求書や領収書は、電子データのまま法律の要件に従って保存することが義務化されています。自社に合った方法で対応しましょう。
これらのポイントを正しく理解し、社内の管理体制を整備することが、将来の予期せぬリスクから会社を守るための最も確実な一歩となります。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…