
消費税の経理処理、特に「税込経理」の仕訳について、不安や難しさを感じてはいないでしょうか。本記事は、そのような悩みを自信に変えるためのものです。
複雑に思える消費税の会計処理がすっきりと整理され、日々の記帳が素早く正確に終わる未来を想像してみてください。経理業務から解放された貴重な時間で、事業の成長により一層集中できるようになります。
この記事を最後まで読むことで、税込経理の仕組みを深く理解し、自社にとって最適な経理方式を自信をもって選択できるようになります。日々の売上から決算時の複雑な仕訳まで、あらゆる取引に迷わず対応できる知識が身につきます。
専門用語をできるだけ避け、具体的な仕訳例を豊富に用いて一歩ずつ解説するため、消費税の経理が初めての方でも、すぐに自身のビジネスに応用できます。多くの事業者が直面する現実的な課題に基づき、本記事は作成されています。
目次
税込経理とは?まず知っておきたい消費税経理の基本
消費税の経理処理には、大きく分けて2つの方法が存在します。それが「税込経理方式」と「税抜経理方式」です。まずは、この基本的な違いをしっかりと理解することから始めましょう。
税込経理方式
税込経理方式とは、取引の金額を消費税を含んだ総額で記帳する方法です。たとえば、11,000円(うち消費税1,000円)の商品を販売した場合、売上を11,000円として記録します。
日々の仕訳は非常にシンプルですが、最終的に納める消費税額は決算時にまとめて計算し、「租税公課」という勘定科目を用いて経費として処理します。
税抜経理方式
税抜経理方式は、取引の金額を本体価格と消費税額に分けて記帳する方法です。同じ例でいえば、売上を10,000円、預かった消費税を「仮受消費税」として1,000円、というように分けて記録します。
日々の手間は税込経理方式に比べて増えますが、期中いつでも正確な利益や納税額を把握できるというメリットがあります。
この2つの方式のどちらを選ぶかは、消費税を納める義務がある「課税事業者」の任意です。一方で、売上規模が小さく消費税の納税が免除されている「免税事業者」は、税込経理方式で処理することが定められています。
ここで最も重要な点は、どちらの方式を選んでも、最終的に国に納める消費税の金額は同じになるということです。選択の違いは、日々の記帳プロセス、経営数値の見え方、そして法人税や所得税といった他の税金への副次的な影響に現れます。
特に2023年10月に始まったインボイス制度をきっかけに、これまで免税事業者だった多くの方が、取引先との関係から課税事業者になることを選択しました。免税事業者としての経験しかない場合、必然的に税込経理に慣れているはずです。
この記事では、そのような方々が現状のやり方を踏まえつつ、戦略的に最適な経理方式を選べるように、丁寧に解説していきます。
あなたはどっち?税込経理と税抜経理のメリット・デメリット徹底比較

自社にとってどちらの経理方式が最適かを見極めるために、それぞれのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
税込経理のメリット シンプルさが最大の魅力
日々の記帳がとにかく簡単
税込経理の最大のメリットは、そのシンプルさにあります。レシートや請求書に書かれている合計金額をそのまま入力するだけなので、直感的でスピーディーに作業が進みます。
会計ソフトを導入していない、あるいは手書きやエクセルで経理を行っている事業者にとっては、この手軽さが大きな魅力となるでしょう。
免税事業者からの移行がスムーズ
インボイス制度への対応などで、免税事業者から課税事業者になったばかりの場合、これまで慣れ親しんだ税込経理を継続することで、経理のやり方を大きく変えることなくスムーズに移行できます。
簡易課税制度との相性が抜群
後ほど詳しく解説しますが、消費税の計算方法のひとつである「簡易課税制度」を選択している場合、税込経理は非常に相性が良いです。
簡易課税は売上にかかる消費税だけで納税額を計算するため、仕入や経費にかかる消費税を細かく管理する必要がありません。そのため、税込経理のシンプルな記帳方法が適しています。
税込経理のデメリット 注意すべき3つのポイント
正確な利益が期中にわからない
売上や経費の金額に消費税が含まれているため、決算で消費税額を計算するまで、事業の本当の利益が見えにくいという大きなデメリットがあります。
期中の試算表を見て「利益が出ている」と思っていても、期末に消費税を費用計上した結果、想定より利益が少なくなってしまうこともあり、経営判断を誤る原因になりかねません。
納税額が期末までわからず、資金繰りに影響する
期末の決算作業が終わるまで、納めるべき消費税額が確定しません。これにより、納税資金の準備が後手に回り、キャッシュフローを圧迫する可能性があります。
特に個人事業主や小規模事業者にとって、予期せぬ大きな納税は深刻な問題です。
税制上の特例判定で不利になることがある
これは見過ごされがちですが、非常に重要なポイントです。経費や資産の計上に関する税制上の特例は、その「取得価額」によって適用できるかどうかが決まります。税込経理ではこの取得価額が消費税分だけ高くなるため、特例の対象から外れてしまうことがあるのです。
例えば、通常30万円未満の資産は購入した年に一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」があります。税抜28万円のパソコンは、税抜経理ならこの特例を使えます。しかし、税込経理では308,000円(280,000円 × 1.1)となり30万円を超えてしまうため、資産として計上し、数年にわたって減価償却しなければならず、節税効果が先送りになります。
また、中小企業では年間800万円までの交際費が経費として認められます。税込経理の場合、この800万円の枠に消費税額も含まれてしまうため、実質的に経費にできる交際費の本体価格が少なくなってしまいます。
一見シンプルに見える税込経理ですが、その実態は日々の手間を期末の大きな手間とリスクに先送りしているともいえます。経理の目的が単なる記帳作業ではなく、安定した事業運営であるならば、このトレードオフを慎重に考える必要があります。
どちらを選ぶべきか?あなたの事業に合った経理方式の選び方
では、結局どちらを選べばよいのでしょうか。以下の基準を参考に、自社の状況に合った方式を選択しましょう。
税込経理がおすすめの事業者
- 簡易課税制度を選択している事業者
- インボイス対応で課税事業者になったばかりで、まずはシンプルな方法から始めたい事業者
- 高額な設備投資や交際費の支出がほとんどない事業者
税抜経理がおすすめの事業者
- 会計ソフトを導入している事業者
- 毎月、正確な利益を把握して経営判断に活かしたい事業者
- 30万円未満の備品購入や、交際費の支出が多い事業者
かつては「税抜経理は複雑で大変」というイメージがありましたが、現代の会計ソフトは税抜・税込の計算を自動で行ってくれるものがほとんどです。ソフトを使っているなら、税抜経理のデメリットである手間の煩雑さは大幅に軽減されます。
むしろ、正確な経営状況の把握や節税といった戦略的なメリットを享受しやすくなるため、会計ソフトの導入と合わせて税抜経理への移行を検討する価値は非常に高いといえるでしょう。
【実践編】取引別!税込経理の仕訳方法
ここからは、税込経理方式における具体的な仕訳例を取引の種類ごとに見ていきましょう。日々の経理業務で頻繁に登場するパターンを網羅しています。
売上・売掛金の仕訳
商品を11,000円(消費税10%込)で販売し、代金は現金で受け取った場合の仕訳です。
| 借方 | 貸方 |
| 現金 11,000 | 売上 11,000 |
代金が後日払いの「掛取引」の場合は、借方の勘定科目が「売掛金」になります。
| 借方 | 貸方 |
| 売掛金 11,000 | 売上 11,000 |
仕入・買掛金の仕訳
商品を5,500円(消費税10%込)で仕入れ、代金は現金で支払った場合の仕訳です。
| 借方 | 貸方 |
| 仕入 5,500 | 現金 5,500 |
代金が後日払いの「掛取引」の場合は、貸方の勘定科目が「買掛金」になります。
| 借方 | 貸方 |
| 仕入 5,500 | 買掛金 5,500 |
経費(消耗品費、交通費など)の仕訳
事務用品を1,100円(消費税10%込)で購入し、現金で支払った場合の仕訳です。
| 借方 | 貸方 |
| 消耗品費 1,100 | 現金 1,100 |
交通費や通信費など、他の経費でも考え方は同じです。支払った総額を該当する経費科目に計上します。
固定資産の購入と減価償却の仕訳
業務用のパソコンを165,000円(消費税10%込)で購入し、現金で支払った場合の仕訳です。10万円以上の資産は原則として固定資産(この場合は「備品」)として計上します。
| 借方 | 貸方 |
| 備品 165,000 | 現金 165,000 |
この場合、減価償却の計算基礎となる取得価額は、消費税込みの165,000円となります。税抜経理であれば取得価額は150,000円となり、毎年の減価償却費もその分少なくなります。
返品・値引きがあった場合の仕訳
先に11,000円で売り上げた商品が返品され、代金を現金で返金した場合の仕訳です。売上時の仕訳をそのまま逆にするだけです。
| 借方 | 貸方 |
| 売上 11,000 | 現金 11,000 |
売掛金がまだ回収できていない場合は、貸方の勘定科目が「売掛金」となります。
軽減税率と標準税率が混在する場合の考え方
飲食店でのテイクアウト(8%)と店内飲食(10%)のように、ひとつの取引に複数の税率が混在することがあります。税込経理の場合、仕訳自体は合計金額で記帳するためシンプルです。
たとえば、取引先への手土産としてお菓子(軽減税率8%対象)5,400円と、雑貨(標準税率10%対象)2,200円をまとめて購入し、合計7,600円を現金で支払った場合(勘定科目は交際費とする)の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 |
| 交際費 7,600 | 現金 7,600 |
ただし、仕訳がシンプルだからといって、管理が不要になるわけではありません。決算時に正確な消費税額を計算するためには、どの取引が標準税率で、どの取引が軽減税率なのかを区別して記録しておく必要があります。
会計ソフトを利用している場合は、仕訳ごとや品目ごとに税率を設定する機能があるため、それを活用することが不可欠です。税込経理のシンプルさは、あくまで仕訳入力の表面的な部分だけであり、正確な税額計算のためのデータ管理は別途必要になることを覚えておきましょう。
決算時の重要ポイント!消費税の確定と納税の仕訳
税込経理における最大の山場が決算時の処理です。ここで1年間の消費税をまとめて計算し、会計帳簿に反映させます。
決算整理仕訳:「租税公課」と「未払消費税」の計上
期末になったら、まず1年間の課税売上にかかる消費税額と、課税仕入・経費にかかる消費税額を集計し、納付すべき消費税額を確定させます。
納付税額 = 課税売上にかかる消費税額 – 課税仕入等にかかる消費税額
たとえば、計算の結果、納付すべき消費税額が150,000円だったとします。この金額を費用(租税公課)と負債(未払消費税)として計上します。これが決算整理仕訳です。
| 借方 | 貸方 |
| 租税公課 150,000 | 未払消費税 150,000 |
この仕訳により、これまで売上などに含まれていた消費税分が費用として計上され、正しい期間の利益が計算されることになります。
ここで重要なのが、この「租税公課」をいつの経費にするかという点です。原則は、消費税の申告書を提出した事業年度の経費となります。しかし、決算時に「未払消費税」として計上(未払経理)することで、その事業年度の経費として計上することが認められています。
これにより、所得税や法人税の課税対象となる所得をその分減らすことができるため、実務上はこちらの方法が有利であり、広く採用されています。
納税時の仕訳
決算整理で計上した未払消費税を、翌期の納税期限までに納付します。納税した際の仕訳は、負債を取り崩すだけのシンプルなものです。
| 借方 | 貸方 |
| 未払消費税 150,000 | 現金預金 150,000 |
中間申告・納付を行った場合の仕訳
前年の消費税額が一定額を超えると、年度の途中で「中間申告」として税金を前払いする必要があります。この中間納付を行った場合、支払った時点で費用として計上します。
たとえば、中間申告で60,000円を納付した場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 |
| 租税公課 60,000 | 現金預金 60,000 |
そして期末の決算整理では、年間の確定税額150,000円から、すでに納付した中間納付額60,000円を差し引いた、残りの90,000円を「未払消費税」として計上します。
| 借方 | 貸方 |
| 租税公課 90,000 | 未払消費税 90,000 |
制度との関連性:インボイス制度・簡易課税制度と税込経理
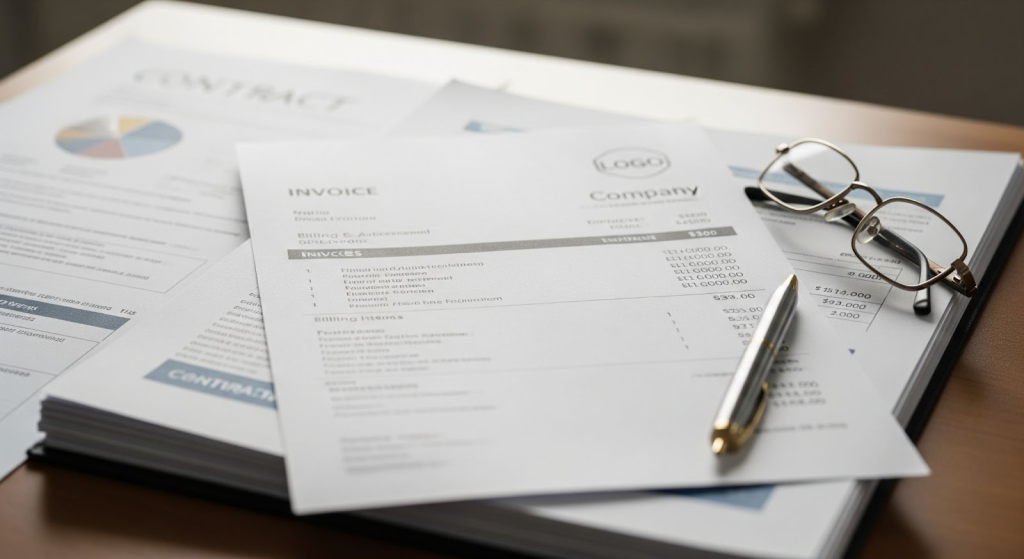
経理方式の選択は、インボイス制度や簡易課税制度といった国の税制と密接に関わってきます。
インボイス制度開始で課税事業者になったら?
インボイス制度への対応を機に、免税事業者から課税事業者になった方も多いでしょう。その場合、まずは慣れている税込経理方式でスタートするのは、非常に合理的で現実的な選択です。新しい義務に対応しながら、経理の仕組みまで一度に変えるのは大きな負担になります。
また、インボイス制度開始に伴う負担軽減措置として「2割特例」という制度があります。これは、売上にかかる消費税額の2割を納税額とするもので、非常に計算がシンプルです。
この特例は売上ベースで計算するため、仕入や経費の消費税を管理する必要がありません。そのため、2割特例の適用期間中は、記帳が簡単な税込経理方式が適しているといえるでしょう。
簡易課税制度を選択しているなら税込経理が断然おすすめな理由
簡易課税制度とは、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる、消費税計算を簡略化する制度です。実際の課税仕入額を使わず、売上にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除を計算します。
この制度の最大のポイントは、実際の経費にかかった消費税額が納税額の計算に一切影響しないことです。そのため、税抜経理方式のように、一つひとつの経費について本体価格と消費税を分けて記帳する作業は、消費税申告においては全くの無駄な手間となってしまいます。
むしろ、税抜経理と簡易課税を組み合わせると、期末に複雑な処理が必要になります。税抜経理で計算した帳簿上の納税予測額と、簡易課税で計算した実際の納税額との間に必ず差額が生じ、この差額を「雑収入」または「雑損失」として調整する仕訳が必要になるのです。
この処理は直感的でなく、経理に不慣れな方にとっては混乱やミスの原因となります。したがって、簡易課税制度を選択している事業者は、その計算方法のシンプルさと完全に一致する、税込経理方式を選択することが最も効率的で間違いのない方法だといえます。
まとめ
消費税の経理方式について、税込経理を中心に詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを再確認しましょう。
税込経理は、日々の記帳がシンプルで分かりやすい反面、期中の正確な利益が見えにくく、期末に納税額が判明するまで資金繰りの不安が残るという側面があります。
一方で税抜経理は、日々の手間は増えますが、正確な経営数値をリアルタイムで把握でき、資産購入や経費計上で税制上有利になるメリットがあります。そして、その手間は現代の会計ソフトによって大幅に軽減できます。
どちらの方式を選ぶかは、あなたの事業の状況に応じた戦略的な判断です。特に簡易課税制度を選択している場合は、計算方法と完全にマッチする税込経理が断然おすすめです。一方で、本則課税で会計ソフトを利用しており、正確な月次決算を経営に活かしたいのであれば、税抜経理がもたらすメリットは大きいでしょう。
この記事で紹介した比較や具体的な仕訳例を参考に、自社の税制(本則課税か簡易課税か)、会計ソフトの利用状況、主な経費の内容などを改めて見直してみてください。そして、あなたの事業の成長と安定を支える、最適な経理方式を自信をもって選択し、正確な経理を実現しましょう。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…