
複式簿記と聞くと、「なんだか難しそう」「専門家ではないと無理だ」と感じてはいないでしょうか。しかし、もしあなたが個人事業主やフリーランスとして、手元に残るお金を最大限に増やしたいと本気で考えているなら、複式簿記は避けて通れない、むしろ最強の武器となり得ます。
なぜなら、複式簿記を実践することで、最大65万円の青色申告特別控除という大きな節税メリットを手にすることができるからです。これは、あなたの努力の結晶である利益から、税金の負担を大きく減らすことができる、国が認めた正当な権利です。
この記事を最後まで読めば、複式簿記に対する漠然とした不安から解放されるでしょう。単なる記帳方法としてではなく、自分の事業の健康状態を正確に把握し、的確な経営判断を下すためのツールとして複式簿記を使いこなせるようになります。
お金の流れが明確になることで、「どんぶり勘定」から脱却し、自信を持って事業を成長させる未来を切り開くことができます。
簿記の知識がないからと心配する必要はありません。この記事では、簿記初心者の方でもつまずかないよう、基本的な考え方から具体的な仕訳の方法、そして個人事業主特有の会計処理まで、一つひとつ丁寧に解説します。さらに、現代では会計ソフトという強力な味方がいます。
これらのツールを使えば、複雑な作業の多くは自動化され、あなたは本質的な部分の理解に集中できます。本記事が示すステップ通りに進めれば、誰でも複式簿記を実践し、その恩恵を最大限に受けることが可能です。
目次
そもそも複式簿記とは?事業経営の土台を理解する
複式簿記は、単なるお小遣い帳の延長線上にあるものではありません。すべての法人や、本気で事業を拡大したい個人事業主が採用する、世界標準の会計ルールです。その本質を理解することが、節税と経営力向上の第一歩となります。
一つの取引を「原因」と「結果」の2つの側面で捉える考え方
複式簿記の最も中心的な考え方は、一つの取引には必ず「原因」と「結果」という2つの側面があると捉え、それを両方記録することです。
例えば、事業用に現金10万円でパソコンを購入したとします。この取引を複式簿記では次のように捉えます。
- 結果:現金という財産(資産)が10万円減った
- 原因:なぜ現金が減ったのか? → パソコンという財産(資産)が10万円増えたから
このように、「資産の減少」という結果と、「資産の増加」という原因をセットで記録するのが複式簿記の基本です。この「取引の二面性」を捉えることで、お金やモノの動きがもれなく記録され、財産全体の状況を正確に把握できるようになります。
この仕組みには、非常に優れた特徴があります。それは、記録に間違いがあればすぐに気づける自己検算機能です。複式簿記では、後述する「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の金額が必ず一致するように記録します。もし計算が合わなければ、どこかで記録ミスがあることが即座に判明します。
この仕組みによって帳簿の正確性が担保されるため、税務署への申告や金融機関への提出資料として高い信頼性が得られるのです。これが、青色申告で高い控除を受けるための「正規の簿記の原則」として複式簿記が求められる理由です。
「単式簿記」との決定的な違い
複式簿記と比較されるのが「単式簿記」です。単式簿記は、お小遣い帳や家計簿のように、お金の出入りという一つの側面だけを記録する方法です。例えば「消耗品費 5,000円」のように、何にお金を使ったかだけを記録していくため、非常にシンプルで簡単です。
しかし、このシンプルさには大きな弱点があります。単式簿記では、現金の増減はわかっても、事業全体の財産(資産や負債)がどのように変動したのかを把握することができません。そのため、事業の健全性を示す重要な書類である「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」を作成することができないのです。
青色申告の65万円(または55万円)控除を受けるためには、この貸借対照表の提出が必須条件です。したがって、最大の節税メリットを享受するためには、複式簿記の実践が不可欠となります。
| 項目 | 単式簿記 | 複式簿記 |
| 記録方法 | 取引の一つの側面(お金の増減)のみを記録する | 取引の二つの側面(原因と結果)を記録する |
| 作成できる書類 | 収支内訳書(損益計算書に類似) | 損益計算書、貸借対照表 |
| 財産状況の把握 | 難しい(現金の増減しかわからない) | 正確に把握できる(資産・負債の状況がわかる) |
| 青色申告特別控除 | 最大10万円 | 最大65万円 |
| メリット | 記帳が簡単で、簿記の知識がほぼ不要 | 経営状況を正確に把握できる 税務上の信頼性が高い 節税効果が非常に大きい |
| デメリット | 財産状況が不明確 節税メリットが小さい | 記帳に一定のルール(簿記の知識)が必要 手間がかかる(ただし会計ソフトで大幅に軽減可能) |
| おすすめの人 | 事業規模が非常に小さい とにかく記帳の手間を省きたい白色申告者 | 青色申告で最大限の節税をしたい個人事業主 正確な経営判断をしたい事業主 すべての法人 |
複式簿記をマスターする3つの絶大なメリット
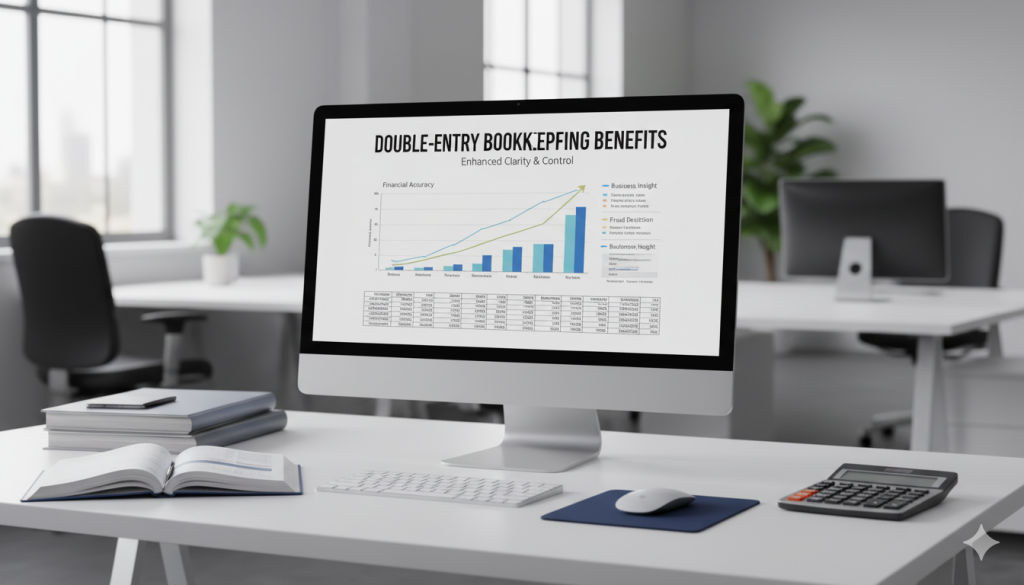
複式簿記を学ぶことは、単に面倒な作業が増えることではありません。あなたの事業を次のステージへ引き上げるための、強力な経営ツールを手に入れることを意味します。ここでは、その絶大なメリットを3つ紹介します。
メリット1:最大の目的「青色申告特別控除65万円」の実現
個人事業主にとって、複式簿記を導入する最大の動機は、やはり青色申告特別控除でしょう。これは、所得税の計算をする際に、課税対象となる所得金額から一定額を差し引くことができる制度です。
- 10万円控除
単式簿記(簡易な帳簿)でも青色申告は可能ですが、その場合の控除額は10万円です。 - 55万円控除
複式簿記で記帳し、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を提出すると、控除額は55万円に跳ね上がります。 - 65万円控除
さらに、e-Tax(電子申告)で確定申告を行うか、電子帳簿保存の要件を満たすことで、控除額は最大の65万円になります。
例えば、課税所得が400万円の人の所得税率が20%だとすると、65万円の控除を受けることで、所得税だけで「65万円 × 20% = 13万円」も税金が安くなる計算です。これは、複式簿記を学ぶ労力に見合う、非常に大きなメリットと言えます。
メリット2:どんぶり勘定からの脱却!正確な経営状況の可視化
「なんとなく儲かっている気はするけれど、実際はどうなのだろうか」という、いわゆる「どんぶり勘定」は、事業の成長を妨げる大きなリスクです。複式簿記は、この状態からあなたを解放してくれます。
複式簿記で日々の取引を記録することで、決算期には2つの重要な財務諸表が自動的に作成されます。
- 損益計算書(P/L)
一定期間(通常1年間)の経営成績を示す書類です。どれだけ売上があり、どれだけ経費がかかり、最終的にいくら儲かったのか(利益)がわかります。 - 貸借対照表(B/S)
決算日時点での財政状態を示す書類です。会社がどれだけの資産(現金、売掛金、備品など)を持ち、どれだけの負債(借入金、買掛金など)を抱えているか、そして純粋な自己資本はいくらか、が一目でわかります。
これらの書類があれば、「利益は出ているのに、なぜか手元にお金がない」といった問題の原因を突き止めたり、事業のどこに課題があるのかを客観的な数字で分析したりすることが可能になります。
メリット3:金融機関や取引先からの「社会的信用」の向上
事業を運営していると、融資を受けたい、あるいは大きな取引先と契約したい、といった場面が出てくるかもしれません。そのようなとき、あなたの事業の信頼性を客観的に証明してくれるのが、複式簿記に基づいて作成された財務諸表です。
金融機関が融資を審査する際、必ず財務諸表の提出を求めます。正確なルールに基づいて作成された貸借対照表や損益計算書は、あなたの事業の健全性や将来性を伝えるための「世界共通のビジネス言語」です。単式簿記の収支報告書では、この信頼性を十分に示すことはできません。
しっかりとした会計帳簿を備えていることは、あなたが計画的に事業を運営している証拠となり、金融機関や取引先からの「社会的信用」を高めます。これは、事業を安定させ、さらに成長させていく上で不可欠な要素です。
複式簿記の基本ルール:5つの要素と「借方・貸方」を攻略
複式簿記にはいくつかのルールがありますが、中心となるのは「5つのグループ」と「借方・貸方」の考え方です。ここさえ押さえれば、複式簿記は決して怖くありません。
会計の構成要素「資産・負債・純資産・収益・費用」とは
会社のすべてのお金やモノの動きは、必ず以下の5つのグループのいずれかに分類されます。まずはそれぞれのグループが何を表しているのか、大まかにイメージしましょう。
- 資産
会社が保有しているプラスの財産です。現金、預金、売掛金(未回収の売上)、建物、車両、備品などが含まれます。 - 負債
会社が将来支払わなければならないマイナスの財産(借金)です。借入金、買掛金(未払いの仕入代金)などが含まれます。 - 純資産
資産から負債を差し引いた、正味の財産です。事業の元手となる元入金や、これまでの利益の蓄積が含まれます。 - 収益
事業活動によって得られた収入です。商品の売上やサービスの提供料などが代表例です。 - 費用
収益を得るためにかかった支出です。仕入代金、地代家賃、水道光熱費、給料などが含まれます。
これらの5つのグループは、損益計算書(収益、費用)と貸借対照表(資産、負債、純資産)を構成する基本要素となります。
「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の覚え方とルール
複式簿記では、仕訳帳という帳簿に取引を記録する際、必ず左側と右側に分けて記入します。この左側を「借方(かりかた)」、右側を「貸方(かしかた)」と呼びます。
この左右の区別は、初心者が最初につまずきやすいポイントですが、簡単な覚え方があります。ひらがなのハネの向きで覚える方法です。
- 「かりかた」の「り」は、左にハネるので左側が借方
- 「かしかた」の「し」は、右にハネるので右側が貸方
この覚え方を使えば、左右を間違うことはありません。
そして、最も重要なルールが、5つのグループのどれが増加し、どれが減少したかによって、借方と貸方のどちらに記入するかが決まっていることです。このルールをまとめたのが以下の表です。この表が、複式簿記のすべての基本となります。
| グループ | 借方(左側)に来る場合 | 貸方(右側)に来る場合 |
| 資産 | 増加 | 減少 |
| 費用 | 発生(増加) | (取り消しなどで減少) |
| 負債 | 減少 | 増加 |
| 純資産 | 減少 | 増加 |
| 収益 | (取り消しなどで減少) | 発生(増加) |
この表の見方は、「資産が増えたら借方(左側)に書く」「負債が増えたら貸方(右側)に書く」という具合です。最初は難しく感じるかもしれませんが、取引を重ねるうちに自然と身についていきます。特に、資産と費用は「借方(左側)」がホームポジション(増える側)、負債・純資産・収益は「貸方(右側)」がホームポジションと覚えておくと便利です。
実践編:個人事業主の「仕訳」具体例ステップ・バイ・ステップ
それでは、実際に上記のルールを使って、日常的な取引を「仕訳(しわけ)」という形で記録してみましょう。仕訳とは、取引を借方と貸方に振り分ける作業のことです。
売上が発生したときの仕訳
例:取引先にサービスを提供し、代金3万円を現金で受け取った
分析
- 現金(資産)が3万円増加した → 資産の増加は借方(左)
- 売上(収益)が3万円発生した → 収益の発生は貸方(右)
仕訳
| 借方 | 貸方 |
| 現金 30,000 | 売上 30,000 |
経費を支払ったときの仕訳
例:事業の広告宣伝費として3万円を現金で支払った
分析
- 広告宣伝費(費用)が3万円発生した → 費用の発生は借方(左)
- 現金(資産)が3万円減少した → 資産の減少は貸方(右)
仕訳
| 借方 | 貸方 |
| 広告宣伝費 30,000 | 現金 30,000 |
備品を購入したときの仕訳
例:事業用のパソコン8万円を現金で購入した
分析
- 備品(資産)が8万円増加した → 資産の増加は借方(左)
- 現金(資産)が8万円減少した → 資産の減少は貸方(右)
仕訳
| 借方 | 貸方 |
| 備品費 80,000 | 現金 80,000 |
銀行から融資を受けたときの仕訳
例:銀行から3万円の融資を受け、事業用の普通預金口座に入金された
分析
- 普通預金(資産)が3万円増加した → 資産の増加は借方(左)
- 借入金(負債)が3万円増加した → 負債の増加は貸方(右)
仕訳
| 借方 | 貸方 |
| 普通預金 30,000 | 借入金 30,000 |
個人事業主特有の処理!これだけは押さえたい5つの重要仕訳

個人事業主の会計が法人と大きく違うのは、事業とプライベートの境界線が曖昧になりがちな点です。同じ財布から生活費と経費を支払ったり、自宅を事務所として使ったりすることは日常茶飯事でしょう。複式簿記では、これらの取引をルールに沿って明確に区別する必要があります。ここでは、個人事業主が必ず押さえるべき5つの特殊な処理について解説します。
事業主貸・事業主借:事業とプライベートのお金の移動
個人事業主は、事業用のお金を生活費に使ったり、逆にお金が足りないときに個人のお金で立て替えたりします。このような事業とプライベート間のお金の貸し借りを記録するための特殊な勘定科目が「事業主貸(じぎょうぬしかし)」と「事業主借(じぎょうぬしかり)」です。
- 事業主貸
事業のお金をプライベートのために使った場合に用います。「事業主が事業からお金を借りた」というイメージです。生活費の引き出しや、所得税・住民税などの個人的な税金の支払いが該当します。
例:事業用の口座から生活費として10万円を引き出した
| 借方 | 貸方 |
| 事業主貸 100,000 | 普通預金 100,000 |
事業主借
プライベートのお金を事業のために使った場合に用います。「事業主が事業にお金を貸した」というイメージです。個人のお金で事業の経費を立て替えたり、事業資金を補充したりした場合が該当します。
例:個人のお金(財布)から、事業で使う消耗品費4,000円を支払った
| 借方 | 貸方 |
| 消耗品費 4,000 | 事業主借 4,000 |
家事按分:自宅兼事務所の家賃や光熱費を経費にする方法
自宅を事務所としても利用している場合、家賃や水道光熱費、通信費などの一部を経費として計上できます。この、事業で使った分とプライベートで使った分を合理的な基準で分ける作業を「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。
重要なのは、税務署に説明できる「合理的で客観的な基準」で按分率を決めることです。
- 家賃
事業で使っている部屋の面積(例:総面積60㎡のうち事業用スペースが15㎡なら25%) - 電気代
事業で使っている時間やコンセントの数など - 自動車関連費
事業で走行した距離の割合など
例:家賃10万円を事業用の口座から支払い、事業使用割合を30%として家事按分する
まず、支払った全額を記録します。
次に、決算時などにプライベート分を経費から除く仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 |
| 地代家賃 30,000 | 普通預金 100,000 |
| 事業主貸 70,000 |
源泉徴収:報酬から天引きされた所得税の処理
ライターやデザイナーなどの特定の職種では、報酬を受け取る際に、あらかじめ所得税が天引き(源泉徴収)されていることがあります。この場合、帳簿には天引きされる前の総額を「売上」として計上する必要があります。
天引きされた源泉徴収税額は、いわば「税金の前払い」です。これは経費ではなく、確定申告で最終的に納める税額から差し引かれます。仕訳では「事業主貸」または「仮払税金」として処理します。
例:原稿料10万円の請求に対し、源泉徴収税額10,210円が差し引かれ、89,790円が普通預金に入金された
| 借方 | 貸方 |
| 普通預金 89,790 | 売上高 100,000 |
| 事業主貸 10,210 |
減価償却:10万円以上の高額な資産を購入した場合
パソコンや車、高価な機材など、取得価額が10万円以上で長期間使用する資産は、購入した年に全額を経費にすることはできません。その資産を使用できる期間(法定耐用年数)にわたって、費用を分割して計上していく必要があります。この手続きを「減価償却(げんかしょうきゃく)」といい、計上する費用を「減価償却費」と呼びます。
ただし、青色申告者には特例があり、30万円未満の資産であれば、購入した年に全額を経費として計上することが可能です(少額減価償却資産の特例)。
例:期末に、24万円で購入した車両(耐用年数6年、定額法)の1年分の減価償却費4万円を計上する
| 借方 | 貸方 |
| 減価償却費 40,000 | 車両運搬具 40,000 |
消費税:税込経理方式での処理
開業したばかりの個人事業主の多くは、消費税の納税が免除される「免税事業者」です。免税事業者の場合、経理処理は消費税額を含んだ金額で行う「税込経理方式」となります。仕訳自体はシンプルで、売上も経費も消費税込みの金額で記帳します。
その後、売上が1,000万円を超えるなどして「課税事業者」になった場合、確定申告で納めることになった消費税額は「租税公課(そぜいこうか)」という経費の勘定科目で処理します。
例:確定した消費税15万円を現金で納付した
| 借方 | 貸方 |
| 租税公課 150,000 | 現金 150,000 |
複雑な作業は不要!会計ソフトがあなたの最強の味方になる
ここまで複式簿記のルールや具体的な仕訳方法を解説してきましたが、「やはり覚えることが多くて大変そうだ」と感じたかもしれません。しかし、現代の個人事業主にはクラウド会計ソフトという非常に強力なツールがあります。これを使えば、複式簿記のデメリットであった「手間」や「複雑さ」を劇的に解消できます。
なぜ今、会計ソフトが必須なのか
かつて複式簿記は、手書きの帳簿や専門的な会計ソフトを使いこなし、簿記の知識がある人だけが行える複雑な作業でした。しかし、クラウド会計ソフトの登場がその常識を根底から覆しました。
現代の会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、AIが取引内容を推測して仕訳を自動で提案してくれます。あなたは提案された内容を確認し、クリックするだけで日々の記帳が完了します。これにより、仕訳作業にかかる時間が大幅に削減され、入力ミスも防げます。
さらに、日々の取引を入力していくだけで、青色申告に必要な貸借対照表や損益計算書、確定申告書まで自動で作成してくれます。つまり、会計ソフトは、簿記の知識が少ない初心者でも、複式簿記の恩恵を最大限に受けられるようにサポートしてくれる、まさに必須のツールなのです。
主要クラウド会計ソフト3社を徹底比較
個人事業主に人気のクラウド会計ソフトは、主に「freee会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」「やよいの青色申告 オンライン」の3つです。それぞれに特徴があるため、自分の知識レベルや使い方に合ったソフトを選ぶことが重要です。
| ソフト名 | 最大の特徴 | 簿記知識 | こんな人におすすめ | メリット | デメリット | 料金目安(年額) |
| freee会計 | 簿記の知識がなくても、質問に答える形式で直感的に入力できる | ほぼ不要 | ・簿記の知識が全くない初心者 ・借方・貸方という言葉に抵抗がある人 | ・UIが革新的で使いやすい ・スマホアプリの機能が充実 ・請求書発行など関連機能も一体化 | ・簿記の知識がある人には逆に使いにくいことがある ・独自の操作感に慣れが必要 | 約12,000円〜 |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 伝統的な会計ソフトに近い操作感と、強力な自動化機能を両立 | ある程度必要 | ・簿記の基本を学びたい、または知識がある人 ・幅広い業務を効率化したい人 | ・金融機関との連携が強力 ・レポート機能が豊富で経営分析に強い ・会計以外のサービスも充実 | ・簿記初心者には少し難しく感じる可能性がある ・機能が多く、最初は戸惑うことも | 約10,000円〜 |
| やよいの青色申告 オンライン | シンプルな機能と圧倒的なコストパフォーマンス。業界シェアNo.1の安心感 | 初心者向け | ・とにかくコストを抑えたい人 ・シンプルな操作性を求める初心者 ・手厚いサポートを重視する人 | ・初年度無料キャンペーンが強力 ・画面がシンプルでわかりやすい ・サポート体制が充実している | ・デザインがやや古く感じることがある ・請求書作成などは別サービス | 初年度無料〜 |
簿記が全くわからない初心者の方は、借方・貸方を意識させないUIの「freee会計」がおすすめです。
少し簿記をかじったことがある、あるいはこれからしっかり学びたい方は、伝統的な会計の考え方に沿いつつも強力な自動化機能を持つ「マネーフォワード クラウド確定申告」が良いでしょう。
コストを最優先し、シンプルでわかりやすいソフトを求める方には、初年度無料キャンペーンが魅力的な「やよいの青色申告 オンライン」が最適な選択肢となります。
まとめ:不安な初心者から、自信を持って経営する事業主へ
複式簿記は、単なる税金計算のための面倒な作業ではありません。それは、あなたの事業の羅針盤であり、成長へのパスポートです。
この記事で解説したように、複式簿記を実践することで、あなたは最大65万円の青色申告特別控除という直接的な経済的メリットを享受できます。それだけでなく、損益計算書や貸借対照表を通じて事業の財政状態を正確に把握し、データに基づいた的確な経営判断を下せるようになります。
かつては専門的な知識と多大な労力が必要だったこの作業も、今ではクラウド会計ソフトの登場により、簿記初心者でも十分に取り組めるようになりました。日々の取引を記録していくだけで、複雑な計算や書類作成はソフトが代行してくれます。
今日から複式簿記への一歩を踏み出すことで、あなたは「税金やお金の管理に不安を抱える初心者」から、「自社の数字を武器に、自信を持って事業を運営する経営者」へと変わることができます。この記事を片手に、ぜひその大きな一歩を踏み出してください。








建設業の2024年問題に向き合う|作業日報の効率化とDXで実…
日々の作業日報に追われる時間を短縮し、しっかりと休息を取る。あるいは、家族と過ごす時間を少しでも増や…