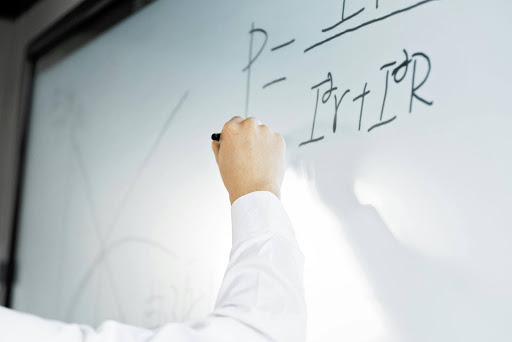
講師謝礼(講師料や講演料)を支払う際、「領収書」が必要になるケースがあります。
大学の事務担当者や企業の経理担当者、そして謝礼を受け取る講師本人にとっても、領収書の扱い方や書き方を正しく理解しておくことは重要です。
本記事では、講師謝礼の領収書が必要な場面や領収書の書き方・ポイントを具体例とともに解説します。さらに、源泉徴収や収入印紙、電子領収書の可否など税務・法務上の注意点についても詳しく説明します。
最後に、領収書作成を簡単にしてくれる便利なツール「INVOY」もご紹介します。
目次
講師謝礼とは?領収書が必要なケース
まず「講師謝礼」とは、講演会や研修、セミナーなどで講師として登壇・協力してもらったことへのお礼として支払われる金銭のことです。
大学でゲスト講師に支払う謝金や、企業が社外の専門家を招いて講義してもらう際の謝礼などが該当します。性質としては報酬(労働やサービスの対価)に近いものですが、厳密には「お礼・感謝」として支払われる位置づけです。
では、講師謝礼に対して領収書が必要になるのはどのような場合でしょうか。基本的な考え方は以下のとおりです
現金手渡しで謝礼を支払った場合
講師に謝礼を現金で手渡しする際は、講師側から支払者(大学や企業)に領収書を発行するのが原則です。日本では、金銭のやり取りがあった場合、受け取った側が領収書(領収証)を発行する義務があります。
特に現金取引では証拠が残らないため、領収書の受け渡しは必須と考えてください。支払者から求められなくても、講師のほうから積極的に領収書を渡すのが望ましいでしょう。
銀行振込で支払った場合
振込で支払った場合、振込記録(振込明細書や通帳記帳)が残るため形式上は領収書がなくても支払いの事実証明は可能です。しかし、経理処理や税務上の証憑として正式な領収書を用意することが望ましいです。
特に企業の経理では、振込であっても取引先からの領収書を保管する運用が一般的です。また、講師側にとっても後日確定申告などで収入の証明が必要になるため、領収書があった方が手続きが円滑になります。
振込の場合でも、可能であれば講師は領収書を発行し、郵送やPDF送付などで支払者に届けるようにしましょう。
少額の謝礼金の場合
謝礼金は少額(数千円〜数万円)であることも多く、「このくらいなら領収書なしでも問題ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし金額に関係なく、経費として計上する意図がある支出であれば領収書を用意すべきです。
領収書がなければ経費処理が難しくなったり、受け取った側も収入の裏付けがなく確定申告時に困る場合があります。したがって、謝礼金の額が小さくても基本的には領収書を発行・受領するという姿勢で臨んだ方がよいでしょう。
講師が法人(会社)の場合
講師が個人ではなく法人に所属し、会社から請求書が発行されるケースもあります。この場合、通常は講師側(法人側)が請求書を発行し、支払側(主催者)が支払い、その後講師側から領収書が発行される流れになります。
法人への支払いであれば厳密には源泉徴収の必要はありませんが(後述)、領収書自体は取引の証憑として発行してもらうのが通常です。
講師が法人か個人かに関わらず、「支払った側が経費処理したい」「受け取った側も収入記録を残したい」という点では共通しているため、領収書は準備しましょう。
以上のように、講師謝礼の支払いが発生したら領収書を発行・受領するのが基本と考えてください。特に大学や企業など組織の会計では、領収書なしで謝礼金を処理するのは避けるべきです。
万一領収書の発行を忘れたり紛失してしまった場合は、代替として振込明細や出金伝票(現金支出の社内記録)などで補完する方法もありますが、可能な限り正式な領収書を用意することが望ましいでしょう。
講師謝礼の領収書の書き方・ポイント
では、講師謝礼の領収書は具体的にどのように作成すればよいのでしょうか。基本的な領収書の書き方は、一般的な領収書と同じですが、講師謝礼特有のポイントもあります。以下に、手書きの場合と電子発行の場合の両方を念頭に、書き方の要点を解説します。
領収書の基本項目と記載内容
領収書には最低限、次の項目を記載します。
日付
金銭を受領した日付を記入します。講演当日に現金を受け取った場合はその日付、振込で後日受領した場合は実際に入金を確認した日付などを記載します。
宛名(支払者)
講師謝礼を支払った相手先の名称を書きます。大学名や会社名など正式名称を記載し、末尾に「御中」を付けるのが一般的です(例:「〇〇大学〇〇学部御中」「〇〇株式会社御中」)。個人が支払った場合は個人名+様でも構いません。
金額
受領した金額を記載します。後述する源泉徴収の有無によって記載金額が変わる点に注意が必要です。金額はできるだけ漢数字や円マークを交えて改ざんされにくい表記(例:「¥50,000-」や「金伍万円」)にすると良いでしょう。
消費税込みの金額か税抜き金額かも明確にします(必要に応じて但し書きで補足)。
但し書き(受領理由)
何の代金として受け取ったお金かを記します。講師謝礼の場合、具体的に「○年○月○日 ○○講演会 講師謝礼として」や「講演料として」など、講義・講演の内容や日付が分かるように記載します。複数の名目の支払いが一緒になっている場合は内訳を示すこともあります。
発行者
領収書を発行する側(=お金を受け取った側)である講師の氏名を記載し、捺印または署名します。個人講師であれば自署し、認め印を押すことが多いです。法人名義で領収書を切る場合は法人名と担当者名を記載し、会社の角印などを押します。
以上が基本項目ですが、市販の領収書用紙やExcelテンプレートを使う場合、それらのフォーマットに沿って記入すれば上記情報は網羅できるはずです。
講師謝礼の領収書の例(手書きの場合)
令和○年○月○日 受領書
〇〇大学〇〇学部御中
金 44,895円也 (※実際受け取った金額)
但し 〇年〇月〇日 講演料 50,000円(税込)
(源泉所得税額5,105円控除後)
発行者:講師氏名(署名) ※収入印紙200円貼付
上記は一例ですが、講師謝礼50,000円(消費税込み)の場合に源泉徴収後の手取額44,895円を受領したケースの書き方例です。実際には状況に応じて金額や但し書きを調整してください。
手書き領収書を書く際のポイント
紙の領収書を手書きで作成する場合は、以下の点に注意しましょう。
改ざん防止策
金額を記載する際、先頭に「¥」を付けたり、数字の後に「-」や「也」を書き足すことで、後から数字を書き足されるリスクを減らします。また、インク(ボールペンなど消えない筆記具)で記入し、訂正が必要な場合は二重線+訂正印で対応します。
収入印紙の貼付
受領金額が5万円以上(後述するように5万円ちょうど含む)であれば収入印紙を貼る必要があります。適切な額の印紙を領収書に貼り、消印としてその上に押印またはサインをすることを忘れないでください。
例えば5万円の領収書なら200円分の印紙を貼り、講師が印鑑で消印します。
控えの保管
市販の領収書には通常複写の控えが付いています。控えまたは写しを講師側(発行者側)でも保管しておきましょう。万一税務調査などで確認された場合に、誰にいくらの謝礼を受け取ったか自分でも証拠を持っておくと安心です。
手書きが面倒な場合は、後述する電子発行やテンプレートの活用も検討してください。
電子領収書(PDF等)を発行する場合のポイント
近年では、紙ではなく電子領収書(PDFやメール文面など)でのやり取りも増えています。講師謝礼についても、講師がExcelやクラウドソフトで領収書を作成し、PDFで支払者に送付する方法が可能です。電子領収書発行時のポイントは次のとおりです。
必要項目は紙と同様に
前述の基本項目(日付・宛名・金額・但し書き・発行者)は電子領収書でもすべて含めます。フォーマットは自由ですが、見やすく正式な書類として失礼のない体裁にしましょう。社名や氏名は正確に、フォントも明瞭なものを使います。
収入印紙は不要
電子データで発行・受領する領収書には収入印紙税が課税されません。紙の領収書は「課税文書」として印紙を貼る必要がありますが、PDFなど電子的に交付されるものは現行では印紙税の非課税扱いとなります。
ただし、受領側(支払者)がそのPDFを印刷して保管することはありますが、それでも発行者が紙で交付したわけではないため印紙は不要という取り扱いになります。これは電子領収書の大きなメリットの一つです。
電子帳簿保存法への対応
2022年以降、電子取引のデータ保存については電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存することが求められています。支払者側では、受け取ったPDF領収書を適切な形で電子保存(または出力して書面保存)する社内ルールがあるかもしれません。
発行者としては特別難しい対応は不要ですが、メール送付時に「電子領収書として発行します」等ひと言断りを入れておくと親切です。必要であればPDFに電子署名や発行者情報(住所や連絡先)を入れて信頼性を高めることも検討してください。
フォーマットやテンプレート活用
Word/Excelで独自に作成しても良いですが、クラウドサービスの領収書テンプレートを利用すると便利です。無料で使える雛形をダウンロードしたり、オンライン上で項目を埋めれば自動生成できるサービスもあります。
後述する「INVOY」のようなサービスを使えば、項目を入力するだけで正式な領収書PDFが出来上がり、そのままメール送信も可能です。こうしたツールを使うことで手書きの手間を省き、計算ミスも防げます。
源泉徴収額の記載方法に注意
講師謝礼の領収書を書く際に特に注意が必要なのが源泉徴収税額の扱いです。日本では、個人に対して講演料や原稿料などの報酬を支払う場合、所定の所得税を源泉徴収(天引き)する制度があります。
講師謝礼もその対象となるため、支払者は講師に支払う前に所得税を差し引き、残額を支払うことになります(差し引いた税額は後日支払者が国に納付)。
領収書には、源泉徴収された旨と金額を記載するのが一般的です。ただし明確な決まりはなく、書き方にはいくつかパターンがあります。ポイントは「報酬額(本来の謝礼額)」と「源泉徴収税額」と「実際の受取額」が分かるようにすることです。
以下に代表的な書き方を紹介します。
方式1:報酬額を金額欄に記載し、源泉徴収額を但し書き等で記載
一般的なのは、領収書の金額欄に源泉徴収前の報酬額(総額)をそのまま記載し、別途「内源泉徴収税額○○円」などと注記する方法です。
例えば講演謝礼50,000円で源泉徴収税額5,105円の場合、金額欄に「50,000円」とし、但し書きに「内源泉所得税額5,105円」と記載します。実際の手取額は但し書きの記述から差し引き計算で分かる形です。
方式2:受取額(手取額)を金額欄に記載し、総額と源泉税額を但し書きで記載
別の方法として、領収書の金額欄には実際に受け取った金額(源泉後の手取り)を記載し、但し書きに「〇〇講師料△△円(源泉所得税額○○円控除後)」のように元の報酬額と源泉徴収額を併記するパターンもあります。
先の例でいえば、金額欄を「44,895円」、但し書きに「講師料50,000円(源泉所得税5,105円控除後)」とします。この方法だと領収金額と実際支払額が一致するため、支払者の経理処理上わかりやすい利点があります。
専用の欄がある場合:領収書フォーマットによっては、「源泉徴収額:_______円」という記入欄が設けられているものもあります。その場合は指示に従って記載してください。ない場合でも上記のように但し書きで十分対応可能です。
どの方式でも間違いではありませんが、報酬額・源泉税額・受取額の対応関係が明確に伝わる書き方を心がけましょう。支払者である経理担当者から事前に「領収書は○○円でお願いします(源泉税差引後の金額)」など指示があるケースもあります。
その場合は指示に従って記載しましょう。不明点があれば支払者に確認し、「総額ベースで書くべきか」「手取り額で書くべきか」をすり合わせておくと安心です。
なお、源泉徴収額の計算方法について補足します。講師謝礼などの報酬に対する源泉徴収税額は、原則として報酬額の10.21%(復興特別所得税を含む)です。ただし1回の支払いが100万円を超える部分については20.42%の税率が適用されます。具体例を挙げると
講演料が100万円以下の場合:報酬額 × 10.21%(例:50,000円なら5,105円)
講演料が100万円を超える場合:超過分に20.42%を適用
(例:120万円なら、最初の100万円で102,100円、残り20万円に20.42%で40,840円、合計142,940円が源泉税額)
通常、講師謝礼で100万円を超えるケースは稀ですが、著名な講師を招く大型イベントなどではあり得ます。該当する場合は正確に計算しましょう。
源泉徴収額の計算は講師側で行って請求書に明記することも多いですが、事前に通知される場合もあります。講師本人としては源泉徴収された金額がいくらかを把握しておき、領収書に反映させることが大切です。
インボイス制度(適格請求書)への対応
2023年10月より開始されたインボイス制度(適格請求書保存方式)により、消費税の仕入税額控除のためには適格請求書の発行・保存が必要になりました。講師謝礼は消費税法上は原則課税取引ですが、講師が適格請求書発行事業者かどうかによって対応が異なります。
講師が適格請求書発行事業者ではない場合(個人事業主で年間売上1,000万円以下など、インボイス未登録のケース)
この場合、講師謝礼には消費税相当額を上乗せしていないことが多く、領収書にもインボイス要件を満たす記載は特に必要ありません(消費税額の記載義務はありません)。
支払者側はその領収書では仕入税額控除ができませんが、元々消費税のやり取りが発生していないので問題はありません。領収書金額は税込・税抜を意識せず「〇〇円(消費税等取扱いなし)」とするか、但し書きに「消費税対象外」等と補足してもよいでしょう。
講師が適格請求書発行事業者である場合(講師が消費税課税事業者でインボイス登録済みのケース)
この場合、講師謝礼にも消費税が含まれている(もしくは別途請求している)はずです。領収書を発行する際は、通常の適格請求書と同様に発行者の登録番号、取引年月日、取引内容(講師謝礼)、税率ごとの消費税額、税込金額、宛名(支払者の名前)などを記載する必要があります。
簡単に言えば、領収書自体をインボイス(請求書兼領収書)の形式にする形です。
例えば「適格請求書発行事業者登録番号:T1234567890123、講師料○○円、消費税○○円、合計○○円、源泉所得税○○円控除後受取額○○円」という詳細な記載になります。
大学など消費税非課税事業者への講師謝礼
大学(学校法人)など消費税の課税事業者でない組織もあります。この場合、そもそも支払者が仕入税額控除を必要としないため、講師側がインボイス発行事業者であっても簡易な領収書(消費税額の記載省略)で問題ないケースもあります。
ただし講師側が発行事業者ならインボイスを発行しないといけない義務はあるので、発行者側の責任としてきちんとした様式で発行しましょう。支払側から「請求書でなく領収書でよい」と言われても、インボイス要件を満たす領収書を発行しておけば安心です。
インボイス制度対応は少し複雑ですが、要は講師が消費税を請求する立場か否かで領収書の書き方が変わります。適格請求書発行事業者であれば自身の登録番号や税額を忘れず記載し、そうでなければ税込金額だけ明記すれば足ります。
講師謝礼は源泉徴収の方が影響大きいため、インボイスについては可能な範囲で対応しましょう。
講師謝礼の領収書における税務・法務上の注意点
講師謝礼の領収書を発行・受領する際に、税金や法規面で注意すべき事項をまとめます。源泉徴収や収入印紙といった税務上の決まりごと、そして実務で起こりがちな点について確認しましょう。
所得税の源泉徴収と事務手続き
上でも触れたように、講師謝礼は基本的に所得税の源泉徴収が必要です。
支払者(大学・企業)は、講師へ謝礼を支払う際に所得税を天引きし、その月の分をまとめて翌月10日までに税務署へ納付します(源泉徴収分の納付期限。特例で半年ごとの納付のケースもあります)。
講師本人は手取り額を受け取りますが、この源泉徴収された税金は最終的に自分の所得税に充当されます。
講師側の留意点
講師は源泉徴収された報酬を受け取った場合、年末調整や確定申告でその分を精算します。会社員が副業的に講師料を得た場合は原則確定申告が必要ですし、フリーの講師であれば事業所得または雑所得として申告します。
その際、源泉徴収された金額分だけ税金を前払いしていることになるので、確定申告書で源泉徴収税額を申告すれば精算(過不足の調整)されます。領収書に源泉額を書いていれば、その金額を手掛かりに申告漏れを防げます。
企業や大学から「支払調書」という書類をもらう場合があります。これは支払者が税務署に提出する法定調書で、講師料の金額と源泉税額が記載されたものです。支払者に交付義務はありませんが、講師にとっては年間いくら源泉徴収されたかを把握できる有益な資料です。毎年1~2月頃に前年度分が発行されることもありますので、受け取ったら大切に保管し確定申告に役立てましょう。
支払者側の留意点
講師謝礼を経理処理する際は、源泉徴収額を差し引いたネット金額で支払いつつ、経費計上は源泉徴収前の総額で行うことになります(源泉税は預り金として処理)。
例えば謝礼50,000円なら、講師に44,895円支払い、5,105円を預り金(後日納税)として仕訳します。領収書にはその両方が示されるので、経理担当者は整合性を確認しましょう。
年間を通じて同じ講師に5万円超の謝礼を支払った場合(※1月~12月の合計が5万円を超える場合)、翌年1月末までに税務署へ「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要となります。
例えば年2回講演を依頼し各3万円支払った場合(合計6万円)などが該当します。支払調書は講師個人のマイナンバーや住所氏名、支払金額と源泉税額を記載する書類です。
作成した支払調書は税務署提出用で、講師本人に交付する義務はありませんが、前述のとおり講師にコピーを提供すると親切でしょう。
収入印紙(印紙税)の貼付義務
領収書を紙で発行する場合、記載金額が5万円以上なら収入印紙を貼るのが原則です。これは印紙税法に基づくルールで、講師謝礼に限らずビジネス上の領収書全般に適用されます。印紙税額は受領金額に応じ段階的に定められています。
収入印紙の金額(領収書の場合)
| 領収書の記載金額(税込) | 印紙税額(収入印紙の金額) |
| 5万円未満 | 非課税(不要) |
| 5万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 600円 |
| 300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 | 10,000円 |
講師謝礼で1,000万円を超えることはまず無いと思われますが、念のため上表のような印紙額のルールになっています。例えば謝礼金額がちょうど50,000円の場合も200円の印紙が必要なので注意してください(5万円「以上」に含まれます)。
印紙は領収書を発行する側(講師側)の負担で貼付するのが建前です。印紙を貼らずに済ませてしまうと、後日発行者にペナルティ(過怠税)が課せられる可能性があります。
過怠税は本来の印紙税額の3倍と言われていますので、うっかりミスで高額な追徴を受けないように気を付けましょう。
もし貼り忘れに気付いた場合は、できるだけ早く税務署に申し出て所定の追納(この場合は過怠税が1.1倍に軽減されます)を行うと被害を最小限にできます。
なお、繰り返しになりますが電子領収書で発行する場合は印紙不要です。ペーパーレス化のメリットとして、印紙代の節約も検討してみる価値があります。発行側・受領側双方が電子データで問題ないと合意できるなら、最初からPDFでやり取りするのもおすすめです。
その他実務上の注意点
最後に、領収書に関連する実務上のポイントをいくつか挙げます。
謝礼と交通費の扱い
講師を招く際、講師料とは別に交通費・宿泊費等を支給することがあります。一般的に講師謝礼とは別建てで交通費等の実費が支払われる場合、それらは実費弁償として扱われ、所得税の源泉徴収は不要です。
ただし、経費精算のため講師が交通費の領収書(例:新幹線の領収書)を提出し、主催者がそれを基に支払う形になります。
主催者が講師に現金で立替経費を渡し、それに対し講師から領収書を発行するケースもありますが、厳密には講師への経費支給は領収書ではなく精算書など内部書類で処理することが多いです。謝礼と経費を混同しないよう注意しましょう。
講師が社内社員の場合
もし社内の人間に対して講師謝礼相当の支払いをする場合(例えば自社社員が研修講師を務め手当を出す等)は、それは給与や手当の一種となり、領収書は不要です(社内処理として源泉徴収も給与所得扱いになります)。
領収書が求められるのはあくまで外部への支払いであり、社内講師へは該当しません。
領収書と請求書の関係
講師によっては、事前に「請求書」を主催者に送り、後日支払いを受けたら「領収書」を発行するという正式なプロセスを踏むことがあります。一方で、口頭やメール合意だけで謝礼金額が決まり、支払い(現金手渡し等)が行われ、領収書受渡しという簡略プロセスも多いです。
どちらでも問題ありませんが、請求書を発行してもらった場合でも最終的な受領確認として領収書をもらうことが望ましいです。請求書だけでは支払った証拠にはならないため、経理上は領収書(または支払側の振込記録)が必要になります。
領収書の保管期間
受領側(支払者)は会社であれば7年間、個人事業主でも原則5~7年間は領収書を保存する義務があります。
講師側(発行者)も、自身の控えを少なくとも確定申告が終わるまでは保管し、その後も数年間は保存しておくと安心です。電子データの場合も保存期間は同様ですので、きちんとフォルダ管理やバックアップをしておきましょう。
以上の点を踏まえれば、講師謝礼の領収書に関するトラブルやミスを防ぎ、税務調査が入っても安心できる対応が取れるはずです。
簡単に領収書を作成できるツール「INVOY」の活用
講師謝礼の領収書を正しく作成するには、記載項目や源泉徴収額の計算など注意すべき点が多々あります。手作業で行うと手間がかかる上に、金額の書き間違いや印紙の貼り忘れといったミスも起こりがちです。
そこでおすすめしたいのが、クラウド請求書・領収書作成サービスの「INVOY(インボイ)」です。
INVOYは、請求書や領収書をオンライン上で簡単に発行・管理できるツールです。請求書発行から送付、入金管理までワンストップで行えるプラットフォームで、基本利用は無料から始められます。講師謝礼の領収書作成にも大いに役立つ機能が備わっています。
項目を入力するだけで書式に反映
INVOY上で日付や金額、宛名、但し書きなど必要情報を入力すると、自動的に正式な領収書フォーマットに反映されます。源泉徴収が必要な場合はチェックを入れて税率を選べば、システムが税額を自動計算してくれます。
例えば「報酬額50,000円、源泉税10.21%適用」と入力すれば、源泉税額5,105円が計算され、適切な但し書きや金額欄が整えられます。計算ミスの心配がありません。
インボイス制度や消費税にも対応
INVOYはインボイス制度対応済みのサービスです。適格請求書発行事業者として登録済みの場合、あらかじめ自社(自分)のインボイス登録番号を設定しておけば、領収書や請求書に自動で登録番号や消費税額を表示できます。
講師謝礼に消費税を課すケースでも、税率ごとの金額内訳を品目ごとに設定できるため、複雑な税込・税抜計算もスムーズです。
電子発行でそのまま送信
作成した領収書はPDF形式でダウンロードできるほか、そのまま取引相手(支払者)のメールアドレス宛に送信することも可能です。紙に印刷する必要がなく、電子領収書として発行・送付を完結できます。
相手が紙の領収書を希望する場合でも、PDFを印刷すればきれいな書式で出力できます(印紙が必要な場合は印刷後に貼付)。クラウド上にデータが残るため、後で再発行や金額確認したい時にもすぐ参照できます。
複数の帳票を一元管理
INVOYでは領収書だけでなく、請求書・見積書・納品書などビジネスに必要な帳票を一括管理できます。
講師業をされている方で、様々な依頼先に請求書→領収書というやり取りが発生する場合でも、INVOY上で案件ごとに整理できるため煩雑になりません。発行した書類は自動で番号付けされ、後から検索もしやすくなっています。
安心の法令遵守
電子帳簿保存法や改正消費税法など、最新の法令にも対応しているため、適切な保存形式やセキュリティで記録が残ります。自分でExcel管理する場合と比べ、法改正に振り回される心配が少なくなります。
このように、INVOYを活用すれば講師謝礼の領収書作成が格段に効率化されます。特に源泉徴収額や消費税計算を自動化できる点、そしてインボイス対応済みである点は大きなメリットです。
まとめ
講師謝礼の領収書について、必要となるケースや正しい書き方、源泉徴収や印紙税といった注意点を詳しく解説してきました。大学事務や企業経理にとっては経費処理の適正化、講師本人にとっては収入管理のため、領収書の発行・受領は欠かせません。
手書きでも電子でも構いませんが、今回ご紹介したポイントを押さえて作成すればトラブルなく済ませられるでしょう。
最後に触れたINVOYのような便利ツールも活用しつつ、正確でスマートな領収書管理を心がけてください。これにより講師謝礼のやり取りを円滑にし、安心して本業に取り組める環境を整えていきましょう。








不動産売買の領収書テンプレートと正しい書き方|印紙税の判定か…
不動産売買における金銭トラブルを未然に防ぎ、税務署への申告をスムーズに進めるためには、正確な領収書の…