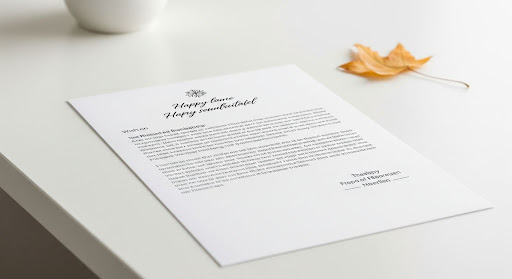
ビジネスで書類を送る際の送付状に、適切な時候の挨拶を添えることで、相手に与える印象は大きく向上します。取引先への手紙やメールに添付する送付状で、季節を感じる挨拶文を添えれば、「礼儀正しく心遣いのできる人だ」という好印象を与えられるでしょう。
この記事では、郵送とメールの両方で使える時候の挨拶の書き方やビジネスマナーを詳しく解説します。さらに、1月から12月までの月別文例、送付状のテンプレート、よくあるNG表現や実務で役立つ文例集まで、幅広く網羅しています。
この記事を読み終える頃には、誰でもすぐに失礼のない、心のこもった送付状が作成できるようになります。
目次
送付状における時候の挨拶とは?
「時候の挨拶」とは、手紙の書き出しに季節を表す言葉を用いた挨拶文のことです。ビジネス文書においても、請求書や契約書などに同封する送付状で使われることが多く、季節感や相手への心遣いを伝える大切なコミュニケーションの一つとされています。
具体的には、「拝啓」などの頭語に続けて「新春の候」や「残暑お見舞い申し上げます」といった言葉を記し、その後に相手の健康や会社の繁栄を喜ぶ文章を続けます。これにより、季節の移り変わりと相手への気遣いを簡潔な一文で表現でき、結果として誠実で丁寧な印象を与えることが可能です。
時候の挨拶は、必ず書かなければならないという厳格な決まりではありません。ビジネスでは簡潔さも重要な要素であるため、状況によっては省略することも可能です。しかし、季節感のある挨拶文を添えることで、相手に与える印象が格段に良くなるのも事実です。
特に、初めての取引先や改まった案内状を送る際には、時候の挨拶を入れることで「丁寧な対応ができる人だ」という評価につながり、円滑な関係構築に役立つでしょう。
時候の挨拶が持つ2つの表現形式
時候の挨拶には、大きく分けて「漢語調」と「口語調」の2種類の表現形式があります。漢語調とは、「○○の候」や「○○のみぎり」といった漢語を用いた簡潔な表現で、ビジネスにおける改まった文書で頻繁に使われます。
一方、口語調は「過ごしやすい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか」のように、より柔らかく話し言葉に近い表現です。こちらは個人宛ての手紙や、少しカジュアルな場面で用いられる傾向があります。
ビジネスシーンではどちらの形式を使用しても問題ありません。一般的には、フォーマルな印象を重視したい場合は漢語調を、親しみや丁寧さをより強調したい場合は口語調を選ぶと良いでしょう。
例えば、「厳冬の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」は漢語調の典型的な例です。一方で、「厳しい寒さが続いておりますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか」とすれば、口語調の柔らかい表現になります。送付状を送る相手との関係性や、伝えたいニュアンスに応じて適切に使い分けることが大切です。
時候の挨拶を書く際の基本マナーとポイント
丁寧な送付状を作成するためには、時候の挨拶そのものだけでなく、手紙としての基本的なマナーを押さえておくことが不可欠です。ここでは、時候の挨拶を添える際の重要なポイントを解説します。
頭語・結語とセットで使う
郵送で送る正式な送付状では、通常「拝啓」で書き始め、文章の最後を「敬具」で結ぶといった、頭語と結語の組み合わせを用います。時候の挨拶は、この頭語の直後に書くのが基本的なルールです。
例えば、「拝啓 初秋の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」のように書き出し、用件を記述した後に「敬具」で締めくくります。頭語と結語は必ず対になる正しい組み合わせ(一般的なビジネス文書であれば「拝啓」と「敬具」)を使用しましょう。ただし、親しい間柄であれば頭語を省略し、季節の挨拶から書き始めることもあります。
「前略」は使用しない
手紙の書き出しに「前略」という言葉を使うと、時候の挨拶や安否の伺いを省略するという意味合いになります。そのため、時候の挨拶を書き入れる場合には「前略」は用いず、必ず「拝啓」から始めて挨拶文を続けるように注意しましょう。
挨拶文は簡潔にまとめる
送付状の本来の目的は、同封した書類の内容を相手に明確に伝えることです。したがって、前置きが長くなりすぎないように配慮し、季節の挨拶や相手への気遣いの言葉も1〜2文程度の簡潔さに留めるのがマナーです。特にビジネスの場では、用件を迅速に伝えることも重要なので、挨拶文で本文が埋もれてしまわないように気をつけましょう。
相手の状況に合わせる
季節の表現を選ぶ際は、自分の地域の暦だけでなく、送り先の地域の気候も考慮することが望ましいです。例えば、自分のいる場所では桜が散っていても、相手先が寒冷地であれば、「春爛漫」といった表現よりも、冬の寒さの余韻を気遣うような挨拶を入れる方が適切でしょう。
また、手紙が相手に届くまでの時間も計算し、投函する時と相手が受け取る時で季節感に大きなズレが生じないか注意することも大切です。
砕けすぎない表現を選ぶ
取引先などへ送るビジネス文書では、親しみを出そうとするあまり、表現がカジュアルになりすぎないように注意が必要です。例えば、「毎日暑いですね!」のような砕けた挨拶は、フォーマルなビジネス文書にはふさわしくありません。時候の挨拶はあくまで礼儀の一環であるため、ビジネスシーンに相応しい丁寧な言葉遣いを心掛けましょう。
メールで送る場合、時候の挨拶は必要か?
昨今では、Eメールで書類を送付するケースも非常に多くなっています。メールの本文では、基本的に頭語や結語、そして時候の挨拶は省略するのが一般的です。オンラインでのコミュニケーションでは、郵送の手紙のような定型的な前文よりも、簡潔さやスピードが重視される傾向にあります。
通常、ビジネスメールの書き出しは「〇〇株式会社 △△部 △△様 いつもお世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。」のように、宛名、社名と氏名、そして日頃の感謝を伝える一文から始め、そのまま本題に入ります。
ただし、新年の挨拶メールなど、特に改まった内容のメールでは、短い季節の挨拶を添えることで、より丁寧な印象を与えることができます。その場合でも、「拝啓」や「敬具」といった頭語・結語は付けずに、「新春の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。」といった一文を挨拶として加える程度に留めます。
結論として、メールにおいて時候の挨拶は必須ではありませんが、内容や状況、相手との関係性に応じて一言添えると、より丁寧なコミュニケーションにつながることがあると覚えておきましょう。
【月別】時候の挨拶 例文集(1月~12月)
日本の豊かな四季を反映し、手紙では月ごとに定番とされる季節の表現があります。以下に、1月から12月まで、ビジネス文書で使いやすい時候の挨拶の例文をまとめました。
それぞれの例文の後半には、相手の健康や会社の繁栄を願う安否の挨拶が続きます。一般的に、宛先が会社全体であれば「ご清栄」、個人宛であれば「ご健勝」を用いるのが適切です。送付状を作成する際の参考にしてください。
1月: 新春の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
2月: 余寒の候、貴社いよいよご清栄の由、大慶に存じます。
3月: 早春の候、皆様のご健勝とご発展を心よりお慶び申し上げます。
4月: 陽春の候、貴社におかれましてはますますご清栄のことと拝察いたします。
5月: 新緑の候、貴社益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。
6月: 梅雨の候、ジメジメした日が続きますが、皆様お変わりございませんでしょうか。
7月: 盛夏の候、貴社の皆様におかれましては、ご健勝にお過ごしのことと存じます。
8月: 残暑の候、猛暑が続いておりますが益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
9月: 初秋の候、日増しに秋の気配が感じられる今日この頃となりました。
10月: 秋冷の候、爽やかな秋晴れの日が続いておりますが、貴社ますますご清栄のことと存じます。
11月: 晩秋の候、朝夕めっきり冷え込んでまいりましたが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。
12月: 師走の候、本年も残りわずかとなりましたが、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
上記の表現はあくまで一例です。同じ月でも上旬・中旬・下旬で表現を使い分けることもできます。例えば、7月下旬から8月上旬にかけては「暑中お見舞い申し上げます」、8月の立秋以降は「残暑お見舞い申し上げます」のように、挨拶状では時期に応じて表現を変えるのが一般的です。
ビジネスシーンでどの表現を使うか迷ったときは、季節を問わず使用できる便利な言葉「時下」を使うという選択肢もあります。「時下(じか)」とは「この頃」という意味で、「時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」のように用います。季節感は薄れますが、年間を通じて失礼なく使える表現として覚えておくと大変便利です。
【シーン別】送付状テンプレート
ここでは、実際に書類を送る場面を想定し、郵送する場合の送付状と、メールに添付する場合の送付状について、それぞれ参考となるテンプレートをご紹介します。自社の名前や日付などを適宜書き換えてご活用ください。
郵送用送付状のテンプレート例
郵送で書類を送る際に添える、正式なビジネスレター形式に則った送付状の例です。頭語・結語や時候の挨拶を含んだ構成になっています。
〇〇送付のご案内
拝啓 〇〇の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度ご依頼いただきました〇〇の資料を同封いたしましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、下記担当までお気軽にお問い合わせください。
まずは書中にて取り急ぎご連絡申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〒123-4567
東京都〇〇区〇〇町1-2-3 〇〇ビル
株式会社〇〇 〇〇部
担当:〇〇 〇〇
TEL:03-1234-5678 / E-mail:xxxxx@xxxx.co.jp
まず、件名にあたるタイトル(例:「〇〇送付のご案内」)を最初に記載します。その後に「拝啓」で始まる前文を2〜3行で構成し、時候の挨拶から日頃のお礼までを盛り込みます。
本文では、送付の旨と確認の依頼を明確に伝えます。必要に応じて、問い合わせ先の案内などを追加すると親切です。末文では「まずは書中にて」といった定型句で結び、最後に「敬具」で締めます。差出人の情報は文面の末尾にまとめて記載し、社名、部署名、担当者名と連絡先を明記しましょう。
メール添付用送付状のテンプレート例
メールに書類を添付して送る場合の文面例です。郵送の場合とは異なり、頭語や結語は用いず、簡潔に用件を伝えるスタイルが基本となります。
件名:〇〇の送付について
△△株式会社
△△部 △△様
いつもお世話になっております。
株式会社〇〇の〇〇です。
先日ご依頼いただきました〇〇の資料を添付ファイルにてお送りいたしますので、ご査収ください。
添付資料に不明な点などございましたら、ご遠慮なくお知らせください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
–(以下、メール署名)– 株式会社〇〇 〇〇部 〇〇 〇〇(氏名) TEL:03-1234-5678 E-mail:xxxxx@xxxx.co.jp
メールの場合、件名は本文とは別の入力項目です。そのため、「〇〇の送付について」など、一目で内容が分かるように簡潔に記載します。
本文では、まず相手の会社名、部署名、氏名を書き、その下に挨拶として「いつもお世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。」と続けます。その後、送付する旨を伝える文章を記載します。前述のとおり、メールでは通常、時候の挨拶は入れませんが、必要であれば「時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。」といった一文を冒頭に添えることも可能です。
結びは「何卒よろしくお願い申し上げます。」などで締め、最後に署名(自社の情報、所属、氏名、連絡先)を忘れずに入れましょう。郵送の送付状と比較して、全体的に短く、前置きも簡潔なのがメール文面の特徴です。
時候の挨拶におけるNG表現と注意点
最後に、送付状に時候の挨拶を盛り込む際に、よく見られる間違いや避けるべきNG例、そしてその改善ポイントを確認しておきましょう。知らず知らずのうちに失礼な表現を使ってしまわないよう、以下の点に注意してください。
前文を省略する「前略」は使わない
前述の通り、時候の挨拶を書く場合は頭語に「拝啓」を用い、「前略」は使用しません。「前略」は「前文を省略します」という意味を持つ言葉であり、ビジネスシーンでは緊急時などを除き、使うことは稀です。送付状では基本的に「拝啓」から始まり「敬具」で終わる形式で、挨拶文をきちんと書いてから本題に入るのがビジネスマナーです。
季節や地域に合わない挨拶は避ける
時候の挨拶が、実際の気候とかけ離れていると、受け取った相手に違和感を与えてしまいます。例えば、実際にはまだ肌寒い日が続いているのに「春爛漫の折」などと書くと、ちぐはぐな印象を与えかねません。
特に相手先が遠方の場合は、その地域の気候も考慮して挨拶文を選ぶ配慮が大切です。もし表現に迷う場合は、無理に季節の言葉を入れず、前述した「時下」を使うのが賢明です。
内容のない形式的な挨拶になっていないか
時候の挨拶は慣用的な表現が多いとはいえ、あまりに形式的すぎると、心がこもっていない機械的な印象を与えてしまうこともあります。季語を入れただけで、相手への気遣いが感じられない文章になっていないか、一度見直してみましょう。
季節の言葉に続けて「いかがお過ごしでしょうか」や「お健勝のことと存じます」といった、相手を思いやるクッション言葉を加えることで、形式的になりすぎるのを防げます。
挨拶が長すぎないか
ビジネス文書では、基本的に改まった表現が求められます。砕けた口語表現(例:「~ですよね。」など)や、不要な絵文字、顔文字の使用は厳禁です。
また、時候の挨拶が長くなりすぎるのも望ましくありません。季節の話題が長文になり、本題に入るのが遅れると、本来の目的から逸れてしまいます。時候の挨拶と相手の安否を気遣う言葉程度で簡潔に切り上げ、速やかに用件に入るように心掛けましょう。
メールでの挨拶の誤用に注意
メールにおいては、時候の挨拶を無理に入れる必要はありません。特に、急ぎの連絡や日常的に頻繁にやり取りしている相手へのメールで、凝った季節の挨拶を長々と書くと、かえって回りくどい印象を与えてしまう可能性があります。
メールでの送付案内では、定型の「いつもお世話になっております」の後は速やかに本題に入り、必要以上に長い前置きは控えるのがスマートです。
実務で使える送付状の定型フレーズ集
最後に、送付状で頻繁に使用される定型表現の文例集をまとめました。季節の挨拶文と組み合わせて使えるフレーズや、本文、結びの言葉として役立つ表現を紹介します。必要に応じて言い回しを調整しながらご活用ください。
相手の繁栄や健康を喜ぶ表現
「時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」(季節を問わず使える万能な表現)
「貴社ますますご発展の由、大慶に存じます。」(相手企業の繁栄を喜ぶ、よりフォーマルな表現)
「〇〇様におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。」(個人宛に送り、健康を願う表現)
日頃の厚情への感謝を伝える表現
「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」(取引関係のある相手への一般的な感謝の表現)
「日頃より大変お世話になっており、心より感謝申し上げます。」(お世話になっている相手への丁寧な謝辞)
「平素のご愛顧に深く感謝いたします。」(顧客などへの感謝を伝える表現)
送付内容を伝える表現
「この度、〇〇を同封いたしましたのでご査収くださいますようお願い申し上げます。」(送付状の本文で最も一般的に使われる文章)
「ご依頼いただきました〇〇の資料をお送りいたしますので、ご笑覧ください。」(資料送付の案内。ただしビジネスでは「ご査収」が無難です)
「同封の書類に不足や誤りがございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。」(書類送付時の定型的なフォローアップ)
結びの挨拶・依頼の表現
「まずは書中にてご案内かたがたご挨拶申し上げます。」(送付状の結びで用いる定型句。「ご案内まで」とすることもあります)
「略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。」(礼状などで用いる結びの定型句)
「今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。」(継続的な支援や取引を依頼する定型表現)
これらのフレーズを適切に組み合わせることで、ビジネス上の様々な送付状や挨拶状をスムーズに作成できます。自社の状況や相手との関係性に合わせて言い回しを調整し、相手に意図が伝わる丁寧な文章に仕上げましょう。
まとめ
送付状における時候の挨拶は、必ずしも記載しなければならないものではありません。しかし、ほんの一言でも季節感や相手への心遣いが感じられる文章を添えることで、相手に与える印象は確実に良くなります。
ビジネスシーンでは簡潔さが求められる一方で、丁寧さや誠実さを伝える心のこもった挨拶は、相手との良好な関係を長く続けていく上で、間違いなくプラスに働きます。
郵送であれメールであれ、今回ご紹介した文例やマナーを踏まえて送付状を作成すれば、どのような相手に対しても失礼のない、印象アップにつながるコミュニケーションが図れるはずです。
ぜひ、この記事で紹介したテンプレートや例文集を参考に、実務で活用しながら、あなたらしい言葉も織り交ぜて、心のこもった季節の挨拶文を作成してみてください。送付物に添えたそのひと手間が、相手への確かな心遣いとして伝わることでしょう。








建設業の2024年問題に向き合う|作業日報の効率化とDXで実…
日々の作業日報に追われる時間を短縮し、しっかりと休息を取る。あるいは、家族と過ごす時間を少しでも増や…