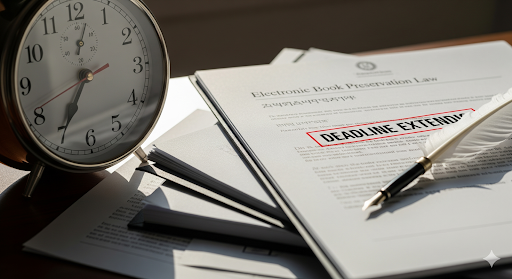
「電子帳簿保存法の対応がまた延長されたらしいけど、結局何をすればいいの?」
このような疑問を抱えているビジネスパーソンの皆様も多いのではないでしょうか。複雑な法改正のたびに、本来注力すべき業務とは異なる経理の対応に頭を悩ませるのは、もう終わりにしましょう。
この記事を最後までお読みいただくことで、2024年から適用される新しいルールを正確に理解できます。そして、最小限のコストと手間で法令に対応できるだけでなく、経理業務のペーパーレス化による生産性向上という、より良い未来を手に入れることが可能になります。
本記事では、国税庁の最新情報に基づき、世間で広まっている「延長」という誤解を解き、事業者が本当に取り組むべきことだけを具体的に解説します。
「システム導入は難しそう」「コストが心配」といった不安にも寄り添い、実はエクセルと簡単な社内ルールだけでも対応可能な方法を、ステップバイステップでご紹介します。事業規模に関わらず、今日から実践できる内容です。
目次
「電子帳簿保存法が延長された」は誤解?2024年からの新猶予措置を徹底解説
多くの事業者が「電子帳簿保存法が延長された」と考えていますが、この認識は正確ではありません。正しくは、2023年末で終了した措置に代わり、2024年1月から新しい条件付きの「猶予措置」が開始されたのです。この違いを正しく理解することが、適切な対応に向けた第一歩となります。
2023年末で終了した「宥恕措置」とは何だったのか
まず、2023年12月31日まで適用されていた「宥恕(ゆうじょ)措置」について振り返ります。この措置は、2022年1月1日に電子取引データの保存が義務化された際に、多くの事業者が準備不足であったことを受けて設けられた経過措置でした。
宥恕措置のもとでは、「やむを得ない事情」があり、かつ税務調査の際にデータを印刷した書面を提示・提出できれば、電子データ保存の要件を満たさなくてもよいとされていました。非常に幅広い事業者がこの措置に頼ることができたため、実質的に義務化が2年間先送りされたような状態でした。
しかし、この宥恕措置は2023年12月31日をもって完全に終了しています。
2024年1月から始まった新たな「猶予措置」の正体
宥恕措置に代わり、2024年1月1日から新たに「猶予(ゆうよ)措置」が導入されました。これは単なる延長ではなく、適用されるための条件がより具体的かつ厳格に定められています。
新しい猶予措置が適用されると、検索機能の確保や改ざん防止措置といった複雑な保存要件を満たさなくてもよくなります。ただし、そのためには以下の2つの条件を両方とも満たす必要があります。
一つ目は、保存要件に従って電子データを保存できない「相当の理由」があると、所轄の税務署長が認めることです。二つ目は、税務調査の際に、電子取引データのダウンロードの求めと、そのデータを印刷した書面の提示・提出の求めの両方に応じられることです。
ここで最も重要な点は、たとえ猶予措置の対象になったとしても、取引で授受した電子データそのものを必ず保存しておく必要があるという点です。以前のように「印刷して紙で保存しておけば、元のデータは不要」ということは認められませんので、注意が必要です。
猶予措置が適用される「相当の理由」とは?具体的なケースを解説
それでは、猶予措置の条件である「相当の理由」とは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか。国税庁は以下のようなケースを例として挙げています。
一つは、電子データを保存するためのシステムや、社内の業務フローの整備が間に合わない場合です。もう一つは、システムを導入・運用するための資金繰りが厳しい、または経理担当者が不足しており、要件に沿った対応が困難な場合です。
これらの理由に該当する場合、猶予措置が適用される可能性があります。この措置を受けるために、事前に税務署へ申請を行う必要はありません。ただし、税務調査の際には、なぜ法令通りの対応ができなかったのかを具体的に説明する責任が事業者側にあります。
資金繰りの状況を示す資料や、人材不足の状況を記録しておくなど、説明責任を果たせるよう準備しておくことが重要です。
猶予措置に期限はあるのか?いつまで頼れるのか?
新しい猶予措置には、法律上、明確な適用期限が定められていません。これは、一律の期限を設けることで、再び準備が間に合わない事業者が続出することを避けるための配慮と考えられます。
しかし、この措置が恒久的なものではないことを理解しておく必要があります。猶予措置は、あくまで事業者が体制を整えるまでの「つなぎ」の期間です。資金繰りが改善されたり、適切なシステムが見つかったりして「相当の理由」が解消された時点からは、本来の要件に従った保存が求められます。
また、将来的な法改正によって猶予措置が廃止される可能性も十分に考えられます。したがって、猶予措置があるからと安心するのではなく、この期間を利用して本格的な対応準備を進めることが、賢明な経営判断といえるでしょう。
【全事業者が対象】猶予があっても避けられない「電子取引データ保存」の義務化
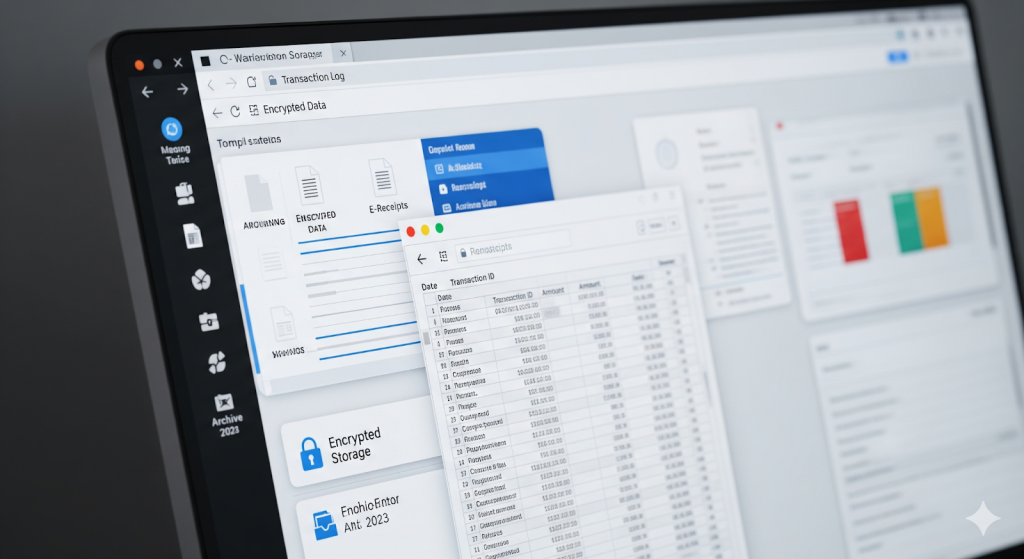
猶予措置の存在が注目されがちですが、すべての事業者が絶対に理解しなければならない大原則があります。それは、電子データでやり取りした取引情報(電子取引データ)は、電子データのまま保存しなければならないという義務です。この義務は、事業規模や業種に関わらず、すべての法人と個人事業主が対象となります。
電子帳簿保存法の3つの区分:義務と任意を正しく理解する
電子帳簿保存法は、大きく3つの区分に分かれています。このうち、すべての事業者にとって義務となるのは「電子取引データ保存」のみです。多くの方が「すべての書類を電子化しなければならない」と誤解していますが、まずはこの区分を正しく理解し、自社が対応すべき範囲を明確にしましょう。
電子帳簿等保存(任意)
会計ソフトなどで作成した国税関係帳簿(仕訳帳、総勘告元帳など)や決算関係書類を、印刷せずにデータのまま保存することです。これは任意であり、従来通り紙に印刷して保存することも認められています。
スキャナ保存(任意)
取引先から紙で受け取った請求書や領収書などを、スキャナやスマートフォンで読み取って画像データとして保存することです。これも任意であり、紙の原本をそのまま保存しても問題ありません。
電子取引データ保存(義務)
メールの添付ファイル(PDF)で受け取った請求書や、ウェブサイトからダウンロードした領収書など、最初から電子データで授受した取引情報を、データのまま保存することです。これが唯一、すべての事業者に課せられた義務です。
何が「電子取引」にあたるのか?具体例で確認
日々の業務の中で、私たちは気づかないうちに多くの電子取引を行っている可能性があります。以下に挙げるものはすべて電子取引に該当し、データの保存義務が発生します。
- 電子メールに添付されたPDF形式の請求書や領収書
- ECサイト(Amazon、楽天市場など)の購入ページからダウンロードした領収書
- クラウド請求書発行システムを通じて授受した請求書
- クレジットカードの利用明細データをウェブサイトからダウンロードしたもの
- インターネットバンキングの振込記録
- スマートフォンアプリでの決済に関する利用明細
- EDI(電子データ交換)取引
簡単に言えば、「紙ではない形で受け取った、あるいは送った取引書類」は、ほぼすべて電子取引に該当すると考えてよいでしょう。
必ず満たすべき2大要件:「真実性の確保」と「可視性の確保」
電子取引データを単に保存するだけでは不十分で、「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要があります。これらは、データの信頼性と検索性を担保するための重要なルールです。
真実性の確保(データの改ざんを防ぐ措置)
保存したデータが本物であり、後から改ざんされていないことを担保するための措置です。以下のいずれか1つの方法を選択すれば問題ありません。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領する
- データ受領後、速やかに自社でタイムスタンプを付与する
- データの訂正や削除の履歴が残るシステム、または訂正削除ができないシステムを利用する
- データの訂正削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿って運用する
中小企業にとって、最も現実的でコストがかからない方法は、4番目の「事務処理規程」を整備する方法です。
可視性の確保(データをすぐに見つけられる状態にする措置)
保存したデータを、税務調査などの際にすぐに見つけ出し、明瞭な状態で確認できるようにするための措置です。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 保存場所に、パソコン、ディスプレイ、プリンタなどを備え付け、操作マニュアルも用意しておく
- 原則として、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの項目でデータを検索できるようにしておく
中小企業向け特例:検索要件が不要になるケースとは
「可視性の確保」で求められる検索機能の確保は、システム導入が必要になるなど、中小企業にとっては負担が大きい場合があります。そこで、特定の条件を満たす事業者については、この検索要件がすべて不要になるという特例措置が設けられています。
以下のいずれかに該当する場合、検索要件は不要となります。
- 基準期間(2事業年度前)の売上高が5,000万円以下の事業者
- 電子取引データを印刷した書面を、取引年月日および取引先ごとに整理された状態で提示・提出できるようにしている事業者
この特例は、単なる負担軽減策以上の意味を持っています。これは、事業者の規模や状況に応じて、段階的に対応を進められるように設計された「コンプライアンスの階段」と考えることができます。
まず、すべての事業者は「電子データを保存する」という第一段をクリアします。そして、事業規模が小さい間は、検索機能の代わりに「整理された紙」を提出することで対応を認め、事業が成長して売上高が5,000万円を超えた段階で、次のステップである「検索機能の確保」が求められるのです。これは、すべての事業者が無理なく法対応を始められるようにという、意図的な制度設計と言えるでしょう。
明日からできる!電子帳簿保存法への具体的な対応ステップ
法律の概要を理解したところで、次に何をすべきか、具体的な行動計画に移りましょう。高価なシステムを導入しなくても、今ある環境で対応を始めることは十分に可能です。
ステップ1:社内の電子取引の現状を把握する
まずは、自社でどのような電子取引が行われているかを洗い出すことから始めます。以下の点について確認しましょう。
どの部署で、誰が、どのような電子取引データ(請求書、領収書など)を受け取っているか。データはどのような形式(PDF、ウェブ画面など)で、どの経路(メール、クラウドサービスなど)で届くか。現在、それらのデータはどこに、どのように保存されているか。
この現状把握を行うことで、対応すべき範囲と作業量が明確になり、効率的な計画を立てることができます。
ステップ2:保存方法と場所を決定する(システム導入 vs. 手動管理)
次に、電子取引データをどこに、どのように保存するかを決定します。選択肢は大きく分けて、システムを導入する方法と手動で管理する方法の2つです。
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトや専用システムを利用する方法は、要件を自動で満たせるため、最も安全で効率的です。特に取引件数が多い場合には、システム導入を検討することをおすすめします。
一方で、社内のファイルサーバーやクラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)を利用し、手作業でデータを保存・管理する方法もあります。取引件数が少ない場合は、この方法でも十分に対応が可能です。
システムを使わない場合の具体的な保存方法(ファイル名規則・索引簿作成)
コストをかけずに手動で管理する場合、国税庁が認めている具体的な方法が2つあります。どちらかの方法で「可視性の確保(検索機能)」の要件を満たすことができます。
方法A:ファイル名に規則性を持たせる
受け取った電子データのファイル名を、「取引年月日_取引先名_金額」といった形式で統一して保存します。例えば、「20241031_株式会社サンプル商事_110000.pdf」のように設定します。
このようにファイル名を統一しておけば、パソコンの検索機能で日付や取引先名を指定して、必要なデータをすぐに見つけ出すことが可能になります。
方法B:索引簿(エクセル管理表)を作成する
ファイル名は自由につけて保存し、別途エクセルで索引簿を作成する方法です。エクセルに「取引年月日」「取引先名」「金額」「ファイル名」などの項目を設け、一覧表を作成します。
| 取引年月日 | 取引先名 | 金額 | ファイル名 |
| 2024/10/31 | 株式会社サンプル商事 | 110,000 | invoice_123.pdf |
| 2024/11/05 | 合同会社テスト | 55,000 | receipt_abc.pdf |
このエクセルファイルのフィルタ機能を使えば、取引年月日や取引先名での検索が可能となり、検索要件を満たすことができます。
改ざん防止のための「事務処理規程」作成方法
「真実性の確保」の要件を満たす最も簡単な方法は、「事務処理規程」を社内に備え付けることです。これは、電子取引データの取り扱いに関する社内ルールを文書化したものを指します。
難しく考える必要はありません。国税庁のウェブサイトには、法人向け、個人事業主向けの規程のサンプル(ひな形)が用意されています。これをダウンロードし、自社の実態に合わせて責任者や具体的な処理手順などを修正するだけで、有効な事務処理規程として認められます。
コストを抑えて賢く対応!IT導入補助金と会計ソフト活用術

手動での管理も可能ですが、将来的な業務効率化を見据えるなら、会計ソフトなどのITツール導入がおすすめです。その際、国の補助金を活用すれば、コスト負担を大幅に軽減できます。
電子帳簿保存法対応に使える「IT導入補助金」とは
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際の費用の一部を国が補助する制度です。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトなどが補助の対象となります。
補助金の枠組み(類型)にもよりますが、ソフトウェアの購入費用やクラウドサービスの利用料(最大2年分)などが対象となり、費用の最大4分の3程度が補助される場合もあります。PCやタブレット、スキャナといったハードウェアの購入費用も対象となることがあるため、経理業務のデジタル化をまとめて進める絶好の機会です。
補助金申請の基本フローと注意点
IT導入補助金の申請は、事業者単独ではなく、「IT導入支援事業者」として登録されたベンダーと共同で行うのが特徴です。申請のプロセスを始めるには、まず行政手続きのオンライン窓口である「gBizIDプライム」アカウントの取得が必要です。
取得には2週間程度かかる場合があるため、早めに準備しましょう。また、情報セキュリティ対策に取り組むことを宣言する「SECURITY ACTION」の自己宣言も求められます。
準備が整ったら、IT導入支援事業者と相談し、導入したいITツールを選定します。その後、IT導入支援事業者と共同で事業計画を作成し、オンラインで交付申請を行います。事務局による審査を経て採択されると「交付決定」の通知が届きます。
ITツールの契約や支払いは、必ずこの交付決定の通知を受けた後に行う必要があります。交付決定前に契約・支払いをした費用は補助金の対象外となってしまうため、順番を間違えないよう注意が不可欠です。事業完了後に実績報告を行うと、補助金が交付されるという流れになります。
主要会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)の電帳法対応機能比較
電子帳簿保存法への対応を最もスムーズに進める方法は、対応済みのクラウド会計ソフトを導入することです。ここでは、国内で広く利用されている3つの主要なソフトの対応状況を比較します。
| 機能 | マネーフォワード クラウド | freee会計 | 弥生 |
| 優良な電子帳簿対応 | ◯ | ◯ | △ (デスクトップ版は対応、オンライン版は一部非対応) |
| スキャナ保存 | ◯ (クラウド経費などで対応) | ◯ (ファイルボックスで対応) | ◯ (スマート証憑管理で対応) |
| 電子取引データ保存 | ◯ (クラウドBoxで対応) | ◯ (ファイルボックスで対応) | ◯ (スマート証憑管理で対応) |
| JIIMA認証 | ◯ | ◯ | ◯ (スマート証憑管理) |
| 特徴 | 銀行・カード連携が豊富で自動化に強い | UIが直感的で簿記初心者でも使いやすい | デスクトップ版の実績が豊富でサポートが手厚い |
| 料金目安(年額) | 約3万円〜 | 約2.3万円〜 | 約2.6万円〜 |
JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトウェアを認証する制度です。この認証を受けているソフトは、法令要件を確実に満たしていると判断できるため、安心して選ぶことができます。
まとめ
最後に、本記事の要点を再確認します。
「延長」という認識は誤解です。2024年からは新たな「猶予措置」が始まりましたが、適用には条件があり、いつまでも頼れるものではありません。対応を先延ばしにすることは経営上のリスクとなり得ます。
次に、「電子取引データ保存」はすべての事業者の義務であるという点です。猶予措置の有無にかかわらず、メールやウェブで受け取った請求書などの電子データは、必ず電子データのまま保存しなければなりません。
そして、対応方法は一つではありません。コストをかけずに手動管理(ファイル名規則やエクセル索引簿)から始めることも可能です。本格的な効率化を目指すなら、「IT導入補助金」を活用して会計ソフトを導入するのが賢明な選択です。
電子帳簿保存法への対応は、単なる法改正への受け身の対応と捉えるべきではありません。これは、ペーパーレス化を推進し、バックオフィス業務の生産性を向上させるための絶好の機会です。この変化を前向きに捉え、自社の成長につなげる一歩として、今日から具体的な行動を始めていきましょう。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…