
電子帳簿保存法への対応と聞くと、「面倒だ」「コストがかかる」「よくわからない」と感じるかもしれません。しかし、この法律への対応を後回しにすると、ある日突然、税務調査で思わぬペナルティを課され、事業の根幹を揺るがす事態になりかねません。
この記事を手に取ったあなたは、そうした漠然とした不安を解消し、罰則のリスクから会社を確実に守るための具体的な知識を求めているはずです。
その目的は、この記事を読み終えることで達成されます。罰則の不安から解放され、むしろ法対応を事業成長の追い風に変える未来が待っています。
本記事は、複雑な法律の条文をビジネスの現場で使える平易な言葉に翻訳した、実践的な記事です。2024年1月から本格施行された新ルールを含め、最新の情報を網羅しています。
この記事を読めば、罰則の具体的な内容から、それを回避するための現実的なステップ、さらにはコンプライアンスを業務効率化やコスト削減につなげる方法まで、すべてを理解できます。
「うちのような小さな会社でも大丈夫だろうか?」「高価なシステムを導入しないと対応できないのでは?」といった心配は不要です。
最も重い罰則は、意図的な不正行為に対して課されるものであり、誠実な事業者が犯しがちな手続き上のミスが、即座に致命的な結果につながるわけではありません。
すべての事業者にとって、規模や業種を問わず実行可能な、賢いコンプライアンスの道筋が存在します。さあ、一緒にその道を一歩ずつ確認していきましょう。
目次
最悪の場合どうなる?電子帳簿保存法に違反した場合の3大罰則
電子帳簿保存法への対応を怠った場合、事業者は主に3つの大きなリスクに直面します。これらはそれぞれ異なる法律に基づいており、税金面だけでなく、会社の信用にも関わる重大なものです。ここでは、それぞれの罰則の内容を具体的に解説します。
罰則1:青色申告の承認が取り消されるリスク
多くの事業者にとって最も身近で影響が大きいのが、青色申告の承認取消しのリスクです。青色申告は、正規の簿記の原則に従って帳簿を記録・保存することを条件に、税制上の様々な優遇措置を受けられる制度です。
電子帳簿保存法は、この「帳簿の保存」に関するルールを定めているため、同法への違反は青色申告の承認要件を満たさないと判断される可能性があります。
具体的に承認が取り消されると、以下のような金銭的なデメリットが発生します。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる
- 事業で発生した赤字(欠損金)を翌年以降の黒字と相殺して法人税を軽減する「欠損金の繰越控除」が利用できなくなる
- 30万円未満の資産を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」が使えなくなる
ただし、法律の要件をわずかに満たしていなかったからといって、即座に承認が取り消されるわけではありません。国税庁は、違反の程度や今後の改善可能性などを総合的に勘案して判断するとしています。
例えば、電子取引のデータを一部、紙で保存していたとしても、その取引が正しく記帳され申告に反映されており、他の書類で取引内容が確認できるような場合には、直ちに取り消されることはないと説明されています。
一方で、税務調査において正当な理由なく電子データの提示を拒否したり、税務署長の指示に従わなかったりした場合は、悪質なケースと見なされ、承認取消しの対象となる可能性が高まります。
ここから読み取れるのは、税務当局が問題視するのは、意図的な隠蔽や調査への非協力的な態度であり、誠実に対応しようとする中での手続き上のミスではないということです。この罰則の適用は、事業者の意図が大きく影響する点を理解しておくことが重要です。
罰則2:最大45%の重加算税が課される可能性
2つ目の罰則は、意図的な不正行為に対するペナルティである重加算税の加重措置です。税務調査で、電子データ(スキャナ保存データや電子取引データ)に関連して、事実の仮装(偽の契約書や請求書の作成など)や隠蔽(売上の除外など)が発覚した場合、通常の重加算税に加えて、さらにペナルティが課されます。
具体的には、まず仮装・隠蔽行為によって生じた申告漏れに対して、本来納めるべき税額の35%が重加算税として課されます。その不正行為が電子データに関連するものであった場合、その税額に対してさらに10%が上乗せされます。
結果として、申告漏れした税額に対して合計45%という非常に重い税率のペナルティが課されることになります。この10%の加重措置は、2022年の法改正で導入されたもので、デジタル化の進展に伴い、電子データの改ざんによる不正行為を厳しく取り締まるという政府の明確な意思表示です。
この罰則が適用されるのは、あくまで「仮装・隠蔽」という悪質な意図が認定された場合に限られます。単なる保存要件の不備や、入力ミスといった過失による申告漏れの場合には適用されません。しかし、ひとたび適用されれば事業経営に深刻な打撃を与えるため、電子データの適正な管理体制を構築することが、不正の抑止力としても極めて重要になります。
罰則3:会社法に基づく100万円以下の過料
3つ目の罰則は、税法ではなく会社法に基づくものです。会社法第976条では、帳簿や事業に関する重要な書類を適切に作成・保存しなかった場合、100万円以下の過料(行政上の秩序罰であり、前科にはならない罰金)に処すると定められています。
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の「適切な保存方法」を具体的に定めた法律です。したがって、特に義務化されている電子取引データの保存を怠ることは、電子帳簿保存法違反であると同時に、会社法が求める帳簿保存義務の違反にも該当する可能性があるのです。
この罰則は、電子帳簿保存法の問題を単なる「税金の問題」ではなく、「企業統治(コーポレート・ガバナンス)の問題」へと引き上げます。帳簿の適正な保存は、株主や債権者といったステークホルダーに対する会社の基本的な責任です。
この責任を怠ることは、会社の信頼性を損なう行為と見なされかねません。経理部門だけでなく、経営層もこのリスクを認識し、全社的な課題としてコンプライアンス体制を整備する必要があります。
罰則の概要
| 罰則の種類 | 根拠法 | 内容 | 主な対象行為 |
| 青色申告の承認取消 | 法人税法・所得税法 | 青色申告の特典(特別控除、欠損金繰越など)が受けられなくなる。 | ・帳簿書類の保存義務違反 ・税務調査でのデータ提示拒否 ・税務署長の指示への不服従 |
| 重加算税の加重措置 | 国税通則法・電子帳簿保存法 | 通常の重加算税35%に、さらに10%が上乗せされ、最大45%の追徴課税となる。 | ・電子データの改ざん、偽造 ・売上除外や架空経費の計上など、電子データを用いた意図的な仮装 ・隠蔽行為 |
| 会社法上の過料 | 会社法 | 100万円以下の過料が科される可能性がある。 | ・帳簿や重要書類の不作成 ・法律の要件を満たさない不適切な保存 |
罰則の対象となる具体的な違反ケース
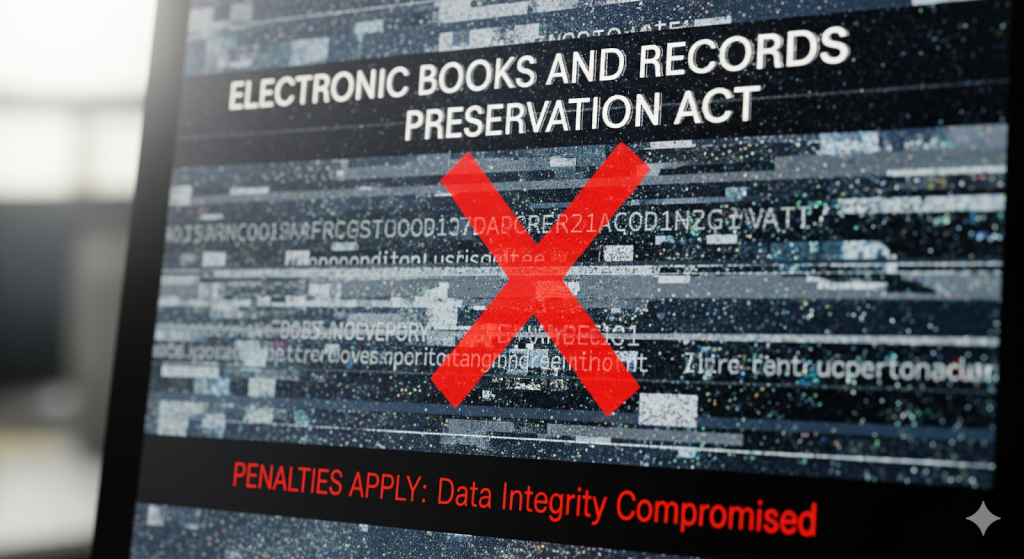
法律の条文だけでは、自社のどの業務がリスクに該当するのか分かりにくいものです。ここでは、罰則の対象となりうる具体的な違反ケースを3つ挙げ、日々の業務に潜む危険性を明らかにします。
ケース1:電子取引データを紙に出力して保存している
これが、現在最も多くの事業者が意図せず違反してしまっている可能性が高いケースです。2024年1月1日以降、メールの添付ファイルで受け取った請求書や、インターネット通販サイトからダウンロードした領収書などの「電子取引」データは、電子データのまま保存することが義務化されました。
これまでは、これらのデータを印刷して紙で保存することも「宥恕措置」として認められていましたが、この措置は2023年12月31日をもって終了しました。したがって、現在、電子データで受け取った請求書を印刷し、紙のファイルに綴じて保管している場合、その行為自体が法律違反となります。
ここでいう「電子取引」の範囲は非常に広く、以下のようなものがすべて含まれます。
- PDFなどの請求書や領収書が添付された電子メール
- Amazonや楽天などのECサイトからダウンロードする領収書データ
- クラウド請求書発行サービスを介して授受するデータ
- EDI(電子データ交換)システムによる取引情報
- メール本文に取引内容が記載されている場合や、Webサイトの画面キャプチャ(スクリーンショット)
現代のビジネスにおいて、これらの電子取引を一切行っていない事業者はほとんど存在しないでしょう。つまり、このルールは事実上、すべての事業者にとって対応必須の課題です。長年の習慣でつい印刷してしまう行為が、コンプライアンス上の大きなリスクとなっているのです。
ケース2:保存要件(真実性の確保・可視性の確保)を満たしていない
電子取引データを単にパソコンのフォルダに保存しておくだけでは、法律の要件を満たしたことにはなりません。法律は、保存するデータが「真実性」と「可視性」の2つの要件を満たすことを求めています。
真実性の確保
「真実性の確保」とは、保存されたデータが後から改ざんされていないことを証明するための措置です。以下のいずれか一つの方法を選択する必要があります。
- 訂正や削除の履歴が残るシステム、または訂正削除ができないシステムを利用してデータを授受・保存する。
- タイムスタンプが付与されたデータを受け取る。
- データを受け取った後、速やかに(最長2ヶ月とおおむね7営業日以内に)タイムスタンプを付与する。
- データの訂正・削除に関して厳格なルールを定めた「事務処理規程」を作成し、それに沿って運用する。
可視性の確保
「可視性の確保」とは、税務調査などの際に、必要なデータをすぐに見つけ出し、明瞭な状態で確認できるようにしておくことです。主な要件は以下の通りです。
- 保存場所にパソコン、ディスプレイ、プリンタなどを備え付け、操作マニュアルと共にいつでもデータを表示・印刷できるようにしておく。
- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目でデータを検索できるようにしておく。
ここで重要なのは、法律が多様な対応方法を認めている点です。高価な専用システムを導入しなくても、例えば4番目の「事務処理規程」を策定し、ファイル名に規則性を持たせる(例:「20241031_株式会社〇〇商事_110000.pdf」)といった運用で、コストをかけずに真実性と可視性の要件を満たすことが可能です。
また、検索要件についても、基準期間(2期前)の売上高が5,000万円以下の事業者であれば、税務調査官のダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、検索機能の確保は不要となる緩和措置があります。自社の規模や状況に合わせて、最適な対応策を選択できるのです。
ケース3:税務調査でデータの提示を拒否、または改ざんが発覚した
これは最も悪質なケースと見なされ、厳しい罰則が適用される可能性が極めて高い行為です。税務調査において、調査官から法令に基づいて電子データの提示を求められた際に、正当な理由なくこれを拒否した場合、青色申告の承認が取り消される直接的な原因となります。
コンプライアンスとは、単にデータを保存することだけでなく、調査に対して誠実に対応する姿勢も含まれます。システムトラブルなどで一時的に提示できない場合でも、その状況を真摯に説明し、復旧に努める姿勢が求められます。
さらに、提示したデータに改ざんや隠蔽の痕跡が見つかった場合は、前述の重加算税10%加重という厳しいペナルティの対象となります。電子データは、その気になれば容易に改変できてしまうからこそ、法律は意図的な不正に対して厳しい姿勢で臨んでいます。データの完全性を保つ管理体制の構築が、結果的に自社を守ることにつながります。
罰則を回避するための具体的な対策
罰則の内容と違反ケースを理解したところで、次はいよいよ具体的な対策です。ここでは、すべての事業者が今日から取り組める、罰則を回避するための方法を解説します。
全事業者が対応必須!「電子取引」の保存方法を理解する
電子取引データの保存は、もはや避けて通れない義務です。以下の4つのステップに従って、社内のルールを整備しましょう。
1. 社内の電子取引をすべて洗い出す
まずは、自社でどのような電子取引が発生しているかを把握することから始めます。経理部門だけでなく、営業や購買など各部門にヒアリングし、メールで受け取る請求書、Webサイトで決済する経費、クラウドサービス経由の契約書など、あらゆるパターンをリストアップします。
2. 真実性の確保の方法を決める
前述した4つの選択肢の中から、自社に合った方法を選びます。多くの中小企業にとっては、コストをかけずに始められる「事務処理規程の策定」が最も現実的な選択肢となるでしょう。
3. 保存場所とファイル名のルールを定める
データをどこに、どのように保存するかを決めます。共有サーバーやクラウドストレージ上に「電子取引データ」といった専用フォルダを作成し、その中に年度別、月別、取引先別などの階層構造を作ると管理しやすくなります。
そして、検索要件を満たすために、ファイル名の命名規則を統一します。例えば、「取引年月日_取引先名_金額.pdf」(例:20241031_〇〇商事_110000.pdf)のようにルール化すれば、手動でも検索要件に対応できます。
4. ルールに従ってデータを保存する
実際にルールを運用します。メールで受信したPDFは命名規則に従ってリネームし、所定のフォルダに保存します。Webサイトから領収書をダウンロードする場合も同様です。メール本文に情報が記載されている場合は、メール自体をPDF化して保存するか、メールソフトのフォルダ機能で保存します。
2024年からの新しい「猶予措置」を正しく知る
「どうしてもシステムの準備が間に合わない」という事業者向けに、2024年1月1日から新しい「猶予措置」が設けられています。ただし、これは以前の「宥恕措置」とは全く異なるものであり、内容を正しく理解する必要があります。
この猶予措置を受けるためには、以下の2つの条件を両方満たさなければなりません。
- 保存要件に従って電子データを保存できなかったことについて、「相当の理由」(システムの導入が間に合わない、資金繰りや人手不足など)があると税務署長が認めること。
- 税務調査の際に、①電子データのダウンロードの求めと、②そのデータを出力した書面の提示・提出の求めの両方に応じられるようにしていること。
ここでの最大のポイントは、猶予措置が適用される場合でも、電子データを破棄してよいわけではないという点です。単に検索要件や真実性の確保(タイムスタンプや事務処理規程など)のルールが免除されるだけで、元の電子データ自体は必ず保存しておく必要があります。
つまり、この猶予措置は、紙での保存を認めるものではなく、完全な法対応へ移行するまでの「橋渡し」的な制度です。安易にこの措置に頼るのではなく、あくまで一時的な対策と位置づけ、速やかに完全な対応体制を構築することを目指すべきです。
中小企業におすすめの実践策:事務処理規程の策定と運用
コストをかけずに電子帳簿保存法に対応する最も有効な手段が、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の策定です。これは、電子データの改ざんを防ぐための社内ルールを文書化したもので、これを備え付けて遵守することで、真実性の確保要件を満たすことができます。
国税庁のウェブサイトでは、この事務処理規程のサンプル(ひな形)が公開されており、誰でもダウンロードできます。このサンプルを基に、自社の実態に合わせて内容を修正するだけで、規程を作成することが可能です。
規程に盛り込むべき主要な項目は以下の通りです。
- 規程の目的を「電子帳簿保存法を遵守するため」と明記する
- 対象となる電子データや部署といった適用範囲を定める
- データの管理責任者と処理責任者を指名する
- ファイル名の付け方や保存先フォルダなどの具体的な運用方法を記載する
- 原則として訂正・削除を禁止し、やむを得ず行う場合の手順(申請、承認、理由の記録など)を厳格に定める
この規程を作成し、社内に周知徹底することで、高価なシステムを導入することなく、法令を遵守した体制を構築できます。
(任意)ペーパーレス化を加速する「スキャナ保存」の要件
電子取引データの保存義務化とは別に、取引先から受け取った紙の請求書や領収書も電子化してペーパーレスを進めたい事業者向けに「スキャナ保存」制度があります。これは任意の対応であり、従来通り紙のまま保存し続けても問題ありません。
スキャナ保存を行う場合は、一定の要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
- 解像度は200dpi以上でスキャンする
- 原則としてカラー画像で読み取る(契約書や領収書などの「重要書類」の場合。見積書などの「一般書類」はグレースケールも可)
- 書類を受領後、最長2ヶ月とおおむね7営業日以内にタイムスタンプを付与するか、訂正削除履歴が残るシステムに保存する
- 14インチ以上のディスプレイやプリンタなどを備え付ける
近年、要件は大幅に緩和されており、例えばスキャン作業者の情報を記録する必要がなくなるなど、導入のハードルは下がっています。ペーパーレス化による業務効率の向上を目指す企業は、導入を検討する価値があるでしょう。
罰則回避だけじゃない!「優良な電子帳簿」で得する未来

電子帳簿保存法への対応は、罰則を回避するためだけの守りの一手ではありません。より高い水準で対応することで、税制上のメリットや経営上の大きな利益を得ることができます。
税務メリット:過少申告加算税が5%軽減される
電子帳簿保存法では、通常の電子帳簿よりも厳格な要件を満たした帳簿を「優良な電子帳簿」として認めています。この優良な電子帳簿を作成・保存している事業者は、税務上の特典として、過少申告加算税が5%軽減される措置を受けられます。
過少申告加算税は、税務調査で申告漏れを指摘された際に、追加で納める税額に対して通常10%から15%が課される附帯税です。優良な電子帳簿の適用を受けていれば、この税率が5%分軽減されます。ただし、仮装・隠蔽といった意図的な不正があった場合には、この軽減措置は適用されません。
優良な電子帳簿として認められるためには、通常の要件に加えて、以下のような高度な機能が必要です。
- 訂正・削除の履歴がすべて記録として残ること
- 帳簿間で取引情報が相互に関連付けられており、確認できること
- 日付、金額、勘定科目などで高度な検索ができること
これは、日頃から透明性の高いデータ管理を行っている企業に対するインセンティブと言えます。万が一、意図しないミスで申告漏れがあったとしても、そのペナルティが軽減される可能性があるのは、企業にとって一種の「税務上の保険」のようなものであり、大きな安心材料となります。
経営メリット:業務効率化によるコスト削減と生産性向上
電子帳簿保存法への適切な対応は、バックオフィス業務のDX(デジタル・トランスフォーメーション)そのものです。これにより、罰則回避という目的を超えた、多くの経営メリットが生まれます。
コスト削減
紙の帳簿や伝票を印刷・保管する必要がなくなり、紙代、インク代、ファイル代、そして何より保管スペース(倉庫の賃料など)にかかるコストを大幅に削減できます。ある企業では、ペーパーレス化により年間30万枚以上の紙を削減したという事例もあります。
業務効率の大幅な向上
書類を探す時間が劇的に短縮されます。紙の書類であればキャビネットを探し回る必要がありましたが、電子データならキーワード検索で数秒で見つけ出せます。また、請求書の承認プロセスなどをシステム化すれば、紙を回覧する手間がなくなり、月次決算の早期化にもつながります。
多様な働き方への対応
帳簿や書類が電子化されていれば、経理担当者も場所を選ばずに業務を行えるようになります。これにより、テレワークの導入が促進され、優秀な人材の確保や従業員の満足度向上に貢献します。
このように、電子帳簿保存法への対応は、単なる義務ではなく、企業の生産性を高め、競争力を強化するための戦略的な投資と捉えることができます。
まとめ
電子帳簿保存法への対応は、もはや他人事ではありません。しかし、その罰則を正しく理解すれば、過度に恐れる必要はないこともお分かりいただけたはずです。最後に、本記事の要点を再確認しましょう。
- 主な罰則は「青色申告の承認取消」「最大45%の重加算税」「会社法上の過料」の3つです。
- 重加算税は意図的な不正行為が対象であり、誠実な事業運営が最大の防御策となります。
- 2024年1月以降、請求書などの電子取引データを紙のみで保存する行為は明確な法律違反です。
- 法令遵守には「真実性の確保」と「可視性の確保」が必要ですが、中小企業はコストをかけずに「事務処理規程」を策定することで対応が可能です。
- 新しい「猶予措置」は完全な免除ではなく、元の電子データの保存は必須です。
- 義務を果たすだけでなく、「優良な電子帳簿」を目指すことで、過少申告加算税の軽減や業務効率化といったメリットを享受できます。
税務調査の通知が来てから慌てるのでは遅すぎます。この記事を参考に、今すぐ自社の業務プロセスを見直してください。今日行うルール作りのための小さな一歩が、未来の大きな安心と事業の成長につながるのです。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…