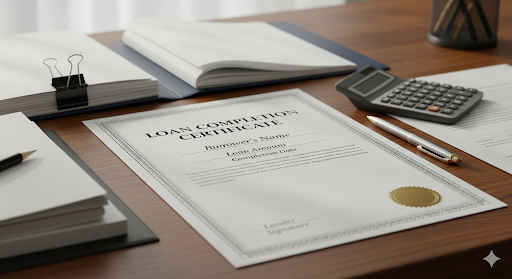
長きにわたる借金の返済、誠にお疲れ様でした。最後の一円を支払い終えた今、大きな安堵感と達成感に包まれていることと存じます。しかし、その安堵感だけで終わらせてしまうのは、少し早いかもしれません。
手に入れたはずの「借金のない未来」を確実なものにするためには、もう一つ、非常に重要な手続きが残されています。
この記事をお読みの方は、ただ漠然とテンプレートを探しているわけではないはずです。
返済という大きな責任を果たしたからこそ、「これで本当にすべて終わりなのか」「後から間違いで請求が来たらどうしよう」といった、漠然とした不安を解消し、完璧な形で締めくくりたいと考えているのではないでしょうか。
その賢明な判断は、ご自身の未来を予期せぬトラブルから守るための第一歩です。
ご安心ください。この記事では、単に書類の雛形を提供するだけではありません。完済証明書の法的な意味から、住宅ローン完済後に絶対に避けては通れない「抵当権抹消」という最重要手続き、さらには個人間のお金の貸し借りにおける注意点まで、網羅的に解説します。
この記事を最後までお読みいただければ、自信を持って借金に関するすべての手続きを完了させ、本当の意味での経済的な自由と心の平穏を手に入れることができるでしょう。
目次
そもそも完済証明書とは?なぜ絶対に必要なのか
完済証明書は、借金の返済が完了したことを証明する、いわば返済における「完了報告書」のようなものです。しかし、その役割は記念品にとどまりません。法的な効力を持ち、ご自身の財産と信用を守るための強力な盾となります。
完済証明書の定義と法的効力
完済証明書とは、「債権者(お金を貸した側)が債務者(お金を借りた側)に対して、特定の債務が全額返済されたことを証明するために発行する公式な文書」のことです。この一枚があることで、法的に「その借金を返済する義務はもうない」という事実を明確に証明できます。
もし将来、金融機関の事務的なミスや合併後の混乱、あるいは悪意ある二重請求などによって「まだ返済が残っている」と主張されたとしても、この証明書を提示すれば、それ以上の支払義務がないことを即座に立証できます。つまり、完済証明書は、万が一の法的な紛争からご自身を守るための決定的な証拠となるのです。
あなたの未来の信用を守る「お守り」
完済証明書の重要性は、過去の債務を清算する「守り」の側面に限りません。ご自身の未来の可能性を広げるための道具にもなり得ます。
例えば、将来新たに住宅ローンを組んだり、事業資金の融資を申し込んだりする場面を想像してみてください。金融機関は返済能力を審査しますが、その際に過去の大きな借入をきちんと完済した実績は、非常にポジティブな評価につながります。完済証明書は、「約束通りに責任を全うする信用できる人物である」ことを客観的に示す強力な証明となります。
この証明は、単なる信用情報機関の記録以上に、具体的な行動実績を示すものです。特に大きなローンを完済した証明は、経済的な信頼性を大きく高め、将来の金融取引を有利に進めるための「お守り」のような役割を果たしてくれます。この書類を手に入れることは、過去を清算する作業であると同時に、未来のご自身のための賢い投資と言えるでしょう。
状況別の完済証明書・債務弁済契約書テンプレートと書き方
完済証明書と一言でいっても、その形式は状況によって異なります。ここでは、一般的なケースから個人間の貸し借り、少し複雑な事業性の融資まで、それぞれの場面で使えるテンプレートと作成時のポイントを解説します。
基本的な完済証明書のテンプレート
金融機関からのローンや一般的な借入を完済した際に使用する、最も基本的な形式です。シンプルで分かりやすい構成が特徴です。
完済証明書
令和〇年〇月〇日
(債務者)
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇‐〇
氏名:〇〇 〇〇 様
(債権者)
住所:東京都〇〇区〇〇町〇‐〇‐〇
名称:株式会社〇〇
代表取締役:〇〇 〇〇 [印]
下記の契約に基づく貴殿の弊社に対する債務が、すべて弁済されたことを証明いたします。
記
- 原契約締結日
平成〇年〇月〇日 - 契約の種類
金銭消費貸借契約 - 借入元本額
金〇〇〇円 - 契約番号(あれば)
〇〇〇〇〇〇
以上
(このテンプレートはあくまで一例です。実際の状況に合わせて修正してください。)
個人間の貸し借りで使えるテンプレートと注意点
友人や親族など、個人間でお金の貸し借りをした場合は、金融機関との取引とは異なる特別な注意が必要です。なぜなら、取引の証拠となる「借用書」の扱いがトラブルの火種になりやすいからです。
個人間の借金を完済した際に最も重要なのは、元の借用書をどう処理するかです。完済の証明を得るだけでなく、元の契約書が無効になったことを明確にしなければ、後々「まだ返してもらっていない」と言われるリスクが残ります。以下の優先順位で対応しましょう。
- 最善策:元の借用書を返してもらう
これが最も確実で安全な方法です。借金の証拠そのものが手元に戻るため、将来の請求リスクを完全に断ち切ることができます。 - 次善策:借用書に「返済済み」と記載してもらう
相手が借用書を紛失した、あるいは返却を渋るなどの場合は、その借用書の余白に「全額返済済みであることを確認します」といった文言と、完済日、相手の署名・捺印をもらいましょう。 - 代替案:別途「完済証明書」を発行してもらう
上記2つの方法が難しい場合の最終手段です。基本的なテンプレートを参考に、誰が誰に対して、いつ、いくらの借金を完済したのかを明記した書類を作成し、相手の署名・捺印をもらいます。
また、いずれの場合でも、最終返済時の「領収書」も必ず受け取るようにしてください。
返済完了証明書(個人間取引向け)
令和〇年〇月〇日
(借主)
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇‐〇
氏名:〇〇 〇〇 様
(貸主)
住所:東京都〇〇区〇〇町〇‐〇‐〇
氏名:〇〇 〇〇 [印]
貴殿が私に対して負担していた、下記借入金債務が、本日をもって全額返済されたことを証明いたします。これに伴い、平成〇年〇月〇日付の金銭消費貸借契約書(借用書)は、その効力を失ったことを確認します。
記
- 貸付日
平成〇年〇月〇日 - 貸付元本額
金〇〇〇円
以上
事業性融資や慰謝料の支払いで使える債務承認弁済契約書の雛形
すでに返済が滞っている売掛金や、口約束で始まった貸し借り、あるいは慰謝料の支払いなど、債務の存在や金額、返済方法を改めて正式に合意し直す際に使われるのが「債務承認弁済契約書」です。これは完済を証明するものではなく、「債務を承認し、このように返済していきます」と約束する契約書です。
この契約書には、トラブル防止のために詳細な取り決めを記載する必要があります。
- 債務の確認
債務の種類(貸金、売掛金、慰謝料など)と、現時点で残っている正確な金額を明記し、債務者がその支払義務を認めることを記載します。 - 弁済方法
一括払いか分割払いか、分割の場合は毎月の支払額と支払日、振込先口座、振込手数料の負担者などを具体的に定めます。 - 利息・遅延損害金
利息や、支払いが遅れた場合の遅延損害金の利率を定めます。 - 期限の利益の喪失
分割払いの支払いを怠った場合に、残額の一括請求を可能にするための重要な条項です。
これらの契約書は内容が複雑になるため、作成にあたっては弁護士や司法書士などの専門家へ相談することも検討することをお勧めします。
住宅ローン完済後に必須となる抵当権抹消手続き
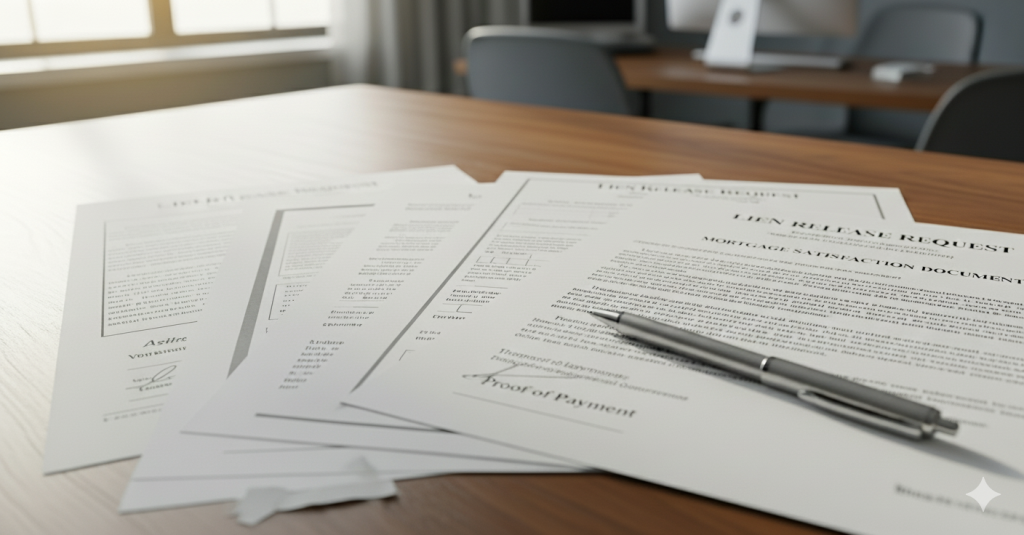
住宅ローンを完済した方が「完済証明書」というキーワードで検索した場合、実は本当に知るべき、そして行動すべきなのは、別の手続きに他なりません。それが「抵当権抹失」です。この手続きは単なる証明書の受け取りとは全く異なり、ご自身の不動産の権利を完全なものにするための、義務にも等しい極めて重要な法的プロセスです。
抵当権とは?なぜ抹消しないと危険なのか
抵当権とは、住宅ローンを組む際に、金融機関が土地や建物を担保として確保する権利のことです。この権利は法務局で「登記」という形で公式に記録されており、万が一ローンを返済できなくなった場合、金融機関はこの権利を行使して不動産を差し押さえ、競売にかけることができます。
ここで最も注意すべき点は、ローンを全額返済しても、この登記記録は自動的には消えないという事実です。ご自身で法務局に申請して、この記録を抹消する手続きを行わない限り、登記簿上は永遠に金融機関の権利が残ったままになってしまいます。
この抵当権を放置すると、将来的に深刻な問題を引き起こします。
- 不動産を売却できない
登記簿に抵当権が残っている物件を買おうとする人はいません。売却を決めた際に、慌てて手続きをすることになります。 - 新たな融資の担保にできない
その不動産を担保に新たなローンを組もうとしても、先の抵当権が残っているため、審査で不利になります。 - 相続時に家族に多大な迷惑をかける
万が一の場合、相続人であるご家族がこの複雑な手続きを引き継がなければなりません。書類を紛失していたり、金融機関が合併していたりすると、手続きはさらに困難になり、余計な費用と手間をご家族に負わせることになります。
抵当権抹消手続きの具体的な4ステップ
抵当権抹消は司法書士に依頼することもできますが、手順を理解すればご自身で行うことも十分に可能です。時間と費用を節約したい方は、挑戦を検討してみてはいかがでしょうか。
ステップ1:金融機関から書類を受け取る
ローンを完済すると、1週間から2週間ほどで金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式が簡易書留などで送られてきます。中身は絶対に紛失しないようにしてください。主な書類は以下の通りです。
- 登記識別情報(または登記済証)
- 抵当権解除証書(または弁済証書)
- 委任状
- 代表者事項証明書(または会社の登記事項証明書)
特に、金融機関の代表者事項証明書は発行から3ヶ月以内という有効期限がある場合が多いため、受け取ったら速やかに手続きを進めましょう。
ステップ2:登記申請書を作成する
法務局のウェブサイトから「抵当権抹消登記申請書」の様式をダウンロードし、金融機関から送られてきた書類と、ご自身の不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を見ながら必要事項を記入します。記入方法で不明な点があれば、法務局の相談窓口で指導を受けることも可能です。
ステップ3:法務局へ申請する
作成した登記申請書と、金融機関から受け取った書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。申請時には「登録免許税」という税金を納める必要があり、これは不動産1つにつき1,000円です(土地と建物なら合計2,000円)。収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて納付します。申請は窓口持参のほか、郵送やオンラインでも可能です。
ステップ4:登記完了書類を受け取る
申請後、1週間から2週間ほどで手続きが完了します。法務局で「登記完了証」と、返却された書類を受け取ります。念のため、手続き完了後に新しい登記簿謄本を取得し、抵当権の記載がきちんと消えていることをご自身の目で確認すれば、すべて完了です。
抵当権抹消にかかる費用は?司法書士への依頼相場
抵当権抹消にかかる費用は、ご自身で行うか、専門家である司法書士に依頼するかで大きく変わります。どちらを選ぶかの判断材料として、費用の内訳を把握しておきましょう。
| 項目 | ご自身で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合 | 備考 |
| 登録免許税 | 2,000円 | 2,000円 | 不動産1筆あたり1,000円(土地・建物の場合) |
| 事前・事後調査費 | 約1,000円 | 約1,000円 | 登記簿謄本の取得費用など |
| 司法書士報酬 | 0円 | 15,000円~20,000円 | 地域や事務所により変動 |
| 合計目安 | 約3,000円 | 約18,000円~23,000円 | 交通費・郵送費は別途 |
コストは重要な判断基準です。ご自身で手続きを行えば費用を大幅に節約できますが、書類作成や法務局とのやり取りに時間と手間がかかります。一方、司法書士に依頼すれば、数万円の報酬はかかりますが、複雑な手続きをすべて正確かつ迅速に代行してもらえます。ご自身の時間的余裕や手続きへの不安などを考慮して、最適な方法を選択してください。
完済証明書に関する法務・税務知識

完済証明書に関連して、収入印紙のルールや書類の保管期間など、知っておくべき法的な知識がいくつかあります。これらの知識を理解しておくことで、余計な税金を払ったり、将来のトラブルに巻き込まれたりするリスクを減らすことができます。
収入印紙の要否と印紙税のルール
「収入印紙」とは、特定の契約書や領収書などを作成した際に課される「印紙税」という税金を納めるための証票です。完済証明書や領収書も、記載された金額によってはこの印紙税の対象となります。
ルールは比較的シンプルです。印紙税法上、借金の返済に対する受取書は「第17号文書」に分類され、以下の基準で納税義務が決まります。
- 受取金額が5万円未満の場合
非課税です。収入印紙は必要ありません。 - 受取金額が5万円以上の場合
課税対象です。借入金の返済のような「売上代金以外の受取書」の場合、税額は金額にかかわらず一律200円です。
ただし、重要な例外がいくつかあります。個人が事業としてではなく友人などにお金を貸した場合、その返済に対する受取書は「営業に関しないもの」として扱われ、非課税となります。また、PDFファイルなどで発行された電子的な完済証明書や領収書は、印紙税法上の「課税文書」に該当しないため、金額にかかわらず収入印紙は不要です。これは現代において非常に大きなメリットと言えるでしょう。
完済証明書が発行されない場合の対処法
万が一、貸主が完済証明書の発行に協力してくれない場合でも、慌てる必要はありません。返済した事実を証明する方法は他にもあります。
まず、銀行振込で返済していた場合、通帳の記帳や振込明細書が最も強力な客観的証拠となります。手渡しの場合でも、返済のやり取りをしたメールやSNSのメッセージなども、貸し借りの存在や返済の事実を推認させる証拠として有効です。
相手に正式に発行を促すため、「内容証明郵便」を送付する方法もあります。この郵便は法的な強制力こそありませんが、「いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、相手に心理的なプレッシャーを与え、請求の証拠を残すことができます。
それでも解決しない場合の最終手段として、「債務不存在確認訴訟」という裁判を起こす方法があります。この訴訟では、「債務がまだ存在すること」を証明する責任は相手方(貸主)にあるため、こちらに決定的な証拠がなくても有利に進められる可能性があります。
書類の保管期間と消滅時効の関係
完済証明書や関連書類をいつまで保管すればよいのか、という疑問は、法律上の「消滅時効」という考え方と密接に関係しています。
消滅時効とは、債権者(貸主)が権利(返済を請求する権利)を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅するという制度です。この期間を過ぎると、たとえ借金が残っていても、債務者(借主)は「時効なので支払いません」と主張(時効の援用)できるようになります。
この時効期間は、貸金業者からの借入や、2020年4月1日以降の個人間の貸し借りの場合、原則として最後の返済日などから5年です。ただし、2020年3月31日以前の個人間の貸し借りについては、10年となる場合があります。ここから導き出される結論は、「完済を証明する書類は、少なくとも10年間は保管しておくべき」ということです。
5年や10年という長い時間が経ってから、記憶違いや勘違いで請求される可能性もゼロではありません。その際に「確かに完済しました」と証明できる唯一のものが、これらの書類なのです。時効という法的なリスク管理の観点からも、書類の長期保管は極めて重要です。
まとめ
借金の完済は、返済そのものだけでなく、その事実を法的に証明する手続きを完了させて初めて、本当の意味で終わりを迎えます。この記事で解説したポイントを再確認し、ご自身の権利と未来を確実に守りましょう。
- ポイント1:証拠を残す
借金を完済したら、必ず「完済証明書」や「領収書」などの書面で証拠を残してください。これがすべての基本です。 - ポイント2:抵当権抹消は必須
住宅ローンの場合は、金融機関から書類を受け取ったら、何よりも優先して速やかに「抵当権抹消」の手続きを行ってください。これは選択ではなく、必須の作業です。 - ポイント3:個人間では借用書の処理が鍵
個人間の貸し借りでは、元の「借用書」を返してもらうか、最低でも返済済みと追記・署名してもらうことが、後のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。 - ポイント4:収入印紙のルールを知る
5万円以上の返済証明書には200円の収入印紙が必要な場合があります。ただし、電子データでの発行であれば不要です。 - ポイント5:書類は10年間保管する
すべての証明書類は、借金の消滅時効(最長10年)を考慮し、大切に長期間保管してください。これが未来のご自身を守る最後の砦となります。
これらの手続きを一つひとつ着実に完了させることで、借金という過去のしがらみから完全に解放され、何の不安もない新しい未来へと踏み出すことができるのです。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…