
クリーニング代の勘定科目に迷い、どの科目を使えば税務上問題ないのか、正しく経費計上できているのか不安に感じていませんか。適切な勘定科目を選ぶことは、正確な帳簿作成を可能にするだけでなく、事業の状況を正しく把握し、適切な節税につなげるための第一歩です。
クリーニング代の経費計上は、その目的や対象によって使用する勘定科目が多岐にわたるため、経理担当者が判断に迷いやすい費用のひとつです。選択を誤ると、税務調査で指摘を受け、追徴課税が発生するリスクも考えられます。
本記事を最後までお読みいただくことで、法人・個人事業主を問わず、従業員の制服からオフィスの清掃、お客様用のリネン類まで、あらゆるクリーニング代に対して自信を持って最適な勘定科目を選べるようになります。
「福利厚生費」「衛生費」「外注費」など、選択肢が多くて混乱しがちですが、勘定科目の選択は、クリーニングの「目的」と「対象」という、いくつかのシンプルな原則に基づいています。本記事では、その原則を一つひとつ丁寧に解き明かし、あなたの経理業務の不安を解消します。
目次
勘定科目の基礎知識と選択の重要性
経理の基本となる「勘定科目」について、まずはおさらいしましょう。勘定科目とは、簡潔に言うと、会社のお金の出入りを事業活動の内容に応じて分類するための「見出し」や「ラベル」のようなものです。例えば、文房具を購入すれば「消耗品費」、電車で移動すれば「旅費交通費」といったラベルを付け、何にお金を使ったのかを明確に記録します。
この勘定科目を使った日々の記録(仕訳)は、最終的に「損益計算書」や「貸借対照表」といった決算書を作成するために不可欠です。これらの財務諸表は、税務署への法人税や所得税の申告、金融機関からの融資審査、株主への業績報告など、社内外のさまざまな場面で利用されるため、その正確性が厳しく求められます。
勘定科目の選択は、単なる事務作業ではありません。それは、税務署や金融機関といった外部の関係者に対して、会社がどのように事業を運営し、お金を使っているかを伝える事業の状況を伝える重要な情報そのものなのです。例えば、従業員の制服クリーニング代を「福利厚生費」で処理することは、従業員の労働環境に配慮し、投資している姿勢を示すことにつながります。
一方で、内容が異なる多くの経費を安易に「雑費」で処理していると、経費管理がずさんであるという印象を与えかねません。特に雑費の金額が多額になると、税務調査においてその内訳や事業関連性について詳細な説明を求められる可能性が高まります。
正しい勘定科目の選択は、会社の会計処理の透明性を高め、社会的な信頼性を維持する上でも極めて重要なのです。
クリーニング代で使用する5つの主要な勘定科目
クリーニング代を経費として計上する際に使われる主な勘定科目は、その目的や状況に応じて以下の5つに分類されます。それぞれの科目が持つ意味合いの違いを理解することが、適切な仕訳を行うための近道です。
- 福利厚生費
- 従業員のために支払う費用です。
- 衛生費
- お客様や職場の衛生環境を維持するために支払う費用です。
- 外注費
- 外部の業者に定期的な清掃などを委託する際に支払う費用です。
- 修繕費
- 資産を元の状態に戻す(原状回復)ために支払う費用です。
- 雑費
- 他のどの科目にも当てはまらず、発生頻度が低く少額な費用です。
これらの使い分けを一覧表にまとめました。まずはこの表で、ご自身のケースがどの勘定科目に該当しそうか、大まかな見当をつけてみましょう。
クリーニング代に関する勘定科目の比較一覧
| 勘定科目 | 主な用途 | 重要な判断基準 |
| 福利厚生費 | 従業員の制服・作業着のクリーニング | 誰のためか:従業員 |
| 衛生費 | お客様用のタオル・おしぼり・リネン類のクリーニング | 誰のためか:お客様 |
| 外注費 | 業者によるオフィスの定期清掃、レンタルマット交換 | 取引の性質:定期的・契約に基づく外部委託 |
| 修繕費 | 賃貸物件の退去時における原状回復クリーニング | 取引の性質:資産価値の維持・回復 |
| 雑費 | 突発的に発生した、少額なシミ抜きなど | 取引の性質:臨時的・少額 |
状況別に見る勘定科目の選び方と具体的な仕訳例
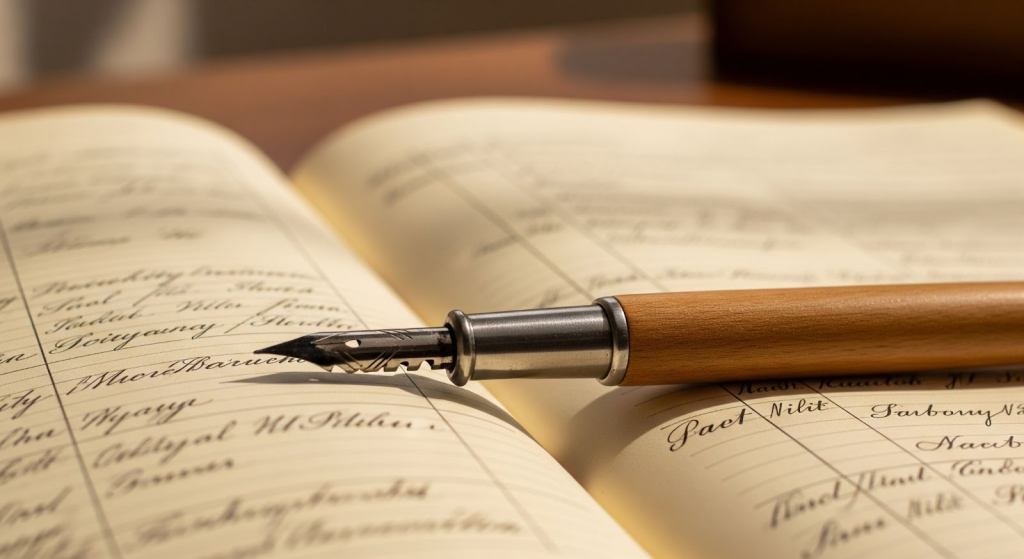
それでは、5つの勘定科目それぞれについて、どのような状況で使うのが適切なのか、具体的な仕訳例を交えながら詳しく解説していきます。
福利厚生費:従業員の労働環境向上のために
「福利厚生費」は、給与や賞与以外で、従業員の労働環境の改善や満足度向上のために会社が公平に負担する費用を処理するための勘定科目です。クリーニング代においては、会社が業務上の必要性から支給した制服や作業着のクリーニング費用を会社が負担する場合に、この科目を使用します。
ただし、クリーニング代を「福利厚生費」として経費計上するには、税務上、以下の重要な条件を満たす必要があります。
- 業務上、その制服や作業着の着用が必要不可欠であること
- 役員を含めた全従業員を対象とした制度であること
- 社会通念上、妥当な金額の範囲内であること
特に注意が必要なのは、「全従業員が対象」という公平性の要件です。特定の役員や一部の従業員だけが着用するスーツのクリーニング代を会社が負担した場合、それは福利厚生とは見なされません。
税務上は、その個人への経済的利益の供与と判断され、給与として扱われる可能性が非常に高くなります。給与と認定されると、会社側では源泉徴収義務が発生し、受け取った個人側では所得税の課税対象となります。
したがって、この勘定科目を使う際は、特定の個人を利するものではないことを明確にするため、社内にクリーニング代の補助に関する公平なルールを「福利厚生規程」などとして明文化し、その規程に基づいて運用することが不可欠です。
仕訳例
従業員全員の作業服のクリーニング代10,000円を現金で支払った。
| 借方 | 貸方 |
| 福利厚生費 10,000円 | 現金 10,000円 |
衛生費:顧客や職場の衛生環境維持のために
「衛生費」は、職場の衛生状態を清潔に保つためや、お客様へのサービス品質を維持するためにかかる費用を処理する勘定科目です。企業によっては「衛生管理費」という名称を使用することもあります。
この科目が使われるのは、主にお客様と直接関わるサービス業や医療機関などです。具体的には、以下のような物品のクリーニング代が該当します。
- 飲食店で提供するおしぼりやテーブルクロス
- 美容院やエステサロン、温浴施設で使用するタオル
- ホテルや旅館で使用するシーツ、枕カバーなどのリネン類
- クリニックや病院で使用する白衣やシーツ
「福利厚生費」との最も大きな違いは、その費用が「誰のために使われたか」という点です。支出の目的が従業員のためであれば「福利厚生費」、お客様やサービスの受け手のためであれば「衛生費」と区別すると分かりやすいでしょう。
特にサービス業においては、清潔なタオルやリネン類はサービスの質を左右し、顧客満足度に直結する重要な要素です。これらの費用を単なる「雑費」として処理するのではなく、「衛生費」として独立させて管理することで、サービス提供に直接かかるコストを正確に把握できます。
その結果、より適切な価格設定や事業部門ごとの収益性分析に役立てることが可能になります。
仕訳例
美容室でお客様用のタオルのクリーニング代20,000円が普通預金から引き落とされた。
| 借方 | 貸方 |
| 衛生費 20,000円 | 普通預金 20,000円 |
外注費:外部業者への業務委託
「外注費」は、自社の業務の一部を外部の業者や個人事業主に委託した際に支払う費用を処理する勘定科目です。クリーニングにおいては、特定の専門業者と業務委託契約などを結び、定期的に清掃サービスなどを受けている場合に使用します。
具体的な例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 清掃業者によるオフィスの定期的な床清掃や窓拭きサービス
- レンタル業者による玄関マットやモップの定期交換およびクリーニング
- 大量の作業服を特定のクリーニング業者にまとめて委託している場合
また、不動産賃貸業を営んでいる場合、アパートの入居者退去に伴う部屋のクリーニングを業者に依頼する費用も、継続的な取引関係があれば「外注費」として処理することがあります。この科目のポイントは「定期的・契約ベース」であるという点です。一度きりの突発的な依頼ではなく、継続的なサービス提供に対して支払う場合に用いるのが一般的です。
外部の専門業者に委託する際は、後のトラブルを避けるためにも、作業範囲や頻度、料金などを明記した業務委託契約書を交わしておくことが望ましいでしょう。
仕訳例
清掃業者に依頼している月次のオフィス清掃費用50,000円を普通預金から振り込んだ。
| 借方 | 貸方 |
| 外注費 50,000円 | 普通預金 50,000円 |
修繕費:資産の原状回復を目的とする場合
「修繕費」は、建物や備品といった固定資産を維持管理したり、故障や破損した箇所を元の状態に戻したりするためにかかった費用を処理する勘定科目です。クリーニングの文脈では、特に「原状回復」を目的としたハウスクリーニング費用などを計上する際に使われます。
最も典型的な例は、不動産賃貸業において、入居者が退去した後の部屋を次の入居者のために清掃するケースです。この場合のクリーニングは、単なる日常的な清掃というよりも、物件という資産の価値を維持し、再び貸し出せる状態に「修復」する行為の一環と見なされるため、「修繕費」が適しています。
「外注費」と「修繕費」の使い分けに迷うことがあるかもしれません。その際の判断の基準は、そのクリーニングが「何によって発生したか」を考えることです。
時間の経過や契約に基づいて定期的に行う清掃は、日常的な維持管理と見なされ「外注費」となります。
一方、入退去や工事など、特定のイベントをきっかけに資産を元の状態に戻すために行う清掃は、資産の修復と見なされ「修繕費」が適切です。
費用の発生原因に着目することで、より実態に即した勘定科目を選択できます。ただし、原状回復の範囲を超えて、物件の価値を向上させるようなリフォーム(例えば、壁紙をより高価なものに変更するなど)を行った場合、その費用は「資本的支出」と見なされ、資産計上が必要になるため注意が必要です。
仕訳例
賃貸アパートの退去に伴う原状回復のためのハウスクリーニング代70,000円を現金で支払った。
| 借方 | 貸方 |
| 修繕費 70,000円 | 現金 70,000円 |
雑費:他の科目に該当しない臨時的・少額な費用
「雑費」は、他のどの勘定科目にも当てはまらず、事業活動の中で発生頻度が低く、金額的にも重要性が低い費用を処理するための勘定科目です。いわば、経費の「その他」のカテゴリーです。
クリーニング代を「雑費」で処理するのは、以下のような限定的なケースに限られます。
- 従業員が作業中に誤って制服を汚してしまい、緊急でシミ抜きに出した場合
- 来客時にカーペットを汚され、部分的なクリーニングをスポットで依頼した場合
このように、定期的・継続的ではなく、予期せず突発的に発生した少額のクリーニング費用が該当します。
ただし、「雑費」は便利な科目である一方、その使用には注意が必要です。雑費の金額が年間を通じて大きくなると、会社の経費構造が不明瞭になり、税務調査の際に「具体的に何に使ったのか」を詳しく説明するよう求められることがあります。
金融機関からの融資審査においても、雑費が多い決算書は経費管理が徹底されていないという印象を与え、評価が下がる要因にもなり得ます。
もし、特定のクリーニング代が頻繁に発生するようになった場合は、それはもはや「雑費」ではなく、事業にとって管理すべき重要な費用と考えるべきです。その際は、翌期から「福利厚生費」や「衛生費」など、より適切な勘定科目に切り替えるか、次に説明する「クリーニング費」を新設することを検討しましょう。
仕訳例
来客がこぼしたコーヒーのシミを落とすため、カーペットクリーニング代3,000円を現金で支払った。
| 借方 | 貸方 |
| 雑費 3,000円 | 現金 3,000円 |
勘定科目「クリーニング費」を新設する選択肢
勘定科目は法律で厳密に定められているわけではなく、企業が自社の経営実態を管理しやすいように、ある程度自由に設定することが認められています。
もし、クリーニング代の発生頻度が非常に高く、金額も大きくなるため、その動向を単独で把握・管理したいと考える場合には、新たに「クリーニング費」という勘定科目を設けることも有効な選択肢です。
例えば、大規模なホテルやクリーニングを伴う製造工場、多数のスタッフを抱える飲食店チェーンなどでは、クリーニング費用が経営の重要なコスト指標となることがあります。
このような場合に「クリーニング費」として費用を独立させることで、予算管理や前年同月比でのコスト比較が容易になります。これにより、コスト削減の意識が高まり、より精緻な経営判断に役立てることができます。
会計ソフトを利用している場合は、勘定科目の設定画面から新しい科目を追加作成することで対応できます。重要なのは、一度設定したルールは継続して適用することです。
個人事業主がクリーニング代を経費計上する際の重要ポイント

個人事業主の場合、事業とプライベートの境界が曖-昧になりがちなため、クリーニング代を経費にする際には法人よりも慎重な判断が求められます。最も重要な原則は、「その費用が事業の売上を上げるために、直接的かつ必要不可欠であったことを客観的に証明できるか」という点です。
個人事業主がクリーニング代に使う勘定科目は、主に「外注費」「雑費」、または新設した「クリーニング費」です。自分自身や家族従業員に対する「福利厚生費」という概念は原則として適用されないため、この科目の使用は避けるべきです。
事業用と私用の境界線:スーツ代は経費にできるか
個人事業主にとって最も判断に迷うのが、スーツのクリーニング代でしょう。原則として、仕事でもプライベートでも着用する可能性があるスーツのクリーニング代は、経費として認められません。税務上、それは事業専用の支出(経費)ではなく、家事上の支出(プライベート費用)と見なされるためです。
しかし、以下のようなケースでは経費として認められる可能性があります。
- 事業でのみ使用することが明確な場合
例えば、特定の講演会やセミナーでのみ着用する衣装のようなスーツで、私用では一切着ないことを客観的に説明できる場合。 - 長期出張中のクリーニング
出張先でやむを得ずクリーニングに出した場合など、その支出が出張という業務遂行上、付随して発生したことが明らかな場合。
重要なのは、「スーツだから経費にできない」と一律に考えるのではなく、「このスーツが100%事業用であることをどう証明するか」という視点を持つことです。経費として計上する場合は、なぜ事業に必要だったのかを具体的に説明できるよう、着用した会議の日時や相手先、目的などを手帳や業務日報に記録しておくといった工夫が求められます。
自宅兼事務所の費用と家事按分の考え方
自宅の一部を事務所として使用している個人事業主が、ハウスクリーニングやエアコンクリーニングなどの費用を支払った場合、その全額を経費にすることはできません。事業で使用している部分とプライベートで使用している部分を、合理的な基準で分ける「家事按分(かじあんぶん)」という計算が必要です。
面積基準による按分方法
家事按分には、主に面積で按分する方法があります。自宅全体の面積のうち、事業用スペースが占める割合で費用を分ける方法で、これが最も一般的で客観的な基準とされています。
計算例:家全体の面積が60㎡で、事務所として使用しているスペースが15㎡の場合
- 事業割合:15㎡ ÷ 60㎡ = 25%
- ハウスクリーニング代が80,000円かかった場合、経費にできるのは 80,000円 × 25% = 20,000円 となります。
時間基準による按分方法
電気代などでは、1週間のうち、事業でそのスペースを使用している時間の割合で計算する方法が用いられることもあります。
どちらの方法を用いるにせよ、なぜその割合で計算したのか、その根拠を明確に説明できるようにしておくことが非常に重要です。事務所スペースを明確に区分した間取り図や、業務時間を記録した日報などを証拠資料として保管しておきましょう。
仕訳例
自宅兼事務所のハウスクリーニング代80,000円を支払った。事業割合は25%とする。
この場合、経費になる20,000円と、プライベート費用である60,000円を分けて仕訳します。プライベート分は「事業主貸」という勘定科目を使用します。
| 借方 | 貸方 |
| 外注費 20,000円 | 現金 80,000円 |
| 事業主貸 60,000円 |
税務調査で指摘されないための実務対応
適切な勘定科目を選択するだけでなく、その経費計上が正当であることを証明するための実務対応も重要です。
証拠書類(エビデンス)の適切な保存
全ての経費計上には、その取引が事実であることを証明する領収書や請求書といった証拠書類(エビデンス)の保存が義務付けられています。これらの書類は、法人であれば原則7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は10年間)、個人事業主は原則5年間(消費税課税事業者は7年間)の保存が必要です。
また、電子帳簿保存法の改正により、電子メールで受け取った請求書などの電子取引データは、紙に出力せず電子データのまま保存することが義務化されていますので注意が必要です。
コインランドリーなど領収書がない場合の対処法
コインランドリーなど、領収書が発行されないサービスを利用した場合でも、経費計上を諦める必要はありません。その場合は、自身で「出金伝票」を作成しましょう。
出金伝票に「日付」「支払先(〇〇コインランドリーなど)」「金額」「内容(作業着の洗濯代など)」を具体的に記録しておくことで、領収書の代わりとして税務上の証拠書類になります。その他、利用日時や金額がわかる写真やメモなども補完的な資料として有効です。
説明責任を果たすための準備
税務調査では、帳簿に記録された取引について、その内容や事業関連性を問われることがあります。
会計ソフトの摘要欄には「クリーニング代」とだけ記載するのではなく、「〇〇社 作業服クリーニング代」や「店舗用タオル クリーニング代」のように、具体的な内容を補足しておくと、後から見返した際に分かりやすく、第三者への説明も容易になります。なぜその勘定科目を選んだのかを含め、常に説明責任を果たせる状態にしておくことが、円滑な税務調査対応の鍵となります。
クリーニング代の経費計上に関する補足知識
最後に、クリーニング代の経費計上に関連して、よくある質問や補足的な知識について解説します。
消費税の取り扱いとインボイス制度への対応
クリーニングはサービスの提供にあたるため、その代金は消費税の課税対象(課税仕入れ)です。2023年10月から始まったインボイス制度により、消費税の「仕入税額控除」を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。
ただし、取引相手がインボイスを発行できない免税事業者(小規模なクリーニング店や個人など)であっても、急激な負担増を避けるための経過措置が設けられています。
- 2026年9月30日まで:免税事業者からの仕入れでも、消費税額の80%を控除可能
- 2029年9月30日まで:免税事業者からの仕入れでも、消費税額の50%を控除可能
この経過措置の適用を受けるためには、帳簿にその旨を記載する必要があります。インボイス制度の開始により、今後は料金だけでなく、取引相手がインボイス発行事業者かどうかも含めて取引を判断することが、税負担を管理する上で重要になります。
会計処理の継続性の原則
会計には「継続性の原則」という大切なルールがあります。これは、一度採用した会計処理の方法は、正当な理由がない限り、毎期継続して適用しなければならないという考え方です。
したがって、同じ内容のクリーニング代であるにもかかわらず、ある期は「外注費」、次の期は「衛生費」というように、安易に勘定科目を変更することは避けるべきです。勘定科目を頻繁に変更すると、期間ごとの業績比較が困難になり、経営状況の正しい分析を妨げるだけでなく、税務署から会計処理の信頼性が低いと判断される恐れもあります。
ただし、事業内容の変更や、より実態に合った会計処理への見直しなど、合理的な理由がある場合は勘定科目の変更も可能です。その際は、なぜ変更したのかを明確に説明できるようにしておくことが重要です。
まとめ
クリーニング代の勘定科目の選択は、一見複雑に見えますが、その本質はシンプルです。
- 誰のための費用か(従業員、お客様、事業所全体)
- どのような性質の費用か(定期的、突発的、資産の原状回復)
この2つの軸で考えることで、自ずと適切な勘定科目が見えてきます。
- 従業員の制服なら「福利厚生費」
- お客様用のタオルなら「衛生費」
- 業者の定期清掃なら「外注費」
- 退去時の原状回復なら「修繕費」
- 突発的で少額なら「雑費」
特に個人事業主の方は、事業用と私用の支出を明確に区別し、必要に応じて「家事按分」を合理的な根拠に基づいて行うことが、正しい経費計上の鍵となります。
また、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応も忘れてはなりません。日々の取引において、適切な証拠書類を確実に保存する習慣をつけ、賢く経費管理を行いましょう。本記事で得た知識を活用し、自信を持って日々の経理業務に取り組んでください。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…