
発注書なしの「口約束」で仕事を進めてしまい、後からトラブルになるケースは後を絶ちません。しかし、法律を正しく理解し、適切な手順を踏むことで、事業者は自らの権利を守り、正当な対価を確保できます。
仕事の対価を正当に、そして期日通りに受け取ることは、事業者として当然の願いです。しかし、「いつも通りだから」という言葉のもと、発注書がないまま口頭で仕事が始まり、後になって「言った、言わない」のトラブルに巻き込まれてしまう経験はないでしょうか。
このような状況を放置すれば、不当な減額や支払遅延に泣き寝入りする未来が待っているかもしれません。
この記事を最後まで読むことで、下請法における口頭発注がなぜ明確な法律違反なのかを完全に理解できます。さらに、すでに起きてしまったトラブルを解決するための具体的な手順と、無料で相談できる公的機関の存在を知ることができます。
これは一部の専門家だけが知る特別な知識ではありません。法律があなたに与えた正当な権利であり、その使い方を学ぶことで、取引における交渉力を手に入れることが可能です。
「クライアントとの関係を悪化させたくない」「法律は難しくてよくわからない」といった不安を感じる気持ちはよくわかります。
しかし、心配はいりません。この記事で紹介する方法は、感情的な対立を避け、法律という客観的なルールに基づいて冷静に対処するためのものです。誰にでも実践できる、再現性の高い手順を通じて、知識を武器に変え、理不尽な状況から抜け出しましょう。
目次
口頭発注の違法性:下請法が事業者保護の盾となる理由
まず、取引の基本について整理しましょう。一般的な契約は、民法上、当事者双方の合意があれば口頭でも成立します。この原則が、「口約束でも契約は契約だ」という考え方の根拠になっています。しかし、すべての取引がこの原則だけで動いているわけではありません。
特に、事業者間の力関係に差が生まれやすい下請取引においては、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)という特別な法律が適用される場合があります。下請法は、立場の弱い下請事業者が不当な不利益を被ることがないよう、優越的な立場にある親事業者の行動を規制するために作られた法律です。
これは、公正な取引を確保するための独占禁止法を補完する役割を持っています。
この法律が適用されるかどうかは、契約の形式ではなく、「取引の内容」と「両社の資本金」によって決まります。例えば、資本金3億円超の企業が資本金3億円以下の企業に製造を委託する場合などが典型例です。
そして、ここが最も重要な点です。あなたの取引が下請法に該当する場合、親事業者が書面を交付せずに口頭のみで発注することは、明確な法律違反となります。これは下請法第3条に定められた「書面の交付義務」に違反する行為であり、たとえ緊急の電話での発注であっても、その直後に書面を交付しなければなりません。
なぜ法律はこれほど厳格に書面を要求するのでしょうか。それは、口頭での発注が「言った、言わない」という水掛け論を生み出し、それが親事業者による不当な要求(代金の減額や仕様変更など)の温床になることを法律が理解しているからです。
書面の交付義務は、取引内容を明確に記録として残すことで、そうしたトラブルを未然に防ぎ、下請事業者を保護するための強力な盾なのです。契約書や発注書がないからといって、下請法が適用されないということには決してなりません。
親事業者の義務「3条書面」とは?記載必須の12項目を解説
下請法が親事業者に交付を義務付けている書面のことを、法律の条文番号にちなんで「3条書面(さんじょうしょめん)」と呼びます。この3条書面は、親事業者が発注をした際に「直ちに」、つまり間を置かずに交付されなければならないと定められています。
この「直ちに」という言葉は非常に重要です。たとえ電話で緊急の発注を受けたとしても、親事業者はすぐに3条書面を作成し、あなたに交付する義務があります。発注から書面の交付までに何日もかかるようでは、この義務を果たしたことにはなりません。
3条書面には、取引のトラブルを防ぐために、法律で定められた12の項目をすべて、明確に記載する必要があります。これらの項目は、取引における潜在的な争点を網羅するように設計されています。
scope(何を作るか)、deadline(いつまでに)、price(いくらで)、payment terms(いつ支払うか)といった、ビジネスの根幹をなす条件を、作業開始前に文書で確定させることを目的としています。これにより、曖昧な口約束ではなく、法的に有効な記録に基づいた取引が保証されるのです。
ただし、例外もあります。発注の時点でどうしても価格などが決められない正当な理由がある場合は、その理由と決定予定日を記載した書面(当初書面)をまず受け取り、内容が確定次第、不足事項を記載した書面(補充書面)を改めて交付してもらうことになります。単に金額欄が空欄のまま放置されることは許されません。
以下に、3条書面に必ず記載されなければならない12項目をまとめました。あなたが受け取った発注書や契約書が、法的に有効なものかどうかをチェックするためのリストとしてご活用ください。
3条書面に記載が義務付けられている12項目
| 項目 | 記載事項 | 解説 |
| 1 | 親事業者及び下請事業者の名称 | 略称や通称ではなく、登記された正式名称が必要です。取引の当事者を特定します。 |
| 2 | 製造委託、修理委託などをした日 | 発注日を明確に記載します。すべての取引期間の基準となります。 |
| 3 | 下請事業者の給付の内容 | 委託する業務内容を具体的に記載します。「〇〇の製造」「〇〇システムの開発」など、誰が見てもわかるように明確にします。 |
| 4 | 下請事業者の給付を受領する期日 | いわゆる「納期」です。具体的な年月日を記載する必要があります。 |
| 5 | 下請事業者の給付を受領する場所 | 納品場所を明記します。これにより、納品に関するトラブルを防ぎます。 |
| 6 | 検査を完了する期日 | 親事業者が納品物を検査する場合、その検査完了日を記載します。支払遅延の口実に使われることを防ぎます。 |
| 7 | 下請代金の額 | 最も重要な項目の一つです。具体的な金額、または客観的に金額が確定する算定方法(例:単価〇円×数量)を記載します。 |
| 8 | 下請代金の支払期日 | 納品物を受領した日から60日以内で、かつ、できる限り短い期間内で定めなければなりません。 |
| 9 | 手形を交付する場合の事項 | 手形で支払う場合、手形の金額(または支払比率)と満期日を記載します。 |
| 10 | 一括決済方式で支払う場合の事項 | 金融機関名、貸付可能額、親事業者が金融機関へ支払う期日などを記載します。 |
| 11 | 電子記録債権で支払う場合の事項 | 電子記録債権の額と満期日を記載します。 |
| 12 | 原材料等を有償支給する場合の事項 | 親事業者から原材料などを購入する場合、その品名、数量、対価、決済方法などを記載します。 |
口頭発注が引き起こす典型的なトラブル事例
3条書面がない状態、つまり口頭発注は、親事業者にとって都合の良い曖昧さを生み出します。この曖昧さが、下請事業者にとって不利な状況を招くのです。書面がないことで、トラブルが起きた際に「何を合意したか」を証明する責任が、不当にも下請事業者側に押し付けられてしまいます。
ここでは、口頭発注が原因で実際に起こりがちな典型的なトラブルを事例と共に紹介します。
代金の不払い・減額
最も多く、そして深刻なトラブルが金銭に関するものです。作業が完了し、請求書を送った後になってから、「予算が削減された」「思ったより成果が出ていない」といった理由で、一方的に代金の減額を要求されるケースです。
ひどい場合には、担当者が代わり「契約内容がわからない」という理由で支払いを拒否されることさえあります。書面がなければ、当初合意した金額を証明することが非常に困難になります。
仕様変更・無償の追加作業
「ついでにこれもお願い」と、契約範囲外の作業を次々と追加されるのも典型的な例です。口頭でのやり取りでは、どこまでが当初の契約範囲で、どこからが追加作業なのかの線引きが曖昧になりがちです。善意で対応しているうちに、無償での手直しや追加作業が常態化し、採算が合わなくなってしまいます。
不当な返品
納品した商品や成果物について、下請事業者の責任ではない理由で返品されるケースです。例えば、「親事業者の販売計画が変わった」「市場で売れ残った」といった理由で、完成品が一方的に返送されることがあります。3条書面で受領拒否ができないルールが明確になっていれば防げるはずのトラブルです。
納期・支払サイトの認識齟齬
「急ぎで」と口頭で言われたものの、具体的な納期が曖昧だったためにトラブルになることがあります。さらに深刻なのは支払サイト(締め日と支払日)の認識違いです。「月末締め、翌月末払い」だと思っていたら、「社内ルールで検収後60日払いだ」などと後から言われ、資金繰りに窮するケースも少なくありません。
これらのトラブルの根源はすべて、取引条件を明確にした書面がないことにあります。口頭発注は、こうした不誠実な行為を許容する土壌そのものなのです。
口頭発注を受けてしまった場合の具体的な対処法
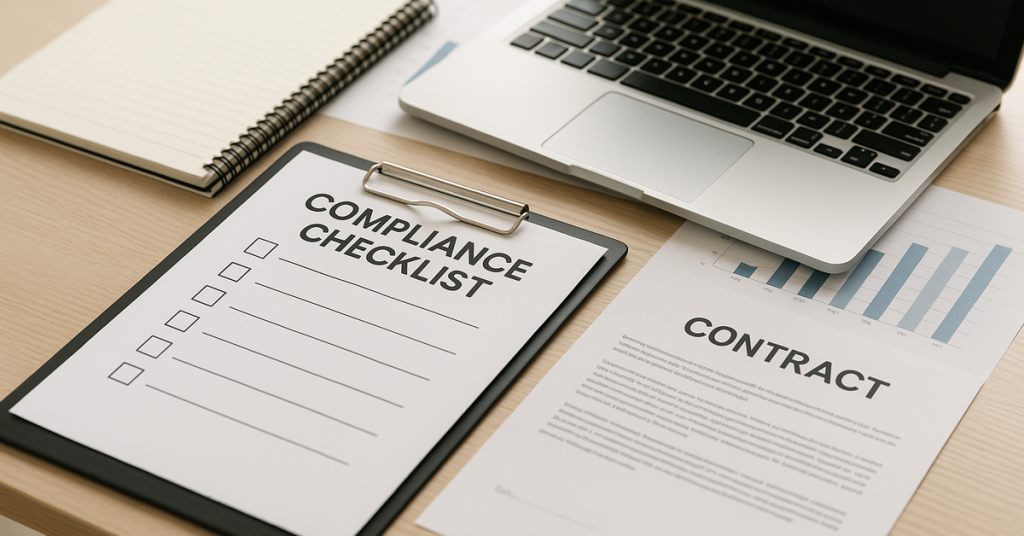
もしあなたがすでに口頭発注で仕事を進めてしまっている場合でも、諦める必要はありません。パニックにならず、冷静に、そして戦略的に行動することで、状況を改善できます。以下に示す3つのステップは、あなたの権利を守り、問題を解決するための具体的な行動計画です。
ステップ1:証拠を確保する
まず最初に行うべきは、取引の存在と内容を証明できるあらゆる証拠を集めることです。3条書面がなくても、これらの断片的な情報を組み合わせることで、強力な証拠となり得ます。
- 電子データ
メールやビジネスチャット(Slack, Teamsなど)のやり取りはすべて保存します。特に、発注内容、金額、納期に関する記述は重要です。 - 書面
あなたが提出した見積書、納品書、請求書の控えは必ず保管します。FAXでのやり取りも証拠になります。 - 音声データ
電話での重要な会話や打ち合わせは録音を検討します。相手の同意がない録音でも、状況によっては法的に有効な証拠となり得ます。 - 議事録・メモ
打ち合わせの日時、出席者、発言内容、決定事項を記録したものは有力な証拠です。
ステップ2:書面の交付を正式に請求する
証拠を確保したら、次は親事業者に対して行動を起こします。感情的にならず、ビジネスライクに、そして記録が残る方法で3条書面の交付を請求しましょう。
最適な方法はメールです。「お世話になっております。先日ご依頼いただきました〇〇の件につきまして、下請法第3条に基づき、お手数ですが発注書面のご交付をお願いできますでしょうか。請求処理を円滑に進めるためにも、ご協力いただけますと幸いです」のように、法律上の義務であることと事務手続き上の必要性を伝えるのが効果的です。
これは単なるお願いではなく、あなたの正当な権利の行使です。この要求をすることで、相手が単なるうっかりだったのか、意図的に書面を出していないのかを判断する材料にもなります。
ステップ3:公的機関や専門家に相談する
ステップ2の要求をしても親事業者が応じない、あるいは不誠実な対応を続ける場合は、一人で抱え込まず、外部の力を借りましょう。あなたには、無料で相談できる強力な味方がいます。
この段階で相談すべき主な窓口は、公正取引委員会、中小企業庁、そして下請かけこみ寺です。これらの機関は、まさにこのような状況にある事業者を救済するために存在しています。次の章で、それぞれの機関の役割と活用法を詳しく解説します。
この3ステップのプロセスは、まず内々での解決を試み、それでもダメなら公的な介入を求めるという、合理的かつ段階的なアプローチです。これにより、可能であれば取引関係を維持しつつ、あなたの権利を確実に守ることができます。
無料で相談できる公的機関と専門家
親事業者とのトラブルに直面したとき、「自分は弱い立場だから」と諦めてしまう必要は全くありません。国は、下請事業者を守るために、複数の相談窓口を設けています。これらの窓口は無料で利用でき、あなたの秘密は固く守られます。どの窓口に相談すべきか、それぞれの特徴を理解し、状況に応じて最適な場所を選びましょう。
公正取引委員会・中小企業庁
公正取引委員会と中小企業庁は、下請法を所管し、その違反行為を取り締まる国の行政機関です。これらの機関に親事業者の違反行為を申告(通報)することができます。
申告に基づき調査が行われ、違反が認められれば、親事業者に対して違反行為の中止や、減額された代金の返還などを命じる勧告や指導が行われます。勧告が出された場合、親事業者の企業名や違反内容が公表されるため、企業にとって大きな抑止力となります。
特筆すべき点として、匿名での情報提供も可能です。報復を恐れることなく、安心して相談・申告できる体制が整えられています。親事業者が書面交付義務に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
下請かけこみ寺
下請かけこみ寺は、中小企業庁が全国48ヶ所に設置している、取引上の悩みに特化した相談窓口です。企業間取引や下請法に詳しい専門の相談員が、無料で親身に相談に乗ってくれます。また、弁護士による無料相談も受けられます。
当事者間での解決が難しい場合、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用できます。これは、弁護士が中立な立場で仲介し、裁判をせずに話し合いでの解決を目指す手続きです。迅速かつ円満な解決が期待できます。まず何から手をつけていいかわからない、という場合の最初の相談窓口として最適です。匿名での相談も可能で、相談したことが取引先に知られることは絶対にありません。
弁護士
弁護士は、あなたの代理人として法的な手続きをすべて行ってくれる専門家です。あなたの代理として親事業者と直接交渉したり、法的拘束力を持つ内容証明郵便を送付して支払いを強く催促したりすることができます。
交渉が決裂した場合は、訴訟などの法的手続きに移行し、あなたの権利を法廷で主張します。最も強力な解決手段ですが、費用がかかります。問題がこじれてしまい、行政機関の介入だけでは解決が難しい場合に頼りになる存在です。
どの窓口を選ぶかは、あなたの目的によって決まります。まずは「下請かけこみ寺」で現状を整理し、アドバイスをもらう。それでも解決しなければ、公正取引委員会に申告して行政の力を借りる。このように段階的に活用するのが賢明な方法です。
主な相談窓口と連絡先
| 相談先 | 連絡先 | 特徴 |
| 公正取引委員会 / 中小企業庁 | フリーダイヤル: 0120-060-110 | 法律違反の申告、行政指導を求める場合に利用。匿名での情報提供も可能です。 |
| 下請かけこみ寺 | フリーダイヤル: 0120-418-618 | 取引上の悩み全般に関する最初の相談窓口。無料で専門家が対応し、ADRも利用できます。 |
親事業者が遵守すべきコンプライアンスと信頼される発注体制の構築

この記事は主に下請事業者の方向けですが、親事業者の担当者にとっても重要な内容を含んでいます。下請法の遵守は、法的な罰則を回避するためだけではなく、企業の社会的信頼を維持し、サプライチェーンを安定させるための重要な経営課題です。
下請法違反、特に書面交付義務違反で公正取引委員会から勧告を受けると、企業名が公表されます。50万円以下の罰金という直接的なダメージよりも、企業の評判に傷がつくことによる間接的な損害の方がはるかに大きい場合があります。優れた技術を持つパートナー企業から敬遠され、結果的に自社の競争力を削ぐことにもなりかねません。
信頼される発注者であるために、社内の体制を今一度確認しましょう。下請法は親事業者に対し、大きく分けて「4つの義務」と「11の禁止行為」を定めています。
親事業者に課せられる4つの義務
- 書面の交付義務(3条書面)
発注時に直ちに必要事項を記載した書面を交付する義務です。 - 支払期日を定める義務
納品物受領日から60日以内で、できるだけ短い支払期日を定める義務です。 - 書類の作成・保存義務
取引の記録(5条書面)を作成し、2年間保存する義務です。 - 遅延利息の支払義務
支払が遅れた場合、年率14.6%の遅延利息を支払う義務です。
親事業者の11の禁止行為
これらは下請事業者の合意があっても違反となる行為です。
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 不当な返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
特に大企業では、発注担当部署と法務・コンプライアンス部署の連携が不可欠です。現場担当者が下請法の知識不足から、無自覚に違反行為を行ってしまうリスクがあります。定期的な社内研修の実施や、発注フローの見直しを行い、全社的にコンプライアンス意識を高めることが、長期的な企業価値の向上につながります。
まとめ
本記事では、下請法における口頭発注の問題点と、その対処法について詳しく解説してきました。最後に、あなたが明日から実践すべき最も重要なポイントを再確認します。
- 口頭発注は明確な法律違反である
あなたの取引が下請法に該当する限り、発注書面のない口頭での発注は許されません。これは交渉の余地のない、法律上のルールです。 - 3条書面はあなたの「権利」である
発注書面を受け取ることは、親事業者にお願いする事柄ではありません。法律によって保証された、あなたの正当な権利です。 - 証拠の記録が身を守る盾になる
万が一のトラブルに備え、メールやチャット、打ち合わせのメモなど、取引に関するあらゆる記録を日頃から整理・保管する習慣が、あなた自身を守る最も確実な方法です。 - あなたには無料で相談できる公的な味方がいる
一人で悩む必要はありません。「下請かけこみ寺」や公正取引委員会など、あなたを支援するために存在する公的機関を積極的に活用してください。
この記事で得た知識は、あなたを理不尽な取引から守るための武器です。これからは、あいまいな口約束を安易に受け入れるのではなく、毅然とした態度で書面の交付を求めてください。それは、健全で対等なパートナーシップを築くための第一歩です。法律を味方につけ、自信を持ってビジネスを進めていきましょう。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…