
下請事業者への発注業務において、「とりあえず口頭でお願いして、書類は後で」といった対応をしていませんか。もしそうなら、あなたの会社は気づかぬうちに大きなリスクを抱えているかもしれません。
下請法における書面交付義務は、単なる事務手続きではありません。違反すれば最大50万円の罰金や企業名の公表といった厳しい罰則につながる、企業の信頼性を左右する重要な法的義務です。
この記事は、公正取引委員会や中小企業庁の公表情報に基づき、書面交付義務のすべてを網羅的に解説する記事です。最後までお読みいただければ、下請法の対象となる取引を正確に判断し、法律に準拠した発注書面(3条書面)を迷いなく作成、交付できるようになります。
本記事では、具体的な記載項目リストや、間違いやすい電子化の注意点など、すぐに実務で使える知識を豊富に盛り込みました。
複雑に思える法律の要点を、誰にでもわかるように、そして確実に実践できるように解説します。コンプライアンスを徹底し、下請事業者との健全なパートナーシップを築くための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
目次
自社の取引が下請法の対象かを確認する
下請法の書面交付義務を理解する前に、まず自社の取引がそもそも下請法の適用対象なのかを正確に把握する必要があります。多くの企業が「うちは製造業ではないから関係ない」「業務委託契約だから大丈夫」といった誤解をしていますが、下請法の適用は事業者の資本金と取引の内容という二つの客観的な基準のみで決まります。契約書の名称や業界は関係ありません。
親事業者と下請事業者の定義
下請法では、取引を委託する側を「親事業者」、受託する側を「下請事業者」と呼びます。どちらに該当するかは、両者の資本金規模の組み合わせによって機械的に決まります。この資本金区分は、取引内容によって二つのパターンに分かれます。
製造委託・修理委託などの場合
物品の製造や修理、プログラム作成、運送、倉庫保管といった取引では、以下の資本金区分が適用されます。
親事業者の資本金が3億円を超え、取引先である下請事業者の資本金が3億円以下(個人事業主を含む)の場合に適用されます。また、親事業者の資本金が1千万円を超え3億円以下で、取引先である下請事業者の資本金が1千万円以下(個人事業主を含む)の場合も対象となります。
情報成果物作成委託・役務提供委託の場合
プログラム作成を除くデザインや映像コンテンツの制作、運送などを除くサービスの提供といった取引では、以下の資本金区分が適用されます。
親事業者の資本金が5千万円を超え、取引先である下請事業者の資本金が5千万円以下(個人事業主を含む)の場合に適用されます。また、親事業者の資本金が1千万円を超え5千万円以下で、取引先である下請事業者の資本金が1千万円以下(個人事業主を含む)の場合も対象となります。
ここで重要なのは、資本金がわずか1円違うだけで下請法の適用関係が変わり得るという点です。例えば、資本金3億円の会社が資本金1千1万円の会社に製造委託をする場合、下請法の対象外です。
しかし、委託側の資本金が3億1円になるか、受託側の資本金が1千万円になれば、下請法が適用される親事業者と下請事業者の関係となります。自社と取引先の資本金は、契約前に必ず確認する習慣をつけましょう。
対象となる4つの取引類型
資本金区分に加えて、取引内容が以下の四つのいずれかに該当する場合に下請法が適用されます。
製造委託
事業者が販売または製造請負する物品の仕様(規格、品質、デザインなど)を指定して、他の事業者に製造や加工を委託することです。例えば、自動車メーカーが部品メーカーに特定のエンジン部品の製造を委託したり、スーパーが食品メーカーにプライベートブランド商品の製造を委託したりするケースが該当します。
修理委託
事業者が請け負った物品の修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品の修理を他の事業者に委託したりすることです。自動車ディーラーが顧客から預かった自動車の板金塗装を専門業者に再委託する場合や、工場が自社で使用する工作機械のメンテナンスを機械メーカーに委託する場合などがこれにあたります。
情報成果物作成委託
事業者が提供または作成する情報成果物(プログラム、映像コンテンツ、デザインなど)の作成を他の事業者に委託することです。具体例としては、ソフトウェア会社が会計ソフトの特定のモジュール開発を別の会社やフリーランスに委託する、広告代理店がクライアントのポスターデザインをデザイン会社に委託するといったケースが挙げられます。
役務提供委託
事業者が請け負ったサービスの提供を他の事業者に委託することです。ただし、建設業者が請け負う建設工事は対象外となります。運送会社が長距離輸送の一部区間を別の運送会社に再委託したり、ビルメンテナンス会社が警備業務を警備会社に委託したりする場合が該当します。
これらの取引類型は非常に広範囲に及びます。特にIT、デザイン、コンサルティングといった現代的なサービス業では、自社が下請法の「親事業者」に該当するという認識がないまま、フリーランス(個人事業主)などに発注しているケースが散見されます。
取引の実態が上記4類型のいずれかに当てはまり、資本金要件を満たす場合は、下請法が適用されることを強く認識する必要があります。
下請法の核となる書面交付義務(3条書面)
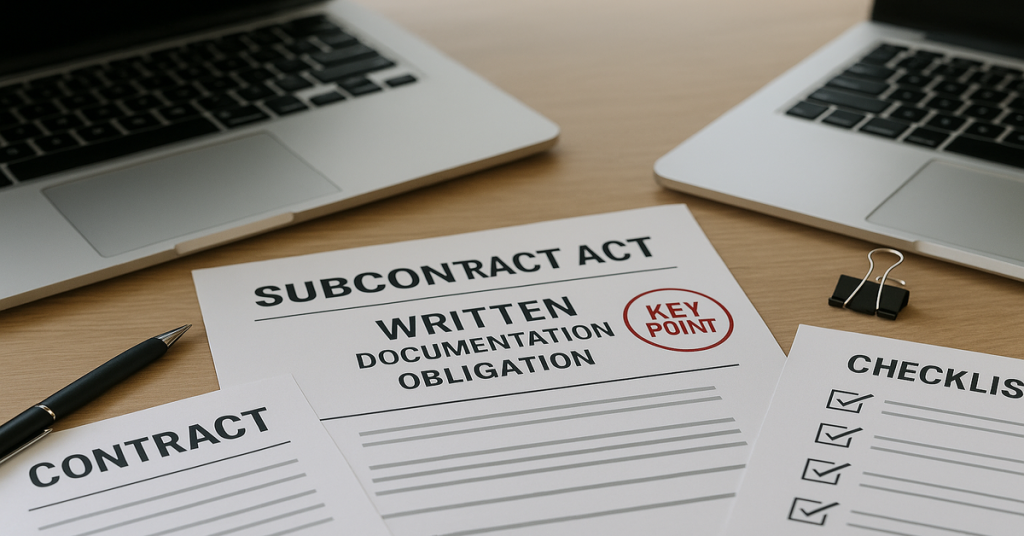
自社の取引が下請法の対象であることが確認できたら、次に理解すべきは親事業者に課される四つの義務です。その中でも最も基本的かつ重要なのが、下請法第3条に定められた書面の交付義務です。この義務に基づき交付される書面は、通称「3条書面」と呼ばれます。
なぜ書面の交付が義務付けられているのか
書面交付義務の目的は、下請取引におけるトラブルを未然に防ぐことにあります。もし発注が口頭のみで行われると、委託内容、納期、金額といった重要な取引条件が曖昧なまま作業が開始されてしまいます。その結果、「言った、言わない」の水掛け論に発展し、立場の弱い下請事業者が不利益を被る事態が起こりがちです。
そこで下請法は、立場の強い親事業者に対し、発注内容を明確に記載した書面を交付することを義務付けました。これにより、取引条件が契約開始時点から明確になり、両当事者の権利と義務が安定します。書面交付は、下請事業者を守るだけでなく、親事業者自身を将来の紛争リスクから守るための重要な手続きなのです。
「直ちに」交付する義務の重要性
下請法第3条は、親事業者が発注に際して「直ちに」3条書面を交付しなければならないと定めています。この「直ちに」という要件は非常に厳格に解釈されます。
例えば、緊急の案件で電話で発注した場合でも、電話連絡のみで済ませることは書面交付義務違反となります。電話で発注内容を伝えた後、遅滞なく、つまり日を空けずに3条書面の要件を満たした注文書などを交付する必要があります。
この要件は、企業の業務プロセスに重要な示唆を与えます。多くの企業では、まず口頭やメールで発注の意思を伝え、正式な発注書は後から経理部門が発行するというフローが一般的かもしれません。
しかし下請法の観点では、法的な「発注(委託)」の行為と「書面の交付」は、ほぼ同時に行われるべき一体の行為とみなされます。したがって、下請法対象取引においては、発注の意思決定と同時に3条書面が発行、送付される業務フローを構築することが、コンプライアンス上不可欠です。
3条書面に記載すべき12の必須項目
3条書面には、法律で定められた12の項目をすべて、かつ明確に記載する必要があります。書面のタイトルは「注文書」「発注書」「業務委託契約書」など、何でも構いませんが、重要なのはその中身です。以下に、各項目の記載ポイントと注意点を解説します。
親事業者及び下請事業者の名称
事業者双方の正式名称を記載します。事業者ごとに付された番号や記号での記載も認められています。
委託日
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託または役務提供委託をした日、つまり「発注日」を具体的に記載します。
下請事業者の給付の内容
委託する業務内容が具体的にわかるよう、品名、仕様、規格、数量などを明確に記載します。「詳細は別途指示」のような曖昧な表現は避けるべきです。知的財産権の譲渡や許諾を含む場合は、その範囲も明記する必要があります。
下請事業者の給付を受領する期日
いわゆる「納期」です。具体的な年月日を記載します。役務提供委託の場合は、役務が提供される期日または期間を記載します。
下請事業者の給付を受領する場所
物品を納品する場所を具体的に記載します。データ納品などで物理的な場所がない場合は記載不要です。
検査を完了する期日
納品物について検査を行う場合に記載が必要です。「納品後〇日以内」のように、受領日から起算して明確に定めます。
下請代金の額
原則として具体的な金額を記載します。消費税額も明確にすることが望ましいです。金額が確定できないやむを得ない事情がある場合に限り、明確な「算定方法」を記載することが認められます。単に「協議の上決定」としたり、仮単価を記載したりすることは認められません。
下請代金の支払期日
給付を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内で具体的な支払日を定めます。「毎月末日締め、翌月末日払い」といった記載も可能です。
手形を交付する場合の事項
代金を手形で支払う場合に記載します。手形の金額(または支払比率)と満期日を明記する必要があります。
一括決済方式で支払う場合の事項
一括決済方式を利用する場合には、金融機関名、貸付可能額、親事業者の金融機関への支払期日などを明記します。
電子記録債権で支払う場合の事項
電子記録債権で支払う際には、電子記録債権の額と満期日を明記します。
原材料等を有償支給する場合の事項
親事業者が下請事業者に原材料などを有償で支給するケースでは、その品名、数量、対価、引渡日、決済方法などを記載する必要があります。
これらの項目の中で、発注時点で内容が確定できない事項がある場合は、その理由と内容を決定する予定期日を当初の書面に記載し、内容が確定次第、速やかに補充の書面を交付する必要があります。
3条書面の電子化(電磁的交付)における注意点

業務効率化の観点から、3条書面を紙ではなく電子データで交付したいと考える企業は多いでしょう。下請法では、一定の要件を満たすことで書面の交付に代えて電子的な方法(電磁的交付)で提供することが認められています。しかし、そのルールは厳格であり、安易な電子化は法令違反につながるため注意が必要です。
電子化が認められる方法
3条書面の交付に代えることができる電磁的方法は、三つの方法に限定されています。一つ目は、電子メールやEDIなどを利用する方法です。これは電気通信回線を通じて送信し、下請事業者が使用するパソコンなどのファイルに記録する方法を指します。
二つ目は、ウェブサイトなどを利用する方法です。親事業者のウェブサーバー上のファイルを下請事業者に閲覧させ、かつ、そのパソコンなどのファイルにダウンロード(記録)させる必要があります。三つ目は、CD-ROMなどを交付する方法で、磁気ディスクやCD-ROMといった記録媒体そのものを交付します。
電子化の絶対条件は下請事業者の事前承諾
上記の方法で電子交付を行うためには、あらかじめ下請事業者から書面または電磁的方法による承諾を得ることが絶対的な条件です。口頭での承諾は認められません。
この事前承諾を得る際には、電磁的方法で提供すること、具体的な提供方法(例:「PDFファイルを電子メールで送信」など)、ファイルへの記録方法、費用負担に関する内容(もしあれば)、そして下請事業者はいつでも電子交付を拒否し書面交付を求められる旨を、下請事業者に明示する必要があります。これらの条件を満たした上で、明確な形で承諾を得て初めて、電子交付が法的に有効となります。
電子交付で陥りやすい失敗例
電子化を進める上で、多くの企業が陥りがちな間違いがあります。例えば、SMSやチャットツールでの連絡は、通常、下請事業者のファイルに永続的に記録されることを保証しないため、不適切とされています。
また、ダウンロード機能のないウェブサイトでの閲覧も認められません。下請事業者が内容を閲覧できるだけでは不十分で、必ずダウンロードしてファイルとして保存できる機能が必要です。
携帯電話へのメール送信も、下請事業者のファイルに記録されない可能性があるため、原則として認められません。ただし、スマートフォンなどで受信し記録できることについて明確な事前合意がある場合は、例外的に認められることがあります。
電子交付の法的要件は、「親事業者が情報を送信した」という事実だけでは満たされません。「下請事業者がその情報を自身のファイルに記録できる状態になった」という結果が重視されます。
親事業者は、選択した方法がこの結果を確実に満たすものであるかを確認する責任を負います。安易にペーパーレス化を進めるのではなく、電子契約サービスなど、下請法の要件を満たすことが明記されたシステムを導入するか、承諾手続きを含めて慎重に運用プロセスを設計することが賢明です。
書類作成と保存の義務(5条書面)と3条書面の違い
3条書面の交付義務を果たすだけで、下請法の書類に関する義務が完了するわけではありません。下請法第5条には、親事業者が取引記録に関する書類を作成し、2年間保存する義務が定められています。この書類は通称「5条書面」と呼ばれ、3条書面とは目的も内容も異なります。この違いを理解していないと、コンプライアンス違反に陥る可能性があります。
両者の主な違いは、その目的とタイミングにあります。3条書面は、発注時に交付し、未来の取引内容を事前に明確化することでトラブルを防ぐことが目的です。一方、5条書面は、取引の実績を事後的に記録し、公正な取引が行われたことの証拠として保存することが目的であり、過去の取引結果を記載します。
また、交付と保存の当事者も異なります。3条書面は親事業者が作成し、下請事業者に交付するものですが、5条書面は親事業者が作成し、自社内で保存するものです。
記載事項についても、5条書面は3条書面の記載事項に加え、実際に給付を受領した日、下請代金の支払日と支払手段、給付内容の変更ややり直しの理由など、取引の実績に関する事項を含む17項目の記載が求められます。
保存期間に関しても、3条書面自体には下請法上の保存義務はありませんが、5条書面は作成後2年間の保存が義務付けられています。重要なのは、発注時に交付した注文書(3条書面)だけでは、5条書面の義務を果たしたことにはならないという点です。
3条書面には「実際に支払った代金額」や「支払った日」といった取引後の情報が含まれていないためです。親事業者は、3条書面とは別に、請求書や支払記録などを関連付けて整理し、5条書面として要求されるすべての情報が揃った記録を作成、保存するプロセスを確立する必要があります。
義務違反に対する罰則と事業リスク
下請法の書面交付義務や書類作成、保存義務を軽視すると、企業は深刻なペナルティを受ける可能性があります。「知らなかった」では済まされず、その代償は金銭的なものにとどまりません。
最大50万円の罰金が科されるケース
親事業者が3条書面を交付しない、または記載事項に不備がある場合や、5条書面を作成・保存しない、または虚偽の記録を作成した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
この罰金は、違反行為を行った担当者個人だけでなく、法人である会社にも科される「両罰規定」が適用される場合があります。つまり、担当者と会社の両方が処罰の対象となり得るのです。また、公正取引委員会や中小企業庁による調査に対して報告を怠ったり、虚偽の報告をしたり、立入検査を拒んだりした場合も、同様に50万円以下の罰金の対象となります。
企業名公表という社会的制裁
罰金以上に企業にとって大きな打撃となり得るのは、企業名の公表という社会的制裁です。下請法違反が発覚し、公正取引委員会が改善を促す「勧告」を行った場合、その事実(違反した企業名、違反内容、勧告の概要など)が原則としてすべて公表されます。
企業名が公表されれば、ニュースなどで報道され、「下請けいじめをする会社」というネガティブな評判が広まります。これにより、取引先からの信用失墜、消費者からのブランドイメージの低下、優秀な人材の採用難など、事業活動に長期的かつ深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。金銭的な罰則よりも、このレピュテーションリスクこそが下請法違反の最大の脅威と言えるでしょう。
遅延利息の支払い義務
書面交付義務とは直接関連しませんが、下請法が定める重要な金銭的ペナルティとして、遅延利息の支払い義務があります。定められた支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、親事業者は給付の受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの日数について、年率14.6%という高い利率の遅延利息を下請事業者に支払わなければなりません。
これらの罰則は、下請法コンプライアンスが単なる事務手続きの問題ではなく、企業の存続に関わる重要な経営課題であることを示しています。
まとめ
下請法の書面交付義務は、中小企業を不当な取引から守るための生命線であると同時に、親事業者が自社の法的、社会的なリスクを管理し、持続的な成長を遂げるための基盤でもあります。本記事で解説した要点を確実に実践することで、法令遵守と健全なパートナーシップの両立が可能です。
まず、発注を行う前に、必ず自社と取引先の資本金、そして取引内容を確認し、下請法の適用対象であるかを判断するプロセスを確立してください。すべての下請法対象取引において、12の必須項目を網羅した3条書面を「直ちに」交付することを徹底し、口頭での発注は厳禁です。
書面を電子化する場合は、必ず下請事業者からの明確な事前承諾を得て、ダウンロード可能な形式など、法律の要件を満たす方法を採用してください。また、交付する3条書面とは別に、取引の実績を記録した5条書面を作成し、2年間保存する義務があることも忘れてはなりません。
義務違反の代償は、罰金だけではありません。企業名の公表による信用失墜は、事業に計り知れない損害を与えます。コンプライアンスはコストではなく、未来への投資です。下請法の遵守は、下請事業者との公正で対等な関係を築き、サプライチェーン全体の競争力を高めることにも繋がります。本記事が、貴社のコンプライアンス体制を強化し、すべての取引先と良好な関係を築くための一助となれば幸いです。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…