
企業の経営者であれば、誰もが考えることがあります。それは、会社の税負担を合法的に軽減し、同時に従業員の手取り収入を増やす方法はないか、ということです。
実は、その両方を実現できる強力な制度が「出張手当」です。多くの企業で導入されていますが、その真の価値を戦略的に活用できているケースはまだ多くありません。
この記事を最後まで読めば、あなたも出張手当制度の全体像を深く理解できます。そして、会社の財務体質を強化し、従業員の満足度を高めるための具体的な導入・運用方法を自信をもって実行できるようになります。
出張手当を単なる経費項目から、会社の成長を加速させる戦略的な財務ツールへと変えるための知識が、ここにあります。
税務や法務と聞くと、複雑でリスクが高いと感じるかもしれません。しかし、心配はいりません。この記事で紹介する正しい手順と法的根拠に基づけば、そのプロセスは驚くほど明快です。あなたの会社でも、安全かつ確実に再現できます。
本記事では、出張手当の基本から、具体的な節税効果、制度の根幹となる「出張旅費規程」の作り方、そして金額設定のための最新データまで、網羅的に解説していきます。
目次
出張手当(日当)とは?今さら聞けない基本を徹底解説
出張手当の目的と役割
出張手当とは、従業員が出張する際に会社から支給される一定額の手当のことで、「日当(にっとう)」とも呼ばれます。この手当は、領収書での精算が難しい細かな個人的経費を補うために支払われるものです。
出張手当には、主に2つの目的があります。一つ目は、出張先での食事代や通信費、その他の雑費など、普段の勤務地では発生しない費用の補填です。
二つ目は、長距離の移動や慣れない環境での業務がもたらす精神的、肉体的な疲労に対する慰労の意味合いです。法律で支給が義務付けられているわけではありませんが、従業員の負担を軽減し、モチベーションを維持するために重要な役割を果たします。
「出張経費」「交通費」との明確な違い
出張に関連する費用には、似たような言葉がいくつかあり、混同されがちです。それぞれの違いを明確に理解することが、適切な経費管理の第一歩となります。
まず「出張手当(日当)」は、出張中の食事代などの雑費を補うために、あらかじめ定められた一定額(定額)が支給されるものです。領収書は不要で、実費精算とは異なります。
次に「旅費交通費」は、新幹線や飛行機などの移動費や、ホテルなどの宿泊費を指します。これらは、領収書に基づいて実際にかかった費用(実費)を精算するのが一般的です。
そして「出張経費」とは、出張に関わるすべての費用をまとめた総称です。先に述べた「出張手当」と「旅費交通費」の両方を含む、より広い概念として理解してください。
なぜ9割以上の企業が導入するのか?その背景
ある調査によると、宿泊を伴う出張において91.2%もの企業が出張手当を支給しています。これは、出張手当が一部の企業だけの特別な制度ではなく、日本のビジネス慣行として広く定着していることを示しています。
この高い導入率の背景には、単なる税務上のメリットだけではない、より深い理由が存在します。出張手当は、今や企業の福利厚生や報酬パッケージの標準的な要素と見なされています。
もし10社のうち9社がこの手当を支給している状況で、自社だけが支給していなければ、従業員、特に頻繁に出張する社員は不公平感を抱く可能性があります。他社の友人と話した際に、自分の会社が手当を出してくれないと知れば、エンゲージメントの低下につながりかねません。
出張には、高くなりがちな外食費や、私生活への影響といった「目に見えないコスト」が伴います。出張手当は、こうした金銭的、精神的な負担に直接応えるものです。したがって、9割以上という導入率は、節税という経営的な動機に加え、従業員のモチベーションを維持し、人材の確保・定着における競争力を保つという、人事戦略上の強い必要性によって支えられているのです。
会社と社員の双方に絶大なメリット!出張手当の節税効果

出張手当制度の最大の魅力は、会社と社員の双方にとって大きな金銭的メリットがある点です。その仕組みを正しく理解し、活用することで、会社の財務を健全化し、社員の可処分所得を増やすことができます。
法人税・消費税・社会保険料を削減する会社側のメリット
会社側にとって、出張手当は3つの側面からコスト削減に貢献します。
一つ目は法人税の削減です。支給した出張手当は、会計上「旅費交通費」という経費(損金)として全額計上できます。経費が増えることで会社の課税対象となる所得が圧縮され、結果として法人税の負担が軽減されます。
二つ目は消費税の削減です。国内出張に対して支給される出張手当は、消費税法上「課税仕入れ」として扱われます。これにより、会社が納める消費税額から、出張手当に含まれる消費税相当額を控除(仕入税額控除)でき、消費税の納税額が減少します。ただし、海外出張への手当はこの対象にはならないため注意が必要です。
三つ目は社会保険料の削減です。出張手当は給与ではないため、健康保険や厚生年金などの社会保険料の算定基礎に含まれません。これにより、会社が負担する社会保険料の増加を抑えることができます。
所得税・住民税が非課税になる社員側のメリット
社員にとっても、出張手当は非常に有利な制度です。出張手当は、社員の給与所得とは見なされず、所得税や住民税が課税されない非課税所得として扱われます。
また、給与ではないため、社員が負担する社会保険料の算定基礎からも除外されます。つまり、会社から支給された金額が、税金や社会保険料で差し引かれることなく、そのまま全額手元に残るのです。
給与を同額上げるより、手当支給が賢い理由
出張手当のメリットをより具体的に理解するために、会社が社員に10,000円を支払う場合を比較してみましょう。
もし「給与」として10,000円を上乗せした場合、会社側は約1,500円の社会保険料を負担する必要があり、社員側も所得税・住民税(約1,500円~2,500円)と社会保険料(約1,500円)が引かれます。結果として、社員の手取りは約6,000円~7,000円になります。
一方、「出張手当」として10,000円を支給した場合はどうでしょうか。会社は社会保険料を負担する必要がなく、国内出張であれば消費税の仕入税額控除も可能です。社員側は、この手当が非課税所得となるため所得税・住民税はかからず、社会保険料の負担もありません。つまり、10,000円がそのまま手取りとなります。
このように同じ金額を原資としても、支給方法を変えるだけで会社のコストは削減され、社員の手取りは大幅に増加します。これは、出張の多い企業にとって、昇給や賞与とは別の形で従業員に報いるための極めて効果的な手段と言えるでしょう。
非課税の鍵を握る「出張旅費規程」の作り方と法的要件
これまで述べてきた出張手当の税務上のメリットは、ある一つの重要な条件を満たすことで初めて享受できます。それが「出張旅費規程」の整備と、それに基づいた適切な運用です。
なぜ規程がなければ「給与」と見なされるのか 法的根拠を解説
出張手当が非課税となる法的な根拠は、所得税法にあります。法律では、職務遂行のための旅行に必要な費用に充てるための金品は、「通常必要であると認められるもの」に限り非課税としています。これは、出張手当が給与ではなく、業務で発生した費用を補填する「実費弁償」という性質を持つためです。
しかし、「通常必要」という基準は曖昧であり、税務調査の際にその正当性が問われる可能性があります。ここで決定的な役割を果たすのが「出張旅費規程」です。この規程は、「私たちの会社では、このルールに基づいて、これだけの金額を『通常必要な費用』として体系的に支給しています」という客観的な証拠となります。
規程が存在しない場合、支給された手当は、その場限りの恣意的なボーナス(給与)と見なされるリスクが非常に高くなります。つまり、出張旅費規程は単なる社内書類ではなく、税務当局に対して手当の正当性を主張し、給与認定されるリスクから会社を守るための法的な盾なのです。
規程に必ず盛り込むべき必須項目
出張旅費規程を作成する際には、いくつかの項目を網羅することが不可欠です。これにより、規程の実効性と法的有効性が担保されます。
まず「目的」として、この規程が何のために存在するのかを明記します。次に「適用範囲」では、規程が適用される対象者(例:正社員、役員)を定めます。特定の役職者だけを優遇するような不公平な内容だと、役員賞与と見なされる可能性があるため、全適用対象者に対して公平な基準を設けることが重要です。
続いて「出張の定義」を具体的に定めます。例えば、「所属する勤務地から目的地までの移動距離が片道100km以上の場合」といった定量的な基準を設けるのが一般的です。また、「旅費の種類」として、規程で定める旅費の内訳(交通費、宿泊費、日当など)を列挙します。
規程の核となる「旅費の金額」では、役職や出張の種類(日帰り・宿泊、国内・海外)に応じた日当の具体的な金額、宿泊費の上限額、新幹線グリーン車などの利用基準を明記します。運用面では「申請・精算手続き」を定めます。出張前の申請書の提出期限や、出張後の精算書の提出方法など、一連の事務手続きの流れを明確にしましょう。
最後に「緊急時の対応」についても定めておくと、従業員は安心して業務に臨めます。出張中の病気や事故、天災といった不測の事態が発生した場合の対応を記載します。
作成から労働基準監督署への提出までの導入4つの手順
出張旅費規程の導入は、大きく分けて4つの手順で進めます。
第1ステップは「規程の草案作成」です。先に述べた必須項目リストを基に、自社の実態に合った規程の草案を作成します。
第2ステップは「株主総会・取締役会での承認」です。作成した規程案を、株主総会または取締役会で正式に承認することで、会社の公式なルールとしての効力が生まれます。
第3ステップは「労働基準監督署への提出」です。出張旅費規程は、全従業員に適用されるため「就業規則」の一部と見なされます。したがって、変更した就業規則と合わせて、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
最後の第4ステップが「従業員への周知」です。規程の内容を全従業員に周知徹底することで、スムーズな運用が可能になります。
金額設定の決定版!役職・出張先別の最新相場データ
出張旅費規程を作成する上で、最も重要なのが手当の金額設定です。金額が低すぎれば従業員の負担を補えず、高すぎれば税務調査で否認されるリスクがあります。
「社会通念上相当」と認められる金額設定のポイント
税務上の非課税扱いを維持するためには、手当の金額が「社会通念上相当な範囲」であることが求められます。これは、同業種・同規模の他社が一般的に支給している金額と比較して、著しく高額ではないか、という観点で判断されます。
この「社会通念」という曖昧な基準をどう判断すればよいのでしょうか。ここで役立つのが、公的機関や調査会社が公表している統計データです。これらのデータは、自社の金額設定が客観的に見て妥当であることを示す強力な根拠となります。
一方で、法律に上限額の定めがないため、一部の専門家からはより高額な設定も可能という見解も示されています。しかし、公表されている平均額から大きく乖離した金額を設定する場合、その合理性を説明する責任は会社側に生じます。例えば、物価が極めて高い都市への出張が多い、あるいは特別な接待を伴う業務である、といった明確な理由が必要です。
したがって、金額設定は単に数字を選ぶ作業ではありません。それは、リスクとリターンのバランスを考慮した戦略的な意思決定です。最も安全なアプローチは、公的データを基準とし、それを超える場合は明確な事業上の理由を文書化しておくことです。
最新調査に基づく国内出張手当の相場(日帰り・宿泊)
金額設定の具体的な参考として、公的な調査データを活用することが有効です。例えば、産労総合研究所の2019年度調査によると、役職別の宿泊手当の平均額は、一般社員で2,355円、課長クラスで2,711円、部長クラスで2,900円となっています。
役員クラスではさらに上がり、取締役は3,802円、社長は4,598円という結果でした。日帰り手当についても同様の傾向が見られます。また、財務省が2023年に公表したデータでは、役職を問わない全体の宿泊手当の平均額は2,621円でした。これらのデータは、自社の規程を作成する際の客観的な基準として非常に有用です。
海外出張における地域別手当の相場
海外出張の場合は、渡航先の物価水準を考慮して金額を設定する必要があります。産労総合研究所の同調査によれば、地域別の手当の目安として、北米地域で5,300円~5,600円、欧州で5,200円~5,500円、中国で4,800円~5,200円、東南アジアで4,900円~5,200円というデータが示されています。
一方で、財務省の2023年のデータでは、地域を問わない海外出張手当の全体平均は5,441円でした。これらのデータを基に、自社の状況に合わせてバランスの取れた金額を設定することが、税務リスクを抑えつつ制度のメリットを最大化する鍵となります。
実務上の注意点とよくある質問(Q&A)
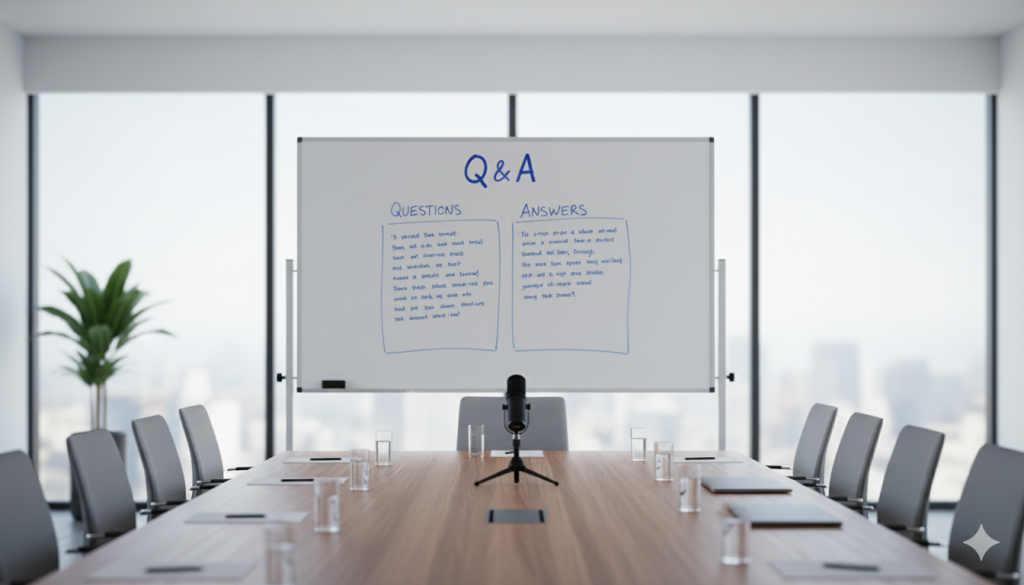
税務調査で否認されないための3つのチェックポイント
出張手当制度を安全に運用するためには、税務調査の視点を常に意識しておくことが重要です。特に以下の3つのポイントを確実に押さえておきましょう。
第一に「規程の存在と遵守」です。正式に承認された出張旅費規程が存在し、すべての手当支給がその規程に厳密に従って行われていることが大前提となります。
第二に「金額の妥当性」です。設定された手当の金額が、前述したような公的データに照らして「社会通念上相当」な範囲に収まっているかどうかが問われます。
第三に「運用の公平性」です。規程が役員や特定の社員だけでなく、適用対象となるすべての従業員に公平に適用されている必要があります。不均衡な運用は、役員への利益供与(役員賞与)と見なされる原因になります。
一人社長・マイクロ法人でも活用できる?
はい、活用できます。むしろ、一人社長や役員のみのマイクロ法人にとって、出張手当は極めて有効な節税・資金移転の手段となります。
役員報酬は、法人税法上の制約(定期同額給与など)により、事業年度の途中で自由に変更することができません。しかし、出張手当であれば、出張の都度、会社の経費として計上し、社長個人は非課税で受け取ることができます。これは、会社の利益を最も税効率の良い形で個人に移転する方法の一つです。
ただし、一点だけ重要な注意点があります。この方法は法人だからこそ可能なスキームです。個人事業主の場合、事業主自身に対して出張手当を支給し、それを経費として計上することはできません。個人事業主が経費にできるのは、実際にかかった交通費や宿泊費などの実費のみです。
経費精算プロセスにおける日当の正しい取り扱い
出張後の経費精算において、日当の扱いは他の経費と異なります。一般的な流れは、出張前に申請書を提出し、必要であれば概算の旅費(仮払金)を受け取り、出張後に旅費精算書と領収書を提出するというものです。
ここで重要なのは、交通費や宿泊費には領収書が必要ですが、出張手当(日当)には領収書が不要であるという点です。日当は、出張旅費規程に定められた日数に基づき、定額で自動的に計算・支給されます。
会計処理上は、他の旅費交通費と同じく「旅費交通費」の勘定科目で計上します。
まとめ:出張手当を戦略的に活用し、企業成長を加速させる
本稿では、出張手当の基本から、その絶大な節税効果、導入に不可欠な出張旅費規程の作成方法、そして具体的な金額設定の目安まで、網羅的に解説しました。
重要なポイントは、出張手当が会社にとって法人税・消費税・社会保険料の「トリプル削減」を可能にする強力なコスト管理ツールであるという点です。同時に、社員にとっては所得税や住民税のかからない非課税収入となり、実質的な手取り額を増やすことで、モチベーションと満足度を向上させます。
そして、これらのメリットを享受するための法的・税務上の正当性は、適切に作成され、公平に運用される「出張旅費規程」によってのみ担保されることを忘れてはなりません。出張手当は、単なる経費精算の一項目ではなく、会社の財務体質を強化し、従業員エンゲージメントを高めるための、極めて効果的な経営戦略なのです。
もし、あなたの会社にまだ出張旅費規程がないのであれば、本稿で示した手順に沿って、今すぐ導入の検討を始めることを強く推奨します。すでに規程がある場合も、最新の相場データと照らし合わせ、内容が最適化されているかを見直す良い機会です。賢明な財務管理への一歩を踏み出し、会社の成長をさらに加速させましょう。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…