
定率法の計算式を正しく理解し活用することは、単なる経理処理にとどまりません。事業初期のキャッシュフローを最大化し、賢い節税を実現して、より大胆な事業投資を可能にするための強力な戦略ツールです。
この知識があれば、税金の支払いを最適化し、手元資金を厚くして、自信をもって次の成長戦略を描けるようになります。
この記事は、複雑に見える定率法の計算を誰にでもわかるように解き明かします。定率法が持つ「計算方法が途中で変わる」という特徴は、多くの経営者や経理担当者を悩ませるポイントです。
しかし、この記事を読めば、その仕組みと具体的な計算手順が明確に理解できます。一つひとつのステップを具体的な数値例と共に解説するため、計算プロセスにおけるあらゆる疑問や不安を解消します。
「会計の専門家でなければ難しいのでは」と感じるかもしれませんが、その心配は不要です。ここで解説する方法や計算例は、会計の深い知識がない方でも実践できるよう、丁寧にかみ砕いて説明します。
この記事で示す手順に従うだけで、誰でも自社の資産に合わせて正確な減価償却計算をおこない、その戦略的なメリットを最大限に引き出すことが可能になります。
目次
減価償却の基本:定率法と定額法の決定的な違い
減価償却とは?資産価値を費用に変換する会計の仕組み
減価償却とは、事業のために使用する高額な資産(例えば、車両、機械、パソコンなど)の取得価額を、その資産が使用できる期間にわたって分割し、少しずつ費用として計上していく会計上の手続きです。資産を購入した年に全額を費用とするのではなく、資産が収益を生み出すのに貢献する期間(耐用年数)に合わせて費用を配分します。
この耐用年数は、企業が自由に決められるものではなく、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」という法律によって資産の種類ごとに細かく定められています。例えば、新品の普通自動車なら6年、パソコンなら4年といった具合です。この法的なルールに従って費用を計上することで、各事業年度の利益をより正確に計算できます。
定率法の特徴:初期に大きく費用計上するメリット
減価償却の計算方法にはいくつか種類がありますが、その代表的なものが定率法です。定率法の最大の特徴は、資産を取得した初期の段階で減価償却費が最も大きくなり、年数の経過とともにその金額が減少していく点にあります。
基本的な計算式は非常にシンプルです。
減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率
ここでいう「未償却残高」とは、資産の取得価額から前年度までに計上した減価償却費の累計額を差し引いた金額を指します。つまり、毎年、まだ費用化されていない残高に対して一定の率を掛けて計算するため、残高が減るにつれて償却費も減少していく仕組みです。
この方法は、多くの資産の経済的な実態とよく合致しています。例えば、自動車や最新の機械設備は、新品の時が最も性能が高く、価値の減少も急激です。定率法は、価値の減少ペースを会計上の費用計上にも反映させるため、より実態に近い損益計算を可能にする考え方といえるでしょう。
定額法との比較:どちらがあなたの事業に適しているか
定率法と比較されるもう一つの主要な方法が定額法です。定額法は、その名の通り、毎年「定額」の減価償却費を計上する方法です。計算式は以下の通りです。
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
定額法では、耐用年数が終わるまで毎年同じ金額が費用となるため、利益計算が安定し、将来の予測が立てやすいというメリットがあります。どちらの方法を選ぶかは、単なる会計処理の選択以上の意味を持ちます。それは、企業の財務戦略や経営姿勢を反映する重要な意思決定です。
定率法は、創業期のスタートアップや、積極的に設備投資をおこなう成長段階の企業に適しています。初期に多くの費用を計上することで課税対象となる利益を圧縮し、納税額を抑えることができます。これにより手元資金(キャッシュフロー)が潤沢になり、その資金をさらなる事業拡大に再投資できます。
一方、定額法は、安定した収益が見込める成熟期の企業や、株主への利益報告の安定性を重視する企業に向いています。毎年の費用が一定であるため、利益の変動が少なく、金融機関からの融資審査などにおいても、安定した経営状況を示しやすくなります。このように、どちらの方法が自社にとって最適かを見極めることは、賢明な経営判断の第一歩となります。
定率法の計算式を徹底解説:基本から改定償却率の適用まで
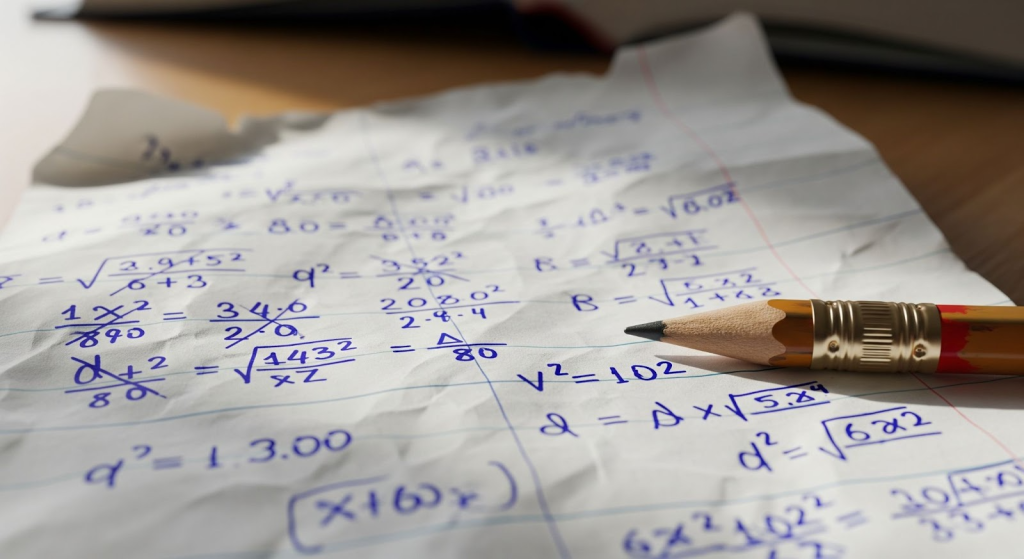
定率法の計算は、一見すると複雑に感じられるかもしれません。特に、計算方法が途中で切り替わる点が難解さの原因です。しかし、3つのステップに分けて考えれば、誰でも正確に計算できます。
ステップ1:基本の計算式をマスターする
まず、基本となる計算式を理解します。これは、減価償却期間の前半で使われる計算方法です。
減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率
各項目の意味は以下の通りです。
- 取得価額
資産を購入するためにかかった金額そのものです。 - 未償却残高
取得価額から、前年までに計上した減価償却費の合計額を引いた金額です。計算初年度は「取得価額」と同じ金額になります。 - 定率法の償却率
資産の耐用年数に応じて法律で定められた率です。国税庁が公表している「減価償却資産の償却率等表」で確認できます。
この式を使って、毎年、期首の未償却残高に償却率を掛けてその年の減価償却費を算出します。
ステップ2:計算方法が変わる分岐点「償却保証額」
定率法の計算が特徴的なのは、ある時点から計算方法が変わる点です。その切り替えのタイミングを判断するのが「償却保証額」です。
償却保証額は、いわば「最低限これだけは償却する」という保証額(セーフティネット)のようなものです。以下の式で計算します。
償却保証額 = 取得価額 × 保証率
「保証率」も償却率と同様に、耐用年数ごとに法律で定められています。毎年、ステップ1の基本式で計算した減価償却費(調整前償却額)と、この償却保証額を比較します。そして、調整前償却額が、はじめて償却保証額を下回った年から、計算方法がステップ3に移行します。
ステップ3:改定取得価額と改定償却率による計算
調整前償却額が償却保証額を下回った年からは、以下の新しい計算式に切り替わります。
減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率
ここで登場する新しい用語の意味は次の通りです。
- 改定取得価額
計算方法が切り替わることになったその年の期首時点での未償却残高を指します。 - 改定償却率
これも耐用年数ごとに法律で定められた率です。この率を使うことで、切り替わった年以降は、毎年同じ金額の減価償却費が計上されるようになります。事実上、ここから定額法のような計算に変わるのです。
このような二段階の仕組みになっているのは、定率法の数学的な性質と、税法の要求を両立させるためです。純粋な定率法の計算だけでは、残高はゼロに限りなく近づきますが、完全にはゼロになりません。しかし、日本の税法では資産の価値が最終的に備忘価額1円になるまで償却することが求められます。この矛盾を解決するために、「償却保証額」をトリガーとして、計算の最終段階で残りをきれいに償却しきるための仕組みが導入されているのです。
具体例で学ぶ:取得価額100万円、耐用年数5年の資産の計算シミュレーション
言葉だけでは分かりにくいので、具体的な数値で計算の流れを見ていきましょう。
【条件】
- 取得価額:100万円
- 耐用年数:5年
- 取得日:2012年4月1日以降(200%定率法を適用)
耐用年数5年の場合、法律で定められた率は以下の通りです。
- 償却率:0.400
- 保証率:0.10800
- 改定償却率:0.500
まず、償却保証額を計算しておきます。この金額が、計算方法を切り替えるかどうかの判断基準になります。
償却保証額 = 1,000,000円 × 0.10800 = 108,000円
| 年度 | 期首未償却残高 | 調整前償却額の計算 | 調整前償却額 | 当期の償却費 | 期末未償却残高 |
| 1年目 | 1,000,000円 | 1,000,000 × 0.400 | 400,000円 | 400,000円 | 600,000円 |
| 2年目 | 600,000円 | 600,000 × 0.400 | 240,000円 | 240,000円 | 360,000円 |
| 3年目 | 360,000円 | 360,000 × 0.400 | 144,000円 | 144,000円 | 216,000円 |
| 4年目 | 216,000円 | 216,000 × 0.400 | 86,400円 | 108,000円 | 108,000円 |
| 5年目 | 108,000円 | − | − | 107,999円 | 1円 |
計算のポイント
計算の1年目から3年目までは、調整前償却額(40万円、24万円、14.4万円)が、いずれも償却保証額(10.8万円)を上回っています。そのため、計算した金額をそのまま当期の償却費とします。
4年目になると、期首未償却残高216,000円で調整前償却額を計算すると86,400円となり、この金額が初めて償却保証額(108,000円)を下回ります。この年から計算方法が切り替わります。
改定取得価額は、4年目の期首未償却残高である216,000円です。この改定取得価額に改定償却率を適用し、216,000円 × 0.500 = 108,000円が4年目の償却費となります。
5年目以降は毎年同じ計算、つまり改定取得価額に改定償却率を掛けます。ただし、最終年度は期末残高が備忘価額1円になるように調整します。そのため、期首未償却残高108,000円から1円を引いた107,999円が最終年度の償却費となります。このように表にしてみると、計算方法が切り替わるタイミングと計算方法が一目瞭然となります。
実践的な知識と戦略:税務手続きと最適な選択
定率法がもたらす節税効果とキャッシュフローへの影響
定率法を選択する最大の戦略的メリットは、節税によるキャッシュフローの改善効果です。減価償却費は、会計上は費用として計上されますが、実際に現金が出ていくわけではない「非資金費用」です。
利益は「収益 – 費用」で計算され、税金はこの利益に対して課されます。定率法では、資産取得の初期に多額の減価償却費を計上できるため、その分、課税対象となる利益が圧縮されます。結果として納める税金の額が少なくなり、その分だけ会社の手元に現金が多く残ります。この税金の軽減効果は「タックスシールド(税金の盾)」と呼ばれます。
特に、事業を始めたばかりの時期や、大規模な設備投資を行った直後は、資金繰りが厳しくなりがちです。このような時期に定率法を活用してキャッシュフローを厚くすることは、事業の安定と成長を加速させる上で非常に有効な戦略です。
償却方法の選択と変更手続き
減価償却の方法は、法律で定められた「法定償却方法」が基本となります。法人は定率法、個人事業主は定額法が原則です。しかし、これはあくまで原則であり、税務署に届け出ることで、異なる方法を選択したり、途中で変更したりすることが可能です。
償却方法を変更したい場合、個人事業主は変更したい年の3月15日までに、「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。法人の場合は、新しい償却方法を採用したい事業年度が始まる日の前日までに、同様の変更承認申請書を提出します。
注意点として、一度採用した償却方法は、原則として3年間は変更できません。ただし、合併など特別な理由がある場合は例外的に認められることがあります。償却方法の変更は計画的に行う必要があります。
注意点:平成24年度税制改正の影響(200%定率法)
減価償却のルールを語る上で、平成24年度(2012年度)の税制改正は非常に重要なポイントです。この改正を境に、定率法の償却率が変更されました。
平成24年3月31日以前に取得した資産には、定額法の償却率を2.5倍した「250%定率法」が適用されます。一方で、平成24年4月1日以降に取得した資産には、定額法の償却率を2.0倍した「200%定率法」が適用されます。
この変更は、政府が企業の利益計上をより平準化させ、税収の安定化を図る政策的な意図を反映したものです。償却率が引き下げられたことで、資産取得初期の減価償却費が以前よりも小さくなりました。
これは、企業側から見ると、初期の節税効果がわずかに弱まったことを意味します。したがって、新しい設備投資の採算性を評価する際には、この200%定率法を前提とした資金計画を立てることが不可欠です。
経理担当者が知っておくべき特例措置と関連知識

通常の減価償却計算に加えて、特に中小企業や個人事業主にとって有利な特例制度がいくつか存在します。これらを活用することで、経理事務を大幅に簡素化し、さらなる節税効果を得ることが可能です。
10万円未満は消耗品費:減価償却が不要なケース
取得価額が10万円未満の資産は、減価償却の対象とする必要がありません。購入した年度に、全額を「消耗品費」などの科目で費用として計上できます。これにより、煩雑な資産管理や減価償却計算の手間を省くことができます。
20万円未満の資産に適用できる「一括償却資産」
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、「一括償却資産」として処理する選択肢があります。これは、個々の資産の耐用年数にかかわらず、取得価額の合計額を3年間で均等に分けて費用計上できる制度です。
この制度の大きなメリットは、経理処理の簡素化だけではありません。一括償却資産として処理した資産は、地方税である「償却資産税」の課税対象から外れるという重要な利点があります。これは見逃されがちですが、確実な節税につながるポイントです。
中小企業者等のための「少額減価償却資産の特例」
青色申告法人である中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)には、さらに強力な特例が用意されています。それが「少額減価償却資産の特例」です。
この特例を使うと、取得価額が10万円以上30万円未満の資産について、取得した事業年度に全額を即時償却(費用計上)できます。ただし、この特例を適用できるのは、年間合計300万円までという上限があります。
この制度は、設備投資を積極的におこなう中小企業の税負担を軽減し、資金繰りを支援することを目的としています。ただし、これは恒久的な制度ではなく、期限が設けられた時限措置であり、現在の適用期限は令和8年(2026年)3月31日までとなっています。
各特例の比較
これらの特例をまとめたものが、以下の比較表です。自社の状況に合わせて最適な処理方法を選択するための判断材料としてご活用ください。
| 取得価額 | 適用ルール | 償却方法 | 償却資産税 | 対象者 | 年間上限 |
| 10万円未満 | 少額の減価償却資産 | 全額を即時費用化 | 対象外 | 全ての事業者 | なし |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 | 3年間で均等償却 | 対象外 | 全ての事業者 | なし |
| 10万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産の特例 | 全額を即時費用化 | 対象 | 青色申告の中小企業者等 | 300万円 |
中古資産を取得した場合の耐用年数の計算方法
新品ではなく、中古の資産を取得した場合、法定耐用年数をそのまま使う必要はありません。より短い耐用年数を設定できるため、減価償却を早く終わらせることが可能です。これを「簡便法」と呼び、計算方法は以下の通りです。
法定耐用年数の全部を経過した資産の場合、耐用年数は「法定耐用年数 × 20%」で計算します。
法定耐用年数の一部を経過した資産の場合は、「(法定耐用年数 − 経過年数) + (経過年数 × 20%)」で算出します。
計算結果に1年未満の端数がある場合は切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。耐用年数が短くなれば、1年あたりの減価償却費が大きくなるため、より早期に投資回収を進めることができます。
まとめ
この記事では、定率法の計算式について、その基本から応用までを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを再確認します。
定率法の計算は二段階の構造になっています。調整前償却額が償却保証額を下回るまでは基本の式で計算し、下回った年からは改定取得価額と改定償却率を用いた計算に切り替わります。この仕組みを理解することが、正確な計算の第一歩です。
また、定率法の選択は、初期のキャッシュフローを改善するための戦略的な意思決定です。大きな節税効果(タックスシールド)により手元資金を確保し、事業の成長を加速させることができます。自社の成長ステージや財務状況に合わせて、最適な償却方法を選択することが重要です。
さらに、30万円未満の資産については、消耗品費、一括償却資産、少額減価償却資産の特例といった有利な制度が存在します。これらを活用することで、経理の簡素化と節税を両立できます。
減価償却は、単なる会計上の義務ではありません。その仕組みを深く理解し、自社の状況に合わせて最適な方法を選択することは、企業の財務体質を強化し、持続的な成長を支えるための重要な経営戦略です。この知識を武器に、より賢い資産管理と財務戦略を実践してください。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…