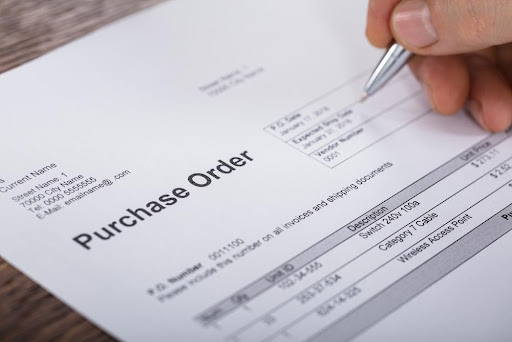
注文書は取引の内容を正しく発注するために必要な書類であり、取引に関する認識違いを防ぐなどの役割があります。本記事では、注文書の書き方や発送方法などについて、画像付きでわかりやすく解説します。
目次
発注書(注文書)とは?

発注書(注文書)とは、商品を注文・発注する際に取引先に提出する書類です。 注文内容を書面でわかりやすく示したものであり、複数の商品をまとめて注文する時や、注文内容が複雑な時などによく使われます。口頭のみで注文するよりも正確で、トラブル回避などに役立ちます。
また、領収書には決められた様式やデザインがあるわけではないので、システム上から発行したり、インターネットで紹介されているテンプレートを使ったりすることが可能です。
注文書と発注書の違いは?
発注書と注文書は似たような言葉ではありますが、法的に違いがあるわけではありません。しかし厳密には、以下のように区別されています。
・発注書:何らかの作業や加工が発生する時に作成する書類
・注文書:商品などを注文するときに作成する書類
発注書はホームページ制作やシステム制作といった作業を依頼する時に作成するのに対し、注文書は具体的な商品・製品を注文するときに作成することが一般的です。
発注書と発注請書の違いは?
発注書は、発注者が取引条件を明示し、注文の意思を伝えるための書類です。一方、発注請書は、受注者が発注内容を承諾し、契約の成立を確認する書類であり、発注書に対する返信として受注者が発行・送付します。
発注請書の発行は法的義務ではありませんが、発注者から注文請書の発行を求められた際には発行することが一般的です。
関連リンク:
注文請書(発注請書)とは?発注書との違いや項目、印紙税、インボイス対応などを解説!
発注書と個別契約書の違いは?
発注書は、発注者が取引条件を提示し、商品やサービスの注文を依頼する書類です。一方、個別契約書は、取引の詳細な条件を明確にし、契約の法的効力を確保するための書類です。
発注書は単体では契約成立とならない場合が多いのに対し、個別契約書は双方の合意によって締結され、法的な効力を持ちます。取引の内容や規模によっては、発注書だけでなく個別契約書を交わすことで、責任範囲を明確にし、契約を円滑に進めることができます。
関連リンク:
売買契約書とは?種類や記載項目、印紙税などよくある疑問を解説
発注書と見積書の違いは?
見積書は、取引の前に受注者が発注者に対して、商品の価格や納期、支払い条件などを提示する書類です。これはあくまで参考資料であり、基本的に契約の義務は発生しません。一方、発注書は、発注者が見積書の内容を確認し、正式に注文する意思を示す書類です。発注書の発行によって契約が成立することもあります。見積書は取引の前段階で使用され、発注書は取引の確定に関わる重要な書類である点が大きな違いです。
関連リンク:
発注書の役割とは?
トラブルを防ぐ
取引を実際に進める前に双方の認識を確認し、食い違いから生じるトラブルを防ぐ役割があります。書類を作成せず口約束だけで取引をしてしまうと「そんなつもりではなかった」といったトラブルが生じることもあるでしょう。
注文書は、あらかじめ取引の内容を詳しく記載することでトラブルを防ぎ、安心して業務を行うことに役立ちます。
公正さを保つ
発注・受注を行う関係は、どちらか一方が弱い立場になってしまうことがあります。特に、下請けの企業や個人事業主が受注する場合は、発注側である企業よりも不利な立場になることもあるでしょう。
注文書を発行することにより弱い立場である受注側を守り、取引における公正さを保つといった役割も存在します。
発注書の発行が義務となるケース
通常、発注書の発行は法的な義務ではありませんが、下請法が適応される取引では発注書の発行は義務になります。
下請法とは、大きな会社(親事業者)と小さな会社(下請事業者)の取引を公正にするための法律です。例えば、大きな会社が小さな会社に製品の製造や修理、サービスの提供を依頼するとき、大きな会社が不当に安い価格を押しつけたり、支払いを遅らせたりしないように、この法律でルールが決められています。
下請法第3条では、親事業者が下請事業者に対して製造委託等を行った場合、下記事項を記載した「発注書」を交付することが義務付けられています。
発注書に記載すべき必要事項
- 下請事業者の給付の内容
- 下請代金の額
- 支払期日および支払方法
- その他の取引条件
発注書の発行義務を怠った場合、下請法第10条および第12条に基づき、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
罰則対象となる行為
- 下請事業者に対して書面を交付しなかった場合
- 必要な書類の作成・保存義務を怠った場合
- 虚偽の書類を作成した場合
- 公正取引委員会や中小企業庁の調査を忌避、拒否、または妨害した場合
- 虚偽の報告を行った場合
取引を透明かつ公平に進めるためにも、発注書の発行とその内容の正確な記載が重要です。
発注書と受注書の違いは?
注文書は発注者から、受注書は受注者から発行する書類です。どちらも注文をした(受けた)ことを証明する役割のある書類ですが、発行する主体で使い分けされています。
受注者が注文を受けた際に取引を行う場合には「受注書」、取引先に代わって業務を行う際に請負契約を締結したい場合は「発注請書」や「注文請書」のように使い分けることもあります。業界の慣習によって使う名称が異なることもあるので、過去に作成された書類や社内ルールなどを参考に決めましょう。
発注書発行の流れを具体例をあげて解説
会社Aが会社Bから商品を購入する場合を例にして、具体的な取引の流れを見てみましょう。
①会社Aが会社Bに対して見積りを依頼する
②会社Bが見積書を発行し、会社Aに送付する
③会社Aは見積書の内容を確認後、会社Bに注文書を送付する
④会社Bは注文書の内容を確認後、会社Aに注文請書(発注請書)を送付する
⑤会社Bは会社Aに商品を納品し、納品書を送付する
⑥会社Bが会社Aに対して請求書を送付する
このほかにも、商品が正しく納品されたことを証明するための検収書を発行する場合もあります。
また、名前を挙げた全ての書類が必要というわけではありません。これらの書類を発行せず、電話やメールなどで注文に必要なやり取りを行ったとしても取引は有効です。商品が少額である場合は、請求書だけ発行して振り込むというシンプルな流れで取引が行われることもあります。
発注書(注文書)を書くときに必要なもの
用紙
基本的にはA4の用紙を使って注文書を印刷します。自社で決まった様式がないのであれば、ネット上のテンプレートを使用することも可能です。
(発注書 テンプレート▶︎コチラから)
封筒・切手
郵送で送る場合は、封筒・切手を用意します。封筒のサイズの決まりは特にありません。
スタンプ
封筒には中身の書類を「○○在中」といった形で明記することが一般的です。 手書きでも構いませんが、注文書を送る機会が多い場合は「注文書在中」のスタンプを用意するといいでしょう。
発注書(注文書)の必須記入項目
書類作成者の氏名又は名称
法人名や担当者名を明記します。
取引年月日
注文書においては、取引年月日が書類の発行日となります。
取引内容
取引の内容を、商品やサービス別にわかりやすく記入します。また、軽減税率の対象品目である旨の記載もします。
取引金額
税率ごとに区分して合計した税込の金額を記入し、取引の最終的な合計金額が分かるようにします。
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
取引先の法人名などを、宛名として記載します。
発注書の雛形・テンプレート

発注書(注文書)に記載する手順
1.宛先
発注先となる法人名や、個人事業主の屋号・名前などを記入します。
2.注文書ナンバー
必須ではありませんが、注文書をわかりやすく管理するために、通し番号を記入する場合もあります。
3.発行日
書類の右上に発行日を記入します。
4.作成者の情報
法人名や連絡先、注文書を作成した担当者の名前などを記入します。
5.商品名
商品名に加え、必要に応じて品番や型番なども記載します。
6.数量・単価
取引に関する具体的な数値を入力します。
7.商品ごとの合計
「数量×単価」で求めた金額を税抜で記入します。
8.小計
すべての商品を税率ごとに分け税抜金額を合計し、小計を記入します。
9.消費税
消費税としてかかる金額や、税率について記入します。
10.合計金額
最終的な合計金額は、必ず税込で記入します。
11.備考
その他、納期や支払い方法など、書いた方がわかりやすいと思われる内容を必要に応じて記入します。
注文書を交付する方法は?
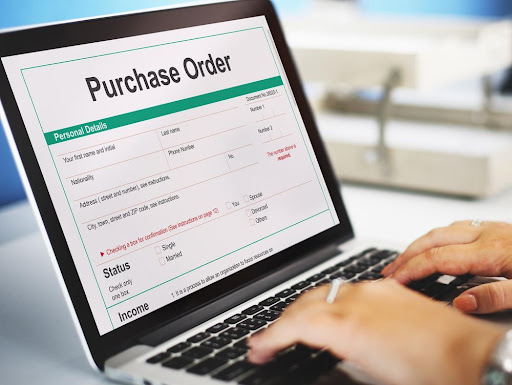
発注書(注文書)の交付にはこれといった決まりがないため、郵送やFAX・メールなど、好きな方法で送ることが可能です。 メールの場合はPDFで添付して送ることが一般的と言えます。
発注書は、取引の内容や金額・納期などについて確認し、発注することが確定した時点で作成・交付を行います。発注する前には、すでに受注側から見積書を受け取り、内容についてのすり合わせも行なっていることが一般的です。注文書はそれらの条件について納得した段階で速やかに作成し、送ることが望ましいでしょう。
領収書などビジネスシーンで使われる書類には、収入印紙を貼ることが求められる場合があります。 しかし注文書は印紙税の課税文書には含まれておらず、原則として収入印紙を貼る必要はありません。
発注書(注文書)で注意すべきこと
見積書と内容をあわせる
注文書は、受注者が作成した見積書の内容にあわせて発行することが基本です。もし注文書と見積書で内容が異なれば、どちらが正しい取引内容なのかがわからなくなってしまいます。
注文書の作成後は見積書の内容と見比べて、相違点がないようにしましょう。もしも見積書の内容で相談したい点などがある場合は、注文書の発行の前に受注者とすり合わせを行うようにします。
下請法の確認を行う
下請法とは、親事業者が下請事業者に発注する場合の取引を公正にすることなどを目的に定められた法律です。「製造委託」「修理委託」など、適応対象となる取引に該当すれば、この下請法を守った上で発注することが必要です。
下請法においては、注文書をはじめとする書類の交付方法などについても明確に定められています。例えば、親事業者が下請事業者のメールボックスに一方的に書類を交付しただけでは、書類を提供したとは認められません。つまり、電磁的方法により注文書を交付する場合には事前に下請事業者からその旨の承諾を得る必要があります。
下請法に関する記事はコチラ▼
下請法とは?違反した場合は?禁止事項も解説!
ミスがないかチェックする
注文書が間違っていれば、プロジェクトの進行中や終了後に、発注先とトラブルに発展することがあります。特に金額や納期については慎重に確認すべきと言えます。また、万が一金額が大きく誤っていた場合には、自社の予算管理や経営に発展する問題になりかねません。注文書を交付する前に、ミスがないかよく確認するようにしましょう。
社内決裁・押印を行う
備品の購入や外部との契約など重要な事項においては、社内決裁や稟議が必要になることがあります。企業のルールや取引の規模に応じて、上層部に確認してもらうなどの機会を設けるといいでしょう。また、交付前には書類の信頼度を上げるために角印を押すケースもあります。
作成後は適切に保管する
注文書は、国税庁が定めるルールに基づき発注後も適切に保管することが求められます。法人は7年間(欠損金が発生する事業年度分は10年間)、個人事業主は5年間(消費税の課税事業者は7年間)の保管が必要です。
欠損金額が発生した場合などのケースにおいては、例外的に保管期間が変更される場合があります。国税庁のホームページを参考に、必要な保管期間を確認しておきましょう。
発注書の保存義務・保存期間は?
発注書は事業で発生した取引の情報を記録する大切な書類であるため、保存が義務付けられています。法人・個人事業主におけるそれぞれの保存期間は、以下の通りです。
| 法人 | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間 ただし、以下の条件に当てはまる場合は10年間 ・青色申告書を提出した事業年度で、欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度 ・青色申告書を提出しなかった事業年度で、災害損失金額が生じた事業年度 |
| 個人事業主 | 青色申告、白色申告ともに5年間 |
発注書など本来保存すべき書類を破棄してしまい、かつ税務調査が行われた場合には、その事実を指摘される可能性があります。必要な経費として計上したものであっても、書類による証明ができないため、経費として認められないかもしれません。追加で税金を支払う必要があるかもしれないことに注意しましょう。
参照:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
参照:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁
発注書に収入印紙は必要か?
原則として発注書には収入印紙を貼る必要はありませんが、一部収入印紙が必要な発注書があります。
そもそも収入印紙とは、課税文書に対して貼り付けることが義務付けられている「印紙税」と呼ばれる税金です。契約書や領収書など、金銭の受け渡しを証明する文書に収入印紙を貼り付けます。
発注書や注文書を取引先に送付した後、申し込みを受け付けることを示すために取引先が「発注請書」を発行する場合があります。その場合、発注請書に効力を持たせるために収入印を貼り付けます。
しかし、取引先が発注請書を発行しない場合には、発注書自体に効力を持たせるために、発注書に収入印紙を貼ることもあります。ただし、発注書をメールやメッセージなどを通じて送る場合や、金額が10,000円に満たない場合には、貼付する義務はありません。
参照:申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|国税庁
発注書のテンプレート
無料で使えるINVOYのテンプレートはこちらから▼
INVOY 発注書テンプレート
注文書の発行が義務になるケースとは
発注書の作成は、一般的には必須ではありません。ただし、下請法が適用される取引の場合、書面を交付するという責任が生じます。そのため、発注書のような書類の作成が求められます。
下請法が適用される発注者には、次のような責任があります。
- 書類の交付
- 書類の作成と保存
- 下請け料金の支払い期限の設定
- 遅延利息の支払い
発注書・請求書の発行から入出金管理までカンタンに行うならINVOY
業務を行う上では、発注書や請求書といった書類を発行することが欠かせません。しかし、より重要度の高い業務に追われて、そのような書類に適切に対応する時間がないというケースも多いのではないでしょうか。
弊社のサービス「INVOY」は、発注書や請求書といった業務に欠かせない各種書類を無料で発行できる機能を備えています。この機会にぜひ利用方法をご検討ください。
無料会員登録はこちら
まとめ

注文書は、商品やサービスの発注を行う上で欠かせない書類です。本記事で紹介したテンプレートや書き方を参考に、取引内容にあわせた注文書を作成してみましょう。
また、注文書はすべての取引において必ず発行されるわけではなく、法律においても特に定められているわけではないため省略するケースもあります。
しかし、下請法が適用になる取引においては、親事業者から下請事業者へ発注内容を明確に記載した注文書・発注書などの書面を交付することが義務付けられており、保存方法についても、具体的な内容が定められています。最新の法律をチェックするとともに、法的に正しい処理を行うことを心がけましょう。








不動産売買の領収書テンプレートと正しい書き方|印紙税の判定か…
不動産売買における金銭トラブルを未然に防ぎ、税務署への申告をスムーズに進めるためには、正確な領収書の…