
「立替金」の処理を正しく理解すれば、面倒な経理作業がスムーズになり、税務調査で指摘されるリスクを回避できます。会社の資金繰りを改善し、安心して事業に集中できる未来を手に入れましょう。
この記事を最後まで読めば、あなたは「立替金」と「仮払金」などの紛らわしい勘定科目を明確に区別し、具体的な仕訳例に沿って正確に会計処理ができるようになります。さらに、インボイス制度や印紙税といった最新の税務ルールにも対応できるよう、専門家が実務レベルで解説します。
「経理は苦手」「細かいルールが多くて不安」と感じる方でも大丈夫です。本記事では、豊富な図解と具体的な事例を用いて、一つひとつのステップを丁寧に説明します。明日からすぐに使える知識と、誰でも実践できる管理フローを提供します。
目次
そもそも「立替金」とは?その本質を理解する
経理業務において頻繁に登場する「立替金」ですが、その本質を正確に理解することが、すべての処理の出発点となります。立替金は単なるお金の移動ではなく、会社の資産に関わる重要な会計処理です。
立替金の定義:一時的に会社が肩代わりするお金
立替金とは、従業員や取引先などが本来支払うべき金銭を、会社が一時的に肩代わりして支払った際に使用する勘定科目です。この定義には、支払いが「一時的」であることと、後日その金銭を相手から「回収する」ことという、2つの重要な前提があります。
この「後で回収できる権利」こそが立替金の本質です。そのため、会計上は将来的に会社にお金をもたらす「資産」として扱われます。具体的には、貸借対照表の「流動資産」の部に計上されます。
立替金は会社の経費ではなく、あくまで他者の債務を一時的に立て替えたことによって生じた、会社が持つ「債権(お金を受け取る権利)」なのです。この点を誤解すると、後の会計処理や税務判断で大きな間違いを犯す原因となります。
立替金が発生する具体的なケース
立替金は、社内の従業員や役員に対して発生することもあれば、社外の取引先に対して発生することもあります。具体的なケースを理解することで、実務での判断が容易になります。
従業員・役員への立替
会社が従業員や役員個人のために支払いを立て替えるケースです。
代表的な例として、従業員が休職などで給与の支払いがない期間に、会社がその従業員に代わって社会保険料を支払い、後日徴収する場合が挙げられます。
また、役員が個人的に参加するセミナーの費用や、従業員が負担すべき親睦会費などを会社が一括で支払った場合も立替金として扱います。従業員の希望に応じて給料日前に給与の一部を支払う、いわゆる給与の前貸しも、会計上は立替金として処理されることがあります。
取引先への立替
会社が取引先のために支払いを立て替えるケースです。
例えば、本来は取引先(買主)が負担すべき商品の配送料を、自社(売主)が運送会社に元払いで支払った場合がこれに該当します。
その他にも、取引において発生する手数料で、取引先が負担すべきものを自社で一時的に支払った場合や、取引先が支払う契約になっている材料費などを、便宜上自社で負担した場合などが考えられます。
これらの例に共通するのは、支払いの義務者が会社自身ではないという点です。この基本原則を常に念頭に置くことが、立替金処理の第一歩です。
もう迷わない!立替金と類似する勘定科目の明確な違い
経理の現場で最も混乱を招きやすいのが、「立替金」と「仮払金」「貸付金」「預り金」といった類似する勘定科目の使い分けです。これらの違いを明確に理解することは、正確な月次決算や税務申告に不可欠です。
立替金と仮払金の比較:金額確定の有無
立替金と仮払金の最も大きな違いは、支払時点で金額が確定しているかどうかです。
立替金は、支払うべき金額が「確定」した後に支払います。例えば、取引先が負担する送料3,000円が確定している場合に、それを支払うのが立替金です。
一方、仮払金は、支払う目的は決まっているものの、最終的な金額が「未確定」の段階で、概算の金額を事前に支払う場合に使用します。例えば、従業員の出張に際して、交通費や宿泊費として5万円を事前に渡しておくケースがこれに該当します。
もう一つの重要な違いは、会社の経費になるかどうかです。仮払金は、出張旅費や交際費など、最終的に会社の経費として精算されることを見越した支払いですが、立替金はそもそも他者が負担すべき支払いなので、会社の経費にはなりません。
立替金と貸付金の比較:契約・利息の有無
立替金と貸付金の違いは、返済に関する契約や利息の有無にあります。
貸付金は、金銭消費貸借契約書などを交わし、返済期日や利息を定めて金銭を貸し付ける場合に使用します。返済期間が1年以内なら「短期貸付金」、1年を超える場合は「長期貸付金」となります。
対照的に立替金は、あくまで一時的な肩代わりであり、通常は契約書を交わさず、利息も発生しません。短期間での回収が前提です。
ただし、注意点として、立替金の回収が長期化した場合、税務調査で実質的な貸付金と見なされるリスクがあります。その場合、会社が受け取るべき利息(受取利息)が認定され、追徴課税の対象となる可能性があるため、立替金の長期滞留は避けなければなりません。
立替金と預り金の比較:資金の流れの違い
立替金と預り金は、お金の動きが正反対です。
立替金は、「会社の資金」で先に支払い、後で回収します。お金が出てから入る流れのため、資産(債権)として扱われます。
預り金は、従業員や取引先から「本人のお金」を先に預かり、会社が本人に代わって第三者に支払います。お金が入ってから出る流れです。例えば、給与から天引きする源泉所得税や社会保険料が代表例で、これらは最終的に支払う義務があるため、負債として扱われます。
この4つの勘定科目の違いを、以下の表にまとめました。この表を参考にすれば、実務で迷うことは格段に減るでしょう。
| 勘定科目 | 目的・内容 | 金額確定のタイミング | 会社の経費性 | 資産/負債 | 具体例 |
| 立替金 | 本来他者が負担すべき費用の肩代わり | 支払時に確定 | 経費ではない | 資産 | 取引先の送料を元払いで支払った |
| 仮払金 | 用途・金額が未確定な費用の概算払い | 支払時に未確定 | 経費になる | 資産 | 従業員の出張費を事前に概算で渡した |
| 貸付金 | 契約に基づく金銭の貸与 | 貸付時に確定 | 経費ではない | 資産 | 従業員や子会社に資金を融資した |
| 預り金 | 本人に代わって支払うための一時預かり | 預かる時点で確定 | 経費ではない | 負債 | 給与から源泉所得税を天引きした |
【基本】立替金の仕訳方法を具体例で解説
立替金の概念を理解したら、次は具体的な仕訳方法を学びます。仕訳は「支払時」と「回収時」の2つのタイミングで発生します。それぞれのケースを例に沿って見ていきましょう。
立替金を支払った時の仕訳
会社が従業員や取引先のために金銭を立て替えて支払った際には、借方(左側)に資産の増加として「立替金」を、貸方(右側)に支払手段の減少として「現金」や「普通預金」を記入します。
【例1】取引先が負担すべき送料5,000円を、現金で立て替えて支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
| 立替金 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 | A社分 送料立替 |
この仕訳により、会社の現金は5,000円減少しましたが、同額の「立替金」という資産(債権)が増加したことが記録されます。
立替金を回収した時の仕訳(消込処理)
立て替えていた金銭を相手から回収した際には、支払時とは逆の仕訳を行い、立替金勘定をゼロにする「消込処理」を行います。
【例2】上記で立て替えていた送料5,000円が、取引先の普通預金口座から振り込まれた。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
| 普通預金 | 5,000円 | 立替金 | 5,000円 | A社分 送料回収 |
この仕訳により、普通預金が5,000円増加し、資産として計上されていた「立替金」が同額減少します。これで一連の取引は完了です。
給与から天引きで回収する場合の特殊な仕訳
従業員への立替金を、翌月の給与から天引きして回収するケースは実務でよく見られます。この場合の仕訳は少し複雑になります。
【例3】従業員に給与の前貸しとして10万円を立て替えていた。翌月、この従業員の総支給額30万円の給与から、立替金10万円を天引きし、差額の20万円を普通預金から振り込んだ。
この場合、給与支払日に以下の仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
| 給料 | 300,000円 | 立替金 | 100,000円 | 給与支払、前貸し分回収 |
| 普通預金 | 200,000円 |
借方には、費用として発生した給料の総額30万円を計上します。貸方には、回収した立替金10万円と、実際に支払った差額の普通預金20万円を計上することで、貸借の金額が一致します。
なお、労働基準法上、給与からの天引き(控除)は、原則として労使協定を結ぶか、本人の個別の同意がなければ行うことができません。トラブルを避けるためにも、必ず書面で従業員の同意を得てから処理するようにしましょう。
立替金に関する税務上の注意点(消費税・印紙税)
立替金の処理で特に注意が必要なのが税務の扱いです。消費税や印紙税のルールを正しく理解していないと、思わぬ追徴課税を受ける可能性があります。2023年10月から始まったインボイス制度も、立替金の実務に大きな影響を与えています。
立替金と消費税の原則:不課税取引
立替金の支払いと回収は、単なる金銭の移動であり、商品の販売やサービスの提供といった「取引」には該当しません。そのため、原則として消費税の不課税取引となり、消費税はかかりません。仕訳の際には、税区分を「対象外」や「不課税」として処理します。
消費税の課税対象となる危険なケース
原則は不課税ですが、請求書の書き方などを誤ると、立替金が売上の一部と見なされ、消費税の課税対象となってしまう危険なケースがあります。
例えば、立て替えた実費に、手数料などの名目でマージン(利益)を上乗せして請求すると、その全額が課税対象となります。
また、自社のサービス料金と立替金を合算して請求したり、請求書上で立替金であることを明記しなかったりすると、合計金額がサービスの対価と見なされ、課税売上になってしまう可能性があります。このような事態を避けるため、請求書では自社の請求額と立替金部分を明確に分けて記載することが鉄則です。
インボイス制度下での立替金精算と仕入税額控除
インボイス制度の開始により、立替金の精算プロセスはより厳格になりました。特に、立て替えてもらった側(本来の支払者)が消費税の仕入税額控除を受けるためには、適切な書類のやり取りが不可欠です。
このプロセスは、立替払いをした会社(B社)が、本来支払うべき会社(A社)に代わって、取引先(C社)に支払いを行うという3社間の関係で成り立っています。A社が仕入税額控除を受けるための流れは以下の通りです。
- C社は、支払いを受けたB社に対して、B社宛のインボイス(適格請求書)を発行します。
- B社は、A社に立替金を請求する際、C社から受け取ったインボイスのコピーと、B社が作成した「立替金精算書」をセットでA社に渡します。
- A社は、この「インボイスのコピー」と「立替金精算書」の両方を保存することで、初めて仕入税額控除の適用を受けることができます。
この仕組みの本質は、税務上の取引の連鎖を書類で証明することにあります。B社がこの手続きを怠ると、A社は仕入税額控除を受けられず、税負担が増えることになります。これは取引先との信頼関係を損なう大きなリスクです。立替金の処理は、単なる社内経理の問題ではなく、取引先との関係性にも影響する重要な業務となったのです。
立替金の領収書と収入印紙の要否
立替金を回収した際に発行する領収書には、印紙税法に基づく収入印紙が必要になる場合があります。
立替金の回収は「売上代金以外の金銭の受取書」(第17号の2文書)に該当するため、受取金額が5万円以上の場合は、200円の収入印紙を貼付する必要があります。5万円未満の場合は非課税となり、印紙は不要です。
ここで実務上、非常に重要な例外があります。それは「相殺」の場合です。自社と相手方の双方に債権・債務があり、それらを相殺処理した場合、その旨を領収書の但し書きに「上記金額を売掛金と相殺しました」などと明記すれば、金額にかかわらず収入印紙は不要になります。
これは、現金の受領が伴わないためです。このルールを知っているだけで、無駄なコストを削減できます。
実践的な立替金の管理と精算業務フロー
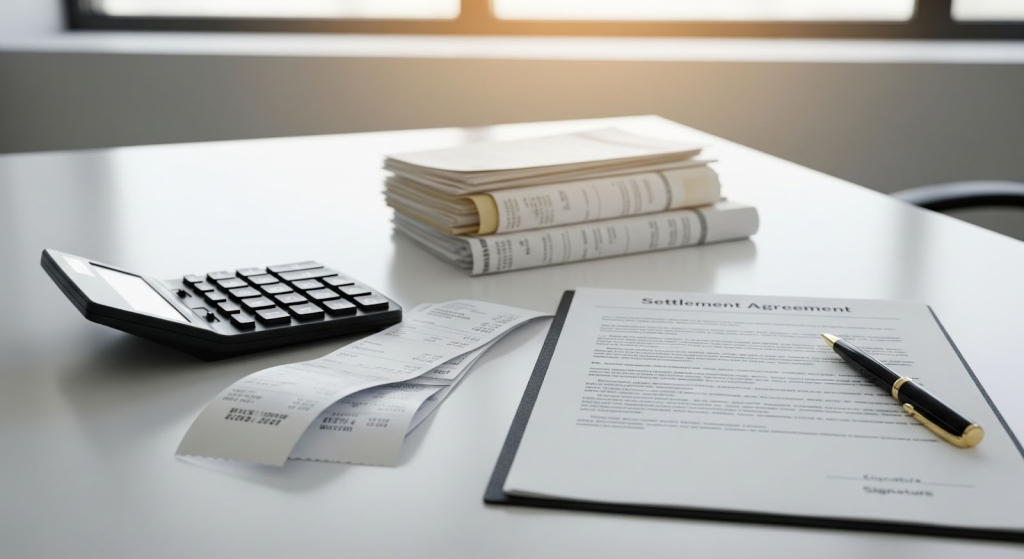
立替金に関するトラブルやリスクを未然に防ぐためには、社内で明確な管理・精算フローを確立することが不可欠です。ここでは、従業員の経費立替と、取引先への立替金請求という2つの場面における実践的なフローを解説します。
従業員の経費立替(実費精算)のフローと注意点
従業員が業務に必要な費用を一時的に立て替える「経費精算」は、多くの企業で日常的に発生します。スムーズで正確な処理を行うための一般的なフローは以下の通りです。
- 立替発生と領収書受領
従業員が交通費や消耗品費などを立て替え、必ず領収書を受け取ります。 - 精算申請
従業員は、会社の規定フォーマットである「経費精算書」に必要事項を記入し、領収書を添付して上長に提出します。 - 承認
上長は、申請内容が業務上適切であるか、金額に誤りがないかなどを確認し、承認します。 - 経理処理と支払
承認された申請書は経理部門に回付され、経理担当者が内容を最終確認して仕訳処理を行います。その後、給与振込と同時になど、定められた期日に従業員へ精算金が支払われます。
このフローを円滑に運用するための注意点として、まず精算期限の設定が挙げられます。「毎月末日まで」「発生から5営業日以内」など、社内規程で明確な精算期限を設け、従業員に周知徹底します。これにより、精算漏れや経理部門の業務集中を防ぎます。
また、2024年1月から本格施行された改正電子帳簿保存法への対応も重要です。電子メールなどで受け取った領収書データは、紙に出力せずデータのまま保存することが義務付けられました。また、紙の領収書もスキャンして電子保存が可能です。これらに対応した精算フローの見直しが必要になります。
取引先への立替金を請求・回収するフロー
取引先のために立て替えた費用を請求する際は、誤解やトラブルを生まないよう、明確で丁寧な手続きが求められます。
まず、立替金が発生したら、速やかに請求書類を作成します。自社のサービス料などと合算する場合は、請求書内で立替金部分を明確に区分します。立替金のみを請求する場合は「立替金支払依頼書」などの表題で作成すると分かりやすいでしょう。
請求書には、書類発行日、請求番号、請求先の会社名、発行者の情報、立替金の明細(日付、内容、金額)、請求合計額、支払期日、振込先口座情報などを正確に記載します。前述のインボイス制度の要件を満たすため、立て替えた際に受け取ったインボイスのコピーを必ず添付することも忘れてはいけません。
作成した請求書を送付し、支払期日までに入金があったかを確認します。期日を過ぎても入金がない場合は、速やかに次のステップに進む必要があります。このフローを徹底することで、回収の遅延を防ぎ、消費税の課税リスクを回避することにつながります。
立替金の回収遅延リスクと法的対応

立替金は会社の資産ですが、回収できなければ損失に変わります。回収遅延は、単なる入金遅れ以上の経営リスクをはらんでおり、放置は禁物です。
立替金の長期未回収がもたらす3つの経営リスク
立替金の長期未回収は、まず資金繰りの悪化を招きます。未回収の立替金は、会社の運転資金を圧迫し、事実上、無利子で資金を貸し出しているのと同じ状態です。この状態が積み重なると黒字倒産の一因にもなり得ます。
次に、税務リスクが挙げられます。回収までに数年かかるなど長期にわたって放置された立替金は、税務調査で「貸付金」と認定される可能性があります。その場合、本来受け取るべきであった利息(認定利息)が収益として計上され、法人税の追徴課税を受けるリスクが生じます。
最後に、貸倒リスクです。回収が遅れれば遅れるほど、取引先の経営状況が悪化するなどして、最終的に回収不能(貸倒れ)になる可能性が高まります。
取引先から立替金が回収できない場合の対応ステップ
立替金の回収が遅れた場合は、段階的に、しかし毅然と対応を進めることが重要です。
初期対応として、まず自社が送付した請求書に誤りがなかったかを確認します。その上で、先方の担当者に電話やメールで連絡を取り、支払いが遅れている理由と、具体的な入金予定日を確認します。単なる失念や事務処理の遅れであることも多いため、最初は丁寧な口調で確認するのが基本です。
連絡をしても支払いに応じてもらえない場合は、催促の段階に進みます。督促状を作成し、送付します。配達証明付きの内容証明郵便を利用すれば、「請求した」という事実を法的に証明できるため、相手に心理的なプレッシャーを与え、後の法的手続きでも有利な証拠となります。
それでも回収できない場合は、弁護士などの専門家に相談の上、法的措置を検討します。主な手段としては、比較的簡易な手続きである「支払督促」、裁判所での話し合いによる解決を目指す「民事調停」、そして最終手段である「訴訟(裁判)」があります。
立替金回収の権利と「消滅時効」
立替金を回収する権利(債権)には、法律で定められた「消滅時効」が存在します。この時効が完成すると、たとえ相手に支払い義務があっても、法的に請求する権利を失ってしまいます。
2020年4月1日に施行された改正民法により、消滅時効のルールが大きく変わりました。複雑だった職業別の短期時効は廃止され、原則として以下のルールに統一されています。
- 債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間
- 権利を行使できる時(客観的起算点)から10年間
このうち、いずれか早い方が到来した時点で時効が完成します。立替金の場合、会社が支払いを立て替えた瞬間に「相手に請求できる権利がある」ことを認識するため、実質的には「立て替えた時から5年」が時効期間と考えられます。この新しいルールは、企業に対して、債権管理をより一層迅速かつ厳格に行うことを求めているのです。
従業員との立替金トラブルを防ぐための法的知識
立替金は、取引先だけでなく、従業員との間でも発生します。ここでは、労働法規の観点から、従業員との立替金トラブルを未然に防ぐための知識を解説します。
従業員への経費立替の適法性
業務に必要な経費を従業員に立て替えさせること自体は、直ちに違法となるわけではありません。多くの企業で、交通費や少額の備品購入費などの立替払いは一般的に行われています。
ただし、出張費などで立替額が高額になったり、立替の頻度が高かったりすると、従業員の経済的負担が過大になる可能性があります。企業としては、従業員の負担を軽減する配慮が求められます。具体的な対策として、法人向けクレジットカードを従業員に貸与する方法や、事前に概算額を支給する「仮払金」制度を活用する方法が有効です。
給与からの天引きと労働基準法
従業員への立替金を給与から天引きして回収する際は、特に注意が必要です。労働基準法第24条は「賃金全額払いの原則」を定めており、会社が一方的に給与から天引きすることは原則として禁止されています。
例外的に天引きが認められるのは、法令(所得税や社会保険料など)に基づく場合か、「労使協定」を締結している場合に限られます。
労使協定がない場合でも、その従業員本人から自由な意思に基づく個別の同意を書面で得ていれば、天引きは可能と解されています。口約束での同意は後のトラブルの原因となるため、必ず書面で合意を残しておくことが、法的なリスクを回避する上で極めて重要です。
会社の倒産と未払賃金立替払制度
万が一、会社が倒産してしまい、従業員への給与や経費精算金の支払いができなくなった場合、従業員を保護するための国の制度があります。それが「未払賃金立替払制度」です。
この制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が、倒産した企業に代わって、未払賃金の一部を労働者に支払うものです。対象となるのは主に定期給与や退職金ですが、このようなセーフティネットが存在することを知っておくことも、従業員との信頼関係を考える上で有益な知識と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、「立替金」という一つの勘定科目を軸に、その定義から仕訳、税務、法務、リスク管理に至るまで、多角的に解説しました。最後に、実務で絶対に押さえておくべき要点を再確認します。
立替金の本質は、一時的な「肩代わり」であり、会社の資産(債権)です。会社の経費とは全く性質が異なります。
類似科目との違いは、「仮払金」とは金額の確定度で、「貸付金」とは契約や利息の有無で、「預り金」とはお金の流れの方向で明確に区別します。
税務上、原則は消費税不課税ですが、請求方法を誤ると課税対象になります。インボイス制度下では「立替金精算書」と元インボイスのセットが必須です。また、5万円以上の回収時に発行する領収書には収入印紙が必要です。
最大のリスクは長期未回収です。会社の資金繰りを圧迫するだけでなく、税務調査で「貸付金」と認定され追徴課税を招く可能性があります。
管理の鉄則は、社内ルールを整備し、立替金が発生したら迅速に処理・回収することです。これが、会計・税務・法務すべてのリスクを回避する最善かつ唯一の策です。
立替金の正確な管理は、単なる経理作業の効率化にとどまりません。それは、会社の資金を守り、税務上のリスクを回避し、取引先や従業員との信頼関係を維持するための、攻めと守りを兼ね備えた重要な経営管理活動なのです。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…