
「大切な取引先に送った納品書の金額が間違っていた」「月末の処理直前に、お客様から納品書をなくしたと連絡があった」。ビジネスの現場では、このような予期せぬ事態が起こりがちです。
納品書の再発行は、些細なようでいて、対応を一つ間違えれば取引先との信頼関係にひびが入りかねない、デリケートな業務といえるでしょう。焦りや不安を感じるのも無理はありません。
しかし、納品書の再発行は、正しい手順と知識さえあれば、決して難しいことではありません。むしろ、迅速で丁寧な対応は、トラブルを解決するだけでなく、かえって自社の信頼性を高めるチャンスにもなり得ます。
この記事では、納品書の再発行が必要になったときに、あなたが自信を持って的確に行動できるよう、そのすべてを網羅したロードマップを提供します。
この記事を最後まで読めば、あなたは納品書の再発行に関するあらゆる場面で、迷わず最適な判断を下せるようになります。依頼する側・される側、双方の立場から具体的な手順を学び、そのまま使えるメール文例を手にすることで、今日からすぐに実務に活かせます。
さらに、電子帳簿保存法やインボイス制度といった最新の法制度への対応方法まで理解し、将来の経理リスクを未然に防ぐ知識が身につきます。
ここで解説するのは、専門家だけが知る特別なノウハウではありません。一つひとつのステップは、あなたの実務に寄り添った、再現性の高いものばかりです。
チェックリストや早見表を活用すれば、誰でもミスなく、安心して納品書の再発行業務を進めることができます。さあ、もう慌てるのはやめましょう。この記事を手に、どんな状況でも冷静沈着に対応できる、頼れるビジネスパーソンへの第一歩を踏み出してください。
目次
納品書再発行の基本 応じる義務はあるのか?
納品書の再発行を依頼されたとき、または依頼しなければならなくなったとき、まず頭に浮かぶのは「そもそも再発行は可能なのか?」「発行側に応じる義務はあるのか?」という疑問ではないでしょうか。
この基本的な問いへの理解が、すべての対応の出発点となります。結論からいえば、再発行は可能ですが、そこには法律上の「義務」とビジネス上の「慣習」という、二つの側面が存在します。
納品書の役割と法的効力
納品書とは、商品やサービスを納品した際に、その事実と内容を証明するために発行される書類です。具体的には、「いつ、誰が、誰に、何を、どれだけ納品したか」を明確にする役割を担います。
この書類は、取引の事実を証明する「証憑(しょうひょう)書類」の一種とされ、取引の透明性を確保し、後の請求業務や検収作業をスムーズにするために非常に重要です。
しかし、ここで最も重要な点は、納品書の発行自体が法律で義務付けられているわけではない、ということです。請求書や領収書とは異なり、あくまで取引を円滑に進めるためのツールとして、商慣習にもとづき発行されているのが実情です。
再発行は「義務」ではなく「商慣習」
納品書の発行が法的な義務ではない以上、その再発行にも法的な義務は存在しません。つまり、取引先から再発行を依頼されたとしても、法律上はそれに応じる必要はないのです。
しかし、ビジネスは法律だけで成り立っているわけではありません。現実の取引においては、再発行に応じることが一般的です。これは、法律を超えた「取引先への配慮・思いやり」という、日本の商慣習に深く根ざしています。
もし合理的な理由があるにもかかわらず再発行を拒否すれば、取引先との良好な関係を損ない、将来のビジネスチャンスを失うことにもつながりかねません。
この「義務ではないが、応じるのが通例」という点を理解することが、再発行業務の核心です。法的な義務がないからこそ、その対応の仕方、つまりスピードや丁寧さが、企業の姿勢を映す鏡となります。依頼を面倒な業務と捉えるのではなく、取引先との信頼関係を維持・強化するための重要なコミュニケーション機会と考えるべきでしょう。
再発行が必要になる主なケース
では、具体的にどのような場面で納品書の再発行が必要になるのでしょうか。主なケースは、以下の二つに大別されます。
一つ目は、受領側の紛失・破損です。納品を受け取った側の担当者が、書類を誤って紛失してしまったり、コーヒーをこぼすなどして破損させてしまったりするケースです。これは、再発行依頼の最も一般的な理由の一つです。受領側は、社内での検品作業や経費精算、そして後述する法律で定められた保管義務を果たすために、納品書を必要とします。
二つ目は、発行側の記載ミスです。発行した納品書に、品名、数量、単価、日付などの誤りがあった場合です。これは発行側の責任であるため、判明した時点、あるいは取引先から指摘を受けた時点ですみやかに謝罪し、正しい内容の納品書を再発行する必要があります。誤った情報のままでは、在庫管理のズレや請求金額の間違いなど、より大きなトラブルに発展する可能性があるため、迅速な対応が不可欠です。
どちらのケースであっても、再発行という行為は取引の記録を正確に残すために必要不可欠なプロセスです。次の章では、これらのケース別に、具体的な実務手順を詳しく解説していきます。
ケース別 納品書再発行の実務マニュアル
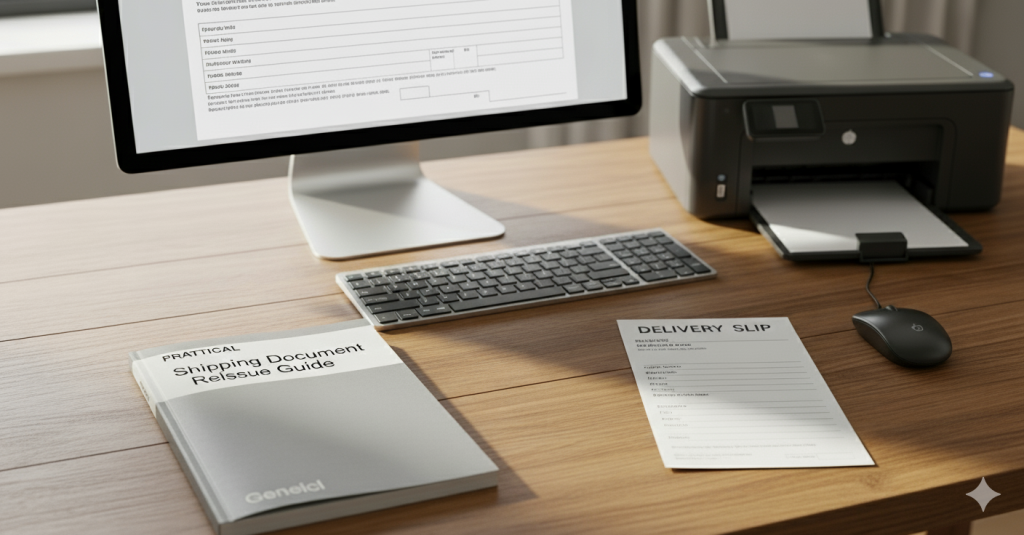
納品書の再発行は、依頼する側と発行する側、それぞれの立場で適切な手順を踏むことが、スムーズな問題解決と信頼関係の維持につながります。ここでは、具体的なステップとそのまま使えるメール文例を交えながら、実務的なマニュアルを解説します。
依頼する側の対応 丁寧かつ明確な依頼方法
自社の都合(紛失・破損)や相手のミスを発見した際に、再発行を依頼する立場になった場合の対応です。重要なのは、丁寧な姿勢を保ちつつ、必要な情報を明確に伝えることです。
事実確認と迅速な連絡
依頼する前に、まずは事実を正確に確認しましょう。紛失の場合は、本当に見当たらないか、再度デスク周りや関連部署に確認します。安易な依頼は相手に手間をかけさせてしまいます。
記載ミスを発見した場合は、どの項目がどのように間違っているのか(例:「商品Aの数量が10個と記載されていますが、正しくは12個です」)、元の注文書などと照らし合わせて具体的に特定します。
事実確認ができたら、できるだけ早く相手先の担当者に連絡を入れます。時間が経つほど、相手も対応が難しくなる可能性があります。
依頼メールの作成
電話で一報を入れた後、記録に残るメールで正式に依頼するのが確実です。状況に応じた文例を参考に、丁寧な依頼メールを作成しましょう。
文例1:自社の都合(紛失・破損)で依頼する場合
件名:納品書再発行のお願い(株式会社〇〇)
株式会社△△
経理部 △△様
いつも大変お世話になっております。
株式会社〇〇の〇〇です。
先日お送りいただきました下記納品書につきまして、誠に申し訳ございませんが、弊社の不手際により紛失(または破損)してしまいました。
納品日:20XX年〇月〇日
納品書番号:No.12345
件名:〇〇の納品
大変恐縮ではございますが、こちらの納品書を再発行いただくことは可能でしょうか。
弊社の都合でご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご検討いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
(署名)
文例2:相手の記載ミスにより依頼する場合
件名:納品書の記載内容ご確認のお願い(株式会社〇〇)
株式会社△△
営業部 △△様
いつも大変お世話になっております。
株式会社〇〇の〇〇です。
先日受領いたしました下記納品書につきまして、一点ご確認させていただきたく、ご連絡いたしました。
納品日:20XX年〇月〇日
納品書番号:No.12345
件名:〇〇の納品
納品書に記載の金額が「〇〇円」となっておりましたが、弊社で保管しております見積書の金額「△△円」と相違があるようです。
お手数をおかけいたしますが、内容をご確認いただき、もし相違がございましたら、正しい納品書を再発行いただけますでしょうか。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
(署名)
再発行された納品書の確認
再発行された納品書を受け取ったら、すぐに内容を確認します。依頼した修正が正しく反映されているか、後述する「再発行」の旨が明記されているかなどをチェックします。問題がなければ、お礼の連絡を入れるとより丁寧な印象になります。
発行する側の対応 信頼を損なわない迅速で正確な処理
取引先から再発行の依頼を受けた側の対応です。迅速かつ正確な処理が、信頼を維持するための鍵となります。特に自社のミスが原因の場合は、誠意ある対応が求められます。
依頼内容の確認と謝罪
まずは依頼内容を正確に把握します。どの納品書について、どのような理由で再発行が必要なのかを確認しましょう。自社の記載ミスが原因の場合は、何よりも先に真摯に謝罪します。電話で直接お詫びを伝え、メールでも改めて謝罪の意を示すのが丁寧な対応です。
元の納品書データの特定
依頼された納品書の元データや控えを探します。日頃から書類管理が整理されているかどうかが、この段階のスピードを左右します。電子データで管理していれば、検索機能ですぐに特定できるでしょう。
再発行版の作成と注意点
元のデータを基に、再発行する納品書を作成します。このとき、後の経理トラブルを防ぐために、絶対に守るべきルールがあります。安易に元の書類をコピーして送付するだけでは、二重計上などの重大なリスクを生む原因となります。
まず、「再発行」と明確に記載することが重要です。元の納品書と区別するため、書類の目立つ場所に「再発行」と明記します。赤いスタンプを押すのが一般的ですが、テキストで大きく記載しても構いません。これにより、受け取った側が誤って二重に処理することを防ぎます。
次に、日付や管理番号は変更しません。納品日や納品書番号は、最初に発行したものと全く同じものを記載します。日付を再発行日に変更してしまうと、別の取引として扱われ、経理上の混乱を招く恐れがあります。あくまで「あの取引の書類を再発行した」という事実を明確にするため、情報はすべて元のものと一致させます。
また、社内管理上、再発行した事実を明確にするために、納品書番号に「-2」や「-R」といった枝番を付ける方法も有効です。これにより、社内の経理システム上でも元の伝票と区別しやすくなります。
送付状を添えて送付
再発行した納品書を送付する際は、送付状や案内メールを添えるのがビジネスマナーです。特に自社のミスでお詫びする場合には、改めて謝罪の言葉と、今後の再発防止策などを簡潔に記載すると、誠意が伝わります。また、元の納品書が見つかった場合に備え、破棄をお願いする一文を添えることも重要です。
文例:自社の記載ミスを謝罪し、再発行版を送付する場合
件名:【お詫び】納品書(No.12345)の再発行につきまして
株式会社〇〇
経理部 〇〇様
いつも大変お世話になっております。
株式会社△△の△△です。
先日は、弊社が発行いたしました納品書(No.12345)の記載内容に誤りがありましたこと、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘いただきました内容を修正し、正しい納品書を再発行いたしましたので、本日、速達にて発送いたしました。(メール送付の場合は「本メールに添付いたしました」)
大変お手数をおかけいたしますが、お手元にございます古い納品書は破棄していただき、こちらの再発行版と差し替えていただけますようお願い申し上げます。
今後は、チェック体制を強化し、再発防止に努めてまいる所存です。
この度の不手際、何卒ご容赦いただけますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
(署名)
これらの手順とポイントを押さえることで、納品書の再発行というイレギュラーな業務を、トラブルなく、かつプロフェッショナルに対応することができます。
最大のリスク「二重計上」を防ぐための鉄則
納品書の再発行業務において、最も警戒すべきリスクが「二重計上」です。これは、一つの取引が誤って二回計上されてしまう経理上のミスであり、自社だけでなく取引先にも多大な迷惑をかけ、企業の信用を大きく損なう可能性があります。このリスクは、発行側と受領側の双方に潜んでいます。
ここでは、二重計上がなぜ起こるのかを理解し、それを防ぐための具体的な「鉄則」を解説します。
なぜ二重計上が起こるのか?
二重計上の典型的なシナリオは、非常にシンプルです。取引先が納品書を紛失したために再発行を依頼し、発行側がそれに応じて「再発行」と明記した納品書を送付します。
その後、取引先が紛失したと思っていた元の納品書を発見し、経理担当者が元の納品書と再発行された納品書の両方を処理してしまうことで、同じ取引に対して二重に支払いや仕入計上が行われてしまいます。
この問題は、単に書類が2枚存在することから生じます。特に、再発行された納品書に「再発行」の明記がない場合や、経理担当者が見落としてしまった場合に発生しやすくなります。発行側においても、再発行の控えと元の控えを別々に管理してしまうと、売上を二重に計上してしまうリスクがあります。
このミスは、単なる経理上の誤りにとどまりません。取引先にとっては過払いとなり、返金手続きなどの余計な手間を発生させます。自社にとっては、売掛金の管理が混乱し、決算数値の信頼性が揺らぐことになります。こうした事態を避けるため、再発行時には細心の注意を払う必要があります。
発行側・受領側双方の具体的な防止策
二重計上の防止は、発行側と受領側の共同責任ともいえます。発行側は「誤解の余地がない書類」を作成する責任があり、受領側は「書類を正しく識別し処理する」責任があります。以下に、双方で実践すべき具体的な防止策を挙げます。
徹底したナンバリング管理
請求書や納品書には、必ず一意の管理番号(ナンバリング)を割り振ることが基本です。会計システム上で同じ番号が入力された際に警告が出るように設定しておけば、機械的に重複を防ぐことができます。再発行の際には、前述の通り元の番号を変更せず、社内管理用に枝番(例:T001-2)を付与するルールを設けることで、追跡が容易になります。
「再発行」の可視化
これが最もシンプルかつ効果的な方法です。再発行する納品書には、誰が見ても一目でわかるように「再発行」というスタンプを押すか、文字を大きく印刷します。この視覚的なサインがあるだけで、経理担当者が誤って処理するリスクを劇的に減らすことができます。これは、発行側が講じるべき最低限の防御策です。
ダブルチェック体制の構築
ヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。そのため、複数人によるチェック体制を導入することが有効です。発行側では、再発行した納品書を送付する前に、別の担当者が「再発行の明記」「日付・番号の一致」などをチェックします。
受領側では、月次の売掛金・買掛金の残高照合の際に、取引先ごとに請求内容を精査し、不審な点がないかを確認します。このような定期的なチェックを業務フローに組み込むことで、ミスを早期に発見できます。
元の伝票の破棄依頼
再発行した納品書を送付する際には、送付状やメールに「万が一、元の納品書が見つかりました際には、お手数ですが破棄していただきますようお願い申し上げます」という一文を必ず添えましょう。これは単なる丁寧な表現ではなく、受領側に対して明確な処理方法を指示し、二重処理のリスクを減らすための重要なコミュニケーションです。
請求書発行システムの活用
手作業での書類作成や管理は、どうしてもミスの温床になりがちです。現代の請求書発行システムや会計システムの多くは、二重計上を防止するための機能が標準で備わっています。
文書番号の自動採番と重複チェック機能、発行・再発行の履歴管理機能、会計システムとの連携による消込作業の自動化などがその例です。これらのシステムを導入することは、単なる効率化だけでなく、経理業務の正確性を担保し、リスクを根本から断ち切るための強力な手段となります。
これらの鉄則を社内でルール化し、徹底することで、納品書の再発行に伴う二重計上リスクを最小限に抑え、健全な取引関係を維持することが可能になります。
納品書再発行に関わる法律と制度
納品書の再発行は、単なる事務手続きではありません。その背景には、企業が遵守すべき法律や制度が存在します。特に、書類の保管義務、そして近年大きく変化した電子帳簿保存法とインボイス制度への対応は、すべての事業者にとって避けては通れない課題です。ここでは、これらの法律や制度が納品書の再発行にどう関わってくるのかを解説します。
納品書の保管義務と保管期間
納品書の発行自体は任意ですが、一度発行または受領した納品書は、法律で定められた期間、適切に保管する義務があります。これは、納品書が税務調査などで取引の証拠として扱われる「国税関係書類」に該当するためです。保管期間は、法人と個人事業主で異なります。
法人の場合
- 原則期間: 7年間
- 例外: 青色申告法人で欠損金(赤字)が生じた事業年度は10年間
- 起算日: その事業年度の確定申告提出期限の翌日から
個人事業主の場合
- 原則期間: 5年間
- 例外: 消費税の課税事業者またはインボイス発行事業者の場合は7年間
- 起算日: その年の確定申告提出期限の翌日から
重要なのは、保管期間のカウントが「納品書の発行日」からではない点です。確定申告の提出期限の翌日からカウントが始まることを覚えておきましょう。万が一、保管期間中に納品書を紛失してしまった場合は、税務調査で経費が認められないなどの不利益を被る可能性があります。だからこそ、紛失した際には再発行を依頼することが重要になるのです。
電子帳簿保存法への対応は必須
経理業務のデジタル化を背景に、電子帳簿保存法が大きく改正され、2024年1月1日からその対応が本格的に義務化されました。この法律は、納品書の扱いに大きな影響を与えます。最大のポイントは、電子データで受け取った取引書類は、電子データのまま保存しなければならないというルールです。
具体的には、取引先からメールに添付されたPDFの納品書や、クラウドサービス経由でダウンロードした納品書などが該当します。以前のように、これらの電子データを印刷して紙で保管する方法は、原則として認められなくなりました。
これは、納品書の再発行においても同様です。再発行を依頼され、PDFをメールで送付した場合、発行側はその送信データを、受領側はその受信データを、それぞれ電子データのまま法律の要件(検索機能の確保など)を満たして保存する必要があります。この変更は、すべての事業者にとって、書類管理のあり方を根本から見直すきっかけとなります。
インボイス制度導入後の注意点
2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)も、納品書の扱いに影響を与えます。通常、納品書はインボイス(適格請求書)そのものではありません。しかし、納品書にインボイスとして必要な記載事項(登録番号、適用税率、消費税額など)がすべて含まれていれば、納品書をインボイスとして扱うことも可能です。
インボイス制度下で特に注意が必要なのは、記載内容に誤りがあった場合の訂正方法です。もし、インボイスの要件を満たす納品書の内容に誤りがあった場合、発行事業者は「修正インボイス(修正した適格請求書)」を交付する義務があります。このとき、再発行した納品書は、修正インボイスの根拠となる重要な補足資料となります。
重要なのは、インボイスの修正は、発行事業者(売り手)側で行わなければならないという点です。受領側(買い手)が勝手に書類を修正することは認められていません。
このため、発行側は記載ミスの指摘を受けたら、より一層迅速かつ正確に修正対応を行う責任があります。これらの法律や制度の本質は「取引の記録を正確に、かつ検証可能な形で長期間保存すること」にあります。
未来のトラブルを防ぐ 納品書業務の電子化と効率化

これまで、納品書の再発行という「起きてしまった問題」への対処法を中心に解説してきました。しかし、最も理想的なのは、そもそも再発行の必要がない状態、つまりトラブルを未然に防ぐことです。そのための最も強力な解決策が、経理業務全体の電子化と効率化です。
紙ベースの管理が抱える根本的な問題
多くの企業でいまだに行われている紙ベースでの書類管理は、数々の根本的な問題を抱えています。これらは、再発行トラブルの直接的・間接的な原因となっています。物理的な紛失・破損リスクは常に存在し、法律で定められた長期間の保管には物理的なスペースとコストがかかります。
また、過去の書類を探し出す際の検索性の低さは時間の浪費につながり、書類がオフィスにしか存在しないためリモートワークへの対応も困難です。これらの問題は、業務の非効率を生み、ヒューマンエラーを誘発する土壌となっています。
請求書発行システムの導入メリット
これらの課題を根本的に解決するのが、請求書発行システムやクラウド会計システムの導入です。システムを活用することで、納品書業務は劇的に変わります。見積書や受注データから納品書を自動作成する機能を使えば、手入力による記載ミスを大幅に削減できます。
万が一再発行が必要になっても、システム上では数クリックで完了し、手作業で発生しがちなミスを防ぎ、迅速な対応が可能になります。信頼できるシステムの多くは、電子帳簿保存法やインボイス制度の最新要件に準拠しており、システムを利用するだけでコンプライアンス負担を軽減できます。
すべての書類が検索可能な状態でクラウド上に一元管理されるため、紛失リスクはゼロになり、いつでもどこでも必要な情報にアクセスできます。請求書発行システムの導入は、単なる「コスト」ではなく、将来のリスクを削減し、生産性を向上させるための「投資」です。納品書の再発行という一つの問題をきっかけに、自社の業務プロセス全体を見直してみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、納品書の再発行に関するあらゆる側面を、基本から応用まで網羅的に解説しました。最後に、明日からの実務で自信を持って行動できるよう、最も重要なポイントを再確認しましょう。
納品書の再発行に法的な義務はありませんが、良好な取引関係を維持するための重要な商慣習です。依頼された場合は、企業の信頼性を示す機会と捉え、迅速かつプロフェッショナルに対応しましょう。依頼する側は丁寧な言葉遣いで必要な情報を明確に伝え、発行する側は迅速・正確を心がけ、自社に非がある場合は真摯な謝罪が大切です。
再発行における最大のリスク「二重計上」を防ぐため、「再発行」の明記、日付と番号の維持、そして元の伝票の破棄依頼を徹底してください。また、納品書には保管義務があり、電子帳簿保存法により電子データで受け取ったものは電子データのまま保存することが義務付けられています。
再発行トラブルへの最善の対策は、トラブルが起きにくい仕組みを作ることです。請求書発行システムなどを活用した業務の電子化は、ヒューマンエラーを減らし、法改正にも対応できる、最も効果的な解決策といえます。
納品書の再発行は、一見すると小さな事務作業かもしれません。しかし、その対応には企業の誠実さ、正確さ、そして未来を見据えた管理体制が表れます。このガイドが、あなたのビジネスにおける信頼の礎を築く一助となれば幸いです。








診断書の添え状テンプレート決定版|休職・復職で失礼のない書き…
診断書を会社に送るという行為は、単なる事務手続きではありません。それは、あなたがこれから心身を休ませ…