
毎月の給与計算、特に雇用保険料の計算は複雑で間違いやすいと感じていませんか。料率が毎年変わる可能性があり、どの手当を計算に含めるべきか迷うことも多いでしょう。計算ミスは、従業員の手取り額に直接影響し、会社の信頼を損なうことにもなりかねません。
この記事を読めば、2025年度(令和7年度)の最新料率に対応した、正確な雇用保険料の計算方法がわかります。複雑な計算が、誰でも自信を持って行えるシンプルなプロセスに変わるでしょう。
計算の「方法」だけでなく、なぜそのように計算するのかという「理由」まで理解できるため、従業員からの質問にも明確に答えられるようになります。
本記事では、具体的な計算例やわかりやすいチェックリストを豊富に用いて、一歩ずつ解説します。小規模事業の経営者から人事・労務の担当者まで、この記事だけで雇用保険料計算のプロフェッショナルになれるよう、必要な情報をすべて網羅しました。
目次
そもそも雇用保険とは?給与から天引きされる理由と制度の目的
給与明細を見ると、毎月「雇用保険料」という項目で一定額が控除されています。この保険料が何のために使われ、どのような役割を果たしているのかを理解することは、計算方法を学ぶ上での第一歩です。雇用保険は、単に失業したときのためだけのものではなく、働く人々が安心してキャリアを継続するための重要な社会インフラといえます。
労働者の生活と雇用を守るセーフティネット
雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定を守ることを目的とした、国が管轄する公的な保険制度です。万が一、会社を離職して収入が途絶えた場合に、再就職までの生活を支える「失業手当(基本手当)」が給付されるのが最もよく知られた役割です。
しかし、その機能は失業時の支援に留まりません。育児や家族の介護で一時的に仕事を休まざるを得ない場合には「育児休業給付金」や「介護休業給付金」が支給されます。また、キャリアアップを目指して指定の教育訓練を受ける際には「教育訓練給付金」が支給されるなど、働き続けることを多角的に支援する制度が整っています。
このように、雇用保険は失業という事態に備えるだけでなく、労働者が様々なライフイベントに直面しても雇用を継続し、能力を向上させていくことを積極的に支えるためのセーフティネットなのです。従業員にとっては安心して働ける基盤となり、事業者にとっては助成金の活用や人材の定着に繋がるというメリットもあります。
雇用保険と労災保険、労働保険の違いをわかりやすく整理
雇用保険の話をするとき、「労働保険」や「労災保険」といった似た言葉が出てきて混乱することがあります。これらの関係を正しく理解しておくことが重要です。
まず、「労働保険」とは、「雇用保険」と「労災保険(労働者災害補償保険)」をまとめた総称です。どちらも働く人を守るための国の保険制度ですが、その目的と役割が明確に異なります。
雇用保険は失業や育児・介護休業など、雇用の継続が困難になった場合に生活を支える保険です。一方、労災保険は仕事中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡といった労働災害に対して給付を行います。
最も大きな違いの一つが、保険料の負担者です。労災保険の保険料は全額事業主が負担します。一方で、雇用保険の保険料は事業主と労働者の双方が負担します。これが、給与から雇用保険料だけが天引きされる理由です。
加入は義務?対象となる従業員の条件
労働者を一人でも雇用する事業所は、原則として労働保険への加入が法律で義務付けられています。その上で、雇用する従業員が以下の2つの条件を両方満たす場合、本人の意思や雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)に関わらず、雇用保険の被保険者として加入させなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
「31日以上の雇用見込み」とは、雇用契約書に期間の定めがない場合や、契約更新の可能性がある場合などが該当します。明確に「31日未満で雇用を終了する」と定めている場合を除き、この条件を満たすと判断されます。
雇用保険料の計算はこの一本式で完結
雇用保険料の計算は、一見複雑に思えるかもしれませんが、基本となる計算式は非常にシンプルです。この式と、計算に使う「賃金総額」の正しい範囲さえ理解すれば、誰でも正確に算出できます。
基本の計算式は「賃金総額」×「雇用保険料率」
雇用保険料を計算するための基本式は、以下の通りです。
雇用保険料 = 賃金総額 × 雇用保険料率
この計算は、毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)が支払われる際にも同様に行います。計算の基となる「賃金総額」とは、所得税や社会保険料などが控除される前の総支給額を指します。
健康保険料との違い「標準報酬月額」は使いません
ここで非常に重要な注意点があります。健康保険料や厚生年金保険料の計算で使われる「標準報酬月額」は、雇用保険料の計算では一切使用しません。
標準報酬月額は、給与額を一定の等級(グレード)に当てはめて保険料を固定化する仕組みです。これに対し、雇用保険料は、残業代や手当の変動を含む、その月に実際に支払われた賃金の総額を基に毎回計算します。
そのため、残業が多ければその分、雇用保険料も高くなります。この違いは、給与計算で最も間違いやすいポイントの一つなので、明確に区別して覚えておく必要があります。
【2025年4月改定】最新の雇用保険料率を事業種別にご紹介
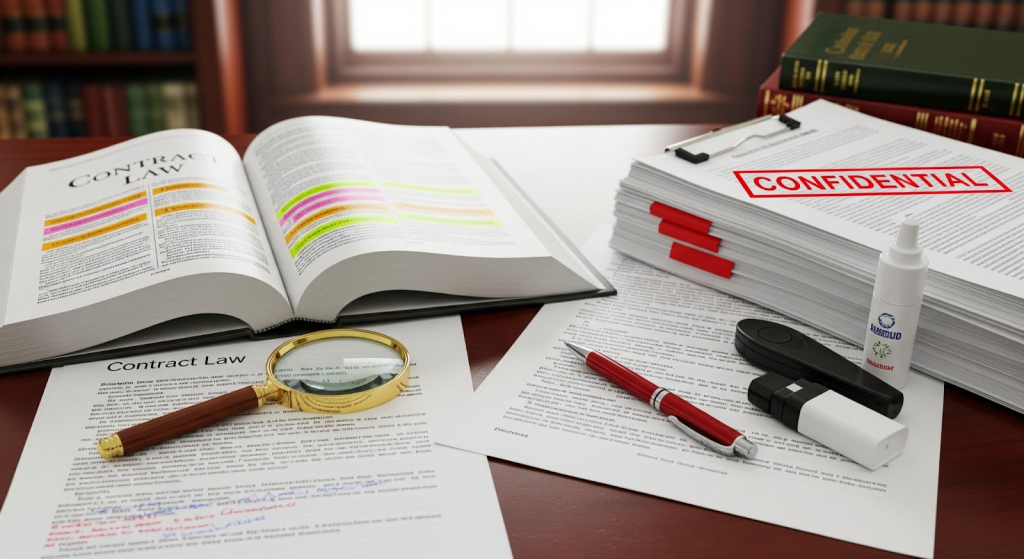
雇用保険料率は、経済状況や失業給付の支給実績などを基に、毎年見直される可能性があります。給与計算を行う上で、常に最新の料率を把握しておくことが不可欠です。2025年度(令和7年度)には、重要な改定が行われます。
令和7年度(2025年度)の雇用保険料率は引き下げへ
2025年4月1日から適用される令和7年度の雇用保険料率は、現行の令和6年度から引き下げられることが決定しました。これは、2017年度以来8年ぶりの引き下げとなります。
近年の新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金の支給増加などで、雇用保険の財政は厳しい状況が続き、保険料率が引き上げられてきました。しかし、その後の雇用環境の改善により財政状況が安定してきたことが、今回の引き下げの背景にあります。この改定は、労働者と事業主双方の負担を軽減するものです。
事業種別ごとの料率一覧(労働者負担・事業主負担)
雇用保険料率は、事業の種類によって3つに区分されています。自社がどの事業に該当するかを確認し、正しい料率を適用してください。以下に、令和6年度と令和7年度の料率を比較した一覧表を示します。
| 事業の種類 | 年度 | 労働者負担率 | 事業主負担率 | 合計 |
| 一般の事業 | 令和6年度 | 6.0/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 令和7年度 | 5.5/1,000 | 9.0/1,000 | 14.5/1,000 | |
| 農林水産業・清酒製造の事業 | 令和6年度 | 7.0/1,000 | 10.5/1,000 | 17.5/1,000 |
| 令和7年度 | 6.5/1,000 | 10.0/1,000 | 16.5/1,000 | |
| 建設の事業 | 令和6年度 | 7.0/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
| 令和7年度 | 6.5/1,000 | 11.0/1,000 | 17.5/1,000 |
(出典: 厚生労働省発表資料)
なぜ事業によって料率が違うのか?
事業種別によって料率が異なるのは、各産業の労働市場の特性や失業リスクが違うためです。例えば、建設業は工事の受注状況によって雇用が変動しやすく、離職率が他の産業に比べて高い傾向があるため、保険料率が高めに設定されています。
また、事業主の負担率が労働者よりも高いことにも理由があります。事業主負担分には、労働者と分担する「失業等給付」の保険料に加えて、事業主のみが負担する「雇用保険二事業」の保険料が含まれているからです。
この「雇用保険二事業」は、雇用の安定、労働者の能力開発、福祉の増進などを目的とした助成金制度の財源となっており、労働市場全体の安定に貢献する費用を事業主が広く負担する仕組みになっています。
計算の基礎となる「賃金総額」に含めるもの・含めないもの
雇用保険料の計算で最も重要なのが、「賃金総額」を正しく把握することです。どのような支払いが賃金に含まれ、どのようなものが含まれないのか。この区別を曖昧にすると、計算結果が大きく変わってしまいます。
雇用保険料の対象となる手当一覧
雇用保険法における「賃金」とは、名称を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものを指します。つまり、その支払いが「仕事をしたことへの対価」であるかどうかが判断基準となります。
この原則に基づくと、給与明細に記載される多くの項目が賃金総額に含まれます。一方で、実費の弁償や慶弔禍福に対する見舞金など、労働の対価とはいえないものは対象外です。以下のチェックリストで、自社の給与項目がどちらに該当するかを確認してください。
| 支払項目 | 対象/対象外 | 備考 |
| 基本給、時給、日給 | 対象 | 賃金の中核となるものです。 |
| 残業手当、深夜手当、休日手当 | 対象 | 時間外労働などに対する対価です。 |
| 通勤手当、定期券・回数券 | 対象 | 所得税法上で非課税であっても、雇用保険では賃金に含まれます。 |
| 住宅手当、家賃補助 | 対象 | 生活を補助する目的でも、労働の対価とみなされます。 |
| 家族手当、扶養手当 | 対象 | 同様に、労働の対価の一部とみなされます。 |
| 役職手当、資格手当、技能手当 | 対象 | 役職やスキルに対する対価です。 |
| 賞与(ボーナス) | 対象 | 労働の対価として支払われる賞与はすべて対象です。 |
| 役員報酬 | 対象外 | 労働者としての賃金ではないため対象外です。 |
| 退職金 | 対象外 | 在職中の労働の対価ではなく、退職に伴う支払いです。 |
| 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金 | 対象外 | 恩恵的な給付であり、労働の対価ではありません。 |
| 出張旅費、宿泊費 | 対象外 | 業務遂行に必要な経費の実費弁償です。 |
| 解雇予告手当 | 対象外 | 労働基準法に基づく手当であり、賃金とは性質が異なります。 |
(出典: 厚生労働省「雇用保険料の対象となる賃金」など)
賞与(ボーナス)の取り扱いと注意点
賞与(ボーナス)も、毎月の給与と同様に雇用保険料の計算対象となります。適用される保険料率は、給与と同じです。
注意すべきは、健康保険や厚生年金保険と異なり、雇用保険料の計算においては賞与額に上限が設けられていない点です。支払われた賞与の全額が、保険料計算の基礎となります。
ただし、すべての賞与が対象となるわけではありません。業績に応じて支払われる通常の賞与は対象ですが、決算賞与の中でも特に恩恵的に支払われる「大入り袋」や「金一封」のようなものは、労働の対価とはみなされず、対象外となる場合があります。
具体例で学ぶ!月給・賞与の雇用保険料計算ステップ
理論を理解したところで、次は具体的な数字を使って計算してみましょう。ここでは、令和7年度(2025年4月以降)の料率を使い、「一般の事業」に勤務する従業員のケースでシミュレーションします。
毎月の給与計算シミュレーション
ある従業員の1ヶ月の賃金総額(総支給額)が30万円だったとします。
労働者負担分の計算
令和7年度の一般の事業における労働者負担率は 5.5/1,000 です。
300,000円×(5.5/1,000)=1,650円
この従業員の給与からは、1,650円の雇用保険料が控除されます。
事業主負担分の計算
同様に、事業主負担率は 9.0/1,000 です。
300,000円×(9.0/1,000)=2,700円
事業主は、この従業員に対して2,700円の雇用保険料を負担します。
賞与(ボーナス)の計算シミュレーション
同じ従業員に、50万円の賞与が支給された場合を考えます。計算方法は給与と同じです。
労働者負担分の計算
500,000円×(5.5/1,000)=2,750円
賞与からは、2,750円が控除されます。
給与と賞与が同じ月に支払われる場合でも、それぞれ別々に計算し、合算してはいけません。必ず、給与と賞与の総支給額にそれぞれ料率を掛けてください。
1円未満の端数処理「50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ」の法則
給与額によっては、計算結果に1円未満の端数が生じることがあります。この端数処理には、法律で定められた厳密なルールが存在します。
従業員の給与から保険料を天引き(源泉控除)する場合、計算結果の端数は以下のように処理します。
- 端数が50銭以下の場合は切り捨て
- 端数が50銭1厘以上の場合は切り上げ
これは一般的な四捨五入(5以上切り上げ)とは異なるため、注意が必要です。このルールは「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に基づくもので、企業が独自に「常に切り捨て」などと運用することは原則として認められていません。ただし、労使協定などで慣習的な取り扱いが定められている場合は、そちらを優先することができます。
具体例1(切り捨て)
賃金総額が332,400円の場合(労働者負担率 5.5/1,000)
332,400円×(5.5/1,000)=1,828.2円
端数は0.2円、つまり20銭です。これは50銭以下なので切り捨て、控除額は1,828円となります。
具体例2(切り上げ)
賃金総額が332,092円の場合(労働者負担率 5.5/1,000)
332,092円×(5.5/1,000)=1,826.506円
端数は0.506円、つまり50銭6厘です。これは50銭1厘以上なので切り上げ、控除額は1,827円となります。
毎月の計算だけじゃない!年に一度の「年度更新」とは
従業員の給与から天引きした雇用保険料は、事業主負担分と合わせて国に納付します。この納付手続きは、毎月行うのではなく、年に一度「年度更新」という手続きでまとめて行います。これは労働保険(雇用保険と労災保険)に共通する手続きで、多くの事業主にとって重要な年次業務です。
確定保険料と概算保険料の仕組み
労働保険料の納付は、「まず概算で前払いし、翌年に実績で精算する」という二段階の仕組みになっています。
まず、新年度(4月1日)が始まると、その年度1年間に支払う予定の賃金総額の見込みを立て、それに基づいて計算した保険料(概算保険料)を前払いします。
そして年度が終了(翌年3月31日)すると、実際に支払った賃金総額が確定します。これに基づいて正確な保険料(確定保険料)を計算し、前払いした概算保険料との差額を精算します。
不足していれば追加で納付し、払い過ぎていれば新年度の概算保険料に充当するか、還付を受けます。この一連の手続きが「年度更新」であり、事業主は毎年これを行う義務があります。
申告と納付の手続きの流れ(6月1日から7月10日)
年度更新の手続き期間は、毎年6月1日から7月10日までと定められています。この期間内に申告と納付を完了させる必要があります。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。まず5月下旬頃、管轄の都道府県労働局から申告書一式が事業所宛に郵送されます。次に、前年度(4月1日から3月31日まで)に支払った全従業員の賃金総額を正確に集計します。
集計した賃金総額を基に、確定保険料と新年度の概算保険料を計算し、申告書に記入します。最後に、作成した申告書を提出し、算出された保険料を納付します。
期限内に手続きを行わないと、政府が保険料を決定し、さらに納付すべき額の10%の追徴金が課される場合がありますので、厳守してください。
納付方法の選択肢
納付にはいくつかの方法があり、事業所の都合に合わせて選択できます。
一つ目は、銀行、信用金庫、郵便局などの金融機関窓口や、所轄の労働局・労働基準監督署で、申告書の提出と同時に現金で納付する方法です。
二つ目は、事前に申し込むことで指定の口座から自動で引き落とされる口座振替です。納付忘れを防げるほか、納付期限が通常より遅くなるというメリットがあります。
三つ目は、政府の電子申請システム「e-Gov」を利用して申告した場合に可能な電子納付です。Pay-easy(ペイジー)に対応したインターネットバンキングやATMで納付できます。なお、概算保険料額が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方のみの場合は20万円以上)の場合、保険料を3回に分けて納付する「延納」も可能です。
間違いやすいポイントとQ&A

雇用保険料の計算や手続きには、特に注意が必要な点がいくつかあります。ここでは、よくある疑問や間違いやすいポイントをQ&A形式で解説します。
65歳以上の従業員の保険料はどうなる?
現在、65歳以上の従業員も、他の従業員と全く同じ条件で雇用保険料の納付が必要です。
かつては、保険年度の初日(4月1日)時点で満64歳以上の労働者については、雇用保険料が免除される経過措置がありました。しかし、この免除措置は令和2年(2020年)4月1日に完全に廃止されました。
したがって、年齢に関わらず、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある従業員は、全員が雇用保険の被保険者となり、給与や賞与から保険料が控除されます。過去の制度を知っていると間違いやすいため、注意が必要です。
パート・アルバイトの計算で気をつけること
パートやアルバイトであっても、雇用保険料の計算方法は正社員と全く同じです。つまり、「その月に支払われた賃金総額 × 雇用保険料率」で計算します。
重要なのは、雇用形態の名称ではなく、加入条件(週20時間以上の所定労働時間、31日以上の雇用見込み)を満たしているかどうかです。条件を満たしていれば、雇用保険に加入し、毎月の給与から保険料を控除する義務があります。
計算を間違えた場合の対処法
保険料率の更新忘れや、対象賃金の範囲の誤認など、計算ミスが発覚した場合は、速やかに正しい対応をとる必要があります。
控除額が少なかった場合は、従業員に状況を丁寧に説明し、同意を得た上で、次回の給与で不足分を合わせて控除します。逆に控除額が多かった場合は、同様に従業員に説明し、次回の給与で過剰分を返金(給与に上乗せ)します。
いずれの場合も、給与明細には調整額であることがわかるように「雇用保険料調整」などの項目を設け、透明性を確保することが重要です。従業員との信頼関係を損なわないよう、誠実なコミュニケーションを心がけましょう。
従業員の入社・退職時に必要な手続き
雇用保険料の計算は、従業員の入社から退職までの一連の手続きと密接に関連しています。これらの手続きが、保険料を正しく徴収・納付するための法的な土台となります。
従業員を雇用し加入条件を満たす場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用した月の翌月10日までに管轄のハローワークへ提出します。この届出によって、その従業員が正式に被保険者として登録されます。
従業員が離職した場合は、離職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。従業員が失業手当の受給を希望する場合は、同時に「離職証明書」も提出し、後日交付される「離職票」を本人に渡す必要があります。
これらの届出を怠ると、保険料の徴収漏れや、退職した従業員が失業手当をスムーズに受給できないといったトラブルに繋がるため、確実な手続きが求められます。
まとめ
雇用保険料の計算は、給与計算業務の中でも特に正確性が求められる重要な作業です。本記事で解説したポイントを押さえることで、複雑に見えるプロセスも、着実にこなすことができます。
本記事の要点再確認
最後に、正確な雇用保険料計算のために必ず覚えておくべき要点を再確認しましょう。
基本の計算式は「賃金総額 × 雇用保険料率」です。
令和7年度(2025年4月)から雇用保険料率が引き下げになります。給与計算システムの設定更新を忘れないようにしましょう。
計算の基礎となる「賃金総額」には、非課税の通勤手当も含まれます。「標準報酬月額」とは違うことを明確に認識してください。
1円未満の端数処理は「50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ」という特有のルールに従います。
年に一度の「年度更新」(6月1日から7月10日)で、保険料の精算と翌年度分の概算納付を行います。
雇用保険料を正しく計算し、納付することは、法律上の義務であると同時に、従業員の生活を守り、企業としての信頼を築くための基本です。この記事が、皆様の正確で効率的な給与計算業務の一助となれば幸いです。








不動産売買の領収書テンプレートと正しい書き方|印紙税の判定か…
不動産売買における金銭トラブルを未然に防ぎ、税務署への申告をスムーズに進めるためには、正確な領収書の…