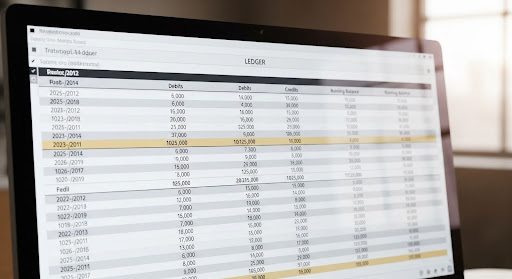
「また新しい法律への対応が必要なのか」と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。2024年1月から本格的に義務化された電子帳簿保存法への対応は、多くの事業者にとって一つの課題かもしれません。
しかし、この法改正は単なる負担増を意味するものではありません。むしろ、国が後押しする「業務デジタル化の絶好の機会」と捉えることができます。
これまで当たり前だった紙の書類のファイリング、保管スペースの確保、そして過去の書類を探すといった手間から解放される未来が、すぐそこまで来ています。
この記事を読めば、電子帳簿保存法への対応が、コスト削減や生産性向上、さらにはテレワークの推進といった、ビジネスを一段階上へと引き上げるための戦略的な一手であることがご理解いただけるはずです。
法改正への漠然とした不安は、具体的な行動計画と、自社に最適なツールを選ぶ自信へと変わるでしょう。
本記事では、複雑な法律の基本から、失敗しないソフトの選び方、そしてコストを抑える補助金の活用法まで、網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、自信を持って電子帳簿保存ソフトの導入へと踏み出せるようになっているはずです。
目次
電子帳簿保存法とインボイス制度の関連性
電子帳簿保存ソフトの選定に入る前に、その背景にある「電子帳簿保存法」と「インボイス制度」という2つの重要な制度の関係性を正しく理解することが不可欠です。これらはそれぞれ独立した法律ですが、実務上は密接に連携しており、両者をセットで考えることが業務効率化の鍵となります。
電子帳簿保存法の3つの保存区分
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類の保存方法を定めた法律です。その保存区分は大きく3つに分けられます。すべての区分に一度に対応する必要はなく、特に重要なのは義務化された「電子取引」への対応です。
電子帳簿等保存(任意)
会計ソフトなどで最初から一貫して電子的に作成した帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など)や書類(決算関係書類など)を、印刷せずにデータのまま保存する方法です。この対応は任意ですが、導入すれば紙媒体での保管が不要になり、管理コストの削減につながります。
スキャナ保存(任意)
取引先から紙で受け取った請求書や領収書、あるいは自社で手書き作成した書類の控えなどを、スキャナーやスマートフォンで読み取って画像データとして保存する方法です。これも対応は任意ですが、導入することでペーパーレス化を大きく推進できます。
電子取引のデータ保存(義務)
これが最も重要な区分です。メールで受け取ったPDFの請求書や、Webサイトからダウンロードした領収書など、電子的にやり取りした取引情報は、データのまま保存することが法律で義務付けられています。
2024年1月1日以降、これらの電子データを紙に印刷して保存する方法は原則として認められなくなりました。この義務化が、ほぼすべての事業者にとって電子帳簿保存ソフトの導入が急務となった直接的な理由です。
インボイス制度とセットで考えるべき理由
2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。一見すると、電子帳簿保存法とは無関係に思えるかもしれません。しかし、実際の取引を考えると、この2つの法律は分かちがたく結びついています。
インボイス制度は、請求書に記載すべき「内容」を定めています。一方で、その請求書(インボイス)がPDFなどの電子データでやり取りされた場合、それは電子帳簿保存法における「電子取引」に該当します。したがって、その電子インボイスの「保存方法」は、電子帳簿保存法のルールに従わなければなりません。
つまり、1つの電子インボイスという文書が、インボイス制度(内容の要件)と電子帳簿保存法(保存の要件)という2つの法律の規制を同時に受けることになります。この事実が、両制度に一括で対応できるソフトウェアの導入を非常に合理的な選択肢にしています。
片方だけの対応では、結局二度手間になったり、コンプライアンス上の漏れが発生したりするリスクが高まります。両制度は、いわば紙ベースの経理業務をデジタル化へと導くための「両輪」として機能しているのです。
失敗しない電子帳簿保存ソフトの選び方 5つのチェックポイント
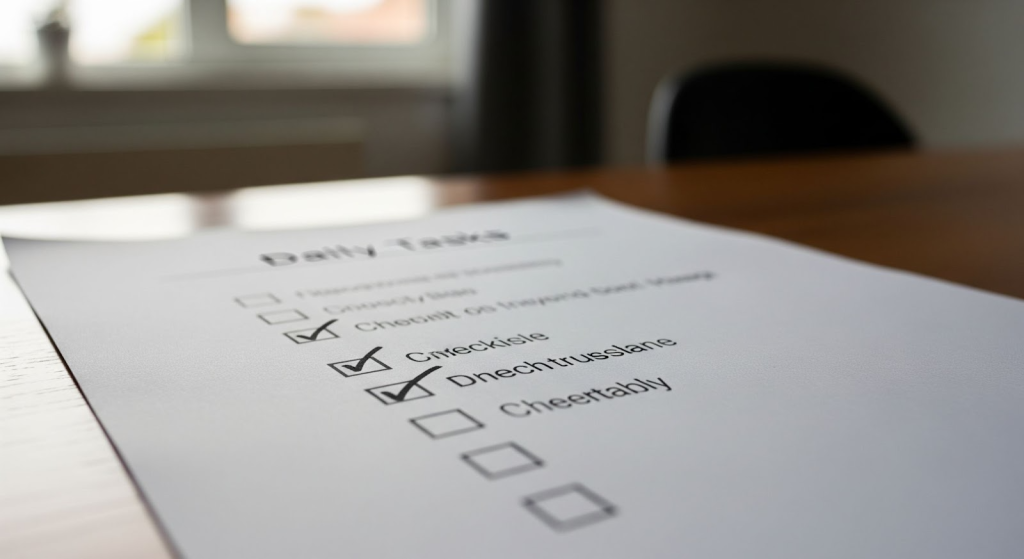
自社に最適な電子帳簿保存ソフトを選ぶためには、単に機能の多さや価格だけで判断するのではなく、自社の業務実態に合わせた多角的な視点が必要です。ここでは、導入後に後悔しないための5つの必須チェックポイントを解説します。
自社の業務に合った対応書類の範囲を確認する
電子帳簿保存ソフトは、その得意分野によって大きく3つのタイプに分類できます。自社が最も効率化したい業務は何かを明確にし、それに合ったタイプのソフトを選ぶことが最初のステップです。
幅広い帳票類に対応する総合型
請求書や領収書だけでなく、契約書、見積書、納品書など、あらゆる国税関係書類をまとめて電子保存したい企業向けのタイプです。全社的なペーパーレス化を目指す場合に最適です。代表的なソフトには「楽々クラウド電子帳簿保存サービス」や「invox電子帳簿保存」などがあります。
請求書の受領・発行に特化した請求書特化型
特に取引先から受け取る請求書の処理に多くの時間を費やしている企業向けのタイプです。請求書の受け取りからデータ化、支払い処理、保管までを一気通貫で効率化します。代表的なソフトには「Bill One」や「マネーフォワード クラウド債務支払」などがあります。
領収書の処理に特化した経費精算型
従業員の経費精算や出張旅費の申請が多い企業向けのタイプです。スマートフォンでの領収書撮影や申請・承認フローの電子化を得意とします。代表的なソフトには「楽楽精算」や「TOKIUM経費精算」などがあります。
事業規模に最適なソフトを見極める
企業の規模によって、ソフトウェアに求められる機能や価格帯は大きく異なります。自社の現状と将来の展望に合った製品を選びましょう。
個人事業主・フリーランスの場合
最優先すべきは、コストパフォーマンスと操作の簡便さ、そして確定申告ソフトとの連携です。日々の記帳から書類保存、確定申告までをシームレスに行えるオールインワン型のクラウド会計ソフトが主流となっています。「やよいの青色申告 オンライン」「freee会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」などが代表的です。
中小企業の場合
従業員数や取引量の増加に対応できる拡張性(スケーラビリティ)、複数人での利用を前提とした承認ワークフロー機能、そして既存の基幹システム(ERP)や会計システムとのデータ連携機能が重要になります。セキュリティやガバナンスの観点も無視できません。「勘定奉行クラウド」や「TKC FXシリーズ」、「バクラク電子帳簿保存」などが中小企業向けの代表的な選択肢です。
無料プランと有料プランの違いと選び分け
多くのソフトが無料プランを提供していますが、その多くには機能制限があることを理解しておく必要があります。無料プランは、主に導入初期のテストや、取引量が非常に少ない個人事業主向けと考えるのが適切です。
無料プランには、利用できるユーザー数が1名などに限定される、月間にアップロードできる書類の枚数や総保存容量に上限がある、といった制限が一般的です。また、AI-OCRによる自動読み取りや承認ワークフローなど、業務効率化に直結する高度な機能が利用できない場合もあります。中には、特定の有料サービスと連携する場合にのみ無料で利用できるケースも存在します。
ソフトを選び分ける際のポイントとして、まずは無料プランや無料トライアルで操作感を試すことが挙げられます。その上で、自社の月間取引量で制限に達しないかを確認しましょう。ビジネスの成長を見越すなら、将来的な拡張性も考慮し、初めから有料プランを検討するのが賢明な判断と言えます。
「JIIMA認証」の有無はなぜ重要か
JIIMA(ジーマ:公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)認証は、そのソフトウェアが電子帳簿保存法の法的要件を満たしていることを第三者機関が証明する制度です。この認証の有無は、ソフト選びにおいて極めて重要な指標となります。
JIIMA認証は、単なる機能の証明ではありません。法改正の複雑な要件(タイムスタンプのルール、検索要件、真実性の確保など)を自社で一つひとつ確認する手間と時間を省き、コンプライアンス違反のリスクを大幅に低減するための、いわば「コンプライアンスの保険」のような役割を果たします。
税務調査の際にも、認証されたソフトを適切に利用していることは、法令遵守の姿勢を示す有力な証拠となります。
利用者は、JIIMA認証ロゴがあるソフトを選ぶだけで、複雑な法的要件の確認作業を専門機関に委託できるのです。これにより、安心して本来の業務に集中できます。認証には「スキャナ保存」「電子帳簿ソフト」「電子取引ソフト」など複数の種類があるため、自社が必要とする機能に対応した認証を取得しているかを確認すると、より確実です。
既存の会計ソフトやシステムと連携できるか
電子帳簿保存ソフトは、それ単体で完結するものではありません。多くの場合、会計ソフトや販売管理システムなど、既存のシステムと連携して使用されます。ソフトの導入によって、データの二重入力といった新たな手間が発生しては本末転倒です。
選定時には、現在使用している会計ソフトとAPI連携(システム同士が自動でデータ連携する仕組み)が可能か、あるいはスムーズなCSVファイルの出力・取り込みに対応しているかを確認しましょう。シームレスなデータ連携は、バックオフィス業務全体の効率を飛躍的に向上させる重要な要素です。
コストを抑えるIT導入補助金の活用術
電子帳簿保存ソフトの導入は、法対応と業務効率化のための重要な投資ですが、コストが障壁となる場合もあります。そこで活用したいのが、国が中小企業のITツール導入を支援する「IT導入補助金」です。この制度をうまく利用すれば、導入コストを大幅に抑えることが可能です。
IT導入補助金の対象となるソフトと申請の条件
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が生産性向上のためにITツールを導入する際の経費の一部を補助する制度です。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応を目的とした会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトなどの導入は、補助金の対象となるケースが多く、特に「インボイス対応類型」という枠が設けられています。
補助金の対象となるのは、資本金や従業員数によって定められた中小企業・小規模事業者で、個人事業主も含まれます。対象となるITツールは、事務局に登録されたものである必要があり、「freee会計」「マネーフォワード クラウド」「弥生会計」といった主要なクラウド会計ソフトの多くは登録済みです。
ソフトウェアの利用料だけでなく、PCやタブレットなどのハードウェア購入費用も対象になる場合があります。
申請から補助金交付までの流れ
IT導入補助金の申請は、事業者自身が単独で行うのではなく、「IT導入支援事業者」として登録されたベンダーと協力して進めるのが特徴です。
まず、自社の課題解決に合ったITツールと、そのツールを取り扱うIT導入支援事業者を選定します。支援事業者が申請のサポートをしてくれるため、安心して手続きを進められます。
次に、オンライン申請に必須の法人・個人事業主向け共通認証システムである「gBizIDプライム」のアカウントを取得します。取得には時間がかかる場合があるため、早めに手続きを始めることが重要です。
その後、IT導入支援事業者と共同で事業計画を作成し、申請マイページから必要情報を入力して交付申請を行います。ITツールの契約や支払いは、必ず「交付決定」の通知を受けた後に行う必要があります。
交付決定前に発注・契約したものは補助金の対象外となるため注意が必要です。ツール導入後、支払いの証拠などを揃えて事業実績報告を行い、審査を経て補助金が交付(振り込み)されるという流れになります。
電子帳簿保存法に関するよくある質問

最後に、実務で直面しがちな疑問点について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
電子データと紙の両方で請求書を受け取った場合はどうすればいいですか?
取引先との間でどちらが正本であるか明確な取り決めがない場合、原則として両方の保存が求められる可能性があります。しかし、実務的な対応として、社内で「電子データで受領したものを正本として扱う」といったルール(事務処理規程)を定めて運用することで、電子データのみの保存とすることが可能です。
電子データで受け取った請求書を印刷して、それをスキャンして保存しても良いですか?
いいえ、できません。メールなどで電子的に受け取ったデータは「電子取引」に該当するため、そのオリジナルの電子データのまま保存しなければなりません。一度紙に出力してスキャンしたデータは、スキャナ保存の要件を満たしたとしても、元の電子取引データの保存義務を果たしたことにはなりません。
ファイル名の付け方にルールはありますか?
専用のシステムを導入しない場合でも、ファイルの検索要件を満たすための工夫として、ファイル名を統一する方法が認められています。例えば、「20251031_株式会社〇〇_110000.pdf」のように「取引年月日_取引先名_金額」といった規則でファイル名を設定すれば、OSの検索機能で要件を満たすことが可能です。
タイムスタンプは必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。タイムスタンプの付与は、データの真実性を確保するための措置の一つに過ぎません。他の方法として、訂正や削除の履歴が残る(または訂正削除ができない)システムを利用する方法や、データの訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて遵守する方法があります。
いずれかの措置を講じれば、タイムスタンプは不要です。多くの中小企業では、コストをかけずに対応できる事務処理規程を整備する方法が採用されています。
2024年1月から完全義務化されましたが、対応が間に合わない場合の救済措置はありますか?
はい、「猶予措置」が設けられています。システムの導入が間に合わないなど、「相当の理由」があると税務署長が認める場合で、かつ税務調査の際に電子データのダウンロードの求めと、そのデータを出力した書面の提示・提出の求めに応じることができれば、検索機能などの保存要件を満たさなくても良いとされています。
ただし、これはあくまで猶予であり、電子データ自体の保存は必須です。恒久的な対策ではないため、早急なシステム対応が推奨されます。
まとめ
電子帳簿保存法への対応は、もはや避けては通れない経営課題です。特に、電子データでやり取りした取引情報のデータ保存は、すべての事業者にとっての義務となりました。しかし、本記事で解説したように、この法改正は単なる規制強化ではありません。
適切なソフトウェアを選び、必要であればIT導入補助金を活用することで、この変化を自社のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる絶好の機会とすることができます。
成功への要点を再確認しましょう。第一に、法対応は義務であると同時に、ペーパーレス化によるコスト削減と生産性向上を実現する機会であると捉えることが重要です。第二に、自社の業務内容、取引量、事業規模を正しく理解し、最適なソフトを選ぶことが成功の第一歩となります。
第三に、JIIMA認証は複雑な法令要件への適合性を自ら検証する手間を省き、コンプライアンス違反のリスクを低減するための有効な判断基準となります。そして最後に、IT導入補助金を活用すれば、法対応への投資を、国からの支援を受けた戦略的な事業改善へと昇華させることが可能です。
変化への対応は、時に困難を伴います。しかし、それは同時に、旧来の非効率な業務プロセスを見直し、より強く、より競争力のある組織へと生まれ変わるためのチャンスでもあります。まずは気になるソフトの無料トライアルに申し込む、あるいはIT導入支援事業者に相談してみるなど、今日からできる小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…