
毎年の確定申告や日々の経理業務に追われる中で、「e-Tax」や「eLTAX」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。
多くの経営者や経理担当者の方が「どちらも電子申告のシステムらしいが、具体的な違いがわからない」「導入手続きが複雑そうで後回しにしている」といった課題を抱えているかもしれません。
しかし、これら二つのシステムの違いを正しく理解し、自社の状況に合わせて活用することは、バックオフィス業務を劇的に効率化し、企業の成長に不可欠な貴重な時間を創出するための重要な第一歩です。
電子申告システムの導入は、単なる事務作業のオンライン化に留まらず、ペーパーレス化の推進、リモートワークへの対応、そして迅速な経営判断に繋がるキャッシュフローの改善にも貢献します。
この記事では、e-TaxとeLTAXの根本的な役割の違いから、それぞれの具体的なメリット、導入から運用までのステップ、そして多くの人が陥りがちな注意点に至るまで、網羅的かつ体系的に解説します。
複雑に見える電子申告の世界を、誰にでも理解できるよう、丁寧に紐解いていきます。本記事を読み終える頃には、あなたは自信を持って自社に最適な電子申告システムを導入し、持続可能な業務効率化を実現できるようになるでしょう。
目次
e-TaxとeLTAXの根本的な違いは納税先
まず、最も重要な結論からお伝えします。e-TaxとeLTAX、この二つのシステムの最大の違いは、「どの行政機関に税金を納めるか」という点にあります。この基本的な区別を理解することが、電子申告システムを正しく活用するための鍵となります。
e-Taxは国税の窓口
e-Tax(イータックス)は、国税庁が管轄する国税の申告および納税手続きを行うためのオンラインシステムです。対象となる主な税金には、所得税、法人税、消費税、贈与税、相続税など、国の財源となる税金が含まれます。個人事業主の確定申告や、法人の法人税申告などで利用される、最も一般的な電子申告システムと言えるでしょう。
eLTAXは地方税の窓口
一方、eLTAX(エルタックス)は、地方税共同機構が運営する地方税の申告・納税手続きを担うシステムです。都道府県や市区町村といった地方公共団体に納める住民税、事業税、固定資産税(償却資産)などが対象です。特に、複数の都道府県や市区町村に事業所を持つ法人が、各自治体への申告・納税を一本化できる点に大きな特徴があります。
なぜ二つのシステムが存在するのかというと、日本の税制度が国に納める「国税」と、事業所や居住地のある地方公共団体に納める「地方税」に分かれているためです。
e-Taxは国税のオンライン窓口、eLTAXは地方税のオンライン窓口として、それぞれが独立した役割を担っています。この「国税はe-Tax、地方税はeLTAX」という原則を覚えておけば、電子申告に関する混乱の大部分は解消されるはずです。
e-TaxとeLTAXの機能比較
e-TaxとeLTAXの主な違いを一覧表にまとめました。まずはこの表で全体像を掴み、その後の詳細な解説で理解を深めてください。
| 項目 | e-Tax(イータックス) | eLTAX(エルタックス) |
| 管轄 | 国税庁 | 地方税共同機構 |
| 目的 | 国税の電子申告・納税 | 地方税の電子申告・納税・申請 |
| 主な対象税目 | 所得税、法人税、消費税、贈与税、相続税など | 法人住民税、法人事業税、個人住民税(給与支払報告)、固定資産税(償却資産)、事業所税など |
| 主な利用者 | 全ての納税者(個人事業主、法人、個人) | 主に法人、個人事業主(特に給与支払者) |
| 主要機能 | 確定申告、各種届出、電子納税、還付金の早期受取 | 複数の地方公共団体への一括申告・納税(共通納税)、給与支払報告書の一括提出、法人設立届出など |
| 利用ツール | e-Taxソフト(WEB版・ダウンロード版)、確定申告書等作成コーナー | PCdesk(WEB版・DL版・SP版) |
この表が示すように、両者は管轄から対象税目、主要機能に至るまで明確な違いがあります。法人が事業活動を行う上では、多くの場合、両方のシステムを利用して国税と地方税の両方を申告・納税する必要があります。ここからは、それぞれのシステムについて、より詳しく掘り下げていきましょう。
国税の手続きをオンラインで完結させる「e-Tax」
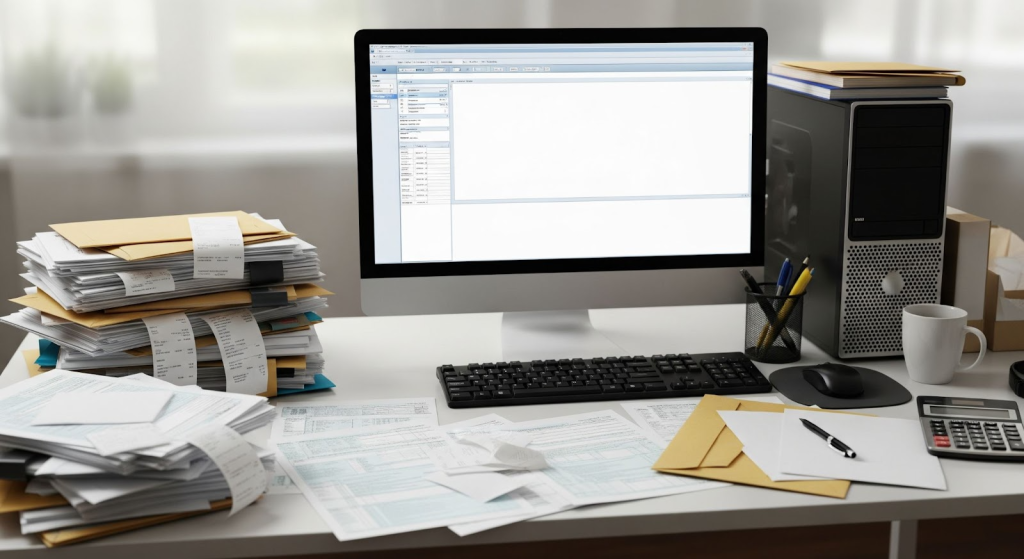
e-Taxは、国税に関する多岐にわたる手続きをインターネット経由で電子的に行うためのシステムです。確定申告の時期に特に注目されますが、その機能は年一回の申告に留まらず、日々の事業運営においても非常に有用なツールとなります。
e-Taxの対象となる税金と主な手続き
e-Taxの主な役割は、国税に関する申告、申請、届出、そして納税です。具体的には、以下のような幅広い税目が対象となります。
- 所得税
- 法人税
- 消費税および地方消費税
- 贈与税
- 相続税
- 酒税
- 印紙税
また、e-Taxはこれらの税金の申告だけでなく、事業運営で発生する様々な行政手続きにも対応しています。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)の提出
- 所得税の青色申告承認申請書の提出
- 納税証明書の交付請求
- 源泉所得税の納付手続き
- 納税地の異動に関する届出
これらの手続きを税務署の窓口に出向くことなく、自社のオフィスや自宅のパソコンから24時間(メンテナンス時間を除く)いつでも行える点は、事業者にとって計り知れないメリットと言えるでしょう。
e-Taxを利用する5つのメリット
e-Taxの導入は、単に手続きがオンラインになるだけでなく、多くの実利的なメリットをもたらします。ここでは特に重要な5つのメリットをご紹介します。
時間と場所を選ばない申告体制の構築
最大のメリットは、税務署の開庁時間に縛られず、自由な時間に申告手続きができる点です。特に確定申告シーズン中は、原則として24時間いつでも利用可能です。これにより、税務署へ移動する時間や長蛇の列で待つ時間が不要となり、その時間を本業や他の重要な業務に充てることができます。
還付申告における早期の資金回収
還付申告を行う場合、e-Taxを利用すると還付金の振り込みが大幅に早まります。書面での提出では、還付までに通常1か月から1か月半程度の期間を要しますが、e-Taxを利用した場合は約3週間程度で処理されます。この期間の差は、キャッシュフローを重視する事業者にとって、運転資金の効率的な活用に繋がり、決して無視できない利点です。
添付書類の一部の提出を省略可能
紙で申告書を提出する際に義務付けられている一部の添付書類について、e-Taxでは提出を省略できます。例えば、生命保険料控除証明書、医療費の領収書、寄附金の受領証などがこれに該当します。
ただし、これらの書類は法定申告期限から5年間、自宅や事務所で保管する義務があり、税務署から提示を求められた際には速やかに提出する必要がある点に注意が必要です。
青色申告特別控除の最大65万円適用
個人事業主にとって節税効果の面で非常に重要なのが、青色申告特別控除の扱いです。最大65万円の控除を受けるための要件の一つとして「e-Taxによる申告(電子帳簿保存法の要件を満たす場合は不要)」が定められています。
郵送や窓口で提出した場合、控除額は55万円に減額されてしまいます。この10万円の所得控除額の差は、所得税・住民税・国民健康保険料の負担軽減に直結するため、e-Taxの利用は必須と言えるでしょう。
会計ソフトとのデータ連携によるミスの防止と効率化
現在市販されている多くの会計ソフトは、e-Taxでの電子申告に対応したデータ形式で申告書を出力する機能を備えています。日々の取引を記録した会計ソフトから申告データを直接出力し、e-Taxソフトにインポートして送信できるため、手作業による転記ミスを根本的に防ぐことができます。
これにより、申告作業の正確性が向上し、時間も大幅に短縮されます。
e-Taxの始め方 2つの認証方式と準備
e-Taxを利用するためには、申告者が本人であることを証明するための認証が必要です。現在、主に2つの方式があり、どちらを選択するかによって準備するものが異なります。
マイナンバーカード方式
国が推奨している最も標準的でセキュリティレベルの高い方法です。今後の行政手続きのデジタル化を見据え、長期的な視点で導入するならばこちらの方式が賢明です。
- 必要なもの
- マイナンバーカード(電子証明書が格納されたもの)
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはICカードリーダライタ
- 手続きの流れ
- e-Taxの公式サイトにアクセスし、「ログイン」を選択します。
- マイナンバーカードでのログインを選び、スマートフォンの専用アプリで画面のQRコードを読み取るか、PCに接続したICカードリーダライタでカードを読み取ります。
- 画面の指示に従い、マイナンバーカード取得時に設定したパスワードを入力して認証を完了させます。
マイナンバーカードには本人確認のための電子証明書が内蔵されているため、別途証明書を取得する必要がなく、手続きが比較的スムーズに進みます。
ID・パスワード方式
マイナンバーカードを保有していない場合の暫定的な措置として用意されている方法です。
- 必要なもの
- 運転免許証などの本人確認書類
- 手続きの流れ
- 所轄の税務署の窓口へ行き、職員による本人確認を受けます。
- その場で「利用者識別番号(ID)」と「暗証番号(パスワード)」
が記載された書類が発行されます。 - 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、発行されたIDとパスワードを使ってログインし、申告書を作成・送信します。
この方法は、マイナンバーカードが普及するまでの過渡的な制度と位置付けられています。手軽に始められる反面、会計ソフトで作成した申告データを直接送信するような高度な機能には対応していない場合があるなど、機能面で制約があります。長期的にe-Taxを活用していくのであれば、マイナンバーカード方式への移行が推奨されます。
複数の自治体への手続きを一本化する「eLTAX」
eLTAXは、都道府県や市区町村といった複数の地方公共団体へ提出する地方税の手続きを、インターネットを利用して一元的に行うためのシステムです。特に、複数の都道府県や市区町村に事業所を展開する法人や、従業員を雇用し給与の支払いを行っている個人事業主にとって、そのメリットは絶大です。
eLTAXの対象となる税金と主な手続き
eLTAXは、主に事業活動に関連する地方税の手続きを幅広くカバーしています。
- 法人住民税・法人事業税・特別法人事業税の申告と納税
- 固定資産税(償却資産)の申告
- 事業所税の申告と納税
- 個人住民税(給与支払報告書の提出や特別徴収に関する手続き、納税)
- 法人設立・設置届出書、異動届などの各種申請・届出
これらの手続きは、従来であれば事業所が所在する各都道府県や市区町村の窓口へ個別に書類を提出する必要がありました。eLTAXを利用することで、これらの煩雑な手続きを一つの窓口で電子的に完結させることができます。
eLTAXを利用する4つのメリット
eLTAXの導入は、地方税に関する煩雑な事務作業を劇的に改善し、経理部門の生産性を大きく向上させます。
複数の提出先へ一度の操作で一括送信
eLTAXがもたらす最大のメリットは、複数の地方公共団体への申告データを一度の操作でまとめて送信できることです。
例えば、東京に本社、大阪と福岡に支店を持つ法人が法人住民税を申告する場合、従来は東京都、大阪府、大阪市、福岡県、福岡市へそれぞれ申告書を郵送または持参する必要がありました。eLTAXを使えば、作成した申告データを一度送信するだけで、システムが自動的にそれぞれの提出先に振り分けてくれます。
地方税の電子納税を一本化する「共通納税システム」
eLTAXには「共通納税システム」という強力な機能が備わっています。これを利用することで、複数の地方公共団体へ納付すべき地方税を、金融機関の窓口に出向くことなく電子的に一括で納税できます。
ダイレクト納付(指定口座からの引落し)、インターネットバンキング、クレジットカードなど、多様な支払い方法に対応しており、納税管理を一元化し、経理業務の負担を大幅に軽減します。
無料で利用可能な公式ソフト「PCdesk」
eLTAXでは、「PCdesk(ピーシーデスク)」という公式の無料ソフトウェアが提供されています。このソフトは、紙の申告書に近いレイアウトで直感的に入力できるほか、税額の自動計算機能も備わっており、申告書の作成を強力にサポートします。また、市販の主要な税務・会計ソフトで作成した申告データを取り込んで送信することも可能です。
事務負担の軽減とコスト削減
上記のメリットが総合的に作用し、地方税に関する事務作業全体の効率化に繋がります。申告書や納付書の作成、印刷、封入、郵送といった一連の作業が不要になることで、人件費、紙代、印刷代、通信費といった目に見えるコストの削減に直結します。
eLTAXの始め方 利用者ID取得から利用開始までの5ステップ
eLTAXの利用開始手続きは、e-Taxとは手順が異なり、特に利用するソフトウェアの種類に注意が必要です。
ステップ1 準備
利用を開始する前に、PC、インターネット環境、メールアドレスを準備します。また、申告データが本人によって作成されたことを証明するための電子署名を行う電子証明書が必要です。法人の場合は商業登記に基づく電子証明書などが、個人の場合はマイナンバーカードに搭載されている公的個人認証サービスなどが利用できます。なお、税理士に申告を依頼する場合は、納税者自身が電子証明書を用意する必要はありません。
ステップ2 利用届出(新規)
eLTAXの公式サイトにアクセスし、「PCdesk(WEB版)」というブラウザ上で動作するシステムから「利用届出(新規)」を行います。この画面で、会社の基本情報や申告書を提出する地方公共団体などを登録し、利用者IDを取得します。この手続き完了画面に表示される利用者IDと仮パスワードは非常に重要ですので、必ず印刷するかスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
ステップ3 「手続き完了通知」の受領
利用届出を提出してから数日から1週間程度で、登録したメールアドレスに「手続き完了通知」メールが届きます。この通知をもって利用者IDが有効化され、eLTAXの各種サービスを利用できる状態になります。
ステップ4 申告用ソフト「PCdesk(DL版)」のインストール
ここがeLTAX導入で最もつまずきやすいポイントです。利用登録は「PCdesk(WEB版)」で行いましたが、実際の申告書の作成や送信は「PCdesk(DL版)」という、パソコンにインストールして使用する別のソフトウェアで行います。eLTAXのサイトからPCdesk(DL版)をダウンロードし、お使いのパソコンにインストールしてください。
ステップ5 申告・納税の開始
インストールしたPCdesk(DL版)を起動し、ステップ2で取得した利用者IDとパスワードでログインします。その後、画面の指示に従い、申告データの作成(または会計ソフトからのインポート)、電子署名の付与、送信といった手順で電子申告を行います。共通納税システムを利用した電子納税も、このPCdesk(DL版)から手続きを行います。
e-TaxとeLTAXの連携に関する重要な注意点
e-TaxとeLTAXはそれぞれ独立したシステムですが、両者の間には手続きの手間を大きく左右する重要な連携関係が存在します。この関係性を正しく理解しているかどうかが、申告業務の効率化、ひいては申告漏れという重大なミスの防止に直結します。
個人事業主はe-Taxでの確定申告で完結
個人事業主の方にとって、これは非常に重要なポイントです。所得税の確定申告をe-Taxで行った場合、その申告データに含まれる住民税や事業税に関する事項が、国税庁から管轄の市区町村へ自動的にデータ連携される仕組みになっています。
この連携により、個人事業主は別途、住民税申告書や事業税申告書を市区町村や都道府県へ提出する必要がなくなります。つまり、個人事業主の所得に関する申告は、e-Taxを利用するだけで国税(所得税)と地方税(住民税・事業税)の両方を一度に済ませることができるのです。この便利な仕組みは、必ず覚えておきましょう。
法人はe-TaxとeLTAX両方での申告が必須
一方で、法人の場合は手続きが全く異なります。法人がe-Taxを利用して税務署へ法人税や消費税の申告を完了しても、その情報が自動的に地方公共団体へ送られることはありません。地方税の申告は、別途eLTAXを利用して行う必要があります。
したがって、法人は必ず以下の二つの手続きを個別に行わなければなりません。
e-Taxを利用して、所轄の税務署へ法人税・消費税などの国税を申告する。
eLTAXを利用して、事業所のある都道府県・市区町村へ法人住民税・法人事業税などの地方税を申告する。
この違いは、特に個人事業主から法人成りした経営者や経理担当者が見落としがちな、極めて重要なポイントです。個人事業主時代の感覚で「e-Taxで申告したから全て完了した」と思い込んでしまうと、地方税の申告漏れとなり、本来納めるべき税額に加えて延滞税や過少申告加算税といったペナルティが課されるリスクがあります。
「法人はe-TaxとeLTAXの両方で申告が必要」と明確に認識しておくことが、コンプライアンス遵守の観点からも極めて重要です。
電子申告の導入前に確認すべき共通の注意点

電子申告への移行をスムーズに進めるために、最後にいくつかの共通の注意点を確認しておきましょう。
事前準備には相応の時間がかかる
e-Taxの利用に必要なマイナンバーカードの取得や、ID・パスワード方式のための税務署訪問、eLTAXで必要となる電子証明書の取得や利用者IDの発行など、どちらのシステムも利用を開始するまでにはある程度の準備期間を要します。
申告期限の直前になって慌てることのないよう、少なくとも1か月程度の余裕を持ったスケジュールで準備に着手することをお勧めします。
システムには利用可能時間がある
オンラインサービスとはいえ、24時間365日いつでも利用できるわけではありません。e-Tax、eLTAXともに、システムメンテナンスのために利用できない時間帯が設けられています。
通常、平日の8時30分から24時までが基本の稼働時間ですが、確定申告期間中は土日祝日も稼働するなど、時期によって変動します。利用する際は、必ず各システムの公式サイトで最新の稼働時間を確認する習慣をつけましょう。
eLTAXは自治体によってサービス内容が異なる場合がある
eLTAXは全国のほとんどの地方公共団体が参加するシステムですが、提供されているサービス内容は自治体によって若干異なる場合があります。
例えば、一部の税目(事業所税など)の電子申告に対応していなかったり、特定の申請手続きが電子化されていなかったりするケースが考えられます。利用を検討している手続きについて、自社の事業所が所在する自治体で対応しているか、事前にeLTAXの公式サイトで確認することが重要です。
まとめ
今回は、混同されがちなe-TaxとeLTAXの違いについて、それぞれの役割からメリット、導入方法、そして実務上の注意点までを網羅的に解説しました。最後に、本記事の最も重要なポイントを再確認しましょう。
- e-Taxは「国税」(所得税、法人税など)の申告・納税システムです。
- eLTAXは「地方税」(住民税、事業税など)の申告・納税システムです。
- 個人事業主の確定申告は、e-Taxだけで住民税・事業税の申告も完了します。
- 法人は、e-Tax(国税)とeLTAX(地方税)の両方で、それぞれ申告が必要です。
これらの電子申告システムを導入するには、初めに一定の学習と準備の時間が必要となることは事実です。しかし、その初期投資を乗り越えれば、その後のバックオフィス業務の効率は飛躍的に向上します。
税務署や金融機関への移動時間、待機時間の削減、ペーパーレス化によるコスト削減と情報管理の効率化、そして何より、経営者や担当者が本来注力すべきコア業務に集中できる環境が手に入ります。
デジタル化が加速する現代において、電子申告はもはや特別な選択肢ではなく、事業を継続・成長させるためのスタンダードな業務インフラとなりつつあります。この機会に、ぜひe-TaxとeLTAXの導入を本格的に検討し、スマートで生産性の高い税務手続きを実現してください。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…