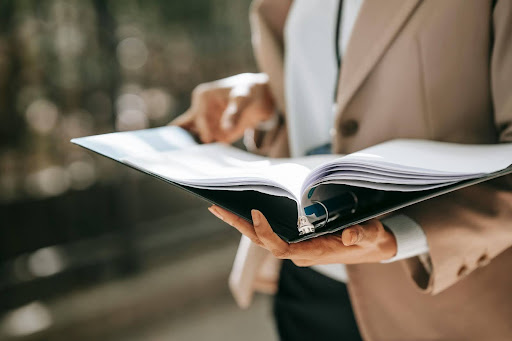
あなたはビジネスメールや郵便物の宛先で「気付」という言葉を目にしたことがあるでしょうか。
郵便物の宛先欄に記載されたこの「気付」の正しい意味や使い方がわからず、戸惑ってしまった経験がある方もいるかもしれません。
特に社会人になりたての方や学生の方にとっては、郵便物の宛名マナーは難しく感じることが多いでしょう。
本記事では、「気付」の意味と読み方から始め、ビジネスシーンでの正しい使用方法、そして「様方」や「御中」との違いや併用のルールを解説します。
さらに、ホテル・職場・実家などシーン別の具体的な宛名の書き方や例文も多数紹介します。最後に、よくある疑問をQ&A形式で取り上げ、「気付」にまつわる間違いやすいポイントをわかりやすく解説します。
それでは、「気付」の正しい使い方を一緒に学んでいきましょう。
目次
気付の意味と読み方
「気付」は漢字で書いて「きづけ」または「きつけ」と読みます。郵便物の宛先に添える言葉で、受取人(届けたい相手)の自宅や本来の住所ではなく、その人が一時的に滞在している別の場所に郵便物を送る際に用いられます。
相手が直接受け取れる場所ではないため、「確実に本人に届けてほしい」という注意喚起・依頼の意味が込められているのが特徴です。「~に気を付けて届けてください」というニュアンスから生まれた表現とも言われます。
例えば、出張中の上司が滞在しているホテルや、友人が入院している病院宛てに書類や手紙を送るようなケースで「気付」を使います。
宛名に「○○ホテル気付 △△様」といった形で記載すれば、ホテルのフロント係の人がその郵便物を受け取り、一時預かってから△△様に手渡してくれるという流れになります。
このように「気付」は、届け先の施設や第三者を通じて確実に相手に届けてもらうための言葉なのです。
読み方について補足すると、「気付」は濁って「きづけ」と読むのが一般的ですが、古い慣用で「きつけ」と読む場合もあります。
また、よく似た言葉に「気付き(きづき)」がありますが、これは「気が付くこと」つまり「新たな発見・悟り」という意味であり、宛先に使う「気付」とは全く別の言葉です。
ここで解説する「気付」は、あくまで郵便物の宛先に付ける特殊な用語だと覚えておきましょう。
一般的な用法と注意すべき誤用例
「気付」はあくまで郵送先が相手本人の住所ではない場合にのみ使用します。裏を返せば、相手の自宅や普段勤務している職場に送る郵便物には「気付」を付ける必要はありません。
例えば相手が会社員で、その人の勤め先に書類を郵送する場合、勤務先住所はその相手自身が所属する場所ですから「気付」を使わず、通常どおり会社名と部署名、相手の氏名(様)を宛名として書けば問題ありません。
なお、「気付」は正式な表記では漢字で記載します。ひらがなで「きづけ」と書くことはせず、必ず「気付」と漢字で丁寧に書きましょう。
「気付」を使う際の基本ルールとして、必ず受取人の名前を後ろに続けます。「気付 ○○様」という形で初めて効力を持つ表現であり、「気付」だけを単独で記載することはありません。
また、「気付」は住所欄の末尾に書き、宛名(受取人の氏名)とは別の行に分けるのが正しい書き方です。同じ行に「○○気付△△様」のように続けて書いてしまうと、宛先が非常に読みにくくなり誤配のもとになります。
封筒の表書きを縦書きにする場合も、住所の最後に「気付」と書いたところで改行し、次の行に受取人名を書くようにしましょう。
さらに、誤用例としてよくあるのが、「気付」を付けなくてもよい場面で使ってしまうケースです。前述の通り、相手が通常所属している場所(自宅や自社オフィス)に送るなら「気付」は不要です。
逆に、相手が一時的に滞在している場所に送るべきなのに「気付」を書き忘れてしまうのも問題です。
例えばホテル側が転送郵便物だと気付かず、受取人に渡してもらえない可能性もありますので、必要な場面では必ず「気付」を添えましょう。
なお、他人の家に居候している相手へ郵送する場合は「気付」ではなく「様方(さまがた)」を使います(この違いについては後ほど詳しく解説します)。
また「気付」はあくまで受取人以外の場所・人を経由することを示す言葉ですので、「○○様方△△様気付」のように「様方」と併記したり、「気付」に「様」を付けたりすることはありません。
不安な場合は、本記事で取り上げる正しい用例を参考にして、誤った使い方をしないよう注意しましょう。
ビジネスメール・郵便物における「気付」の正しい使い方
ビジネスシーンで郵便物を送る際、「気付」を正しく使いこなせると非常に役立ちます。封筒の宛名書きでは、住所を書いた最後に「◯◯会社 気付」といった形で一旦区切り、その下の行に相手の氏名と敬称(様)を記載します。
ポイントは、「気付」は住所欄に属する情報だということです。宛名(相手の名前)と混同しないよう、必ず改行して分けて書きましょう。
また、企業名や施設名などが長い場合でも、「気付」の文字自体は小さめに書き添え、受取人の氏名が目立つように配慮すると良いでしょう。
もし封筒ではなく社内メール(電子メール)の場合、「気付」の出番は基本的にありません。メールは相手個人のアドレスに直接届くため、わざわざ第三者を経由する概念がないからです。
例えば同僚に代わりに転送してもらう必要がある場合でも、CCや転送機能を使えば済みますので、「気付」といった表記をメール本文に書くことは通常ありません。
したがって、「気付」は紙の郵便物における宛名マナーと覚えておきましょう。
ビジネスでは、取引先からの資料返送用に宛名が印刷された返信用封筒が同封されていることがあります。その宛名欄に「気付」が含まれている場合、絶対にその「気付」の文字を消してはいけません。
依頼主が「この住所(施設)を経由して自分に届けてほしい」という意図で記載しているためです。
一方で、返信用封筒に印刷された宛名に「○○行」や「○○宛」となっている場合には、その部分を二重線で消し、個人宛なら「様」、会社宛なら「御中」に書き換えるのがマナーです(「行」「宛」は差出人が自分をへりくだって書いている表記なので、受取側で訂正します)。
「気付」については消さず、印刷どおりに利用しましょう。
気付と「御中」「様方」の違いと敬称の使い分け
郵便物の宛名で「気付」と合わせて覚えておきたいのが「御中」と「様方」です。これらは用途や意味が異なりますが、混同しやすいポイントでもありますので整理しておきましょう。
まず「御中(おんちゅう)」は、会社・団体・部署など宛先が個人ではない場合に付ける敬称です。
宛名が個人名でなく「○○株式会社」「△△部」のような組織名の場合、その後に「御中」を添えることで「○○会社の皆様へ」「△△部のみなさまへ」という意味になります。
例えば、取引先の総務部あてに書類を送るときは宛名を「○○商事株式会社 総務部 御中」とします。
一方で、個人名には「御中」を使いません。
個人宛には後述の「様」を使いますが、「会社名+御中」と「個人名+様」を同じ宛名内で併用することはない点に注意しましょう(宛名が長くなる場合は、会社名と担当者名を別の行に分け、「御中」と「様」をそれぞれ対応する位置につけます)。
次に「様方(さまがた)」です。これは送り先の住所にある世帯主の名字と受取人の名字が異なる場合に使う表記です。
たとえば、親戚の家に一時的に身を寄せている人や、苗字の異なる友人宅に下宿している学生に手紙を送る場合に「様方」を使います。
具体的には、鈴木さんの家に山田さんが居候している場合、宛名は「鈴木太郎様方 山田花子様」となります(鈴木さんを経由して山田さんへ届けるイメージ)。逆に、送り先の世帯主と受取人が同じ苗字であれば一種の家族扱いとなるため、「様方」は付けません。その場合は単に氏名(様)だけを書けば郵便は届きます。
それでは、「気付」と「様方」はどのように使い分けるのでしょうか。簡単に言えば、経由先が個人の家であれば「様方」、経由先が会社や施設であれば「気付」を使います。
たとえば実家や知人宅を経由するなら「様方」、ホテル・会社・学校・病院などを経由するなら「気付」です。両者を同時に用いることはないため、「○○様方△△様気付」のような併記は誤りです。
最後に「気付」と「御中」の併用について補足します。「気付」と「御中」は同じ宛名内で併用するケースがあります。 それは、送りたい会社や団体が別の企業や施設に入っている場合です。
例えば、株式会社B宛ての郵便物を、そのB社がオフィスを借りている株式会社Aの住所に送るようなとき、「住所~ ○○市△△1-1 A株式会社 気付 株式会社 御中」という形で記載します。
経由先としてA社名に「気付」を付け、最終的な送り先としてB社名に「御中」を付けるわけです。
このように、宛名が法人の場合は「御中」、経由地が法人の場合はその名前の後に「気付」を使い分け、状況に応じて両方を使うことも覚えておきましょう。
気付を使うシーン別の宛名書き例
では、具体的にどのように「気付」を書き入れるか、シーンごとの例を見てみましょう。それぞれの状況に応じた宛名書きのポイントと例文を紹介します。
ホテルに滞在中の相手に送る場合
出張先や旅行先のホテルにいる相手へ荷物や書類を送りたいときは、ホテル名に「気付」を添え、その人の名前(様)を宛名とします。ホテル側が荷物を預かり、フロント等で保管して本人に渡してくれます。
郵便物が確実に届くように、滞在しているホテルの正式名称で記載しましょう。
宛名書き例(ホテル宛て封筒の記載例)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
帝国ホテル東京 気付
田中太郎様
病院に入院中の相手に送る場合
入院患者宛てに手紙や品物を送る場合も、「気付」を使います。病院の住所を書いた後、病院名に「気付」を付け、次の行に患者さんの名前(様)を記載します。入院している科や病棟がわかれば住所欄に併記するとより確実です。
宛名書き例(病院宛て封筒の記載例)
〒105-0000 東京都港区芝公園1-1-10
国立東京医科センター 気付
山田花子様
他社オフィスに常駐している人に送る場合
取引先企業Aのオフィスに、別の会社Bの社員が常駐して働いているケースがあります。例えばB社の山田さんがA社内で勤務している場合、山田さん宛ての郵便物はA社の住所に送ります。
宛名はA社名に「気付」を付け、最終的に届けたい人物である山田さんの氏名(様)を書きます。
宛名書き例(他社オフィス宛て封筒の記載例)
〒140-0000 東京都品川区東品川2-2-4
ABC株式会社 気付
山田太郎様
※山田さんの所属(B社名)は宛名に含めなくても構いません。A社の郵便受付担当者が山田さんの名前宛の郵便であると認識できれば、社内の山田さんの元へ届けてもらえます。
親戚や知人の家に送る場合(「様方」の例)
相手が自分の家ではなく、親戚や友人の家から郵便物を受け取る場合、その家の世帯主の名字と受取人の名字が異なれば「様方」を使います。
経由先となる世帯主を立てる形で、「○○様方 △△様」と記載することで「○○様のお宅にいらっしゃる△△様宛」という意味になります。
宛名書き例(様方を用いた封筒の記載例)
〒180-0000 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-2
佐藤太郎様方
鈴木花子様
上記の例では、佐藤さん宅に滞在している鈴木さん宛ての郵便という意味になります。なお、受取人と世帯主が同じ苗字の場合は「様方」は不要で、単に受取人名(様)を書くようにしましょう。
企業が他社オフィスに間借りしている場合
送り先の会社が自社ビルを持たず、他社のオフィススペースを借りている場合にも「気付」を活用できます。
郵便物は間借り先の企業に届きますので、その企業名に「気付」を付け、宛名には最終的に届けたい会社名を記し「御中」を添えます。
宛名書き例(会社宛て封筒の記載例)
〒150-0000 東京都渋谷区渋谷1-1-7
ABC株式会社 気付
XYZ株式会社 御中
このように記載すれば、ABC株式会社(間借り先)の受付担当者が郵便物を受け取り、XYZ株式会社宛ての書類であることを認識して取り次いでくれます。
結婚式場・葬儀場に電報を送る場合
結婚披露宴の会場や、お通夜・葬儀が行われる斎場へ電報(祝電・弔電)を送るケースでも「気付」を使用します。
基本的な書き方は郵便と同じで、会場(式場や葬儀場)の名前に「気付」を付け、次の行に宛名として届けたい相手の名前を書きます。
祝電の場合は新郎新婦の名前(様)を、弔電の場合は故人のご家族(喪主)の名前(様)を宛名に記載するのが一般的です。
宛名書き例(弔電を葬儀場に送る場合の記載例)
○○斎場 気付
(喪主である田中花子)様
結婚式場に送る場合も、「○○式場 気付 ○○(新郎新婦)様」といった形になります。なお、自宅宛てに電報を送る場合は通常「気付」を使いません(自宅にいない場合を除く)。
SNSやWeb上での「気付」の表記・用法について
現代ではメールやSNSなどオンラインでのやり取りが主流となり、「気付」という表現が登場する機会は少なくなっています。
TwitterやInstagramなどで個人宛のメッセージを届ける際に「誰々さん気付で送ってください」と書くことはまずありません。
デジタル通信では宛先に直接コンタクトできるため、第三者を経由する必要がないからです。
ただし、企業やイベントの公式サイト上で連絡先住所を掲載する場合などには、「気付」を用いた住所表記が登場することがあります。
例えば、ある団体が他の施設内に事務所を置いている場合、Web上の問い合わせ先住所に「○○ホール気付 △△イベント事務局」といった記載がされることがあります。このような場合も書き方のルールは封筒の宛名と同じです。
SNS上ではむしろ、「気付ってどういう意味?」と疑問に思った人が検索したり質問したりする光景が見られます。本記事をご覧の方も、Webで情報を探して「気付」の意味に辿り着いたのではないでしょうか。
ネット上で話題になること自体が少ない用語ですが、いざというときに正しく使えるよう知識として押さえておきましょう。
「気付」に関するよくある質問
最後に、「気付」の使い方について読者から寄せられがちな疑問をQ&A形式でまとめました。うっかり間違えやすいポイントを再確認しておきましょう。
Q: 「気付」は何と読み、どんな意味ですか?
A: 「気付」は「きづけ」と読みます(「きつけ」と読むこともあります)。郵便物の宛先に添える言葉で、送り先が相手本人の住所ではなく別の場所に一時的に滞在している場合に「経由先」を示す意味で使われます。
いわば「○○経由で△△さんに届けてください」というお願いの表現です。なお、「気付き(きづき)」という言葉(気が付くことを意味する)は別物なので混同しないようにしましょう。
Q: 相手の自宅に送る場合も「気付」を付けるべきですか?
A: いいえ、相手の自宅宛てであれば「気付」は不要です。「気付」はあくまで相手が不在の場所(自宅以外)に郵送物を送る場合にのみ使うものです。
同様に、相手が普段勤務している職場宛てに送る場合も「気付」は付けません(勤務先住所は本人が所属する場所なので直接届けば問題ありません)。
Q: 「様方」と「気付」はどう使い分けるのですか?
A: 「様方(さまがた)」は、送り先の住所の世帯主と受取人の苗字が異なるとき、その世帯主を経由して送ることを示す表現です(例:「鈴木太郎様方 山田花子様」)。
一方、「気付」は世帯以外の施設や企業などを経由する場合に使います(例:「○○ホテル気付 山田花子様」)。
送り先が個人の家なら「様方」、会社やホテルなどなら「気付」と覚えるとよいでしょう。両方を同時に使うことはありません。
Q: 「御中」と「気付」は一緒に使えますか?
A: はい、使えます。宛名が会社や団体の場合、「御中」はその名前に付けます。そして経由地として別の会社名を書く必要がある場合、その会社名に「気付」を付けます。
たとえば「A社 気付 B社 御中」のように書けば、A社を経由してB社に届けるという意味になります。
Q: 返信用封筒に「○○気付△△」と印刷されていました。この「気付」は消した方がいいですか?
A: 消さずにそのまま使ってください。返信用封筒に「気付」の記載があるのは、送り主が「この住所(施設)経由で自分に届けてほしい」という意図を示しているためです。消してしまうと郵便が届かない恐れがあります。
なお、宛名に「行」や「宛」と印刷されている場合は二重線で消して「様」や「御中」に直しましょう。「気付」の部分は消さずに残すのが正解です。
Q: メールやSNSで「気付」を使うことはありますか?
A: 通常、メールの宛先やSNS上のメッセージで「気付」を使うことはありません。メールは相手のメールアドレスに直接届きますし、SNSのDM(ダイレクトメッセージ)なども相手本人に直接送られるものです。
郵送とは違い、第三者に取り次いでもらう必要がないため、オンライン上で「気付」を用いる場面はないと考えてよいでしょう。
以上、「気付」の意味や使い方について詳しく解説しました。正しいルールを理解しておけば、いざというときにスムーズに対応できます。
宛名マナーはビジネスや日常の信頼感にもつながりますので、この記事を参考に、「気付」を適切に使いこなし、大切な郵便物を確実に届けましょう。今後、宛名を書いていて迷ったときは、ぜひ本記事の内容を思い出してみてください。








建設業の2024年問題に向き合う|作業日報の効率化とDXで実…
日々の作業日報に追われる時間を短縮し、しっかりと休息を取る。あるいは、家族と過ごす時間を少しでも増や…