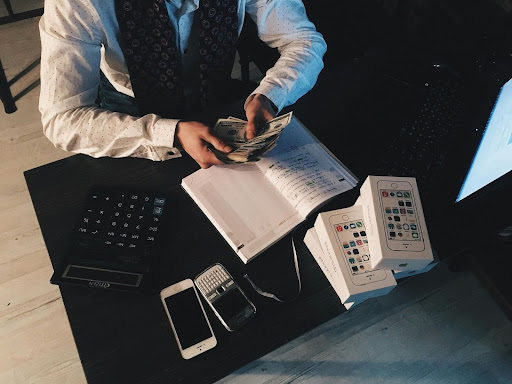
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から始まった新しい消費税の請求書ルールです。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として税務署に登録した事業者が発行する、一定の項目を満たした請求書(インボイス)を保存することで、仕入れ時に支払った消費税を控除できる仕組みになりました。
これにより、個人事業主や中小企業にも経理対応や税務負担の変化が生じています。
本記事では「インボイス 補助金 個人事業主」という検索意図にお応えし、フリーランス・個人事業主や中小企業経営者、税理士の方々に向けて、インボイス制度の概要と影響、そしてインボイス制度に関連する補助金・支援策について詳しく解説します。
さらに、補助金の申請条件や申請方法、注意点やサポートツール、今後の変更点にも触れます。インボイス対応に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
インボイス制度の概要と中小事業者への影響
まずはインボイス制度そのものを簡単に押さえておきましょう。制度のポイントと、小規模事業者への主な影響を解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式が変わる制度です。具体的には、仕入れや経費にかかった消費税を差し引く(控除する)ために、「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。
適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみがインボイスを発行でき、請求書には以下のような事項を記載することが義務付けられます。
- 請求書発行者の氏名・登録番号
- 取引日付・取引内容・対価の金額
- 消費税額または税率ごとの税込金額
- 取引先(受領者)の氏名 など
これにより、買い手側は受け取ったインボイスを保存することで仕入税額控除が可能となり、売り手側はインボイス発行のために消費税の計算・申告が必要になります。
インボイス制度による主な影響
インボイス制度の導入は、特にフリーランスや小規模企業にとって次のような影響を及ぼします。
経理・事務作業の増加
インボイス発行事業者の登録申請や、請求書様式の変更、インボイスの保存管理など、新たな事務対応が発生します。今まで免税事業者だった人も、発行事業者として登録すれば消費税の申告と納税が必要になり、経理処理が煩雑になります。
システム導入や設備投資の必要
請求書発行や帳簿管理を効率化するため、会計ソフトやレジシステムのアップデート、パソコン・タブレットの導入などを検討する事業者が多いです。インボイス制度対応のITツールを導入することで事務負担を軽減できますが、そのための初期費用が発生します。
消費税の負担増
これまで売上規模が小さく消費税の納税義務が免除されていた免税事業者も、インボイス発行事業者になるには課税事業者(消費税の納税義務者)になる必要があります。
課税事業者となると、売上に対する消費税を預かり、仕入税額控除をした上で差額を納税しなければなりません。そのため、実質的な手取り収入が減少する可能性があります。
例えば年間売上が1,000万円以下の個人事業主がインボイス発行事業者になると、今後は売上に含まれる消費税を納税しなければならず、負担増となります。
取引機会への影響
インボイスを発行できないままだと、取引先(買い手)は仕入税額控除ができず不利になるため、取引継続が難しくなるリスクがあります。
特にBtoB取引では「インボイス発行事業者でないと取引しない」という方針の企業も出てくる可能性があり、フリーランスや小規模事業者でも顧客からインボイス発行への対応を求められるケースが多いです。
以上のように、インボイス制度は事業運営に様々な変化をもたらします。こうした負担や不安を軽減するため、政府や各種団体は補助金・助成金による支援策を用意しています。
次の章では、個人事業主や中小企業経営者が利用できるインボイス制度関連の補助金について詳しく見ていきましょう。
インボイス制度に関連する補助金・助成金
インボイス制度対応に伴う経済的負担を和らげるため、政府は既存の補助金制度に「インボイス対応」の特例や枠組みを設けています。個人事業主から中小企業まで広く対象となっており、条件を満たせばこうした支援策を利用することができます。
ここでは主要な補助金・助成金を紹介し、その概要や特徴を解説します。
▼ 主なインボイス対応関連の補助金・助成金一覧
| 制度名(支援策) | 対象となる事業者(主な条件) | 補助率・上限額(インボイス特例) | 特記事項・補足 |
| IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠・インボイス対応類型) | 中小企業・小規模事業者(法人/個人事業主)※業種要件あり | 補助率1/2〜3/4(経費区分による)上限:350万円 | 会計ソフトや受発注システム、PC等の導入費用を補助。インボイス制度対応ツールも対象。申請にはgBizID要取得。 |
| 小規模事業者持続化補助金(インボイス特例あり) | 小規模事業者(常時雇用<=5人※商業サービス業等)※個人事業主・フリーランス含む | 補助率2/3(通常枠)上限:50万円(通常枠)+インボイス特例50万円 = 最大100万円 | 販路開拓や事業継続の取組を補助。インボイス発行事業者に登録した元免税事業者は上限+50万円。商工会議所等の支援書類が必要。 |
| ものづくり補助金(生産性向上促進補助金) | 中小企業・小規模事業者(製造業等幅広い業種) | 補助率2/3以内上限:750万円〜1,250万円程度(枠により変動) | 業務効率化や制度変革対応のための設備投資等を補助。インボイス対応や働き方改革などの取組も対象。電子申請(gBizID要)。 |
| 業務改善助成金(厚労省管轄の助成金) | 中小企業・小規模事業者(事業内最低賃金要件あり)※従業員ありの場合に利用可 | 補助率3/4〜9/10(企業規模・賃上げ幅による)上限:50万円〜数百万円超(引上げ額・人数による) | 生産性向上の設備投資と賃金引上げを行う場合に経費の一部を助成。インボイス対応機器導入も対象になり得る。賃金を一定額以上引上げることが条件。 |
| 事業再構築補助金(事業再構築促進事業) | 中小企業・中堅企業(コロナ等で売上減少or新分野展開) | 補助率2/3以内上限:最大8,000万円(通常枠、小規模企業は上限6,000万円) | 業態転換や新市場進出を支援する大型補助金。インボイス制度への対応を機に事業再編を図る場合などに活用可能。要事前計画策定。 |
それでは、各補助金・助成金について個別にもう少し詳しく見ていきます。
IT導入補助金(インボイス対応のデジタル化基盤導入枠)
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールを導入して業務効率化や売上アップを図る際に、その費用の一部を補助してもらえる制度です。インボイス制度開始に伴い、IT導入補助金の中に「デジタル化基盤導入枠(インボイス対応類型)」が設けられています。
これは、会計ソフト・受発注システム・決済システムなどインボイス制度対応に役立つITツールの導入を支援する枠組みで、パソコンやタブレット、対応レジ等のハードウェア購入費も補助対象になっている点が特徴です。
対象事業者
インボイス対応のITツール導入によって業務効率化を目指す中小企業・小規模事業者(法人・個人事業主)。業種により資本金や従業員数の制限がありますが、ほとんどの中小企業が該当します。個人事業主やフリーランスも、要件を満たせば申請可能です。
補助率・上限額
購入するツールや費用区分によって補助率が異なりますが、おおむね1/2以内〜3/4以内と高い補助率が設定されています。上限額は通常枠で350万円程度までとされており、中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に後押しする内容です。
特に、会計・受発注・請求管理などインボイス対応機能を有するソフトウェアについては手厚い補助が受けられます。
主な対象経費
クラウド会計ソフト、受発注管理システム、請求書発行システム、POSレジ、電子決済端末、そしてそれらを動かすためのPC・タブレット端末やプリンター等の購入費用まで幅広くカバーします(インボイス対応類型に限りハードウェアもOK)。
たとえば「インボイス制度対応版の会計ソフトを導入したい」「電子帳簿保存法も踏まえてシステムを一新したい」といった場合に、この補助金を活用すれば費用の1/2〜2/3(場合によっては3/4)が補助されるため、自己負担を大きく減らせます。
申請のポイント
IT導入補助金は基本的に事前に登録されたITツールのみ補助対象となるため、まずは公式サイトで補助金対象となっているソフトウェア・サービスを探す必要があります。
次に、それらを提供するIT導入支援事業者(補助金の手続きをサポートしてくれる販売事業者)を通じて申請する流れになります。
また、電子申請システム(jGrants)での手続きとなるためgBizIDプライムの取得が必須です(取得に2週間程度かかるので早めに準備しましょう)。インボイス関連の経費で補助を受けたい場合は、このインボイス対応類型の公募に応募する形になります。
※補助例: 例えば50万円の会計ソフト導入費用を申請した場合、補助率3/4が適用されれば37万5千円が補助され、自己負担は12万5千円で済みます。また、パソコンやプリンター購入費10万円について補助率1/2なら5万円が補助されます。
このように、インボイス制度対応のIT環境整備を低コストで実現できるチャンスです。
小規模事業者持続化補助金(インボイス特例あり)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、小規模事業者が経営計画に基づいて行う販路開拓や業務効率化等の取り組みに対し、経費の一部を補助する制度です。
従来より販促費や設備導入費など幅広い用途で使えるため、個人事業主を含む小規模事業者によく利用されています。この補助金にもインボイス制度に関連した特例措置が追加されています。
対象事業者
小規模事業者であることが条件です。小規模事業者とは業種ごとに定義があり、例えば商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)では常時使用する従業員数5人以下、製造業その他では20人以下となっています。
多くの個人事業主やフリーランスは従業員がいないかごく少数でしょうから、この人数要件はクリアできます。会社組織でも上記従業員数以内なら対象です。なお、商工会議所や商工会の管轄地域で事業を営んでいることも必要です(申請時に商工会議所等のサポートを受けるため)。
補助率・上限額
補助率は基本的に2/3以内(対象経費の3分の2まで補助)で、上限額は通常50万円(一般型・通常枠の場合)です。ただしこの補助金にはさまざまな特別枠があり、例えば賃上げ等を行う特別枠では上限200万円など拡大措置があります。
そしてインボイス特例として、免税事業者から課税事業者(適格請求書発行事業者)に転換した場合は上限額が一律50万円上乗せされます。つまり通常枠であれば上限50万円→100万円に、賃上げ特例枠なら上限200万円→250万円に、それぞれ引き上げられます。
インボイス特例の条件
上乗せ措置を受けるには、「2023年10月のインボイス制度開始に合わせて免税事業者だった小規模事業者がインボイス発行事業者に登録し、課税事業者となったこと」が条件です。
要するにインボイス対応のため消費税を納めることになった小規模事業者への特別支援です。申請時にはインボイス発行事業者の登録通知書の写しや、課税事業者選択届出書の控えなどを提出して、要件を満たすことを示す必要があります。
補助対象となる経費
持続化補助金は使途の幅が広く、広告宣伝費、販促品制作、ホームページ作成、業務用機器購入、システム導入、研修費、展示会出展費など事業計画の達成に必要なほとんどの経費が対象になります。
インボイス制度対応に絡めて言えば、「請求書発行システムを導入して取引先に適格請求書を発行できるようにする」「インボイス対応を周知するためWebサイトを改修する」「消費税分の値上げに対応するため新サービスを開発・PRする」といった取り組みも計画に盛り込めるでしょう。
申請のポイント
申請には経営計画書と補助事業計画書を作成し、所轄の商工会議所または商工会から事業支援計画書(支援機関による助言計画書)を発行してもらう必要があります。これは事前に商工会議所等に相談し、計画内容の妥当性について確認・助言を受けるプロセスです。
計画書には、自社の強み弱み分析や今後の方針、具体的な補助事業の内容、そして経費明細などを書きます。インボイス特例を使う場合でも、補助金の使い道自体は販路開拓や業務効率化に資する内容である必要があります。
書類準備は手間ですが、地域の商工会などが丁寧にサポートしてくれますので、積極的に相談しましょう。
※補助例: 例えばデザイン業のフリーランスが、インボイス発行に伴う会計ソフト導入費5万円と、営業強化のためのホームページ改良費45万円を計画したとします。合計50万円の経費に対し2/3補助なら約33万円が補助されます。
さらに自身が免税→課税に転換したケースなら上限引上げで満額補助が受けられる可能性が高まり、自己負担17万円程度で必要な投資ができる計算です。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(いわゆるものづくり補助金)
一般にものづくり補助金と呼ばれるこの制度は、中小企業が生産性向上や業態転換のために行う設備投資やシステム導入、新サービス開発等を支援する大型の補助金です。
インボイス制度そのものに特化した補助金ではありませんが、「インボイス対応や働き方改革、最低賃金引上げなど制度変更への対応に苦労する事業者を下支えしつつ、革新的な取り組みを支援する」という位置づけがあり、インボイス制度への対応費用も幅広いプロジェクトの一環として認められるケースがあります。
対象事業者
中小企業基本法で定める中小企業および小規模事業者が対象です。製造業だけでなく商業・サービス業も対象枠があります。何らかの新規性・革新性のある取り組み(例:新商品の開発、生産ラインの合理化、新サービスの創出)を行う意欲が求められます。
インボイス対応のみを理由に申請するのは難しいですが、例えば「インボイス対応のため受発注フローを電子化し、それに合わせてサービス提供プロセスを刷新する」といった業務プロセス変革につなげる計画であれば対象になり得ます。
補助率・上限額
補助率は基本2/3以内(中小企業の場合)です。小規模事業者や一定条件を満たす企業は一部経費について3/4や4/5といった優遇があることもあります。
上限額は事業の類型によって異なり、通常枠で750万円または1,250万円程度が一般的です(過去の公募では設備投資額に応じてA類型750万、B類型1,250万など)。非常に規模の大きなプロジェクト向けには上限数千万円の特別枠もあります。
補助対象経費
機械装置費、システム購入費、技術導入費、専門家経費、運搬費、建物改修費など広範囲です。
たとえば「インボイス対応をきっかけに業務のデジタル化を進め、受発注から請求・在庫管理まで一元化できるシステムを導入する」ような場合、そのシステム導入費や関連機器購入費、人件費の一部まで補助対象となります。
また製造業であれば、生産プロセスを自動化する機械の導入など、生産性向上につながる投資を幅広くカバーします。
申請のポイント
ものづくり補助金は事業計画の革新性や市場の成長性などが重視されるため、申請書の作り込みが重要です。
インボイス対応だけでは「革新性」が弱いため、例えば「インボイス制度対応=DX推進」と位置付けて業務改革を行い、新たなサービス提供モデルを確立するなど、一歩踏み込んだ計画に仕立てると良いでしょう。
また、申請は電子申請のみで行われ、こちらもgBizIDプライムが必要です。採択率は公募回によって異なりますが競争倍率は高めなので、専門家(中小企業診断士など)のアドバイスを受けるのも有効です。
業務改善助成金(インボイス対応設備も対象にできる可能性)
業務改善助成金は、インボイス制度対応のコスト直接補填というよりは、人件費と設備投資の両面から小規模事業者を支援する厚生労働省所管の助成金です。
具体的には「事業場内で最も低い賃金を一定額引き上げる(※各コースで30円以上など)こと」と「生産性向上につながる設備投資等を行うこと」を組み合わせることで、その設備投資等にかかった費用の一部を助成してもらえます。
対象事業者
中小企業・小規模事業者で、なおかつ事業場内最低賃金が地域の最低賃金+30円以下程度の水準にある事業場が主な対象です。簡単に言えば、パートや従業員の時給があまり高くない小規模事業者が、それを底上げ(賃上げ)する場合に支給されます。
注意: 賃金引上げを行うことが前提のため、従業員を一人も雇っていない個人事業主(純粋なフリーランス)の場合はこの助成金は利用できません。一方、アルバイトでも誰か雇用していれば対象になり得ます。
助成率・上限額
助成率は非常に高く、3/4から最大9/10(小規模事業者の場合)とされています。つまり対象経費のほとんどを助成でまかなえる計算です。ただし助成上限額があり、引き上げる賃金額や引き上げ人数によって段階的に設定されています。
例えば「従業員1名の時給を30円以上引き上げる」場合は上限50万円、「5名の時給を45円引き上げる」場合は上限150万円、さらに大規模に引き上げる場合は上限数百万円まで段階的に拡大します。
2023年度の拡充で最大で600万円超の助成が受けられるコースも設定されました。
補助対象経費
生産性向上につながる設備、機器、ツール等の導入費用が幅広く対象です。例えば、インボイス制度対応として新しい会計ソフト・受注管理ソフトを導入する、レジや決済端末を新調するといったケースも該当し得ます。
他にも業務用エアコンや作業効率を上げる機械設備、従業員研修費用、コンサルティング導入費など様々な経費に使えます。ポイントは「その投資によって業務効率が上がり、生産性が向上すること」を示すことです。
インボイス対応のITツール導入も、手作業を減らしミスを防ぐなど生産性向上に資するものであれば立派な対象経費になります。
申請と活用のポイント
他の補助金と異なり、業務改善「助成金」は基本的に応募順で受け付け、予算が無くなり次第終了という性格が強いです(審査はありますが要件を満たせば概ね支給される傾向です)。
そのため、公募開始後は早めに申請することが大切です。
申請先は都道府県の労働局や労働基準監督署となり、書類として賃金引上計画や設備投資計画を提出します。交付決定を受けた後に設備の購入・導入を行い(※事前に購入してしまうと助成対象外になるので注意)、実施報告を行うと助成金が支給されます。
賃金を引き上げたことを証明するために給与台帳などを後日提出する必要もあります。
→インボイス対応に関連して、「新しい会計システムを入れて事務効率が向上、その結果生まれた余力で従業員に還元する形で時給を30円アップ」というシナリオであれば、この助成金のコンセプトに沿います。
インボイス対策と職場環境改善を同時に達成できるので、該当する事業者は検討の価値があります。
事業再構築補助金(必要に応じて活用可能な大型補助金)
事業再構築補助金は、新型コロナ以降に創設された大規模な補助金で、自社の事業転換や新分野進出など思い切った事業再構築を行う企業を支援するものです。
直接インボイス制度対応費を補助する趣旨ではありませんが、「環境変化に適応するための事業再構築」を支援する性格上、インボイス制度導入による取引環境の変化や収益構造の変化に対して、新たなビジネスモデルに転換する場合などに活用可能です。
対象事業者
コロナ禍で売上が一定程度減少した中小企業や、中堅企業、新分野展開を目指す企業などが中心です。基本的には法人企業向けのイメージが強いですが、要件を満たせば個人事業主でも申請可能です(売上減少要件等を証明する必要があります)。
例えば「インボイス制度でBtoB取引が減ったので、BtoC向けの新サービスに事業転換する」というようなケースは、この補助金の趣旨に当てはまります。
補助率・上限額
中小企業の場合、補助率は2/3以内が基本です(従業員規模によって1/2になる場合もあります)。
上限額は事業計画の類型によりますが、通常枠で100万円〜6,000万円(従業員数5人以下なら上限6,000万円)、卒業枠やグローバルV字回復枠など特別な類型では上限1億円超もあります。
ただしこれら大きな上限の枠は相応に厳しい要件を満たす必要があります。インボイス対応絡みで小規模企業が利用するなら、現実的には数百万円〜1,000万円程度の補助を狙うイメージでしょう。
補助対象経費
新事業実施のための建物費、設備費、システム購入、人件費、広告宣伝費、研修費など幅広い経費が対象です。
インボイス対応を契機に事業モデルを変える場合、そのために必要となる設備やシステム導入費、新サービスPR費用などを大きなスケールで補助してもらえます。
逆に、単に会計システムを変えるだけとか、事務作業を効率化するだけでは採択は難しく、何か思い切った事業上の挑戦が必要になります。
申請のポイント
事前に認定経営革新等支援機関(金融機関や士業など)のサポートを受けて事業計画書を作成することが求められています。
非常に競争率が高い補助金であり、記載内容も多岐にわたるため、税理士・中小企業診断士などの専門家と二人三脚で計画を練り上げることが重要です。
インボイスによる影響を「危機」と捉え、それを乗り越えるための大胆なプランを示せれば、補助金を獲得して大きな事業転換の資金源にすることも可能です。
以上、インボイス制度に関連して活用できる主な補助金・助成金を紹介しました。個人事業主も対象となるものばかりですので、自身の事業規模や目的に合ったものがあれば、ぜひ前向きに活用を検討してみてください。
補助金以外の支援策:インボイス対応の税制特例(2割特例など)
補助金・助成金のほかにも、インボイス制度への移行に伴う中小事業者の負担を軽減するための税制上の特例措置が設けられています。代表的なものが「2割特例」と呼ばれる措置です。
インボイス発行事業者の2割特例とは?
インボイス制度開始によって新たに課税事業者となった小規模事業者に対し、消費税の納税額を大幅に軽減する特例措置が設けられています。通称「2割特例」(正式には「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する税負担軽減措置」)と呼ばれるものです。
対象者
2023年10月1日のインボイス制度開始に合わせて適格請求書発行事業者の登録を受けた小規模事業者が対象です。
具体的には、今まで消費税免税事業者だった人が課税事業者(インボイス発行事業者)になったケースを想定しています。基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下だった個人事業主や、中小法人などが該当します。
逆にもともと課税事業者であった事業者(売上高1,000万円超だった人や大法人)はこの特例は受けられません。
内容
消費税の計算において、本来納めるべき税額の8割相当額を控除できます。平たく言えば「消費税納税額が実質2割になる(80%減免される)」イメージです。
具体的には、売上にかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を引いた残額(本来の納税額)のさらに8割を減らせる仕組みです。
例えば通常なら年間20万円の消費税を納めるはずの事業者が2割特例を使うと、納税額はその2割の4万円で済むことになります。非常に強力な負担軽減措置です。
適用期間
2023年10月1日から2026年9月30日までの間に含まれる各課税期間が対象となります。個人事業主の場合は課税期間は通常1年間(1月〜12月)ですから、2023年分(10-12月部分)から2026年分までの3年間が該当します。2026年10月以降はこの特例は終了する予定です。
利用方法
特別な事前申請は不要で、確定申告書の中で「2割特例」を適用する旨を明記して計算すればOKです。免税事業者から課税事業者への届出(インボイス登録)は済ませておく必要がありますが、2割特例自体は届出無しで使えます。
ただし適用期間が限られているため、2024年〜2026年分の消費税申告を忘れずに行い、特例を適用することが重要です(免税事業者から転換したばかりだと消費税申告自体になじみがないため、申告漏れに注意しましょう)。
この2割特例により、インボイス発行事業者となった小規模事業者は消費税の実質負担を抑えつつ取引先にインボイスを提供できます。
先ほどの補助金と合わせて考えると、例えばインボイス対応のシステム導入費は補助金で賄い、初期3年間の消費税納税分は2割特例で大幅軽減する、といった活用でスムーズな移行が可能になります。
その他の負担軽減策
インボイス制度に関しては他にも以下のような経過措置があります。
仕入税額控除の経過措置
インボイスがなくても仕入税額相当額の一部を控除できる措置。2023年10月〜2026年9月はインボイスのない経費でも80%相当を仕入税額控除可能、2026年10月〜2029年9月は50%控除可能、その後は0%となります。
これは買い手側の措置ですが、インボイス未対応の事業者との取引による影響を段階的に緩和するための制度です。2029年以降は完全にインボイスが無い取引は控除できなくなるため、小規模事業者も遅かれ早かれインボイス発行事業者になることが求められるでしょう。
少額特例(適格簡易請求書)
1万円未満の小口取引については、インボイスの簡易版(適格簡易請求書)で対応可能とする緩和措置があります。レシートなどでも一定の事項が満たされていれば仕入税額控除が可能です。コンビニや飲食店の少額領収書などはこの扱いです。
個人事業主でも日々の細かい経費はこの特例で対応できますが、発行側として留意すべき点は少額取引であっても自社が発行者である場合は原則インボイス要件を満たすよう注意することです。
補助金ではありませんが、以上のような税制上の特例や経過措置も組み合わせて活用することで、インボイス制度による負担増をできるだけ抑えながらビジネスを継続・発展させることができます。
補助金申請の条件とスケジュール
実際に補助金を利用するにあたっては、各制度ごとに細かな応募条件や公募スケジュールがあります。ここでは共通するポイントを中心に、申請条件とスケジュールの考え方を解説します。
共通する応募・申請条件
補助金はそれぞれ目的や管轄が異なるため条件も異なりますが、共通して押さえておきたい事項があります。
中小企業・小規模事業者であること
ほとんどの補助金は大企業は対象外です。前述の各制度の対象条件を満たしていることが大前提になります。特に個人事業主やフリーランスでも応募できるかどうか、不安な場合は公募要領の「応募資格」欄を確認しましょう。
今回紹介した制度はいずれも個人事業主OKですが、事業再構築補助金など一部は「認定支援機関と計画策定」など追加条件があります。
申請ごとに事業計画・使途が明確であること
補助金は「これから行う取り組み」に対して支給されるものであり、漠然とインボイス対応費用が欲しいというだけでは採択されません。具体的な計画と目的、使い道を示す必要があります。
また、補助対象とならない経費(汎用性が高いものや税金の支払いそのもの、人件費の一部など)が各制度で定められているので、計画時に要チェックです。
税の滞納や反社会的勢力でないこと等
補助金申請者として基本的な遵守事項があります。過去に不正受給で処分を受けていないことや、申請時に直近の確定申告を済ませていること、税金を滞納していないことなどです。
特に法人の場合は決算書類の提出なども求められるので、きちんと税務処理をしてから臨みましょう。
他の補助金との重複に注意
同じ経費について複数の補助金から二重に資金を受け取ることはできません。インボイス対応で色々な制度がありますが、「この部分はIT導入補助金、あの部分は持続化補助金で」などと経費を分けて申請することは可能でも、一つの経費を二重取りするのは不可です。
また、一部補助金では類似目的の他制度との併用禁止のルールがある場合もあります。公募要領の「他制度等との重複受給禁止」項目を確認しましょう。
公募のスケジュールを把握しよう
補助金は通年いつでも申請できるものと、年に数回まとめて公募・審査が行われるものがあります。自分が狙う補助金のスケジュール感を掴んでおくことが重要です。
IT導入補助金
毎年複数回の公募期間が設定されています。例えば2024年は4〜5回程度の申請締切が設けられ、2025年も引き続き実施予定です。年度の早い時期(春頃)から募集が始まる傾向があるので、年明けには最新情報を確認しましょう。
持続化補助金(一般型)
年に3〜4回、公募の締切日が設定されています。過去を見ると3月、6月、9月、12月といった四半期ごとに締切がある年もありました。応募書類の準備に時間がかかるので、締切の2か月前くらいには商工会議所に相談を始めるのがおすすめです。
ものづくり補助金
こちらも年に3回程度、公募締切があります(例年、初回は春、次いで夏〜秋、そして冬頃)。採択発表まで数ヶ月要するため、実際に資金を使えるようになるのは応募から半年後くらいになるケースもあります。設備投資の時期と照らし合わせて計画しましょう。
業務改善助成金
この助成金は年度当初から予算上限まで随時受付という形式です。原則として年度内(毎年4月〜翌3月)で締切がありますが、人気が高い場合は早めに受付停止となる可能性があります。賃上げのタイミングや設備導入の予定があるなら、年度の前半に動き出す方が確実です。
事業再構築補助金
年2回程度の公募が行われています。公募開始から締切まで2ヶ月以上の猶予がありますが、認定支援機関との事前調整が必要なため、こちらも早め早めの準備が必要です。
スケジュール管理のポイント
補助金は「申請→審査→採択決定→交付手続き→事業実施→報告→補助金受取」という長い流れになります。応募してからお金が振り込まれるまで半年〜1年近くかかることも珍しくありません。そのため、資金繰りに余裕を持って計画することが大切です。
急ぎで資金が必要な場合には補助金より融資等の方が適しているケースもあります。一方で、補助金は採択されれば返済不要な資金援助となるので、タイミングが合うならぜひチャレンジしてみましょう。
各補助金の最新スケジュールは担当省庁や事務局の公式サイト、プレスリリースなどで公表されます。「〇〇補助金 公募要領 令和○年度」といったキーワードで検索すると見つかります。
税理士や商工会から情報提供を受けることもできますので、日頃からアンテナを張っておくと良いでしょう。
補助金の申請方法(手順と必要書類)
それでは、実際に補助金を申請する際の大まかな手順と必要書類について説明します。細部は制度によって異なりますが、多くの補助金申請に共通する流れを把握しておきましょう。
申請までの基本的な手順
情報収集と制度選定: まず、自社(自分)の事業内容やニーズに合った補助金を探します。インボイス対応が目的の場合、本記事で紹介したような補助金が候補になります。公式発表資料や公募要領を取り寄せ、応募条件や使い道がマッチするかを確認しましょう。
事業計画の立案: 補助金で何を行いたいか、その目的・内容・必要な経費を整理します。例えば「インボイス対応のために○○システムを導入し、事務負担を軽減することで△△(効果)を狙う」といったストーリーを描きます。
計画期間や目標、成果指標なども考えておきます。
必要書類の準備: 申請書類一式を作成します。後述の必要書類リストを参考に、事前に揃えるべき書類(例えば確定申告書の写し、見積書など)もチェックしておきます。申請書(交付申請書、事業計画書など)は公募要領のフォーマットに沿って記入します。
ここが一番時間を要するステップです。
関係機関への相談・依頼: 補助金によっては、事前に商工会議所や認定支援機関、IT導入支援事業者などに相談・確認を受ける必要があります。
該当する場合は早めにアポイントを取り、自分の作成した計画書を見てもらってアドバイスを受けましょう。また、電子申請システム(jGrants等)を利用する場合、gBizIDの取得や利用者登録を済ませます。必要なら電子署名用のICカード準備なども行います。
申請書類の提出(応募): 期限までに書類を提出します。提出方法は制度により異なり、オンライン提出(WebフォームやPDFアップロード)が増えていますが、持続化補助金のように郵送提出を受け付けているものもあります。
オンラインの場合は事前にログインや操作方法を確認し、余裕をもって送信しましょう(締切直前はシステムが混雑することもあります)。
審査結果の通知: 締切後、事務局で審査が行われます。書類審査の他、必要に応じて面談やプレゼンを求められる補助金もあります(大規模なものや特殊枠の場合)。採択・不採択の結果はメールやWebサイト上で通知されます。
採択された場合、ここから交付申請手続きに進みます。
交付申請・交付決定: 採択されたら正式に「この内容で補助金を交付してください」という交付申請を行い、事務局から交付決定通知を受けます。これで晴れて補助事業の実行許可がおりたことになります。
補助事業の実行: 計画書に沿って事業を実施します。インボイス対応システムの発注・導入、研修の実施、設備購入などを行います。注意: 交付決定前に発注・契約・支出をした経費は原則補助対象になりません。必ず交付決定後に事業着手するようにしましょう。また、事業期間内に計画を完了させる必要があります。
実績報告・精算手続き: 補助事業が完了したら、実績報告書を提出します。
当初の目的が達成できたか、経費はいくら使ったか(領収書・請求書のエビデンス提出)、自己負担分も含め支払いが完了しているか等を報告します。事務局で内容確認・経費精算が行われ、最終的な補助金交付額の確定が通知されます。
補助金の受け取り: 指定した銀行口座に補助金額が振り込まれます。ここに至るまでしっかり手続きを踏めば、一連の補助金活用プロセスが完了です。その後も一定期間、事務局から事業の効果に関するフォローアンケートや状況報告を求められることがあります。
申請時に必要となる主な書類
申請段階および実績報告段階で必要になる代表的な書類は以下の通りです。
補助金交付申請書(応募申請書)
所定の申請様式です。事業者情報や申請額、事業概要など基本事項を記入します。
事業計画書・経費明細書
補助事業の内容を詳しく説明する書類です。目的、具体的な取組内容、期待される効果、事業のスケジュール、資金計画などを記載します。
経費明細書には、使う予定の経費を項目ごとに積算して記載します。インボイス関連なら「〇〇ソフト導入費○円」「会計事務所への相談費○円」など具体的に書きます。
見積書・カタログ
計画している経費について、金額の根拠となる見積書や商品カタログ、ウェブサイトの価格表示などを添付します。例えばソフトウェア導入費であればベンダーからの見積書、機器購入ならメーカーの価格表などです。
直近の決算書または確定申告書の写し
事業の財務状況を示すために提出します。個人事業主であれば直近1期分の確定申告書(第1表と青色申告決算書など)のコピー、法人なら貸借対照表・損益計算書のコピー等です。
税務関連証明
税の納付状況を確認するため、納税証明書(「その2」など滞納がない証明)を求められる場合があります。発行に時間がかかる場合もあるので、必要なら事前に税務署で取得しておきましょう。
会社概要書や定款の写し(法人の場合): 事業内容や組織を把握するために提出することがあります。個人事業主なら不要なケースが多いです。
商工会議所の事業支援計画書(持続化補助金の場合)
前述のとおり、商工会議所等に発行してもらう書類です。これを申請書類に綴じ込んで提出します。
gBizIDアカウント情報(オンライン申請の場合)
jGrantsで申請する際には、法人・個人のgBizIDとパスワードが必要です。また、電子証明書が必要な補助金も一部あります。
その他誓約書類
反社会的勢力でないことの誓約や個人情報同意書など、細かな書類も用意されています。公募要領の添付書類一覧をよく確認しましょう。
これらは一例ですが、「応募の手引き」に必要書類がチェックリスト付きで記載されていますので、漏れなく用意してください。提出書類に不備があると形式審査で落とされる可能性があります。
特にミスしやすいのが押印漏れやサイン漏れ、日付の記入ミスなどです。提出前に必ずダブルチェックしましょう。
補助金申請時の注意点
補助金を確実に受け取るためには、申請から事業完了までいくつか注意すべきポイントがあります。ここでは代表的な注意事項を挙げます。
必ず採択されるわけではない
補助金は応募すれば自動的にもらえるものではありません。予算に限りがあるため、審査による選考があります。書類をしっかり作り込んでも競争率次第では落選もありえます。「条件を満たしているのに落ちるなんて…」ということも珍しくありません。
したがって、補助金に過度に依存した資金計画は危険です。万一不採択でも事業自体は遂行できるよう、他の資金調達策も検討しておくことが大切です。
書類準備に時間と手間がかかる
補助金申請はとにかく書類作業が煩雑です。事業計画書の作成には緻密な計画立案やデータ収集が必要ですし、添付書類の収集・作成にも時間がかかります。締切ギリギリに焦って作ると誤字脱字・記入漏れの原因にもなります。
余裕を持った準備を心がけ、可能であれば早い段階で税理士や中小企業診断士など専門家に相談しましょう。自治体や商工会議所が無料相談会を開くこともあります。
事前着手はNG
補助金は基本的に「交付決定後に発生した経費」が支払対象です。申請前・採択前に発注や購入をしてしまうと、その費用は補助の対象外となってしまいます。
インボイス制度対応を急ぐあまり、補助金申請中に先にシステムを買ってしまった…ということがないよう注意しましょう。我慢が必要な局面もあります。
自己負担資金を用意しておく
補助金は後払いで支給されるため、事業実施に必要な費用は一旦自分で立替える必要があります。例えば100万円の経費で2/3補助なら、まず100万円を自力で支払い、後から約66万円が戻ってくる形です。
この立替資金が用意できないと、せっかく採択されても事業が実行できなくなります。必要に応じて日本政策金融公庫の低利融資なども検討し、キャッシュフローを確保しておきましょう。
経費管理と証拠保存を徹底する: 補助事業の実行段階では、支出経費の領収書・請求書、銀行振込の控えなど証拠書類をきちんと保存してください。実績報告時にこれらを提出・提示してチェックを受けます。
不備があるとその部分は補助金がもらえなくなったり、最悪全額返還を求められることもあります。また、補助事業期間中に計画変更や中止が必要になった場合は必ず事前に事務局へ相談し、承認を得ましょう。勝手に計画と違うことをすると違約になります。
補助事業終了後の報告義務: 補助金によっては事業完了後○年間は成果を報告したり、帳簿を保存しておく義務があります(例:持続化補助金では5年間の状況報告、ものづくり補助金でも事後調査があります)。
これらのフォローアップにも誠実に対応しましょう。将来また別の補助金に応募する際に、過去の報告未了などが問題になるケースもあります。
専門家の力を借りる: 自力での申請が難しい場合、申請代行やサポートを行う専門家に依頼する選択肢もあります。税理士・行政書士・中小企業診断士などで補助金申請の実績がある人に相談すれば、書類のクオリティも上がり、採択率向上が期待できます。
ただし報酬が発生する(成功報酬の場合が多い)ので、その支出も織り込んで判断してください。小規模事業者持続化補助金などは商工会議所が無料で計画書添削をしてくれるので、まずは公的機関の支援を活用するのも手です。
以上の点に注意すれば、補助金申請・活用は決して怖いものではありません。手間はかかりますが、しっかり準備すれば高額の補助を受け取れる大きなチャンスです。インボイス対応に追われる中小事業者こそ、使える制度は積極的に使ってみましょう。
申請サポートに使えるツール・サービス
補助金申請やインボイス対応をスムーズに進めるために、活用できるツールや支援サービスもいろいろと存在します。いくつか代表的なものをご紹介します。
公的な情報提供サイト
中小企業庁や各補助金事務局の公式サイトでは、公募要領やQ&A、申請様式のダウンロードができます。まずは信頼できる公式情報源を活用しましょう。
また、中小企業基盤整備機構の「ミラサポPLUS」やJ-Net21といったサイトでは、補助金・助成金の公募情報をまとめて検索できます。「補助金・助成金検索サイト」を利用すれば、自社の条件に合った支援策を探しやすくなります。
電子申請システム(jGrants)
国の主要な補助金はオンライン申請システム「jGrants(ジェイグランツ)」で手続きします。事前にgBizIDプライムというアカウントを取得し連携させることで、申請書類の提出や採択結果確認がウェブ上で完結します。
紙提出に比べスピーディーで、提出後の差し替え等も容易です。まだ使ったことがない方は、この機会にアカウント登録しておくとよいでしょう。
会計・業務ソフトウェア
インボイス制度対応という点では、クラウド会計ソフトや請求書発行ツールが非常に役立ちます。
例えば弥生やfreee、マネーフォワードといったクラウドサービスでは、インボイスに必要な項目が自動でレイアウトされた請求書を発行できたり、適格請求書の保存要件を満たす形でデータ管理できたりします。
さらに2024年から本格施行された電子帳簿保存法(電子取引データ保存の義務化)にも対応済みのソフトが多く、インボイス対応と電子保存対応を一括で実現できます。
結果として経理業務全体の効率化・ペーパーレス化が進み、事務負担軽減につながるでしょう。これらのソフトの導入自体が先述の補助金(IT導入補助金など)の対象ともなり得ます。
補助金申請サポートサービス
最近では、補助金申請を支援する民間サービスも登場しています。オンラインで質問に答えていくと事業計画書のひな形が作れたり、専門家にチャットで相談できたりするサービスもあります。
また、「補助金コンシェルジュ」「助成金ポータル」などのウェブサイトでは、無料の情報提供から有料の申請代行まで行っています。費用はかかりますが、「初めてで不安、時間もない」という場合は検討してもよいでしょう。
商工会議所・よろず支援拠点
各地の商工会議所や商工会、都道府県の中小企業支援センター(よろず支援拠点)では、補助金申請や事業計画策定の無料相談を受け付けています。
専門の経営指導員や中小企業診断士がアドバイスしてくれるため、大いに活用しましょう。持続化補助金のように支援機関と連携が必須のケースだけでなく、他の補助金でも親身に相談に乗ってくれるはずです。
税理士・行政書士等の専門家
顧問税理士がいる場合は、インボイス対応に関して当然頼れる存在ですし、補助金情報も提供してくれるでしょう。補助金申請については行政書士や中小企業診断士で経験豊富な方もいます。
専門家と契約する場合は費用対効果を考える必要がありますが、不備なく申請書を作成する安心感は得られます。特に事業再構築補助金のような大掛かりな申請は、支援機関(税理士等)抜きでは難しいですので、チームで取り組むことも検討してください。
これらのツールやサービスを上手に使えば、補助金申請のハードルはかなり下がります。また、インボイス制度そのものへの対応も、ITツールの活用や専門家の知見によってスムーズに進めることができます。
最初から一人で抱え込まず、利用できるリソースはフル活用していきましょう。
今後の変更や注意すべき点
最後に、インボイス制度および関連補助金の今後の動向について、押さえておきたいポイントをまとめます。
2割特例の終了時期
前述した消費税2割特例は2026年9月30日までの措置です。それ以降は、インボイス発行事業者となった小規模事業者でも通常通り(=全額)消費税を納める必要があります。
特例適用中に売上規模拡大や経費構造の見直しを進め、2026年以降に備えることが重要です。場合によっては価格設定の見直し(消費税転嫁の徹底)や経費削減策を検討する必要があるでしょう。
仕入税額控除の経過措置の段階的縮小
2026年10月以降、インボイスのない取引に対する仕入税額控除の割合が80%→50%に下がります。そして2029年10月以降は0%になります。これは買い手側の話ですが、買い手から見たインボイス未登録事業者のデメリットが徐々に大きくなることを意味します。
2023~2025年頃は「取引先が免税事業者でも8割控除できるからまあ良いか」としていた企業も、2029年には「控除できないから取引条件見直しを」となる可能性が高いです。
フリーランス・個人事業主の方も、遅くとも2029年までにはインボイス発行事業者になる前提で事業計画を立てた方が良いでしょう。
今後、免税事業者のままでいることのメリット(消費税を納めなくてよい)とデメリット(取引機会減少)を天秤にかけた判断がますます重要になります。
補助金制度の変更
補助金・助成金の制度内容や重点テーマは、毎年の予算や政策方針によって変わります。インボイス導入初年度の2023年度は関連特例が多く盛り込まれましたが、この特例措置がずっと続くとは限りません。
例えば持続化補助金のインボイス特例は現時点で明確な終了時期は決まっていませんが、インボイス制度定着後には廃止される可能性もあります。
IT導入補助金の「インボイス枠」も将来的には通常のデジタル化支援枠に統合されるかもしれません。常に最新の公募情報をチェックし、「今年使わないと損」というものがあれば逃さないようにしましょう。
デジタルインボイス・電子化の進展
インボイス制度は紙の請求書でも対応可能ですが、今後は電子インボイス(デジタルな請求書データの標準規格)や電子帳簿保存法の普及により、請求業務のデジタル化がますます進むと考えられます。
2025年以降、政府もデジタル技術の活用を強力に推進していく方針です。そうした流れに沿って、新たなIT補助金やDX支援策が登場することも予想されます。補助金を活用して導入したシステムもうまくアップデートし続け、時代の変化にキャッチアップすることが肝要です。
消費税率や経済環境の変化
現在の消費税率10%に対するインボイス制度ですが、将来的に消費税率が変わったり軽減税率制度が見直されたりする可能性もゼロではありません。
また物価高騰や賃金上昇など経済状況によって、中小企業向けの支援策も適宜変更されていくでしょう。
インボイス対応は一度やれば終わりというより、継続的な経営管理の一部として捉え、最新情報に注意を払ってください。特に税理士等の専門家から定期的に情報収集する習慣をつけると安心です。
今後の変化に柔軟に対応しつつ、現在利用できる制度はしっかり活用していく姿勢が大切です。インボイス制度そのものは中長期的に見れば企業間取引の透明性向上につながるものですので、前向きに適応していきましょう。
まとめ
インボイス制度の開始により、個人事業主や小規模企業には新たな負担が生じています。しかし、ここで紹介したように国や自治体から様々な補助金・助成金、支援策が用意されています。
うまく活用すれば、インボイス対応のシステム導入費や経理体制整備費、さらには初期数年間の税負担までも大きく軽減することができます。
ポイントのおさらい
インボイス制度とは何かを理解し、自社への影響(事務作業増、コスト増、取引先への対応)を把握する。
IT導入補助金、持続化補助金、業務改善助成金など、個人事業主でも申請可能な補助金が多数ある。インボイス特例やインボイス枠を活用すれば補助上限額・補助率がアップする。
補助金申請には計画づくりと書類準備が重要。早めに情報収集し、専門家や支援機関の力も借りて、採択を目指す。
2割特例など税制上の支援措置も忘れずに適用する。免税から課税になった最初の3年間は消費税の納税額を大幅に減らせる。
申請手順や必要書類をしっかり確認し、締切スケジュール管理や経費エビデンスの保存など基本を徹底する。
会計ソフトや電子申請システムなど便利なツールを活用し、インボイス対応と補助金申請の手間を減らす。困ったら公的機関や専門家に遠慮なく相談する。
今後の制度変更にも注意を払い、使えるうちに支援策を使っておく。インボイス制度への対応は長期戦なので、計画的に取り組む。
インボイス制度は最初こそ戸惑いますが、経理のデジタル化や業務効率化を進める良い機会とも捉えられます。補助金で資金面の後押しを受けながら対応を進めれば、結果的に事業の競争力向上や新たな成長につなげることも可能です。
「知らなかった…」ではもったいないので、是非本記事をきっかけに行動に移してみてください。必要に応じて税理士や支援機関のサポートを得ながら、インボイス時代を賢く乗り切りましょう!
以上、インボイス制度に伴う補助金と申請方法の総合ガイドでした。あなたの事業に適した支援策が見つかり、スムーズにインボイス対応が進むことを願っています。これからも最新情報をチェックしつつ、ビジネスの発展にお役立てください。








開業届の提出方法とは?節税から事業の始め方まで解説
「いつかは自分の力で事業を始めたい」。その熱い想いを胸に、独立への道を歩み始めたあなたへ。開業届の提…