
支払っている税金の中に、実は経費として認められるものがあることをご存知でしょうか。多くの経営者が法人税や所得税の節税に頭を悩ませていますが、意外と見落とされがちなのが「事業税」の扱いです。
事業税は、正しく理解すれば法人税や所得税の課税対象となる所得を減らし、結果として手元に残るキャッシュを増やすことができる重要な要素です。
この記事では、「事業税の損金算入」というテーマを徹底的に掘り下げます。
法人と個人事業主、それぞれのケースにおける損金算入の正確なタイミング、具体的な会計処理(仕訳)、そして税務申告書での正しい記載方法まで、網羅的に解説します。複雑な税法のルールを一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
税金の話は難しいと感じるかもしれません。しかし、この記事を最後まで読めば、事業税の損金算入に関する不安は解消され、自信を持って税務処理に臨めるようになります。
知識は最大の防御であり、そして賢い節税への第一歩です。あなたの会社の利益を最大化するため、この機会に正確な知識を身につけましょう。
目次
事業税と損金算入の基本|なぜ「経費」になる税金とならない税金があるのか?
事業税がなぜ経費として認められるのか、その根本的な理由を理解することが重要です。すべての税金が同じように扱われるわけではありません。税金には、その性質によって「損金(法人)」や「必要経経費(個人事業主)」になるものとならないものが明確に区別されています。
この違いを生むのは、税金の「目的」です。事業税は、事業を行うにあたって道路や警察、消防といった地方自治体の公共サービスを利用することへの対価、つまり事業活動を営むためのコストと見なされます。そのため、事業を運営する上で発生した費用として、損金または必要経費への算入が認められています。これは、事業用の事務所にかかる固定資産税や、事業用車両の自動車税が経費になるのと同じ理屈です。
一方で、法人税や法人住民税は、事業活動によって生み出された「利益(所得)」そのものに対して課される税金です。これらは利益を獲得するためのコストではなく、利益が出た結果として社会に還元(納税)するものと位置づけられています。したがって、これらは損金として算入することはできません。
この基本的な考え方の違いを理解することで、どの税金が経費になるのかを迷わず判断できるようになります。以下の表で、代表的な税金の損金算入の可否をまとめました。
| 税金の種類 | 損金算入の可否 | 理由・根拠 |
| 法人税・地方法人税 | 不可 | 利益処分的な性質のため |
| 法人住民税 | 不可 | 利益処分的な性質のため |
| 法人事業税 | 可 | 事業活動の対価(コスト)と見なされるため |
| 固定資産税・自動車税 | 可 | 事業用資産にかかるコストのため |
| 印紙税 | 可 | 取引に付随するコストのため |
| 延滞税・加算税 | 不可 | 納税義務の不履行に対するペナルティのため |
このように、ペナルティとして課される延滞税や加算金なども、当然ながら損金には算入できません。
【法人向け】法人事業税の損金算入について
法人における事業税の損金算入は、個人事業主とはルールが大きく異なります。特に「いつ損金になるのか」というタイミングの理解が極めて重要です。ここでは、法人が押さえるべきポイントを網羅的に解説します。
損金算入の最重要ポイントは「いつ」経費になるか
法人事業税の損金算入時期に関する原則はただ一つ、「その事業税の額を記載した申告書を提出した事業年度」の損金となる、という点です。これは、税額が申告によって法的に確定する「債務確定主義」に基づいています。会計上の発生主義とは異なる、税法特有の考え方であるため注意が必要です。
具体的なケースごとに見ていきましょう。
確定申告
3月決算の法人が2024年3月期(X1期)の利益に基づき計算した事業税を、2024年5月に申告・納付したとします。この事業税は、申告書を提出した2025年3月期(X2期)の損金となります。X1期の費用にはならない点がポイントです。
中間申告
3月決算の法人が2025年3月期(X2期)の中間申告を2024年11月に行う場合、その中間申告で納める事業税は、申告書を提出した2025年3月期(X2期)の損金となります。
修正申告・更正
過去の事業年度(例えばX0期)について税務調査などで誤りを指摘され、2024年(X2期中)に修正申告書を提出したり、税務署から更正を受けたりした場合を考えます。それによって発生した追加の事業税は、修正申告書を提出した、あるいは更正・決定があった2025年3月期(X2期)の損金となります。
会計の感覚では「X1期の利益に対応する費用なのだからX1期の損金にすべき」と考えがちですが、税法ではあくまで法的に納税義務が確定したタイミングを重視します。この会計感覚と税法ルールのズレが、後述する申告書上の調整(別表四)が必要になる理由です。
損金算入時期の特例
原則があれば例外もあります。法人税法では、直前の事業年度分の事業税について、その事業年度の終了日までに申告等がなされていなくても、その事業年度の損金の額に算入できるという特例が認められています。これは、決算で未払計上した場合に、申告調整の手間を省き、会計実務に配慮した規定です。
会計処理と仕訳例
事業税の損金算入を正しく行うためには、日々の会計処理が基礎となります。一連の流れを仕訳例で確認しましょう。
中間納付時の仕訳
中間申告で事業税を含む法人税等を納付した場合、その時点では税額が確定していないため、「仮払法人税等」として資産計上します。
(借方)仮払法人税等 500,000 / (貸方)現金預金 500,000
期末の決算整理仕訳
決算を迎え、当期の法人税、住民税、事業税の納税額が確定したら、その全額を費用として計上します。同時に、中間納付した仮払分を取り崩し、差額を「未払法人税等」として負債計上します。
(借方)法人税、住民税及び事業税 1,200,000 / (貸方)仮払法人税等 500,000
(貸方)未払法人税等 700,000
確定申告・納付時の仕訳
翌期になり、確定申告とともに税金を納付した際は、前期末に計上した未払法人税等を取り崩します。
(借方)未払法人税等 700,000 / (貸方)現金預金 700,000
外形標準課税の特別な会計処理(資本金1億円超の法人は要注意)
資本金が1億円を超える法人の場合、事業税の計算方法が変わり、会計処理も特別になるため注意が必要です。この制度を「外形標準課税」と呼びます。
外形標準課税では、事業税が以下の3つの要素で構成されます。
- 所得割
利益(所得)に応じて課税される部分。 - 付加価値割
給与や純支払利子、純支払賃借料など、事業活動の規模(付加価値)に応じて課税される部分。 - 資本割
資本金等の額に応じて課税される部分。
ここでの重要な会計上の違いは、勘定科目にあります。所得割は利益に連動するため、通常の事業税と同様に「法人税、住民税及び事業税」として処理します。一方、付加価値割・資本割は利益の有無にかかわらず発生する税金であり、所得に対する税ではないため、販売費及び一般管理費の中の「租税公課」として処理します。
この会計処理の違いは、財務諸表の分析において大きな意味を持ちます。「租税公課」として処理された付加価値割と資本割は、営業利益を直接減少させます。一方で、「法人税、住民税及び事業税」は営業利益よりも下の段階である税引前当期純利益から差し引かれます。
つまり、外形標準課税の対象となる法人は、同じ税額を支払っていても、対象外の法人に比べて営業利益が低く算出される可能性があるのです。これは、金融機関からの評価や経営分析を行う上で見逃せないポイントです。
法人税申告書「別表四」での具体的な調整方法
法人事業税の損金算入を完了させる最後の関門が、法人税申告書「別表四(所得の金額の計算に関する明細書)」での調整です。別表四は、会計上の利益(当期純利益)と税法上の所得金額の差を調整するための書類です。
事業税に関する調整は、一見すると複雑に見えますが、「一度リセットして、税法のルールで再計算する」という2段階のロジックで考えると理解しやすくなります。
ステップ1 加算(リセット)
別表四の出発点は、会計上の「税引後」当期純利益です。まず、損益計算書で費用として計上した「法人税、住民税及び事業税」の全額を、所得に加算します。これは別表四の「損金の額に算入した納税充当金」という欄に記載します。
なぜなら、法人税・住民税はそもそも損金にならず、当期の事業税も原則として当期の損金にはならないからです。この加算処理によって、会計上の税金費用を一旦すべてなかったことにし、税引前の状態に戻すイメージです。
ステップ2 減算(税法ルールで再計算)
次に、リセットされた所得から、税法上、当期に損金として算入が認められる金額を減算します。事業税の場合、これは「前期の申告で確定し、当期中に納付した事業税(中間納付分も含む)」の金額です。この金額を、別表四の「納税充当金から支出した事業税等の金額」という欄に記載して減算します。
この「加算して減算する」という一連の処理によって、会計上の利益と税法上の所得のズレが正しく調整され、適切な法人税額が計算されるのです。
【個人事業主向け】個人事業税を確実に経費にする方法

個人事業主の場合、事業税の扱いは法人と比べてシンプルですが、それでも押さえるべき重要なポイントがいくつかあります。特に、経費計上のタイミングは法人と全く異なるため、混同しないように注意が必要です。
個人事業税の納税義務者
個人事業主であれば誰でも個人事業税を支払うわけではありません。納税義務が発生するのは、以下の2つの条件を両方満たす場合です。
- 法定業種であること
地方税法で定められた70種類の「法定業種」に該当する事業を営んでいること。 - 所得が一定額を超えていること
年間の事業所得が、一律で適用される「事業主控除」290万円を超えること。
ライター、プログラマー、システムエンジニア、画家といった一部の職種は、この法定業種に含まれていないため、原則として個人事業税は課税されません。
自身の事業が課税対象かを確認するために、以下の法定業種一覧を参照してください。
| 事業区分 | 税率 | 主な該当業種 |
| 第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業、飲食店業、不動産貸付業、請負業、製造業、コンサルタント業など |
| 第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業 (30業種) | 5% | 医業、弁護士業、税理士業、デザイン業、理容業、美容業など |
| 第3種事業 (一部) | 3% | あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復、装蹄師業 |
経費計上のタイミングと法人との決定的な違い
ここが個人事業主にとって最も重要なポイントです。個人事業税は、実際にその税金を支払った年の必要経費として計上します。
例えば、2023年分の所得に対する確定申告を2024年3月に行うと、個人事業税の納税通知書が2024年8月頃に届き、通常8月と11月の2回に分けて納付します。この場合、2024年に支払った事業税は、2024年分の経費として、2025年3月に行う確定申告で計上することになります。
法人と個人事業主のルールを明確に区別して覚えましょう。
- 法人:申告書を提出した年の損金
- 個人事業主:税金を支払った年の必要経費
この違いを混同すると、経費計上のタイミングを誤り、所得を過大または過少に申告してしまう原因となります。特に、個人事業主から法人成りした直後は注意が必要です。
会計処理と仕訳例
個人事業主の会計処理は非常にシンプルです。
使用する勘定科目
支払った個人事業税は、「租税公課」という勘定科目で費用計上します。
仕訳例
8月に個人事業税の第1期分として50,000円を事業用口座から支払った場合、以下のように記帳します。
(借方)租税公課 50,000 / (貸方)普通預金 50,000
なお、個人の所得税や住民税は事業の経費にはなりません。これらを事業用口座から支払った場合は、経費ではなく「事業主貸」として処理する必要があります。
事業税の損金算入の活用方法
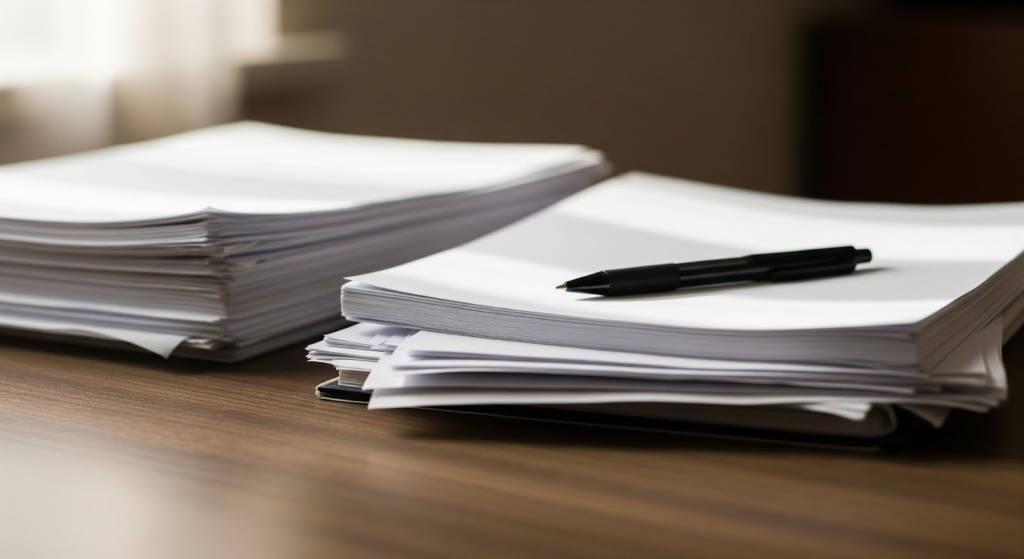
事業税の損金算入ルールを理解したら、次はその知識を経営戦略に活かす段階です。特に、多くの個人事業主が悩む「法人成り」の判断において、この知識は重要な役割を果たします。
法人成りの判断と所得別の税負担シミュレーション
「所得がいくらになったら法人化すべきか」という問いに、単純な答えはありません。法人税率の低さだけに注目すると、判断を誤る可能性があります。法人化のメリット(役員報酬の給与所得控除など)と、デメリット(社会保険料の負担増など)を総合的に比較検討する必要があります。
特に、社会保険料の負担は法人化における最大のゲームチェンジャーです。個人事業主が加入する国民健康保険・国民年金に比べ、法人が加入する健康保険・厚生年金は、会社と個人で保険料を折半するものの、総額としては大幅に増加するケースがほとんどです。この負担が、税金の節税効果を上回ってしまうことも珍しくありません。
ここでは、所得500万円と800万円のケースで、税金と社会保険料を考慮した手取り額のシミュレーションを見てみましょう。(※東京都、40歳未満、青色申告65万円控除、経費は考慮しないなど一定の前提に基づく概算値です)
| 項目 | 所得500万円の場合 | 所得800万円の場合 |
| 個人事業主 | 法人(役員報酬同額) | |
| 税金 | ||
| 所得税・住民税 | 約88万円 | 約48万円 |
| 個人事業税 | 約11万円 | – |
| 法人税等 | – | 約23万円 |
| 税金合計 | 約99万円 | 約71万円 |
| 社会保険料 | 約67万円 | 約140万円 |
| 税・社保合計 | 約166万円 | 約211万円 |
| 手取り額 | 約334万円 | 約289万円 |
このシミュレーションが示すように、所得500万円の段階では、税金面では法人の方が有利に見えますが、社会保険料の負担が大きいため、結果的に手取り額は個人事業主の方が多くなります。
所得800万円のケースでも同様に、社会保険料の壁が大きく立ちはだかります。法人化を検討する際は、必ず社会保険料を含めたトータルコストで判断することが不可欠です。
節税効果を最大化するための注意点
事業税の損金算入による節税効果を確実に享受するため、以下の点に注意しましょう。
ペナルティは損金にならない
申告漏れや納付遅れによって課される延滞税や加算税は、いかなる理由があっても損金(必要経費)にはなりません。期限内に正確な申告と納税を行うことが、無駄な支出を避けるための基本です。
正確な記録管理
すべての経費計上の大前提は、その支出が事業に関連するものであることを客観的に証明できることです。領収書や帳簿を正確に管理し、いつでも説明できる状態にしておきましょう。
キャッシュフローへの影響
事業税が損金になるからといって、税金の支払いがなくなるわけではありません。あくまで課税所得が減るだけであり、納税のための資金繰りは別途必要です。損金算入のメリットと、実際のキャッシュアウトフローを混同しないようにしましょう。
まとめ
事業税の損金算入は、知っているかどうかで納税額に差がつく重要な知識です。最後に、法人と個人事業主それぞれが押さえるべき最重要ポイントを再確認します。
法人経営者の皆様へ
重要なのはタイミングです。損金算入できるのは、申告書を提出した事業年度です。会計上の利益と税法上の所得のズレを、別表四で正しく調整することを忘れないでください。また、資本金1億円超の法人は、外形標準課税の付加価値割・資本割を「租税公課」として処理する特別なルールを徹底しましょう。
個人事業主の皆様へ
こちらも重要なのはタイミングです。経費にできるのは、事業税を実際に支払った年です。法人とはルールが全く異なるため、混同しないように注意してください。また、自身の事業が法定業種に該当するかを事前に確認し、会計処理では「租税公課」の勘定科目を使いましょう。
戦略的な視点
事業税が経費になることは、法人化を検討する際の重要な判断材料の一つです。しかし、税率の比較だけで判断するのではなく、社会保険料という大きなコスト要因を含めたトータルな資金繰りでシミュレーションすることが、賢明な経営判断につながります。
税務のルールは複雑で、個々の状況によって最適な対応は異なります。本記事で基本的な知識を深めた上で、具体的な判断に迷う場合は、顧問税理士などの専門家に相談することをお勧めします。正しい知識を武器に、健全で力強い事業運営を目指しましょう。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…