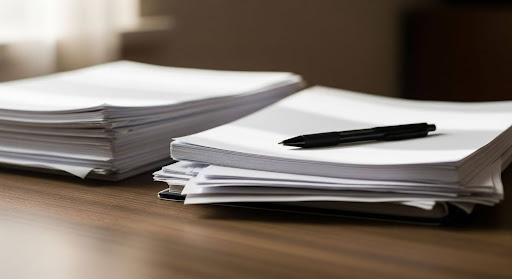
毎年7月、多くのビジネスパーソンが頭を悩ませる算定基礎届。もし、この手続きがミスなく、スムーズに、そして自信を持って完了できるとしたら、どれだけ安心できるでしょうか。本記事は、その未来を実現するための具体的な羅針盤です。
この記事を最後まで読めば、算定基礎届の目的から具体的な記入方法、複雑なケースの対処法、そして万が一の罰則まで、全体像を完全に理解できます。もう断片的な情報を探して時間を無駄にすることはありません。
専門用語はかみ砕いて解説し、豊富な図解と具体的な記入例を交えて、誰にでも実践できるよう構成しました。あなたが経理や労務の初心者であっても、この記事に沿って進めるだけで、正確な書類を期限内に提出できます。
目次
算定基礎届とは?社会保険料が決まる年に一度の重要手続き
算定基礎届は、年に一度、全従業員の社会保険料を見直すための非常に重要な手続きです。この手続きを正しく理解することが、ミスのない申告への第一歩となります。
算定基礎届の基本 「定時決定」の心臓部
算定基礎届とは、正式名称を「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。これは、健康保険や厚生年金保険の保険料を計算する基礎となる「標準報酬月額」を、年に一度、実態に合わせて見直すために提出する書類です。この毎年行われる見直しの手続きを「定時決定」と呼びます。
事業主は、毎年4月、5月、6月に従業員へ支払った給与をもとに届出書を作成し、日本年金機構や健康保険組合へ提出します。提出された算定基礎届に基づき、その年の9月から翌年8月まで適用される新しい標準報酬月額が決定されるのです。
なぜ毎年必要なのか?報酬の変動を保険料に反映させるため
従業員の給与は、昇給や手当の変更、残業時間の増減など、さまざまな理由で変動します。もし保険料が何年も同じままでは、実際の給与額と保険料負担の間に大きな乖離が生まれてしまいます。
そこで、年に一度の定時決定によって、実際の報酬額と標準報酬月額のズレを修正します。これにより、従業員と事業主が負担する社会保険料が、常に公平で適正な金額に保たれるのです。
この手続きは、単なる事務作業ではなく、社会保険制度の公平性を支える根幹的な仕組みといえます。従業員の将来の年金受給額にも影響を与えるため、正確な申告が求められます。
重要用語をわかりやすく解説
算定基礎届を理解する上で、いくつかの専門用語を知っておく必要があります。ここでは、特に重要な3つの用語を解説します。
標準報酬月額
標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするために、従業員の月々の給与を一定の範囲(等級)で区切ったものです。実際の給与額そのものではなく、保険料額表に定められた等級に当てはめて決定されます。例えば、報酬月額が21万円から23万円の間の従業員は、すべて「22万円」の等級として扱われ、同じ保険料が適用されます。
報酬
算定基礎届でいう「報酬」とは、基本給だけではありません。労働の対償として事業主から受け取るすべてのものが含まれます。具体的には、基本給、役職手当、通勤手当、住宅手当、残業手当などが対象です。
さらに、通勤定期券や社宅といった金銭以外で支給される「現物給与」も報酬に含まれます。一方で、結婚祝い金のような一時的なものや、出張旅費などの実費弁済的なものは報酬に含めません。
支払基礎日数
支払基礎日数は、給与計算の対象となった日数のことで、算定基礎届の計算において最も重要な項目の一つです。給与形態によって数え方が異なります。
月給制の場合は原則としてカレンダー上の日数(暦日数)ですが、日給や時給制の場合は実際に出勤した日数となります。この日数が、後述する計算の対象月を判断する基準となります。
提出期限と対象者 「いつまでに、誰の分を」を正確に把握する
算定基礎届の手続きで最も重要なのが、提出期限と対象者を正確に把握することです。「いつまでに」「誰の分を」提出すべきかを間違えると、手続きの遅延や漏れにつながります。
提出期限は毎年7月10日 1日でも遅れてはいけない絶対のルール
算定基礎届の提出期間は、毎年7月1日から7月10日までと定められています。この期限は厳守しなければなりません。
ただし、7月10日が土曜日、日曜日、または祝日にあたる場合は、翌営業日が提出期限となります。例年6月中旬ごろに、日本年金機構から対象者の情報が印字された算定基礎届の用紙が事業所に郵送されてきます。書類が届いたらすぐに内容を確認し、余裕をもって準備を始めることが大切です。
提出対象となる従業員 「7月1日時点」がすべての基準
算定基礎届の提出対象となるのは、原則として7月1日時点で社会保険の被保険者であるすべての従業員です。この「7月1日時点」という基準がすべてを判断する上での絶対的なルールとなります。
対象者には、正社員だけでなく、以下の従業員も含まれます。
- 社会保険の加入要件を満たすパートタイマーやアルバイト
- 産前産後休業、育児休業、介護休業、または病気で休職中の従業員
- 70歳以上の被用者
(厚生年金保険の被保険者ではないが、健康保険の被保険者である場合など)
重要なのは、給与の支払いがあったかどうかではなく、7月1日時点で在籍し、被保険者資格を持っているかどうかで判断する点です。
提出が不要になる主なケース 間違いやすいポイントを整理
一方で、7月1日時点で被保険者であっても、算定基礎届の提出が不要となるケースがあります。これらを正しく理解することで、無駄な作業を減らし、ミスを防ぐことができます。
まず、6月1日以降に入社した従業員は提出が不要です。算定の基礎となる4月、5月、6月の給与支払実績がないため、その年の定時決定の対象外となります。これらの従業員の標準報酬月額は、翌年の定時決定で見直されます。
次に、6月30日以前に退職した従業員も対象外です。7月1日時点では被保険者の資格を喪失しているため、提出は不要となります。たとえ6月分の給与が支払われていたとしても、7月1日に在籍していなければ対象にはなりません。
また、7月に月額変更届を提出する従業員も、算定基礎届の提出は不要です。4月の昇給などにより固定的賃金に大きな変動があり、7月改定の「月額変更届」を提出する場合、月額変更届による「随時改定」が優先されます。
同様に、8月または9月に月額変更が予定されている従業員も提出は不要です。5月や6月の昇給により、8月または9月に随時改定が行われることが確定している場合も、随時改定が優先されるためです。これらの除外ケースを判断する際も、基準は常に「7月1日時点」の状況と、それ以降に「随時改定が優先されるか」という点にあります。
算定基礎届の書き方完全マニュアル 項目別・ステップバイステップ解説
ここからは、実際に算定基礎届を記入する手順を、ステップバイステップで詳しく解説します。各項目の意味を理解しながら進めることで、正確な書類作成が可能になります。
準備するものリスト 書類作成を始める前に
スムーズに作業を進めるため、事前に以下の書類を手元に用意しましょう。
- 算定基礎届の用紙
(6月中旬に郵送されるもの、または日本年金機構のウェブサイトからダウンロードしたもの) - 賃金台帳(4月、5月、6月分)
- 出勤簿またはタイムカードなど(4月、5月、6月分)
- 就業規則・給与規程(欠勤控除のルールなどを確認するため)
STEP 1 支払基礎日数の計算 最も重要で間違いやすい項目
まず、算定基礎届の⑩「支払基礎日数」欄を記入します。この日数は、後の計算すべての基礎となるため、最も正確性が求められる項目です。給与形態によって数え方が異なるため、注意が必要です。
| 給与形態 | 支払基礎日数の数え方 | 注意点 |
| 月給制 | 暦日数(カレンダーの日数) | 欠勤控除がある場合は「所定労働日数 − 欠勤日数」で計算します。 |
| 日給制 | 実際の出勤日数 | 有給休暇を取得した日も出勤日数に含めます。 |
| 時給制 | 実際の出勤日数 | 有給休暇を取得した日も出勤日数に含めます。 |
例えば、月給制で4月分の給与を計算する場合、支払基礎日数は「30日」となります。日給制の従業員が4月に20日出勤し、1日有給休暇を取得した場合、支払基礎日数は「21日」です。
STEP 2 報酬月額の記入 通貨と現物を分けて正しく集計
次に、4月、5月、6月の各月に支払った報酬を記入します。報酬は「通貨」と「現物」に分けて記入する必要があります。
通貨(項目⑪)には、基本給、各種手当、残業代など、現金で支払われた税引前の総支給額を記入します。現物(項目⑫)には、通勤定期券や食事、社宅など、金銭以外で支給されたものの価額を記入します。これらは厚生労働大臣が定める価額に基づいて金銭に換算し、現物支給がない場合は空欄または「0」を記入してください。
最後に、合計(項目⑬)として、通貨と現物の合計額を記入します。通勤手当を現金で支給している場合は「通貨」に、会社が購入した定期券を現物で渡している場合は「現物」に記入するなど、支給形態に応じて正しく分類することが重要です。
STEP 3 総計と平均額の算出 3ヶ月の平均を出す
3ヶ月分の報酬を記入したら、⑭「総計」と⑮「平均額」を計算します。ここで重要になるのが「17日ルール」です。原則として、支払基礎日数が17日以上の月のみが算定の対象となります。
支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上の場合、3ヶ月分の合計額(⑬)を足して総計(⑭)に記入し、その額を3で割ったものを平均額(⑮)に記入します。小数点以下は切り捨ててください。
支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、17日以上の月の合計額(⑬)だけを足して総計(⑭)に記入します。そして、その対象となった月数(1ヶ月または2ヶ月)で割ったものを平均額(⑮)に記入します。
支払基礎日数が3ヶ月とも17日未満の場合は、3ヶ月とも算定対象外となり、原則として従前の標準報酬月額が引き続き適用されます。これは「保険者算定」と呼ばれ、総計や平均額の欄は記入しません。この平均額が、新しい標準報酬月額を決定するための「報酬月額」となります。
STEP 4 備考欄の記入 特殊ケースを正しく伝える
最後に、従業員の状況に応じて「備考」欄に正しくチェックを入れる、または記入します。この欄は、年金事務所に特殊な事情を伝えるための重要なシグナルです。
特に、8月または9月に月額変更届を提出予定の場合(3. 月額変更予定)、4月1日以降に入社した場合(4. 途中入社)、算定対象期間中に休職していた場合(5. 病休・育休・休職等)などが重要です。
また、週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3未満などの特定の要件を満たす場合は「6. 短時間労働者」、これに該当しないパートタイマーの場合は「7. パート」にチェックします。これらの情報を正しく伝えることで、年金事務所側での審査がスムーズに進み、適切な標準報酬月額が決定されます。
特殊なケースの対応方法 パート、休職者、報酬変動の大きい従業員
現代の多様な働き方に対応するため、算定基礎届には多くの例外規定が設けられています。ここでは、特に判断に迷いやすい特殊なケースの対応方法を解説します。
パート・アルバイト従業員の算定(短時間就労者・短時間労働者)
パート・アルバイト従業員の算定では、まず「短時間労働者」に該当するかどうかを確認する必要があります。
「短時間労働者」とは、週の所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が8.8万円以上などの特定の要件をすべて満たす従業員です。この場合、支払基礎日数が11日以上の月を算定対象とし、備考欄は「6. 短時間労働者」にチェックします。
上記の短時間労働者に該当しない一般的なパートタイマーは「短時間就労者」に分類されます。この場合は、原則通り支払基礎日数が17日以上の月を対象とします。ただし、3ヶ月とも17日未満の場合は、15日以上の月を対象とする特例があります。備考欄は「7. パート」にチェックします。このように、パート従業員と一括りにせず、どちらの区分に該当するかを正しく判断し、適用される支払基礎日数の基準を使い分けることが重要です。
産休・育休・病気休職中の従業員
4月、5月、6月の全期間にわたって産休、育休、または私傷病による休職で給与の支払いが全くなかった、あるいは著しく低額だった従業員も、7月1日時点で在籍していれば算定基礎届の提出対象です。
この場合、報酬の変動は一時的なものであるため、新しい標準報酬月額は計算せず、休職に入る前の標準報酬月額がそのまま継続されます。これを「保険者算定」といいます。
記入の際は、報酬に関する欄(⑪から⑮)はすべて「0」と記入します。そして、備考欄の「5. 病休・育休・休職等」にチェックを入れ、さらに「9. その他」の欄に「〇月〇日から育児休業中」のように具体的な理由と期間を記入します。これにより、年金事務所は保険者算定として処理を行います。
繁忙期などで報酬が著しく変動する場合(年間平均)
通常、算定基礎届は4月、5月、6月の3ヶ月間の報酬で計算しますが、この期間が会社の繁忙期にあたり、残業代が急増するなどして、年間の平均的な給与と比べて著しく高くなることがあります。
このような場合、本来の標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの1年間の報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、従業員が同意すれば、特例として年間平均で算定することが認められています。
この特例を適用するには、「年間報酬の平均で算定することの申立書」などを添付して申請する必要があります。従業員の不利益にならないよう、このような救済措置があることも知っておくとよいでしょう。
賞与が年4回以上支給される場合
賞与(ボーナス)は通常、算定基礎届の月額報酬には含めず、別途「賞与支払届」を提出します。しかし、年間の支給回数が4回以上となる賞与は、給与の一部とみなされ、算定基礎届の計算に含める必要があります。
この場合の計算方法は、前年7月1日から当年6月30日までの1年間に支払われた賞与の合計額を12で割り、その金額を4月、5月、6月の各月の報酬に加算して平均額を算出します。年3回以下の賞与とは取り扱いが全く異なるため、自社の賞yo支給規定をよく確認する必要があります。
最重要知識!算定基礎届と月額変更届の違いと優先順位
労務担当者が最も混同しやすいのが、「算定基礎届」と「月額変更届」の違いです。どちらも標準報酬月額を見直す手続きですが、目的とタイミングが全く異なります。この違いを理解することが、適切な手続きを選択する鍵となります。
「定時決定」と「随時改定」 年1回の見直しと、都度行う見直し
まず、二つの手続きの根本的な違いを整理しましょう。算定基礎届によって行われる「定時決定」は、年に一度、全被保険者を対象に行う定期的なメンテナンスです。4月から6月の報酬を基に、9月からの保険料を決定します。
一方、月額変更届によって行われる「随時改定」は、昇給や降給などで固定的賃金に大幅な変動があった特定の被保険者を対象に、その都度行う緊急メンテナンスです。
変動後の3ヶ月間の報酬を基に、速やかに保険料を実態に合わせます。簡単に言えば、定時決定は「全従業員の定期健康診断」、随時改定は「給与が大きく変わった従業員の緊急手術」のようなイメージです。
月額変更届が必要になる3つの条件
月額変更届(随時改定)は、いつでも提出できるわけではありません。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
第一に、昇給・降給などにより、固定的賃金(基本給、役職手当など)に変動があったこと。第二に、変動後の3ヶ月間に支払われた給与の平均額から算出した標準報酬月額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたこと。
そして第三に、変動後の3ヶ月間とも、支払基礎日数が17日以上であったことです。残業代などの非固定的賃金の増減だけでは、月額変更の対象にはなりません。
どちらを優先する?7月から9月改定のルール
算定基礎届の提出時期と月額変更のタイミングが重なる場合、どちらの手続きを優先するのでしょうか。答えは明確で、月額変更届(随時改定)は、常に算定基礎届(定時決定)よりも優先されます。
例えば、4月に昇給があり、4月、5月、6月の給与で月額変更の要件を満たす場合、月額変更届を提出し、7月改定が優先されます。この従業員の算定基礎届は提出不要、または備考欄に「7月改定者」と記載します。5月昇給で8月改定の場合も同様に、随時改定が優先されます。
6月昇給の場合は少し複雑です。まず、算定基礎届を通常通り提出し、9月分の保険料は定時決定された額で納付します。その後、6月、7月、8月の給与で月額変更届を提出し、10月からは随時改定された新しい標準報酬月額が適用されます。
この優先順位を理解していないと、誤った保険料を徴収してしまう可能性があるため、特に4月から6月に給与改定がある場合は注意が必要です。
| 項目 | 算定基礎届(定時決定) | 月額変更届(随時改定) |
| 手続きの名称 | 定時決定 | 随時改定 |
| 目的 | 年に一度の定期的な見直し | 大幅な報酬変動に応じた都度の見直し |
| 対象者 | 全ての被保険者 | 3つの条件を満たした被保険者 |
| 提出時期 | 毎年7月1日〜7月10日 | 固定的賃金の変動があった都度 |
| 適用開始月 | 9月分の保険料から | 変動後4ヶ月目の保険料から |
| 優先度 | 随時改定が優先される | 定時決定より優先される |
提出が遅れたらどうなる?遅延・不提出のリスクと罰則
算定基礎届の提出は法律で定められた事業主の義務です。提出が遅れたり、提出しなかったりした場合には、単なる手続きの遅れでは済まされない、さまざまなリスクが伴います。
まずは年金事務所からの督促
提出期限である7月10日を過ぎても提出がない場合、まず年金事務所から文書による督促状が届きます。この段階で速やかに対応すれば大きな問題にはなりませんが、これを無視し続けると、電話での催促や、年金事務所への来所を求められるなど、対応はより厳しいものになっていきます。
立ち入り調査と遡及手続きの発生
度重なる督促にも応じない場合、年金事務所の職員が事業所に直接訪れる「立入検査」が行われる可能性があります。
さらに、最終的には年金事務所が職権で標準報酬月額を決定することになります。この場合、過去に遡って算定基礎届の作成と、差額保険料の納付を命じられます。過去の給与データを洗い出し、一人ひとりの保険料を再計算する作業は、非常に大きな事務負担となります。
法律上の罰則 懲役または罰金のリスク
算定基礎届の不提出や虚偽の記載は、法律違反です。健康保険法や厚生年金保険法に基づき、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。これは企業にとって直接的な経済的損失であると同時に、社会的な信用を損なう重大な事態です。
見えないコスト 従業員からの信頼失墜
罰則以上に深刻なのが、従業員からの信頼を失うことです。算定基礎届の提出が遅れると、9月からの正しい保険料が確定せず、従業員の給与から天引きする保険料額が誤っている可能性があります。
保険料を過剰に徴収すれば従業員の生活を圧迫し、不満の原因となります。逆に過少に徴収すれば、将来受け取る年金額が減ってしまうなど、従業員の将来に直接的な不利益を与えかねません。給与や社会保険という、従業員の生活の根幹に関わる部分でのミスは、企業への不信感を増大させ、職場の士気を著しく低下させる「見えないコスト」となるのです。
業務効率化のヒント 電子申請と年間労務スケジュールの活用

毎年発生する算定基礎届の手続きは、少しの工夫で業務負担を大幅に軽減できます。ここでは、電子申請の活用と、年間を通じた計画的な業務管理について解説します。
e-Govによる電子申請のススメ
算定基礎届は、郵送や窓口持参だけでなく、政府のオンラインサービス「e-Gov(イーガブ)」を利用した電子申請が可能です。電子申請には以下のようなメリットがあります。
- 24時間365日、いつでも申請可能
- 郵送コストや移動時間がかからない
- 申請データの控えを管理しやすい
- 処理の進捗状況をオンラインで確認できる
電子申請を始めるには、事前の準備が必要です。まず、法人向けの共通認証システム「GビズID」のアカウントを取得します。次に、日本年金機構が提供する専用ソフトをPCにインストールし、申請用のCSVデータを作成します。
最後に、e-Govの利用に必要なソフトウェアのインストールや設定を行います。最初は少し手間がかかりますが、一度環境を整えれば、翌年以降の手続きが格段にスムーズになります。
算定基礎届を年間スケジュールに組み込む
算定基礎届を「7月の突発的なイベント」と捉えるのではなく、年間の労務管理サイクルの一部として計画に組み込むことが重要です。これにより、慌てずに準備を進めることができます。
| 月 | 主な手続き |
| 4月 | 36協定の届出(更新)、新入社員の社会保険手続き |
| 6月〜7月 | 労働保険の年度更新 |
| 7月 | 算定基礎届の提出、高年齢者・障害者雇用状況報告書 |
| 10月 | 最低賃金改定の確認・対応 |
| 11月〜12月 | 年末調整の準備・実施 |
| 1月 | 法定調書・給与支払報告書の提出 |
このように、年間を通じて主要な労務手続きは決まっています。6月の労働保険年度更新の準備と並行して、算定基礎届に必要な4月、5月分の給与データを整理し始めるなど、計画的に業務を進めることで、7月の繁忙期を乗り切ることができます。
よくある質問(Q&A)
ここでは、算定基礎届に関して特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 届いた算定基礎届に、最近入社した社員の名前がありません。追記すべきですか?
A1. いいえ、追記しないでください。郵送される用紙は5月中旬時点の情報で作成されています。5月31日以前に入社した従業員で名前がない場合は、後日、追加でその従業員用の用紙が送付されます。6月1日以降に入社した従業員は、そもそも今年の算定基礎届の対象外です。
Q2. 提出後に間違いに気づきました。どうすればいいですか?
A2. 速やかに管轄の年金事務所または健康保険組合に連絡してください。誤った箇所を訂正した「算定基礎届訂正届」を再提出する必要があります。放置せず、自ら速やかに訂正することが重要です。
Q3. 7月1日以降に退職予定の社員がいます。提出は必要ですか?
A3. はい、必要です。算定基礎届の対象者は「7月1日時点」で在籍しているかどうかで判断します。7月1日時点では被保険者であるため、通常通り算定基礎届を作成し、提出する必要があります。
Q4. テレワーク手当は報酬に含めますか?
A4. ケースバイケースです。通信費や光熱費などの実費を弁償する目的で支払われる場合は報酬に含めませんが、実費に関わらず一律で支給される手当は、原則として報酬に含まれます。支給の実態や就業規則の定めに基づき、慎重に判断する必要があります。
Q5. 4月に昇給があり、7月改定の月額変更届を提出します。算定基礎届はどうすれば?
A5. その従業員については、月額変更届(随時改定)が優先されます。算定基礎届の報酬に関する欄は記入せず、備考欄の「3. 月額変更予定」にチェックを入れるか、二重線で氏名を抹消し「7月改定」と明記して提出します。別途、月額変更届の提出を忘れないようにしてください。
提出前の最終チェックリストと要点の再確認

最後に、算定基礎届を提出する前に確認すべき要点と、最終チェックリストをまとめました。万全の準備で、ミスのない提出を目指しましょう。
要点サマリー
提出期限は7月10日厳守です。対象者は7月1日時点の全被保険者であり、休職者も含まれますが、6月1日以降の入社者や6月30日以前の退職者は対象外となります。
計算の基礎となるのは、4月、5月、6月に支払われた報酬と、給与形態に応じた正しい「支払基礎日数」です。そして最も重要なルールとして、月額変更届(随時改定)は、算定基礎届(定時決定)より常に優先されることを覚えておきましょう。
提出直前!最終確認チェックリスト
[ ] 全ての対象者がリストにいるか?(除外すべき人は除いたか?)
[ ] 各従業員の支払基礎日数の計算は正しいか?(月給制と時給制を混同していないか?)
[ ] 報酬に含めるべき手当(通勤手当など)は全て計上したか?
[ ] 3ヶ月平均の計算は正しいか?(17日未満の月は除外したか?)
[ ] パートタイマーや休職者など、特殊ケースの備考欄記入は漏れていないか?
[ ] 月額変更届が優先される従業員を正しく処理したか?
[ ] 事業主情報、押印(または電子署名)は完璧か?
この記事が、あなたの算定基礎届に関する不安を解消し、確実な手続きを遂行するための一助となれば幸いです。








閑散期とは?産業別の閑散期についても解説
資本主義経済におけるビジネスサイクルは、決して一定の速度で進行するものではありません。需要と供給のバ…