
日々の業務で何気なく扱っている「納品書」と「送り状」。これらの書類を正確に使い分けることで、取引先との信頼関係が深まり、経理処理や在庫管理が驚くほどスムーズになる未来を想像したことはありますか。書類一枚の違いが、ビジネスの効率と信用を大きく左右します。
もし「違いをうまく説明できない」「法律的に問題ないか不安」と感じているなら、それは業務改善の大きなチャンスです。
この記事を読めば、納品書と送り状の根本的な違いから、それぞれの役割、正しい作成方法、そして法律上の注意点まで、実務で本当に役立つ知識がすべて手に入ります。
複雑に思える「信書」のルールや、近年対応が必須となったインボイス制度、電子帳簿保存法についても、専門家でなくても理解できるよう、一つひとつ丁寧に解説します。
「法律は難しそう」「新しい制度に対応できるか心配」という不安に寄り添い、明日からすぐに実践できる具体的な手順や注意点を示します。
この記事を最後まで読めば、書類の扱いで迷うことはありません。自信を持って業務をこなし、取引先からも社内からも頼られる存在になるための一歩を、ここから踏み出しましょう。
目次
納品書とは-取引の信頼を支える内容証明の役割
納品書とは、商品やサービスを納品する際に、受注者(売り手)が発注者(買い手)に対して発行する書類です。その主な目的は、「いつ、何を、いくつ、いくらで納品したか」を明確に伝え、取引内容に間違いがないことを証明することにあります。
法的には、納品書の発行は義務付けられていません。しかし、日本の商習慣において、ほとんどの取引で発行されています。なぜなら、納品書がなければ、受け取った側は注文した通りの品物がすべて揃っているかを正確に確認するのが難しくなるからです。
特に、同じ商品を複数回に分けて発注した場合など、納品書がなければ、どの納品がどの注文に対応するものなのかがわからなくなり、混乱を招く可能性があります。
納品書は、単なる物品のリストではありません。取引の透明性を確保し、双方の認識のズレを防ぐための重要なコミュニケーションツールです。受け取った側は納品書と現物を照合することで、契約通りの納品が行われたことを確認でき、安心して検収作業を進められます。
万が一、数量の間違いや品違いがあった場合でも、納品書があれば速やかに問題を指摘し、解決につなげることができます。
このように、納品書は法的な強制力はなくとも、取引の円滑化とトラブル防止に不可欠な役割を果たしています。経理上も、納品書と請求書を紐づけることで、請求内容が正しく、納品済みであることを確認できるため、支払処理を効率化する助けとなります。それは、取引相手への「思いやり」の表れとも言えるでしょう。
送り状とは-荷物を確実に届けるための伝票
送り状とは、荷物を発送する際に荷物本体に貼り付ける伝票のことです。配送伝票、宅配伝票、荷札などとも呼ばれますが、その役割はすべて同じです。
送り状の唯一かつ最大の目的は、配送業者が荷物を送り主から届け先まで正確かつ安全に運ぶための情報を提供することです。送り状には、以下の重要な情報が記載されています。
- 届け先の住所、氏名、電話番号
- 送り主の住所、氏名、電話番号
- 内容物の品名
- 配達希望日時や「ワレモノ注意」などの取り扱いに関する指示
これらの情報に誤りがあると、配送遅延や誤配、最悪の場合は荷物の紛失といったトラブルに直結します。そのため、送り状は物流における「命綱」とも言える非常に重要な書類です。
また、送り状には「送り状番号(追跡番号)」が記載されており、これを使って荷物が今どこにあるのかをオンラインで追跡できます。これにより、送り主も届け先も安心して荷物の到着を待つことができます。送料の支払い方法によって、送り状の種類も異なります。
- 元払い(発払い) – 送り主が送料を負担する場合
- 着払い – 届け先が送料を負担する場合
- 代引き – 届け先が商品代金と送料を荷物と引き換えに支払う場合
納品書が「取引の当事者間」で交わされる書類であるのに対し、送り状は「送り主、届け先、そして配送業者」という三者をつなぐ、物流プロセスの根幹をなす書類なのです。
納品書と送り状の決定的な違い
納品書と送り状は、どちらも商品の納品時に使われるため混同されがちですが、その目的と役割は全く異なります。両者の違いを正しく理解することが、業務のミスを防ぐ第一歩です。
根本的な違いは、「誰が」「何のために」見る書類かという点にあります。納品書は取引先(買い手)が「契約通りの商品が届いたか」を確認するための書類です。一方、送り状は配送業者が「荷物をどこへ届けるか」を把握するための書類です。
この目的の違いが、記載される内容の差に直結します。納品書には商品の単価や合計金額といった金銭的な情報が含まれますが、送り状には通常、これらの情報は記載されません。
以下の比較表で、その違いを明確に整理しましょう。
| 項目 | 納品書 | 送り状(配送伝票) |
| 目的 | 納品内容が注文通りかを確認する | 荷物を正確に目的地へ届ける |
| 主な利用者 | 取引先(買い手) | 配送業者 |
| 記載内容 | 商品名、品番、数量、単価、合計金額など | 届け先・送り主の住所、氏名、電話番号、品名、追跡番号など |
| 発行者 | 受注者(売り手) | 荷送人(送り主) |
| 法的義務 | 発行義務なし | 荷物の発送に必須 |
| 信書該当性 | 該当する | 該当するが、「貨物に添付する無封の添え状」として例外扱いあり |
基本的に、送り状を納品書の代わりにすることはできません。ただし、例外的に送り状に商品の数量や単価、金額などを詳細に記載すれば、納品書としての役割を兼ねることも不可能ではありませんが、これは一般的な運用ではありません。業務を明確に分けるためにも、納品書と送り状はそれぞれ別の書類として正しく準備することが重要です。
法律上の注意点-納品書は「信書」
納品書の扱いで最も注意すべき点が、法律上の「信書(しんしょ)」に該当するという事実です。これを知らずにいると、意図せず法律違反を犯してしまう可能性があります。
信書の定義
信書とは、郵便法で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。具体的には、手紙や請求書、領収書、契約書などがこれにあたり、納品書も「取引先に納品の事実を通知する文書」であるため、明確に信書に分類されます。
信書の送付に関する法的ルール
日本の法律では、信書の送達は原則として日本郵便株式会社および国から許可を得た信書便事業者に限定されています。そのため、ヤマト運輸の「宅急便」や佐川急便の「飛脚宅配便」といった一般的な宅配便サービスで信書を送ることは、法律で禁止されています。
違反した場合、送った側も運んだ側も罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。
実務上の正しい送付方法と例外措置
「では、いつも商品と一緒に宅配便で送っている納品書は違法なのか?」と不安に思うかもしれません。しかし、心配は不要です。法律には、商習慣の実態に合わせた例外規定が設けられています。
それが、「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」は、宅配便で送ってもよい、というルールです。ここで重要なポイントは2つです。
- 貨物(商品)に添付されていること
納品書単体を宅配便で送ることはできません。あくまで商品が主役で、納品書はそれに付随する書類である必要があります。 - 無封(むふう)であること
「封をしていない」状態を指します。封筒に入れて糊付けしたり、テープで封をしたりすると違反になります。封筒に入れない、クリアファイルに入れる、あるいは封をしない状態の封筒に入れるといった方法であれば、この例外規定が適用され、合法的に商品と同梱できます。
したがって、実務上の最も一般的な対応は以下の通りです。
- 商品と同梱する場合
納品書をクリアファイルに入れるか、封をしない封筒に入れて、商品と一緒に梱包します。 - 納品書を別途送る場合
日本郵便の普通郵便やレターパックなどを利用します。
このルールは、国の郵便事業の独占を守るという歴史的背景と、現代の商業活動の利便性を両立させるための重要な妥協点です。この例外措置を正しく理解し活用することで、コンプライアンスを遵守しながら効率的な業務を維持できます。
業務フローの効率化-納品書と送り状の電子化

紙ベースでの書類作成や管理は、多くの時間とコストを要します。近年、業務効率化とペーパーレス化の流れの中で、納品書や送り状を電子データで扱う「電子化」が急速に普及しています。
納品書・送り状を電子化するメリット
電子化には、以下のような多くのメリットがあります。
- コスト削減
紙代、印刷代、インク代、郵送費、そして書類を保管するためのファイルやキャビネット、倉庫スペースといった物理的なコストが不要になります。 - 業務効率の大幅な向上
書類の作成から印刷、三つ折り、封入、発送という一連の手作業が不要になります。システムを使えば数クリックで発行・送信が完了し、本来のコア業務に集中できます。 - ヒューマンエラーの防止
手作業による転記ミスや宛先間違い、発送漏れといった人為的なミスを大幅に削減できます。 - 検索性と管理の容易さ
電子データは、取引先名や日付、書類番号などで簡単に検索できます。過去の取引をすぐに確認できるため、問い合わせ対応や監査の際にも迅速に対応可能です。 - セキュリティの強化
アクセス権限の設定やパスワード保護により、不正な閲覧や持ち出しを防げます。また、バックアップを取ることで、紛失や災害によるデータ消失のリスクにも備えられます。
電子化の注意点と課題
多くのメリットがある一方で、電子化を進める際にはいくつかの注意点も存在します。
- 導入コストとシステム連携
新たなシステムを導入するには初期費用や月額利用料がかかります。また、既存の販売管理システムや会計システムとスムーズに連携できるかどうかの確認も重要です。 - 取引先の協力
自社が電子化を進めても、取引先が紙の書類を希望する場合があります。その場合、紙と電子の両方に対応する必要が生じるため、事前に取引先の理解と協力を得ることが不可欠です。これは技術的な課題以上に、取引関係における調整が必要な点です。 - セキュリティ対策
電子データはサイバー攻撃やウイルス感染による情報漏洩のリスクを伴います。信頼できるセキュリティ対策が施されたシステムを選ぶことが極めて重要です。
納品書・送り状の作成に便利なシステムとツール
納品書の作成
ExcelやWordでも作成可能で、インターネット上には無料で利用できる多様なテンプレートが存在します。しかし、発行枚数が多い場合は、見積書から請求書まで一気通貫で作成・管理できるクラウド型の請求書発行システムを利用すると、転記ミスなく効率的に業務を進められます。
送り状の作成
ヤマト運輸の「B2クラウド」や佐川急便の「e飛伝Ⅲ」など、主要な配送業者は無料で利用できる送り状発行システムを提供しています。これらのシステムは、住所録の管理やCSVデータの一括取り込み、ECサイトとの連携など、出荷業務を大幅に効率化する機能を備えています。手書きに比べて、宛名間違いなどのミスを劇的に減らすことができます。
最新法令への対応-インボイス制度と電子帳簿保存法

近年、経理・総務担当者が必ず押さえておくべき2つの重要な法改正がありました。インボイス制度と電子帳簿保存法です。これらは納品書の作成と保存方法に直接影響します。
インボイス制度と納品書
2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。
この適格請求書は、「請求書」という名称である必要はありません。法律で定められた項目が記載されていれば、納品書や領収書でも適格請求書として扱うことが可能です。納品書を適格請求書として利用する場合、従来の記載項目に加えて、以下の情報を追記する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
(税務署から通知される「T」で始まる13桁の番号) - 適用税率(税率ごと、10%または8%に区分して記載)
- 税率ごとに区分した消費税額等(税率ごとに合計した消費税額を明記)
なお、請求書と納品書など、複数の書類を組み合わせて、全体として適格請求書の記載要件を満たすことも認められています。
電子帳簿保存法と納品書
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。納品書もこの法律の対象となります。
特に重要なのが、2024年1月1日から完全施行されたルールです。メールの添付ファイル(PDFなど)やクラウドサービス経由で受け取った納品書は、電子データのまま保存することが義務化されました。これを印刷して紙で保存することは、原則として認められません。
保存方法のパターンは以下の通りです。
- 電子データで受け取った納品書
電子データのまま保存が必須です。 - 紙で受け取った納品書
従来通り紙のまま保存するか、一定の要件(スキャナ保存要件)を満たしてスキャンし、電子データとして保存することも可能です。
これらの法改正は、単なる事務手続きの変更ではありません。企業に対して、取引書類のデジタル化への対応を強く促すものです。特に電子取引のデータ保存義務化は、これまで紙ベースで業務を行ってきた企業にとって、業務フローの根本的な見直しを迫る大きな変化と言えます。
なお、納品書の保存期間は、紙でも電子データでも変わりません。法人は原則7年間(欠損金が生じた事業年度は10年間)、個人事業主は原則5年間(消費税の課税事業者は7年間)の保存が必要です。
実践編-トラブルを防ぐ作成と再発行のポイント
日々の業務で発生しがちなトラブルを未然に防ぐため、納品書と送り状の作成時および再発行時の具体的なポイントを押さえておきましょう。
納品書・送り状の正しい書き方
納品書の作成ポイント
- 宛名の敬称
会社や部署宛ての場合は「御中」、担当者個人宛ての場合は「様」を正しく使い分けます。 - 必須項目の網羅
宛名、納品日、納品書番号、発行者情報、そして納品内容(品番、品名、数量、単価、金額)を正確に記載します。 - 管理番号の記載
必須ではありませんが、社内管理や問い合わせ時のために、連番の納品書番号を記載することが推奨されます。
送り状の作成ポイント
- 正確性が命
届け先の住所、会社名、担当者名、電話番号に誤りがないか、複数回確認します。配送業者のシステムが持つ住所検索機能を活用すると、入力ミスを防げます。 - 品名の具体性
内容物は「雑貨」や「書類」などと曖昧に書かず、「書籍」「衣類」「精密機器」など、できるだけ具体的に記載します。これにより、配送業者が適切な取り扱いをしやすくなります。
納品書の再発行を依頼された場合の対応
取引先から納品書の紛失や記載ミスを理由に再発行を依頼されることは珍しくありません。その際は、以下のルールを徹底してください。これがトラブルを避ける鍵となります。
日付と番号は変更しないことが重要です。再発行する納品書の「納品日」と「納品書番号」は、最初に発行したものと全く同じものを記載します。日付を再発行日に変更してしまうと、二重計上や経理処理の混乱を招く原因となります。
書類のどこかに「再発行」という文言をはっきりと記載するか、スタンプを押します。これにより、後から元の納品書が見つかった場合でも、どちらが正しい書類か一目でわかり、二重処理を防ぐことができます。
迅速かつ丁寧な対応も求められます。特に自社の記載ミスが原因の場合は、速やかにお詫びの連絡を入れ、丁寧に対応することが信頼関係を維持するために不可欠です。納品書の再発行依頼は、単なる事務作業と捉えず、自社の受注から納品までのプロセスに不備がないかを見直すきっかけとすることが、より戦略的な対応と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、納品書と送り状という、ビジネスの現場で不可欠な2つの書類について、その違いから法律上の注意点、最新の制度対応までを網羅的に解説しました。最後に、円滑な取引を実現するための重要なポイントを再確認しましょう。
- 明確な役割の違いを意識する
納品書は「取引内容」を買い手に証明する書類であり、送り状は「荷物の輸送情報」を配送業者に伝える書類です。この目的の違いが、すべての基本です。 - コンプライアンスを徹底する
納品書は法律上の「信書」です。宅配便で商品と同梱する際は、必ず「無封(封をしない)」の状態にするというルールを遵守しましょう。 - デジタル化の波に乗る
電子帳簿保存法により、電子データで受け取った書類の電子保存が義務化されました。もはやデジタル化は単なる効率化の手段ではなく、法対応のために必須の取り組みです。 - 最新制度へのアップデートを怠らない
インボイス制度に対応するため、必要に応じて納品書のフォーマットを見直し、登録番号などの必須項目を追加しましょう。 - 正確性をすべての土台とする
書類一枚の記載ミスが、請求の遅れや取引先との不要なトラブルにつながります。正確な書類作成は、コスト削減と信頼構築の第一歩です。
納品書と送り状は、日々の業務における小さなパーツかもしれません。しかし、これらを正しく、かつ効率的に扱うことで、ビジネス全体の流れはよりスムーズになり、取引先との良好な関係を築く強固な土台となります。本記事が、あなたの業務改善の一助となれば幸いです。







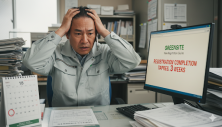
造園施工管理技士1級で手にする高収入と現場の権限!働きながら…
1級造園施工管理技士を取得すれば、あなたの市場価値は劇的に向上し、年収アップやキャリアの自由が手に入…