
複雑な原価計算や確定申告は、多くのビジネスパーソンにとって悩みの種です。しかし、適切な知識を身につければ、これらの課題は解決できます。この記事では、在庫や仮想通貨などの資産評価に用いられる「総平均法」について、計算方法から節税のポイントまで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、複雑な原価計算に頭を悩ませることはなくなります。総平均法をマスターし、自社の利益を正確に把握できるようになるでしょう。その結果、自信を持って確定申告を終え、データに基づいた的確な経営判断を下し、事業を次のステージへと導くことが可能になります。
現在、「在庫の評価額はどう計算するのか」「仮想通貨の利益計算が複雑でわからない」といった不安や焦りを感じている方もいるかもしれません。
間違った計算は、予期せぬ税金の追徴や経営判断のミスにつながるリスクをはらんでいます。多くの方が同様の悩みを抱えていますが、ご安心ください。
この記事では、会計の専門家でなくても理解できるよう、総平均法の計算式から具体的な計算手順、さらには税務上の注意点まで、豊富な図解と事例を用いてわかりやすく解説します。この記事を読み終える頃には、誰でも正確な計算を実践できるようになるはずです。
目次
総平均法とは?会計における基本を理解する
総平均法は、棚卸資産(在庫)や有価証券、暗号資産(仮想通貨)などの資産の取得価額を評価するための計算方法の一つです。会計や税務の世界では、資産の価値を正しく評価することが、企業の財政状態や経営成績を正確に報告するための基本となります。
具体的には、一定期間(通常は1事業年度や1ヶ月間)の期首に保有していた資産と、その期間中に新たに仕入れた資産の合計金額を、それらの合計数量で割ることで、1単位あたたりの平均単価を算出します。そして、この算出された平均単価を用いて、期末に残っている資産の評価額や、期間中に販売された資産の原価(売上原価)を計算します。
この方法は、法人税法や会計基準で公式に認められている「原価法」という評価方法群に属します。原価法には、総平均法の他にも、仕入れたものから順に払い出されると仮定する「先入先出法」、仕入れの都度平均単価を計算し直す「移動平均法」、あるいは宝石や不動産のように個別に原価を管理する「個別法」など、複数の方法が存在します。
総平均法の最大の目的は、仕入れのたびに価格が変動するような資産の単価を平準化し、計算プロセスを簡素化することにあります。特に、同じ種類の商品を大量に、かつ頻繁に仕入れる小売業や卸売業、あるいは価格変動が激しい暗号資産の損益計算などで有効な手法として広く利用されています。
総平均法の計算式と具体的な計算ステップ
総平均法の計算は、その考え方さえ理解すれば非常にシンプルです。ここでは、基本となる計算式と、誰でも簡単に実践できる4つのステップを具体的に解説します。
基本となる計算式
総平均法の中核となるのは、資産1単位あたりの「平均単価」を算出する式です。この平均単価がわかれば、期末の在庫評価額や売上原価も簡単に計算できます。
平均単価の計算式
平均単価 = (期首棚卸資産価額 + 当期仕入総額) ÷ (期首棚卸資産数量 + 当期仕入総数量)
この式を構成する各要素は以下の通りです。
- 期首棚卸資産価額
事業年度の開始時点(期首)で保有していた在庫の評価額です。前期末の棚卸資産価額がそのまま引き継がれます。 - 当期仕入総額
事業年度中に新たに仕入れた在庫の取得価額の合計です。購入代価だけでなく、引取運賃などの付随費用も含まれます。 - 期首棚卸資産数量
期首時点で保有していた在庫の総数です。 - 当期仕入総数量
事業年度中に新たに仕入れた在庫の総数です。
この平均単価を基に、以下の重要な数値を導き出します。
期末棚卸資産評価額の計算式
期末棚卸資産評価額 = 平均単価 × 期末在庫数量
売上原価の計算式
売上原価 = (期首棚卸資産価額 + 当期仕入総額) – 期末棚卸資産評価額
この売上原価の式は、簿記で用いられる売上原価の算定ボックスと同じ考え方に基づいています。
4つのステップによる具体的な計算手順
それでは、簡単な例を使って、実際の計算手順を見ていきましょう。
前提条件
- 期首在庫: 100個, 単価100円 (合計10,000円)
- 4月の仕入: 200個, 単価110円 (合計22,000円)
- 9月の仕入: 150個, 単価120円 (合計18,000円)
- 期間中の売上: 300個
- 期末在庫数量: (期首100個 + 仕入200個 + 仕入150個) – 売上300個 = 150個
ステップ1: 総取得価額を計算する
まず、期首の在庫価額と期間中の仕入総額を合計します。これが、期間中に販売可能だった商品の総原価となります。
計算: 10,000円 (期首) + 22,000円 (4月) + 18,000円 (9月) = 50,000円
ステップ2: 総数量を計算する
次に、期首の在庫数量と期間中の仕入総数量を合計します。
計算: 100個 (期首) + 200個 (4月) + 150個 (9月) = 450個
ステップ3: 平均単価を算出する
ステップ1で計算した総取得価額を、ステップ2で計算した総数量で割ります。これで平均単価が算出されます。
計算: 50,000円 ÷ 450個 = 111.111…円
実務上、計算結果に円未満の端数が出た場合は、税法や社内ルールに基づき、切り捨て、切り上げ、または四捨五入などの処理を行います。ここでは四捨五入して「111.11円」とします。
ステップ4: 期末棚卸資産評価額と売上原価を確定する
最後に、算出した平均単価を使って、期末の在庫評価額と当期の売上原価を確定させます。
- 期末棚卸資産評価額: 111.11円 × 150個 (期末在庫数量) = 16,667円
- 売上原価: 50,000円 (総取得価額) – 16,667円 (期末棚卸資産評価額) = 33,333円
この4つのステップを踏むことで、誰でも簡単に総平均法による評価額と原価を計算することができます。
【実践編】ケース別・総平均法を用いた計算例

総平均法は、一般的な商品の在庫管理だけでなく、仮想通貨や株式など、さまざまな資産の評価に活用されます。ここでは、具体的なケース別に計算例と会計処理を詳しく見ていきましょう。
在庫(棚卸資産)の評価と決算整理仕訳
小売業や卸売業では、期末の在庫を正しく評価し、決算書に反映させる必要があります。総平均法は、この在庫評価を効率的に行うための有力な手段です。
計算例
前項の「4つのステップによる具体的な計算手順」で算出した数値を用いて、決算整理仕訳を見ていきましょう。
- 期首商品棚卸高: 10,000円
- 当期商品仕入高: 40,000円 (22,000円 + 18,000円)
- 期末商品棚卸高: 16,667円 (総平均法で算出)
- 売上原価: 33,333円
決算整理仕訳(三分法を前提)
日本の多くの中小企業で採用されている「三分法」では、期中の仕入はすべて「仕入」勘定(費用)で処理します。そのため、期末に決算整理仕訳を行い、売上原価を正しく算定する必要があります。
まず、期首にあった在庫は当期に販売された(費用になった)と考えるため、「仕入」勘定に振り替えます。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| 仕入 | 10,000 | |
| 繰越商品 | 10,000 |
次に、期末に残っている在庫は、まだ販売されていない(費用ではない)ため、「仕入」勘定から除外し、「繰越商品」という資産勘定に振り替えます。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| 繰越商品 | 16,667 | |
| 仕入 | 16,667 |
この2つの仕訳の結果、損益計算書の「仕入」勘定の残高は「期首在庫10,000円 + 当期仕入40,000円 – 期末在庫16,667円 = 33,333円」となり、これが当期の「売上原価」となります。同時に、貸借対照表には資産として「繰越商品」が16,667円計上され、企業の財政状態が正しく示されます。
仮想通貨(暗号資産)の損益計算
個人の仮想通貨取引によって得られた利益は、原則として「雑所得」として確定申告が必要です。その際の所得計算方法として、国税庁は総平均法または移動平均法のいずれかを選択することを認めています。
計算例
- 1月1日: 1 BTCを400万円で購入
- 6月1日: 1 BTCを500万円で購入
- 10月1日: 0.5 BTCを300万円で売却
平均取得単価の計算
年間の購入総額を総数量で割ります。
(400万円 + 500万円) ÷ (1 BTC + 1 BTC) = 450万円/BTC
売却原価の計算
売却した数量に平均取得単価を掛け合わせます。
450万円/BTC × 0.5 BTC = 225万円
所得金額の計算
売却額から売却原価を差し引きます。
300万円 (売却額) – 225万円 (売却原価) = 75万円
この75万円が、雑所得として申告すべき金額となります。
注意点:予期せぬ税負担のリスク
仮想通貨の計算で総平均法を用いる際には、注意すべき点があります。それは、平均単価が年末にならないと確定しないという特性です。例えば、上記の例で、10月1日に売却した際、投資家は直近の購入単価である500万円を意識しているかもしれません。
その感覚だと、売却原価は250万円(500万円×0.5 BTC)となり、利益は50万円程度だと錯覚しがちです。
しかし、総平均法では年初の安い購入(400万円)も加味されるため、最終的な平均単価は450万円まで下がります。その結果、計算上の利益は75万円となり、想定よりも納税額が大きくなる可能性があります。
期中に利益が出ていると考えていても、年末の計算で初めて正確な所得がわかるため、納税資金の準備が遅れないよう、年間を通じて概算の計算を行っておくことが賢明です。
株式・投資信託の取得価額計算
株式や投資信託を複数回にわたって購入(いわゆる「ナンピン買い」や積立投資など)した場合、売却時の取得価額を計算するために「総平均法に準ずる方法」が用いられます。これは、売却の都度、それまでの取得総額を総株数で割って平均単価を計算する方法です。
計算例
- 期首保有: A社の株式を100株、取得価額10,000円で保有
- 6月1日: A社の株式を60株、5,200円で追加取得
- 8月1日: A社の株式を30株売却
売却時点までの平均単価を計算
売却するまでの全取得価額を、全取得株式数で割ります。
(10,000円 + 5,200円) ÷ (100株 + 60株) = 95円/株
譲渡原価(取得費)を計算
売却した株数に、算出した平均単価を掛け合わせます。
95円/株 × 30株 = 2,850円
この2,850円が、譲渡所得を計算する際の取得費となります。
総平均法と移動平均法の比較
棚卸資産や仮想通貨の評価方法を選ぶ際、総平均法と必ず比較されるのが「移動平均法」です。どちらの方法を選ぶかによって、計算の手間や期中の損益把握の精度が大きく変わります。ここでは両者を比較し、選択の指針を示します。
計算タイミングと手間の違い
両者の最も根本的な違いは、平均単価を計算するタイミングにあります。
- 総平均法
年間や月間など、一定期間の最後にまとめて1回だけ平均単価を計算します。取引回数がどれだけ多くても、計算は期末に一度きりなので、手間が圧倒的に少ないのが特徴です。 - 移動平均法
資産を仕入れる(取得する)たびに、その都度、手持ちの在庫と合算して平均単価を計算し直します。取引回数が多ければ多いほど、計算の手間は比例して増大し、非常に煩雑になります。
損益への影響
計算タイミングが異なるため、同じ取引内容であっても、単年度で認識される利益額は両者で異なる場合があります。例えば、価格が上昇傾向にある局面では、移動平均法の方が常に新しい(高い)仕入価格が反映されるため、売上原価が高く計算され、利益は低めに出る傾向があります。
ただし、これはあくまで短期的な差異です。長期的に見て、保有するすべての資産を売却した時点での累計利益額は、総平均法と移動平均法で最終的に一致します。つまり、どちらの方法が絶対的に有利・不利ということはなく、利益をどのタイミングで認識するかが異なるだけです。この違いは、各年度の納税額や業績評価に影響を与える可能性があります。
比較表
| 特徴 | 総平均法 (Total Average Method) | 移動平均法 (Moving Average Method) |
| 計算タイミング | 期末などにまとめて1回 | 仕入の都度 |
| 計算の手間 | 簡単 (取引回数が多くても手間は同じ) | 煩雑 (取引回数に比例して手間が増大) |
| 損益把握の適時性 | 低い (期末まで原価・利益が確定しない) | 高い (常に最新の原価・利益を把握可能) |
| 価格変動への影響 | 期間全体の価格が平均化され、影響が平準化される | 直近の価格変動がすぐに平均単価に反映される |
| 向いているケース | 計算の手間を省きたい場合、期中のリアルタイムな原価管理が不要な場合 | リアルタイムで損益を把握したい場合、正確な原価管理に基づき価格設定を行いたい場合 |
評価方法の選択と経営戦略
評価方法の選択は、単に計算の手間だけで決めるべきではありません。この選択は、企業の経営戦略を反映するものでもあります。
総平均法を選択する企業は、管理業務の効率化を優先していると言えます。マージンが安定しており、日々の原価変動が経営判断に大きな影響を与えない業態であれば、これは合理的な選択です。
一方で、移動平均法を選択する企業は、データに基づいた迅速な意思決定を重視しています。価格変動の激しい市場で競争していたり、原価に基づいて販売価格を細かく調整する必要があったりする場合、リアルタイムの原価情報は不可欠な武器となります。会計システムへの投資を行ってでも移動平均法を採用するのは、それが競争上の必要性だと認識しているからです。
したがって、評価方法の選択は単なる会計上の手続きではなく、自社のビジネス環境、管理哲学、そして事業の成熟度を考慮して行うべき戦略的な判断なのです。
総平均法を採用するメリットとデメリット
これまでの比較を踏まえ、総平均法のメリットとデメリットを改めて整理します。
メリット:計算がシンプルで価格変動の影響を受けにくい
総平均法の最大のメリットは、その計算のシンプルさにあります。期首と期中のデータを集計し、一度の割り算で平均単価を算出できるため、簿記の専門知識がなくても比較的容易に計算が可能です。
また、期間中のすべての仕入価格が平均化されるため、一時的な価格の急騰や急落が期末の評価額に与える影響を和らげる効果があります。これにより、年度ごとの利益のブレが少なくなり、安定した業績報告につながりやすくなります。
デメリット:リアルタイムな原価把握が不可能
総平均法の最大の、そしてしばしば致命的となるデメリットは、期末(または計算期間の末日)になるまで平均単価、すなわち売上原価が確定しないことです。
これにより、期中のどの時点においても「この商品はいくらの原価で、販売して利益が出ているのか」を正確に把握することができません。月次決算で正確な利益を計算することが困難になり、価格改定や販売促進策の策定、追加仕入の判断といった、タイムリーな経営判断の妨げとなる可能性があります。
特に、利益率の低いビジネスや価格競争が激しい業界では、このデメリットは無視できないリスクとなります。
税務・会計上の重要ルールと手続き

総平均法を採用するにあたっては、会計基準や税法で定められたルールを遵守する必要があります。ここでは、知っておくべき重要なポイントを解説します。
「棚卸資産の評価に関する会計基準」との関係
総平均法は、日本の会計ルールを定める企業会計基準委員会(ASBJ)が公表している「棚卸資産の評価に関する会計基準」において、正式に認められている原価算定方法の一つです。
重要原則「低価法」の適用
ここで注意すべきは、総平均法で計算した単価がそのまま期末評価額になるとは限らない点です。会計基準では、「低価法(ていかほう)」という大原則が定められています。これは、棚卸資産の評価額を、原価(総平均法などで計算した金額)と期末時点の時価(正味売却価額)とを比較して、いずれか低い方の金額で計上しなければならないというルールです。
正味売却価額とは、その在庫を今売ったらいくらになるかという見積額から、販売にかかる経費などを差し引いた金額を指します。例えば、流行遅れになったアパレル商品や、技術革新で価値が下がった電子部品などは、仕入れた時の原価よりも時価が大幅に下落している可能性があります。
このような場合、たとえ総平均法で計算した原価が高くても、時価まで評価額を切り下げ(評価損を計上し)なければなりません。これは、貸借対照表に過大な資産が計上されるのを防ぎ、企業の財政状態をより保守的かつ正確に表示するための重要なルールです。
総平均法の計算はあくまで第一ステップであり、適切な会計処理のためには、その後の時価評価というプロセスが不可欠なのです。
税法上のルールと評価方法の届出義務
税務上、どの評価方法を採用するかは企業の任意ですが、一度決めた方法を勝手に変更することはできません。
「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出
法人や個人事業主は、どの棚卸資産の評価方法を採用するかを決定し、「棚卸資産の評価方法の届出書」という書類を通じて、所轄の税務署に届け出る必要があります。この届出は、法人の場合は設立第1期の確定申告書の提出期限まで、個人事業主の場合は事業を開始した年の確定申告期限までに行わなければなりません。
届出をしなかった場合の「法定評価方法」
もし、この届出を怠った場合、税法が定める「法定評価方法」が自動的に適用されてしまいます。注意すべきは、この法定評価方法が個人と法人で異なる点です。個人の仮想通貨計算では「総平均法」が適用されます。しかし、法人の棚卸資産の場合は「最終仕入原価法」という方法が適用されます。
最終仕入原価法は、期末に最も近い時期に仕入れた単価をすべての期末在庫の単価とみなす方法です。計算は簡単ですが、実際の原価と大きく乖離する可能性があります。さらに重要なのは、この最終仕入原価法は、会計上、一般的に公正妥当と認められる会計処理の方法ではないとされている点です。
届出をしないという不作為によって、税務上は認められるものの、会計上は不適切とされる評価方法を強制されることになりかねません。その結果、作成された決算書は企業の経営実態を正しく反映せず、金融機関からの融資や投資家からの評価、そして経営者自身の判断を誤らせる原因になり得ます。
したがって、事業を開始する際には、法定評価方法に頼るのではなく、自社の戦略に合った評価方法を主体的に選択し、必ず届け出ることが極めて重要です。
評価方法の変更
一度選択した評価方法は、特別な理由がない限り、原則として3年間は変更できません。変更を希望する場合は、「所得税の(法人税の)棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を提出し、税務署長の承認を得る必要があります。
まとめ:総平均法をマスターして正確な経営判断を
本記事では、総平均法の計算式から具体的な活用例、そして税務・会計上の注意点までを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを再確認しましょう。
総平均法は、一定期間の仕入をすべて平均して資産単価を算出する、シンプルでわかりやすい計算方法です。
計算の核となるのは「総取得価額 ÷ 総数量」というシンプルな式であり、これを用いて平均単価を求めます。
計算が簡単という大きなメリットがある一方、期中のリアルタイムな原価把握ができないという経営判断上のデメリットも存在します。
移動平均法との比較では、自社の業種、取引量、そして「どの程度タイムリーに損益を把握したいか」という経営戦略に基づいて選択することが重要です。
採用する評価方法は、必ず税務署に届け出る必要があります。届出を怠ると意図しない評価方法が自動的に適用されるため、注意が必要です。
総平均法は、その手軽さから多くの場面で有効なツールです。しかし、その特性と限界を正しく理解し、自社の状況に合わせて適切に運用することが、正確な会計処理と的確な経営判断につながります。





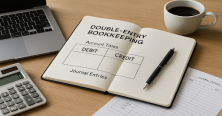


複式簿記とは?経営が変わる仕組みを初心者向けに解説
事業の財務状況を正確に把握し、税金の負担を賢く軽減したい。そして、データに基づいた的確な経営判断を下…