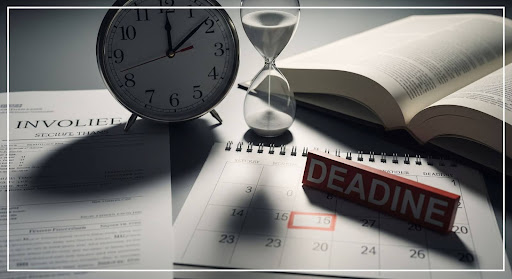
この記事では、2020年の民法改正によって大きく変更された請求時効の仕組みを、基本から丁寧に解説します。かつて複雑であった時効のルールがどのように整理され、私たちの生活やビジネスにどのような影響を及ぼすのか、その全体像を明らかにします。
時効が成立する期間、時効の進行を停止またはリセットする方法、そして「時効の援用」という最終的な手続きに至るまで、今何をすべきかが具体的に理解できる内容です。専門的な知識がない方でも、この記事を読めば、自信を持って次の一歩を踏み出せるでしょう。
目次
なぜ権利は消滅するのか?2020年民法改正の核心
請求時効制度は、私たちの経済活動における「時間」に関するルールを定めたものです。なぜ一定期間が経過すると、金銭を請求する権利が消滅するのでしょうか。そして、2020年の民法改正は、この基本的なルールにどのような変革をもたらしたのでしょうか。ここでは、制度の根本的な考え方と、改正の核心部分を解き明かします。
消滅時効とは?法律が「時間の経過」を重視する理由
消滅時効とは、権利を持つ人(債権者)が、法律で定められた一定期間にわたってその権利を行使しない場合に、権利自体が消滅する制度です。この制度が存在する背景には、いくつかの重要な理由があります。
第一の理由は、法的な安定性の確保です。長期間にわたり権利が行使されない事実状態が継続している場合、その状態を尊重し、法律関係を安定させる必要があります。いつまでも過去の権利を主張できるとすれば、社会の法律関係が不安定になってしまうためです。
第二に、証拠が時間とともに失われることから義務者を救済する目的があります。時間が経過するにつれて、契約書や領収書といった証拠は失われがちです。何十年も前の取引について、支払いの有無を証明するよう求めることは、義務を負う側(債務者)にとって過酷な要求となる場合があります。
第三に、権利を行使できるにもかかわらず、長期間にわたって何もしなかった債権者を、法律は積極的に保護する必要はないという考え方があります。これは「権利の上に眠る者は保護に値せず」という法諺にも表れています。これらの理由から、法律は「時間の経過」という事実を重視し、消滅時効という制度を設けているのです。
2020年4月1日、何が変わったのか?民法改正の主要ポイント
2020年4月1日に施行された改正民法は、日本の契約法に関するルールを大きく見直すものでした。特に消滅時効に関する変更は、私たちの生活やビジネスに直接的な影響を与える重要な改正点です。
主な変更点の一つは、時効期間の統一です。改正前の法律では、医師の診療報酬は3年、弁護士の報酬は2年、飲食店の代金は1年など、債権者の職業によって時効期間が異なっていました。この「職業別の短期消滅時効」は非常に分かりにくく、現代の取引社会に適合しないものとされていました。
今回の改正で、これらの複雑な短期時効は原則として廃止され、ルールが大幅に簡素化されました。
次に、時効の進行を管理する概念が刷新されました。改正前は「時効の中断」「時効の停止」と呼ばれていた概念が、より分かりやすい「時効の更新」「時効の完成猶予」という言葉に整理されました。これは単なる言葉の言い換えではなく、それぞれの効果や発生事由がより明確に定義し直されたものです。
この変更により、時効の進行を止めたり、リセットしたりするためのルールが分かりやすくなりました。
さらに、新たに「協議による時効完成猶予制度」が導入されました。これは、当事者間で支払いの話し合いをしている最中にも時効が進行してしまうという、改正前の問題点を解決するための制度です。書面で協議を行う旨の合意をすれば、訴訟などの強硬な手段をとらなくても、一定期間、時効の完成を遅らせることが可能になりました。
この改正は、法律の専門家でなくても理解しやすく、予測可能性の高いルールを目指すという、法制度の近代化を象徴するものと言えるでしょう。
新ルールの基本:「知った時から5年」「行使できる時から10年」
民法改正によって導入された新しい時効ルールの核心が、改正民法第166条に定められた二つの原則です。具体的には、債権は以下のいずれか早い方の期間が経過したときに時効によって消滅します。
一つ目は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」というルールです。これは、債権者が「金銭を返してもらえる権利がある」という事実と、「その権利を今すぐ行使できる(例:支払日が到来した)」という事実の両方を知った時点からカウントが始まります。
これを主観的起算点と呼びます。金銭の貸し借りや商品の売買など、ほとんどの取引では契約時に支払日を定めるため、債権者は当初から権利の存在を知っているとみなされます。そのため、実務上、多くのケースでこの「5年」という期間が適用されることになります。
二つ目は「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」というルールです。こちらは、債権者が権利の存在を知っていたかどうかにかかわらず、客観的に権利を行使できるようになった時点(例:支払日)からカウントが始まります。これを客観的起算点と呼びます。
この規定は、債権者が権利の存在に気づかないまま長期間が経過した場合でも、無期限に請求が可能となる事態を防ぐための、最終的な打ち切り期間としての役割を果たします。
結論として、新しいルールでは、原則として「5年」で時効が完成すると理解しておけば、大半のケースに対応可能です。
ケース別・債権の時効期間|民法改正前後の比較
2020年の民法改正で時効期間は原則5年に統一されましたが、全てのケースで話が単純になったわけではありません。いつ発生した請求権なのかによって、適用される法律が異なるためです。ここでは、ご自身の状況にどの時効期間が当てはまるのかを、具体的なケース別に詳しく見ていきましょう。
2020年4月1日を境にした時効期間の考え方
法律の世界には「法の不遡及(ふそきゅう)」という大原則が存在します。これは、新しく制定された法律は、その法律が施行される前の出来事にはさかのぼって適用されないというルールです。
消滅時効に関してもこの原則が適用されます。具体的には、2020年3月31日以前に発生した債権(その原因となる契約がされた債権)には、原則として改正前の旧民法が適用されます。
一方で、2020年4月1日以降に発生した債権には、改正後の新民法が適用されます。この日付は、特に個人間での金銭の貸し借りなど、改正によって時効期間が大きく変わった債権において、非常に重要な意味を持ちます。
主要な債権の時効期間一覧(民法改正前後)
それでは、具体的にどのような債権の時効期間がどう変わったのか、改正前と改正後を比較しながら見ていきましょう。以下の表は、ご自身の権利がいつ時効になるのかを判断するための重要な指針となります。
| 債権の種類 | 改正前(2020年3月31日以前の契約) | 改正後(2020年4月1日以降の契約) | 関連法規・注意点 |
| 消費者金融・銀行・カード会社からの借金 | 5年 | 5年 | 改正前から商法上の「商事時効」が適用されていたため、期間に変更はありません。 |
| 個人・信用金庫・奨学金からの借金 | 10年 | 5年 | 個人間の貸し借りや、商人ではない信用金庫などからの借入は、時効期間が半分に短縮されました。 |
| 売掛金(商取引の代金) | 2年(製造業・小売業など) | 5年 | 旧民法では職業別に2年と定められていましたが、改正により商事債権・一般債権の区別なく5年に統一されました。 |
| 未払い給与(賃金請求権) | 2年 | 5年(当分の間は3年) | 労働基準法が改正され、労働者の権利保護が強化されました。ただし、急激な変更を避けるため、経過措置として当面は3年とされています。 |
| 退職金 | 5年 | 5年 | 労働基準法上の退職金請求権は、もともと5年だったため変更はありません。 |
| 飲食代・宿泊費 | 1年 | 5年 | いわゆる「ツケ」などの短期消滅時効が廃止され、他の債権と同様に5年となりました。 |
| 医療費 | 3年 | 5年 | 医師の診療報酬債権なども、職業別の短期時効が廃止され、5年に統一されました。 |
| 不法行為による損害賠償 | 損害・加害者を知った時から3年 | 生命・身体の侵害:5年 財産上の損害:3年 | 人の生命や身体を害する不法行為(交通事故の慰謝料など)の時効は、被害者保護の観点から5年に延長されました。不法行為の時から20年という長期の時効は維持されています。 |
時効の時計を止める・戻す方法:「完成猶予」と「更新」
時効は、単に時間が経過するのを待っているだけで必ず完成するわけではありません。債権者の行動や債務者の言動によって、時効の進行は一時的に停止したり、完全にリセットされたりすることがあります。
この仕組みを理解することは、債権者にとっては権利を守るために、債務者にとっては意図せず時効の完成を妨げてしまう事態を避けるために不可欠です。改正民法では、この仕組みが「完成猶予」と「更新」という言葉で整理されました。
時効の進行を一時停止させる方法
「完成猶予」とは、時効のカウントダウンを一時的に停止させる(ポーズする)ことです。猶予されている期間が過ぎると、停止していた時点から再びカウントダウンが再開します。それまでに経過した期間が無駄になるわけではありません。
催告
債権者が債務者に対して「支払ってください」と請求することを「催告」といいます。口頭でも可能ですが、証拠を残すために内容証明郵便が利用されるのが一般的です。催告を行うと、その時から6か月間、時効の完成が猶予されます。
この6か月の間に訴訟を起こすなど、次の法的手段を準備するための時間稼ぎとして利用されます。ただし、催告による猶予期間中に再度催告をしても、猶予期間は延長されません。この効果は最初の1回限りです。
協議を行う旨の合意
民法改正で新設された、非常に実用的な制度です。債権者と債務者が、権利について協議を行う旨の合意を書面(または電磁的記録)で交わすと、所定の期間、時効の完成が猶予されます。
具体的には、合意があった時から1年、あるいは当事者間で定めた協議期間(1年未満の場合)などが経過するまで猶予されます。この合意は最大5年まで更新可能で、訴訟という対立的な手段を避け、円満な解決を目指す当事者にとって大きな利点があります。
仮差押え・仮処分
債権者が、裁判の判決が出る前に債務者の財産が処分されてしまうのを防ぐため、裁判所に申し立てて財産を一時的に凍結させる手続きです。これらの保全手続きが行われると、手続きが終了した時から6か月間、時効の完成が猶予されます。
天災
地震、洪水、戦争といった、当事者の力では避けられない事変によって裁判上の請求などができなくなった場合、その障害が消滅した時から3か月間、時効の完成が猶予されます。
時効をリセットし、ゼロから再スタートさせる方法
「更新」とは、それまで進行していた時効期間をすべて白紙に戻し、ゼロからもう一度カウントをやり直すことです。時効期間がリセットされるため、非常に強力な効果を持ちます。
裁判上の請求と確定判決
債権者が裁判所に訴訟を提起すると、まず裁判が終了するまで時効の完成が猶予されます。そして、判決が確定し、権利が認められると、その時点で時効は更新されます。さらに重要なのは、この場合、新たにスタートする時効期間は原則として10年となる点です。
つまり、もともと5年で時効になるはずだった借金も、一度裁判で判決が確定すると、そこから10年間は時効が完成しなくなります。
強制執行
確定判決などの「債務名義」に基づき、債権者が債務者の給与や預金などを差し押さえる手続きです。強制執行の手続きが終了した時点で、時効は更新され、新たに時効期間が進行を開始します。
債務の承認
債務者にとって最も注意すべきなのが「債務の承認」です。債務者が、自身に債務があることを認める言動をとると、その時点で時効は更新されます。時効の完成が間近に迫った債権者にとって、これは最も簡単かつ効果的に時効をリセットする手段です。
債権回収の専門家は、この仕組みを熟知しており、債務者に承認させるための様々なアプローチを試みてきます。
例えば、「少しでもいいので支払っていただけませんか」「支払いの意思があるかだけでもお聞かせください」といった言葉で、債務者からの支払いや支払約束を引き出そうとします。これに応じてしまうと、時効によって消滅するはずだった債務が、完全に有効な債務として復活してしまうのです。
具体的には、借金の一部を支払う行為(たとえ1円でも)、支払いを約束する発言、債務の存在を認める念書への署名などが「承認」とみなされます。したがって、古い借金の督促を受けた場合の鉄則は、時効の援用手続きを完了する前に、決して支払わず、支払いを約束せず、安易に連絡を取らないことです。
最終ステップ「時効の援用」とは?権利を確定させるための手続き
時効期間が過ぎたからといって、自動的に借金の支払い義務がなくなるわけではありません。時効の利益を得るためには、債務者自身による特定の行動が必要です。それが「時効の援用(えんよう)」です。この最終ステップを踏むことで、初めて法的に権利が確定します。
なぜ「援用」が必要なのか?待っているだけでは借金はなくならない
消滅時効は、時間が経過すれば自動的に成立するものではありません。法律は、時効によって利益を受ける人(債務者)が、「私は時効の利益を受けます」という意思表示をすることを求めています。この意思表示こそが「時効の援用」です。
もし援用をしなければ、債権者は依然として裁判を起こすことができます。そして、裁判の場で債務者が時効の援用を主張しなかった場合、裁判所は時効を考慮せずに支払い命令の判決を下す可能性があります。つまり、時効という強力な権利を持っていても、それを行使しなければ意味がないのです。
内容証明郵便を使った時効援用の方法
時効を援用する方法に厳密な決まりはありませんが、後日のトラブルを防ぎ、確実に意思表示をした証拠を残すために、「内容証明郵便」に「配達証明」を付けて送付するのが最も安全で一般的な方法です。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
具体的な手続きは、まず時効期間の満了を確認することから始まります。最後の返済日や支払期限から、必要な期間(原則5年)が経過しているか、途中で時効の更新事由(債務の承認など)がなかったかを慎重に確認します。
次に、後述の事項を盛り込んだ時効援用通知書を作成し、同じ内容の文書を3部(債権者送付用、郵便局保管用、自身の控え用)用意します。最後に、内容証明郵便を取り扱っている郵便局の窓口で発送手続きを行います。
時効援用通知書の書き方と記載事項
時効援用通知書に決まった書式はありませんが、以下の要素を盛り込むことが不可欠です。まず、通知書を作成した日付、そして通知人(債務者)の住所・氏名・生年月日を記載します。同姓同名を避けるため、生年月日の記載は重要です。
次に、被通知人である債権者(会社)の住所と名称を明記します。どの債務に関するものかを明確にするため、契約番号や会員番号、当初の契約日など、債権を特定する情報を請求書などから転記します。
そして、「貴社に対し、本書面をもって上記債権について、消滅時効を援用します」といった、誰が読んでも時効を主張していることが分かる明確な一文を記載します。
万が一、時効が成立していなかった場合に備え、「なお、本書面は債務の存在を承認するものではありません」という一文を加え、この通知書自体が債務の承認とみなされるリスクを避けることも重要です。
【時効援用通知書 テンプレート】
消滅時効援用通知書
令和〇年〇月〇日
(被通知人)
〒〇〇〇-〇〇〇〇
東京都千代田区〇〇町〇-〇-〇
〇〇債権回収株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
(通知人)
〒〇〇〇-〇〇〇〇
神奈川県横浜市〇〇区〇〇町〇-〇
〇〇 〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)
前略
貴社が私に対して有すると主張される下記債権については、最終の弁済期から既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成しております。
記
1.契約番号:12345-67890
2.当初契約会社:〇〇クレジット株式会社
つきましては、私は貴社に対し、本書面をもって上記債権について消滅時効を援用いたします。
これにより、私の貴社に対する債務は消滅いたしましたので、今後は請求及び連絡等の一切を行わないよう、お願い申し上げます。
また、貴社が信用情報機関に登録されている私の情報について、速やかに削除・訂正の手続きをされるよう、併せて請求いたします。
なお、本書面は、債務の存在を承認するものではないことを念のため申し添えます。
草々
時効援用で絶対に避けるべきこと
時効の援用を成功させるためには、慎重な行動が求められます。特に致命的な過ちにつながる行為として、援用通知を送る前の債務承認が挙げられます。繰り返しになりますが、債権者から連絡があった際に、安易に支払いの約束をしたり、少額でも支払ったりすることは、時効の利益を自ら放棄する行為に他なりません。
また、証拠が残らない方法での援用も避けるべきです。電話や普通郵便での通知は、「言った、言わない」「受け取っていない」といった水掛け論になるリスクが非常に高いです。個人が自ら手続きを行う場合は、確実な証拠となる内容証明郵便を選択するのが賢明です。
時効援用後の世界|信用情報への影響と専門家への依頼
無事に時効の援用が成功し、借金の支払い義務がなくなった後、どのような変化が訪れるのでしょうか。多くの方が気になるのは、「信用情報はどうなるのか」という点と、「そもそも専門家に依頼すべきか」という点でしょう。ここでは、援用後の現実について解説します。
時効援用と信用情報|事故情報は本当に消えるのか?
まず理解すべきは、「ブラックリスト」という名称のリストは存在しないということです。個人のローンやクレジットの利用状況は、「信用情報機関」という第三者機関に登録されており、延滞などの金融事故情報が登録されている状態を俗に「ブラックリストに載る」と表現します。主要な信用情報機関にはCIC、JICC、KSCの3つがあります。
時効の援用が成功すると、この信用情報は機関によって異なる対応がなされます。JICC(日本信用情報機構)では、時効援用が成功すると、多くの場合、該当する債務の情報そのものが削除されます。
一方、CIC(株式会社シー・アイ・シー)やKSC(全国銀行個人信用情報センター)では、情報のステータスが「完了」などに変更されるものの、過去に延滞があったという事実は、そこから最長5年間残ることがあります。
この違いが意味するのは、時効援用は法的な支払い義務を消滅させますが、必ずしも即座に信用情報が完全にクリーンになるわけではない、ということです。また、信用情報機関のデータとは別に、時効援用をされた金融機関は「社内ブラック」として独自に情報を保管することがあります。
そのため、その会社やグループ会社から、将来的に新たな借り入れやカード作成をすることは極めて困難になると考えておくべきです。
専門家への依頼:弁護士、司法書士、行政書士の違いと費用相場
時効援用の手続きは自身で行うことも可能ですが、時効期間の計算ミスや、意図せず債務を承認してしまうリスクなどを考慮すると、専門家に依頼するのが最も安全かつ確実です。依頼できる専門家には主に行政書士、司法書士、弁護士がおり、それぞれに依頼できる業務範囲と費用が異なります。
| 専門家 | 費用相場 | 主な業務範囲と対象ケース |
| 行政書士 | 1万円~3万円 | 時効援用通知書の作成と発送代行のみ。時効成立が確実で、争いになる可能性が極めて低い場合に適しています。 |
| 司法書士 | 3万円~8万円 | 時効成立の調査から通知書作成・発送、債権者との交渉まで一任できます。ただし、代理人として扱えるのは元金140万円以下の債務に限られます。一般的な消費者金融やカードローンの時効援用に適した選択肢です。 |
| 弁護士 | 5万円~ | 金額の制限なく代理人になれます。債権者から訴訟を起こされた場合の裁判対応も可能です。借金の元金が140万円を超える場合や、すでに裁判を起こされているなど、法的な紛争に発展しそうなケースで頼りになります。 |
どの専門家を選ぶかは、ご自身の状況(借金の額、債権者の性質、訴訟リスクなど)によって決まります。多くの場合、元金140万円以下の消費者金融からの借金であれば、司法書士がコストと対応範囲のバランスが取れた選択肢となるでしょう。
よくある質問(Q&A)
請求時効に関しては、個別の状況に応じた多くの疑問が寄せられます。ここでは、特に不安を感じやすいシナリオについて回答します。
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法
裁判所から書類が届いた場合でも、手遅れではありません。むしろ、これが最後のチャンスと捉えるべきです。書類を無視することが最悪の選択であり、放置すれば、あなたの言い分が考慮されないまま判決(欠席判決)が下され、時効がそこから新たに10年間延長されてしまいます。
指定された期限内に「答弁書」(訴状の場合)や「異議申立書」(支払督促の場合)を裁判所に提出し、その中で明確に「消滅時効を援用する」と主張することが必要です。適切に対応すれば、債権者が訴えを取り下げ、問題が解決するケースも少なくありません。この段階に至った場合は、速やかに弁護士や司法書士に相談することを強く推奨します。
身に覚えのない債権回収会社から請求が来た場合の対処法
これは非常に一般的なケースです。金融機関は、回収が困難になった古い債権を、専門の債権回収会社(サービサー)に売却することがあります。しかし、債権者が変わっても、時効のルールはそのまま引き継がれます。
重要なのは、時効期間のカウント開始日(起算点)は、あなたが元の債権者(銀行や消費者金融)への支払いを最後に行った日であり、債権が売却された日ではないという点です。
したがって、他のケースと同様に、まずは請求書に記載された情報を元に最終返済日を確認し、安易に連絡を取ったり支払いの約束をしたりせず、時効が成立している可能性を検討してください。
保証会社が代位弁済した場合の時効起算日
保証会社があなたの代わりに貸主へ返済することを「代位弁済」といいます。この場合、元の貸主に対するあなたの借金は消滅しますが、代わりに保証会社があなたに対して「支払った分を返済せよ」と請求する権利(求償権)を取得します。
この求償権の消滅時効は、保証会社が代位弁済を行った日(あなたの代わりに返済した日)から新たにスタートします。したがって、元の借金の最終返済日から5年が経過していても、代位弁済の日から5年が経過していなければ、時効は完成していないことになります。請求書に記載されている代位弁済日を正確に確認する必要があります。
時効成立後に一部を支払ってしまった場合
残念ながら、ほとんどの場合、もはや時効を援用することはできません。時効期間が経過した後に、債務があることを認める行為(一部の支払いや支払約束など)をすると、「時効の利益を放棄した」とみなされます。
債権者側は、あなたが時効を援用しないものと信頼するため、その信頼を保護すべきという考え方(信義則)に基づき、一度放棄した時効の利益を後から主張することは、裁判所も認めない傾向にあります。このルールは、督促を受けた際に専門家に相談する前に、決して自己判断で行動してはならない理由を明確に示しています。
まとめ
請求時効は、法律が認めた正当な権利です。この知識を正しく使うことで、長年の悩みから解放され、新たな一歩を踏み出すことができます。最後に、あなたが未来を切り拓くために心に刻むべき3つの鉄則を再確認します。
原則は「5年」と心得る
2020年の民法改正により、時効のルールは大きく簡素化されました。消費者金融、銀行、クレジットカード、個人間の借金、売掛金など、身の回りのほとんどの金銭債権は、最後の取引から5年が経過していれば、時効が成立している可能性があります。まずはこの「5年」という数字を基準に、ご自身の状況を確認することから始めてください。
安易な「承認」は命取り
時効援用における最大の落とし穴は、意図せず時効の進行をリセットしてしまう「債務の承認」です。債権者からの連絡に対し、たとえ1円でも支払うこと、支払いを約束することは、時効という切り札を自ら捨てる行為に等しいと肝に銘じてください。時効の援用通知を正式に送付するまでは、債権者との安易な接触は絶対に避けましょう。
「援用」しなければゼロにならない
時効期間が過ぎるのをただ待っているだけでは、借金は消えません。時効は、あなたが「この権利を使います」と積極的に主張(援用)して初めて完成します。そのための最も確実な方法が、内容証明郵便による「時効援用通知書」の送付です。
これは、あなたの権利を法的に確定させるための、避けては通れない最終ステップです。少しでも不安や疑問があれば、リスクを冒さず専門家に相談することが、最も賢明な選択です。








予想EPSで株価の未来を読み解き、投資の勝率を上げるための必…
株式投資で大きな富を築きたいと願うのは、誰にとっても自然な欲求です。もし、目の前の銘柄が1年後にいく…