
ビジネスシーンで書類を送る際、送付状の作成に迷った経験はないでしょうか。たった一枚の書類ですが、送付状を添えるだけであなたの評価は大きく変わる可能性があります。
この記事を最後まで読めば、もう送付状で悩むことはありません。どのような相手、どのような状況でも、自信を持って完璧な送付状を作成できるようになり、あなたのビジネスコミュニケーションは次のレベルへと引き上げられます。
この記事を読んでいるあなたは、おそらく「これで本当に合っているだろうか」と不安を感じながら、送付状を作成しているのではないでしょうか。
実は、多くのビジネスパーソンが同じ悩みを抱えています。しかし、送付状は単なるマナーではなく、相手への配慮と信頼を伝えるための強力なツールです。
この記事では、基本的な構成要素から、転職活動、請求書、社内連絡、官公庁向けといったあらゆるシーンに対応する具体的なテンプレートまで、すべてを網羅しています。
テンプレートをコピーして少し修正するだけで、誰でもすぐにプロフェッショナルな送付状が完成します。今日からあなたの書類送付は、単なる「作業」から「信頼構築の機会」へと変わるでしょう。
送付状の揺るぎない基礎
送付状を作成する上で、テンプレートの利用は非常に効率的です。しかし、その背景にある目的や基本的なルールを理解することで、応用の利く確かなスキルが身につきます。ここでは、すべての送付状に共通する土台となる知識を解説します。
送付状が持つ目的と役割
送付状は、単なる形式的な挨拶状ではありません。ビジネス取引を円滑に進めるための、戦略的かつ機能的なツールです。その主な役割は、大きく3つに分けられます。
第一に、明確化と効率化です。送付状は「誰が、誰に、何を、なぜ送ったのか」を一覧で示す目録の役割を果たします。受け取った担当者は、封筒を開けて送付状を見るだけで、同封されている書類の種類と部数を瞬時に把握できます。これにより、内容物の確認作業が大幅に効率化され、その後の処理へスムーズに移行できます。
第二に、プロフェッショナリズムと信頼の構築です。適切に作成された送付状を添えることは、ビジネスマナーを遵守している証となります。これは相手に対する敬意の表明であり、丁寧で信頼できる取引相手であるという印象を与えます。特に初めての取引や公的な手続きにおいて、この第一印象は非常に重要です。
第三に、リスクの軽減です。送付状は、送付した書類の内容を記録する証拠としての側面も持ちます。万が一、「書類が入っていなかった」「部数が足りない」といったトラブルが発生した場合でも、送付状があれば送付内容を客観的に確認でき、迅速な問題解決につながります。このように、送付状は送り手と受け手の双方を不要な誤解や混乱から守る、リスク管理のツールでもあるのです。
これらの役割を理解すると、送付状が単なる「丁寧さの表現」にとどまらないことがわかります。送付状は、受け手の業務効率を直接的に向上させ、取引全体の円滑な進行に貢献する、きわめて実践的なビジネス文書なのです。
完璧な送付状の9つの構成要素
美しい送付状は、定められた構成要素が正しい位置に配置されることで完成します。この配置ルールは、受け手が情報を瞬時に、かつ直感的に把握できるよう洗練された結果です。多忙な担当者は文書を上から順に読むのではなく、まず全体をスキャンします。各要素が定位置にあることで、「誰宛てか」「何についてか」「何が入っているか」を数秒で理解できるのです。
この構成は単なる形式美ではなく、相手の時間を尊重し、業務効率を高めるための機能的なデザインと言えます。以下に、送付状を構成する9つの必須要素とその配置を解説します。
日付
書類をポストに投函する日、または持参する日を記載します。作成日ではない点に注意が必要です。用紙の右上に配置するのが一般的です。
宛名
送付先の会社名、部署名、役職、氏名を正式名称で正確に記載します。「(株)」などの省略は避けましょう。会社や部署宛ての場合は敬称に「御中」を、個人宛ての場合は「様」を使用します。日付より一段下げて、用紙の左上に配置します。
差出人
自身の郵便番号、住所、会社名、部署名、氏名、電話番号、メールアドレスなどを記載します。宛名より一段下げて、用紙の右側に配置します。
件名(表題)
「書類送付のご案内」「請求書送付の件」など、内容が一目でわかる簡潔なタイトルをつけます。用紙の中央に、本文より少し大きなフォントで配置すると見やすくなります。
前文
「拝啓」などの頭語(とうご)と、季節感や相手への配慮を示す時候の挨拶で構成されます。件名から一行空けて、左揃えで書き始めます。
主文
「さて、この度は〜」のように本題に入り、書類を送付した目的や経緯を簡潔に説明します。
末文
「ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます」といった結びの挨拶で締めくくります。
結語
頭語と対になる言葉を記載します。「拝啓」で始めた場合は「敬具」で結びます。本文から一行空けて、右揃えで配置します。
記書き
同封書類を箇条書きで明記する部分です。中央に「記」と書き、その下に書類名と部数をリストアップします。最後に右揃えで「以上」と書いて締めくくります。結語の後、一行空けて記載します。
この9つの要素から成る構造は、あらゆる送付状の基本形となります。
すべての送付状に共通するマナー
送付状の作成と送付には、内容以前に守るべき普遍的なマナーが存在します。これらのお作法は、あなたの丁寧さとビジネスパーソンとしての信頼性を示す重要なポイントです。
用紙とサイズ
清潔感のある白いA4用紙を使用するのが基本です。内容は簡潔にまとめ、必ず1枚に収めるようにします。伝えたいことが多くても、送付状が2枚以上にわたるのは、その役割から逸脱してしまいます。
作成方法
現代のビジネスシーンでは、手書きではなくパソコンでの作成が一般的です。フォントは明朝体などの標準的な書体を選び、文字サイズは10.5から12ポイント程度が見やすいでしょう。奇抜なフォントや色使いは避け、ビジネス文書としての品格を保ちます。
同封時の配置と保護
送付状は、必ず同封書類の一番上に置きます。これは、受け取った人が封筒を開けた際に、まず用件を把握できるようにするための最も重要な配慮です。送付状を含むすべての書類は、クリアファイルに入れてから封筒に入れるのが丁寧な方法です。これにより、郵送中の雨濡れや折れ、汚れから大切な書類を守ることができます。
折り方と封筒
書類を三つ折りにする場合は、長形3号(なががたさんごう)の封筒が適しています。書類を折らずに送る場合は、A4サイズがそのまま入る角形2号(かくがたにごう)の封筒を選びます。三つ折りにする際は、まず書類の下側3分の1を上に折り、次に上側3分の1を下に重ねて折ります。こうすることで、受け取った人が開いたときに書き出しが最初に見えるようになります。
これらのマナーを実践することで、あなたの送付物はよりプロフェッショナルな印象を与えることができます。
あらゆるビジネスシーンに対応する実践文例集
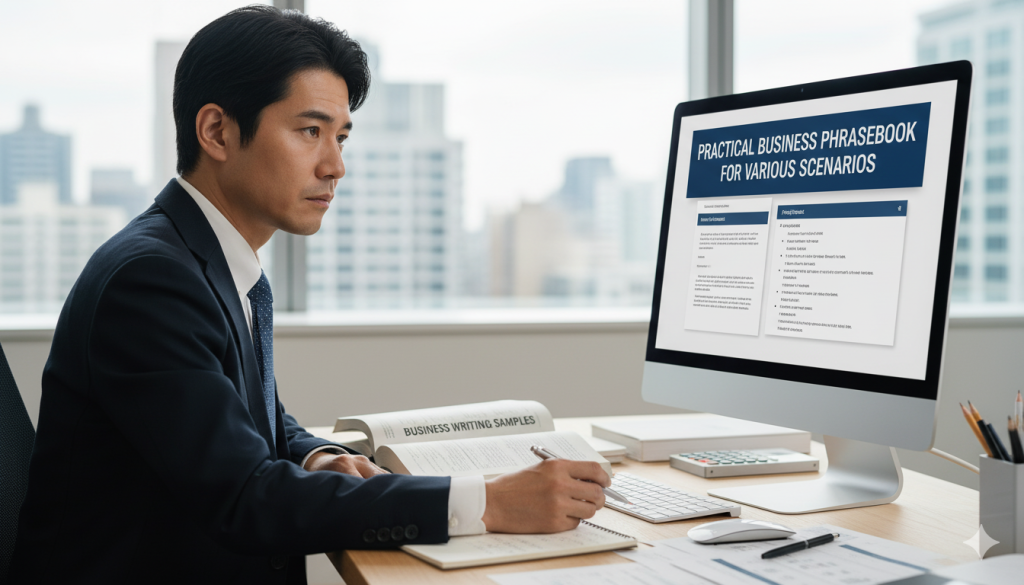
ここでは、さまざまなビジネスシーンでそのまま使える送付状のテンプレートを紹介します。各テンプレートには、カスタマイズする際のポイントも記載しています。自身の状況に合わせて適宜修正し、ご活用ください。
転職・就職活動
採用担当者は多くの応募書類に目を通します。送付状は、あなたの第一印象を決定づける重要な書類です。簡潔さの中に、応募への熱意とビジネスマナーを盛り込むことが重要です。
郵送の場合のテンプレート
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇
人事部 採用ご担当者様
〒XXX-XXXX
東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇マンション101
電話番号:090-XXXX-XXXX
メールアドレス:your_name@example.com
氏名:〇〇 〇〇
応募書類の送付につきまして
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、〇〇(求人媒体名など)にて貴社の求人を拝見し、〇〇職に応募させていただきたく、応募書類一式を送付いたしました。
これまでの〇〇業界における〇年間で培った〇〇の経験は、必ずや貴社に貢献できるものと確信しております。
ご多忙の折とは存じますが、書類をご査収の上、ぜひ一度面接の機会をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 履歴書 1通
2. 職務経歴書 1通
以上
メールで送付する場合のテンプレート
メールで応募書類を送る際は、メール本文が送付状の役割を果たします。件名で「誰が」「何の目的で」連絡したのかが一目でわかるようにしましょう。
件名:〇〇職応募の件/氏名:〇〇 〇〇
株式会社〇〇
人事部 採用ご担当者様
初めてご連絡をさせていただきます。
〇〇 〇〇と申します。
この度、貴社ウェブサイトにて〇〇職の求人を拝見し、ぜひ応募させていただきたくご連絡いたしました。
つきましては、履歴書と職務経歴書を添付ファイルにて送付いたします。
ファイルにはパスワードを設定しております。パスワードは後ほど別途メールにてお送りいたしますので、併せてご確認をお願い申し上げます。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご査収いただき、面接の機会をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
————————————-
氏名:〇〇 〇〇
郵便番号:〒XXX-XXXX
住所:東京都〇〇区〇〇1-2-3
電話番号:090-XXXX-XXXX
メールアドレス:your_name@example.com
————————————-
取引・請求業務
請求書や契約書といった重要書類を送付する際は、送付状を添えるのがビジネスマナーです。取引先に安心感を与え、スムーズな処理を促します。
請求書送付のテンプレート
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇
経理部 御中
〒XXX-XXXX
東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇ビル4F
株式会社△△ 営業部
電話番号:03-XXXX-XXXX
担当:〇〇 〇〇
請求書送付のご案内
拝啓
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、下記の通り請求書を送付いたしましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
1. 請求書(No.202408-001) 1通
以上
支払いが遅れている請求書を再送付する場合
丁寧さを保ちつつ、要件を明確に伝えることが大切です。行き違いの可能性にも配慮した一文を加えます。
(前略)
さて、〇月〇日付でご請求いたしました下記代金につきまして、お支払い期日を過ぎておりますが、本日時点でご入金の確認が取れておりません。
つきましては、誠に恐縮ですが、再度請求書を送付いたしますので、ご確認の上、〇月〇日までにお振込みいただきますようお願い申し上げます。
なお、本状と行き違いでお振込みいただいている場合は、何卒ご容赦ください。
敬具
記
1. 請求書(No.202408-001)【再発行】 1通
以上
契約書送付のテンプレート(返送依頼)
相手に何をしてほしいのか(署名・捺印、返送)を明確に記載することがポイントです。
(前略)
さて、先般合意いたしました〇〇に関する契約書を2部送付いたします。
つきましては、内容をご確認の上、ご署名ご捺印いただき、同封の返信用封筒にて1部をご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
1. 〇〇契約書 2部
2. 返信用封筒 1通
以上
一般的な資料送付
顧客や取引先へ資料を送る際のテンプレートです。送付の経緯(「先日お問い合わせいただいた」「ご要望のありました」など)を一言添えると、より丁寧な印象になります。
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇様
〒XXX-XXXX
東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇ビル4F
株式会社△△ 広報部
電話番号:03-XXXX-XXXX
担当:〇〇 〇〇
資料送付のご案内
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、先日お問い合わせいただきました新製品「〇〇」に関する資料を下記の通り送付いたしました。
ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。
ご不明な点などございましたら、お気軽に担当〇〇までお問い合わせください。
敬具
記
1. 新製品「〇〇」パンフレット 1部
2. 導入事例集 1部
以上
社内連絡
社内文書の場合、時候の挨拶などの形式的な要素は省略し、簡潔さと分かりやすさを優先します。宛名も「〇〇部長」や「〇〇部各位」のように、よりシンプルになります。
令和〇年〇月〇日
営業部 各位
経理部 〇〇 〇〇
内線:1234
経費精算に関する書類送付の件
お疲れ様です。
下記の通り、先月の経費精算に関する書類を送付いたします。
ご確認の上、処理をお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、〇〇までご連絡ください。
記
1. 経費精算書(7月分) 1式
2. 領収書原本 1式
以上
公的機関への提出
官公庁へ書類を提出する際は、敬称の使い分け(省庁宛てなら「貴省」、一般的な役所なら「貴庁」など)や、簡潔で正確な表現が求められます。時候の挨拶は省略しても問題ありませんが、丁寧な印象を与えるために含めることもあります。
令和〇年〇月〇日
〇〇市役所 〇〇課
御中
〒XXX-XXXX
東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇ビル4F
株式会社△△ 総務部
電話番号:03-XXXX-XXXX
担当:〇〇 〇〇
〇〇申請書類の提出について
拝啓
貴庁ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、先日ご指示いただきました〇〇の申請に関し、下記の通り書類を提出いたします。
ご査収の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
1. 〇〇申請書 1部
2. 添付資料一式 1部
以上
ワンランク上のプロフェッショナルを目指す応用技術

送付状の基本をマスターしたら、次はその知識を応用し、より洗練されたビジネスコミュニケーションを目指しましょう。ここでは、メールでの対応や時候の挨拶、そして最後の仕上げとなる押印や封筒の作法について掘り下げます。
メールの作法
現代のビジネスでは、書類をPDF化してメールで送る機会が急増しています。この場合、メールの本文そのものが送付状の役割を果たします。紙の送付状の原則である「明確さ、効率性、敬意」をデジタル媒体でいかに表現するかが鍵となります。
件名
メールの件名は、受け手が受信トレイで内容を即座に識別し、後から検索しやすくするための最も重要な要素です。「【株式会社〇〇】〇月分請求書送付の件」「〇〇職応募書類のご送付(氏名)」のように、用件と差出人を明記するのが鉄則です。これにより、相手はメールを開かなくても重要度を判断できます。
本文の構成
メール本文は、紙の送付状の構成を簡略化したものと考えます。まず「株式会社〇〇 〇〇様」のように宛名を正確に記載し、「いつもお世話になっております」といった簡潔な挨拶で始めます。「拝啓」「敬具」といった頭語・結語は通常使用しません。
次に、添付ファイルの内容を「〇〇の請求書を添付いたしましたので、ご査収ください」のように明確に伝えます。
混乱を避けるため、「【添付ファイル】請求書_202408.pdf (1通)」のように添付したファイル名を明記すると親切です。最後に「何卒よろしくお願い申し上げます」などで締めくくり、会社名、部署、氏名、連絡先が記載された署名ブロックを必ず付けます。
添付ファイル
ビジネス文書は、相手の環境に依存せず、改ざんされにくいPDF形式で送るのが基本です。機密性の高い書類を送る際は、ファイルにパスワードを設定し、パスワードは別のメールで通知するのが安全な方法です。この対応により、万が一メールを誤送信しても、第三者にファイルを開かれるリスクを低減できます。
時候の挨拶
時候の挨拶は、日本の手紙文化に根ざした、季節の移ろいと相手の健康や繁栄を気遣う心を表現する美しい習慣です。これを使いこなすことで、あなたのビジネス文書には知性と品格が加わります。
毎月適切な言葉を選ぶのが難しいと感じる場合は、季節を問わず使える万能なフレーズ「時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」を覚えておくと安心です。より細やかな配慮を示したい方のために、以下に月ごとの時候の挨拶をまとめた一覧表を用意しました。状況に応じて使い分けてください。
月別・時候の挨拶一覧表
| 月 | 漢語調(改まった表現) | 口語調(柔らかな表現) |
| 1月 | 新春の候、初春の候、厳寒の候 | 新たな年を迎え、皆様におかれましてもご健勝のことと存じます |
| 2月 | 立春の候、梅花の候、余寒の候 | 立春とは名ばかりの寒さが続きますが、お変わりなくお過ごしでしょうか |
| 3月 | 早春の候、春暖の候、弥生の候 | 日差しに春の訪れを感じるこの頃、いかがお過ごしでしょうか |
| 4月 | 陽春の候、桜花の候、春爛漫の候 | 桜の便りが聞かれる季節となりました |
| 5月 | 新緑の候、薫風の候、立夏の候 | 風薫るさわやかな季節となりました |
| 6月 | 向暑の候、梅雨の候、深緑の候 | 梅雨空の続く毎日ですが、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます |
| 7月 | 盛夏の候、猛暑の候、大暑の候 | 厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか |
| 8月 | 残暑の候、晩夏の候、立秋の候 | 暦の上では秋となりましたが、なお厳しい暑さが続いております |
| 9月 | 初秋の候、秋涼の候、爽秋の候 | 朝夕はめっきり涼しくなり、過ごしやすい季節となりました |
| 10月 | 秋冷の候、紅葉の候、錦秋の候 | 秋晴れの心地よい日が続いております |
| 11月 | 晩秋の候、向寒の候、落葉の候 | 日増しに寒さが加わってまいりました |
| 12月 | 師走の候、寒冷の候、歳末の候 | 何かと気ぜわしい毎日ですが、皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます |
押印と封筒の作法
押印について
送付状自体に押印は法的に義務付けられていません。しかし、差出人情報の会社名や氏名に角印や担当者印を重ねて押印すると、文書の信頼性が高まり、より丁寧な印象を与えます。同封する契約書や請求書への押印は非常に重要です。相手に署名・捺印を依頼する際は、「ご署名ご捺印の上」といった丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
封筒の書き方
封筒の宛名は、中の書類と同様に、会社名から部署名、役職、氏名まで正確に記載します。縦書き封筒の場合、表面の住所は右側に、会社名・宛名は中央に大きく書きます。裏面には、中央の継ぎ目を避けて左下に差出人の住所・氏名を記載します。横書き封筒の場合は、表面の宛名は中央に、郵便番号は右上に記載し、差出人情報は裏面の下部にまとめて記載します。
添え書き
封筒の表面には、中身が何かを示す添え書きを記載します。請求書なら「請求書在中」、応募書類なら「応募書類在中」と、封筒の左下(横書きの場合は右下)に赤字で記載します。この一工夫により、相手先の郵便物担当者が仕分けしやすくなり、重要書類として迅速に適切な部署へ届けられる可能性が高まります。
まとめ
この記事では、送付状の作成に関するあらゆる知識を網羅的に解説しました。最後に、自信を持ってビジネス文書を送付するために、最も重要なポイントを再確認しましょう。
- 送付状は単なるマナーではなく、受け手の業務を効率化し、信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐための重要なビジネスツールです。
- 「日付」「宛名」「差出人」「件名」「前文」「主文」「末文」「結語」「記書き」という普遍的な型が、あらゆる送付状の基礎となります。
- 転職活動、請求書発行、社内連絡など、シーンに合わせて最適な言葉遣いや構成を選ぶことが、効果的なコミュニケーションにつながります。
- メールの場合は本文が送付状の役割を果たし、件名の工夫や添付ファイルの扱い方など、デジタルならではの作法が不可欠です。
- 清潔なA4用紙、クリアファイルでの保護、適切な封筒の使用といった普遍的なマナーが、あなたのプロフェッショナリズムを支えます。
この記事で得た知識とテンプレートを活用すれば、あなたはもう送付状の作成で迷うことはありません。どんな場面でも、自信と配慮に満ちた書類を送付できるスキルは、あなたのビジネスパーソンとしての価値を確実に高めるでしょう。








一人親方給付金2025最新ガイド|最大250万円を勝ち取る全…
一人親方として働くあなたにとって、将来への不安を解消し、手元の資金を厚くできる未来はすぐそこにありま…