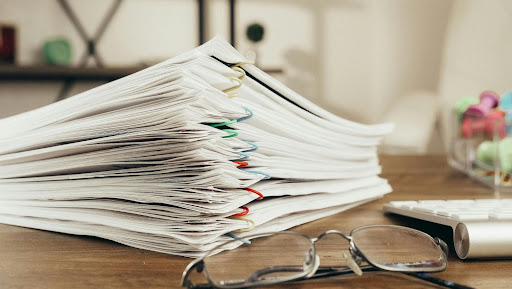
ビジネスシーンにおいて、経費精算や取引の証明に不可欠な領収書。その取り扱いに際して、日付に関する疑問を抱いた経験はないでしょうか。
経理担当者やフリーランス、個人事業主の方々にとって、領収書の扱いは日常的な業務の一部です。しかし、「領収書に記載された発行日と、実際にお金を支払った日(領収日)は異なっていても問題ないのか」という問いは、意外にも多くの方が直面する悩みです。
例えば、取引先との会食費を立て替えた後、後日まとめて領収書を受け取るケース。あるいは、オンラインショッピングで購入した商品の領収書を、数日経ってからウェブサイトで発行するケース。このように、領収書の日付が実際の支払日とずれてしまう場面は、頻繁に起こり得ます。
この記事では、領収書の発行日と領収日の違いを基点に、正しい日付の記載方法、遵守すべきルール、そして万が一、日付がずれてしまった場合の具体的な対処法について、専門的かつ網羅的に解説します。領収書の日付に関する正確な知識を身につけ、日々の経費精算や税務対応を円滑に進めるための一助となれば幸いです
目次
領収書の日付の基本原則|発行日と領収日は一致させる
領収書に記載される日付について考えるとき、「発行日」と「領収日」という二つの言葉が浮かびます。これらは異なる概念のように思えるかもしれませんが、会計および税務上の原則として、これら二つの日付は一致させる必要があります。
「領収日」と「発行日」の定義
まず、それぞれの言葉の定義を明確にしましょう。
「領収日」とは、文字通り「代金を受領した日」を指します。つまり、商品やサービスの対価として、現金やその他の決済手段によって金銭のやり取りが完了した日付のことです。これは取引の事実を証明する上で最も重要な日付となります。
一方で「領収書発行日」とは、その領収書という書類を作成し、発行した日付を指します。通常、金銭の授受と同時に領収書も発行されるため、実務上は「領収日」と「領収書発行日」は同日になるのが一般的です。
なぜ日付の一致が原則なのか
領収書は、金銭の授受があったという事実を客観的に証明するための証憑書類です。税法上、経費として計上するためには、その支出がいつ、誰に、何のために、いくら支払われたかを明確にする必要があります。
この中で「いつ」という情報を担うのが日付です。もし領収書の発行日が、実際の支払い日と異なっていれば、その取引がいつ行われたのかが不明確になり、証拠としての価値が低下してしまいます。
例えば、発行者が都合の良い日付で領収書を発行できてしまうと、経費計上時期の意図的な操作や、架空の取引の捏造といった不正行為につながるリスクが生じます。こうした不正を防ぎ、取引の透明性を確保するために、領収書には実際の金銭授受があった日付を記載することが、揺るぎない大原則とされているのです。
一部の領収書フォーマットには「発行日」と印字されていることがありますが、これも特別な事情がない限りは「金銭を受領した日」を記載するべきです。言葉の違いに惑わされず、取引の事実があった日を記すことが重要であると理解しておきましょう。
領収書に記載すべき正しい日付とは?ケース別徹底解説
領収書の日付は「金銭の授受があった日」を記載するのが原則ですが、決済方法によって判断に迷うケースもあります。ここでは、具体的な取引ケース別に、記載すべき正しい日付について詳しく解説します。
現金取引の場合
最もシンプルなのが現金取引です。店舗での買い物や対面でのサービス提供など、現金で支払いを行った場合は、その場で金銭の授受が完了します。したがって、領収書に記載すべき日付は、まさしくその現金を支払った日となります。
これは発行者側から見れば、現金を受け取った日です。事業者はお金を受け取った時点で速やかに領収書を作成し、その日の日付を記入して買主に渡す義務があります。受け取る側も、記載された日付が支払日と一致しているかをその場で確認する習慣をつけることが望ましいでしょう。
銀行振込の場合
銀行振込によって支払いが行われた場合、領収書の日付は「相手方の口座への着金が確認できた日」とするのが一般的です。振込手続きを行った日ではありません。
例えば、6月25日に振込手続きをしても、銀行の営業時間外であれば、実際の着金は翌営業日の6月26日になることがあります。この場合、金銭の授受が完了したのは6月26日であるため、領収書の日付も「6月26日」と記載するのが正確です。
発行者側は、自社の口座への入金履歴を確認した上で、その日付をもって領収書を発行する必要があります。受領者側が領収書の発行を依頼する際は、振込日とともにその旨を伝えると、よりスムーズなやり取りが期待できます。
クレジットカード決済の場合
クレジットカードでの支払いは、少し複雑な要素を含みます。利用者、加盟店(事業者)、カード会社の三者間で取引が行われるためです。しかし、領収書の日付に関する考え方は明確です。
この場合、領収書に記載すべき日付は「クレジットカードで決済手続きを行った日(カード利用日)」です。後日、銀行口座から利用代金が引き落とされる日ではありません。
金銭の直接的な移動は後日発生しますが、カード決済が承認された時点で、利用者と加盟店との間の売買契約は成立し、加盟店はカード会社から代金を受け取る権利を得ます。この契約成立日が取引日と見なされるため、領収書の日付もその日に合わせるのが適切です。
ただし、クレジットカード払いの場合は、領収書に「クレジットカード利用」と明記することが一般的です。
キャッシュレス決済(QRコードなど)の場合
PayPayや楽天ペイといったQRコード決済や、その他の電子マネーによる支払いの場合も、基本的な考え方はクレジットカード決済と同様です。
領収書に記載すべき日付は、利用者がスマートフォンアプリなどで「決済を完了した日」となります。チャージした日や、銀行口座から引き落とされる日ではありません。決済が完了した瞬間に、事業者への支払いが確定するため、その日が取引日として記録されます。
キャッシュレス決済は取引履歴がデータとして正確に残るため、発行者も受領者も日付の確認が容易です。領収書を依頼する際は、取引履歴画面などを参考に、正確な決済日を伝えることが重要です。
前払いや分割払いの場合
商品やサービスの提供前に代金の一部または全額を支払う「前払い」の場合、領収書は金銭を実際に受け取った都度、その日付で発行するのが原則です。例えば、10万円の商品の手付金として3万円を6月25日に受け取り、残金7万円を7月10日に受け取った場合、領収書は2枚発行することになります。
1枚目は6月25日付で3万円、2枚目は7月10日付で7万円の領収書です。あるいは、7月10日にまとめて10万円の領収書を発行する場合は、但し書きに「6月25日分3万円、7月10日分7万円として」といった内訳を明記し、日付は最終的な受領日である7月10日とすることが考えられます。
分割払いの場合も同様で、それぞれの支払いがあった日付で都度領収書を発行するのが最も正確な処理方法です。
領収書の日付がずれるのはなぜ?よくあるケースとその影響
原則として支払日と一致すべき領収書の日付ですが、実務上はやむを得ずずれてしまうケースも発生します。ここでは、日付のずれが起こりがちな典型的な状況と、それが経理・税務に及ぼす影響について解説します。
後日発行されるケース
最も多いのが、取引当日に領収書が発行されず、後日になってから発行されるケースです。例えば、接待や会食で支払いを立て替えた社員が、後日、会社名義の領収書を店舗に依頼するような場合がこれにあたります。
このような場合でも、領収書に記載すべき日付は、あくまでも実際に支払いが行われた本来の取引日です。発行を依頼する側は、正確な支払日を店舗に伝え、その日付で作成してもらう必要があります。発行する側も、レシートや売上帳簿などの記録を基に、事実に基づいた日付を記載する責任があります。
宿泊費などサービス提供日と支払日が異なるケース
ビジネスホテルなどでの宿泊費の支払いも、日付の認識にずれが生じやすい例です。例えば、チェックイン時に前払いで宿泊費を支払ったにもかかわらず、領収書の日付がチェックアウト日になっていることがあります。
この場合、厳密には支払いが完了したチェックイン日が領収日となります。しかし、実務上は宿泊というサービスが完了したチェックアウト日で発行されることも少なくありません。税務上、経費の帰属時期が年度をまたがない限り、この程度の日付のずれが大きな問題となることは稀です。
ただし、決算月をまたぐ場合は注意が必要です。3月31日に宿泊し、前払いを済ませたにもかかわらず、領収書の日付が翌年度の4月1日になっていると、経費計上の時期について説明を求められる可能性があります。
日付のズレが経理・税務に与える具体的な影響
領収書の日付のずれは、特に決算期や確定申告の時期において、深刻な問題を引き起こす可能性があります。
決算期をまたぐ場合のリスク
法人の決算や個人の確定申告では、特定の期間(事業年度)内に発生した収益と費用を対応させて、正確な利益を計算します。これを「費用収益対応の原則」と呼びます。例えば、3月決算の法人が、3月30日に支払った経費の領収書を、相手方の都合で4月5日付で受け取ったとします。この経費は、実際の取引が発生した3月期の費用として計上するのが正しい会計処理です。
しかし、証拠となる領収書の日付が4月5日になっていると、税務調査の際に「これは翌期(4月期)の経費ではないか」と指摘されるリスクが生じます。そうなった場合、本来計上できたはずの経費がその期で認められず、結果として課税所得が増え、納税額が過大になってしまう恐れがあります。
税務調査で指摘される可能性
税務調査官は、提出された領収書が取引の実態を正しく反映しているかを厳しくチェックします。日付が不自然に操作されていたり、実際の取引日と大きく乖離していたりすると、架空経費の計上や利益操作を疑われるきっかけになり得ます。
特に、日付のない領収書や、明らかに後から追記したような不自然な日付は、証拠能力を著しく欠くと判断されかねません。正確な日付の記載は、企業の経理の信頼性を担保する上で極めて重要な要素なのです。
このようなトラブルを避けるためには、領収書は可能な限り取引と同時に受領することを徹底し、やむを得ず後日受け取る場合でも、正しい日付を記載してもらうよう強く依頼することが肝心です。
領収書の日付を間違えた・ずれてしまった場合の対処法
細心の注意を払っていても、人間が介在する以上、日付の記載ミスや記載漏れが発生することはあります。そのような事態に直面した際、発行者と受領者それぞれの立場で、どのように対処すべきかを解説します。
発行者側の対応(再発行・訂正)
領収書を発行した側が日付の誤りに気付いた場合、最も確実で望ましい対応は、誤った領収書を回収・破棄し、正しい内容で新しい領収書を再発行することです。
相手方に渡す前に誤記を発見した場合は、単純に正しいものを作成し直せば問題ありません。しかし、すでに相手方に渡してしまった後に誤りが発覚した場合は、まず相手方に連絡を取り、事情を説明して謝罪の上、再発行に応じる旨を伝える必要があります。
再発行する際には、二重発行による不正利用を防ぐため、いくつかの注意点があります。まず、可能な限り元の誤った領収書を回収します。そして、新しく発行する領収書には「再発行」と明確に記載し、以前の領収書が無効であることを示します。こうすることで、新旧両方の領収書が不正に経費計上されるリスクを防げます。
正しい訂正の方法(二重線と訂正印)
どうしても再発行が難しい事情がある場合は、手元にある領収書の控えと、相手方が所持している領収書の両方に対して、訂正処理を施す方法もあります。
具体的な訂正方法は、誤った日付の部分に二重線を引き、その上か近くに正しい日付を明記します。そして、訂正箇所に発行者の社印や担当者印を押印します。この訂正印は、誰が訂正したかを明らかにし、改ざんではないことを証明するために不可欠です。
ただし、訂正跡のある領収書は、税務調査などでより注意深く確認される可能性があります。取引の信頼性を維持する観点からも、原則としては手間を惜しまず再発行するのが最善の策と言えるでしょう。
受領者側の対応(発行元への依頼)
領収書を受け取った側が、日付の間違いや空欄に気づいた場合、絶対にしてはならないことがあります。それは、自分で日付を書き加えたり、修正したりすることです。
領収書は発行者がその内容を証明する公的な書類です。受領者が勝手に手を加える行為は、たとえそれが正しい日付への修正であったとしても「文書の改ざん」と見なされる重大なリスクを伴います。改ざんされた領収書は証憑としての効力を失い、経費として認められなくなるだけでなく、企業の信頼を損なうことにもつながります。
日付に誤りや記載漏れを発見した場合は、速やかに発行元に連絡を取り、事情を説明して正しい領収書の再発行を依頼するのが唯一の正しい対応です。その際、手元にある誤った領収書は、発行元の指示があるまで保管しておきましょう。再発行時に回収を求められることが一般的です。
再発行が困難な場合の代替措置
万が一、発行元が廃業してしまった、あるいはどうしても連絡がつかないなど、再発行の依頼が極めて困難な状況も想定されます。
このようなやむを得ない場合に限り、代替措置として、他の客観的な資料で取引の事実を補強する方法が考えられます。例えば、支払いの事実が記録されたメールのやり取り、請求書、納品書、クレジットカードの利用明細などを、当該領収書に添付して保管します。
さらに、別紙に「取引年月日:YYYY年MM月DD日、発行元連絡不能のため再発行不可」といった経緯を記したメモを作成し、一緒に保管しておくことで、税務調査の際に事情を説明しやすくなります。ただし、これはあくまで例外的な対応であり、証拠能力としては不完全です。基本は発行元からの正式な領収書の入手を目指すべきです。
【要注意】領収書の日付に関する法的論点と罰則
領収書の日付は、単なる事務手続き上のルールにとどまらず、税法とも深く関わっています。日付の取り扱いを誤ると、意図せずとも法的な問題に発展する可能性があるため、注意が必要です。
関連する法律(法人税法・所得税法・消費税法)
領収書は、法人税法や所得税法において、損金(経費)を計上するための証拠書類として位置づけられています。これらの法律では、事業に関連する支出であることを証明するために、取引の年月日、金額、内容、相手方の氏名または名称などを記載した帳簿や書類の保存を義務付けています。日付は、その取引がどの事業年度に帰属するかを決定する上で、極めて重要な要素です。
また、消費税法においても、仕入税額控除の適用を受けるためには、同様の記載要件を満たした請求書や領収書の保存が必要です。日付が不正確であれば、適切な期間での税額計算ができず、仕入税額控除が否認されるリスクも生じます。
意図的な日付の改ざんが招くペナルティ
もし、経費計上時期を操作するなどの目的で、意図的に領収書の日付を改ざんしたり、事実に反する日付で発行したりした場合、それは不正行為と見なされます。
税務調査でこのような不正が発覚すると、本来納めるべきだった税額に加えて、ペナルティとして「過少申告加算税」や、特に悪質と判断された場合には「重加算税」が課されることになります。重加算税は最大で本税の40%にも上る重い罰則であり、企業の財政に大きな打撃を与えるだけでなく、社会的な信用も失墜させます。
電子帳簿保存法とタイムスタンプの重要性
近年、ペーパーレス化の推進に伴い、電子データで領収書を授受するケースが増えています。この電子取引のルールを定めているのが「電子帳簿保存法」です。
電子領収書の場合、そのデータがいつ作成され、その後改ざんされていないことを証明する仕組みが重要になります。その一つが「タイムスタンプ」です。タイムスタンプは、ある時刻にその電子文書が存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する技術です。
電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子領収書を保存する場合、このタイムスタンプが付与されているか、あるいは訂正や削除の履歴が残るシステムを利用することが求められます。これは、紙の領収書における「日付」の信頼性を、デジタルの世界で担保するための仕組みと言えるでしょう。電子取引においても、日付の正確性と非改ざん性の担保が、法的に強く要請されているのです。
領収書の日付に関するQ&A
ここでは、領収書の日付に関して実務上よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. 領収書の日付は和暦と西暦どちらが良いですか?
A. 和暦(令和など)と西暦のどちらで記載しても、法的な効力に違いはありません。どちらでも有効です。ただし、社内の経理規定でどちらかに統一されている場合や、会計システムへの入力形式が決まっている場合は、それに従うのが望ましいでしょう。
重要なのは、年、月、日を省略せずに明確に記載することです。「R7.6.25」や「25.6.25」のような省略形は、後から見たときにどの年か判別しにくくなる可能性があるため、避けるべきです。「令和7年6月25日」や「2025年6月25日」のように、誰が見ても一義的に理解できる形式で記載することが推奨されます。
Q. 日付が空欄の領収書は有効ですか?
A. 日付が空欄の領収書は、証憑書類として不完全です。税法上、経費として認められるためには取引年月日が記載されている必要があるため、日付のない領収書は税務調査で否認されるリスクが非常に高くなります。
日付が空欄のまま発行されてしまうと、受領者が後から都合の良い日付を書き込むことが可能になり、不正の温床となりかねません。発行者は必ず日付を記入して渡す義務があり、受領者も日付が空欄の領収書を受け取った場合は、その場で記載を求めるべきです。
Q. ネットショッピングの領収書の発行日はいつになりますか?
A. ネットショッピングでは、「注文日」「発送日」「決済確定日」「領収書発行日」など、様々な日付が存在し、混乱しやすいかもしれません。経費計上の基点となるのは、原則として「商品の購入日(注文日)」または「サービス提供が確定した日」です。
領収書をウェブサイトからダウンロードする場合、そのダウンロードした日が「発行日」として記載されることが多いですが、経費処理上は実際の購入日や利用日が重要になります。注文確認メールや納品書など、実際の取引日を証明できる他の書類も併せて保管しておけば、領収書の発行日が多少ずれていても、実務上問題になることはほとんどありません。
Q. 収入印紙の消印の日付は領収日と同じでなければいけませんか?
A. 5万円以上の領収書には収入印紙を貼り、消印を押す必要があります。この消印は、印紙の再利用を防ぐためのものであり、印紙税法上、必ずしも領収書の日付と一致している必要はありません。後日、印紙を貼って消印を押すことも認められています。
ただし、消印を忘れると過怠税が課されるため、領収書を発行した際に速やかに行うのが賢明です。実務上は、領収書の日付と消印の日付が同じであることが一般的であり、その方が管理上も混乱が少ないでしょう。
まとめ
この記事を通じて、領収書の日付が持つ重要性と、その正しい取り扱い方法について解説してきました。最後に、本記事の要点を改めて整理します。
領収書の日付は、原則として「実際に金銭の授受が行われた日」を記載します。「発行日」と「領収日」は、この取引の事実があった日として一致させるのが大原則です。
日付を意図的にずらしたり、事実に反する日付を記載したりする行為は、経理上の不正を疑われる原因となります。常に真実の取引日に基づいて、正確な日付を記載し、受け取ることが鉄則です。
取引の都合上、領収書の発行が後日になった場合でも、記載すべき日付は本来の支払日です。もし受け取った領収書の日付にずれを発見した場合は、速やかに発行元に連絡し、訂正または再発行を依頼しましょう。
万が一、日付の記載を誤ってしまった場合、発行者は再発行や訂正印による正式な訂正を行う責任があります。受領者側が自分で日付を書き換えることは、文書改ざんにあたり絶対に避けなければなりません。
領収書の日付管理は、一見すると些細な事務作業に思えるかもしれません。しかし、日々の経費精算から決算、確定申告に至るまで、企業の会計と税務の根幹を支える極めて重要な要素です。
正確な日付が記載された、信頼性の高い領収書を適切に取り交わす文化を社内に根付かせること。それが、円滑な経理処理を実現し、税務上のリスクを回避し、ひいては社会的に信頼される企業体制を築くための、確かな第一歩となるのです。








不動産売買の領収書テンプレートと正しい書き方|印紙税の判定か…
不動産売買における金銭トラブルを未然に防ぎ、税務署への申告をスムーズに進めるためには、正確な領収書の…