
企業で扱う書籍やカタログの発送コストについて、より安価な方法を探している方も多いのではないでしょうか。ゆうメールを正しく活用すれば、発送コストを大幅に節約できる可能性があります。
しかし、「この荷物はゆうメールで送れるのか」「梱包方法はこれで合っているのか」「信書とは何か」といった疑問や不安を感じることも少なくないでしょう。
この記事では、ゆうメールに関するあらゆる疑問を解決します。基本的な送り方の手順から、送料をさらに安くするためのテクニック、他の配送サービスとの詳細な比較まで、網羅的に解説します。記事を読めば、ゆうメールを自信を持って使いこなし、常に最も経済的で最適な発送方法を選べるようになるでしょう。
本記事が提供するのは、単なる手順の紹介だけではありません。ゆうメールのルールに隠された背景を理解し、なぜそのような決まりがあるのかを知ることで、迷いをなくすことができます。ゆうメールの全てを学び、発送コストを賢く管理する第一歩を踏み出しましょう。
目次
ゆうメールとは?基本を理解して送料を節約する第一歩
ゆうメールは、日本郵便が提供する配送サービスの一つです。その最大の特徴は、特定の品物を送る際に、他の方法と比較して送料を安く抑えられる点にあります。しかし、この「安さ」には理由があり、利用するにはいくつかのルールを理解する必要があります。
サービスの概要
ゆうメールは、冊子状の印刷物やCD・DVDなどの電磁的記録媒体を、1kgまでの重さで送るために特化したサービスです。料金は荷物の重さのみで決まり、日本全国どこへ送っても同じ料金が適用される「全国一律料金」が採用されています。このシンプルな料金体系が、ゆうメールの大きな魅力です。
このサービスは、一般的な小包を送るためのものではありません。むしろ、特定の用途に絞り込むことで、効率的な配送と低価格を実現した専門的なサービスと考えるべきです。この専門性こそが、ゆうメールの利用条件が厳格である理由です。送付可能な品目を限定することで、日本郵便は取り扱いのプロセスを簡素化し、その分を料金に反映させています。
具体的には、以下のような品物を送る際に非常に便利です。
- 書籍、雑誌
- 商品カタログ、会報誌
- 各種マニュアル類
- CD、DVD、ブルーレイディスク
フリマアプリで書籍を販売する個人から、顧客にカタログを送付する企業まで、幅広い層にとってコスト削減の強力な味方となります。
サイズ・重さ・料金
ゆうメールを利用する上で、まず把握すべき基本的な規格はサイズ、重さ、そして料金です。以下の表にまとめましたので、発送したい荷物が条件に合っているか確認しましょう。
| 重量 | 料金 | サイズ規定 |
| ~150g | 180円 | 長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内 |
| ~250g | 215円 | 長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内 |
| ~500g | 310円 | 長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内 |
| ~1kg | 360円 | 長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内 |
| 料金は2025年9月時点のものです。 |
この表が、ゆうメールを利用するかどうかを判断する際の基本となります。荷物の重さを計測し、この料金表と他のサービスを比較することが、賢い送料節約の第一歩です。
送れるものと送れないもの
ゆうメールの利用で最もつまずきやすいのが、「送れるもの」と「送れないもの」の区別です。ここを誤ると、荷物が返送されたり、意図せず高い料金を請求されたりする可能性があります。
送れるもの
ゆうメールで送ることが認められているのは、主に以下の2種類です。
- 冊子とした印刷物
- 書籍、雑誌、カタログ、会報、各種マニュアル類など。コイル状の金具で綴じられたカレンダーも対象です。
- 電磁的記録媒体
- CD、DVD、ブルーレイディスク、ビデオテープ、カセットテープなど。
送れないもの
一方で、以下のものはゆうメールで送ることができません。
- 信書
- 手紙、請求書、納品書、領収書など(詳細は後述します)。
- 手書きの書類
- 印刷されていない、手書きのメモや手紙は送れません。
- 冊子ではない印刷物
- 一枚もののチラシやパンフレットは、原則として対象外です(特約ゆうメールを除く)。
- 物品全般
- 衣類、雑貨、アクセサリー、化粧品、食品など、印刷物や電磁的記録媒体以外のものは全て送れません。
同封できるもの
ゆうメールの本来の目的は、ダイレクトメールや通信販売の促進にあると考えられます。そのため、主要な内容物(カタログなど)に関連するものであれば、以下のものを同封することが認められています。
- 付録
- 内容物より軽く、「付録」という文字を表示する必要があります。
- 返信・注文用の書類
- 申込用紙、アンケート用紙、払込書用紙、返信用封筒やはがきなど。
- 商品見本
- 「見本」「試供品」「サンプル」のいずれかの文字を記載したもの。
- その他
- 割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、アンケート記入用のボールペンなど。
これらのルールは、ゆうメールがビジネス、特にマーケティングや販売活動で活用されることを想定して設計されていることを示しています。この背景を理解することで、ルールの意図がより明確になります。
ゆうメールの送り方:4つのステップ
ゆうメールの送り方は、4つの簡単なステップで完了します。一つひとつの手順を確実に実行すれば、誰でも迷うことなく発送できます。
ステップ1:梱包
まず、送りたいものを梱包します。ゆうメールには専用の梱包材はありません。サイズ規定(縦34cm × 横25cm × 厚さ3cm、重さ1kg)に収まるものであれば、市販の封筒や薄い段ボール箱が利用できます。
書籍や雑誌の場合は、雨濡れ防止のためにビニール袋に入れた後、中身が透けない封筒やクッション付き封筒に入れると安心です。CDやDVDの場合は、破損を防ぐため、必ず緩衝材(エアキャップなど)で包んでから封筒に入れましょう。
梱包材の厚みや重さも全体のサイズ・重量に含まれるため、梱包後の状態で規定内に収まるように注意してください。
ステップ2:内容物の提示
ここがゆうメールの最大の特徴であり、最も重要なポイントです。ゆうメールは、中身が「送れるもの」であることを郵便局員が確認できるようにしなければなりません。そのための方法は3つあります。
一つ目は、封筒の一部を開ける方法です。最も手軽な方法で、封筒の角を小さく切り落とし、中身の冊子やCDケースが見えるようにします。切り込みが配送中に広がらないよう、上から透明なテープで補強しておくと良いでしょう。
二つ目は、透明の窓を設ける方法です。封筒の一部に透明な部分を作る方法で、市販の窓付き封筒を利用したり、荷物全体を透明な袋(OPP袋など)に入れてから、その上にあて名ラベルを貼る方法があります。企業がダイレクトメールを送る際によく使われる、見た目がきれいな方法です。
三つ目は、郵便局の窓口で見本を提示する方法です。荷物を完全に密封したい場合は、この方法を選びます。封をしていない状態で荷物を郵便局の窓口へ持っていき、局員に中身を確認してもらいます。確認が終わったら、その場で封をして発送手続きを行います。
このような手間が必要なのは、ゆうメールの低料金が「送れるもの」を限定することで成り立っているためです。この確認作業は、利用者がルールを守っていることを証明するための、いわば「信頼の証」なのです。この理由を理解すれば、一手間をかけることにも納得がいくはずです。
ステップ3:外装への「ゆうメール」表記
梱包した荷物の見やすい場所に、赤ペンなどで明確に「ゆうメール」と記載します。手書き、スタンプ、あるいはあらかじめ印刷された表示でも問題ありません。
この表示がない場合、荷物はゆうメールとして扱われず、より料金の高い定形外郵便物として処理されてしまう可能性があります。せっかく安く送るための工夫が無駄にならないよう、忘れずに記載しましょう。
ステップ4:発送手続き
最後のステップは発送です。発送方法は2通りあります。
一つはポスト投函です。ステップ1から3までの条件(サイズ、重量、内容物の確認措置、ゆうメール表記)を全て満たし、料金分の切手を貼ってあれば、郵便ポストに投函するだけで発送できます。24時間いつでも発送できる手軽さが魅力です。
もう一つは郵便局窓口での手続きです。送料を現金で支払いたい場合や、内容物の確認方法として「窓口で見本を提示する」を選んだ場合、荷物の重さが分からず正確な料金を知りたい場合、荷物が厚くてポストの投函口に入らない場合などは、郵便局の窓口を利用します。窓口に持っていけば、重さの計測から料金の支払いまで、局員が対応してくれるので確実です。
ゆうメール利用の最重要知識「信書」のルール

ゆうメールを利用する上で、絶対に避けて通れないのが「信書(しんしょ)」のルールです。このルールを正しく理解していないと、意図せず法律に違反してしまう可能性もあります。
「信書」の定義
郵便法において、信書は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。
これを簡単に言い換えると、「特定の人にだけ伝えたい、個人的なメッセージや事実が書かれた文書」のことです。「この手紙は、他の誰でもない、あなたに宛てたものです」という性質を持つものが信書にあたります。
信書の配達は、法律によって日本郵便株式会社と国から許可を得た特定の事業者だけに許可されています。ゆうメールは信書を送ることができないサービスのため、これを使って信書を送ることは法律違反となります。
信書と判断される書類の具体例
では、具体的にどのようなものが信書にあたるのでしょうか。以下に代表的な例を挙げます。
- 請求書類(請求書、納品書、領収書、見積書など)
- 証明書類(免許証、認定書、証明書の写し、履歴書など)
- 通知書類(契約書、会議の招集通知、結婚式の招待状など)
- パーソナライズされたダイレクトメール(DM)
特に企業が注意すべきは、パーソナライズされたDMです。以下のような表現は、受取人を特定していると見なされ、信書に該当する可能性が非常に高くなります。
- 「〇〇会員の皆様へ」
- 「〇〇サービスをご利用のお客様限定」
- 「先日は〇〇をご購入いただきありがとうございます」
- 顧客の購入履歴やポイント残高に言及する内容
不特定多数に向けたチラシや広告は信書にはあたりませんが、上記のように顧客との関係性に基づいたメッセージを送る場合は、信書と判断されるリスクがあります。
例外的に同封が許可される「添え状」
信書は送れませんが、一つだけ例外があります。それは「無封の添え状」です。
これは、送る荷物(書籍やカタログなど)に添える簡単な挨拶状や、内容物の説明書きのことです。ただし、添え状として認められるには条件があります。あくまで荷物が「主」で、添え状は「従」の関係であること、簡単な挨拶や内容物の説明にとどまること、そして封筒などに入れず、そのまま同封すること(無封)が求められます。
この信書のルールは非常に厳格で、多くの企業がDM発送時に頭を悩ませる問題です。その結果、DMの文面を信書にあたらないように工夫する「非信書化」を専門とするコンサルティングや、発送代行会社が存在するほど、ビジネスに与える影響は大きいのです。個人で利用する場合も、手紙などをうっかり入れてしまわないよう、十分な注意が必要です。
ゆうメールのオプションサービス活用術
ゆうメールは基本サービスでは追跡や補償がありませんが、追加料金を支払うことで様々なオプションを付加できます。用途に応じてこれらのサービスを組み合わせることで、ゆうメールをさらに便利に、そして安全に利用することが可能です。
| オプション名 | 追加料金 | 機能 | こんな時に便利 |
| 特定記録 | +160円 | 荷物の引受けと配達を記録。追跡サービスで配達状況を確認可能。 | 相手の郵便受けに届いたことを確認したいが、補償までは不要な場合。 |
| 簡易書留 | +350円 | 引受けから配達までの過程を記録し、追跡も可能。5万円までの実損額を補償。 | 紛失や破損が心配な、少し価値のあるものを送る場合。 |
| 一般書留 | +420円~ | 簡易書留より手厚い。損害要償額に応じた補償(上限500万円)。 | 高価な書籍や絶版のCDなど、万全の補償が必要な場合。 |
| 速達 | +330円 | 通常より早く届ける。土日・祝日も配達される。 | 少しでも早く相手に届けたい場合。 |
| 配達日指定 | +52円 | 差出日の3日後から10日以内の希望日を指定可能。土日・祝日も指定できる。 | 記念日など、特定の日付に届けたい場合。 |
これらのオプションは、ゆうメールの弱点である「追跡なし」「補償なし」「土日祝の配達なし」といった点を補うためのものです。
例えば、「ゆうメール(180円)に特定記録(160円)を付けて合計340円」と、「初めから追跡付きの他のサービス」のどちらがニーズとコストに合っているかを比較検討することが重要です。必要な機能だけを追加料金で選べる、カスタマイズ性の高さがゆうメールのオプションの魅力です。
法人・大口向け「特約ゆうメール」によるコスト削減
個人利用だけでなく、ゆうメールは法人や個人事業主が大量の発送物を送る際にも非常に有効なツールです。特に「特約ゆうメール」という制度を活用することで、通常料金よりも大幅にコストを削減できます。
特約ゆうメールとは
特約ゆうメールとは、年間発送数などの条件を満たす大口の差出人が日本郵便と直接契約を結ぶことで、通常よりも安い特別運賃でゆうメールを利用できる制度です。これは一般の利用者が窓口で利用できるサービスではなく、事業者向けの割引契約です。
利用条件とメリット
契約を結ぶための条件は郵便局との交渉によりますが、一般的には「年間500個以上」の差出が一つの目安とされています。その他、差出方法(地域ごとに仕分けるなど)にも条件が設けられることがあります。
最大のメリットは、通常料金よりも格段に安い単価で発送できる点です。発送量が多ければ多いほど、割引率も大きくなる傾向にあります。また、特約契約を結ぶと、通常のゆうメールでは送れない「冊子でない印刷物(チラシなど)」も発送対象となる場合があり、DMの自由度が格段に上がります。
発送代行業者の活用
年間の発送数が契約条件に満たない中小企業や個人事業主でも、この特約ゆうメールの恩恵を受ける方法があります。それは、日本郵便と大口契約を結んでいるDM発送代行会社を利用することです。これらの会社に発送を委託することで、自社が直接契約していなくても、特約運賃の安い料金でDMなどを発送できます。
他の発送方法との徹底比較
ゆうメールは確かに安いサービスですが、常に最安とは限りません。送るものの種類、重さ、厚さ、そして追跡や補償の要不要によって、最適な発送方法は変わります。ここでは、ゆうメールとよく比較される主要な発送サービスとの違いを見ていきましょう。
発送サービス別 料金・サイズ・特徴 比較一覧表
| サービス名 | 料金 | サイズ・重量 | 追跡 | 補償 | 信書 | 配達速度/土日祝 | 特徴 |
| ゆうメール | 180円~360円 | ~1kg、厚さ3cm以内 | オプション | オプション | × | 遅い/× | 冊子やCD/DVDに特化。条件が合えば安い。 |
| 定形外郵便(規格内) | 140円~750円 | ~1kg、厚さ3cm以内 | オプション | オプション | ○ | 遅い/× | ゆうメールで送れない小物などを送る場合に利用。 |
| 定形外郵便(規格外) | 260円~1,750円 | ~4kg、3辺合計90cm以内 | オプション | オプション | ○ | 遅い/× | 厚さ3cm超の荷物を安価に送る選択肢。 |
| クリックポスト | 全国一律185円 | ~1kg、厚さ3cm以内 | ○ | × | × | 速い/○ | 全国一律料金で追跡付き。オンライン決済・ラベル印刷必須。 |
| ゆうパケット | 250円~360円 | ~1kg、厚さ3cm以内 | ○ | × | × | 速い/○ | 厚さで料金変動。追跡付きで安心。 |
| レターパックライト | 全国一律430円 | ~4kg、厚さ3cm以内 | ○ | × | ○ | 最速/○ | A4サイズ・4kgまで対応。信書も送れる。 |
| レターパックプラス | 全国一律600円 | ~4kg、厚さ制限なし | ○ | × | ○ | 最速/○ | 厚さ3cm超でもOK。対面手渡しで確実。 |
| 料金は2025年9月時点のものです。 |
この表は、どの方法で送るべきかという問いに答えるための羅針盤です。送料だけでなく、追跡の有無や配達速度といったサービス内容を総合的に比較することが、最適な選択につながります。
ケース別・最適な発送方法の選び方
上記の比較表を基に、具体的なシナリオで最適な発送方法を考えてみましょう。
ケース1:A4サイズの雑誌(200g)をとにかく安く送りたい場合
このケースでは、ゆうメールなら215円です。一方、クリックポストは全国一律185円で、さらに追跡サービスも付いています。したがって、クリックポストが最適と言えるでしょう。ゆうメールが優位になるのは、オンラインでの決済やラベル印刷ができない場合に限られます。
ケース2:追跡が必要な薄い商品(Tシャツなど)を送りたい場合
まず、Tシャツは「物品」なのでゆうメールでは送れません。定形外郵便(規格内)は追跡がオプションです。クリックポスト(185円)やゆうパケット(250円~)は初めから追跡が付いています。価格とサービスのバランスを考えると、クリックポストが最も優れた選択肢です。
ケース3:厚さが3cmを超える本(厚さ4cm、重さ700g)を送りたい場合
厚さが3cmを超えているため、ゆうメール、クリックポスト、ゆうパケット、レターパックライトは全て利用できません。選択肢は定形外郵便(規格外)かレターパックプラスになります。
定形外(規格外)だと920円かかりますが、レターパックプラスなら全国一律600円です。レターパックプラスが圧倒的に安く、さらに速達扱いで追跡も付いているため、最適な選択肢です。
ケース4:信書(請求書)を送る必要がある場合
ゆうメールやクリックポストで信書を送ることは法律で禁じられています。この場合は、定形外郵便やレターパック(ライトまたはプラス)など、信書の送付が許可されているサービスを必ず利用してください。
このように、荷物の特性に合わせてサービスを使い分けることが、賢い発送の秘訣です。
ゆうメールに関するよくある質問
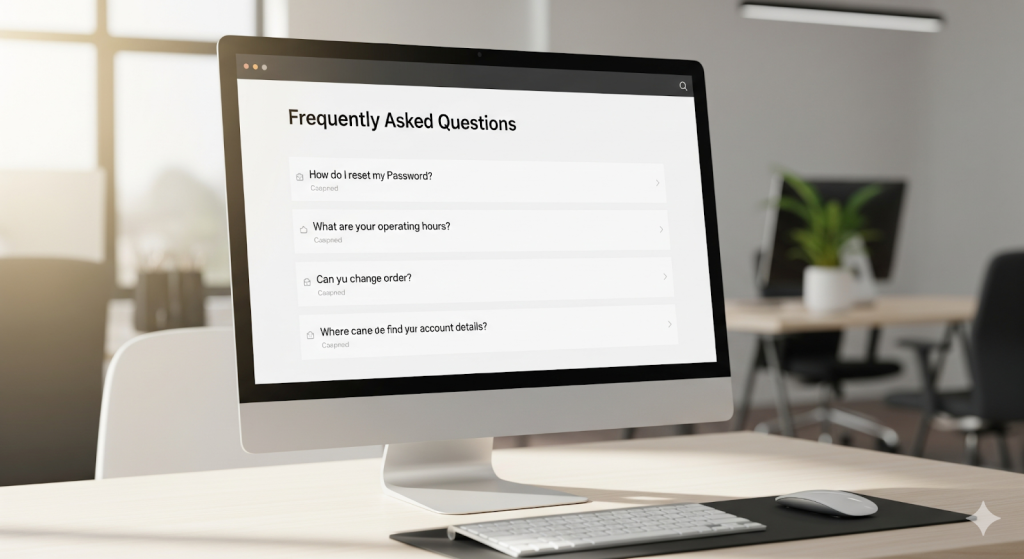
配達日数と土日祝日の配達について
配達日数は、おおむね差出日の翌々日以降で、通常の郵便物と同程度です。ただし、最も注意すべき点は、土曜日、日曜日、祝日は配達されないことです。金曜日に差し出した場合、配達は早くても翌週の月曜日以降になるため、急ぎの荷物には向いていません。
コンビニからの発送について
原則として、コンビニのレジカウンターからゆうメールを発送することはできません。ただし、ローソンなど店内に郵便ポストが設置されているコンビニであれば、切手を貼ったゆうメールをそのポストに投函することは可能です。ゆうパックのようにコンビニで受付や支払いができるサービスとは異なるので注意が必要です。
料金の支払い方法について
料金は切手で支払うことが可能です。郵便ポストから投函する場合は、料金分の切手を貼る必要があります。郵便局の窓口で手続きをする場合は、現金または切手で支払うことができます。
信書を誤って送付した場合について
郵便局で発見された場合、荷物が差出人に返還されることがあります。また、悪質なケースと判断されると郵便法違反に問われる可能性もゼロではありません。トラブルを避けるためにも、発送前に中身をしっかり確認することが非常に重要です。
まとめ
ゆうメールは、その特性を正しく理解し、ルールを守って利用すれば、送料を大幅に節約できる非常に優れたサービスです。最後に、ゆうメールを賢く使いこなすための要点を再確認しましょう。
ゆうメールの核心は、「1kgまでの書籍・カタログ・CD/DVDなどのメディアを、追跡なし・平日配達でよければ格安で送れる」という点にあります。利用する上で最も重要なルールは、以下の3つです。
- 送れるのは印刷物とCD/DVDのみと心得る。
- 必ず中身が確認できる梱包(角を切る、窓を付けるなど)を施す。
- 手紙や請求書などの「信書」は絶対に入れない。
ゆうメールは強力な節約ツールですが、万能ではありません。発送のたびに、その荷物が本当にゆうメールに適しているのかを考え、クリックポストやレターパックといった他の選択肢と比較検討する習慣をつけること。それが、送料を最も賢く管理し、常に最適な方法で荷物を送るための最善の道筋です。








労災と傷病手当金の違いを徹底解説!いくらもらえる?申請方法は…
働けない期間の収入を最大限に確保して、お金の不安を一切感じることなく治療に専念できる安心な毎日を手に…