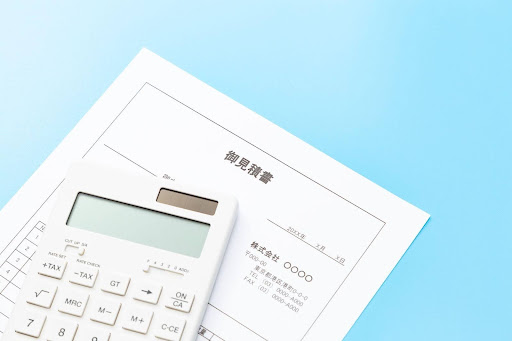
見積書とは、契約前に「この内容で商品やサービスを提供します」という意思を示すために作成する書類です。本記事では、見積書と請求書・発注書の違いや、見積書を発行した方がいい理由などについてわかりやすく解説します。
目次
見積書とは?簡単に解説
見積書とは、対象となる商品やサービスの金額・数量などを、受注側が発注側に対して提示するための書類です。発注者は見積書を確認し、発注するかどうかを決定します。双方が内容に同意できれば、契約に至ります。
見積書を作成する段階では契約は締結していないため、商品やサービスの内容が変更になったなどの理由で、最終的な金額と見積書の金額が一致していなくても問題はありません。
見積書を作成した場合には、事業における取引を示す書類となるため、納品書や領収書など同様に保存が義務付けられています。なお、見積書の作成自体は法律によって義務付けられているわけではなく、作成しないケースもあります。
関連リンク:見積書の正しい書き方を解説!【見本付き】作成目的や注意点もご紹介
見積書を書く際に必要なもの
見積書を作成するには、必要なものがいくつかあります。まず、見積書用紙を準備します。用紙の選び方に法的な制限はありませんが、用紙のサイズはA4が一般的です。
用紙がない場合は、テンプレートをダウンロードしたり、Webサービスを利用して作成することができます。
完成した見積書は、メールで送信されるケースが多いですが、FAXや郵送で送ることもあります。郵送する場合は、以下のものを準備する必要があります。
- 封筒:長形3号(120mm × 235mm)が一般的です。
- 切手:2024年10月1日以降、定型郵便物の切手代は50gまで110円となります。
- 見積書在中のスタンプ:手書きでも対応可能です。
見積書の書き方を項目ごとに解説
見積書に記載する項目は以下の通りです。
- 書類のタイトル
- 通し番号
- 発行日
- 有効期限
- 宛先
- 自社の情報
- 社印
- 商品の情報
- 見積もり金額
- 納期予定
- 備考
各項目について詳しく解説します。
見積書の書き方・作り方を無料のテンプレートを用いてわかりやすく解説!ポイントや注意点も!-INVOY
1. 書類のタイトル
書類の目立つ位置に「見積書」「御見積書」などのタイトルを記載します。
場合によっては「簡易見積書」や「正式見積書」といった表現を用いることもあります。
タイトルは書類の一番上に配置し、相手がどのような書類なのかすぐに見分けられるように記載します。フォントを大きくしたり、太字で記載したり、アンダーラインを使用すると良いでしょう。
2. 通し番号
通し番号は必須ではありませんが、たくさんの見積書を発行する場合に、見積書を管理しやすくする目的で記載することもあります。特に、書類の発行システムを通して見積書を発行する場合にはこの通し番号が表示されることが多いでしょう。
「No.001」のように番号を付け、発行順に記録することで、複数の見積書を発行する際の混乱を防ぎます。通し番号は、社内での書類管理にも役立ち、後から内容を確認する際にスムーズに該当の見積書を見つけることができます。
また、年度ごとに番号をリセットしたり、案件ごとに特定の番号を付けるなど、自社の運用に合わせた管理方法を取り入れると効率的です。
3. 発行日
書類の右上には見積書の発行日を記載します。この日付は自分が見積書を発行した日で構いません。
一般的に、西暦で「2025年1月11日」のように記載しますが、和暦を使用する企業もあります。発行日を記載することで、見積書の有効期間や納期の基準日が明確になり、取引先との契約内容の確認に役立ちます。発行日が不明瞭だと、取引時のトラブルにつながる可能性があるため、正確に記載することが重要です。
また、見積書に修正が生じた場合は、再発行日を改めて記載して、発行日を常に最新のものに保つように注意しましょう。
4. 有効期限
商品の価格が変更になるなどの事態に備えたり、顧客に早めの発注を促したりする目的で、見積書には有効期限を設けます。特に、原材料や人件費の変動で商品の価格が変わる可能性がある場合などには、有効期限を短めに設定するといいでしょう。
有効期限は、「〇〇年〇〇月〇〇日まで有効」と具体的な日付を明記するのが一般的です。「発行日から30日以内有効」といった期間で記載する方法もありますが、具体的な日付を記載したほうが、より分かりやすいでしょう。
5. 宛先
見積書を送付する宛先を記載します。取引先の会社名、部署名、担当者名を正式名称で記載しましょう。「〇〇株式会社 御中」や「〇〇株式会社 〇〇様」といった敬称をつけるのがマナーです。
個人事業主に対して書類を送付する場合は、ビジネス用の名称である屋号か、もしくは相手の個人名を記載します。
宛先に誤字脱字があると、取引先に失礼にあたるため、事前にしっかりと確認しましょう。また、複数の担当者に送る場合は、「〇〇株式会社 営業部 御中」のように、広範囲な部署名を記載するのも有効です。
6. 自社の情報
見積書の発行者である自社の情報について記載します。会社名・部署名・担当者名・住所・電話番号などを記載しましょう。また、連絡手段に応じてメールアドレスやFAX番号を入れることもあります。
これにより、取引先が迅速に連絡を取ることが可能になります。また、法人番号の記載が求められる場合もあるため、相手方の要望に応じて対応しましょう。自社情報が不明瞭だと、取引の信頼性に影響を及ぼすため、正確に記載することが大切です。
7. 社印
見積書に社印を押さなくてはいけないという法的な決まりはありませんが、会社のルールで押印するよう定められていることもあります。
社印を押印することで「しっかりとした会社だ」「正式な文章だ」という印象を与えられる可能性があります。自社の情報の右側に、文字に少し重なるようにして押印しましょう。
押印は、見積書の最終確認が完了したことを意味するため、内容を確認した後に行います。押印する際は、押印が不鮮明にならないよう、しっかりと押すことが重要です。見積書のデザインが崩れないように押印する位置にも配慮しましょう。
なお、電子見積書の場合は、電子印鑑を利用することも可能です。
8. 商品の情報
ここが見積書の中心となる部分です。見積もりの対象となる商品名や型番、内容や数量、単価、商品ごとの金額を記載します。商品が複数ある場合は、商品ごとに細かく分けることで、相手にとって分かりやすい見積書になります。
商品以外にも請求することになる費用(送料など)があればここに記載しましょう。また、割引を適用する場合には金額をマイナスにして記載することも可能です。
商品説明が不足していると、取引先が内容を誤解する可能性があるため、必要に応じて補足説明を加えることも検討しましょう。例えば、商品の写真やイラストを添付すると、より分かりやすくなります。
9. 見積もり金額
各商品の金額を合計した金額を「見積もり金額」として記載します。税抜・税込のルールは特に定められていませんが、相手が合計額を把握しやすく、後々のトラブルを防ぐためにも、税込価格を基本としつつ、税抜価格も併記する方法が望ましいでしょう。
商品の合計金額を記載する「小計」と、それに対して発生する「消費税」、それらを足した「合計」の欄も設けましょう。金額の間違いがあると、取引先に不信感を与える可能性があるため、計算ミスには十分注意が必要です。
誤解やトラブルを防ぐために、効果的に金額を記載する方法を以下に示します。
- 金額を挟む記号や文字の使用:たとえば「¥13,510.-」のように、金額の前に「¥」や「金」、後ろに「.-」や「-」、「円」や「円也」の追記
- 大字(だいじ)の使用:アラビア数字ではなく、「壱」「弐」「参」などの大字の使用
分かりやすく正確に記載したうえで、改ざん防止策を実施することで、取引の信頼性が増し、良い印象を与えることができます。
10. 納期予定
相手が発注を検討しやすくなるよう、納品予定日も記載しましょう。「〇〇年〇〇月〇〇日納品予定」のように具体的な日付を記載すれば、取引先のスケジュール調整がスムーズになります。また、「受注から5営業日以内」「発注から3週間で納品いたします」といった表現を用いることも可能です。
確実な納品日がわからない場合は、「納期についてはご相談ください」などと記載するケースもあります。ただし、納期が曖昧だと取引先に不安を与えるため、できるだけ明確に記載することが望ましいです。万が一、納期の変更が生じた場合は、速やかに連絡することも重要です。
11. 備考
これまでに記載した情報のほかに伝えるべきことや注意事項などがあれば、備考欄に記載します。「振込手数料は弊社で負担いたします」「お支払い期限は○月○日までとさせていただきます」などの書き方があります。
見積内容に調整可能な部分がある場合は、備考欄にその旨を記載しましょう。また、特に追加情報がない場合でも、「ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください」と一言添えることで、取引がよりスムーズになります。
見積書作成の3つのポイント!
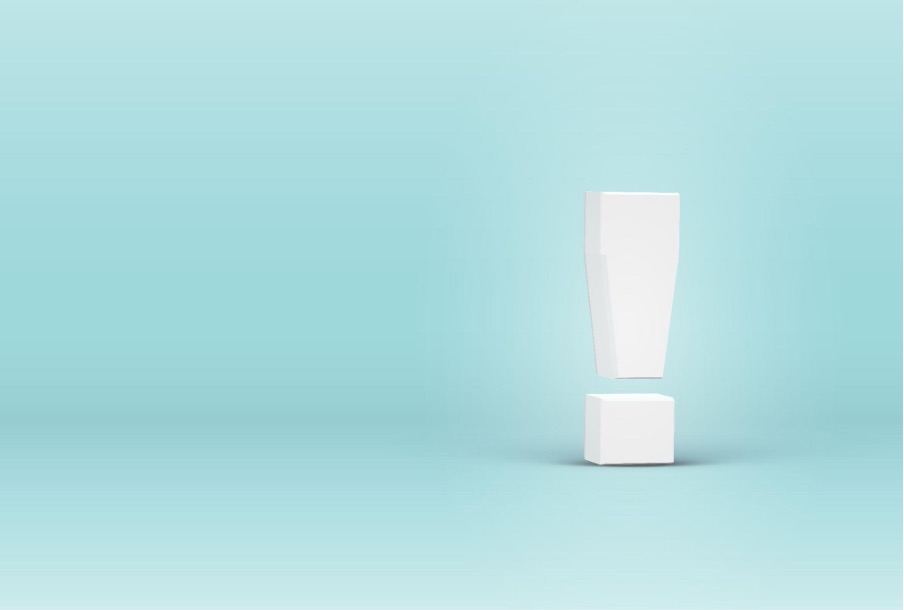
見積書を作成するにあたって、定められた書き方があるわけではありません。しかし、必要な情報をわかりやすく伝えられるように、以下のポイントに基づいて作成することをおすすめします。
書類の様式を統一する
会社や部署ごとに見積書の様式を統一することで、作成や保管がしやすくなります。使用する見積書のフォーマットを用意し、担当者に共有しましょう。
内訳と合計金額を明記する
どの商品に対して金額がいくらかかるのか内訳を明記すると、変更や追加があった時に対応しやすくなります。また、最終的な合計金額がいくらなのか分かりやすいよう、四角で囲ったり、大きな文字で記載したりすると親切です。
必要に応じてその他の事項も記載する
見積書に備考欄を設ければ、商品や金額以外の情報も発注側に伝えられます。支払い方法や納期・見積書の有効期限など、必要と思われる情報を記入し、認識の相違からくるトラブルを防ぎましょう。
関連リンク:見積書の正しい書き方を解説!【見本付き】作成目的や注意点もご紹介
見積書の作成にはテンプレートやシステム利用がおすすめ

見積書は、発注側が実際に発注するのかどうかを検討するために使う書類です。見積書を適切に作成することで、信頼できる会社であることを示し、将来的な売上に繋げられる可能性があると言えるでしょう。また見積書はその時々によって異なる様式を使うのではなく、決まった作成方法で統一することが一般的です。作成方法を統一することによって、記載漏れや紛失を防ぎ、双方にとって管理がしやすくなるでしょう。
見積書は、インターネットで紹介されているテンプレートをダウンロードしたり、クラウドシステムを通じて簡単に作成したりする方法があります。使いやすい方法を採用し、取引の効率化に繋げましょう。
関連リンク:見積書 無料エクセルテンプレート
見積書作成を楽に行うならINVOY
見積書は自社の商品やサービスを注文してくれるかどうかに関わる重要な書類です。しかし、日頃からやるべきことが多く、そのような事務作業にあまり時間をかけられないという方も多いのではないでしょうか。
弊社のサービス「INVOY」は、見積書や請求書・納品書をはじめとする書類を無料で作成・管理できる機能を備えています。見積書を簡単に作成したいという方は、この機会にぜひ利用をご検討ください。
まとめ
見積書とは、契約前に「この内容・金額で商品やサービスを提供できます」という意思を示すために発行する書類です。発注側は見積書に記載された内容を見て取引を行うかどうか検討するため、見積書は丁寧でわかりやすいものを発行することが望ましいとされています。
テンプレートやシステムを利用してわかりやすい見積書を発行することで、スムーズな取引を目指しましょう。
▶ 見積書の基礎知識








診断書の添え状テンプレート決定版|休職・復職で失礼のない書き…
診断書を会社に送るという行為は、単なる事務手続きではありません。それは、あなたがこれから心身を休ませ…