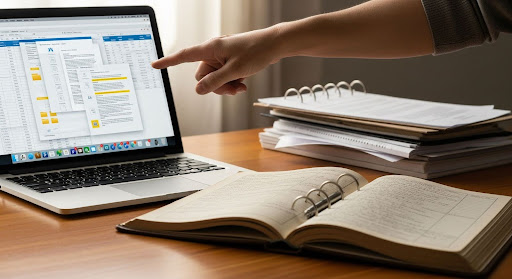
煩雑な紙の領収書のファイリングから解放され、経理業務を劇的に効率化したいと思いませんか。電子帳簿保存法は、単なる義務ではなく、ペーパーレス化によるコスト削減やテレワーク推進を実現する絶好の機会です。
この法律を正しく理解し活用すれば、あなたの会社はよりスマートで競争力のある組織へと進化できます。
この記事を最後まで読めば、あなたは電子帳簿保存法の全体像を正確に把握できます。紙で受け取った領収書の具体的な対処法から、義務化された電子取引データの保存ルール、万が一の罰則、そして導入コストを抑える補助金制度まで、実務に必要な知識を網羅的に習得している状態になります。
「法律は難しそう」と不安に感じる必要はありません。本記事では、専門用語を一つひとつ丁寧に解説し、図や表を多用して、誰にでもわかるように説明します。この記事で示すステップに従うだけで、あなたの会社も今日から迷うことなく、電子帳簿保存法への対応を始めることができます。
目次
電子帳簿保存法の3つの区分を理解する
電子帳簿保存法への対応を考えるとき、多くの事業者が混乱する最大の原因は、この法律を一つのルールだと誤解してしまうことにあります。実際には、法律は大きく3つの区分に分かれており、それぞれで対応の要否が異なります。この違いを理解することが、正しい対応への第一歩です。
法律の構造は、政府のデジタル化戦略を反映しています。まず、デジタルで生まれた情報が紙に出力されてデジタル上の追跡が途切れることを防ぐため、「電子取引データ保存」を義務化しました。これは、デジタル時代の情報管理の根幹をなす部分です。
一方で、すべての事業者に紙書類の完全な電子化を強制するのは現実的ではありません。そのため、紙を電子化する「スキャナ保存」は任意とし、その要件を年々緩和することで、各事業者が自社のペースでデジタル化を進めることを後押ししています。
この構造を理解すれば、自社が今すぐ、最優先で取り組むべきは「電子取引データ保存」への対応であることが明確になります。
電子帳簿等保存 (任意)
会計ソフトなどで最初から一貫して電子的に作成した帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)や決算関係書類を、データのまま保存することです。これは任意の対応であり、義務ではありません。
スキャナ保存 (任意)
取引先から紙で受け取った領収書や請求書、または自社で手書き作成した書類の控えなどを、スキャナーやスマートフォンで読み取って電子データとして保存することです。これも任意の対応です。
電子取引データ保存 (義務)
メール添付のPDFや、Webサイトからダウンロードした領収書など、電子的にやり取りした取引情報を、電子データのまま保存することです。これが2024年1月から完全義務化された、法人・個人事業主を問わず、ほぼすべての事業者が対応必須の項目です。
| 区分 | 対象書類 | 対応の要否 |
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作成した仕訳帳、総勘定元帳、決算書など | 任意 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った領収書、請求書、契約書など | 任意 |
| 電子取引データ保存 | メールで受け取ったPDF請求書、Webでダウンロードした領収書など | 義務 |
紙で受領した領収書の具体的な取り扱い方法
ここからが本題です。多くの経理担当者が頭を悩ませる「取引先から紙で受け取った領収書」の取り扱いについて解説します。2024年1月以降も、紙で受領した書類については、法律で認められた2つの選択肢があります。
この選択肢は、事業規模やリソースが異なる多様な事業者が、無理なく法対応を進められるようにという政府の現実的な配慮を反映したものです。すぐに完全なペーパーレス化が難しい企業には従来の道を残しつつ、デジタル化を選ぶ企業には業務効率化という明確なメリットを提示することで、緩やかに全体のデジタルシフトを促す狙いがあります。
選択肢1:紙のまま保存する
最もシンプルな方法は、これまで通り、受け取った紙の領収書を日付や取引先ごとに整理してファイリングし、法人であれば原則7年間保存することです。この方法を選択する場合、後述する電子帳簿保存法の「スキャナ保存」に関する複雑な要件を気にする必要はありません。
ただし、この方法には従来からのデメリットが伴います。
- 書類を保管するための物理的なスペースが必要になる。
- 紙の劣化や、火災・水害などによる紛失リスクがある。
- 過去の書類を探すのに時間がかかり、業務効率が上がらない。
選択肢2:スキャナ保存で電子化する
もう一つの道は、紙の原本をスキャナーやスマートフォンのカメラで読み取り、法律で定められた要件を満たす電子データとして保存する方法です。
この方法の最大のメリットは、法要件を正しく満たしてスキャンすれば、紙の原本を廃棄できる点です。これにより、保管スペースの問題から解放されるだけでなく、データの検索性が飛躍的に向上し、経理業務全体の効率化や、場所を選ばないテレワークの推進にも大きく貢献します。
ただし、これはあくまで任意の選択肢であり、すべての事業者に電子化が義務付けられているわけではありません。自社の状況に合わせて、紙のまま保存するか、スキャナ保存に挑戦するかを判断できます。
重要な注意点
ここで絶対に混同してはならないのは、この2つの選択肢は、あくまで「紙で受け取った書類」に限定された話であるという点です。メールの添付ファイルやWebサイトからのダウンロードなど、最初からデータとして受け取った領収書や請求書を紙に印刷して保存することは、2024年1月1日以降、原則として認められていません。
これらは「電子取引」に該当し、データのまま保存することが義務付けられています。
スキャナ保存による紙の領収書の電子化ガイド
「選択肢2:スキャナ保存」を選び、ペーパーレス化による業務改善を目指す事業者のために、その具体的な方法と要件を詳しく解説します。スキャナ保存は単なる義務対応ではなく、経営の効率化に向けた戦略的な一手と捉えることができます。
なぜスキャナ保存を選ぶのか?4つの大きなメリット
スキャナ保存を導入することで、企業は多くのメリットを享受できます。
ペーパーレス化による物理的スペースの削減
大量のファイルを保管していたキャビネットや倉庫スペースが不要になり、オフィスを有効活用できます。
業務効率の向上
「あの領収書はどこだっけ?」と探す時間がなくなります。データ化されていれば、取引先名や日付で瞬時に検索でき、経費精算や月次決算のプロセスが大幅にスピードアップします。
テレワーク・多様な働き方の推進
経理担当者が出社しなくても、自宅やサテライトオフィスから安全に領収書データにアクセスし、業務を遂行できます。これは、現代の働き方のニーズに応える上で非常に重要です。
BCP(事業継続計画)対策
紙の書類は、火災や地震、水害などの災害で失われるリスクがあります。データをクラウド上などにバックアップしておくことで、万が一の事態が発生しても重要な経営情報を守ることができます。
スキャナ保存の要件を徹底解説
スキャナ保存を正しく行うためには、国税庁が定める要件を満たす必要があります。要件は、書類の性質によって「重要書類」と「一般書類」の2つに区分されており、特に領収書などの重要書類には厳しい基準が設けられています。
| 要件項目 | 重要書類(領収書、契約書、請求書など) | 一般書類(見積書、注文書、検収書など) |
| 入力期間 | 以下のいずれかを選択 ・早期入力方式:受領後、速やか(約7営業日)以内 ・業務処理サイクル方式:最長2か月と約7営業日以内 | 制限なし(適時入力で可) |
| 解像度 | 200dpi相当以上 | 200dpi相当以上 |
| カラー/階調 | 24ビットカラー(フルカラー)が必須 | グレースケール(白黒)も可 |
| タイムスタンプ | 原則必要 (訂正削除履歴が残るシステム等を利用する場合は不要) | 原則必要 (訂正削除履歴が残るシステム等を利用する場合は不要) |
| 検索機能 | 「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索が必要 (緩和措置あり) | 「取引年月日」「取引金額」「取引先」での検索が必要 (緩和措置あり) |
| 帳簿との相互関連性 | 必要(仕訳と領収書データが紐づいていること) | 不要 |
入力期間の制限
重要書類である領収書は、受け取ってから入力するまでの期間に厳しい制限があります。
一つは「早期入力方式」で、書類を受領してから、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャンして保存する方法です。
もう一つは「業務処理サイクル方式」で、経費精算の締め日など、社内で定めた業務サイクル(最長2か月)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャンする方法です。この方式を採用するには、あらかじめ社内規程を定めておく必要があります。
入力期間を過ぎた書類はスキャナ保存が認められないため、紙のまま保存する必要があります。
解像度・階調
領収書などの重要書類は、解像度200dpi以上、かつ24ビットカラー(約1677万色を表現できるフルカラー)で読み取る必要があります。これは、書類の細部や色付きの印鑑などを正確に再現するためです。一方、見積書などの一般書類は、グレースケール(白黒)での保存も認められています。
タイムスタンプの付与
スキャンしたデータがその時刻に存在し、その後改ざんされていないことを証明するために、原則としてタイムスタンプの付与が必要です。しかし、この要件には重要な緩和措置があります。
データの訂正・削除の履歴が確認できるシステム、またはそもそも訂正・削除ができないシステムを利用して保存する場合、タイムスタンプは不要となります。現在市販されている多くの電子帳簿保存法対応システムは、この機能を有しています。
検索機能の確保
保存したデータは、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの項目で検索できる状態でなければなりません。ただし、これも緩和措置があります。税務調査の際に税務職員からのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、日付や金額の範囲指定検索などの要件は不要になります。
さらに、基準期間(法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下の事業者は、この検索要件のすべてが不要となります。
相互関連性の確保
重要書類にのみ求められる要件です。スキャンした領収書データと、会計帳簿の仕訳記録とが、相互に結びついている必要があります。例えば、会計ソフトの仕訳画面から、その証拠となる領収書の画像データをワンクリックで呼び出せるような状態を指します。
スマートフォンのカメラでも大丈夫?
結論から言うと、要件を満たせばスマートフォンのカメラで撮影した画像データも正式な証憑として認められます。
重要なのは、スキャナーと同様に解像度(200dpi以上)やカラー(24ビットカラー)といった画質の要件を満たすことです。近年のスマートフォンのカメラは非常に高性能なため、多くの場合、これらの要件はクリアできます。
ただし、撮影時には注意が必要です。手ブレや影が映り込んだり、斜めから撮影して画像が歪んだりしないよう、「真上から」「明るい場所で」撮影し、紙の書類と同程度に明瞭な画像を確保することが求められます。
多くの経費精算システムには、スマートフォンのカメラで綺麗に撮影するための補助機能(台形補正や影の除去など)が搭載されており、こうしたツールの活用が推奨されます。
全事業者が対象となる電子取引データの保存ルール
ここからは、法人・個人事業主を問わず、すべての事業者に義務として課せられている「電子取引データ保存」のルールについて解説します。紙の領収書の扱いとは異なり、こちらは任意ではなく必須の対応です。対応を怠ると罰則の対象となる可能性があるため、正確な理解が不可欠です。
「電子取引」とは何か?具体的なケース
電子取引とは、注文書、請求書、領収書といった取引に関する情報を、電子データでやり取りするすべての取引を指します。具体的には、以下のようなケースがすべて該当します。
メールでのやり取り (PDF形式の見積書や請求書をメールに添付して送受信する)
Webサイトからのダウンロード (AmazonなどのECサイトや、交通機関の予約サイトの購入履歴ページから領収書データをダウンロードする)
クラウドサービスの利用 (クラウド型の請求書発行サービスや経費精算サービスを通じて請求書や領収書を授受する)
その他 (EDI(電子データ交換)取引、ペーパーレスFAXで受信した文書、クレジットカードのWeb利用明細データなど)
重要なポイントは、取引先からデータで受け取った場合だけでなく、自社がデータで発行した場合の控えも、同様に電子データのまま保存する義務があるという点です。
守るべき2大要件「真実性の確保」と「可視性の確保」
電子取引データを保存する際には、国税庁が定める2つの大きな要件、「真実性の確保」と「可視性の確保」を満たす必要があります。
真実性の確保(データが改ざんされていないことの証明)
保存されたデータがオリジナルであり、後から改ざんされていないことを証明するための措置です。以下のいずれか1つの方法を選択して実施する必要があります。
タイムスタンプが付与されたデータを受領する。
データを受領した後、速やかに(または業務サイクル内に)自社でタイムスタンプを付与する。
データの訂正・削除の履歴が残るシステム、または訂正・削除ができないシステムを利用してデータを保存する。
データの訂正や削除を原則禁止し、やむを得ず行う場合の手順などを定めた「事務処理規程」を社内で作成し、それに沿って運用する。
可視性の確保(データをいつでも見られる状態にすること)
保存したデータを、税務調査などで求められた際に、いつでも明瞭な状態で確認・出力できるようにしておくための要件です。以下の3つをすべて満たす必要があります。
関連書類の備え付け: 保存場所にパソコン、ディスプレイ、プリンターと、利用しているシステムの操作説明書などを備え付ける。
見読可能性: 保存したデータを、ディスプレイの画面や紙に、整然とした形式で明瞭に、速やかに出力できるようにしておく。
検索機能の確保: スキャナ保存と同様に、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できる機能を確保する。(スキャナ保存と同様の緩和措置が適用されます)
システムを使わない場合の現実的な対応策
「高価なシステムを導入する予算がない」と悩む中小企業や個人事業主の方も多いでしょう。しかし、工夫次第でコストをかけずに法対応することは可能です。特に、小規模な事業者にとって最も現実的なのが、前述の「真実性の確保」の4番目の選択肢である事務処理規程の策定と、ファイル名の工夫を組み合わせる方法です。
この「事務処理規程」という選択肢は、高価なIT投資が難しい事業者にもコンプライアンスの道を開く、非常に重要な手段と言えます。法律が一方的に負担を強いるのではなく、手続き的なルールを守ることでも要件を満たせると示している点は、この法律の柔軟な側面です。この方法を正しく理解し実行すれば、コストをかけずに義務を果たすことができます。
ステップ1:事務処理規程の作成・備付け
国税庁のウェブサイトには、法人用、個人事業主用の「事務処理規程」のサンプルがWord形式で公開されています。これをダウンロードし、自社の状況に合わせて修正・追記して印刷し、社内に備え付けます。これだけで「真実性の確保」の要件の一つを満たしたことになります。
ステップ2:ファイル命名規則の策定と運用
検索機能を確保するため、保存する電子データのファイル名を統一ルールで変更します。例えば、「20250415_株式会社〇〇_110000.pdf」のように、「日付_取引先名_金額」といったルールを定めて運用します。
ステップ3:フォルダによる整理
「2025年」→「04月」→「株式会社〇〇」のように、年度別、月別、取引先別などでフォルダを分けてデータを保存し、整理します。
ステップ4:索引簿(Excelなど)の作成
ファイル名を変更するだけでは検索要件を完全に満たせない場合に備え、Excelなどで索引簿(インデックスファイル)を作成します。この一覧表に「取引年月日」「取引先名」「金額」「ファイル名」といった項目を記録しておけば、検索要件を確実に満たすことができます。
未対応の事業者向け「猶予措置」の正しい理解
「2024年1月から義務化されたと聞いたが、まだ何も準備できていない」と焦っている事業者の方もいるかもしれません。そのような事業者向けに、一定の条件下で要件が緩和される「猶予措置」が設けられています。ただし、この措置を正しく理解しないと、かえってリスクを高めることになりかねません。
まず、2023年12月31日で終了した「宥恕(ゆうじょ)措置」と、現在適用される「猶予(ゆうよ)措置」は全くの別物です。宥恕措置は、理由を問わず電子データを紙に出力して保存することが認められた時限的な特例でした。
一方、現在の猶予措置は、適用されるための条件が定められています。
これは、単なる先延ばしを許容するのではなく、対応できない「やむを得ない事情」がある事業者を救済しつつ、コンプライアンスへの移行を促すための、より柔軟かつ厳格なアプローチと言えます。したがって、事業者は「なぜ対応できないのか」という理由を、税務調査の際に説明する責任を負うことになります。
猶予措置とは?
電子取引データの保存要件(特に検索機能など)を満たせない「相当の理由」があると所轄の税務署長が認める場合に、それらの要件が免除される制度です。
「相当の理由」とは?
法律上、明確な定義はありませんが、国税庁は例として以下のようなケースを挙げています。
電子帳簿保存法に対応するためのシステム導入や社内ワークフローの整備が、間に合わない場合。
資金繰りの悪化や人手不足により、対応したくてもできない場合。
猶予措置を受けるための2つの条件
「相当の理由」があることに加え、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
税務調査の際に、保存している電子取引データのダウンロードの求めに応じられること。
税務調査の際に、電子取引データを紙に印刷した書面の提示・提出の求めに応じられること。
重要な注意点
猶予措置は、あくまで検索要件などが免除されるだけであり、電子取引データそのものを保存する義務がなくなるわけではありません。データ自体は必ずPCやサーバー上に保存しておく必要があります。
また、この措置を受けるための事前申請は不要です。しかし、税務調査の際には「相当の理由」を客観的に説明できるよう、システム選定に苦慮した際の記録や、資金繰りが厳しいことを示す資料などを準備しておくとよいでしょう。
猶予措置に期限は定められていませんが、いずれ廃止される可能性が高いと考えるべきです。この措置に頼り続けるのではなく、準備が整い次第、速やかに本来の要件を満たす体制を構築することが求められます。
電子帳簿保存法違反に関する罰則
電子帳簿保存法のルールに従わなかった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。この法律自体に直接的な罰則規定はありませんが、データの改ざんや保存義務の不履行などが発覚した場合、関連する他の法律に基づいて重い罰則が科される可能性があります。
| 罰則の種類 | 内容 | 根拠法 |
| 青色申告の承認取消 | 悪質な違反と判断された場合、最大65万円の特別控除などの税制優遇が受けられなくなる。 | 法人税法・所得税法 |
| 重加算税の加重 | データ改ざん等で申告漏れがあった場合、通常の重加算税35%にさらに10%が加算される。 | 国税通則法 |
| 過料 | 帳簿書類の保存義務違反として、100万円以下の過料(罰金)が科される可能性がある。 | 会社法 |
罰則1:青色申告の承認が取り消される可能性
電子データの保存義務を無視するなど、悪質な違反と税務署に判断された場合、税務上の大きなメリットである青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。承認が取り消されると、最大65万円の青色申告特別控除や、赤字の繰越控除といった優遇措置が受けられなくなり、結果として納税額が大幅に増加する可能性があります。
罰則2:重加算税が10%加重される
スキャナ保存や電子取引で保存したデータについて、意図的な改ざんや隠蔽といった不正行為が発覚し、それによって申告漏れが生じていた場合、ペナルティはさらに重くなります。通常の申告漏れに課される重加算税(追徴税額の35%)に、さらに10%が加重された、合計45%もの重加算税が課されることになります。
罰則3:会社法違反による過料
帳簿や取引に関する書類を適切に保存することは、会社法でも定められた義務です。電子帳簿保存法の要件を満たさずにデータを保存しなかった場合、この会社法の保存義務違反にも該当する可能性があり、その場合は100万円以下の過料(行政上の罰金)が科されることがあります。
これらの罰則は、コンプライアンス違反が企業の経営に直接的な打撃を与えることを示しています。リスクを正しく理解し、適切な対応をとることが重要です。
システム導入と補助金の活用による円滑な移行
ここまで法律の要件や罰則について解説してきましたが、最も確実かつ効率的に対応するためには、やはり専用のシステムを導入することが推奨されます。ここでは、システムの選び方と、導入コストを抑えるための補助金活用法について解説します。
対応システムの選び方と「JIIMA認証」の重要性
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトや経費精算システム、文書管理システムは数多く存在します。自社に合ったシステムを選ぶ際に、非常に重要な目印となるのが「JIIMA(ジーマ)認証」です。
JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が、そのソフトウェア製品が電子帳簿保存法の法的要件を満たしていることを客観的に認証する制度です。この認証ロゴが付いている製品を選べば、事業者が自ら複雑な法要件を一つひとつチェックする必要がなく、安心して導入することができます。
| サービス名 | 特徴 | JIIMA認証 | 価格帯(月額) |
| マネーフォワード クラウド会計 | AIによる自動仕訳学習機能が強力。他サービスとの連携も豊富。 | 〇 | 2,480円~ |
| freee会計 | 簿記の知識がなくても直感的に使えるUIが特徴。個人事業主から中小企業まで幅広く対応。 | 〇 | 980円~ |
| 弥生会計オンライン/Next | 老舗ならではの信頼感と安定性。スマート証憑管理で電帳法にしっかり対応。 | 〇 | 2,166円~ |
| 勘定奉行クラウド | 専門家(税理士等)とのデータ共有がスムーズ。証憑のAI-OCR読み取り機能も搭載。 | 〇 | 6,600円~ |
導入コストを抑える「IT導入補助金」活用ステップ
システムの導入にはコストがかかりますが、中小企業や小規模事業者は、経済産業省が推進する「IT導入補助金」を活用して、その費用の一部を補助してもらうことができます。
対象者
補助金の対象となるのは、業種ごとに定められた資本金や従業員数の要件を満たす中小企業・小規模事業者です。例えば、サービス業であれば「資本金5,000万円以下または常勤従業員100人以下」の企業が対象となります。
申請の主な流れ
補助金の申請は、事業者単独ではなく、国から認定された「IT導入支援事業者」(システムの販売代理店など)と協力して進める必要があります。
まず、様々な行政サービスにログインできる共通認証システム「GビズID」の「プライム」アカウントが必須です。発行に2週間程度かかることもあるため、早めに取得手続きを行いましょう。
次に、導入したいシステムを取り扱っているIT導入支援事業者を選定し、相談します。事業者は、ツールの選定から事業計画の策定、申請手続きまでをサポートしてくれます。最後に、IT導入支援事業者と共同で事業計画書などを作成し、オンラインで事務局に申請します。
注意点
最も重要な注意点は、補助金の交付が決定する前に、ITツールの契約や支払いを行ってはいけないという点です。必ず事務局から「交付決定」の通知を受け取った後に、発注・契約・支払いの手続きを進めてください。先に支払ってしまうと、補助金の対象外となってしまいます。
まとめ
最後に、電子帳簿保存法への対応について、重要なポイントを再確認します。
要点1:取引の種類で対応を分ける
「紙で受け取った書類」は紙のまま保存も可能であり、スキャナ保存は任意です。しかし、「電子データで受け取った書類」は電子データのまま保存することが絶対の義務です。この区別が最も重要です。
要点2:スキャナ保存は業務改善のチャンス
紙の領収書の電子化は義務ではありませんが、保管スペースの削減や業務効率化、テレワーク推進に直結します。要件を正しく理解し、自社の成長戦略として導入を検討する価値は十分にあります。
要点3:義務化への対応は待ったなし
電子取引データの保存は、すべての事業者の義務です。システムを使わない手作業での対応も可能ですが、ヒューマンエラーのリスクや管理の手間を考えると、長期的には対応システムの導入が最も確実で安全な道です。
要点4:罰則リスクを理解し、補助金を賢く活用する
コンプライアンス違反のリスクは決して小さくありません。IT導入補助金のような制度を賢く活用し、コストを抑えながら、将来にわたって安心できる確実な対応体制を構築しましょう。
電子帳簿保存法への対応は、単なるコストや手間のかかる義務ではありません。これは、自社の業務プロセスを根本から見直し、デジタル化を推進することで、より強く、より効率的な経営基盤を築くための重要な「投資」です。この変化の機会を前向きに捉え、ぜひ事業の成長へとつなげてください。








不動産売買の領収書テンプレートと正しい書き方|印紙税の判定か…
不動産売買における金銭トラブルを未然に防ぎ、税務署への申告をスムーズに進めるためには、正確な領収書の…