
下請代金が期日通りに支払われない、あるいは自社が気づかぬうちに下請法に違反していないか、といった不安を抱えていませんか。
下請法における支払いのルールは複雑に思えるかもしれませんが、その基本を理解しないまま取引を続けることには大きなリスクが伴います。もし支払いが遅延すれば、年率14.6%という重い遅延利息が発生する可能性があるのです。
これは単なる法律上の義務ではなく、会社の資金繰りに直接影響を与える重要な経営課題です。
この記事は、下請法の支払いルールに関する決定版ガイドです。この記事を読めば、法律の基本から具体的な支払いルールの適用方法、違反した場合のリスク、そして問題が発生した際の具体的な対処法まで、一貫して理解できます。
下請取引に関わるすべてのビジネスパーソンが、公正かつ合法的に取引を進めるための知識と自信を得られるようになります。
下請法は専門的で難しいと感じるかもしれません。しかし、このガイドでは法律の専門家ではないビジネスの実務担当者に向けて、複雑なルールをシンプルなステップと具体的な事例でわかりやすく解説します。
明日からすぐに実践できる知識を身につけ、安心して取引を進められるようになりましょう。
目次
そもそも下請法とは?自社が対象かまず確認
下請法の支払いルールを理解する前に、まず法律そのものの目的と、自社の取引がその対象となるのかを正確に把握することが不可欠です。
下請法の目的 なぜ支払ルールは厳しいのか
下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。その名の通り、この法律の根本的な目的は、取引における「公正さ」を確保することにあります。一般的に、発注者である親事業者と受注者である下請事業者との間には、交渉力に差が存在します。下請法は、この優越的な立場にある親事業者がその力を濫用することなく、立場の弱い下請事業者の利益を保護するために制定されました。
法律の目的が下請事業者の保護であるという点は、なぜ支払ルールがこれほど厳格に定められているのかを理解する上で重要です。もし法律による規制がなければ、親事業者が自社の都合で支払いを遅らせたり、不当な条件を押し付けたりすることで、下請事業者の資金繰りが悪化し、経営が立ち行かなくなる恐れがあります。
このような市場の失敗を防ぎ、中小企業の経営基盤を安定させ、ひいては日本経済全体の健全な発展に寄与することこそが、下請法が目指す姿なのです。60日以内の支払義務や年率14.6%という高い遅延利息は、この力関係の不均衡を是正し、公正な取引環境を強制的に作り出すための具体的な仕組みといえます。
親事業者と下請事業者の定義(資本金区分)
自社の取引が下請法の対象になるかどうかは、契約書の内容ではなく、取引当事者双方の資本金規模によって自動的に決まります。取引内容によって、適用される資本金の基準が異なるため注意が必要です。
物品の製造委託・修理委託の場合
- 親事業者の資本金が3億円超で、下請事業者の資本金が3億円以下
(個人事業主を含む) - 親事業者の資本金が1,000万円超3億円以下で、下請事業者の資本金が1,000万円以下(個人事業主を含む)
情報成果物作成委託・役務提供委託の場合
- 親事業者の資本金が5,000万円超で、下請事業者の資本金が5,000万円以下(個人事業主を含む)
- 親事業者の資本金が1,000万円超5,000万円以下で、下請事業者の資本金が1,000万円以下(個人事業主を含む)
これらの条件に一つでも当てはまれば、その取引は下請法の適用対象となります。たとえ契約書に下請法に関する記載がなくても、法律上の義務と禁止事項が強制的に適用されることを覚えておく必要があります。
対象となる4つの取引類型
下請法は、主に以下の4つの取引類型を対象としています。
製造委託
事業者が物品の仕様を指定して、他の事業者にその製造や加工を委託することです。例えば、自動車メーカーが部品メーカーに特定の部品の製造を依頼するケースがこれにあたります。
修理委託
事業者が物品の修理を他の事業者に委託することです。自社で請け負った修理業務を、別の修理業者に再委託する場合などが該当します。
情報成果物作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなど、情報成果物の作成を委託することです。例えば、企業がソフトウェア開発会社に業務システムの開発を委託したり、広告代理店がデザイナーに広告デザインの作成を依頼したりするケースが含まれます。
役務提供委託
運送、情報処理、ビルメンテナンスなど、サービスの提供を委託することです。運送会社が貨物輸送の一部を別の業者に委託する場合や、ビル管理会社が清掃業務を専門業者に委託する場合などがこれにあたります。
自社の事業がこれらの取引に該当し、かつ資本金区分を満たす場合は、下請法のルールを遵守しなければなりません。
下請法支払いの絶対原則「60日ルール」を徹底解説

下請法の支払いに関するルールの中で、最も重要かつ基本的な原則が「60日ルール」です。このルールを正確に理解することが、法令遵守の第一歩となります。
支払期日は「受領日」から60日以内
下請法は、親事業者が下請代金の支払期日を、物品やサービスの提供を受けた日(給付を受領した日)から起算して60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定めなければならないと規定しています。
ここで重要なのは、「出来る限り短い期間内」という文言です。これは、業界の慣行や他の下請事業者との取引条件に照らして、不当に長い支払期日を設定することを禁じる趣旨です。
例えば、通常30日サイトで取引しているにもかかわらず、特定の事業者に対してのみ正当な理由なく60日の支払期日を設定した場合、たとえ60日以内であっても問題視される可能性があります。
間違いやすい起算日の数え方(検収日や請求書発行日ではない)
60日ルールで最も誤解されやすいのが、起算日(カウントを開始する日)の考え方です。下請法では、60日のカウントは親事業者が物品を現実に受け取った日、またはサービスの提供が完了した日(受領日)から始まります。
親事業者の社内で行われる検収が終わった日(検収日)や、下請事業者から請求書が届いた日(請求書発行日)ではないという点が極めて重要です。
具体的な例で考えてみましょう。4月10日に下請事業者から商品が納品された場合、この日が受領日となります。親事業者の社内検査が5月15日に完了し、下請事業者から請求書が5月20日に届いたとしても、60日のカウントは4月10日から始まります。
法律上の数え方では、受領日当日を1日目として計算するため、支払期日は60日目にあたる6月8日までに設定し、その日までに支払いを完了させる必要があります。たとえ社内手続きが遅れたり、請求書の到着が遅れたりしても、支払いを遅らせる正当な理由にはなりません。
支払期日を定めていない場合はどうなる?
もし親事業者と下請事業者の間で支払期日を明確に定めていなかった場合、法律は「給付を受領した日」そのものが支払期日であるとみなします。つまり、納品されたその日のうちに支払わなければならないということになり、現実的には極めて厳しい条件となります。
また、もし60日を超える不当な支払期日を定めていた場合は、「給付を受領した日から60日を経過した日の前日」、つまり受領日から60日目が法的な支払期日とみなされます。このように、法律は親事業者が曖昧な定めや違法な定めによって利益を得ることを許さない仕組みになっています。
知らないと危険!60日ルールの例外ケース
下請法の60日ルールは厳格な原則ですが、実際の商取引の慣行に合わせるためのいくつかの例外が認められています。ただし、これらの例外は恣意的に利用できる抜け道ではなく、厳格な条件のもとで適用されるものです。例外規定の根底にも、下請事業者の利益を不当に害さないという大原則が流れています。
月単位の締日制度の扱い
多くの企業で採用されている「毎月末日締め、翌月末日払い」といった月単位の締日制度は、実務上広く認められています。しかし、この制度では、例えば5月1日に納品された物品の支払いが6月30日となり、受領日から60日を超えてしまうケースが発生します。
このような実務慣行を考慮し、締日制度を採用している場合には、支払期日の計算が「受領後60日以内」ではなく「受領後2か月以内」として運用されることが一般的です。ただし、これはあくまで実務上の運用であり、締日制度を理由に支払いが恒常的に60日を大幅に超えるような場合は、下請法違反と判断される可能性があるため注意が必要です。
支払日が金融機関の休業日だった場合の順延ルール
支払期日が土日祝日や年末年始など、金融機関の休業日にあたってしまう場合があります。この場合、支払いを翌営業日に順延することが考えられますが、それには明確なルールが存在します。親事業者が一方的に順延することは違反となります。
順延が認められるためには、あらかじめ下請事業者との間で書面による合意があることが大前提です。その上で、順延後の支払日が「受領日から60日を超える」場合、順延できる期間は最大でも2日間に限られます。例えば、支払期日が土曜日にあたり、翌営業日の月曜日に支払う場合などが該当します。
一方で、順延後の支払日が「受領日から60日以内」に収まるのであれば、ゴールデンウィークや年末年始などで金融機関の休業が続く場合でも、2日を超えて順延することが可能です。ただし、この場合も書面での事前合意が必須です。
やり直し(再納品)が発生した場合の起算日
納品された物品に瑕疵があり、その原因が下請事業者の責任である場合、親事業者はやり直しを求めることができます。この場合、60日ルールの起算日はリセットされ、やり直しを終えた物品が改めて納品された日(再受領日)から新たにカウントが始まります。
しかし、注意すべきは、やり直しの理由が親事業者側の都合(例えば、発注後の仕様変更など)である場合です。これは下請法で禁止されている「不当なやり直し」にあたる可能性があり、この場合は当初の支払期日を変更することはできません。あくまで下請事業者に責任がある場合にのみ、起算日のリセットが認められます。
これだけは押さえたい!親事業者の4つの義務と11の禁止事項
下請法は、公正な取引を実現するために、親事業者に対して4つの基本的な義務と、優越的な地位の濫用にあたる11の行為を具体的に禁止しています。
親事業者が必ず守るべき4つの義務
これら4つの義務は、下請取引の根幹をなすものであり、公正な取引の土台となります。
書面の交付義務
親事業者は発注に際し、直ちに給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法などを明記した書面(発注書)を下請事業者に交付しなければなりません。口頭での発注はトラブルの原因となるため、法律は書面による契約内容の明確化を義務付けています。
支払期日を定める義務
前述の「60日ルール」です。給付の受領日から60日以内で、できるだけ短い期間内に支払期日を定めなければなりません。
書類の作成・保存義務
親事業者は、下請取引に関する記録(給付の内容、受領日、支払った代金の額など)を記載した書類を作成し、2年間保存する義務があります。これは、万が一トラブルが発生した際に、取引の事実関係を客観的に証明できるようにするためです。
遅延利息の支払義務
定めた支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、親事業者は下請事業者に対し、遅延利息を支払わなければなりません。利率は年率14.6%と定められています。
これら4つの義務のうち3つが書面や記録に関するものであることは、下請法が「言った、言わない」といった曖昧な状況を排除し、文書による透明性と説明責任をいかに重視しているかを示しています。法律は、記録に残らない非公式な合意が、立場の強い側に有利に働きやすいことを前提としています。
そのため、発注から支払いまでのプロセスを徹底的に文書化させることで、違反行為の立証を容易にし、紛争解決の道筋を明確にしているのです。この手続き上の厳格さは、支払ルールそのものと同じくらい重要な法律の要素です。
特に注意すべき支払い関連の禁止事項
親事業者が優越的な地位を濫用することを防ぐため、下請法は11項目の具体的な行為を禁止しています。ここでは、特に支払いに直接関連する代表的な禁止事項を取り上げます。
下請代金の支払遅延
定められた支払期日までに代金を支払わない、最も基本的な違反行為です。
下請代金の減額
下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決めた代金から減額する行為です。「協力金」の名目で一方的に差し引いたり、事前の合意なく振込手数料を下請事業者に負担させたりする行為も該当します。
買いたたき
市場価格や類似品の対価に比べて、著しく低い代金を不当に定める行為です。原材料価格が高騰しているにもかかわらず、一方的に単価を据え置くといった行為も「買いたたき」とみなされることがあります。
割引困難な手形の交付
換金が難しい手形で支払うことです。これについては次の項目で詳しく解説します。
以下の表は、親事業者に禁止されている11の行為をまとめたものです。自社の取引に当てはまるものがないか、確認してみてください。
| 禁止事項 | 概要 | 具体例 |
| 1. 受領拒否 | 理由なく納品を拒否する | 発注元の都合で仕様変更になったからと、完成品を受け取らない |
| 2. 下請代金の支払遅延 | 期日までに代金を支払わない | 社内検査が終わらないという理由で60日を超えて支払う |
| 3. 下請代金の減額 | 理由なく代金を値切る | 振込手数料を一方的に差し引いて支払う |
| 4. 不当返品 | 理由なく受領した物品を返す | シーズン終了後に売れ残った商品を返品する |
| 5. 買いたたき | 通常より著しく低い価格を強要する | 原材料が高騰しているのに、一方的に単価を据え置く |
| 6. 購入・利用強制 | 指定の物やサービスを強制的に買わせる | 仕事を発注する代わりに自社の保険に加入させる |
| 7. 報復措置 | 公取委への通報を理由に不利益な扱いをする | 通報したことを理由に取引を停止する |
| 8. 有償支給原材料等の対価の早期決済 | 有償支給材料の代金を不当に早く決済する | 材料の代金を、製品の代金支払日より早く相殺する |
| 9. 割引困難な手形の交付 | 換金しにくい手形で支払う | サイトが60日を超える手形を交付する |
| 10. 不当な経済上の利益の提供要請 | 協賛金などを不当に要求する | 決算対策として協賛金を要求する |
| 11. 不当な給付内容の変更・やり直し | 費用を負担させ、不当に変更ややり直しをさせる | 親事業者の都合での仕様変更費用を下請に負担させる |
2024年11月から厳格化!手形サイトも60日以内に
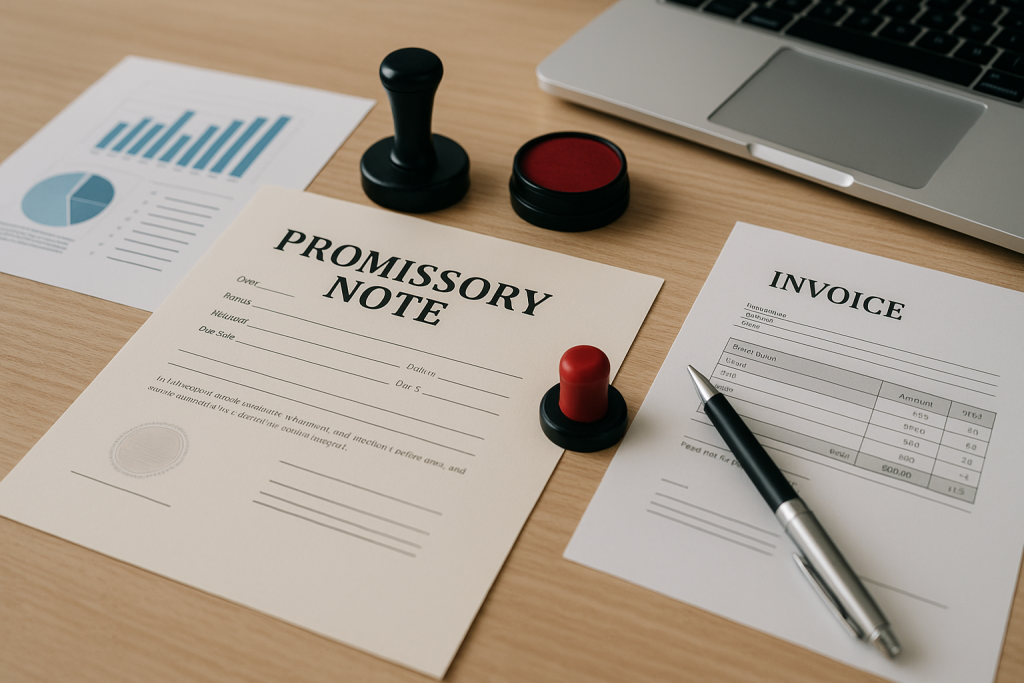
下請代金の支払い方法に関して、近年大きな変更がありました。それは、約束手形などによる支払いに関するルールの厳格化です。
従来、繊維業では90日、その他の業種では120日を超える長期の手形サイト(手形の振出日から満期日までの期間)が「割引困難な手形」として問題視されていました。しかし、2024年11月1日以降、この運用が変更され、業種を問わずサイトが60日を超える手形等は、下請法違反のおそれがあるとして行政指導の対象となります。
このルール変更は、単なる下請法の運用見直しにとどまりません。これは、長年にわたり中小企業の資金繰りを圧迫してきた手形取引という商慣習そのものを見直し、サプライチェーン全体の金融健全性を高めようとする、より大きな経済政策の一環です。
手形払いは、下請事業者に割引手数料という金融コストや、親事業者の倒産リスクを負わせる側面がありました。政府は現金による支払いを強く推奨しており、2026年度末をめどとした紙の約束手形の廃止も視野に入れています。今回の60日ルール厳格化は、その大きな流れの中の重要な一歩と位置づけられます。
もし下請法違反が起きたら?ペナルティと対処法
下請法に違反した場合、親事業者には金銭的な負担だけでなく、社会的な信用の失墜につながる厳しい措置が待っています。
公正取引委員会による調査・指導・勧告
下請法の運用は、公正取引委員会と中小企業庁が連携して行っています。これらの行政機関は、定期的な書面調査や、下請事業者からの申告に基づいて調査を実施します。
調査の結果、違反行為が認められた場合、まずは改善を促す「指導」が行われます。しかし、違反が悪質であったり、下請事業者が被る不利益が大きいと判断されたりした場合には、より重い行政処分である「勧告」が出されます。勧告には、違反行為の即時停止、減額した代金の返還、再発防止策の策定などが含まれます。
違反すると企業名が公表されるリスク
公正取引委員会から「勧告」を受けることの最大のリスクは、企業名と違反事実の概要が公に発表される点にあります。これは企業のブランドイメージや社会的信用を大きく損なうことにつながり、株価の下落や取引先からの信用不安など、事業活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。金銭的なペナルティ以上に、このレピュテーションリスクを経営者は重く受け止める必要があります。
年率14.6%の重い遅延利息
支払遅延が発生した場合、親事業者は下請事業者に対し、年率14.6%の遅延利息を支払う義務があります。この利息は、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から、実際に支払いが行われた日までの日数に応じて計算されます。
重要なのは、この利率が「強行法規」であるという点です。これは、たとえ当事者間の契約でこれより低い遅延損害金利率を定めていたとしても、その合意は無効となり、法律で定められた年率14.6%が強制的に適用されることを意味します。
親事業者が違反を自発的に申し出た場合の扱い
もし親事業者が社内調査などで自社の違反行為に気づいた場合、「自発的申出」という制度を利用することができます。これは、行政機関による調査が開始される前に、親事業者が自ら違反の事実を申告し、下請事業者に与えた不利益を回復する措置を講じた場合に、公正取引委員会が勧告を行わない(つまり企業名の公表をしない)という運用です。
この制度は、違反に対する厳しい罰則と、自浄作用を促す柔軟な対応を組み合わせた、実用的な仕組みです。企業にとっては、過ちを犯してしまった場合に、迅速かつ誠実に対応することで、レピュテーションへのダメージを最小限に抑えるための重要な選択肢となります。
この制度の存在は、親事業者が日頃からコンプライアンス体制を整備し、定期的に自己点検を行う強い動機付けとなるでしょう。
下請法に関する相談窓口
下請取引に関するトラブルや疑問が生じた場合、一人で抱え込まずに専門の窓口に相談することが重要です。国は、事業者が安心して相談できる窓口を複数設けています。
| 相談窓口 | 電話番号 | 特徴 |
| 公正取引委員会 不当なしわ寄せ相談 | 0120-060-110 (フリーダイヤル) | フリーダイヤル。匿名での相談が可能。下請事業者が主な対象 |
| 公正取引委員会・中小企業庁 各地方事務所 | 地域ごとに異なる | 親事業者・下請事業者双方からの相談に対応。具体的な法律の考え方など |
| 下請かけこみ寺 | 0120-418-618 (フリーダイヤル) | 中小企業庁の委託事業。弁護士など専門家による無料相談、ADR(裁判外紛争解決手続)も |
公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口
公正取引委員会は、全国各地に相談窓口を設置しています。フリーダイヤル(0120-060-110)にかけると、最寄りの窓口につながります。
下請事業者にとって最も大きな懸念は、相談したことが親事業者に知られ、報復措置として取引を打ち切られることかもしれません。この点について、公正取引委員会は相談者の情報が特定されないよう、秘密を厳守することを徹底しています。安心して相談することが可能です。また、匿名での情報提供を受け付ける専用フォームも用意されています。
下請かけこみ寺とは?
「下請かけこみ寺」は、中小企業庁の委託を受けて全国中小企業振興機関協会が運営する相談窓口です。ここでもフリーダイヤルで気軽に相談できるほか、企業間の取引問題に詳しい弁護士などの専門家による無料相談や、裁判をせずに紛争解決を目指す「裁判外紛争解決手続(ADR)」のあっせんも行っています。より具体的な解決策を求める場合に非常に有用な窓口です。
相談前に準備しておくと良いこと
相談をよりスムーズかつ効果的に進めるために、事前に以下のような資料を整理しておくと良いでしょう。
- 発注書、契約書
- 納品書、受領書、請求書
- 取引相手とのメールや議事録など、やり取りの記録
- 問題となっている取引の経緯を時系列でまとめたメモ
これらの客観的な資料があることで、相談員が状況を正確に把握し、より的確なアドバイスを提供しやすくなります。
まとめ
最後に、この記事の要点を再確認します。
下請法は、立場の弱い下請事業者を保護し、公正な取引関係を築くための法律です。支払いは「受領日」から60日以内に行うのが絶対原則であり、起算日は検収日や請求書発行日ではありません。違反した場合、年率14.6%の遅延利息や企業名の公表といった厳しいペナルティが科せられます。
親事業者も下請事業者も、自社の権利と義務を正しく理解し、遵守することが求められます。取引で困ったことがあれば、公正取引委員会や下請かけこみ寺など、無料で利用できる匿名の相談窓口があります。
下請法の遵守は、単に法律違反のリスクを回避するための消極的な対応ではありません。公正な支払いを徹底することは、下請事業者との信頼関係を深め、サプライチェーン全体の安定と競争力強化につながる積極的な経営戦略です。信頼に基づいた長期的なパートナーシップこそが、持続的な事業成長の礎となるのです。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…