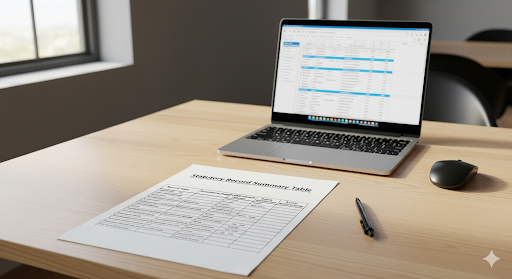
年末調整という大きな業務を終えた後、最後に待ち受けるのが「法定調書合計表」の作成と提出です。この手続きを正確かつスムーズに完了させることは、一年間の経理・労務業務を締めくくるための重要なステップとなります。
この書類を適切に提出することで、法令を遵守し、税務署との信頼関係を維持することができます。
しかし、いざ書類を前にすると、どの項目に何を書けばいいのか、この金額は含めるべきか、そもそもなぜこの書類が必要なのか、といった疑問や不安が次々と湧いてくるのではないでしょうか。
特に初めて担当する方や、年に一度しか触れない業務だからこそ、その複雑な様式や専門用語に戸惑いを感じるのは当然のことです。一つの記載ミスが、後々の問い合わせや修正手続きにつながるかもしれないというプレッシャーは、決して小さくありません。
この記事は、まさにそのような悩みを持つビジネスパーソンのために作成されました。専門家でなくても理解できるよう、法定調書合計表の各項目を一つひとつ分解し、具体的な書き方を丁寧に解説します。
この記事を最後まで読めば、単に空欄を埋めるだけでなく、それぞれの項目が持つ意味を理解し、自信を持って書類を完成させることができるようになります。面倒でストレスの多い義務作業を、管理された確実なプロセスへと変えていきましょう。
目次
法定調書合計表とは?まずは基本を3分でおさらい
詳細な書き方に入る前に、法定調書合計表がどのような書類なのか、その役割と基本を理解しておくことが重要です。この点を把握するだけで、全体の作業が格段にスムーズになります。
法定調書合計表の役割は「法定調書の表紙」
法定調書合計表の正式名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」といいます。この長い名前が示す通り、この書類は単体で完結するものではありません。会社が一年間に支払った給与や報酬に関する各種の「法定調書」(例えば、従業員一人ひとりの源泉徴収票など)を税務署に提出する際に、それら全体の内容を要約する「表紙」や「総括表」のような役割を果たします。
税務署は、この合計表を見ることで、その会社が年間で「何人に」「総額いくら」の給与や報酬を支払い、「総額いくら」の税金を源泉徴収したのかを一目で把握できます。個別の法定調書を確認する前に、まずこの合計表で全体像を掴むのです。
そのため、合計表に記載された金額や人数は、添付する個別の法定調書の内容と完全に一致している必要があります。この書類は、税務当局が企業の支払い実態を効率的に把握するための、きわめて重要なデータ集約ツールなのです。
集計対象となる6種類の法定調書
法定調書合計表で集計するのは、所得税法などによって税務署への提出が義務付けられている、以下の6種類の法定調書です。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
多くの中小企業や個人事業主の場合、主に関係するのは最初の3種類、特に「給与所得の源泉徴収票」と「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。自社がどの支払いを行っていたかを確認し、該当する法定調書を準備します。
提出義務者と提出期限
この書類に関する基本情報を正確に押さえておきましょう。
提出義務者は、給与や報酬などの支払いを行った事業者(法人または個人事業主)です。
提出期限は、支払いが確定した年の翌年1月31日までです。この日付は厳守する必要があります。例えば、2024年(令和6年)中の支払いに関する書類は、2025年(令和7年)1月31日が提出期限となります。
提出先は、事業所の所在地を管轄する税務署長宛に提出します。もし年の途中で事業所を移転した場合は、移転後の新しい所在地を管轄する税務署に提出してください。また、一部の税務署では郵送先が「業務センター」に指定されている場合があるため、事前に国税庁のウェブサイトで確認すると確実です。
【項目別】法定調書合計表の書き方を徹底解説
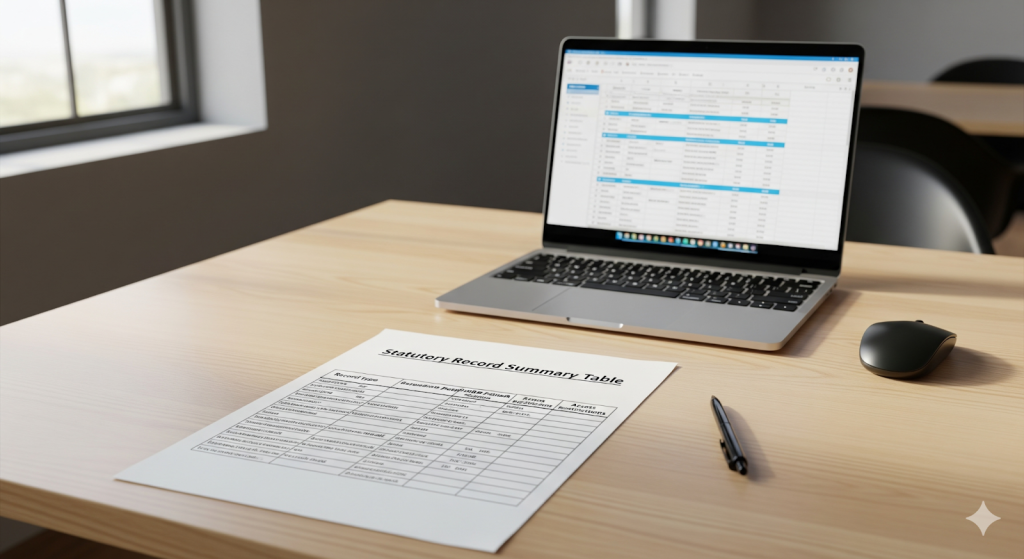
ここからは、実際の書類に沿って、各項目の具体的な書き方をステップバイステップで解説します。一つひとつの意味を理解しながら進めれば、間違うことはありません。
準備編:作成前に手元に揃えるべき書類
作業を始める前に、必要な書類をすべて手元に揃えましょう。途中で書類を探す手間が省け、ミスを防ぐことにもつながります。
- 全従業員分の作成済み源泉徴収票(年の途中での退職者も含む)
- 弁護士や税理士、フリーランスなどへの支払いがある場合の支払調書
- 自社の基本情報
(法人の場合は正式名称、本店所在地、法人番号。個人事業主の場合は氏名、住所、マイナンバー)
「提出者」情報の正確な記入方法
まず、書類の左側にある「提出者」欄を記入します。ここは自社の基本情報を記載する部分です。
整理番号は、税務署から通知されている場合に記入します。不明な場合は空欄で問題ありません。提出媒体は、書面で提出する場合は「30」、e-Taxで提出する場合は「14」など、提出方法に応じたコードを記入します。
住所(又は所在地)は、個人事業主で自宅を事務所としている場合は自宅の住所、事業所を構えている場合はその所在地を記入します。氏名(又は名称)には、法人名または個人事業主の氏名を記入してください。連絡の取れる電話番号も忘れずに記載します。
個人番号又は法人番号の欄には、法人は13桁の法人番号を、個人事業主は12桁のマイナンバーを正確に記入します。ここは提出義務のある重要な項目です。
作成担当者は、この書類を作成した担当者の氏名を記入します。税理士に作成を依頼した場合は、その税理士が署名し、税理士番号を記載する必要があります。なお、2021年4月以降、税務関係書類への押印は原則不要となったため、押印欄はありません。
調書の提出区分は、通常の提出であれば「1(新規提出)」を記入します。提出後に内容を追加する場合は「2(追加提出)」、訂正する場合は「3(訂正提出)」、取り消す場合は「4(無効)」を選択します。ほとんどの場合は「1」になりますが、後のトラブルシューティングで重要になるため、他の区分の存在も覚えておきましょう。
法人番号とマイナンバーの記載ルール
提出者が法人の場合は法人番号、個人事業主の場合はマイナンバーの記載が義務付けられています。税務署へ提出する書類には必ず記載が必要な情報ですので、間違いのないように転記してください。
「1. 給与所得の源泉徴収票合計表」の書き方
このセクションは、従業員へ支払った給与や賞与の合計を記入する、最も重要な部分の一つです。特にA欄とB欄の違いを正確に理解することがポイントです。
A欄「俸給、給与、賞与等の総額」のポイント
A欄には、その年に給与の支払いをしたすべての従業員の合計を記入します。個別の源泉徴収票を税務署に提出する必要があるかどうかは、この時点では関係ありません。
人員の欄には、1年間に給与を支払った実人数を記入します。年の途中で退職した人も必ず含めてください。この人数は、会社が作成した源泉徴収票の総枚数と一致するのが基本です。支払金額には自社がその年に支払った給与・賞与の総額を、源泉徴収税額には自社が源泉徴収した所得税の総額を記入します。
ここで最も注意すべきは、中途入社した社員の扱いです。年末調整の際には前職分の給与も合算して税額を計算しますが、この合計表のA欄に記入する「支払金額」には、自社が支払った金額のみを記載し、前職の給与額は含めません。これは非常によくある間違いなので、特に注意してください。
B欄「源泉徴収票を提出するもの」の判断基準
B欄には、A欄に含めた従業員のうち、個別の「給与所得の源泉徴収票」を税務署へ添付して提出しなければならない人だけの合計を記入します。
つまり、A欄が全従業員の「総集計」であるのに対し、B欄は税務署が特に内容を確認したい特定の従業員の「抜粋集計」という関係です。この二段階の考え方をすることで、混乱を防ぐことができます。まずA欄で全員の合計を出し、次にその中からB欄に該当する人を選び出して集計する、という手順で進めましょう。
どのような人がB欄の対象になるのでしょうか。提出範囲は役職や年収、年末調整の有無によって細かく定められています。以下の基準で自社の従業員が該当するかどうかを確認してください。
年末調整をした人
- 法人の役員: 年間の支払金額が150万円を超える
- 弁護士、税理士等への給与: 年間の支払金額が250万円を超える
- 上記以外の一般従業員: 年間の支払金額が500万円を超える
年末調整をしなかった人
- 年の途中で退職した人: 年間の支払金額が250万円を超える(ただし法人の役員は50万円超)
- 主たる給与が2,000万円を超える人: 全員
- 乙欄・丙欄適用者: 年間の支払金額が50万円を超える
この基準に該当する従業員の人数、支払金額、源泉徴収税額の合計をB欄に記入します。
「2. 退職所得の源泉徴収票合計表」の書き方
このセクションは、退職金を支払った場合に記入します。
A欄「退職手当等の総額」には、その年に退職金を支払ったすべての人員、支払総額、源泉徴収税額を記入します。
B欄「Aのうち、源泉徴収票を提出するもの」には、税務署へ個別の「退職所得の源泉徴収票」を提出する必要がある対象者のみを集計します。提出が必要なのは、原則として法人の役員に対して支払った退職金のみです。一般従業員への退職金はA欄には含めますが、B欄の集計対象にはなりません。
「3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の書き方
このセクションは、外部の専門家やフリーランスなどに支払った報酬をまとめます。
「個人」と「個人以外」の区別
「人員」の欄が「個人」と「個人以外」に分かれているのが特徴です。「個人」にはフリーランスや個人事業主の人数を、「個人以外」には税理士法人やデザイン会社といった法人への支払先数を記入します。支払金額や源泉徴収税額は、この区別なく合計額を記入します。
支払調書の提出が必要なケースとは?
給与所得と同様に、このセクションも上段がすべての支払いの合計、下段のB欄(Aのうち、支払調書を提出するもの)が税務署へ個別の支払調書を提出する必要があるものの合計となります。提出が必要となる金額の基準は、報酬の種類によって異なります。主な基準は以下の通りです。
- 年間5万円を超える支払: 弁護士、税理士、作家、講演者などへの報酬・料金
- 年間50万円を超える支払: 外交員、モデル、ホステスなどへの報酬・料金、広告宣伝のための賞金
これらの基準に該当する支払先について、個別の支払調書を作成・添付し、その合計をB欄に記入します。
不動産関連の支払調書合計表(4, 5, 6)の書き方
これらのセクションは、不動産に関する特定の取引があった場合にのみ記入します。
「4. 不動産の使用料等の支払調書合計表」は、オフィスの賃料や権利金などを同一の相手に年間15万円を超えて支払った場合に記載します。
「5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表」は、不動産などを購入し、同一の相手に年間100万円を超える対価を支払った場合に記載します。
「6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表」は、不動産の仲介手数料などを同一の相手に年間15万円を超えて支払った場合に記載します。これらの取引がなければ、すべて空欄のままで問題ありません。
これで安心!提出方法とトラブルシューティング
書類が完成したら、あとは提出するだけです。ここでは提出方法の選択肢と、万が一のトラブルに備えた対処法を解説します。
提出方法の選択肢:窓口、郵送、そしてe-Tax
提出方法は、事業者の状況に合わせて選ぶことができます。
一つ目は、税務署の窓口へ直接持参する方法です。控えに受付印をもらえるというメリットがあります。二つ目は、管轄の税務署(または業務センター)へ郵送する方法です。控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封します。
三つ目は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する方法です。インターネット経由で電子申告するため、時間や場所を選ばずに提出でき、受付通知もデータで残るため便利です。四つ目として、データを記録した光ディスク等(CD、DVDなど)を税務署に提出する方法もありますが、事前に税務署の承認が必要となります。
近年、e-Taxの利用は単なる提出方法の選択肢にとどまらなくなっています。e-Taxで源泉徴収票のデータを提出すると、その内容がマイナポータルを通じて従業員本人の確定申告書作成時に自動入力されるようになります。これは従業員にとって大きなメリットとなり、企業のデジタル化推進の一環としても価値があります。まだ導入していない場合でも、将来的な効率化と従業員満足度の向上のために、e-Taxへの移行を検討する価値は高いでしょう。
e-Tax(電子申告)が義務になるケース
特定の条件下では、e-Taxまたは光ディスク等による電子提出が義務となります。その基準は、「提出する年の前々年に発行した法定調書の種類ごとの枚数が100枚以上であった場合」です。
例えば、2025年1月に2024年分の法定調書を提出する場合、2022年(前々年)に発行した「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上であれば、今回の提出は電子的に行う必要があります。
よくある質問(FAQ)

最後に、担当者が抱えがちな疑問や不安について、Q&A形式で回答します。
Q1. 提出が期限に遅れたらどうなりますか?
提出期限である1月31日を過ぎてしまっても、所得税の納付遅れのように直ちに延滞税などのペナルティが課されるわけではありません。
しかし、だからといって提出しなくて良いわけではありません。法定調書の不提出や、意図的に虚偽の内容を記載して提出した場合には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い罰則が所得税法で定められています。
税務署が重視しているのは、期限厳守以上に、正確なデータが提出されることです。もし期限に間に合いそうにない場合でも、慌てて不正確な書類を提出するのは避けるべきです。期限を多少過ぎてしまっても、内容を完璧に確認し、正確な書類を一日でも早く提出することが重要です。遅れたとしても誠実に対応する姿勢が求められます。
Q2. 提出後に間違いに気づいた場合の訂正方法は?
提出後に誤りを発見した場合は、訂正手続きを行います。書面で提出した場合、まず正しい内容で法定調書と合計表を作成し直します。この新しい合計表の「調書の提出区分」欄には「3(訂正)」と記入します。
次に、最初に提出した誤りのある法定調書のコピーを用意し、その右上余白に「無効」と赤字で記載します。この「無効」分に対応する合計表も作成し、提出区分を「4(無効)」とします。そして、「訂正分」と「無効分」の書類一式を税務署に再提出します。訂正する書類には、間違っていた箇所のみを記載すればよく、すべての項目を書き直す必要はありません。
また、従業員に交付した源泉徴収票の内容が間違っていた場合は、正しいものを作成し直し、「再交付」と明記して本人に改めて渡す必要があります。
Q3. 従業員からマイナンバーの提供を拒否されたらどうなりますか?
これは実務上、非常に悩ましい問題です。法律上、事業者は従業員にマイナンバーの提供を求める義務があります。しかし、従業員が提供を拒否した場合、それを強制することはできません。
このような場合、マイナンバー欄を空欄のまま書類を提出しても、事業者が罰せられることはありません。ただし、その際には「事業者はマイナンバーの提供を適切に依頼した」という事実が重要になります。
万が一、税務署から問い合わせがあった場合に備え、いつ、どのように提供を依頼したかという経緯を記録として残しておくことを強く推奨します。例えば、採用時に書面で依頼した記録や、その後改めて依頼した日付などを従業員ファイルにメモしておくだけでも、事業者が義務を果たそうとした証拠になります。この記録があれば、責任の所在は事業者側にはないと示すことができます。
Q4. 作成した書類は何年保管すればよいですか?
法定調書合計表や、源泉徴収票などの年末調整関連書類は、法律により7年間の保管が義務付けられています。
この7年間という期間は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から起算します。例えば、2024年分の書類(提出期限2025年1月31日)であれば、2032年末まで保管する必要があります。退職した従業員の書類も同様に保管義務があるため、誤って破棄しないように注意してください。
まとめ
最後に、法定調書合計表を正確に作成するための最も重要なポイントを再確認しましょう。
- 書類の役割が「表紙」であることを理解する
- 提出期限である1月31日を厳守する
- 内容の正確性を最優先する
- 提出範囲の基準を正しく理解する
- 対応プロセスを記録に残す
- e-Taxの活用を積極的に検討する
この記事が、あなたの年末調整後の業務を少しでも楽にし、自信を持って手続きを完了させるための一助となれば幸いです。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…