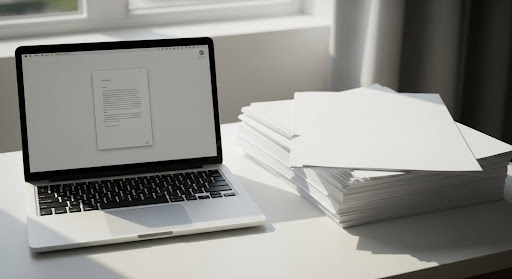
「できることなら、余計なコストや手間はかけたくない」。多くの中小企業経営者や個人事業主の方が、電子帳簿保存法(以下、電帳法)に対してこのように感じているかもしれません。しかし、その「様子見」が、今や大きな経営リスクになりつつあります。
2024年1月1日から、メールで受け取った請求書やインターネットで購入した際の領収書データといった「電子取引」で生じた国税関係書類を、電子データのまま保存することが、すべての事業者に対して法律上の義務となりました。
これは、企業の規模や業種、個人事業主であるか否かを問わない、統一されたルールです。
この記事では、電帳法に対応しない場合に具体的にどのような罰則や事業上の不利益が生じるのかを、専門家の視点から徹底的に解説します。さらに、万が一対応が間に合わない場合の「猶予措置」の正しい使い方から、今からでも間に合う具体的な対応ステップまで、網羅的にご紹介します。
この記事を最後まで読めば、漠然とした不安が解消され、自社が取るべき明確な行動計画を立てられるようになるでしょう。この義務化を単なる負担と捉えず、業務効率化とガバナンス強化の好機と変えるための第一歩を踏み出しましょう。
目次
電子帳簿保存法を導入しない場合の3大罰則
電帳法の要件を満たさない場合、単に税務調査で指摘を受けるだけでは済みません。事業の根幹を揺るがしかねない、具体的な3つの罰則が待ち受けています。
これらの罰則は独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。ひとつの法令違反が、税法だけでなく会社法上のペナルティにも発展する可能性があるのです。
特に、電子データの改ざんといった不正行為に対しては、意図的に重い罰則が設けられており、これは国がデジタル時代の不正に対して厳しい姿勢で臨んでいることの表れといえます。
最も影響が大きい「青色申告の承認取消」とその判断基準
電帳法に違反した場合に最も深刻な影響を及ぼすのが、青色申告の承認取消です。青色申告は多くの事業者にとって節税の柱であり、その承認が取り消されると、経営に直接的な打撃を与えます。
具体的には、最大65万円の青色申告特別控除や、純損失(赤字)の繰越控除、30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる少額減価償却資産の特例など、様々な税務上の優遇措置がすべて受けられなくなります。
これらの優遇措置を失うことは、納税額の増加に直結します。さらに、金融機関や取引先からの信用も低下し、融資や取引の継続に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
では、どのような場合に承認が取り消されるのでしょうか。重要なのは、電子取引データを一部、電子保存しなかったからといって、直ちに承認が取り消されるわけではないという点です。取引の事実が紙の請求書などで正確に確認でき、他に悪質な問題がなければ、いきなり最も重い処分が下される可能性は低いとされています。
しかし、税務調査の際に正当な理由なく帳簿書類の提示を再三にわたり拒否した場合や、意図的に所得を隠蔽・仮装するなど不正行為が発覚した場合には、承認取消のリスクが現実のものとなります。帳簿の記録が著しく不十分な場合や、法人で2期連続して期限内に申告書を提出しなかった場合も同様です。
ここで注意すべきは、税務調査の現場における力学です。法令違反が発覚した場合、調査官は青色申告の承認取消という重い処分を交渉材料として用いる可能性があります。実際に承認が取り消されずとも、法令違反を理由に他の指摘事項で不利な判断を受け入れざるを得ない状況に追い込まれるリスクがあるのです。
悪質な場合は税金が加重される「追徴課税・重加算税」
税務調査で意図的な隠蔽や仮装といった不正行為が発覚した場合、本来納めるべき税額に加えて、ペナルティとして重加算税が課されます。通常の重加算税は、追徴税額の35%です。
しかし、2022年の法改正で、このルールがさらに厳格化されました。もし、その不正行為が電子取引データやスキャナ保存されたデータに関わるものであった場合、通常の重加算税35%にさらに10%が加重され、合計で追徴税額の45%もの重加算税が課されることになったのです。
「悪質な不正行為」の具体例としては、取引先からメールで受領した請求書PDFを意図的に削除したり、PDF編集ソフトなどを使って請求書の金額を改ざんしたりする行為が挙げられます。存在しない取引を装った架空の領収書データを作成することも、もちろん不正行為に該当します。
また、帳簿書類の不備が著しい場合には、税務署が事業者の売上や経費の状況から所得を推定して課税する「推計課税」が行われることもあります。この場合、実態よりも多くの税金を支払うことになるケースが少なくありません。
会社法違反による「100万円以下の過料」
電帳法への違反は、税法上の問題にとどまりません。会社法という、会社の設立や運営に関するルールを定めた法律にも抵触する可能性があります。
会社法第976条では、企業に対して帳簿や事業に関する重要書類を適切に作成し、保存することを義務付けています。電帳法で定められた電子取引データの保存義務を果たさないことは、この会社法の義務に違反すると解釈される可能性があるのです。
会社法違反と判断された場合、100万円以下の過料が科されることがあります。これは追徴課税のような税金ではなく、行政罰としての金銭的なペナルティです。この事実は、電帳法への対応が単なる経理部門の問題ではなく、取締役などの経営陣が責任を負うべき、企業の基本的なガバナンスの問題であることを示しています。
罰則だけではない!見過ごされがちな4つの経営デメリット
電帳法に対応しないことのリスクは、法律上の罰則だけではありません。むしろ、日々の業務に潜む「見えないコスト」が、じわじわと会社の体力を奪っていくことのほうが深刻かもしれません。これらのデメリットは、一度きりの罰金とは異なり、非対応を続ける限り継続的に発生する経営上の負担です。
経理業務の非効率化と生産性の低下
紙ベースの業務フローは、非効率の温床です。過去の請求書を確認するために、キャビネットが並ぶ書庫へ行き、ファイルの中から目的の一枚を探し出す。この作業にどれだけの時間がかかっているでしょうか。
また、受け取った請求書の内容を会計ソフトに一件ずつ手で入力する単純作業は、時間もかかり、担当者のモチベーションを削ぎます。請求書を発行し、封筒に入れ、切手を貼り、ポストへ投函するという一連の作業も、取引先に届くまでには数日かかります。
デジタル化された業務では、これらの作業は劇的に改善されます。キーワード検索で瞬時に書類が見つかり、データは自動で会計システムに連携され、請求書はクリック一つで送信できます。
取引先の多くがデジタル化を進める中で、自社だけが紙のやり取りに固執していると、相手にとって「手間のかかる取引先」となり、ビジネスチャンスを失うことにもつながりかねません。
人的ミスとそれに伴う信用の失墜リスク
手作業には必ずミスが伴います。金額の桁を間違える、日付を誤って入力するといった単純なミスは、手作業である以上避けられません。支払うべき請求書を誤って別のファイルに綴じてしまい、支払いが遅延する。こうした処理ミスは、取引先との信頼関係に傷をつけます。
これらの人的ミスは、時に大きなトラブルに発展します。電帳法に対応したシステムを導入し、データ入力やチェックを自動化することで、こうしたリスクを大幅に削減できます。
書類の紛失・劣化とガバナンスの低下
紙の書類は物理的に脆弱です。紙は光や湿気で時間とともに劣化し、文字が薄れて読めなくなることがあります。また、閲覧後の戻し間違いや単純な紛失のリスクも常に存在します。
火災や水害、地震といった災害が発生した場合、紙の書類は一瞬で失われてしまう可能性があります。書類のキャビネットに鍵をかけても、内部の人間による不正な閲覧や持ち出しを完全に防ぐことは困難です。
一方、電子データは適切にバックアップを行えば、災害時にも復元が可能です。また、ファイルごとにアクセス権限を設定したり、誰がいつデータにアクセスしたかの記録を残したりできるため、内部統制や情報セキュリティの強化に直結します。
保管スペースと管理にかかる物理的コスト
国税関係書類は、原則として7年間の保存が義務付けられています。毎年増え続ける書類を保管するためには、相当な物理的スペースが必要です。
用紙代、プリンターのインク代、ファイルやバインダー、キャビネットの購入費用など、目に見えるコストがかかり続けます。しかし、最も大きなコストは、書類保管のために費やされるオフィスの賃料です。そのスペースを、より生産的な活動のために使えたはずの機会損失は計り知れません。
ペーパーレス化を実現すれば、これらの物理的な保管スペースとそれに付随するコストを根本から削減できます。
どうしても対応が間に合わない場合の「猶予措置」とは
「義務化は理解したが、すぐには対応できない」という事業者も少なくないでしょう。そのような状況を想定し、国は「猶予措置」という一時的な救済策を設けています。
ただし、これは恒久的な免除ではなく、あくまでも条件付きの「執行猶予」であると理解することが重要です。この措置は、2023年末で終了した「宥恕(ゆうじょ)措置」とは異なり、より厳しい要件が課されています。
猶予措置が適用される「相当の理由」の具体例
この猶予措置を受けるために、税務署への事前の申請は不要です。しかし、税務調査の際に、なぜ電帳法の要件通りに電子データを保存できなかったのか、その「相当の理由」を説明する責任が事業者にあります。
国税庁が示す「相当の理由」には、電子保存に対応するためのシステム導入に必要な資金が不足しているといった資金繰りの問題や、社内にITに詳しい人材がおらず運用を担える担当者がいないといった人材不足の問題が含まれます。また、システム導入を準備していたものの、ベンダーの都合などで義務化開始までに間に合わなかった場合も該当します。
ここで最も重要なのは、これらの理由が客観的に証明可能でなければならないという点です。「忙しかったから」という理由では認められません。資金繰りが厳しいことを示す試算表や、システム導入を検討した際の議事録など、客観的な証拠を保管しておくことが求められます。
猶予措置を受けるために税務調査で求められる2つのこと
「相当の理由」があったと認められるためには、税務調査において以下の2つの要求に応じられなければなりません。この両方を満たして初めて、猶予措置が適用されます。
一つ目は、調査官から要求があった際に、対象となる電子取引データをダウンロード可能な形式で提供することです。単にパソコンの画面上でデータを見せるだけでは不十分であり、例えばUSBメモリにコピーして渡すといった対応が必要です。
二つ目は、その電子データを紙に印刷したものを、整然とした形式かつ明瞭な状態で提示・提出することです。この2つの要求に応じられなかった場合、たとえ「相当の理由」があったとしても猶予措置は適用されず、前述した罰則の対象となる可能性があります。
今からでも間に合う!電子帳簿保存法への具体的な対応ステップ
電帳法への対応は、単にシステムを導入すれば終わりというわけではありません。自社の状況を正しく理解し、ルールを定め、適切なツールを選ぶという、計画的なアプローチが不可欠です。このプロセスを正しく踏むことで、法令遵守はもちろんのこと、業務全体の効率化を実現できます。
Step 1: 自社の取引を把握する(電子取引・スキャナ保存の対象範囲)
まず、自社で行われている取引のうち、どれが電帳法の対象になるのかを正確に把握することから始めます。電帳法が定める保存区分は大きく3つありますが、それぞれ「義務」か「任意」かが異なります。
必ず対応しなければならないのは「電子取引データ保存」です。電子データでやり取りした取引情報は、電子データのまま保存する必要があり、紙に印刷しての保存は原則として認められません。具体的には、メールで受け取ったPDFの請求書や、ECサイトの購入履歴、クレジットカードの利用明細などが該当します。
任意で対応できるものとして「スキャナ保存」があります。これは、紙で受け取った請求書などをスキャンして電子データとして保存する制度で、原本の破棄が可能になります。もう一つは「電子帳簿等保存」で、会計ソフトで作成した帳簿を電子データのまま保存する制度です。
まずは義務である「電子取引データ保存」に確実に対応し、余力があれば「スキャナ保存」によるペーパーレス化へと進むのが現実的な進め方です。
Step 2: 運用ルールを定める(事務処理規程の作成と形骸化させないポイント)
電子データを保存する際には、データが改ざんされていないことを証明する「真実性の確保」が求められます。この要件は、高価なタイムスタンプを付与する方法の他に、「事務処理規程」を定めて運用することでも満たせます。
事務処理規程とは、電子データの訂正や削除を原則禁止とし、やむを得ず行う場合の手順や責任者を定めた社内ルールのことです。国税庁のウェブサイトにひな形が用意されているため、それを自社の状況に合わせて修正するのが効率的です。
規程を作っただけで、実際の運用が伴っていなければ意味がありません。形骸化を防ぐためには、責任者を役職で明確に定め、実際に従業員がデータを削除できないようにアクセス権限を設定するなど、ルールとシステムを連動させることが不可欠です。また、定期的な教育や規程の見直しも重要となります。
Step 3: 対応システムを選定する(個人事業主・中小企業向けツール紹介)
電子取引データを保存する際には、「取引年月日・取引金額・取引先」で検索できる「可視性の確保」も求められます。ファイル名の工夫による手作業での対応も可能ですが、手間やミスを考えると、対応システムを導入するのが最も現実的で安全です。
現在、会計ソフト一体型、請求書受領サービス、経費精算システム、文書管理特化型など、様々なタイプのシステムが提供されています。システムの選定にあたっては、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認証する「JIIMA認証」も一つの目安になります。
freee会計 / マネーフォワード クラウド
会計・確定申告機能と一体化しており、請求書や領収書データをAI-OCRで読み取り、自動で仕訳を作成できます。すでに同社の会計ソフトを利用している場合、多くは追加費用なしで基本的な電子保存機能が使えます。
バクラク電子帳簿保存
シンプルな操作性が特徴で、AI-OCRによる項目自動入力や、インボイス制度の登録番号判定にも対応しています。コストを抑えて電子保存を始めたい事業者におすすめで、無料プランも用意されています。
OPTiM 電子帳簿保存
AIによる高精度なデータ読み取りが強みで、あらゆる取引関係書類の保存に対応します。書類の種類が多く、手入力を極力減らしたい事業者に向いており、こちらも無料プランから始めることができます。
電子帳簿保存法とインボイス制度の切っても切れない関係
2023年10月に開始されたインボイス制度と、2024年1月から義務化された電子取引のデータ保存。この2つの制度は無関係ではありません。むしろ、実務上は密接に連携しており、この関係性を理解することが、効率的な対応の鍵となります。
電子インボイスの保存は電子帳簿保存法のルールに従う
インボイス制度と電帳法の最も重要な接点は、「電子インボイス」の扱いです。インボイス制度で仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要ですが、これは電子データ(電子インボイス)で授受することも認められています。
ここで電帳法のルールが登場します。取引先からメールやウェブサイト経由で受け取った電子インボイスは、電帳法における「電子取引」に該当します。したがって、電子インボイスを保存する際は、電帳法が定める電子データ保存のルール(真実性の確保、可視性の確保)にも従わなければならないのです。
受け取った電子インボイスを紙に印刷して保存しただけでは、電帳法の保存義務を果たしたことにはならず、結果として仕入税額控除が認められないリスクが生じる点には注意が必要です。
両制度に一括対応するメリットと業務効率化
電子インボイスの保存には、電帳法とインボイス制度の両方のルールが適用されるため、この2つの制度への対応は、別々に考えるのではなく、セットで進めるのが圧倒的に効率的です。
両制度に対応したシステムを一度に導入すれば、業務フローの変更を一度で済ませることができます。請求書の受け取りから、インボイス要件の確認、会計システムへの入力、そして電帳法の要件に沿った保存まで、一連の流れをデジタル上で完結させることが可能になります。
この法改正を単なる「やらされ仕事」と捉えるのではなく、バックオフィス業務全体を見直し、デジタル化を加速させる絶好の機会と捉えるべきです。ペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化は、企業の競争力強化に直接つながります。
まとめ
本稿では、電子帳簿保存法に対応しない場合のリスクについて、多角的に解説してきました。対応を怠ると、「青色申告の承認取消」や「重加算税の加重措置」といった厳しい罰則が科されるだけでなく、日々の業務非効率化という見えないコストも発生します。
しかし、対応は「対象範囲の把握」「運用ルールの策定」「システムの選定」という3ステップで計画的に進めることが可能です。また、電子インボイスの扱いに見られるように、インボイス制度との一括対応は業務効率化の鍵となります。
電子帳簿保存法への対応は、もはや避けては通れない経営課題です。これを単なる負担と捉えるのではなく、自社の業務プロセスを見直し、デジタル化を推進するための「未来への投資」と捉えることが重要です。
法令を遵守してリスクを回避し、その先にある業務効率化や生産性向上という果実を得るために、今日から具体的な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。








敷金とは?返還される条件や礼金との違い、退去トラブルを防ぐ全…
敷金の仕組みを正しく理解すれば、退去時に手元に残る現金を最大化し、理想の引越しを実現できます。浮いた…