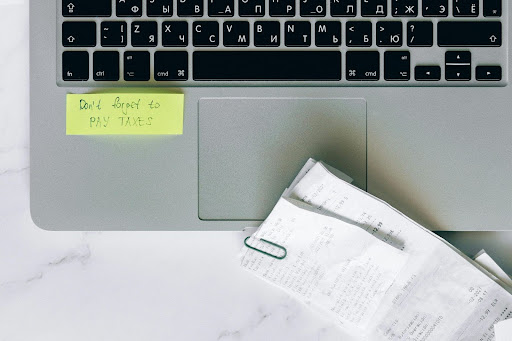
領収書は、ビジネスや経理においてお金のやり取りを証明する大切な書類です。
しかし、例えば領収書を紛失してしまったときや、経費を水増ししたい誘惑に駆られたとき、自分で領収書を作成したり書き換えたりしてしまおうと考える人もいるかもしれません。
結論から言えば、領収書を発行権限のない人が勝手に作成する行為は違法であり、重大なリスクがあります。
本記事では、個人事業主・経理担当者・会社員の方々に向けて、領収書を「勝手に作る」ことの違法性や、その行為によって実際に起こったトラブル事例を解説します。
また、領収書を紛失してしまった場合の合法的な対処法や、トラブルを未然に防ぐための予防策、さらには領収書にまつわるよくある疑問(Q&A)にもお答えします。
専門的な内容もできるだけ分かりやすく丁寧に説明しますので、日頃の経費管理や会計処理の参考にしてください。
目次
領収書を勝手に作る行為の違法性【刑法・税法上のリスク】
まずは、他人が発行すべき領収書を自分で勝手に作成したり、白紙の領収書に書き込んだりする行為が法律上どんな問題を抱えるか確認しましょう。
有印私文書偽造罪・変造罪(刑法上の罰則)
領収書は通常、発行者(お店や会社)が署名・押印して交付する「有印私文書」にあたります。
発行権限のない人が領収書を勝手に作成したり、もらった領収書の内容(金額や日付、宛名など)を改ざんしたりすると、刑法上「有印私文書偽造罪」または「有印私文書変造罪」が成立する可能性があります。
有印私文書偽造罪
他人になりすまして文書を作ったり、無断で他人のハンコやサインを使用して文書を作成する行為です。領収書の場合、正式な発行者以外の人が領収書を作る行為が該当します。
有印私文書変造罪
正規に作られた文書の一部を書き換える行為です。例えば領収書の金額を書き直すなどが該当します。
これらの罪に問われた場合、3ヶ月以上5年以下の懲役刑という重い刑罰が科される可能性があります。仮に「実際に支払った正しい金額を書いただけ」であっても、発行者以外の人間が書き込んだ時点で違法です。
さらに、その偽造・改ざんした領収書を実際に使用すると、「偽造私文書行使罪」にも問われます。会社や税務署に提出すれば、それは犯罪行為を行使したことになるためです。
詐欺罪・横領罪(不正経費精算による刑事リスク)
領収書を偽造する目的の多くは、経費の不正請求やお金の着服でしょう。例えば、実際には支払っていない架空の経費をでっち上げたり、金額を水増しした領収書で多額の精算を受け取れば、会社や事業主を騙して金銭を得たことになります。
これは刑法の「詐欺罪」に該当し、10年以下の懲役という厳しい罰則が規定されています。たとえ発覚前に未遂で終わっても、詐欺の未遂罪として処罰対象です。
また、会社の立場から見れば、従業員が不正に経費を受け取るのは会社のお金を横領したことにもなりかねません。業務上、自分の管理するお金を着服した場合は「業務上横領罪」にもなり得ます(こちらも10年以下の懲役などが規定されています)。
税法上のリスク(重加算税・追徴課税)
領収書の偽造は、税務面でも大きなリスクを伴います。もし偽造した領収書で経費を水増しし、それが税務調査で発覚した場合、本来納めるべき税金を過少に申告していたことになります。
税務署は悪質な仮装・隠蔽と判断した場合、「重加算税」という非常に重いペナルティを科します。重加算税は、不正に免れようとした税額に対して35%もの高率で追徴される税金です。
通常の税金とは別に課されるため、多額の追徴課税となり会社や事業に大打撃を与えます。
例えば、経費を数百万円水増しして法人税や所得税を少なく申告していた場合、後から数百万円×35%に当たる重加算税を追加で支払う必要が生じます。これは本来の納税額に加えてです。
さらに、不正が悪質であれば刑事告発され、先述した私文書偽造罪や詐欺罪で逮捕・起訴されることもあります。
まとめると:領収書を勝手に作成・改ざんする行為は、刑法上も税法上も重大な違法行為です。一時的にバレなくても、発覚すれば懲役刑や多額の罰金・追徴を受け、社会的信用も失墜します。決して「ばれなければいいだろう」と安易に考えてはいけません。
実際に起きた領収書不正のトラブル事例
領収書の偽造や不正利用は、現実にさまざまなトラブルを引き起こしています。ここでは過去の事例をいくつか紹介し、その深刻さを確認しましょう。
経費水増しによる懲戒解雇・刑事処分の事例
ある企業では、営業担当の社員が取引先との会食費用を水増し請求していた事例があります。社員は飲食店からもらった領収書の金額を書き換えたり、複数回利用した領収書を改ざんして合算することで、実際より高額な経費を請求していました。
この不正は社内監査で発覚し、会社は社員を懲戒解雇。さらに会社は被害届を出し、警察が捜査に乗り出しました。社員は有印私文書偽造と詐欺の疑いで逮捕される事態となりました。
金額が小さくても、会社の資金を騙し取る行為は背信行為として厳しく処分されることを裁判所も認め、このケースでは懲戒解雇も有効と判断されています。「たかが数万円」「ばれたら返せばいい」という言い訳は通用しないのです。
偽造領収書で多額の資金を詐取した事例
別の事例では、何十回にもわたり偽造領収書を提出し、合計で数百万円規模の金額を勤務先から騙し取っていたケースがあります。
例えば、ある元社員は架空の飲食代の領収書を自作しては経費精算を繰り返し、トータルで700万円以上を不正に得ていました。最終的にこの人物は社内調査から警察沙汰となり、詐欺罪で逮捕されています。
このように大がかりな不正は長期間にわたり発覚しない場合もありますが、もし税務署の調査などで異常な領収書が検出されたり、内部告発があれば一気に露見します。
不正発覚後は、不正に取得した金額の全額返還はもちろん、会社の信用も大きく傷つける結果となりました。
税務調査で領収書の改ざんが発覚した事例
ある中小企業では、経営者がプライベートな支出を経費で落とすため、既存の領収書の日付や用途を改ざんして申告していました。
しかし、数年後の税務調査で帳簿と領収書の辻褄が合わない点を指摘され、偽造が発覚。税務署はこれを悪質な隠蔽とみなし、会社に対して重加算税を含む多額の追徴課税を行いました。
最終的に経営者は修正申告を受け入れ、本来の税金に加えて数百万円の追徴を支払う羽目に。さらに悪質性から経営者個人が刑事告発される寸前となり、事業存続の危機に陥りました。
以上の事例からも明らかなように、領収書の不正は必ずしも小さなイタズラでは済まないということです。一度でも不正に手を染めてしまうと、発覚したときのペナルティは金銭的・社会的に計り知れません。
では、領収書を失くしたり足りない場合はどうすれば良いのでしょうか?次の章で、正しい対処法を詳しく解説します。
領収書を紛失した場合などの合法的な対処法
経理担当者や個人事業主にとって、領収書の紛失は時折起こりうるトラブルです。また、やむを得ず領収書がもらえなかったケースもあるでしょう。しかし、だからといって自分で架空の領収書を作成するのは絶対にNGです。
ここでは、領収書が手元にない場合に取るべき合法的で適切な対処法を紹介します。
1. 領収書の再発行を依頼する
領収書をなくしてしまったことに気づいたら、まず最初に検討すべきは発行元への再発行依頼です。購入先のお店やサービス提供者に事情を説明し、領収書を再度発行してもらえないかお願いしてみましょう。
ただし、領収書の再発行は必ずしも簡単ではありません。法律上、領収書は「支払者から求めがあれば発行しなければならない」と定められていますが、再発行の義務までは規定されていません。そのため、多くの事業者は再発行に慎重です。理由は2つあります。
二重経費申請のリスク
一度の支払いに対して領収書が2枚存在すると、悪用すれば経費の二重計上・水増しが可能になってしまいます。発行側からすると、依頼者が本当に領収書を紛失したのか、それとも不正目的なのか判断がつきません。そのため軽々しく応じられないのです。
税務署からの疑い
仮に知らずに不正目的の再発行に応じてしまうと、発行元の事業者も「脱税幇助」に加担したと見なされる恐れがあります。後日同じ番号の領収書が二重に出回っていれば、税務署から事情を問われるかもしれません。
以上の理由から、多くの店や会社では「領収書の再発行はできません」と案内されることが一般的です。ただし、取引先など信頼関係のある相手であれば、領収書に「再発行」「○月○日再発行分」といった再発行である旨の但し書きを入れて対応してくれる場合もあります。
再発行分であることを明記すれば不正利用を防ぐ効果があります。取引先に失礼にあたらないようであれば、一度相談してみる価値はあるでしょう。
2. レシートや明細書で代用する
万一領収書が再発行してもらえなかった場合や、最初から領収書ではなくレシートしか受け取っていない場合でも、諦める必要はありません。レシート(レジでもらう細長いお会計票)やクレジットカードの利用明細は、多くの場合領収書の代用証憑として認められます。
一般に経費精算や確定申告では「会社名が入った正式な領収書」が必要と思われがちですが、実際には支払先、日付、金額、支払い内容が明記されている書類であれば経費の根拠資料として有効です。
レシートには店名・住所、購入日時、品目や金額がきっちり印字されていますから、それ自体が支出の証拠となります。
会社によっては経費精算書にレシートの添付を認めているところも多いです。また税務署に対しても、レシートであっても正当な経費であれば必要経費や仕入税額控除の証拠として通用します(領収書と同様の扱いが可能)。
ただし注意点として、レシートは通常宛名(誰から受け取ったか)が書かれていないため、会社から「宛名入りの領収書を提出するように」と言われている場合は、事前に経理担当者に相談すると良いでしょう。
小規模な支出であればレシートで問題ないケースが多いですが、高額だったり重要な経費の場合は一筆説明書を添えて理解を得ることも検討してください。
3. 出金伝票を作成して経理処理する
領収書が紛失してどうしても再発行もレシート代用もできない場合の最後の手段として、「出金伝票」を活用する方法があります。出金伝票とは、現金で支払った取引を記録する社内用の伝票の一つで、領収書が何らかの理由で存在しない支出の証拠として使われます。
出金伝票で明記すべき主な項目:
- 支払日付
- 支払先(どこに支払ったか。店舗名や業者名)
- 金額
- 支払いの内容・用途(何のための支出か)
- 支払った担当者名、作成者名(必要に応じて)
これらを記載した出金伝票を作成し、社内で上長や経理担当者の承認印をもらえば、ひとまず社内的には「領収書の代わり」として処理できます。さらに、可能であれば支払いを裏付ける他の証拠も一緒に保管しましょう。
例えば、現金で支払った場合は現金出納帳への記録、取引に関係する契約書や納品書があればそれも添付するなどです。複数の証拠を組み合わせて保存しておくことで、後日の監査や税務調査でも信頼性が増します。
注意:出金伝票はあくまでやむを得ない場合の内部処理です。誰か第三者が発行した領収書と異なり、どうしても客観性が弱い(自作の書類である)ため、頻繁に多用すると税務署に疑われる可能性があります。
高額経費で出金伝票ばかり使っていると「本当は領収書があるのでは?」「架空の経費では?」とチェックされやすくなります。したがって、出金伝票の使用は最終手段として、日頃から領収書やレシートの管理を徹底することが大切です。
4. その他の証明書類を活用する(ケース別)
業種や支出内容によっては、上記以外にも代替できる証明書類があります。例えば、医療費で領収書をなくした場合には、病院に頼めば「支払証明書」という書類を発行してくれることがあります。
これは○月○日にこれだけの治療費を受領しました、という病院発行の証明書です。医療費控除のための証明として有効です。
また、高速道路の利用料金など領収書がそもそも発行されない取引(ETC利用など)の場合、利用明細書やクレジットカードの明細が証拠書類となります。交通機関のICカード利用履歴や、スマホ決済の履歴なども、経費の支払い事実を示す記録として保存しておきましょう。
トラブルを未然に防ぐための領収書管理と不正防止策
領収書をめぐる不正やトラブルを防ぐためには、日頃からの管理と社内ルールの整備が何より重要です。ここでは、個人事業主や企業の経理担当者ができる予防策をまとめます。
社内ルールの明確化と社員教育
会社員の場合、会社側で経費精算に関する明確なルールを設け、全社員に周知徹底することが大切です。例えば
白紙領収書の禁止
取引先から白紙の領収書(金額未記入のもの)を絶対にもらわない、提出させない。やむを得ず受け取った場合も自分で書き込まず必ず経理に報告する。
不備領収書の扱い
宛名が「上様」や金額・日付抜けなど不備があれば、その場で正しいものを再発行してもらうか、上司に相談するルールを作る。
経費精算時の確認
経理担当者は提出された領収書の内容・筆跡をチェックし、不自然な点があれば問い合わせる体制を整える。
さらに、定期的にコンプライアンス研修を行い、「領収書の不正は犯罪である」「発覚すれば懲戒解雇や刑事告訴もあり得る」ことを社員に教育します。不正を働かせない企業風土作りが大切です。
社員一人ひとりも、「たかが経費」と甘く見ず、倫理観を持って業務にあたるよう促しましょう。
クラウド会計・経費精算システムの活用
テクノロジーの力で不正を防止する方法も有効です。最近では、クラウド経費精算システムや会計ソフトが普及しており、領収書の写真を撮ってそのままデータ保管したり、クレジットカードと連携して自動的に経費データを取り込むことができます。これらのシステムを活用すると
改ざんの防止
領収書画像を保存するため、人手で金額を書き換える余地がない。オリジナル画像とデータが残ります。
不正の早期発見
経費の申請内容が一元管理・数値分析できるので、不自然な経費(特定社員だけ金額が多いなど)を発見しやすい。
内部統制の強化
ワークフローで承認プロセスを踏むため、一人で経費を処理できずチェックが入る。
また、電子帳簿保存法の要件を満たすクラウドサービスであれば、領収書を電子データで保存でき、紙の保管コスト削減にもなります。経費精算のデジタル化は、業務効率アップだけでなく不正抑止策としても非常に有効です。
日頃からの領収書管理を徹底する
個人事業主にとっても社員にとっても、領収書の適切な管理は基本中の基本です。トラブルを避けるために以下を心がけましょう
領収書はその場で中身を確認
受け取ったらすぐ、金額・日付・宛名・但し書き・印紙の有無などをチェック。不備があればすぐ訂正を依頼。
領収書の保管ルール
領収書専用のファイルや封筒に日付順・案件順に整理し、紛失を防ぐ。月末ごと、出張ごとなどカテゴリー分けも有効。
電子化の活用
スマホで領収書を撮影しておけば、万一原本を紛失しても情報が残ります。ただし電子化したからといって原本をすぐ捨てず、税法に沿って一定期間は原本も保管しましょう(電子保存法の要件を満たす運用であれば原本破棄も可能ですが、慣れないうちは併用がおすすめ)。
私的経費と事業経費の区別
プライベートな支出を経費で混同しないよう、領収書の段階から分けて管理する。会社員なら会社カードを使う、事業主なら事業用財布とプライベート用を分けるなども有効です。
小さな心掛けの積み重ねが、大きな不正やトラブルの芽を摘むことにつながります。
領収書に関するよくあるQ&A
最後に、領収書について多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。基礎知識のおさらいとしてお役立てください。
Q1. 「領収書」と「レシート」は何が違うのですか?
A: 一般的な違いは形式と宛名の有無です。領収書は通常、宛名(受取人名)や但し書きが手書きまたは印字され、発行者の署名・捺印がある正式な受取証です。
一方、レシートはレジから自動的に出力される明細票で、宛名はなく、購入品や金額・日時などが記載されています。
ただし、法的には両者とも「金銭の受取証」であり、記載項目(支払先、日付、金額、取引内容)が満たされていれば証拠書類としての効力は同じです。
ビジネスでは取引先名を入れた領収書を求める習慣がありますが、経費精算や税務上はレシートでも問題ありません。強いて言えば、領収書の方が宛名が入る分「誰の支払いか」が明確になる程度の違いです。
Q2. 電子領収書やメールでもらった領収書は経費として認められますか?
A: はい、現在では電子的な領収書も十分に認められます。例えばオンラインショップの支払い後に送られてくるPDFの領収書や、メール本文に記載された領収データも法的な領収書とみなされます。
ただし、電子帳簿保存法の規定により、それら電子領収書を保存する際には一定のルール(真実性の確保や検索要件など)を守る必要があります。
ポイントは、受領した形式で保存すること。電子で受け取った領収書は紙に印刷して保存するより、電子データのままタイムスタンプ付きで保存する方が正式です(2024年から紙保存は原則認められなくなりました)。
クラウド経費システムなどを使えば、受信メールやPDFをそのまま保管できます。
また、電子領収書には収入印紙が不要というメリットもあります。紙の領収書では5万円以上の取引に収入印紙を貼る義務がありますが、PDF等の電子領収書は印紙税法上「文書の作成」が電子的な場合は非課税扱いとなるためです。
Q3. 領収書の宛名を「上様」にしても大丈夫でしょうか?
A: 「上様」宛名の領収書は、厳密には誰宛かわからない表現ですが、日本では昔から小売店などで広く使われてきました。
結論として、上様の領収書でも経費として認められるケースが多いです。ただし、好ましいかどうかで言えば「できれば具体的な名前を書いてもらう方が良い」です。
税務上は宛名が空白だと問題ですが、「上様」であれば形式上は埋まっていますし、金額や日付、発行者情報が正しければ支出の証拠にはなります。実際、法人税法基本通達でも宛名が空欄でも接待費等の証拠として認める趣旨があります。
ただ、会社の経理規程によっては禁止されている場合もあります。上様だと誰が使った経費か曖昧になりがちなので、社内チェックが厳しい場合は避けた方が無難です。
Q4. 領収書に収入印紙はいつ貼る必要がありますか?
A: 収入印紙は、領収書などの金銭の受取書に一定額以上の金額が記載される場合に必要な「税金(印紙税)」です。具体的には、5万円以上の売上代金を受け取ったことを証明する領収書には所定の印紙を貼らなければなりません。
金額に応じて印紙税額が異なり、5万円以上~100万円以下なら200円、以降受取金額が増えるごとに段階的に税額が上がります(例えば100万円超~200万円以下は400円など)。
注意点として、クレジットカード払いの場合は領収書でも印紙が不要なことがあります。これは、代金をカード会社が立て替えて支払い、後日カード利用者がカード会社に支払う仕組みのため、領収書の受取主体が事業者ではないと解釈されるからです。
また、電子領収書は先述の通り印紙不要です。店頭でも最近はメール送付など電子交付が増えています。その場合は印紙税の対象外となります。
なお、領収書の宛名が「上様」であっても金額が5万円以上なら印紙は必要です(宛名は印紙税要件に関係ありません)。
まとめ:領収書は正しく扱い信頼を守ろう
領収書を「勝手に作る」行為の違法性やリスク、正しい対処法や予防策について詳しく解説してきました。領収書は単なる紙切れではなく、法律上もビジネス上も重要な証拠書類です。
それを不正に扱うことは、自分自身の信用を失うだけでなく、会社や取引先、さらには税務当局との信頼関係も壊しかねません。
領収書の偽造・改ざんは犯罪行為であり、懲役刑や罰金・追徴課税など重大な処罰の対象になります。
万一領収書を紛失しても、再発行の依頼やレシート・出金伝票での対応など、正規の対処法があります。不正に手を染める必要はありません。
企業は社内規則の整備やシステム導入、社員教育を通じて、経費精算の透明性を高め不正を防止しましょう。個人でも日頃から領収書管理の習慣をつけることが肝心です。
領収書に関する基本知識(レシートとの違い、電子領収書の扱い、上様問題、印紙税ルール)もしっかり押さえておくと、慌てず適切に対応できます。
信頼できる経理処理は健全なビジネスの土台です。領収書の取り扱い一つをとっても、その積み重ねが会社や個人の信用を支えています。ルールを守って正しく領収書を扱い、安心して経理・会計業務に臨みましょう。








不動産売買の領収書テンプレートと正しい書き方|印紙税の判定か…
不動産売買における金銭トラブルを未然に防ぎ、税務署への申告をスムーズに進めるためには、正確な領収書の…