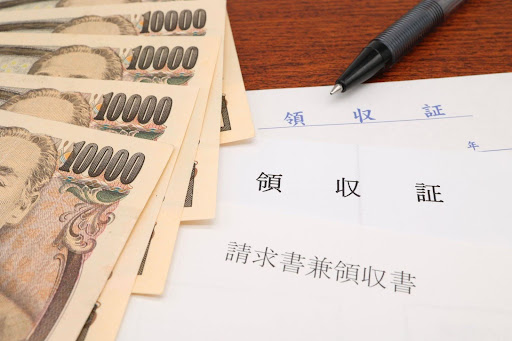
領収書はお金などのやりとりがあったことを示す役割があり、ビジネスシーンでは欠かせない書類です。本記事では、領収書を発行・受領する際に覚えておきたいポイントなどについてわかりやすく解説します。
目次
そもそも領収書とは
領収書とは、お金が支払われた事実を証明するために用いる書類です。
会社では、外出や出張の際に生じた経費を精算するために領収書が使われることが一般的です。また、事業におけるお金の流れを記録して決算や確定申告を行うために必要であるほか、税務調査が入った際に適切な経費であったことを示すためにも使われます。
領収書の意味
領収書によって商品やサービスの対価としてお金が支払われたことを証明できます。具体的には、お金を支払う側は「お金を支払ったこと」を、お金を受け取った側は「お金を受け取ったこと」を証明するために作成します。
領収書と領収証の違いとは
領収書と領収証はどちらもお金を受け取ったことを証明する目的で発行するものであり、明確な違いは意識されていないことがほとんどです。
国税庁のホームページでは、領収書などの書類と印紙税の扱いについて以下のように記載しています。
| (引用)金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。 |
つまり、領収書と領収証はもちろん、レシートなどその他の書類に関しても、同じような意味合いを持つ書類であることがわかります。
領収書とレシートの違いとは
領収書とレシートの違いについては、以下の記事で解説しています。
領収書とレシートの違いとは?代わりにできる?証明力や経費精算での注意点を解説-INVOY
領収書と預り証の違いとは
預り証とは、他者の金銭などを一時的に預かることを証明するために作成する書類です。高額の商品を取引する際に前金を受け取った場合や、不動産会社が敷金を預かった場合などに発行します。したがって、預り証は商品やサービスがまだ実際に取引されていない状態でも発行することが一般的です。
領収書は、領収書の受領側から発行者へとお金の持ち主が移行したことを示します。それに対して預り証は、ただ預かっているという状態であるため、お金の所有権が実際に移動したわけではありません。
領収書の無料エクセルテンプレート一覧
無料でダウンロードできる領収書のテンプレートをいくつか紹介します。どれもシンプルで直感的に使えるベーシックなデザインとなっており、さまざまな業種やシーンで幅広く活用できるものばかりです。
読みやすい明朝体を使用した無彩色のデザインが特徴です。そのため、誰でも簡単に使用できるオーソドックスな領収書のテンプレートです。
領収書には、商品名、数量、単価、金額など、必要な項目がすべて記載されており、消費税も別途記載されています。これにより、税率変更があった場合でも、簡単に対応できます。
さらに、備考欄も設けているため、取引先に特別なコメントを残したい場合などにも便利です。シンプルで使い勝手の良い、定番の領収書テンプレートとして、さまざまなシーンで利用できます。
ダウンロードはこちらから。
【無料】領収書(ベーシック×明朝×赤色) エクセルテンプレートダンロード- INVOY
【無料】領収書(ベーシック×明朝×紫色) エクセルテンプレートダンロード- INVOY
【無料】領収書(ベーシック×明朝×無彩色) エクセルテンプレートダンロード- INVOY
【無料】領収書(ベーシック×明朝×オレンジ) エクセルテンプレートダンロード- INVOY
領収書の書き方
領収書はパソコンからExcelや作成システムによって作成する方法のほか、市販の領収書に手書きで記入する方法もあります。詳しい作成方法は以下の記事で解説しています。
領収証の正しい書き方を解説!【見本付き】注意点なども詳しく紹介-INVOY
事業者が領収書を発行しなければいけない理由
民法第486条では、領収書の発行について以下のように定めています。
| (引用)第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。 |
引用:民法(486条)
「弁済」とは、債務(支払う義務)を履行して債権(支払いを受ける権利)が消滅することです。つまり、商品やサービスの代価としてお金を支払う際は、書面・データのいずれかの方法で領収書の請求をすることが民法によって認められているということを意味します。
領収書の発行が必要なケース
前項で解説した通り、お金を支払った側から領収書の請求があれば、原則として領収書を発行しなくてはいけません。また、相手から領収書の請求がなかったとしても、次の理由から領収書を発行することが一般的です。
領収書が果たす重要な役割
領収書は商品やサービスの対価が支払われたことを示す重要な書類であり、対価を二重に請求したり、誤った金額で取引したりすることを防ぐ役割があります。もし領収書がなければ「払った、払っていない」という認識の相違が生まれて、トラブルに発展してしまうかもしれません。
また、領収書は社内における不正を防ぐためにも役立ちます。領収書がないのにもかかわらず経費を請求できる仕組みにしてしまうと、実際に支払っていない架空の経費を請求し、着服するといった不正が行われる可能性があります。そのような不正を防ぐためにも、社員に領収書の提出を求め、業務に関連する支払いがあったことを確認するルールを設けます。
領収書の発行が不要なケース
クレジットカードで決済が行われる場合は、商品やサービスを提供した店舗などは領収書を発行しなくても構いません。購入した段階ではあくまで、クレジットカード会社が代金を立て替えている状態であるためです。
購入した側は、店舗などから発行される利用明細書を証憑(取引に関する事項を証明するための書類)とすることができます。
領収書の発行が必ず必要ではない業種
ECサイトでは、必ずしも領収書を発行しなくてはいけないというわけではありません。コンビニ払いやクレジットカード払いなどによって決済することで、消費者に商品を引き渡す時と、代金を受け取る時のタイミングが異なるケースが多いためです。
また、○○ペイといった決済代行会社を通すことも多いため、消費者とECサイトが直接お金のやり取りを行わず、領収書を発行する機会は比較的少ないと言えるでしょう。
上記業種が領収書を発行した方がいいケース
領収書を発行する義務のないECサイトであっても、消費者の要望に応えるため領収書を発行した方がいいケースもあります。クレジットカード払いなどであっても、ECサイトの事業者が領収書を発行することは可能です。
その際は、クレジットカード会社が発行する書類と区別するために、通常の記載項目に加え「クレジットカード払い」などと記載するといいでしょう。なお、消費者の要望に応じてクレジットカード払いの領収書を発行する場合は、正式な書類ではないため、取引金額に応じて貼り付ける収入印紙は不要です。
銀行振り込みの場合
銀行振込の場合は、消費者が振り込んだ際、振込完了時に発行される「振込明細書」が領収書の代わりとして使えます。
しかし、その場合でも消費者が領収書を送付するよう希望してくる可能性もあります。事務処理を削減したい場合には、発注書や契約書にあらかじめ「振込明細書の受領をもって領収書の受領に代える」と記載して発行することで、領収書を発行する機会をできるだけ少なくする方法もあります。
領収書発行の手順
領収書を発行する際の基本的な流れは、以下の通りです。
①支払いがあったことを確認した後、支払い側が領収書を発行する
②金額に応じて収入印紙を貼り付ける
③領収書の控えを保管する
領収書の収入印紙については、以下の記事で詳しく解説しています。
領収書の収入印紙はいくらから必要?金額や貼り方、貼らない場合のペナルティを解説-INVOY
収入印紙について
領収書に記載される金額が5万円以上の場合、印紙税の課税対象となるため、収入印紙を貼り付ける必要があります。
しかし、印紙税が課税されるのは紙の文書のみと定められており、データとして領収書をやり取りする場合には収入印紙は不要です。例えば、Excelで領収書を発行してメールで送付するといったケースや、共有フォルダに格納する形で受け渡しをしているといったケースでは、収入印紙は必要ありません。
参照:
取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い|国税庁
関連リンク:領収書の収入印紙とは?印紙税額一覧や貼り方、注意点を解説
収入印紙を貼らないとどうなる?
収入印紙が必要な領収書に印紙を貼っていなかった場合は、発行者には過怠税が課せられてしまいます。過怠税は貼るべき印紙税額の3倍と決められているため、10万円の領収書で収入印紙を貼らなかった場合、600円の過怠税が発生します。後から税務署に申し出れば、過怠税は1.1倍に減額されます。しかし、税務署の調査後に申し出ても減額は適用されません。
領収書を受け取った側にはペナルティはなく、正式な領収書として効力は失われず、経費処理も通常通り行えます。
領収書発行時のポイント
領収書を発行する際に押さえておきたいポイントを7つ紹介します。
適格請求書発行事業者の場合
2023年10月から施行されたインボイス制度では、制度に登録した適格請求書発行事業者は、課税事業者から求められた場合に適格請求書を発行する義務があると定められています。
なお、この義務があるのは国内における課税取引のみです。また、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送や、郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービスなどについては適格請求書を交付することが困難であるため、適格請求書の義務が免除されます。
領収書に不備があった場合
インボイス制度においては、適格請求書に不備があった場合、領収書を再発行して正しい内容の適格請求情報を再度送付する必要があります。送付後に誤りに気づいたからと言って、取引先に追記や修正をしてもらうことは原則としてできません。
クレジットカード決済の場合
クレジットカードによって支払いが行われた場合は、原則として領収書を発行する必要はありません。クレジットカードを利用したことを証明する「クレジット売上票」を領収書の代わりとして利用できます。
クレジットカード決済の場合は実際に代金を受け取ったわけではないため、クレジット売上票として書類を発行したり「クレジットカード利用分」と明記したりすることで、領収行為がないことを示します。
領収書をメールに送付する場合
領収書をデータとして発行してメールなどの方法で送付する場合、後から編集がしにくいようにPDFでやり取りすることが一般的です。業務の効率化や印紙税の節約といった目的から、今後はこのような方法で書類をやり取りする機会がさらに増えていくだろうと考えられています。
宛先の書き方について
手書きの領収書を発行する際に「宛先は空欄で」と頼まれるケースもあります。宛先が空欄であっても領収書としては使用できるため、その状態で領収書を発行することは特に問題ありません。
また、インボイス制度では不特定多数の者に対して販売を行う小売業・飲食業・タクシー業については、宛先のない「適格簡易請求書」を発行することが法的に認められています。
参照:インボイス制度の概要|国税庁、適格請求書等保存方式の概要(6ページ)
領収書の印鑑について
領収書に印鑑を押さなくても書類として使用できます。領収書の印鑑は商慣習のために押印されていることがほとんどで、法的に必要であるといった決まりはないためです。
しかし、会社としての信用力をアピールしたり、偽造や改ざんを防止したりする目的で押印することもあります。また、会社の規定で押印が必要と定められているケースもあるため、自社や取引先の都合にあわせて対応することが望ましいでしょう。
領収書受け取り時のポイント
領収書を受け取る際に押さえておきたいポイントを9つ紹介します。
領収書の発行義務について
取引先や店舗に何らかの理由で領収書の発行を拒否された場合、どのように対処すればいいのでしょうか。民法の486条には「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」とあります。つまり、お金を支払った側は領収書の発行を請求する権利があるということです。
それでも領収書の発行を拒否された際は、出金伝票に日付や支払い内容・店名などを記録した上で、領収書の発行に応じてもらえなかった旨をメモしておくといいでしょう。
参照:民法(486条)
領収書を紛失してしまった場合
領収書を紛失してしまうと、支払った金額を経費にするのが難しくなります。しかし、経理担当者などと相談の上取引を行ったという事実が証明できれば、経費にできることもあるかもしれません。
また、取引先に領収書の再発行を依頼したり、領収書の代わりにレシートで対応したりすることも検討しましょう。出金伝票を作成して対応することもありますが、多用しすぎると税務調査の際に疑われることもあるので注意が必要です。
領収書の「上様」について
領収書の宛名の欄に、社名などを記入する代わりに「上様」と記載するケースもあります。これは「あなた」といった代名詞の役割があり、どんな人にでも当てはまる便利な言葉です。
これまでも解説してきた通り、不特定多数に対して販売を行う飲食店や小売業などの適格請求書発行事業者に関しては、宛先のない適格簡易請求書を発行できるため、宛先が「上様」でも問題はないでしょう。
しかし、宛名のない領収書は税務調査や社内での経費精算で問題になりやすいため、できるだけ宛名を正確に記載してもらうことをおすすめします。
領収書の保管について
法人の場合は、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間領収書を保管しなくてはいけないと定められています。
事業所得などのある個人事業主の場合、青色申告では原則として7年間、白色申告では5年間です。
領収書は税務調査が入った時に事業に必要な支払いであったことを証明するための根拠となります。領収書がないと経費として認められず、追加で税金を支払ったり、青色申告事業者の承認が取り消されてしまったりすることもあるので注意しましょう。
参照:
事業所得や不動産所得等のある方には帳簿の記帳・保存義務があります!https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou02.pdf
クレジットカードを利用した場合
クレジットカードを利用していると、一定期間の利用内容が一覧になった請求明細書がカード会社から発行されます。内容が一気に確認できて便利なように思えますが、消費税法で規定する請求書等には該当せず、その明細では仕入分の消費税が控除される「仕入税額控除」の適用を受けることはできません。
したがって、クレジットカードを利用する場合であっても、通常通り取引先や店舗などで発行される領収書を保管しておきましょう。
領収書の代わりとなる書類について
領収書やレシートがない場合には、以下をはじめとする書類を代用することもあります。
・出金伝票
・銀行の振込金受取書(振込明細書)
・預金通帳
・通販サイトの確認メール
社員が領収書を紛失してしまった場合などには、これらの書類によって経費精算を行うケースもあるでしょう。ただし、仕入税額控除を受けるためにはインボイス制度や消費税法で規定された内容の書類が必要です。
交通費を交通系ICカードで支払う場合
SuicaなどのICカードで交通費を支払う際は、券売機の「領収書」のボタンを押すと領収書や利用履歴を発行できます。モバイルSuicaなどの場合、Webサイトからログインして履歴を確認可能です。
例えば、社員が個人用のICカードから電車賃を立て替えて支払った場合は、券売機などで利用履歴を発行してもらいます。電車の利用があったことを確認した上で、出金伝票を作成して処理するなどの方法があります。
PDFで領収書を受け取った場合
PDFなどの電子的な方法で領収書を受け取った際は、電子帳簿保存法に基づいて書類を保管する必要があります。この法律では、メールなどで電子的に受け取った書類はプリントアウトせず、データのまま保管するなどの要件が定められています。
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを導入したり、保管のための規定を定めてフォルダに保管するといった方法で対応しましょう。
領収書の再発行について
領収書を何回も発行すると、複数回にわたって経費を計上・請求できてしまうことから、基本的には領収書の発行は1回のみです。
しかし、受け取った領収書を紛失してしまった場合、取引先に話せば再発行に応じてくれる可能性があります。その際の領収書には「再」といった記載によって初回に発行した領収書と区別することが一般的です。
領収書を簡単に作成なら「INVOY」
「INVOY」なら、領収書を簡単に作成可能。必要な項目を上から順番に入力するだけで正確な領収書が作成できます。
また領収書はスマートフォンからも作成できます。隙間時間や外出先で急を要する場合でもすぐに対応できるのが特徴です。もちろん電子帳簿保存法にもとづいた、クラウド管理にも完全対応しています。領収書の枚数や取引先数、メンバー管理なども無制限です。まずは無料で始めてみてください。
領収書に関する業務を効率化したいと考える方は、ぜひ利用をご検討ください。
まとめ
領収書はお金のやりとりが生じた時に発行される書類で、ビジネスシーンには欠かせない書類です。領収書がなくても出金伝票といった他の書類で代用できることはありますが、多用すると税務調査の際に「不正に経費を計上しているのでは?」と思われてしまうリスクがある点に気をつけましょう。
また、領収書はインボイス制度や電子帳簿保存法といった法制度にも関わる書類であり、法制度の動向を確認しながら対応することも重要です。迷った際は経理部や税理士などに相談することも検討するといいでしょう。








【決定版】お礼状テンプレ集|ビジネスから日常まで、好印象を与…
お礼状を正しく送るだけで、あなたは周囲から圧倒的に信頼されるようになります。ビジネスの世界では、感謝…